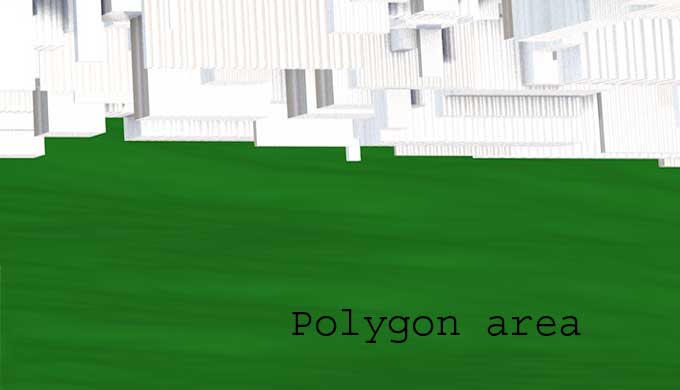アタリショックとファミコン帝国時代の任天堂
ビデオゲームの歴史において、任天堂は、ファミコン、スーファミという、家庭用ゲーム機一強時代、暴君状態だったと言われる。
しかしそれは先人の失敗から学んだ礼でもある。
1980年代の前半。
家庭用ゲーム機の北米市場が、 急激な売り上げ不振で崩壊してしまうという、今では『アタリショック(Video game crash of 1983)』と呼ばれる事件があった。
アタリとは、当時ゲーム業界の最大手であったアタリ社までもが、分裂するほど追い込まれたことからついた名前である。
アタリショックの失敗は諸説あるが、外部メーカー、いわゆる『サードパーティ』の参入を全面的に許可しすぎていたために起きた、駄作の乱立である。
販売するゲームのことごとくがつまらないものばかりになり、ユーザーからの信頼を失ってしまったという見方が一般的である。
任天堂が業界のトップに躍り出ることができた1980年代の後半という時代には、まだアタリショックは、つい最近の話であったのだ。
サードパーティの参入条件を厳しく設定するのも仕方がないとも言えよう。
ただし、あまりにもな唯一神状態に、強気が増していたのも間違いはないと思われる。
結果的にそれは、他のゲーム会社の敵意を生んでしまったが、それは二十世紀最後の、さらなる次世代機戦争においての、任天堂の敗北の原因の一端となった。
 「任天堂の歴史」ファミコンによる家庭用ゲーム機の市場制覇まで
「任天堂の歴史」ファミコンによる家庭用ゲーム機の市場制覇まで
ハドソンのPCエンジン。光学ディスクシステムの始まり
パソコンに近づいたハドソンとNEC
後(2012年)にコナミ社に吸収されたハドソンは、ファミコンのブームが巻き起こる以前からファミコンへと接近し、最初のサードパーティとなったメーカーである。
そのハドソンは、自らも家庭用ゲーム機自体にも強い感心を持ち、1987年にはついに自社ハードを開発する。
NECグループのNEC-HC(ホームエレクトロニクス)と提携販売されたそのゲーム機は『PCエンジン(1987)』と、「(ファミリー)コンピュータ」に比べたら、いかにもPC的家庭用ゲーム機という名称である。
実際に、かなりPCとの差別化を意識しているファミコンに比べれば、オプション機器接続によって機能拡張を見越したそのマシンは、かなりPC寄りであったといえよう。
性能は明らかにファミコンよりも上だった。
PCエンジンが採用していたCPUは「MOS6502」というのを拡張した「Hu6280」チップ。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
ファミコンのと同じく8ビットだが、クロック周波数が4倍であり、 集積回路の構成的にグラフィック表現も大幅強化されている。
 「ビットとは何か」情報量の原子は本質的にも原子であるのか
「ビットとは何か」情報量の原子は本質的にも原子であるのか
性能の強化は、どんどん最新のものが投入されるアーケードゲームの最新作の移植にも最適であった。
特に、アイレム社のシューティングゲーム『R-TYPE(1988)』などは大きな話題を呼び、PCエンジンはファミコンを越える、高級ハードとしてのイメージを持つことに成功した。
PCエンジンduo。史上最初の光ディスクシステムゲーム機
PCエンジンはいわばコアであり、様々な拡張機器が販売されるに至るわけだが、そういう拡張要素の中でも、特にゲーム史において強い意味を放っているのが、『CD-ROM^2(シーディーロムロム)』である。
これは名前そのままで ゲーム機として史上初の『CD-ROM』、すなわち『光学ディスク(Optical disc)』のメディアドライブを採用したゲーム機であった。
まだ音楽ソフトとしてのCDが、ようやく一般的にも認知されて、それほど経っていないような時期である。
さらには、ゲームデータをセーブする専用外部メモリーまで採用。
まさにいろいろな意味で、 早すぎた次世代ゲーム機であった。
そして『PCエンジンDuo(1991)』においては、標準的に光学ディスク式を採用。
拡張機器を次々つけるという、PC的なカスタム思想は捨てられ、 従来の家庭用ゲーム機へと近づいたが、それはPC からの再差別化とも言えるかもしれない。
イースI・II。光学ディスクの利点
光学ディスクはデータの読み込み時間が明らかに不利な点であった。
しかし従来のカセットとは違い、音楽や映像データに多くの容量を用意できることが何よりの強みである。
特に、日本のオタク達が望んでいたアニメ的演出が初めて、ある程度まで思い通りの形で実現できるようになったのは大きい。
PCから、二作をひとまとめにしてPCエンジンに移植された『イースI・II(1989)』などは、 美麗なグラフィック表現に、「CV(キャラクターボイス)」などが印象的であり、それなりにヒットした。
セガサターン。ゲーマーたちが望んだハード
ゲーム機としては史上初の16ビットCPUを採用したセガのゲーム機『メガドライブ(1988)』は、北米市場でこそそれなりに成功したものの、日本ではどうしても高性能なマニアック機として立場でPCドライブには勝てなかった。
しかし、そのメガドライブの後継として、セガが新たにリリースしたゲーム機が『セガサターン(1994)』である。
セガは、サターン販売の前年には、 世界初の3D対戦格闘ゲーム『バーチャファイター(1993)』をアーケード業界に投下し、成功をおさめていた。
3Dポリゴン(多角形)モデルで描かれたゲームキャラクターは、新しい時代をプレイする者たちに感じさせたという。
セガサターンは、家庭用ゲーム機においても、そういう3Dの世界観をうまく表現することを目的のひとつとしていた。
一方で古株メーカーであり、ユーザーのニーズをよく理解していたセガは、従来の2Dゲームを望むファンにも対応出来る多様性を実現するため、日立製作所製の「SH-2」というCPUを2基搭載。
これはようするに、当時はまだあまり例のなかったマルチプロセッサ方式であり、だからこその実際の高機能は、正しく次世代機の呼び名にふさわしいものだった。
ニンテンドー64。あくまでカセットに固執した任天堂
セガと、この時代のソニーと比べると、保守的な戦略をとって失敗したのが任天堂である。
勃発済みの次世代機戦争の只中に、満を持して任天堂が放り込んできた『ニンテンドー64』は、あくまでもカセットROMに拘り、素早いレスポンス(短いロード時間)など、強みも確かにあった。
特に採用されていた「R4300」というCPUは、 プレステのそれの4倍の処理性能を誇っていたと言われている。
ニンテンドー64は、少なくとも当時は、体感的に3D描写をもっとも上手く使いこなせるゲーム機だった。
ただし、CD-ROMメディアを利用した、大容量の長編を作るにはどうしても不利であった。
そして、それこそ多くのユーザーが最も待ち望んでいたものだった。
プレイステーション。もっとも可能性を広げたゲーム機の初代
サードパーティを味方につけたソニー
ソニーは電化製品メーカーとしては古株だが、ゲーム業界では新参者だった。
彼らが、おそらく世界で最も成功したビデオゲームプラットフォームである「プレイステーション」、すなわち『プレステ(1994)』を販売するまで経緯としてよく語られるのが、本来は任天堂と共同での開発だったという話。
CD-ROMを使うゲームを共同開発しようという話が任天堂との間に持ちあがるも、交渉が決裂し、結局自社で、独立に新ハードを出すに至ったという流れ。
実際のところは、ソニーは初めから、自社からハードを出す予定だったと見る、妙な陰謀説もある。
ソニータイマー(ソニー製品に仕掛けられてるという、保証期間の終わりから間もなく製品を内部から破壊するようになっているチップ)の都市伝説みたいなものかもしれないが。
とにもかくにも、ソニーはセガサターンにやや遅れながらも、いよいよプレステの初代作、いわゆる『PS1』を世に送り出す。
PS1は、3d描写に特化したチップの搭載など、セガサターンとコンセプト的には似通っていながらも、より3D描写を重視していたようである。
ただ、とりあえずソニーという会社独自の大きな強みとして、音楽CDの流通ノウハウを応用することで、比較的柔軟な商品供給モデルを構築することができたことがあった。
それはようするに、小売店からの要求に応じて、比較的、発注数を調整しやすく、売上が未知数な新規タイトルでも、新たに販売しやすいということを意味していた。
ナムコのリッジレーサーと鉄拳
結果的にソニーは、ファミコン時代に地に這いつくばされていた多くのサードパーティを味方にひきこむことができた。
特にセガとはアーケード業界で対立し、また任天堂の暴挙に怒りを貯めながら耐えていたナムコを、最初から味方につけれたのは幸運であった。
 「日本のゲーム機の歴史の始まり」任天堂、ナムコ、セガ、タイトー
「日本のゲーム機の歴史の始まり」任天堂、ナムコ、セガ、タイトー
ナムコがプレステと同時に、いわゆる「ローンチソフト」として販売したレースゲーム『リッジレーサー』は、3Dポリゴンを駆使し、リアルな車の乗り心地を再現したタイトルで、 新ハードの実力を世間に示す宣伝にもなった。
当時は完全に、セガのバーチャファイターの二番煎じではあったものの、3D格闘「鉄拳」も、それなりにPSに貢献したと言われる。
3Dで作られた仮想世界。アクアノートの休日、太陽のしっぽ
サードが参入しやすく、かつ3Dポリゴンというまだまだ未知数だった要素が合わさり、 プレステ2は多くの写真のタイトルが多く登場した。
もはやゲームと言えるのかすら怪しい、まさしく仮想体験を楽しむ『アクアノートの休日(1995)』や『太陽のしっぽ(1996)』などは、ただ目新しいだけというわけでなく、多くの人にVR世界の夢を抱かせることになったのではなかろうか。
自分の潜水艦で海を探検したり、原始人となって自由に生きたりと、そんな、とても叶えることなんて無理そうな夢であっても、仮想世界でなら実現できるのだ。
バイオハザードが巻き起こしたホラーゲームブーム
そして、そのようなゲームリアリティの中でも、特に人々に衝撃を与えたのが、カプコンの『バイオハザード(1996)』を初めとした、3Dポリゴンのホラーゲームだった。
まだまだ荒い3Dは、いわゆる「不気味の谷」という現象をよく引き起こす。
ようするに、ただ3Dのキャラを作ると、結構怖くなることが多かったのだ。
しかし、その未熟だった技術を逆手にとったのが、バイオハザードの他、スクウェアの『パラサイト・イヴ(1998)』や、コナミの『サイレントヒル(1999)』である。
セガサターンにも、『エネミー・ゼロ(1996)』や、マルチだが『Dの食卓(1995)』など、とにかくホラーが多かった。
待ち望まれていた長編RPG大作
意識していたにせよ、していなかったにせよ、多くの人が待ち望んでいたものが、壮大なストーリーのRPG だったというのは間違いない。
そしてCD-ROM形式によって大きく増えた容量が、それを可能にした。
言うなれば、かつて任天堂のビデオゲームが玩具以上になりえなかったのは、 ハード性能の制限のための、ちゃちな演出のせいだった。
人気を集めるアニメや映画。
それらのようなストーリーに、プレイという形でより深く入り込める新しい体験こそ、新しい時代の遊びであり、新しいビデオゲームの大目玉であった。
ソニー自身が、勝利の鍵がRPGというジャンルにあることを明らかに理解していた。
「アークザラッド(1995)」、「ポポロクロイス物語(1996)」、「ワイルドアームズ(1996)」など、かなり力を入れたと思われるタイトルも多い。
ファイナルファンタジーVII。勝利のキラータイトル
そして、いよいよプレステの勝利を決定したのが、スクウェアの大人気シリーズ最新作、『ファイナルファンタジーVII(1997)』のプレステでの販売であった。
FFというビッグタイトルは、まだ次世代機にそれほど馴染みのなかったライト層をも呼べるものであるが、ビッグタイトルゆえに、ハード性能を最大限に活かした作品であるはずというプレッシャーもかかっていた。
そこでファイナルファンタジーVIIは、従来の2D表現から脱却し、さらには容量の増加を存分に活かしたムービー表現を強化。
壮大なSF性の強い世界観を、当時の限界レベルで、見事に創造してみせたのだった。
そして、このキラータイトルの販売が、プレステの勝利を完全に確実なものとしたのであった。
ゲーム市場はどう変わったか
プレステとセガサターンはゲーム市場を大きく変えた。
音楽メディアとしても普及していたCD-ROMは、スタイリッシュなソニーやセガハードの見た目と相まって、カセット時代のおもちゃ感を薄め、大人も楽しめるクールな遊びというイメージも形成されたのである。
これに関しては前世代の王者である任天堂が、96年販売の新ハード、ニンテンドー64があくまでも優れた玩具という感じを拭いきれていないことが、比較的な意味でプラスにも働いたと思われる。
任天堂は販売戦略としては失敗したかもしれないが、大局的に見れば、というかゲーム業界全体からしてみれば、自らを人身御供にして、市場を拡大させてくれたと言えなくもない。
任天堂の強みは専用機でも問題なしなポテンシャルか
プレステの勝利は、実質的にはサードパーティの任天堂への下克上の成功劇的で、ソニーコンピューターエンターテイメント(SCE。ソニーのゲーム部門ブランド)というメーカーは最初からサードパーティに頼っているという印象がひたすら続いていくことになる。
一方で任天堂は、例えサードが一本も参入してくれなくても、任天堂専用機上等な姿勢でいれるくらいには、多くの長寿人気シリーズを自社で持っているし、なんだかんだ新しいゲーム体験を作るのが上手い。
ニンテンドー64よりもずっと負けハードとされている、後の『ゲームキューブ』や『Wii U』の時代にすら、『ピクミン(2001)』や『スプラトゥーン(2015)』を生み出せたのは、任天堂がソニーでなく任天堂であったからなのは確かな事実と思われる。