三原則を考えたアイザック・アシモフ自身が書いたロボットもの長編
SF発の概念としては、かなり有名かつ影響力の強い『ロボット三原則』を背景として、様々な話を展開した、アイザック・アシモフのロボットシリーズの長編の物語は、基本的には(最初は)ロボット嫌いのベイリ刑事と、ロボットの相棒R・ダニール・オリヴォーの物語から、だんだんとスケールを大きくして、最終的にはアシモフのもう1つの長編シリーズである『ファウンデーション』へと繋がる構成になっている。
ただしファウンデーションとの繋がりは完全に後付けとされていて、初期のシリーズではそれっぽい伏線とか特にない。また、明確に繋がりが意識されるようになってからの作は、両シリーズ(ロボットシリーズとファウンデーションシリーズ)ともに作風もけっこう変わるので人によっては「そうなるまでが面白い」という場合すら普通によくあると思う。
ここではファウンデーションシリーズと特に関係のなかった初期2作を紹介する。
鋼鉄都市。R・ダニール・オリヴォー初登場作
地球外のいくつかの惑星に人類が移住しはじめてから、幾千年。
もともと植民地のような存在であったいくつかの移住惑星が、地球から完全に独立し、むしろ文明発達が遅れた地球が、スペーサーと呼ばれる彼らに実質的に支配されている未来世界。
ある日地球の刑事ベイリは、なんとスペーサー達が住まう地球居住区の街で起きた殺人事件の調査を任されてしまう。スペーサー達の社会は完璧なセキュリティで守られている為、犯人は必ず地球人のはずだったのである。
さらに捜査の為、スペーサー達にロボットであるR・ダニール・オリヴォーを相棒としてつけられるベイリ。
そしてダニールと共に捜査を続ける内、ベイリはある疑惑を抱き始める。もしかすると全てはスペーサー達の陰謀なのではないかと。
というようなストーリーの、記念すべきロボットシリーズ長編第1作。
『鋼鉄都市』
ファウンデーションシリーズとの合流後も重要な役割を担うことになる、R・ダニール・オリヴォーの初登場作品でもある。
ロボット三原則とは?
1、ロボットは人間に危害を加えてはならない。
2、原則1に反しない限り、ロボットは人間の命令に従わなければならない。
3、原則1と2に反しない限り、ロボットは自己を守らなければならない。
設定された以上のルールが、ロボット三原則である。
アシモフ作品のロボットの設定の基本であるが、他作品や、現実のロボット工学にも、強い影響を与えてきたという。
この鋼鉄都市では、ベイリは三原則を疑う。
この流れは逆に、三原則のせいで、事件捜査が難航する続編「はだかの太陽」に繋がるようになっている。
ロボットと異星人達に支配された未来社会
人間の仕事をロボットが行うようになり、単純作業の労働者などはお役ごめん。とは、わりと現実になりつつある訳だが、この作品では、実際ロボットのせいで失業者が溢れた地球社会で、ロボットという存在自体がかなり敵視されている。
一方、偏見を持たず、労働力としてのロボットを存分に活用したスペーサー達の社会は経済的に発展を続け、いつの間にか支配下におかれてしまっていた地球。
アシモフは後にエッセイにて、「SF作家は未来の技術を描くのではなく、それによって現在とは変化した社会を描くのだ」と述べるのだが、まさにこの作品では独立した元地球人のスペーサー。ロボットがあらゆる労働力として使える環境と、確かにそうなっているかもしれない未来社会を描いている。
長寿は科学を停滞させるのか
スペーサーたちは周囲の環境などから、病原菌などを徹底的に取り除き、寿命かかなり伸びているという設定。この設定のために、スペーサーは、人間との接触を非常に恐れたりする。
アシモフは、この作品で、(例えば数百年レベルの)長い寿命は、停滞をもたらす可能性を描いている。
簡単に言うと、一人一人に与えられた時間が長くなると、問題などを個人で考え、自己完結する者ばかりとなり、知識などの共有が発生しづらくなってしまうのだとしている。
クラウドネットワークというようなシステム概念がある現在の視点から見ると、このスペーサーたちの設定はちょっと違和感あるかもしれない。ロボットは地球で嫌われ、スペーサー達には非常に身近な存在という設定があるから、なおさらだ。
現実ならば、ロボットが浸透した機械化社会の最大の強みは、むしろ情報共有性の高い精度であろう。
ロボットと人間の違いとは何か
アシモフが最も描きたかったのは単にロボットよりも、ロボットでない人間だったのかもしれない。
「ダニール、人間よりもずっと論理的に正しい選択が出来る君にはわからないかもしれないが、人間は時に論理的に正しくない選択こそをよしとする時があるんだ。今がその時だ」
作中ベイリはある場面でこんな事を言う。
それはベイリの奥さんと息子それぞれに危険が迫っている可能性があり、ベイリが息子を優先しようとした場面での事。その時、危険度などから奥さんの方を先にした方がよいのではないかと提案したダニールに、ベイリは上記のような台詞を告げる。
感情のせいか、計算能力の低さのせいか、とにかく人間はそれでも人間。決してロボットがそれと全く同じにはならないだろう。というアシモフの主張を感じる。と共に、このシーンが、終盤のある重要な場面で、重要な鍵となるのは、まったくお見事だと思う。
ミステリーとしてもなかなか
アシモフはミステリーにも造詣が深い。(特に『灰色の脳細胞』ことポワロシリーズで有名なアガサ・クリスティがお気に入りらしい)
そのためか彼のSF作品には、たびたびミステリー的な演出などが見られるが、この『鋼鉄都市』をはじめとしたロボットシリーズには特にその傾向が見られる。この小説は、れっきとした未来世界もののSFではあるが、その未来世界で描かれるのは、ミステリーでよく使われる題材である「凶器なき殺人事件」である。また主人公の刑事と相棒のロボットが、時に衝突しながらも、着々と捜査を進めていくプロットは、完全にバディもののそれ。
と、そういう感じで、まさしくこの『鋼鉄都市』は、SF、ミステリーのどちらのファンにもお薦めできる、極上のエンターテイメント作品となっている。
はだかの太陽。ロボット三原則ミステリーシリーズの2作目
アイザック・アシモフの、ロボット三原則を主なテーマとした、SFミステリーの長編シリーズ、いわゆるロボットシリーズの2作目。個人的にはロボットシリーズどころか、アシモフの作品の中でも、最高傑作級と思う。
1作目である「鋼鉄都市」と同じで、地球外の惑星を植民地とした(起源は地球である)宇宙人たち、彼らや彼らの築いたロボット文明を嫌う地球社会という世界観で、地球人の刑事イライジャ・ベイリと、パートナーのロボット、ダニール・オリヴォーの活躍が描かれている。
前作の舞台が地球であったのに対し、今作の舞台は、宇宙人が支配している50の惑星の1つ『ソラリア』。ソラリアは、他の宇宙国家からもかなり変わり種扱いされているほど、最もロボットに依存した社会で、そのような(機械文明がいくところまでいった場合に誕生しうるだろう)社会のメリット、デメリットも、この作品の1つのテーマとなっている。
また前作は、凶器の持ち込めない領域での殺人事件の話だったが、今作は、人間1人と三原則を守るロボットしかいないところで、なぜ殺人が起きたのかという話。さらに端的に言ってしまえば「ロボットは三原則を破って人を殺せるか、あるいは三原則を守るロボットをかいくぐって人を殺すことは可能か」というのが主題となる。
『はだかの太陽』
とりあえず、(作中での表現ではあるが)「動機がなく、手段がなく、少ない証拠は破棄され、唯一の証人(であるロボット)までもさっさと解体されてしまった事件」とだけ書くと、ミステリーとしてかなり面白そうではなかろうか。
陽電子頭脳とはどういうものか
まずこの作品のロボットには、共通して『陽電子頭脳』というものがあるという。
 「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか?
「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか? 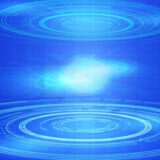 「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
それがどういうものにせよ、普通に何かルールに従ったり、行動したり、まるで意識を持っているように振る舞ったりするためには、人間の脳、神経系のようなものが必要なはずである。
少なくとも大量の原子が利用される我々のようなスケールでは、そのはずだろう。一般的にはハードSF(科学的にある程度納得できるようなSF)であるこの作品では、その辺りは常識として説明されもしない。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で  「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
しかし陽電子頭脳というのは、決して破壊ができないものなのだろうか。人間の脳が損傷を受けて、予期せぬパターンを発見することはよくある(時々それは精神病とかそういうふうに言われる)
ちなみに、かなりの程度で損傷したロボットに関して「ロボットの最先端国であるのに修理はできなかったのでしょうか」という問いがある。そして、ソラリアでもロボット学の最大の権威であるリービックは、それについては「無理」とあっさり答えている。とすると、陽電子頭脳の不可逆性は高く、再現性は低いのだろうか。
三原則はバグらないのか
前作でもそういう描写があるように、ロボット三原則に従う者は、「自己を守らなければならない」という第3条よりも先に、「人間に危害を加えてはならない」と「人間の命令に従わなければならない」という第1条、第2条が先に来ている。つまり、「お前は動くな、絶対にじっとしていろ」と命令した後に、ロボットを武器で傷つけたりする事はごく簡単である。
この物語のテーマとして、ロボット三原則が適用されているようなロボットは人を殺すことができるのか、というものがある。
しかし冷静に考えてみると、予期せぬ破壊が部分的に起こって、三原則を守れないロボットができることはないのだろうか。
三原則が何らかのプログラムによって成り立っているものならば、プログラムバグにより、それが崩壊することは必ずありえると思われる。
そもそも最初から、三原則に縛られないロボットを、悪意ある誰かが作る可能性を、考える者が宇宙人側に全然いないのは、さすがに不思議としか言いようがない。その辺りのことは、この話の作中でもほのめかされているにも関わらずである。
最も、例えば兵器として使う場合においては、三原則を守るロボットを作るのは、使用者の安全を確保するため必要とは推測できる。
「ロボットをいくら完璧にしても、人間が不完全であるために、完璧な社会を作ることはできない」とか、「人間にも三原則が本当は必要なのかもしれない」というようなセリフなどは意味深。
心の痛み
三原則の適用されたロボットに関して、少しでも元の状態から離れてしまったら、全てが崩壊するような構成を作っている設定なのかもしれない。実際作中でも、そうなのかと思わせるセリフがいくつかある。
つまり三原則も守れないような状態になる場合は、それが勝手に破壊されるような、あるいはロボット自身がそうなる可能性に直面した時に、自らを自己破壊するようになっているのかもしれない。
だが、その判断や自己破壊が間に合わない場合もあるだろう。実際この作品においても、人間にある2つの危険が差し迫る時に、どちらの危険がまだマシなのか、ということをロボットが判断する際、まるで人間がためらいを見せているかのように、しばらく硬直してしまったり、とかいう描写がある。
また、目の前の殺人や、そこまではいかなくとも、人間に危害が及ぶのをどうしても物理的に止められないために、ロボットがショックを受けるシーンがいくつかある。オリヴォーはそれを「おそらく人間が心を痛めるのと同じようなものでしょう」と語ったりもする。
ロボットの苦悩
とりあえず、あちこちに出てくる三原則的選択は面白い。
例えばダニールは、ベイリが、地球人を嫌う国家保安責任者代行のアトルビッシュについたある嘘に乗っかったのだが、それに関して以下のように言うわけである。「それは当然の選択でした。もし嘘を肯定すればそれは相手をやや傷つける結果になるが、しかしもしもそこで嘘を否定していたとしたらそれ以上にあなたが傷つけられることになっていたはず」
知能回路操作の恐怖
三原則を破れるような頭脳への変化もそうだが、それ以上にもっと恐ろしいシナリオパターンもあると思う。
それは記憶の改変。
ロボットに限らず、記憶とかの情報が神経系の状態によって作り出されたものならば、そこに意図的な操作を加えることで、見てもいない 、本当の話でもない情報を本当だと思う神経系を作れるのでないか、と考えると恐ろしい話でなかろうか。いくらでも嘘の事件のでっち上げが可能となる。
そのような偽の記憶を植え付ける場合、おそらくは人間よりもロボットに対してのほうが簡単であろう。この話の作中では、「地球ではロボットの証言は事件の根拠とされないが、ソラリアでは根拠として適用される」というような説明がある。
別に、そのようなハイテクロボットが浸透した社会を想定するまでもなく、単純に今、ネットとかにも偽情報が(意図されたものにせよ、そうでないにせよ)かなり溢れているとも言われる。もしかしたら、情報の発信源と、それがめぐる速度が大きくなれば大きくなるほど、大きな影響力のある嘘が誕生しやすい社会となるかもしれない。その時に、確かな証拠とされる個人個人の神経系がもたらす記憶に、監視するロボットたちの記録に、 (影響力の大きな)嘘が仕込まれてしまっていたら、どうなるのであろうか。
また、「地球では足跡は証拠として認められるのでしょう。あちらの方がロボットよりももっと人間とかけ離れていると思われるのに」というオリヴォーのセリフも少し興味深いか。足跡というか、つまり痕跡であろう。しかしこれはもうロボット関係なく、痕跡か証言か、という議論なような気もする。
ソラリアの社会は理想か
ソラリアの社会は、 ある意味で今、現実の我々がAI技術を使って目指している世界に近いような気がする。少なくとも理想とされている世界のパターンの1つに近い。
人間1人ずつに、自分のしたくないこと全てを、代わりに行ってくれるロボットたちが割り当てられていて、人間たちは本当に、気ままに自分の好きなことを好きなだけ出来る。
作中で、ソラリアの社会学者クェモットの、「この世界はつまり人類史上初めて、ピラミッド構造の社会階層の頂点にのみ人間がいる社会。ピラミッドのそれ以外の階層すべてにロボットが割り当てられているという社会」という表現があるが、まさにそんな感じと言えよう。
ただし、おそらく現実の多くの人にとっては微妙な、いくつかの余計な要素も存在している。
とりあえずこの世界では、遺伝子情報を基準とした間引き、あるいは調整があるように描かれている。ようするにこの世界には、デザイナーベビーしかいないと思われる。
もし自分は欲望まみれの人間で、なんでも自由にできるようなテクノロジーを手にしたら、その欲望のままにいろいろしたいと考えている人がいたら、この世界は微妙に違いない。というか、そういうふうになる可能性が高い人は、最初からこの世界には入れられない。
さらに、幼少時代の教育により人間同士が触れ合うことはとても気持ち悪いという先入観を強く植えつけられているために、人々は直に会うことをとても嫌う。基本的に彼らのコミュニケーションはすべて、自宅というにはあまりにも巨大なそれぞれの自宅内で、三次元映像を介して行われる。このあたりは想像の仕方によるだろうが、結構恐いと思う人もいるだろう。
例えばこのような社会の中に、もし突然悪意ある人が現れ、 殺意を持って近づいてきたらどうなるか。誰もが1人であるこの世界では、助けを求めることもできないだろう。この小説の物語自体が、そのような恐怖を示唆している。例え誰もが、ロボットのテクノロジーに守られているのだとしても、それが「バグのない」という奇跡のようなテクノロジーでない限り、危険はやがて発生しうる。
もっとも、ソラリアのような、言ってしまえば個人を最大に重視した社会が欲しいと望む人にとっては、上記のことなど些細な問題なのかもしれないが。
文字通りの地球外生命体?
実はソラリアに関して一番興味深い記述は、クェモットの「ソラリアには、人類が移住する前からすでに生命体が存在していたし、調整を行うまでもなく人類が住みやすい環境も整っていた」というようなセリフかもしれない。
一見それはなんてことないセリフだろうが、しかしこの作品に登場する宇宙人たちの起源は、基本的に全て地球にあるということを考えると、なかなか面白くなってこないだろうか。
 「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
深い説明はないが、後のアシモフのエッセイなどから読み取れる 彼の生命イメージから推測するに、そこで元々いたソラリアの生命体とは、おそらく植物とかだったのではないか、と思う。
少なくとも微生物ではなかったろうと思われる。それなら「人類が住みやすい環境が整っていた」という部分はなかったであろう。
ミステリーとして
ミステリーとしての出来は前作以上、というよりも、前作よりミステリー小説っぽさが増している。
前作はどちらかと言うとミステリー要素のあるSFという感じだったが、今作は完全に、SF要素のあるミステリーになっていると思う。シャーロック・ホームズよろしくな、「不可能なものを除外していって、残ったものがあるならそれが真実」というセリフまで完備。
登場人物の半分くらいは、まさしく、犯人候補として考え出されているような感じに思われなくもない。
とにかく、ミスリードを狙ってるような怪しさを前面に押し出しているように思う。
発生する事件も、凶器なき殺人。モニター越しでの毒殺未遂。無邪気な(とだけ表現するにはちょっと恐すぎる気もするが)子供が放ってきた毒の矢など、いかにもミステリー小説的。
何より終盤の、推理披露の際に、それまでの登場人物(という容疑者たち)を一堂に集めるシーンが、なんか笑っちゃう。まさしく、探偵小説の解答編。
これ以降のシリーズ作品について
噂によると、このロボットシリーズというのは元々3部作の予定だったらしい。
作中でも、「おそらくそうなるだろうな」と思わせるような記述がいくつかあるように、おそらくは最強の宇宙国家惑星オーロラを舞台とした3作目が想定されていたものと思われる。
しかしアシモフが、ノンフィクションに強い興味を抱くようになったために、一旦このシリーズもここで打ち切りのような形となる。
その後、多量なノンフィクションを経てから、実際、オーロラを舞台とした3作目は書かれたが、おそらくは(というかまず間違いなく)初期構想の内容からかなり変わっている。
個人的には、この作品以降のシリーズはわりと微妙。ファウンデーションシリーズと世界観が繋げられるが、まずそこから微妙。
これはファウンデーションシリーズとも合わせてのことだけど、次作以降、 あちらのシリーズよりかなり過去の話のはずなこちらのシリーズでも、やたらと歴史心理学の話が出てくる。人によっては、世界観の崩壊レベルの違和感あると思う。
ちなみに次回作では、ベイリと、ソラリアで彼が出会ったグレディアが恋人(というより愛人)のような関係になるが、それも今作の2人の距離感が好きな人には微妙かもしれない。





陽電子頭脳ってP型半導体製コンピュータの古い翻訳なのかな、と高校生ぐらいのときに思ったな。
この記事を書いた当時にはまだ読んでなかったのですけど、アシモフのエッセイの1つ(地球から宇宙へ)にある陽電子頭脳(positronic brain)に関するQ&Aはちょっと興味深かったです。
「Q陽電子ロボットとは何ですか?→A陽電子頭脳を持っているロボットさ。
Q陽電子頭脳とは何ですか?→A生きている人間の頭脳では電子が移動するのに対して、陽電子が移動する頭脳さ。
Qそういう目的のために、電子工学より陽電子工学の方がすぐれているというのはなぜ?→A知らん。
Q陽電子が電子と結合して物凄いエネルギーになり、ロボットが溶けてどろどろの金属になってしまうのを、どうやって防ぐのですか?→Aまったく見当もつかないね」