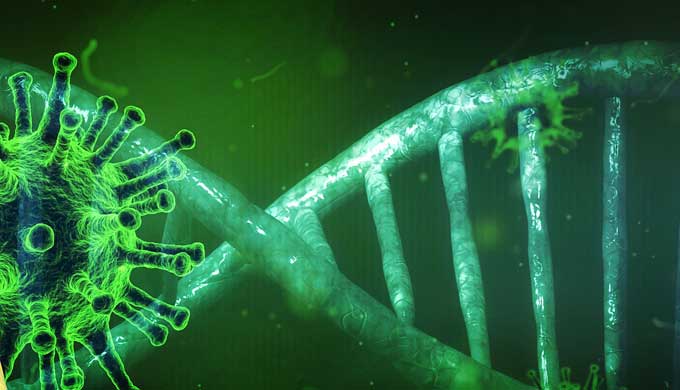モンスター、ハイテク、サイエンスの暴走
リンカーン・チャイルド(Lincoln Child)は、基本的にSF要素のあるミステリーやアクションをよく書く作家である。
基本的に現代を舞台としたサイエンス、テクノロジーの暴走みたいな作品が多いが、特に有名なのはモンスターを描いた物語か。
レリック
巨大な博物館があって、 ネズミなどがまったく見られず、時々猫とかが行方不明になったり、何か奇妙なものを見たというような証言があれば、確かに、そこには怪物が潜んでいる、というような噂が流れてもおかしくはない。
そういう都市伝説的なものがある大きい博物館を舞台に、連続して起こる怪奇的な殺人事件と、その犯人である怪物と、科学者や警察官との攻防を描いたSF小説。
構成的には、前半ミステリー、後半モンスターパニックみたいな感じの流れであり、その両ジャンルのどちらも好きという人には、かなりお勧めできる内容。
ただ、SFミステリーというよりは、ミステリーぽい雰囲気のSFという感じ。
普通のミステリーで、何かの事件の犯人はどこの誰だみたいなことが謎として描かれるように、博物館に潜んでいるという怪物はどのような存在なのか、というのがメインの謎として描かれる。
謎のFBI捜査官ペンダーガストの魅力
数年前に別の地域で起きた、似たような手口の未解決事件を担当していた過去を持ち、その犯人を追い続けているという設定で、 物語の要所要所で活躍するFBI捜査官ペンダーガスト。
この男自体が、謎の人物みたいな感じで描かれているのが、なかなか面白いところである。
FBI当局の間では、ちょっと変わり者という評判だが、能力自体は優秀なように描かれる。
作中で、シャーロック・ホームズ的な推理をまったく自然としてみせた時は、まさしくそういうふうに例えられたりもする。
そして、そう言われてみれば、確かにこのキャラはホームズ的なキャラかもしれない。
よくシェイクスピアやギリシアの哲学者などを引用したり、絵画に詳しかったりと、芸術方面の知識が深そうな一方で、今は亡き妻と夫婦揃ってハンターだったこともあるという。
とにかくいろいろと濃いキャラクター。
未知の生物の調査という謎解き
時々、古生物学と未知動物学の調査の記録とかは、まるで探偵小説のようと例えられることがあるが、まさにそういうのを小説として描いてみました的な感じである。
呪われている謎の木箱と、その周辺で起きる猟奇的殺人事件、というだけなら普通のミステリーのようである。
しかしそこに、「絶滅したと考えられるジャングル奥地の種族の探索の記録」、「遺体から検出されたDNAサンプルの中に、なぜか人間と爬虫類の遺伝子が入り混じっているという解析結果」、「明らかに鳥(というより恐竜)のものかもしれないと言っていいような鉤爪の傷痕」などといった、 未確認動物好きの心にはよく刺さるであろう謎が次々と絡んでくる。
ただ物語全体としては、怪物の謎解きの比率が大きく、怪物との戦いを期待する人には微妙かもしれない。
カリスト効果のアイデア
この作品の最大のポイントは、まず間違いなく、作中の生物学者フロックが提唱している「カリスト効果」であろう。
彼自身が、「フラクタル進化」という著書で、それを一般にも広めているという設定(そして彼は、その著書のせいで、ちょっと頭がイっちゃってるというふうに噂されてしまっているという設定)
カリストとはは、ギリシア神話に登場するニュンペー(下級女神)の一人。もとは美しい乙女で女神アルテミスに仕えていた。しかしある時、神々の父ゼウスに見初められ、彼に騙された挙げ句、嫉妬したゼウスの妻ヘーラーにより、あるいは純潔を好むアルテミスの怒りに触れ、呪いにより怪物(クマ?)に変えられてしまったとされる。
またフラクタルは、数学者ブノワ・マンデルブロ(Benoît B. Mandelbrot。1924~2010)が導入したという幾何学概念。何らかの全体の部分から、特定の方法で部分をとっていったとして、結局その特定の部分に、全体と同じような幾何的構成要素が残っているようなパターンのこと。自然界に多く見られるということで、生物学の分野でもよく取り上げられる。例えばフラクタルの具体的な例としてよく挙げられるのが海岸線。通常、複雑とされるものであっても、拡大していくと単純な部分が現れるものであるが、海岸線はいくら拡大しても、前のスケールでは無視できた、さらに微細な複雑形状が現れるとされる。ただし現実のものは、おそらくなんでも、実際的な極限として原子レベルまで考慮にいれると厄介である。
とにかくそのカリスト効果は、進化生物学と、物理的限界による予測不可能な複雑性の理論であるカオス理論を、合わせた研究により示された概念とされている。
その概要としては、進化は基本的に徐々に起こるものだが、時に飛躍的なものとなり、異常種とも言える怪物(モンスター)を生み出す。
恐るべき捕食者でもあるそのモンスターは、大規模な絶滅の原因にもなり、進化の方向を分岐させる、というようなもの。
作中、フロック自身の「わたしは恐竜が、異常種の殺戮によって滅びたのだと信じている」というようなセリフもある。
そしてそのような恐ろしいモンスターは、当然、自分の餌となる生物群をあっという間に絶滅させてしまうため、自分たちもその後すぐに絶滅する。
生存期間がわずかな期間だから、後に化石としても残りにくい。
カリスト効果の設定は、二人の作者、特にアイデアを提供したというリンカーン・チャイルドのお気に入りらしく、彼の他の小説とかでも出てきたりする。
また、カリスト効果という名称自体は、その理論を面白がったマスコミが勝手に名付けたという設定。
ちなみにそのフロックという博士も、すべてが怪物の仕業だとはっきり確定したところで、恐怖などの感情とともに、少し喜びを見せたりといった、マッドサイエンティスト的な気質が描かれたりしていて、キャラクター的に魅力となっている。
それは自然においてどのような役目を担うか
これもまた作中でフロックが語っているようなことだが、カリスト効果により生み出されるモンスターも自然システムの一部であるとするなら、その役割はおそらく、繁栄しすぎた生物の消去。
しかしそうだとするなら、人間は果たして繁栄しすぎた生物なのだろうか。
人間は繁栄しすぎというより、生態系を乱しすぎる生物というようなイメージも強い。
しかしそうだとしても、(少なくとも20世紀までは)小型生物への影響力は大したものではなかったろう(?)。
我々は、確かに陸上に限っては、我々が保護区と定義しているような地域以外から、大型動物をほとんど消滅させてしまったが、小型生物は今でもありとあらゆる場所にいる。
おそらく我々の多くが最も絶滅してほしいと願っているゴキブリに関しても、我々は物量作戦で押されっぱなしというような状況と言える。
そもそも微生物というものを考慮にいれないとしても、繁栄しているというのなら、ゴキブリ含む節足動物の昆虫がまさにそうではなかろうか。
昆虫のカリストモンスターはこれまでに出現したことがないのだろうか。
我々は、自分たちの種である人間を、やたら特別扱いしたがるという話があるが、それと同じくらいに、我々は我々と同じようなスケールの大型動物たちを、特別な枠組みとして考えたがる傾向にあるから、こういう問題はより難しい。
中間種のシミュレーション
カリスト効果の研究にも存分に利用されたという、ある生物種と、別の生物種の、進化学的中間種をシミュレーションするためのソフトウェアが出てくるが、これもなかなか興味深い。
そのソフトを開発したプログラマーは、フロックの支援を受けていたわけだが、カリスト効果には否定的だった。
しかしこのソフトによって、時に特定の生物と生物の間の中間種が、普通には考えにくいようなグロテスクなモンスターになる可能性が示されたことが、カリスト効果の根拠の一つになっているという皮肉も、なかなか面白いであろう。
オーロラの魔獣
アラスカの雪原地帯を舞台に、地球温暖化の影響や、古生物を研究している科学者のチームと、ドキュメンタリー番組を撮影しに来たテレビスタッフたちが、氷付け状態から蘇らせてしまった怪物を描くSF。
タイトルはちょっと微妙な感じである。
確かに、オーロラは物語のガジェットのひとつにはなっているが、肝心の怪物との関連性は薄い。
また、この作者の作風がわりとそうだが、怪物が出てくる、紛れもない生物学SFでありながら、その怪物との戦いのシーンなどは比較的少なめ。
多くの部分は、その怪物がいったいどのような存在か、という謎解きであり、ミステリー的な雰囲気が強い。
それと、怪物が実際に暴れだすのと、怪物の存在を科学者たちを突き止めるシーンがほとんど同じくらいのタイミング。
そういうわけで、この手の物語にありがちな、がんばってみんなに怪物に関する警戒を促すが、みんな信じてくれない、というような場面はほぼ無い。
人によっては、その後のカタルシス的なものが足りないと感じるかもしれない。
そもそも、怪物が実際にその姿を晒すまで、当の科学者たちも、自分たちの考えに対し、けっこう半信半疑という感じで描かれている。
そこはある意味、リアルと言えるかもしれない。
神秘的な面が強調されているモンスター
出てくる怪物は異形の巨大スミロドン(サーベルタイガー)という感じで、同作者の以前の作であるレリックでも登場している、「カリスト効果」という理論が適用できる、怪物種という設定。
ただし今作は、怪物の科学的側面より、むしろ神秘的な面が強調されている感じがする。
 レリック、ユートピア、マウント・ドラゴン「リンカーン・チャイルド」
レリック、ユートピア、マウント・ドラゴン「リンカーン・チャイルド」
銃もあまり効かないし、すぐさま再生する回復能力を持つのだが、ある弱点を持っている。
しかし、その弱点がどういう原理に由来しているものなのかが謎のままに終わってしまう。
重要キャラである、テュニット(ドーセット文化の人?)という、古いイヌイット族の生き残りの老人ウースーグークは、その怪物を、作中通して、自分たちの文化に伝えられる恐ろしい悪魔クールシュクだと信じる。
そして作中通して、その可能性はあまり否定されない。
 「イヌイット」かつてエスキモーと呼ばれた、北の地域の先住民たち
「イヌイット」かつてエスキモーと呼ばれた、北の地域の先住民たち
個人的には「(カリスト効果は)継承者であるフロックが失踪して以来、支持者はいなくなったと思ってた」というようなセリフがあったのが気になった。
(そこまで表沙汰にはなっていないぽいとはいえ)レリックの事件などがあった世界観だというのに、カリスト効果は、まだちょっとトンデモ気味なイメージだったりするのだろうか。
現代社会で孤独な自然主義者
典型的なB級モンスターパニック的設定の、シンプル一辺倒かと思いきや、これがなかなか、上手いこと練られたプロットとなっている。
最初、小さな集落の最後のシャーマンとして生きているウースーグークが、不吉な霊的存在の怒りを理解し、それをどうにか儀式で抑え込もうとするシーンから物語は始まる。
そしてウースーグークは、氷河に隠れていた洞窟で、氷漬けとなったスミロドン(と最初は考えていた生物)を発見した科学者たちに警告をする。
このウースーグークの語る神話が、怪物の演出のひとつにもなっているわけだが、さらに彼は、冷戦時代からの基地での怪事件にも関わっていたり、物語前から現実に怪物を知る唯一の存在として、物語の要所要所で重要な役割を担う。
しかし、ある手がかりから、テュニットこそが、真実を知っていると考えた生態学者のマーシャルが、ウースーグークに助けを求めにきた場面。
「あなたたちは世界に闇をもたらした。私は警告をしたが、あなたたちは聞いてくれなかった」
というウースーグークに対し、マーシャルは以下のように返す。
「我々の無知の代償としては、残虐な死なんてあまりにも高すぎないでしょうか」
このやりとりは案外考えさせられるものかもしれない。
実際の我々の歴史において、無知というものがもたらし続けている、恐ろしい悲劇を考えるなら。
youtubeが話題に出てくるなど、これは少なくとも、書かれた時点でのハイテクな現代を描いた物語である。
その現代にあって、どちらかと言うと自然回帰主義に対する、科学の冷たさが描かれているようにも思う。
それと、単純に話をエンタメ的に盛り上げるセリフとして、「私が戻ってきた理由のひとつは、あなたがあれをクマよりも大きいと言っていたことだ。50年前の悲劇を引き起こしたあれは、キツネと同じサイズだった」というのもある。
緊張感を高める場面としてはなかなかであろう。
生物学に無知な人が、生物学のドキュメンタリーを監督することがあるのだろうか
作中に登場する、ドキュメンタリー番組の監督が、結構やばいやつとして描かれている。
平時の段階からすでに、自分の思い通りの演技をしてくれない科学者たちに研究室を立ち去ってもらい、科学者に変装させたスタッフを使って科学ドキュメンタリーの撮影に臨むという、エンターテイナー(笑)っぷりを存分に発揮。
「1分ごとに50万ドルを支払っているスポンサーたちが、何のひねりもない「驚いた」なんてセリフだけで、満足すると思うかね」
ちょっと、なるほどである(?)
怪物が現れ、死人が出ても、逆にそれをリアル惨劇ドキュメンタリーにしようとするような人。
こんなだから、作中でもしっかりと、「お前こそ真の怪物だ」とツッコまれている。
しかし、現実でもこういう奴が、実はけっこう世間的には人気だったりすると嫌だな。
ただ、いくらなんでも、生物学のドキュメンタリーを、自分の最高傑作にしようなんて考える映像監督が、生物学研究というものに対して無知であるというようなこと、逆にありえるのだろうか。
究極的な冷凍
SF的には、今作で最も重要なガジェットは、自然クライオニクスとも言うべき、「究極的な冷凍(ターミナルフリーズ)」であろう。
非常に急速に凍結されることにより、細胞に対する致命的な結晶構造がそれほど大きく形成されないまま、冷凍保存されてしまった、というような推測である。
ようするに、通常氷づけになってしまうような場合、その過程で細胞はどうしようもないほど傷ついてしまうが、その過程が非常に高速であったために、それほど傷つくことなく、生きたまま冷凍された、という設定。
しかし、そのような自然の冷凍保存の、実際の有用性などに関しても、わりと謎という感じで終わる。
結局、普通の生物はそのような急速冷凍でも、生きたまま保存されることはない。
長い間氷づけで生きていて、かつ溶けた時に復活できたのは、あくまでも怪物自身の驚異的な生命力のおかげだろう、というような結論も、作中で出されている。
怪物への興味
怪物は、かなり特殊化した組成の白血球により、かなり高い傷の修復能力を持っていて、かつ体内に、麻酔の役割を果たすような化学成分を生成できるために、痛みにも強い。
ただこのような段階に来るともはや、意図的な感がかなり強くなってしまってる感じもする。
驚異的な生命力を持って、通常の多細胞生物の神経系なら完全に機能が破壊されてしまうであろう高い高圧電流を浴びても、全然無事といった場面もある。
より興味深いのは、やはりこの生物が、いきなり凶暴だったというよりも、単に遊んでいるのではないか、と推測されたりもすること。
それに、怒って人を殺しはするが、別に食べたりはしないということ。
結局最後に、その怪物を倒せたことについても、空腹で弱っていた可能性もある、とされているが、何も食べるものがなかったのだろうか?
この怪物がカリスト効果によるものなら、獰猛な捕食者のはずである。
そういう感じで、結局これがどのような生物だったのかはなかなか考える余地があるような感じで終わっている
ミステリーとしては謎が残るために微妙な人も多いであろうが、案外SFとしては、 考察の余地がいくつも残る、このような演出で正解なのかもしれない。
ユートピア
『メタネット』 というAIのネットワークが管理するハイテクテーマパークを舞台に、パーク関係者たち(+1)と、 テロリストグループとの戦いと駆け引きを描いたSFサスペンス。
部屋に作ったハイテク領域をテーマとしたSF系作品としては、暴走した機械が人間に害を及ぼすという、ある意味典型的プロットとは異なり、それを悪意あるプログラムを持って、恐ろしい武器とする人間たちを描いている。
この小説には三つの側面があると思う。
まず、息詰まるような駆け引きを描いたエンターテイメントとしての面(1日どころか、数時間の話という短い時間設定が、サスペンス的な緊張感をかなり高めているとも思う)。
次に、セキュリティという概念に関する問題提起。
そして、タイトル通りに、理想郷(ユートピア)とはいったい何か、という問いかけ。
また、テーマパークの、様々な仮想体験アトラクションのアイデアが散りばめられてもいて、そこもいろいろ考察の余地がある。
作者はよく、作風が似ているとされるマイクル・クライトンと比べられているらしいが、この作品はテーマ的にはクライトンの、小説ではなく映画であるウエストワールドと似ている。
テーマパークの裏側の人間関係
この作者の作品の中では、キャラクターや、その人間関係の設定がわりとよく練られてる方と思う。
主人公であろうウォーンの元恋人で、エリート街道をひたすら走ってきたものの、意外といろいろ悩みを抱えるセーラ。
それに、味方側では唯一の一般客であった、わりと謎の男プールなんかが、個人的には好きなキャラ。
ちなみに主人公ウォーンは、話の肝と思いきや、単に1ガジェット的なものとも言える程度のメタネットの開発者である
経営者、母親、得意不得意
セーラは、人命第一というよりは、いろいろな責任問題や損得などを第一として考えているような、なかなかドライな有能経営者というような感じだが、テロリストにいいようにやられるうちに、だんだんと弱さもさらけ出してしまう。
ウォーンと、彼の亡き妻との間の娘ジョージアとの関係性は、いろいろ興味深かったりする。
セーラは、ジョージアとよい関係を築くことができなかったということは自覚していて、その原因を「セーラが母親としての時間を長く用意してくれるようなタイプではないことを、ジョージアが最初から見抜いていたからだろう」などと分析したりもしている。
こういう問題はわりと現実にもあるだろう。
仕事と、家族との時間の両立。
仕事が生き甲斐という人も、とにかく家族を最低限養うために働きまくっているという人も、世の中に大勢いるだろうが、結局そのせいで、親が一緒にいてほしい子供の願いが儚くなったりしてしまう。
とりあえずエンタメ的には、終盤、ある事実をウォーンから伝えられ、敗北を認めてしまっていた心境から一転、怒りの気持ちを取り戻したかのようなシーンがなかなか熱かったように思うが、正直その後に、もうちょっと活躍させてほしかった気はする。
ひとりアクションシーンを担う軍人キャラ
プールは、「レリック」のペンダーガスト的な、ちょっと変人な感じの善人という感じである。
軍隊経験のあるボディガード。
とても気に入っていたアトラクションが、 爆破されてしまったことでその原理を知ってしまったことに怒りを感じたりするところが、なんかよかった。
テロリストグループのある狙いに関して、 今日一日それを防ぎ続けてさえくれれば無期限のフリーパスをあげる、というセーラのセリフがあるが、最後にこの件がどうなったのかは必見である。
理想の世界なんてありえるか
セーラとジョージアの問題なども、結局はそういうことだろうが、そもそも社会の発展と、家庭の温かさを両立するということ自体が、通常は不可能である。
というか不可能なはずだったが、人工知能産業の発展が、事態を変えそうなのは、現実でもそうであろう。
まさに機械的に作られた楽園である。
人間が生きるための苦労仕事を、かつて奴隷が担っていたように、機械たちが様々なことを行ってくれる。
確かにそれなら、人間たちにとっては理想的な世界になるのかもしれない。
だがそもそもそんな楽園を本当に作ることができるのかどうか、というような問いかけが、この作品には含まれているように思う。
これはまあ、これまで社会の根本原理として、共産主義での民主主義だのいろいろなものが、最も理想として考え出されてはきたものの、結局いつも新しい問題が現れてくる、というような話の延長でもあるかもしれない。
恐ろしい悪意が現れた時
この小説がまさにそういう話だが、たとえ機械が管理する世界であっても、機械を作り、動作プログラムを構築しているのが人間である限り、そこに悪意が発生した時の問題が生じてしまう。
この話では、ハイテクテーマパークの中でいろいろな仮想体験が描かれている。
そして、店の店員をしているロボットが突然人を襲ったり、それどころか普通にアトラクションで爆発が起きても、 そのような演出を楽しみに来ている客たちは、それを何かの演出だと考えてしまったりする。
それのせいで実際に怪我をしたり、死んでしまうまで。
実際にそういう仮想空間で楽しめるようになったとしよう。
そうなった時に、かっこいいアクション映画の体験をするつもりで、偽物のはずの爆発が本物にすり替えられてしまっていたらどうなってしまうか。
そんな未来にあるような話じゃなくても、例えば普通に今もあるような、人と握手が出来たりするロボット。
そういうロボットに爆弾でも仕掛けられていたら。
そういうのはありえる話である。
システムのどこかで、人間の手が介入している限りは。
では全てを機械任せにしてしまった場合はどうか。
これに関しては、もっと多くのSFが語っているところであるが、この作品では、その点はあまり触れられない。
ロボットの特攻シーンに関して
昔なにかの本で、 ある意味では日本人よりもアメリカ人の方が機械に対する熱意が強いという話が書かれていたのを見たことがある。
どういうことかと言うと、日本人はロボットをより本格的に人工生物として扱いたがる節があり、アメリカ人はどちらかと言うとドライな考え方で、あくまでも機械は人間のための道具であると考える傾向が強いのだという。
つまりアメリカ人にとっては、機械は楽をするための道具で、楽になりたいという熱意もアメリカ人は強いのだとか。
この作品の終盤。
主人公が、かわいがっていたロボットの犬を、爆弾持たせて特攻させるシーンがある。
この特攻作戦は失敗しかけるも、ロボット犬が意図されていないような行動をとったおかげで、結局うまくいくという場面。
これは、ロボットに対する思想の違いによって、いろいろな解釈のズレが生じやすいと思う。
マウント・ドラゴン
タイトルにもなっている「マウントドラゴン」とは、作中に登場する、遺伝子工学と、危険な細菌を扱う目的で作られた、最先端の研究施設。
作中での表現を借りるなら、「遺伝子工学の行く末」というのが、この小説の最大のテーマと思う。
後々の世代にも残るような、意図的な遺伝的変異(直接的な遺伝子の改変)の中でも、特に絶滅にも繋がりかねないような危険な操作を、核兵器よりも恐ろしい産物として描いている。
また、恐ろしい致死性を誇る人工ウイルスが、非常に重要なガジェット(要素)となっているが、パンデミック(病原菌の大流行)は描かれない。
物語としては、パンデミックの話じゃなくて、パンデミックが起こらないように、なんとか頑張る話。
あるいは、人類を滅ぼしかねないくらいの、恐ろしいウイルスの研究をめぐるサスペンス的なもの。
遺伝子工学は、本当に恐ろしい兵器となりうるか
作中では、ボノボ(ピグミーチンパンジー)に発見された、対インフルエンザの免疫を作る遺伝子「Xフル」を、人間の遺伝子配列に含ませようという研究が行われている設定。
さらに、未来の世代にも残るように、DNAにその遺伝子情報を、なんとか安全にねじ込む研究がされている。
しかし必要なウイルスの無害化がなかなかできず、結果「Xフル2」という、より恐ろしい人工ウイルスまで誕生してしまう。
 DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」 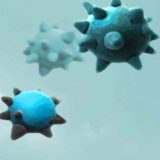 「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
ここまであくまでフィクションだが、決して、現実にも起こらないと断言できるような話でもないであろう。
少なくとも現在、遺伝子内の、人間の欠陥とされるものに繋がりそうな配列は除去、そして有益そうな遺伝情報は選択的に埋め込めれるのが、むしろ理想と考えられることが多い。
作中で、「いつか世界には、最初から全てにおいて優秀な美男美女しかいなくなる」というようなセリフもあるが、これはまさしく、そうなりそうとよりも、そういうのが理想的だというような感じなのが恐怖、という人もいるのでなかろうか。
実際に、容姿とか、遺伝病とか、そういうものに苦しまされている人は多い。
自分の子供にはそういう思いを味わってほしくない、という人も多いと思う。
これは倫理観の問題にすぎないのだろうか。
例えば、自分に何か、遺伝的かつ気に入らない要素があるとする。
時間の針を戻して、あなたの起源となった最初の胚細胞の遺伝コードから、その気に入らない様子を除去したとする。
すると、その改変された時空でのあなたは、確かに今あなたが気に入らないと思っている要素を持っていないかもしれない。
だけど、それは自分なのだろうか。
世の中には、整形というものが気に入らない人がいるらしい。
だが自分の体の形を物理的に変えるくらい、自分の意識に繋がりかねない遺伝情報などを直接改変するのに比べたら、大した変化でもないであろう。
遺伝子のデザイン的改変なんて、もう本当にその人自身を別人へと変えているイメージが強い。
 「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
なんてことを言ってみても、本当にそういうものに苦しんでいる人にとっては、「それは自分のことでないからだ」という反論があるかもしれないが。
もっとも、これも技術的な問題にすぎないのかもしれない。
分裂を始める前の最初の細胞の方が、そういう改変を行いやすいのだけはまず間違いない。
だがやがて、ある程度自分の意識を持つくらい成長してからでも、自分という存在を改変するのかどうか、その程度まで選択できるほどに、このようなコントロール技術は進歩する可能性もある。
 「幹細胞」ES、iPS細胞とは何か。分化とテロメア。再生医療への利用
「幹細胞」ES、iPS細胞とは何か。分化とテロメア。再生医療への利用
遺伝子工学技術のみならず、遺伝子工学ビジネスも、この小説のテーマであろう。
この作品では、結局金のためならば何でもする人間は必ずいるからこそ、使い方を誤った場合に危険な技術は恐ろしいのだ、というような語られ方もよくしている。
仮に上記のような技術が実現されても、社会が平等になるかはまた別問題というわけだ。
超サイバーシステムでの会社管理
マウントドラゴンを所有しているジーンダイン社の社長スコープスは、実質的に物語上の悪役なんだけど、この人自身、科学者としてなかなか魅力的な方。
おそらく、大金を前に金の亡者になってしまった系だが、自分が開発したサイバーシステムが凄すぎて(それを商品にすればいいのに)自分専用にしちゃう人。
最も、そのシステムを会社全体の管理に使っているから、利益には繋がっているのかもしれないが。
「彼は寝もしないで、会社のサイバー空間をひたすらにうろつき、全ての会社員に口出しする」
というように表現されたりしているが、経営者側の視点からしてみれば、これはまさしく理想的なものなのかもしれない。
 「ネットワークの仕組みの基礎知識」OSI参照モデル、IPアドレスとは何か
「ネットワークの仕組みの基礎知識」OSI参照モデル、IPアドレスとは何か
恐ろしいウイルスを人類が使うこと
スコープスの古い友人で、かつての研究仲間でもありながら、遺伝子操作技術の未来を危惧し、ジーンダイン社と敵対しているレバインというキャラがいる。
このレバインが、そのような危険なウイルスがマウントドラゴンに存在することを、マスコミの前で発表するシーンでこそ、いろいろ考えさせられるかもしれない。
ウイルスが広がることもそうだが、(そこまで強力なこと自体が、今はまだSFかもだが)それこそ人類を本当に滅ぼしかねないような危険なウイルスが世間にあまり知られていない状態で、一企業とかに管理されていることが、告発されたらいったいどうなるのか。
世間はいったいどういう反応を示すだろうか、自分ならいったいどういう反応を示すだろうか、というようなこと。
どこかの研究施設で、公表されないまま、「潜伏期間一週間。初期症状から死に至るまで5分から2時間程度。最終的に脳が爆発する。さらに通常の風邪より感染力が強い。当然ながら致死率100%」なんてウイルスが普通にあって、そのことがついに(もちろん社会的信用のある)誰かに公表されたら、世間はどのくらい同様するだろうか。
それとも案外、「まあさすがに、管理されてるし大丈夫だろ」みたいな感じであっさりすまされるだろうか。
だが例え安全な施設に厳重に管理されていると言っても、とんでもなく危険な病原菌を、結局は人間が管理していることには変わりがない。
いつかはすべて機械が管理するというような日が来るかもしれないが、それはそれで心配であろう。
「もし、管理者自身がひどく神経をおかしくして、誰かを殺したい衝動にでもかられてしまったら。そして、恐ろしい殺人兵器にもなれるウイルスを外部へと持ち出すことになんてなってしまったら」
というようなセリフも(レバインのじゃないけど)作中にあるが、現実のシナリオとしてはありうる。
感情を封じれる人ばかり集められるのか
危険なエリアで密閉服が破けるトラブルのシーンが、わりと前半にある。
そして、そういう決まりだし、覚悟は決まっているはずだろうに、何人かが取り乱し、挙句、さらに犠牲者を増やしてしまうというような事態が描かれている。
そこの描写はけっこう印象的だったと思う。
(少なくとも人類規模での)正しい選択と言えば、ウイルスに感染した疑いのある者を、やはり確認して、感染していたなら潔く死なせるしかない。
状況をごく単純化すれば、1人を殺せば何十億人という人が助かるという状況で、その1人の命を奪うことは果たして正しいのか、みたいな感じだ。
むしろこの辺りは、あまりリアルではないのだと考えたい。
このような、危険な病原菌を扱っているような研究所で働く職員が、万が一の時の覚悟を決めていないというような話が本当だったら、それだけでちょっと怖いような気もしないでもない。
というか、そういう覚悟を持っている人を集められないのなら、そんな研究所、始めるべきではないだろう。
だが、この世界にはお金というものがあるのである。
裏主人公、道化師の戦い
作中、レバインに協力する謎のハッカー『道化師』の正体が、作中の誰なのか、というのを推理するミステリー的要素があるのかと思いきや、そんなことはなかった。
「なぜ直接ここに来て手伝ってくれないんだ。君は臆病者じゃないと私は知っているぞ」というレバインに対し、彼はただサリドマイドという物質の化学式だけを伝えてくる。
そしてレバインが「そういうことか。だからそんなに製薬会社を憎んでいるのか」と理解するシーンは、ある意味では、この物語の中で一番胸が熱くなる場面だと思う。
これは現実の話だが、サリドマイドは、免疫系の強化や、催眠効果があるという化学合成物質。
1950年代くらいにそれを利用した薬が登場したが、妊婦が服用した場合に、 生まれてくる子供に大きな副作用が生じるとして1960年代に問題視されたというもの。
特に妊娠初期にこの薬が服用された場合に生まれた子供の多くが死んでしまい、死ななかった者も、手足や内臓、感覚器官などに障害を持って生まれてくることが多かったそうである。
また、そのようなサリドマイドが原因と見られる障害を生まれ持った人は、サリドマイド児とも呼ばれる。
レバインは、道化師の正体を(どうしても直接的には手伝えないということもあって)サリドマイド児と考えたが、そこは明確に明かされないのが、様々な解釈を残す余地になったと思う。
(例えば日本は特にその傾向が強かったらしい)障害児は親の血筋のせいにされ、国もなかなか非を認めず、サリドマイド児だけでなく、その家族一同も酷い目にあったというのは、わりと聞く話である。
むしろ個人的には(年代的に)薬の直接の被害者よりさらに子供世代の誰かぽく思った。
新しいヒーローのタイプ
意図的なのかどうかはわからないが、この作品では明らかに、その姿も本名も一切出てこない道化師が、1番かっこよく活躍を描かれてるような気がする(文字通り裏主人公的な感じ)
現実ではあまり冴えないタイプだったりするような人が、ヒーロー的な活躍をする架空の話は、大昔からあると思う。
そして共感しながらも、その活躍ぶりに元気をもらったりする人も多いと思う。
だけどファンタジーでもない限り、そういう活躍って、なりふり構わなかったら実際できそうなことばかりでもある(おそらくそうでないと結局、共感しにくくなるから)
道化師はコンピューターネットの時代に登場した、まさしく新しいヒーロータイプじゃないかなって思う。