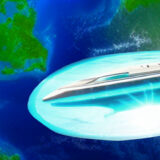失われた世界
ホームズシリーズで有名なアーサー・コナン・ドイル(Arthur Ignatius Conan Doyle)が生んだ、ジョージ・エドワード・チャレンジャー(George Edward Challenger)というキャラクターは、 その容姿的にも普通にものすごく頭の大きな人物とされている。世間的にはかなりの変人学者で、すごく短気な危険人物でもある。
この「失われた世界」は、この奇妙な博士の研究と冒険を描いたSFシリーズの1作目。
冷えていく地球における生命の起源
ウォールドロンという人の講演の話。
「科学的に解き明かされた天地創造の鳥瞰図(上空から地上を見下ろすようにして見た場合の図)。燃えるガスの大きな塊となって、宇宙を赤くして回っていた地球。そして凝固し、冷却し、シワができて、シワが山々となって、水蒸気が水となり、生命の不可解のドラマを演じる舞台が準備されたこと。しかし生命の起源ということに関しては彼も慎重にお茶を濁した。生命の起源種が初期の高温状態を貫いて生き残ることはほとんどできなかったであろう。それは確実であると彼は言った。生命はその後に出現したが、それは冷却しつつある地球の無機物質から生まれたか、あるいは他の流星により地球にたどり着いたのか」
そしてさらに進化論についての話が続く。
実に当時らしい(しかし見事な)科学的理解で、ドイルの博識ぶりがよくわかる。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
失われた世界はどのように形成されたのか
南米のアマゾンのジャングルの先住民たちが恐れる、クルプリと呼ばれる森の精霊が住んでいる禁断の領域。その方角の先に存在しているような、ジュラ紀(中生代?)に生きていた恐竜たちの失われた世界。
 「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
チャレンジャーが推測する、そのような世界が現在に残った理由は、「南アメリカは花崗岩の大陸。そして内陸のある地域に、大きな火山性の隆起が起こったことがある。そしてサセックス州ほどの広い地域が、そこに住んでいた動物ごと持ち上げられて、浸食を受け付けない程の硬さを持つ切り立った絶壁によって閉ざされた、閉鎖的な世界を作った。そこは普通の自然法則が停止されて、他の世界に見られるような生存競争に影響を与えるあらゆる制限が無効になるか、変わってしまった世界。そのために、それ以外の世界では滅んでしまった太古の生物が変わらぬ姿で生き残っている」というようなもの。
 「絶滅」クレードはどのように進化し、そして消滅してきたのか
「絶滅」クレードはどのように進化し、そして消滅してきたのか  「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。
「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。
剣竜の絵、論文
序盤、記者のマローンが見せられた、南米の未開のジャングルの奥地から逃げてきたようだった、おそらくは詩人か画家のメイプル・ホワイトなる人の残した記録。科学のことをあまり知らないといえるマローンも、異様な存在と認識できた謎の動物の描写。
「1ページにわたって、私が今まで見たことないような奇妙な動物が描かれていた。アヘン常用者の悪夢とも、精神錯乱症の幻覚ともつかぬもの。頭は鳥のようで、胴体は太ったトカゲのよう。長く引きずった尻尾には上向きのトゲがくっついていて、曲線を描いた背中には大きな鋸の歯のようなひだが刀のように並び、まるで大量のニワトリのトサカを互い違いに置いたかのよう。この生物の前には、人間の格好をした小人みたいのがいて、その怪獣を眺めている」
マローンはこの生物に関して、奇怪、グロテスクという感想を発していてる。
小人というのも、そもそも小人ではなく普通のヨーロッパ人で、動物の巨大さをわかりやすくするために描き入れられたものとするチャレンジャーに対し、マローンは馬鹿馬鹿しいと考えるが、教授はさらに1冊の本を見せる。
「わしの才能ある友人であるレイ・ランケスターの優れた論文だが、ここに君の関心を引くような挿し絵もある。そして説明が書いてある。ジュラ紀に生息した恐竜の1種、剣竜の生態想像図。後脚だけで成人男性の丈の2倍はある。さあどう思うかね?」
頭が鳥に似てるとか、グロテスクだとか、マローンの感想はなかなか興味深い。
鳥類の祖先、恐竜の描写
その大きな足跡を見つけた時、勇敢な冒険家の仲間であるジョン・ロクストン卿は言う。「これは全ての鳥類の祖先の足跡に違いない」
そしてその足跡を辿った先、いよいよ現れる奇怪な巨大生物たち。ゾウ程の子供3体にとても巨大な大人2体。石版色の皮膚、トカゲのようなウロコ、幅の広いしっぽ。巨大な3本指の後ろ足でバランスを取りながら、5本指の小さな前足で枝を押さえ葉を食べている。つまりは、黒いワニのような皮膚の巨大なカンガルーのような動物。
他、多くの既存の動物にその見かけが例えられている。
湖で見られた、水際をそろそろ歩き回るような巨大な白鳥のような動物は、それが水の中へ飛び込むと、曲がった首と突き出た頭だけが水面で揺れ、次には水中に消えてしまう。
続いて水飲み場に現れた、巨大なアルマジロのような動物、巨大なシカのような動物。そして次には剣竜も現れる。
タルのような胴体と、ヘビに似た巨大な首の後ろにある、巨大な水かき。蛇頸竜(プレシオサウルス)は、淡水に住むとされる。
恐ろしい肉食獣として現れる、巨大なヒキガエルにような、ぴょんぴょん跳び跳ねる生物。 皮膚はイボだらけで、体を動かすたびに太陽の光で七色に変化する。さらにこの生物は、例えば人間のような獲物をその体で押しつぶしてから、さらに次の犠牲者に取りかかる。ライフルを撃ってみても平気。痛みはあるのかもしれないが、それにはかなり鈍感らしい。
その巨体が持つ力はやはり恐ろしいものの、基本的に恐竜は、その脳が小さいために、本能だけで生きてるバカな動物というように扱われている。ことあるごとに反対意見を持って議論するチャレンジャーと、ライバル的なサマリー博士も、共に認めている見解として、「恐竜が絶滅したのはその知能の低さのため」とも。
結局キョウチクトウ科の有毒植物の液につけた腐肉にひたした毒矢が、恐ろしい肉食の怪物の命を奪うことになるわけだが、ともに怪物を退治した土人たちは、その毒のために疫病が広がらないよう、さっさと死骸を処分した。
ただし爬虫類の心臓だけは、規則的に波打つことをなかなか止めなかった。3日ほど経って、神経中枢が衰えてきたのか、恐ろしい心臓はついに静止する。
終盤、この探検によって確認された動物の話の中では、魔法の湖の3つ目の魚トカゲや、巨大なミズヘビなどの話も。
毒ガス帯
失われた世界(ロストワールド)の冒険から3年。
とりあえずは、「酸素を持ってこい」という電文をチャレンジャーから受け取った、かつての冒険の仲間たち、という始まり、再会はわくわくすると思う。
スペクトルから読み取れた、エーテルの異常
チャレンジャーの新たな研究。
惑星、恒星からの(作中で簡単に、本来7色である光をプリズムを通して分解した場合に表されるそれらの色の配列、いわゆるスペクトルと説明されている)フラウンホーファー線の変化にかんしての論文。
惑星はそもそも太陽光を反射したものだから、惑星と恒星のどちらからのスペクトルもおかしいということは、つまりそれらに同時に異常が発生しているのかもしれない。しかしそれは考えにくいから、第三の可能性として、輻射媒体、つまり星と星の間に広がる空間に充満するエーテルに何か変化が生じているのではないか、という説が唱えられる。
ここで当たり前のようにエーテル帯が、特に説明もなく語られていて、当時の物理的世界観の一般的イメージを思わせる。
スマトラでの謎の疫病も、エーテルの異常が原因かもしれない。
「エーテルというのは地球のどこでだって同質。ゆえに、地球の一部だけで異常が発生するなんてこと考えにくい。それが本当に人間の精神とかにまで影響を及ぼすような影響を受けているなら、すでに世界中が悲惨なことになっているはず」というサマリーの反論もある。
実際にはすでに、彼らからして精神に異常をきたしているかもしれない事態という理解に続いていく。
太陽系のどこにでも充満するエーテルを媒介とする毒というのは、 考えてみれば非常に恐ろしいものである。まさしく世界の危機。いわばただ感染力の強い病原菌より、ずっと恐ろしいようなパンデミックがここでは描かれる。
しかし最後には毒ガス帯を抜け、生き残ったチャレンジャーたちが死んだ世界を確かめた後、あらゆる生物はまた復活する。いくつかの仮説は語られるものの、結局、全世界に一時的な死をもたらしたものが何だったのかは、かなり謎のままという結末
死ぬこと、魂、物質の哲学
世界の終わりの時、生き残る時間を増やせるかもしれない、エーテルの毒の効果を遅らせれるかもしれないという酸素ボンベを複数用意した密閉された部屋。その中で、世界が終わる時を自分たちで確かめようという最期の時への冒険。
いよいよ死が間近に迫っているような状態の時に、酸素ボンベによって気力を取り戻した時のチャレンジャー教授の勝利の叫び「効くぞ。わしは正しかった」はかなり印象的。
ドイルなりの、物質や生き物、そして死についての哲学を感じさせる記述も多い。
「死は気持ちのよいものかもしれん。衰弱しきった肉体はその印象を記録することができないが、我々は夢の中や昏睡状態で感じる精神的な快楽を知っている。自然は美しいドアを作って、光り輝くカーテンをぶら下げ、我々の迷える魂をそこから新しい世界へ導きいれるかもしれない。わしは現実の底を探る度にそこには必ず知恵と思いやりがあることを発見する」
「物質を利用はするが、それ自体物質ではない何か。死を滅ぼしこそすれ、死によって滅ぼされることがない何かがある」
「万一、地球上に生命が存在し続けると仮定して、精神の次元から物質の次元にかけて、我々がどのような観察の機会に恵まれるかは誰にも断定できない。物質的現象を観察し、判断を下すのに最も適しているのは、われわれ自身が物質的存在である間だということぐらい」
やはりエーテルに関する記述は、興味深いというか、 面白いかもしれない。チャレンジャーもまた、地球上で生命体が完全に絶滅していない根拠として、密閉された空間のアメーバが、自分たちと同じように生きていることに注目する。つまり密閉された空間に酸素は入り込めないが、エーテルなら関係なく入り込める(というか、宇宙のどこにでも等しい量充満している)。そうすると、酸素で満たされた部屋により生きながらえているチャレンジャーたちとは違い、エーテルの毒に無防備であるにも関わらず、アメーバが自分たちと同じだけ生きていることを示していると。
人間の特殊性。特別性
下等な生物が生き残るなら、そこからまた長い時間をかけての進化が人類を生み出すだろうというチャレンジャーは、まるで地球が作られた目的が、人類(あるいはそのような生物)を発生させ、維持していくためというような考えとサマリーは言い、チャレンジャーは否定しない。
サマリーは言う「この地球という舞台が、人類がその上を気取って歩き回るために作られたとする考えが、実は人類のとんでもないうぬぼれではないかと心配になることがある」
チャレンジャーが言うように、地球上で人類が一番の高等動物であることは認めながら、それでもサマリーは、無生物状態の、あるいはそこまでは言わなくても、人類の痕跡のない地球が、宇宙空間の中を歩み続けた長い時間、それらすべてが人類が登場するための準備期間だったなんて、軽々しく断定できないとする。
むしろチャレンジャーの「ではいったい誰のため、何のための準備というのか」 という問いが興味深いか。サマリーは「そんなことが我々にわかるものか。計り知れない何かの理由があるのかもしれない。人類の出現は単なる偶然、発生の過程に紛れ込んだ副産物かもしれない」と答える。
サマリーの、(チャレンジャーの考えは)まるで海面に浮かんでいる水の泡が、海というものが自分を作り出して維持するために存在していると考えているとか、寺院に巣食うネズミがその建物が最初から自分の住居として造られたと考えているようなものという批判。この辺りは、インテリジェントデザインや進化論、自然淘汰の重要性などについての、20世紀の生物学者たちの激化した議論を思わせる。
分子分解機
物質を分子、原子の段階にまで分解して、そして再び復元することもできるという機械が開発されたという話があり、マローンとチャレンジャー教授は、その真偽を確かめに行く。
開発者のネーモルは、自らのマシンについて「ある種の結晶体、例えば塩とか砂糖は水に入れると溶解し、形が見えなくなる。しかし蒸発させたりして水を減少させると再び結晶体が前と同じ形で現れる。機械の原理としては、ある有機体を同じように宇宙の中へと溶解し、さらに諸条件はそっくり逆転させ、再び元の物質の形に戻らせるというもの」
チャレンジャーも、なぜかを問うが、ネーモルは「私としては、分子構造は完全に復元すると答えるしかない。何らかの目に見えない骨組みがあり、全ての分子が自動的に本来の場所に収まるのだ」などとさらに説明する。
オカルティズムにおける、ある物体の瞬間移動、アポーツと呼ばれる現象も、バラバラになった分子構造が電磁波によって運ばれ、そして何らかの法則に従い、再び分子の配列を元通りに復元するというものだろうという仮説が示される。
そして実演されたその現象に、チャレンジャーも心底驚かされる。 確かに消えて つまり分子の雲となってそして再び復元される。それどころか、振動数の異なると表現される異なる組織(例えば体毛)だけ限定的に復元しなかったりといったことも可能なのである。
物語の構成としてちょっとホームズ的な感じがする。最後の、チャレンジャーの自分の行動を正当化するための言葉は、なかなかユーモアも感じる。
地球の悲鳴
語り手がマローンではなく、マローンが信頼できるとチャレンジャーに紹介した友人になっている。
そしてこの話では、地球そのものが生命体であるという仮説が語られる。全自然界を通して存在している、ある種の類似。植物生い茂る平坦地は、巨大な動物の毛むくじゃらの脇腹。長い年月をかける大地の隆起陥没は呼吸作用。そのちょっとした身動きが地震や地殻変動。火山活動という皮膚の温点。
地球は両極で扁平になっている。つまり極点は他の場所より地球の中心に近く、中心部の高温を最も感じやすい。そして極地の気候条件は熱帯のそれと同じ。というような説明に続いて、その形はまるでウニのよう、地球は言わば巨大なウニなのだと語られる。
そしてここでもまたエーテルが出てくる。ウニは自らを取り巻く海水が、管状器官を通過する時に養分を供給する。同じように地球は、宇宙空間の中で動きながら、その内部を貫流していくエーテルを養分として活動力を得る。そしてここで地球だけでなく、他の惑星もそれぞれ独自の空間から養分を摂取していると示唆される。
しかしここで語られている、地球が生物であるという仮説は、システム的にそう考えることができるというような、つまりは後のガイア仮説のようなものではなく、本当にただ生物であるというもの。
チャレンジャーは、小さな虫が人間の皮膚を削ることでその存在を示せるように、自らの存在をその皮膚である地殻を傷つけることで、地球に知らせようとする。そしてその運命の実験の時、地球の不気味な叫び声、噴出した血液あるいは防衛のための分泌物、そして世界中で起きた怒りの災害などの反応。
この世界観では、地球以外の惑星の事、そしてこの宇宙自体のことをどう考えるべきか。この話の後では、「毒ガス帯」でのチャレンジャーとサマリーの議論も、より興味深いかもしれない。