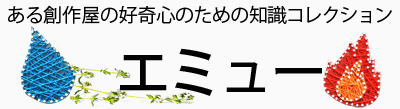大進化と小進化
一般的にいう『進化(evolution)』がどのような現象かというと、『地理的隔離(Geographical isolation)』や、性格趣向などの違いのために生じる障害など様々な要因によって、種が文化していく現象。
そして、種レベル程度での(ライオンとトラで分化するくらいの)変化を『小進化(microevolution)』という。遺伝子や染色体の突然変異による、相対的にはわずかな変化がそう言われることもある。
さらにより根本的な、つまりは分類学的に種よりも深くの、科や目といったレベルでの(イヌとネコ、食肉目と霊長目で分化するくらいの)変化は、『大進化(macroevolution)』と呼ばれもする。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
大進化が小進化の単なる積み重ねかは、かなり議論がある。
ドメインの文化は始まりの特殊か
仮に現生のすべての種に、共通の先祖がいるとする。すると、これまでに、大進化により、目どころか、界レベル(植物と動物の分化くらい)やドメインレベル(細菌、真核生物、古細菌という分類)の変化も起きたことになる。
どこかの段階で、部分的に固定するような作用が働いていないなら、隔離した状態でそれぞれに進化していくことになった同じ種の動物たちも、やがては植物と動物くらいに違う存在になり、核生物と細菌くらいに別の存在になることになる。
本当にそう単純な話なのだろうか。
例えばドメインの分化が初期だけのものだったなら、それは何を意味してるか。
ある動物種を、それぞれ隔絶された世界で進化させ続けたら、やがて植物と動物くらい(界レベルで)違う存在になり、ドメインを新しく誕生させることすらあるだろうか。
普通、多細胞生物である動物種は、体内に大量の微生物を住まわせているが、そこにまで進化の法則はしっかり及ぶはず。もし隔絶されたばかりのその世界において、十分に生態系の中のニッチ(生態的地位)が存在しているというのなら、それらを埋める生物は、どこから生じる可能性が高いのだろうか。
多細胞生物の生殖に関係のない細胞に関してはどうであろう。我々は大量のDNA遺伝情報を有する細胞で構成されているが、引き継がれるのは生殖細胞のみである。それ以外はすべて生殖細胞の遺伝子引き継ぎを安定的に行うための、保護や、調整する役目を担っているかのようだが。
 DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
確認されてる限りのことを信じるなら、ドメインレベルでの分化は、遥か過去に起こったが、これまででは全然起こってない。
これ(ドメイン)は単に積み重なった結果、じゃないとすると、下位レベルでの多様性が、根本の分化を妨げているのかもしれない。
出現し、適応し、絶滅していくプロセス
微生物を含めない場合、地球には870万ほどの種がいるとされている。微生物の多様性はその比ではなく、数億種以上だと考えられている。
個々の種の存続期間、動植物の化石記録がある程度はっきりしてきている時期(普通はカンブリア紀。5億5000万年前くらいから)の種数を、適当に用意すれば、現在までに、いったいこの地球上でどのくらいの種が生まれ、絶滅してきたのかも計算することができよう。
しかし、わりと控えめと思われるような数字で算出したとしても、現生種の数は、絶滅種の1%以下くらいになるとされる。
出現し、適応し、絶滅していくプロセスとパターン。生物多様性の歴史自体を、大進化という場合もある。
小進化の検出、大進化の推測
小進化に関しては、検出しやすい。
世代間での形質の変化を追跡して、タンパク質の違いを生み出す遺伝子発現の変化や、突然変異と関連付けたりもし、形質に対する自然淘汰の強さなどを定量化したりもできる。つまり個体群の進化に対して、自然淘汰がどれくらい影響しているかを見積もれる。
実際の個体群を使って実験が行われることも多い。
一方で大進化は(それが小進化の積み重ねであるというのなら、なおさら) 人間の寿命に比べたらはるかに長い時間が最低限必要だと考えられていて、実験による観察などほとんど不可能である。
そこで化石記録の研究が非常に重要となる。それらはかつて地球に生きていた古生物のサンプルであるから。
 「化石記録と進化」骨はどのように石になるか、バイオマーカーとは何か
「化石記録と進化」骨はどのように石になるか、バイオマーカーとは何か
化石記録と分子時計
現在の生物に関する、『分子系統進化学(molecular phylogenetics)』、『ゲノミクス(genomics)』、『進化発生学(Evolutionary developmental biology。evo-devo)』なども、大進化の重要な手がかりにもなっている。
分子系統進化学は、生物のもつタンパク質のアミノ酸配列や遺伝子の塩基配列を用いて系統解析を行う分野。
ゲノミクスは遺伝情報自体の研究。
進化発生学は、異なる生物の発生過程の比較研究により、進化系統を考える。
そしてこれらの研究結果を、化石記録と合わせると、より確かな情報も得られたりする。
ところで、生物間の分子的な変異。例えば核酸やタンパク質の分子進化の速度が一定と仮定することで、各種生物の分子配列の違いを進化速度を計る時計とみなせる。これを『分子時計(Molecular clock)』という。
全然使われてなさそうな遺伝暗号の塩基配列など、機能的に重要でないだろう分子は自然淘汰(外部要因)の影響を受けにくいので、分子時計として特に実用的とされる。
 「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
クレード、単系統群
例えば、主なクレード(単系統群)が分岐したのがいつなのかは、分子時計で推定できる。そしてその結果を化石記録と比較することで、複数の進化仮説の中から、特に可能性の高いものを選ぶこともできる。
『単系統群(monophyletic)』、または『クレード(clade。分岐群)』とは、単一の進化的系統に属する生物すべて。つまりは、1つの仮想的共通祖先と、その子孫すべてを含める群。系統樹の1つの枝の全体とも言える。
もちろん、扱うスケールは結構自由である。規模は異なるが、ヒト属も、哺乳類も、脊椎動物も、おそらくは共通先祖から進化したクレードである。もしこの地球で、生物の発生がただ1度しか起こらなかった奇跡だったのなら、地球生物も独立したクレードといえる。
本当に共通先祖はいたか
現存する地球生物は、少なくともリンネ式の階層分類において、同ドメインは(長いスケールでは)単系統群と考えるのは一般的に思える。だが実は、生命体と定義できる最初の段階から、系統はかなり分かれていた可能性はあるだろうか。
そうだとすると、細胞など見られる多くの共通要素をどう考えればよいか。
それが、各自が単細胞であった時代のことなら、異種との生体物質交換が実現できたものたちが、生き残るための共通性質を持つことができて、進化の法則により生き残ってきたとか、そういう可能性もあるかもしれない。つまり今の生物の分子レベルでの共通点は、単系統だからでなく、大昔の自然淘汰の影響。
そんなこと、考えれるだろうか。
絶滅をどのように考えるか
進化が機能している生態系の中で、種の多様性はどのように変化し、保たれるのか。
群多様性の変化の計算
生物と環境の相互作用を扱う学問分野である『生態学(ecology)』において、特に『個体群(population)』を研究対象とするのが、『個体群生態学(population ecology)』。
個体群とは、一定の空間の中に存在している同種グループの全体のこと。個体群は(協力や争いなど)相互作用し合うほどの集まりばかりとは限らないが、だとしても潜在的には作用しあっておかしくないことが普通。
個体群生態学では、『n + b + i – m – e = N』という式がよく使われるという。この式の、nは現在の個体群サイズ、bが個体出生数、iが個体移入数、mが個体死亡数、eが個体移出数、Nが次世代の個体群サイズである。
また、nを現在の多様性d、Nを次世代の多様性Dとして、さらにb、i、m、eの単位を個体でなく種として(つまり個体出生数を「種の出現数」、個体死亡数を「種の絶滅数」として)上記の式を使うこともできる。つまりは『d + b + i – m – e = D』で、多様性の変化を推定するための式となる。
世界規模のスケールで、上記の変化の式を扱う場合はやや特殊なケースで、おかげで実質的に式は単純になる。つまり世界(地球?)規模では、種の移出と移入はありえず、考慮しなくてよいと考えられるから、多様性変化を扱う式は『d + b – m = D』となる。
その式は、大進化を考える時に、重要となる要素をよく示している。つまりは、種の分化と、絶滅。
出現率と絶滅率
化石記録は、種が新しく誕生しうることと、絶滅することの両方を示す。
そして、ある期間の、クレード内での新種の出現率αと、絶滅率Ωの割合は、地質学的証拠の量に応じて設定される様々な単位時間ごとの、それらの数の変化として計算できる。
クレード内のα(出現率)とΩ(絶滅率)は、『現存多様性(standing diversity)』、つまりある時点での多様性の合計を決める。ある時の多様性をd、それからいくらか経ってからの多様性をDとして、『d + α – Ω = D』。つまり、dからDまでの時間において、α>Ωなら多様性は増していくが、逆にΩ>αなら多様性は減っていくだろう。そして、Ω>αが長く続けば、Dはやがて0となる。つまりそのクレード自体の絶滅となる。
基本的にはほとんどの分類群において、α>Ωのようだが、αがΩに比べて極端に大きすぎることはないという。
仮にαがΩよりとてつもなく大きいクレードがあったとすれば、生態系はすぐにそのクレードで埋め尽くされると思われる。
ターンオーバー。絶滅スケール
ある期間の出現と絶滅の総数は『ターンオーバー(turnover)』と呼ばれることがある。ターンオーバー率は、高いクレードと低いクレードがあり、そのままαとΩの和の大きさでもある。
『ターンオーバー(metabolic turnover。代謝回転)』といえば、生物が、生体分子を合成、一方では分解し、新旧の分子がバランスよく入れ代わっている動的平衡状態。または、その結果として、古い細胞や組織が新しく入れ替わることを意味する名称でもある。
クレードでのターンオーバーは、種の入れ代わりだが、別に平衡状態とは限らない。
恐竜の絶滅の場合
絶滅率(Ω)が増えれば多様性は減少するが、出現率(α)が減ることでも多様性は減少する。恐竜の絶滅の流れは、おそらくそっちだった。
 「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。
「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。  「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
恐竜の化石記録の特徴は、700万年くらいの、「期」と呼ばれる期間だけに生きていたようである属の数が、非常に多いとことを示している。
(鳥類を除く)恐竜は白亜紀(Cretaceous period。1億4500万年前~6600万年前)の終わりに絶滅したが、絶滅自体はそれまでに何度もあった。ただ、それまでと違って、その時には新しい種の恐竜が出現しなかった訳である。化石記録も、その時期、恐竜の出現率が急速に減少していたことを示しているという。
大量絶滅はなぜ起こるか
気候の変化、生息地の消失、他者との競争、新しい捕食者。 様々な要因によって、絶滅という現象はおそらくいつでも起こっている。
もちろん、どの瞬間にも生物が絶滅しているという訳ではない。どの生物にも、常に絶滅の影は迫ってきているということ。しかしクレードは新しい種を生み出し続けることで、絶滅から逃げ続ける。
Ωは0になることはないが、αもゼロになることがないと言い換えてもいい。ただし変化する「Ω-α」の値がどこかで0になることはあり、それが絶滅の瞬間(あるいは決定)である。
絶滅というのは、「あるクレードや『生物相(biota)』の分類学的多様性が永遠に回復不能になること」とも定義できる。
背景絶滅。通常考えられるペース
絶滅の典型的なペースは『背景絶滅(Background extinction)』と呼ばれている。 しかし時々、この背景絶滅から、統計的に有意に逸脱してしまうことがある。それは通常、絶滅率(Ω)がさまざまなクレードで一斉に上昇することで起こる。そして実際に、多くの種が(地質年代的に)短期間で絶滅する。それがいわゆる『大量絶滅(Great extinction)』である。
大量絶滅は世界規模のものとも限らない。化石記録での大量絶滅は、絶対的大きさではなく、通常からどのくらい逸脱しているかを基準にする。そしてその基準が、局所的な大量絶滅を示唆することもあるのだ。
ビッグファイブ
1982年に、海生無脊椎動物の科の絶滅率を、100万年単位で示したラウプ(David M Raup。1933~2015)とセプコスキー(Joseph John Sepkoski Jr。1948~1999)は、これまで地球上で起きた、5つの絶滅のピークを発見した。
『ビッグファイブ(Big five。five mass extinctions)』と呼ばれるその5つの大量絶滅はそれぞれ、オルドビス紀(Ordovician period。4億8830万年前~4億4370万年前)の末、デボン紀(Devonian period。4億1600万年前~3億5920万年前)の末、ペルム紀(Permian period。2億9900万年前~2億5100万年前)の末、三畳紀(Triassic period。2億5190万年前~2億130万年前)の末、白亜紀の末に起きたもの。
ビッグファイブの時期は、地質年代区分の用語では、それぞれ2つの区分の境目ということで、それぞれ、『O-S境界(Ordovician–Silurian boundary)』、『F-F境界(Frasnian–Famennian boundary)』、『P-T境界(Permian-Triassic boundary)』、『T-J境界(Triassic-Jurassic boundary)』、『K-Pg境界(Cretaceous-Paleogene boundary)』とも呼ばれる。
F-F境界は、後期デボン紀のフラニアン期とファメニアン期の境界。
K-Pg境界のKは、ドイツ語のKreideから。英語の頭文字がCで始まる地質年代区分が他にもいくつかありややこしいために、ドイツ語から取ってるそうである。
オルドビス紀、ペルム紀、白亜紀の大量絶滅は、絶滅率の急激な増加によるものとされる。残りの2つは、 絶滅率増加に加えて、出現率の減少も顕著。
化石記録の不完全さが絶滅時期を誤解されることもある
化石記録の一部が失われてしまうということはよくある。それが「大量絶滅したのではないか」という勘違いを誘発することも。
例えば、海水面が低下すると陸地が露出するが、そうなると、そこに海洋堆積物が堆積しなくなるので、実際にはまだ繁栄していた海生生物の化石が、発掘された地層から消滅してしまうということもありうる。
絶滅したと思える分類群が、別の新しい時代の地層で再び現れることもあり、そのような復活現象は、 聖書でイエスキリストが蘇らせた友人の名前をとり『ラザロ効果』とか呼ばれる。
ラザロ効果の主な原因は、普通は、絶滅時期の勘違いと思われる。
逆に古い化石が、洪水などで流され、上方の新しい堆積物中に入ってしまったため、その化石種の上限が過大評価されることもある。
第6の大量絶滅
ここ最近では、人類、つまりはホモ・サピエンスが原因と思われる絶滅は非常に多い。人類のために、ビッグファイブは、ビッグシックスになりつつあると考える者もいる。
アンソニー・バーノスキー(Anthony David Barnosky)らの研究によると、15000年前くらいに、人類がアメリカ大陸に到着してから、哺乳類の多様性は半分以下に低下したという。
さらに彼らは、過去の絶滅と、最近500年で起きた絶滅とを比較。すでに絶滅してしまった種に加え、保護しない限りは絶滅を免れられないと思われる絶滅危惧種も将来的に絶滅したとして、現在の絶滅の大きさと、絶滅率を計算した。
500年の間に、すでに絶滅している生物のみで考えても、絶滅の大きさはけっこうだが、絶滅危惧種まで含めると、現在の絶滅状況はビッグファイブにも近づくという。
絶滅率に関しては、現時点ですでにビッグファイブと並ぶか、上回っているともされている。
しかも、人類が引き起こしていると思われる環境の変化は、加速しているようにも思われる。つまり、その影響がこれからさらに大きくなる可能性が十分に考えられる。