宇宙の旅よりも、地球外でのコンタクトが重要
アーサー・C・クラーク(Arthur Charles Clarke。1917~2008)の書いた長編シリーズとして、『宇宙の旅』と並んで代表的なものであろう。描かれる世界観や、物語に込められたテーマは、あちらと似ていると思う。例えば、どちらも主に宇宙の構造、進化のような世界システムの最終的帰結、宇宙に誕生した様々な知的生物の共生関係などが重要と考えられる。
ただし、宇宙の旅シリーズが、地球の時代に生きる地球の知的生物(人間)の研究を介して、謎が語られるというスタイルを一貫していたのに対して、こちらは実際に地球から遠く離れた世界を冒険するキャラクターがしっかり描かれ、あちらよりも、異星知性とのコンタクトが直接的な印象が強い。
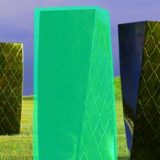 「宇宙の旅」モノリス。人工知能HAL。エネルギー生命。ミレニアムのIF
「宇宙の旅」モノリス。人工知能HAL。エネルギー生命。ミレニアムのIF
科学テクノロジーと妄想的な魔法との関連性、宗教に関する議論なども多く、いくらか、『幼年期の終わり』とかの大長編版というような感じもあるかもしれない。
 幼年期の終わり、渇きの海、楽園の泉、銀河帝国の崩壊「アーサー・C・クラーク長編」
幼年期の終わり、渇きの海、楽園の泉、銀河帝国の崩壊「アーサー・C・クラーク長編」
宇宙のランデヴー、最初の作品。人類とラーマの出会い
宇宙の旅シリーズもそうだと思うけど、明らかに最初の1作目は、それ単体で完結していると言ってもいいような内容であり、続編はおそらくほぼ後付け。
従って、この1作目『宇宙のランデヴー』は、シリーズのプロローグとしてだけでなく、単体作品としても評価しやすい作品。
単体作品として見るなら、この作品のテーマの1つは、「宇宙の広大さを前にした人類の無知」かもしれない。
太陽系を掌握しようとしている時代の人類の前に現れた、謎の(他星系からと思われる)物体(宇宙船?)。そこを調査する者たちが次々目撃することになった謎の機能、それらの原因に関する議論、テクノロジーの遅れた人類を嘲笑うかのような結末に、クラークらしい皮肉さが感じられる。
宇宙のランデヴー
しかし、この作品が、大きな謎を提示して終わる、ということは重要であろう。それは、今の人類にはまだ想像すらできないような、つまりは人類の誰も知らない宇宙の部分に関する謎。ところが、後の作品では、その謎が解き明かされていく流れとなる。
ただ結局のところ、後々の作品で描かれるのは、宇宙SFにおいてよくあるようなものである。つまり、わかっていない世界の知識を、ほぼファンタジー的に説明する、言ってしまえば神話のような世界観。また作者自身が考えたとされる、「優れた科学テクノロジーは魔法と見分けがつかない」という言説を非常に都合よく利用されてる気がする。そのあたりの演出のことは、続編が、クラークの単独著作でなく、他の作者との共作になったことも原因かもしれない。
特に、太陽系を通過する謎の物体ラーマに関しては、かなりはっきり、それがどういうものかの説明が後のシリーズである。
ある意味、奇妙な話なのかもしれないが、説明されるスケールを広げることによって世界観を縮小してしまったような印象も受ける。
個人的な感想としては、この1作目だけが名作で、後の作品群を失敗だったと考える人の気持ちはわかる。
宇宙監視と社会組織
ヨーロッパの地理を大きく変えるほどの大隕石衝突の悲劇を超えて、(「かつては自滅もかまわず、互いの富を奪い合うため使われていた」などと表現される)軍事兵器を、地球という共有の土地を守るために利用するようになった未来。
その宇宙の危機を監視する〈宇宙監視(スペースガード)計画〉が、自然の天体としたら、明らかに挙動が奇妙な謎の物体よ発見し、それが「ラーマ」と名付けられたというのが始まり。
 「インド神話の神々」女神、精霊。悪魔、羅刹。怪物、神獣の一覧
「インド神話の神々」女神、精霊。悪魔、羅刹。怪物、神獣の一覧
おそらく遠い宇宙からの訪問者に関して、報道機関が騒ぎ立てるという描写がある。大げさな内輪揉めはかなり減っていそうではあるものの、宇宙の監視システムが作られた時代において、個人個人の自由性より、国家(社会組織)の安定した管理が強まっているような。
精神状態の管理、複雑な小さな社会
(人類にとってはミニチュアの地球というように、本来の生活環境を内部に再現した乗り物というような解釈も見られる)宇宙船のような、本来人類が対応していない環境に人類を、滞在させるための装置(システム)における、精神状態の問題と、そのような問題解決のための感情操作のようなテクノロジーが語られる。様々な要素が絡み合う複雑系を管理する難しさに対する、クラークの警戒も思わせる。
例えば男性の搭乗員の性的影響による動作スイッチ。性的関心のための、精神状態のコントロールしにくい乱れ。女性の乳房の、無重力状態での揺れが、男性に意図されてない興奮をもたらすとか。
しかし、感情の調節の工夫や、宇宙船内部という小社会の中での交流関係のルールによる制限などにより、指揮官の威厳とかも含めて、小社会自体が安定して機能するように調整される。
優秀な労働者としてのスーパーチンパンジー
「二階級以上離れた者同士の情事は、かたく戒められるが、それ以外に艦内でのセックスを規制する唯一のルールは、「通路での実行や、シンプ(スーパーチンパンジー)たちを驚かすようなことの禁止」ぐらい」と、社会的、精神的な問題と、その対策に関する説明の中で、スーパーチンプという名称も出てくる。
 「知性化宇宙」超空間で繋がりあう五つの銀河。知的生物で溢れる物質世界
「知性化宇宙」超空間で繋がりあう五つの銀河。知的生物で溢れる物質世界
スーパーチンパンジーとは呼ばれていても、それは厳密にはチンパンジー種ではなくて、そもそも類人猿でもなく、しかしある程度知能が高いサルを遺伝改造した人工種。
ゼロ重力下での、把握力がある尻尾の有用性の研究。そして人間や類人猿にしっぽを生やそうとして失敗した、というのが、この改造生物誕生の背景。
ある程度簡単な料理とか、道具の運搬などが可能で、一方で食料と酸素は人間の半分くらいしかいらない、にも関わらず、人間よりも長時間労働を苦にしない。「人類を雑事から解放してくれた」とも。労働者の代用としてのロボットや機械知能と、同じような発想だろうか。
(厳密には知性体ではない)機械労働者と比べる場合、日常的なことはともかく、非常事態の特殊な行動が、そもそもその必要性さえ理解しにくい(そのため、足手まといになりがち)、というようなところも注目すべきか。
また、性的なことの精神への影響の話と合わせて考えると、無性生殖(クローン)化により、性もなく、厄介な習性上の問題がないというのも、なかなか興味深いかもしれない。
宇宙時代のキリスト教会
〈宇宙飛行士(コズモノート)キリスト第五教会〉という、未来世界で、比較的知られた宗教が出てくる。イエス・キリストが宇宙からの訪問者であるという前提にもとづいて、神学体系を構築したもの。
その信仰との関係か、宇宙で仕事をしている信者が多く、しかもその信念のため、有能で誠実で、かなり頼りになる。しかも他人に改宗をあまり勧めないという設定。
クラークの考えていた宗教の実用的側面の例であろうか。
「高等な科学技術教育を受けた人間がどうして、この派の信者たちがよく口にする論議の余地ない事実なるものを、いくらかなりとも信じこめるのか……どうしても理解できない」というような疑問は、(教会などへの忖度の可能性もあるかもしれないが)聖書の内容とかを無条件に信じていた、懐疑論者寄りの哲学者とかへの疑問に通じるか。
変化する生物のために、変化する都市のパターン
ラーマ内に現れた、地球の過去の都市にそっくりな光景。しかしそれが本物ではないはずの重要な根拠が、あまりにも完璧な調和とパターン。
つまり、人類の住居地としての都市は、決して完成することはない完全な完成図、理想的な設計段階すらない。
一方で、一貫した調和とパターンは、管理能力の高い知性により考案、設定され、完成されたものの証とも。ようするに「ちょうど何か特別の目的に合わせて考案された機械のよう……完成してしまった後では、もう成長や変化を遂げる可能性など残されていない」
おそらく住居区が完成しないのは、人間のような生物が変化する系であるから。それも一貫した方向性がない変化系。言ってしまえば非線形な変化パターンだから。仮に最も快適な都市を追求するとして、快適さのために必要なものがその時々の状況で変わる。都市も常に変化を続けるというのが、理想的。
小社会の精神状態の話とは違って、知性の認識の領域のより外側、物理的世界の話。しかし結局のところ、複雑性の管理に関する問題を示唆もする、似たような話と思う。
パート2。再びラーマの調査、探索の物語
地球上に現れた第二のラーマの調査の話。
基本的には、ここからの新三部作の第一部という感じだが、この作品単体だと、1作目の焼き直し感もある。ただし、結末が新たな物語につながる形になっている。
宇宙のランデヴー〈2〉
このシリーズ全体の話として、あまり意味のある設定かは微妙であるが、1作目の時代と人類世界の模様も大きく変わった設定。これは話の都合とかいうより、作者自身の考え方の変化もあるかもしれない。
またはこの辺りの設定も、クラークの小説でよく見られる、テクノロジー管理の急加速のための失敗可能性みたいなものを示唆しているか。
例えば前作では、地球以外の他の太陽系惑星が植民地として描かれていたが、経済的厄災が宇宙社会に広がることで、大なり小なり母惑星(地球)からの補給に頼っていた、太陽系の各植民地は、生活環境が酷くなった。それで、多くの者たちが地球に戻ってきた。そして大混乱の収束と、社会の再興を早めた、民族国家、君主制国家、カトリック教会などが、崩壊した惑星連合の時代の自由性とは対照的とも言えるくらいに影響力を強めた。といった状況で、宇宙研究、開発が再開されて、十数年ほど、というような設定。
情報の少なさの影響もあると思うが、現実でもよく語られるような宇宙の謎をよく考えさせられる作り、という印象の1作目と比べると、この作品で提示される謎は、作中に登場したオリジナルのシステムに関するものが多く思う。
例えば1つ目のラーマとの繋がりについて。ラーマ内のある地球環境の再現では、1つ目のラーマに持ち込まれていたものばかりが再現されているなど。
個人的には、SFとしては微妙だが、ミステリー、サスペンス作品としては、こちらの方が面白いと思う。
パート3。知的生物たち。共同体のドラマ
特に序盤の、遺伝、男女間系などの問題は、クラークとよく比べられるアシモフやハインラインも、よく描きがちなイメージがある、未来におけるセックスフリー思想や世界観と比較すると興味深いかもしれない。
宇宙のランデヴー〈3〉
この作品では、いよいよ明確に、異星の知的生命体が登場する。
クラークの他のいくつかの作品でも見られる、宇宙の知的生物たちの、ある種の大規模ネットワーク的なものも。この作品では、かなり直接的に、キャラクターたちとそういう存在が関わる。また、他の類似的な描写のある作品と比べると、話自体が長めであるから、結果として丁寧に描かれてる感じはある(しかしだからこそ、神秘性は少し薄いような気がする)。
ラーマの目的も、まさしくそれを利用する知性集団たちから、説明がある。
基本的には前作までの謎が解き明かされていくばかりであって、ミステリー的な要素は薄くなっている。その代わりに、真実を知り、自分たちの運命を知った1つの家族である者たちの、ヒューマンドラマ要素が強くなっている印象。
特に、地球外で生まれながら、熱心なキリスト教徒となった少女シモーヌの決断はドラマチックと思う。
「お願いだから、最後まで聞いて。わたしの解決案は、大人には絶対に思いつけないものよ。わたしだけが言いだせるものなの……イーグルより途方もない話? 地球から八光年の旅をして、知能を持つ巨大な三角形とランデヴーしたのに、それがわたしたちを反対の方向へ戻らせようとしているという事実ほど、ばかばかしいかしら?」
終盤は、新たに地球外へと、多人数の地球人たちを連れ出す展開になるが、ラーマ内での小社会がまた問題となるが、よくある人間同士のいざこざが多い。
パート4。宇宙の進化論、高次元存在、人間の愚かさ
クモダコと呼ばれるようになる宇宙生物の話が多い。聴覚を持たない生物であって、光のスペクトルの言葉で、意思の疎通をする生物。
宇宙のランデヴー〈4〉上
宇宙のランデヴー〈4〉下
宇宙のどこでも普遍的な進化論法則というようなものが、重要な要素であると思われる。人類は地球で、少なくともその地球上という閉鎖系においては、自然的なプロセスで誕生した知的生物。特に作中では、そのような高等知的種族としては、驚くべきほど、各個体が利己主義的であるとされる。「宇宙渡航種族として、社会学的には驚くべきほど幼稚」だとも。
クモダコは高等知的種への進化の過程で、先に遺伝操作テクノロジーを得ていた別種族からの介入があったらしい種族。特に、この生物群が、人間の歴史の中で、テクノロジーの飛躍が主に戦争によってもたらされていた、という事実が非常に興味深いとされているのが、興味深いかもしれない。
例えば見方によっては、戦争というのは1つの手段でしかないだろう。よくある戦う理由とは何か、土地や資源、奴隷(労働力としての人)の確保など。戦争はそれらを獲得するための方法として使える。特に、2つの別々の組織において、戦闘に利用できる技術力に差がある場合はそうだろう(だからこそ、互いに等しい強力な武器を持って、ひたすらに牽制し合うという状況が、まだましな状況として語られることさえある)。
しかし争いが決して生まれない社会モデルのパターンなど、そもそもありうるのだろうか?
クモダコは、徹底した管理社会を実現して、文字通りに内部での予期せぬ争いがない、あるいは極めて少ない社会を実現しているような印象。そして(他作品でもそうだが)このシリーズにおいてクラークはよく、管理しきれない複雑さという問題に、間接的にでも触れているように思える。
作中の人間の視点においては、クモダコの世界は、少し冷たいというような感じだが、実際的には冷たい生物世界というより、機械的世界なのではなかろうか。そこにあるのは、あちこち全ての要素(ポイント)が安定している、つまり結果的には総体として安定したネットワーク、というような。
終盤では、多元宇宙(マルチバース)という宇宙構造と、各宇宙の、いわば観察モニターの役割の知的機械群のような存在を、宇宙に置いた、さらに高次元の存在の話が出てくる。
クモダコ関連の話では、宇宙の生物の進化プロセス、知的種への移行プロセス、遺伝システムの自然性と、それを機械的に管理した場合のコントロール可能性などに関して触れられる。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか  「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
多元宇宙における神の目的。善の定義の謎
終盤に出てくる、真の宇宙構造、あるいは真の宇宙構造の有力仮説は、かなりシミュレーション宇宙的である。
そこには、神と定義できるような存在はいても、あくまでもそれはこの宇宙の生物たちから見た神。つまりその神は、数学的システムを背景とした、宇宙を作るコンピューター、あるいはそのコンピューターを操作する何者かのようでもある。
 「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「われわれはみな神の大いなる実験に参加している……それは完全性を追求しているのであって、ささやかな初期パラメーターの範囲が、いったんこの宇宙がエネルギーの物質への変換によって動かされたあと、何十億年にもわたって進化していき、ついには一つの完全な調和へと至り、それが創造主の円熟した技量の証拠となる」
究極的に調和した宇宙を求めている。それが神の最終目標というような感じがする。しかし具体的に、全てが調和しているとはどういうことを意味するのか。生物のすべての要素が善と考えられるものに向いているような宇宙、というような推測もあるわけだが、極端な話を言えば、それは完璧に平和な世界を素晴らしいと定義しているだけのような気もする。つまり、神は矛盾した宇宙を嫌い、完全に矛盾のない世界を目指しているかのような印象で、その矛盾には人間の道徳体系とかも(少なくとも1つの基準として)入っているかのよう。そして、ある生物とある生物種の間に哲学的な議論が難しいほどに、世界観が違っているというような話(この話の、人間とクモダコの議論などは、まさにその具体例を、なるべく具体的に描こうとした結果のようにも思える)もある。合わせて考えると、少なくともそのような完全に全ての生物にとっての平和な世界というのが、相当に難しい課題だということは確かと思われる。
しかしクラークは、善のみが存在する(そういう世界観と思われる)調和した宇宙というものを、自身の抱く理想としても考えていいだろうか。そんな気はする。




