ダーウィンの影に隠れてしまった、偉大な進化論者
かのチャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin。1809~1882)以前の時代の代表的な進化論者と言えば、やはりジャン=バティスト・ラマルク(Jean-Baptiste Pierre Antoinede Monet, Chevalierde Lamarck。1744~1829)の名が真っ先に上がることだろう。「biology(生物学)」という言葉を、生物学(生物を研究する学術分野)を意味する言葉として初めて使ったらしいことでも有名なこの人が提唱、あるいは熱心に支持した進化論は、後のダーウィン的な進化論とはいろいろ違うこともよく知られている。結局それが間違っていたらしいことも。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
ラマルクの生涯
軍人時代。勇敢な若者の冒険
ラマルクは、1744年8月1日、北フランスのピカルディの小さな村、バザンタン・ル・プチで生を受けた。
父はフィリップ・ジャック・ド・モネ・ド・ラマルク。サンマルタンの男でバザンタンの領主だったとされる。彼は1729年マリー・フランソワーズ・ド・フォンテン・ド・クィニヨルと結婚した。どちらも代々軍人の家系。
夫婦の間には11人の子が生まれた。
ラマルクは末子。上には4人の兄と6人の姉があった。比較的、孤独を好む子供だったという。そして伝統的な軍人の道を歩む兄たちとは違い、聖職者になる予定だった。
アミアンにある寄宿制の学校に、11歳のラマルクは入学した。各部屋には鉄製の寝台、毛布、枕、燭台、腰掛、本棚、衣服用の戸棚、薪台、湯呑みなどがあった。
学校生活は六年。一年生の時、ラテン語で聖書を読み、説教集、ラテン語文法、ギリシア語文法を学び、ラテン語のテキストもいくらか読んだ。二年目からはデカルト(René Descartes。1596~1650)やニュートン(SirIsaac Newton。1643~1727)も読むようになる。ただラマルクは、兄たちが歩んだ軍人の道への憧れを捨てられなかったそうである。そして1759年、父の病死を機に、ラマルクは軍への入隊を決意したらしい。
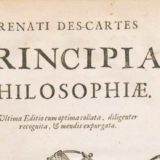 「デカルト、哲学原理」第一原理要約と考察。思想のまとめの書
「デカルト、哲学原理」第一原理要約と考察。思想のまとめの書
アミアンの学校が間もなく廃止されることも知ったラマルクは、5月にアミアンを発ち、ラマルク家と親しかった将官の未亡人ラメス婦人に書いてもらった紹介状を手に、ブログリ将軍の旗下ラスティック歩兵連隊長を訪ねた。
明日にブロシアの軍隊との決戦を予定していた連隊長は、いかにも、憧れだけでやってきた世間知らずの若者に困惑したともされる。しかし連隊長は、とりあえず彼に、テントで一泊するよう言った。
翌朝、連隊長は擲弾兵(手榴弾を投げることを主な任務とした兵士)の先頭に、昨日やってきたばかりの若者を見つけた。
彼はすぐに叫ぶ。「ここで何をしてる? お前の場所ではない。お前は輜重隊(輸送部隊)を手伝え」
ラマルクは答えた。「連隊長殿、私はあなた方の役に立つために来たのであります。連隊と共に戦いに参加する名誉を与えてください」
血気盛んな若者を、隊長が説得する時間はなかった。
1760年7月13日の夜明けが戦いの始まりの時。
しばらくの戦いの後、ブログリ将軍は、プロシアの軍隊が数的に優勢であるため、退却を命じる。
ラマルクのいた中隊では、ド・カンドル中隊長が死に、通常、隊の指揮官の役割を引き継ぐ士官も残ってなかった。
生き残りの兵士たちは、有名な軍人家族の出身ということで、ラマルクを新たな隊長に選ぶ。
戦いは完全に敗北の様相を呈していた。他の隊も退却していく。ラマルクも、仲間たちに退却を求められた。しかし彼は言った「そうしたい者は退却してくれていい、私は、私にその命令が届くまで、ここから離れない」
一方、司令部では、ラマルクのいる中隊にのみ退却命令を伝えることを忘れていたことに気がついた。もちろんすぐに伝令が出たが、中隊と敵が近すぎたので、退却命令を伝えるには、遠くからハンカチを振る必要があったという。
その後、勇敢にも、退却するその時まで使命を全うしようとした若者に、連隊長も感服。ブログリ将軍のもとに連れてこられた
ラマルクは、将軍から将校の資格を与えられる。
1762年に、七年戦争が終わると、ラマルクの連隊は各地を経て、モナコに駐屯。しかし酒の席で力だめしの際に、ラマルクは首に痛みを感じた。そして結局、軍医もその痛みを癒すことはできなかった。残念ながら、そんな状態で、いつまでも軍にいるわけにはいかない。
1768年に彼は除隊した。
しかし、首の痛みは生涯の問題にはならなかった。
ルネ・テノパリのサルペトリエール病院の外科医であったジャックは、初診で、「首の深部が化膿しリンパ腺がはれている」ことに気づき、切開手術によってそれは治った。
学問放浪時代。植物研究、雲の分類、貝の収集
ラマルクは軍人として各地に駐屯したが、その様々な環境ごとの植物群の多様性は、彼の好奇心をよく刺激していた。
ツーロン駐屯以降は、家から持ってきてたらしい、ショメル(James Francis Chomel)の『有用植物誌綱要(Traitédes plantes usuelles)』なる本を片手に、暇な時間を植物観察に費やしていた。
年老いた母のいる生家に戻った。
ラマルクは、パリの中心イル・ド・フランスに近い田園にあった長兄ルイ・フィリップの家に1年ほど世話になったが、そこで兄の所有していたディドロ(Denis Diderot。1713~1784)、コンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolasde Caritat, marquisde Condorcet。1743~1794)、ダランベール(JeanLe Rondd’ Alembert。1717~1783)、ヴォルテール(Voltaire。François-Marie Arouet。1694~1778)、ビュフォン(Georges-Louis Leclerc, Comtede Buffon。1707~1788)、ルソー(Jean-Jacques Rousseau。1712~1778)などの思想や哲学についての著書を読んだ。
しかし一説によると、この頃の彼が特に熱中したのは楽器のチェロで、兄の反対で断念したものの、真剣に音楽家になりたい考えたとも。
年老いた母は、次女の入った修道院の近くの保養院にて看護生活。ラマルクの生まれた家自体は長男が売った。
そして1770年、退職中尉の年金だけが頼りの不安定な状況をどうにかするため、26歳のラマルクは、パリに向かった。
モンターニュ、サント・ジュヌヴィエーヴの屋根裏部屋での暮らしを開始した彼は。見晴らしよい窓から見える、雲の形を研究、「ヴェール状雲」「寄り集り雲」「錆雲」「掃き屑雲」「群雲」などいろいろ分類。さらに彼は空や大気の変化を調査、気象観測もするようになり、得られたデータを毎年発表した。天気予報の可能性を説いた例として、これはかなり古い記録とされている。
 「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
大学では医学を学ぶことにした。当時のフランスでは、医学を学ぶ過程は4年。薬学と薬材学、それに生理学の第一学年。薬学、病理学、外科学の第二学年。生理学、薬材学、病理学の第三学年。生理学、外科学、病理学の第四学年。
病気の治療に役立つ動植鉱物を学ぶために、医学部には植物学教授もいた。しかし自然物の専門的研究は王立植物園で行われた。ラマルクはいつからか医学部よりも植物園の雰囲気に引かれるようになった。
またラマルクが貝の収集を始めたのもおそらくこの頃。フランスの冒険家たちの海外進出は、持ち帰るのが難しい鳥獣(大型動物)より、はるかにたくさんの、小さな貝殻をもたらしてくれた。
 「貝」二枚貝、巻貝の進化分類。生物ジャングル、家、畑、特殊化の謎
「貝」二枚貝、巻貝の進化分類。生物ジャングル、家、畑、特殊化の謎
植物採集と貝の収集は、どちらも知識人の間での流行だったようである。
ラマルクは、収集した貝に関する論文も書いたが、それが、後に彼が無脊椎動物教授の席を与えられた遠因ともされる。
植物学者時代。革命の中で
ラマルクは医学の勉強から離れ、植物園の「植物学校」に通うようになる。
ラマルクは、鉱物学者のドーバントを通じて、園長であったビュフォンと知り合えたそうである。ラマルクは自身が書いた気象学の論文をビュフォンに見てもらおうとしたが、ビュフォンの論文に関しての感想はわずかで、後は引き出しにしまってしまう。
しかし2人の関係がこれだけで終わってしまったわけではない。
後にラマルクを科学アカデミーの植物学の準会員(アジョアン)に推薦したのもビュフォンである。
1778年。ラマルクは『フランス植物誌、またはフランスに自生する全植物の簡潔な記述(Florefrançoise,ou, Description succincte de toutesles plante squicrois sentnature llementen France)』を執筆。それには最初に検索表が付けられたが、その方式は後に、図鑑に標準的なものとなった。
それに関してビュフォンは、ラマルクの書いた文のいくらかをドーパントンに修正させた。そして1780年には、王立印刷局から三巻本として印刷される。
後には、後輩学者のド・カンドル(Augustin Pyramusde Candolle。1778~1842)にも協力してもらい、共著として全五巻が1805年に、さらに1815年に補遺を加えた全六巻が販売。ラマルクが残した著作の中でも、これらは人びとに長く愛された。
ビュフォンは、息子に学びのための遍歴の旅をさせたがった。そして同行者、家庭教師の役割を植物学者となったラマルクに頼む。
1781年5月13日に、二人を乗せたアムステルダム行きの馬車は、パリを発った。
二人はオランダ、ドイツ、オーストリア、ハンガリーと、ヨーロッパのあちこちを巡り、これはラマルクとしても重要な学びの旅となった。各地の大学、博物館、植物園で、その地の高名な学者と知り合い、多くの標本も集めた。
しかし、ビュフォンの息子は、文字通りどこにでも常に同行しようとしたらしいラマルクを嫌うようなり、結局ラマルクは、最後のイタリアへの旅行は断念し、帰ることになってしまう。
ラマルクが科学アカデミーの植物学部門の正式な会員(アソシエ・ボタニスト)となったのは1783年。
しかし1789年のフランス革命で、王立植物園は機能を停止する。
 「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
財務委員会は王立標本館を植物園に合併し、標本館に働いていたラマルクと鉱物を管理していた地質学者フォジャド・サン・フォンの職がまず廃止されてしまう。
ラマルクは自分のこれまでの仕事の報告と、将来計画の2つの書類を国民公会に提出。
園長の座をビュフォンから次いでいたフロ・オー・ド・ラ・ビアルドリはラマルクを支援したが、ほぼ無力だった。
1791年、植物園長ラ・ビアルドリは罷免、7月1日に新たに作家のペルナルダン・ド・サン=ピエールが園長に指名される。
また、ジョセフ・ラカナル(1762~1845)が公民公会に自然博物館の創立を提唱して認められ、設立法令が1793年6月10日に出る。王立植物園の土地、施設すべてはそちらに移される。
園長(アンダンタン)という職自体が廃され、ベルナルダン・ド・サン=ピエールも必然的に職を失った。館長(ディレクトール)は教授が任命された後に、教授間の互選でドーパントンにきまった。
ラマルクは昆虫、蠕虫を担当することになった。これは、「他に誰もいないから」という消去法的な決定だった。植物園の植物担当の枠は先に埋まっていて、昆虫、その他の虫、顕微鏡でしかほぼ確認できない微生物などは、あまり人気のない分野だったらしい。
おそらく長く、動物といえば脊椎動物だった。無脊椎動物への関心は驚くほど低かったと思われる。自然世界を長い書物にまとめようとしたビュフォンの壮大な試み『自然誌』においても、その扱いはひどい。ビュフォンは自身が哺乳類について書き、鳥類、両生類(当時は一般に爬虫類もふくむ分類)、魚類は他の学者にたのんで書いてもらった。しかし昆虫類や蠕虫類は書かれなかった。おそらくまともな専門家がいなかったため。
 「ビュフォン、博物誌の地球の理論」太陽系の冷却と、生命のための有機分子の謎
「ビュフォン、博物誌の地球の理論」太陽系の冷却と、生命のための有機分子の謎
だいたい、昆虫はともかく、蠕虫に関しては、ようするに、一般的であった分類(脊椎動物か昆虫)にあてはまらない、つまりよくわかっていないあらゆる生物を、とりあえず入れておくゴミ箱のような分類だったとされる。
 「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
ラマルクも、単に趣味的な貝の研究を除けば、ほとんど門外漢状態で、このマイナーな分野を担当することになった。すでに50歳くらいだった。
そして彼は、近代科学において、おそらくこの分野(無脊椎動物学)の最初期の専門家(スペシャリスト)となった。
そもそも『無脊椎動物(invertebrates)』という用語自体、彼が作ったものである。
さらに後1802年に、彼は「生物学(biologie)」という用語も作る。
無脊椎動物学者時代。進化論の提唱
フランス革命暦8年(西暦1800年)の花月21日。革命前はシュヴァリエ(ナイト)、要は下級貴族であったラマルクは、その頃にはただの市民。彼は革命思想自体は快く受け入れていて、貴族の称号に未練もなかったようだ。
この年のラマルクは、パリ自然史博物館動物学部門が開催した年間講義第一回にて、自らの進化理論を公にしたことが、特によく知られている。
ラマルクは翌年にその講義の内容を、無脊椎動物に関する論考『無脊椎動物学大系』第一巻にまとめた。
ラマルクの無脊椎動物の分類研究に関する集大成が、1815~1822年に出版された『無脊椎動物誌(Histoire naturelle des animaux sans vertèbres)』全7巻。そして彼は、その研究過程の中で、自らの進化観の修正と拡張も進めていた。1809年の大著『動物哲学(philosophie zoologique)』は、文字通りに生物の多様性の原因としての進化理論が重要なテーマの1つ。
なぜ進化論は認められなかったのか
ラマルクの、植物学、動物学に関する仕事は、生前にもかなり高い評価を受けていた。しかし進化論の場合はまったく事情が違っていた。
「動物哲学」で語られた、見方によっては、ダーウィンのそれよりずっと壮大である進化論。しかしその内容を正しく理解できた者も少なかったかもしれない。進化論という理論自体、一般に広く知られるのに、50年ほど待つ必要があった。つまりダーウィンの「種の起源」の出版。しかしその本が世に出たのは、ラマルクの死から30年ほども後。
貪欲すぎた試み、壮大すぎた世界観
19世紀前半の自然史科学には、実際的な経験主義を尊ぶ気風が台頭していたともされる。それで、おそらくラマルクが好んだ「体系構築の精神」、壮大で包括的な理論を求めるスタイルは、時代遅れとされたかもしれない。
後のダーウィンの進化論が、例えば「生物の真の起源」など、ほとんど手がかりのない領域を”とりあえず無視して”、生物世界での多様性増加の理由に焦点を絞ったのに対し、ラマルクは、まさしく生物世界がこの宇宙に存在できる理由までも、自分の理論体系に含めようとした。しっかり全ての疑問に完全に答えようとした(そして、当然ながら、今見れば明らかに、いくつかは完全に失敗している)
 種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
また、学会における晩年のラマルクの弱い立場の原因の一端は、彼が、アントワーヌ・ラヴォアジエ(Antoine-Laurentde Lavoisier。1743~1794年)の始めた化学革命の成果を拒否したためかもしれない。例えばラマルクは、否定された熱素(フロギストン)を、自身の化学体系に残し続けた。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
ラマルクとは違い、新しい化学を受け入れていた同僚のキュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier。1769~1832)は、化石の原因の説明としての、ラマルクの進化論に反対した。キュヴィエ自身は、化石はかつて、一度、あるいは複数回起きた天変地異による大絶滅の痕跡と考えた。
 「化石の謎」大地の動きの理論、無生物起源説。いくつかの論争
「化石の謎」大地の動きの理論、無生物起源説。いくつかの論争
キュヴィエの進化論への攻撃
しかし、キュヴィエの天変地異説も、それなりの根拠があって、しっかりと考えられた上でのものであったが、彼が参考にした書物の中には聖書(のノアの大洪水の記述)があったために、現代では盲目的な信仰のための愚かな間違いとかいうイメージを持つ人もいる。
 「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説
「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説
そして現代の不当な評価は、進化論者の後輩であるダーウィンと同じく、宗教からかなり背を向けたラマルクの進化論も同じと思われる。
生物や進化論をテーマとした多くの書籍において、ラマルクはただ、「獲得形質の遺伝」、または「用不要説」という、オカルト的な説の提唱者として紹介されてきた。そんな物語をメタ的視点で見た場合には、それはまるで、ダーウィンが提唱した、非常に優れた自然世界のメカニズム『自然淘汰』の引き立て役である、バカな理論かのよう。
しかしとにかく、キュヴィエは、ラマルク(というか彼の進化論)の評判を明らかに落とした(あるいは落とそうとした)。
単に傑出した生物学者というだけでなく、文才ある賢い政治家で、影響力強い反進化論者であった彼は、同じ博物館の先輩であるラマルクの死に際して弔(とむらいの言葉。挽歌)をしたためることになった。それは1832年11月26日、パリのフランス科学アカデミーで朗読され、後『フランス王立科学アカデミー回想録(Memoiresdel’ Académie Royaledes Sciencesde l’Institutde France,vol.XIII。1835)』に掲載されたという。英訳版も『エディンバラ新哲学ジャーナル(Edinburgh New Philosophical Journal Vol.XX。1836)』に掲載された。
「すばらしい博物学者の生涯。その人物が学会にて成し遂げた有益な業績を賞賛するのは当然であろう。しかしまた、生き生きとした空想に耽りすぎたあまりにもたらされた、疑問視すべき類の業績をも重視するべきと私は考える。その原因、逸脱に至った系譜とでも言うべきものを指摘することも、我々の義務であろう。
これは我々が、歴史から学んできた原則である。それ(愚かな業績の適切な批判)を行うことで、仲間との思い出のために、残された者たちの敬意もより純粋なものになると考えている……」
そして彼は、まもなくラマルクの人生を簡潔に紹介し、いくつかの重要な業績を紹介し賞賛した後、しかしラヴォアジェなどの新しい化学体系に対するラマルクの態度には疑問を呈したりする。そして話題は進化論に移る。
「1802年に彼は……彼自身に特有の生理学を含む『生体の研究』を出版した。彼の意見では、卵には受精する前に生命のために準備されたものは何も含まれておらず、ひよこの胎児は精液蒸気の作用によってのみ生命活動を受けやすくなる。この蒸気は、胚の場合のように、有利な環境に置かれた物質に作用することができ、それが組織化され、生命に適合するため、私たちは自然発生の概念を形成することができるのだと。おそらく熱が、そのような初期組織生成に関連する自然要素。電気も連動して動作することがあるかもしれない。
ラマルク氏も、鳥や馬、昆虫などは、そのように直接形成できるとは信じなかった。しかし多様な生物種の中でも、特に最も単純な生命群に関して、完全にそのような理由のみで形成されることも想像するのに彼は抵抗を感じなかった」
そして自然発生では生じないようである複雑な生物はどのように生じたか、という問題に関して、ラマルクの進化論が説明され、そしてキュヴィエは、それを実にシンプルにこき下ろした。
「……組織化された液体により興奮したオーガズムが長引くと、含まれている部分の一貫性が増し、含まれる動く液体に反応しやすくなり、過敏性が生じ、結果……自ら発展させ始めた存在の最初の努力は、生存手段を獲得し、それ自体で栄養器官を形成する傾向にあるとした。
……様々な状況によって生み出された他の欲求や欲望が、別の努力にもつながり、さらに様々な器官も生み出す……
水鳥の足に膜を形成するのは、泳ぎたいという欲求とその試み。さらに水の中を歩くと同時に、濡れることを避けたいという欲求から、頻繁に川の岸辺を歩く人たちの足は長くなる。飛びたいという欲求はすべての鳥の腕を翼に変えた……
そんな原理が認められるなら、単純なモナドやポリプスが、徐々にカエル、コウノトリ、ゾウに変身するために必要なのは、時間と状況だけということは、確かに容易に理解できるだろう……
……ラマルク氏がその後に出版したすべての動物学の著作に、そのような生命理論が含まれている……しかしその体系的な部分が攻撃の対象となるほど危険であるとは誰も考えもしなかった。それは彼の化学理論と同様にそのまま残されたが、同じような理由だろう。詳細における多くの誤りはともかく、それが2つの任意の仮定に基づいていることを誰もが認識できたから。仮定の1つは、胚を組織するのが精液の蒸気であるということ。もう1つは、努力と欲望が臓器を生み出す可能性があるということ。
そのような基盤に基づいて確立されるシステムは、詩人の想像力を楽しませるだろうし、形而上学者が新しいシステムを導く手がかりにもなるかもしれない。しかし、そんなのは、手や内臓や羽を実際に解剖したことある人の検査にわずかさえ耐えることなどできないのだ……」
 「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
生物種の変化
キョヴィエと同じく、国立自然誌博物館でのラマルクの若い同僚であった動物学者エチエンヌ・サンチレール(Étienne Geoffroy Saint-Hilaire。1772~1844)も、ラマルクの進化論を受け入れなかった。
しかし彼は、生物種の変化という現象は認めていた。彼は、種が変る原因が主に奇形と考えた。奇形の個体が十分に数を増せば、それはもう奇形でなく新しい種にもなりうると。
サンチレールの説は、遺伝学とダーウィンの自然淘汰説を繋げる役割を果たした後の突然変異説の先駆とされる。
しかしキュヴィエは、奇形の個体はすぐ死ぬと、サンチレールの進化論にも賛同しなかった。
 DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
ただサンチレールは、そもそも進化論自体に、それほど執着していたわけでもなかったそうである。
彼が最も重要であると考えた自身の業績は「プランの統一性」の仮説。つまりは「全ての動物には、ただ1つの基礎プランがある」という仮説。これは「動物は、絶対的に別れている4つの型からなる」というキュヴィエの考えとまったく相容れない。それで両者の論争は、キュヴィエがコレラで死ぬまで続いていたという。
ダーウィンとイギリス
ダーウィンは、ラマルクの説をどう見ていただろうか。
まず彼が、自身の進化論を提唱する以前から、ラマルクのことを知っていたことはかなり間違いない。
『動物哲学』は、出版から5年後(1814年)に、英訳された。ただし訳者は、例えば「besoin(欲求)」を「will(意志)」と訳し、ダーウィンを含めた多くのイギリス人に、ラマルクの考えを少し(神秘主義的な方向に)誤解させたともされるが。
 「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い
「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い
そもそもダーウィンに大きな影響を与えたとされるライエル(Sir Charles Lyell,1st Baronet。1797~1875)も、ラマルクの説を英国に紹介した1人であり、その支持者でもあった。
ライエルは、地球の表面の地形が、長い時間をかけて徐々に今のものになったという説を強く唱えた。彼は斉一説、つまりは今起きていることは過去にもずっと起きていたことのはずだという思想を基盤としている。キュヴィエの語る大激変というのは、彼の自説にとっては都合の悪いものだった。
人間の目では確認できないくらいの小さな変化の積み重ねが、今の世界を作ってきたという考え方。そういうところが、ラマルクの仮説と適合しやすかったのだと思われる。
真理か、空想の産物か
彼は、自分の考え(推測)のいくらかは、まさに革新的であるのだと、はっきり自覚していた。
彼自身の見解は「……世に認められている見解は、一般に、みずからをしりぞけようとする新しい見解に対して影響力を行使する……古い思想がはじめて現われた思想にふるう権力は偏見を助長する。すこしでも利害がからむ場合には、ことにそうである。行きつくところ、自然を研究して新しい真理を発見することがどれほど困難であるにせよ、その真理を世に認めさせることのほうがさらにむずかしいということになる」
ただし彼は、知識に対するそのような懐疑的な見方に関して、総合的には好意的だったようだ。
「この種の困難はさまざまの原因に由来するが、結局、知識一般のありかたに対して有害というよりは、有益である。というのは、新しく提出された見解をやすやすと真理と認めさせない厳正さのおかげで、多少はもっともらしいけれども根拠のない山ほどの奇異な考えは、現われたかと思うと、たちまち忘れ去られるからである」
例え、真理が最初は排除されたりする問題があるとしても、空想の産物が簡単に受けられるよりはいいと。
おそらく彼自身が発見した進化論や、それが存在する生物世界は、彼としては受け入れられにくいだけの真理だった。
ただ、実際受け入れなかった者たちにとっては、それもまた想像の産物。
娘の言葉
確かに、ラマルクの晩年は明らかに不遇だったと思われる。
彼は、生物に興味を抱いた時からの自らの世界観を、研究データが増えるたびに調整しただけでない。ついには、自身の世界観を全く変えた(しかもそれは、誰に動かされたわけでもないだろう。完全に彼自身が考えた説。1つの単純な生物から、驚くべき地球生物の多様性が生まれえるという世界観)にもかかわらず、彼には(キュヴィエなどがそう指摘しているように)細かな実験結果とかよりも、自身の壮大な世界観に適合する考え方を優先する傾向があった。
だからこそ彼は、新しい化学をどうしても受けれなかったし、ダーウィンほどに説得力のある進化のシナリオパターンを思い描けなかった。
それでも、生物学の歴史全体を見た時、彼の貢献は計り知れないほど大きいと思われる。
パリの植物園のラマルクの銅像の台座の背面には、1つの青銅板がはめこまれている。晩年には盲目となっていたラマルクを娘のロザリーがなぐさめている様子。青銅板の右下には、ジョフロア・サン・チレールがある時に聞いたらしい、ロザリーの言葉が刻まれている。
「後世の人々は覚めてくれるでしょう。彼らが必ず仕返しをしてくれますよ、お父さん(La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon père)」
動物哲学
「……多数の事実が知らせるとおり、種のあるものの個体は、状況、気候、生存様式あるいは習性を変えるにつれて、その影響をうけるために、諸部位の堅実さと比例、形態、能力、体制までもがすこしずつ変わっていく。こうして、それらの個体にそなわる一切は、時間とともに、個体がこうむった変動をともにする。
同じ気候においても、状況と地勢が非常に異なると、はじめは、そこに身を置いている個体を変異させるだけであるが、代々同じ環境のもとで生活し繁殖して、棲息の場所がひき続いて相違していると、時の経過とともに、いわば生存に欠くことのできない相違が個体にもたらされる。こうして、多くの世代があいついだのち、これらの個体は、もともとある1つの種に属していたのに、ついに、それとは異なる新しい種に姿を変えてしまう」
この大著は、ラマルクの著書の中で、今となっては最も有名である大著。一般的にこれは、彼の生物学研究の集大成。
『科学の名著 第Ⅱ期 5 ラマルク : 動物哲学』
不完全から完全への系列
「……実際、動物の系列をもっとも完全なものからもっとも不完全なものへとくだるにつれ、体制の構成に見出される漸退(少しずつの退化)という特異な事態に直面するはず。多くの証拠から証明されたその事実の由来を。私は探究せずにいれなかった。そしてまさに、『自然は、あらゆる動物に生命をもたらす時、最初にもっとも単純なものからはじめ、複雑で構成的なものを順次生みだしていった』と私が推測したのは当然でなかろうか。動物系列の階梯(段階)をもっとも不完全なものからもっとも完全なものまで見ていく時、そこに確認できるのは、『しだいに構成的となっていく体制』、そしてやがては『驚くべきほど複雑な構成』も見つけられる」
少なくともある時期、ラマルクは、古くからの宗教的世界観、などでお馴染みである、「生物(あるいは生物構造)の序列」を普通に見ていた。ある「完全な生物」に対して「不完全な生物は~」というような言い回しも、「動物哲学」の中でよく見られる。全体の構成(構造)のある部分に関して「もっとも不完全」と表現することも。そして、完全なものと不完全なものの違いというより、それらの連続的な変化を見いだしたことが、重要なきっかけ。
「……人間において、体制は構成と完成との終局にまで達しており、生命現象の原因、感性の原因、人間のそなえるさまざまの能力の原因において最大の複雑さを提示しているので、多数の現象の源泉をつきとめる参考にはなりにくい」とした彼にとって、注目すべきだったのは、見いだすことが可能な、もっとも単純な生物。つまりは「すべての体制のうちでもっとも単純な体制」、明らかに「どんな特別な器官も確認できないような体制」。
ただし、生物(というか何らかの体制、構造)として定義できる時点で、文字通りそこに「何もない」はずはない。ラマルクは、もっとも単純な生物が有するわずかな器官は、まさに生物の最低条件要素、全生物(あるいはそこから始まる系統の全生物)に共有されるような基礎要素と考えた。
ただし、(同系統の)全生物に、まさに単純な一直線の道のような段階(これが多くの古い世界観で一般的な説であるのは、人間をもっとも優れた生物と考えるためと思われる)を見るなら、生物種を(特徴、性質、複雑度合いなどを手がかりに)分類してみた時、それら分けられた生物種は、段階ごとに並べられることになる。ところがそうなると、例えば人間は鳥より先の段階にいるとして、鳥には人間にはない飛翔に利用できる翼があるのはなぜか(鳥類と考えられる生物群内だけで考えても、例えば翼が退化した飛べない鳥などをどう考えればよいか)。このことに関しては、一応、ある(以前より優れた)複雑な構造では、以前の(より単純な)場合には問題なかった要素が、全体にとって厄介な問題になってしまうから、とか考えられなくもないが。
結果的にラマルクは、枝分かれする系統樹という説を立てることになるが、それは今の進化論に慣れている我々には想像も難しい、困難な道だったろうか。
ただし、枝分かれ進化で本当に大きな問題は、ある生物(例えば人間)が他のどの生物より絶対的に優れているという、ある世界観における事実だけかもしれない。
 「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
生物世界の多様性は、創造者のデザインか
「動物哲学」においては、ラマルクはあまりキリスト教的な創造世界を前提とした思想に気を遣っている感じは薄い。少なくとも後のダーウィンの「種の起源」よりは。これは革命直後であったフランスと、イギリス、あるいは周囲の人たちの思想の違いや、当人の気質なども関係していたと考えられる。
それでも、(そういう節がある訳だが)ラマルクがなかなか一本道(でなくともそれほど多くはない系統パターン)から、彼が集めた様々なデータを説明しやすいはずの枝分かれ進化に、なかなか転向できなかったのは、(間接的にでも)宗教的理由かもしれない。
まず、当時(18~19世紀)のヨーロッパにおいて、創造説、つまりは「この宇宙と、全生物が、神と呼ばれる創造が可能な何者かに創られた」という説は、平均的にどんな扱いだったか。
(キリスト教のような)ヤハウェなる神に関連する多くの宗教とかで、人間が特別な生物であるのは、創造神がそのように創ったからだろう。もちろん創造神が、ある文明の機械屋(プログラマー)とかであるとしたら、それは(この宇宙が例えばコンピューターシミュレーション上のバーチャル宇宙として)そういう設定、とする方がいいかもしれないが、そのような、世界が実はバーチャルワールド説が、コンピューターもない時代にそれほど一般的だったとは考えにくい。
 「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
創造が行われたのがいつのことにせよ。それは少なくともこの宇宙において、ある構造がなぜこの宇宙に発生できたのかを簡単に説明できる理由となる。始まりなどない、無限の宇宙(世界)というのは、むしろある宇宙を(方法はどうでもいい、魔法でもテクノロジーでも)創る何者かよりも、想定するのは困難かもしれない。今でもそれはそうだろう。
もちろん創造説では、”創造者自身の起源が謎”という問題が残る。しかし我々の宇宙が創造されたものとしたら、つまりそれは、他に起源が説明しようがないような構造の世界というだけの話なのかもしれない。つまり現実の創造者の元々の世界は、始まりが明らかか、あるいは無限に続いていて何もおかしくないような、そういう、”我々の知らない”世界観なのかもしれない。
 「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
では、仮に創造者がいるとして、どんな世界を作ったのか。よく語られているように、ダーウィンが、自身の進化論研究が進むにつれて、幼い頃から持っていた信仰を棄てたというような話。それに確かに、進化論が、なかなか教会に受け入れられなかったという歴史の話は、注目すべきものかもしれない。
明らかに、創造者がこの宇宙を創ったと考えることは奇妙ではない。少なくとも自然の進化システムの存在が、その否定の根拠になるはずがない。単に、そういう原理が存在する、または定義できるような宇宙を創造者が造ったと考えればいいだけだ。
また、完全な決定論的世界観は、神の前で、よき者、悪い者という、おそらく多くの宗教で好まれている設定と明らかに矛盾する。この世界の何もかもが神のシナリオ通りにしか動くことのできない映画のようなものであるならば、そもそも誰がいいも悪いも(あるいは信じるも信じないも、信じなさいも)ないだろう、全部単に、絶対変えることのできない脚本通りのことであるだけ。少なくとも世界をこの宇宙に限定する限りは、決定論は、実質的に道徳だの自由だの罪だの、そういうのすべて、それらのカテゴリーのどれかに最初から当てはまることが完全に決まっている自分たちにとって、議論に意味のない話になってしまうと思う。
だから通常、宗教は、この世界に生きる者たちにある程度の自由が許されていると考える必要がある(そうしないと、こういうことを考える意味がなくなる)。
だが今でも、(それがどういうものかはともかく)最も基本的な物理原理は、おそらくこの宇宙で不変だろうとよく推測されているように、創造者が決めた絶対的な要素はないと想像するのもまた難しいのでなかろうか。例えば、仮に完全に何もかも変化が自由な宇宙であるならば、おそらく決定論的世界観と同じような問題が生じる。例えば、何がよきことで何が悪いことか、それどころかどのような存在が神であるのかも変化するような宇宙を想像してみたらいい。仮に何かの宗教が正しき宗教なのだとして、世界の変化に合わせて、それ自体も変化する必要がある訳である。ある時によき宗教であっても、世界が変化した後では悪になる可能性もあるだろうから。常に正しい状態に変化し続けることなんてできるだろうか、とか。
とにかく、宗教的世界観は、たいてい主張している内容と矛盾しないように、世界にある程度の自由性とある程度の不変設定のどちらも存在する必要がある。そしておそらく生物という存在の、原理的な基礎は、不変カテゴリーに含まれるというのが、一般的な考え方だったのだと思う。おそらくそうでないと、「神に愛された特別な生物、人間」というような設定も危うくなるからだろう。そして進化論から見出される自然のシステムは、明らかに不変の生物界という設定を危うくする。
ただし今においてさえ、進化システムは、生物種を生み出すことは説明できても、生物なる存在それ自体の発生をうまく説明することはできない。誰も無生物の領域で、生物が発生するのを確認したことはないようだし、そうだとはっきり言えるような痕跡が見つかっているわけではない。
例えば、進化システムによって生物種が増えていったというパターンには、明らかに時代ごとに(ただし全く別の存在から別の存在とかでなく、共通の有効そうな器官などを残しながら)変化していた多種多様な生物の化石群など、強い証拠がある。
しかし、創造者は生物を造り、その後それらが自由に様々な世界の領域に対応し、広がっていけるよう、枝分かれ系統樹システムを世界に設定した、とか言うように考えるのも嫌だったのだろう。結局、ヤハウェの信仰者たちが、進化論から守りたかったものは、神聖な世界観というより、人間(それも、劣っているとされた人種の議論なども踏まえると、特別な一部の人間種)の特別性だったと言えるのかもしれない。
 「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種
「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種
そのような宗教的思想の影響が、実際のところどのくらいだったのかは、今となってはあまりわからない(例えば、処刑の恐怖などから、実際の思想と別のことを口では言っていた者がどれくらいいたのかなどは、かなり謎だろう)。だが様々な大胆な発想をした科学者たちでも、ある生物種がある生物種に変化することもある(場合によっては、今は全然関係ないようなある2種の生物種でも、長く時間をさかのぼれば、共通の祖先を共有してもいる)というような考えを、なかなか抱けなかったらしいのは、かなり確かなことと思われる。
新たな種を次々生むような生物構造の変化がないものとしたら、存在する全ての生物種は、それぞれ創造者のデザインによるものと考えるのは妥当だろう(他の可能性が何か考えられるだろうか?)。創造主を仮定しないとしても、それぞれの生物が、時空間の場の別々のところで各自に発生したと考える必要があるはず。
よく考えてみると、生物種が変化しないことが明らかなのだとしたら、まさに生物種の多様性こそが、創造者の実在の強い根拠になるのかもしれない。
ラマルクは、変化の分岐による生物種の増加という現象に傾いたばかりの頃は、まだ発生源の場に関しては複数あると考えていた節がある。明らかに彼は、その研究のためのデータが集まるにつれて、考えを変えていった。つまり発生の場を少なくしていって、最終的には2つ、もしかしたら1つとした。
ただ、どうもその1つの発生というのが、この宇宙の中でただ一度起こった発生というわけではなくて、今の様々な生物種が、1つの共通の系統に属している、というように考えただけのようでもある。
そのような彼の考え方の変化も、「動物哲学」からは読み取れる。
万物の創造者の意志
わずかながら、「動物哲学」の中で、創造説は当たり前の事のようにも語られてもいる。ただしそういう部分からは、「そういう事実に関して別にどうでもいい」というようなスタンスも読み取れるかもしれない。
「……もちろん万物の至高の創造者の意志によらなければ、一切のものは存在しないだろう。しかし私たちは、彼が意志を実行するにあたっての諸規則を決定し、彼の従った方式を定めることができるのでなかろうか。彼の無限の力は、私たちの眼にするすべてのもの、そして存在してはいるが私たちの知らぬすべてのものをつぎつぎに生みだしていく事物の秩序を創造することができたのではないか。
たしかに、彼の意志がいかなるものであったにせよ、彼の力が無限であるのはどこまでも同じである。そして、至高の意志がどのようなやりかたで実行されたにせよ、なにものもその偉大さを減じることはできない。
だからこの無限の叡智の命令を尊重するものとして私は一介の自然観察者の枠内にとどまっている。そこで、自然がその産物をもたらすのに従ってきた歩みに、私がなにごとかを洞察することができたとするなら、私はみずからを欺くおそれもなく、こう言いたい。自然がこの能力との威力をそなえることが、創造者の意にかなったのである、と」
生物の型はファンタジー的か
生物構造不変の世界観について、もう少しだけ考えてみる。
つまり生物種ごとの型という発想。
そういうのは、例えば神秘的に聞こえるだろうか。しかし、長い時間をかければ、例えばムカデのような生物から、ゾウのような生物への変化もありうるというような考え方よりも、各生物種には各個体に基本構造を与えるような型があるという方が、説得力あるように聞こえた時代もあったかもしれない。
我々、現代の多くの人は、進化論をよく知っているだろう。そして、十分な条件が整えば、ある生物種が別の生物種に変化したり、あるいはそのような変化から新たな生物種が分岐して誕生することもある、というような世界観にかなり慣れてしまっていると思う。
例えば、表面には地球以上に(そういうものが実際あるのなら、まさに生物に適した)多様な環境があり、一方で特殊な外部環境のために、地球よりもずっと長い時間を存続可能な惑星が見つかったとする。
しかし、生物が存在しやすい環境にも関わらず、生物が見つからないその惑星に、10種類の地球生物をばらまいてみたとする。そして、そこから去って、50億年後に戻ってきたとする。50億年前にばらまいた生物が絶滅せずに繁栄し続けていたとして、そこに存在しているのが、ばらまいた10種類のみだったら、驚くのでなかろうか。
だがもしも生物の種の構造に不変な型があって、ある種がどれほど世代交代をどのような環境で繰り返したとしても、いつまでもその種でしかないというような世界観であるならば、たとえ長い時間が経った後に、10種類の生物が(同じ)10種類の生物のままなのだとしても、特に驚くべきことではないはず。型の変化はなくとも、生物の自然発生がありえるというような世界観でも、そこは自然発生した生物は除外することのできるシステムでもあると考えればいい。
生物の型という考え方は、ファンタジーの設定的な印象を持つ人もいるかもしれない。だがそうとして、それもまた、小さな素粒子ばかりを基礎とする原子論的世界観とかに慣れているからかもしれない。
例えば我々が一般的に(それ以上分割できない最小要素の意味での)原子と聞いて、イメージするよりもずっと大きな原子があるとする。ある生物構造に必ず必要なものが、その巨大な原子Aだとすれば、それはまさに、その構造の型のように考えられるのでなかろうか。
そもそも、生物構造の情報保存コードのようなものとも考えられるDNAとかでも、その実態は、ある種の配列の物理的構造というイメージが一般的と思う。それは時空間の中、外部の影響により普通に変化もできるようなもの。
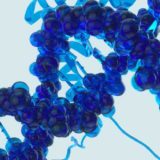 「DNAの発見」歴史に消えた多くの功績、歴史に残ったいくつかの功績
「DNAの発見」歴史に消えた多くの功績、歴史に残ったいくつかの功績
ようするに、生物構造に最低限必要な要素でも、すでに構造体というイメージが、おそらく現代の人にはなじみ深すぎる。ある構造体が不変というのはある種の非物質的な原理を思わせだからこそ神的に感じるのでなかろうか。もしもその生物の型となるものが巨大原子的なものであるならば、少なくともそれを構造体と考えるよりは神秘性が薄れるのでなかろうか。
ただ、真の原子(最小構成要素)というものがあって、また原子にすでに種類があるとして、ある原子の集合構造よりも、巨大な別の原子があるというのは、どういうことか。時空間の中を原子が漂う時、空間のある部分を、その原子が埋めていると考えることができると思う。大きさを有するならそうであるはず。
それとも、分割できない物質が存在できる、時空間という領域を奇妙に考えるべきか。
特に、唯物論的宇宙において、原子論が完全に正しいのだとしたら、全ての原子が完全に同じものであると考えるのは、どうにもおかしい気がしてならない。大きさか場所か形か、何も違わない場合、様々な物質の構造のための違いを生み出せるだろうかと。だが原子に種類があるのは、やはりそれはそれで妙かもしれない。
では、どう考えるべきか。
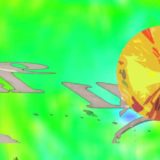 「超ひも理論、超弦理論」11次元宇宙の謎。実証実験はなぜ難しいか。
「超ひも理論、超弦理論」11次元宇宙の謎。実証実験はなぜ難しいか。
しかし現代の我々が考えるなら、型は背景に埋め込まれてる設定とか考えた方がわかりやすいだろう。この世界がもし、コンピューターシミュレーション上のバーチャル宇宙であるならば、生物種の型を不変にするために、クリエイターは、基盤となるプログラム内に、その設定を書き込んでいるとか。
地球の世界、地球外の世界
しかしラマルクの時代。生物構造の、一本道の序列が真であるとしたら、明らかに奇妙なことは、もはや観察事実との矛盾だけではなかったろう。
 「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
すでに宇宙における様々な天体と、その動作原理(ニュートンの万有引力)らしきものも知られていた。地球表面というこの世界が、真の全体から見るとごくわずかな領域ということもかなり明らかだったはず。
おそらく、この生物の世界は地球表面(地球内部に)のもの。
 「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
また、火星や金星など隣の惑星に関しても、わかっていないことがあまりに多かった。さらに神の教義は、他の惑星の生物世界を禁じるものでない、というような説もあったらしい。ようするに、宗教にもそれほど関係なく、地球外生物を想像する向きも普通にあったろう。
ただし想像された他の惑星の生物世界も、たいていは、地球と同じような世界だったと思われる。少なくとも人間が最も優れているというような生物構造の序列パターン(というか人間に限らず、あらゆる生物の序列が)が、不変なものであるなら、例えばどの惑星世界においても、そこで最も優れた生物は人間ということになるはず。仮にそこが地球よりもさらに進歩した状態にある世界だったとして、また人間よりも優れた生物が実は存在するのだとしても、考え方としては変わらないだろう。
もちろん生物構造から別の生物構造が生まれることのないような創造世界なら、他のどの世界においても、様々な生物をデザインしておいたのは創造者に違いない。しかし、そうだとして、そのような世界がいくつもある理由は何か。世界自体に多様性がないというのなら、創造者がたくさんの世界を造ったのはなぜかを、どう説明すればいいのか。世界の存在する場所が重要なのだとしても、そういう仮定を増やせば増やすほどおそらく世界自体は世界全体としてはとても複雑となって結局のところこのちっぽけな地球世界の重要性はどんどん小さくなっていくのでなかろうか。自分たちを特別な存在と考えたい宗教的思想の上で、本末転倒もいいとこだろう。
 「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
生物の多様性の一般的な原因
ラマルク自身の語るところによると「私は自然博物館において、脊柱を欠くゆえに無脊椎の動物と私が命名した動物群の講義をまかされたので、これらの動物を多数調査し、関連する観察と事実とを蒐集し、さらに比較解剖学に解明の手がかりを借りた。おかげで、この研究に多大の興味をそそられ、これにもっとも高い評価をあたえるようになった」
確かに、最も単純な(あるいはそうとされた)生物の研究を始めたのは他に対象がなかったからという、消極的理由だったとされるが、ただ彼は、「生物種の起源のようなむずかしい問題を解決する的確な手段は、あらゆる体制のうちでいちばん単純な体制を見出すことだろう。なぜなら、この体制のみが生命の存在に欠くことのできない諸条件の充足を示しているはずだから」とも書いた。
どれくらいにそれは、研究対象として無視されていたのか。「動物哲学」には、ある種の説得のような言葉も見られる。
「実際、無脊椎動物の研究は博物学者の関心を強くひきつけるはず。第一に、これらの動物種は自然界において脊椎動物の種よりもはるかに多い。第二に、数が多いために、種は当然いっそう変化に富む。第三に、体制の変異がはるかに大きく、際立ち、特異である」
そして最後に示した第四の理由が「自然が動物のさまざまの器官を順次形成するのにもちいる秩序は、無脊椎動物の器官がこうむった変動によりよく示されている」。だからこそ、様々な体制の起原の研究サンプルとして、それらは非常に適しているとする。
ただし、単純な生物が様々な変化をして、だんだんと様々な複雑構造を生んだ、というような世界観の場合、それが少しずつでも、急速でも、実際の複雑構造の部分部分が、本当に単純構造に生えてくるものなのか、という疑問が当然ある。
「私はそこで、観察の結果すでに到達していたつぎの2つの考察をもちいれば、この問題の解決を発見できると信じる」
それでラマルクが到達していた考察とは以下のようなもの。
まず第一が「ある器官を休みなく使用すると、発達がうながされ、器官は強化されたり、大きくなることがある。一方で、不使用が習性となれば、発達は阻害され、その器官は小さく、役立たずになっていく。さらに不使用が、生殖の連鎖の中で、全個体で長期間継続する場合、ついにはその器官が消滅もすること」。
さらに流動体の運動と、流動体を含むきわめて柔軟な部位への作用力のことを考えていて、ふと悟ったらしい第二が「ある有機体内部の流動体は、(例えば複雑化する構造の影響もあり)運動を加速されるにつれ、みずから動く場としている細胞組織に変化をあたえ、そこに通路を開き、多様な導管を形成し、ついにはその流動体が含まれる体制の様態(様相)に応じ、さまざまな器官を創造するようであること」
彼なりに見出したこれらの事象と、生物が生息地を広げるにつれ直面するであろう様々な環境の方の多様性を合わせ、ラマルクは、彼の進化論の重要なキーとして有名な『用不用説(use and disuse theory)』を導出したらしい。
ただし、「現在の生物の多様性の、二つの一般的原因」とラマルクが考えた上記の内、今では前者(第一)に比べ、後者(第二)はマイナーと思われる。
第一はわかりやすい。よく使う器官は発達して、あまり使わない器官は退化していく。それが子に受け継がれ、やがて生物グループの中で長く使われてない器官は完全に消滅すらすると。だが多分ラマルク自身も、これだけだとおそらく単なる空想にすぎないと、いくらかは考えていた(少なくとも、第一だけに注目し、彼を空想詩人学者というように評価するのは不当と思う)
第二は、そのような世界観の動作機構を考えようとする試みと言えよう。確かにラマルクは、動物哲学のあちこちの考察において、「流動体」というものによく注目している。おそらく彼は、観察できる世界の物理現象から、全体の動作を考えるにあたり、ある構造の(ただしその構造が有する、例えば生物の条件要素を破壊しないような)変化や転移などは、流動体の相互作用によって起こりうるのだろうと推測した。
ただ、確かに彼には、ほとんどはっきりとした証拠もないのに推測に推測を重ねすぎていた節もある。この宇宙の中で、生物がどのように発生し、どんなふうに進化システムのようなものが機能する場を用意するのか、彼は全てを説明しようとした。しかしそんな試みは、おそらく今でさえもかなり無茶な試みである(一方で、伝統的に、すでに古代ギリシャの哲学者が挑戦してたりしたようだが)。
「私は、もっとも単純な体制における生命の存在に欠くことのできない諸条件、もっとも不完全な動物から完全な動物にいたる動物体制の構成の増大を生みだした諸原因を叙述するだけではない。その考察により、多くの動物がそなえる、感性というものの物理的原因さえ認識したかもしれない」
つまり感覚、意識、何かを理解して何かを考えるというような生物の能力。それについての彼の理論も、やはり、流動体が世界の中でどのように機能するかを考える中で、見出されたように思われる。
今でもかなり重要なことの1つは、そうした、感覚というものを動物論的に解釈する物事の捉え方だろう。「……感性それ自体は、それを生みだす能力を有する一定の器官系の諸機能に結果する現象にすぎないと、私は考える……」
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
つまり「動物哲学」という大著は、明らかに、進化という現象について語ったというだけの内容ではなかった。その中で生じる進化現象も含めた、生物と、生物の生きる世界の特殊な場、それら自体を全てまるごと考察しようという(はっきり言って、かなり無謀な)試みだった訳である。
結果はどうあれ、「生物学」という、かなり広範囲を含められる名称を提唱した者らしい。実際、元々は「生物学」という本を書こうと思って集めていたデータの考察も、全てこの本に詰め込んだらしいから、彼自身の認識としては、この試みは生物学以上だったのかもしれない。結果はどうあれ。
だが、何もかも失敗してしまったろうか?
少なくとも初期に生じた生物が、進化現象によって様々な種へと枝分かれしていくというような世界観は、生物学の重要な遺産となった。だがそれ以外は?
境界線の存在しない自然
不完全から完全への系列、自然界におけるそのような順序の存在は、ラマルクもあまり強く否定していないように思える。一方で、それと両立できるものかは疑問である、自然界のはっきりとした「分類」というものには、かなり懐疑的。ラマルクはさらに、ある種が、少しずつの変化により、他の様々な種へと分岐していくという世界観を考えたのだから、なおさら奇妙かもしれない。
分類という方法自体の評価は、たとえ人為的なものでしかなかったとしても、様々な生物種を特徴に応じてグループごとに分けるその手段は、科学研究において非常に便利としている。これは現在でも、多くの人がそうであると思う。
「一、体系的分類。全般、特殊。二、綱。三、目。四、科。五、属。六、各種の区切りおよび個々の事物の名辞。これら六種の方策が自然諸学において一般に使用されているが、これらは人為的に生みだされたもので、観察の対象となるさまざまの自然の産物を配列し、区分するために使用しなければならなかった方策……膨大な数の自然物についての知識を定めるのに助けとなる……
それでもくりかえして言うが、それらは人為的な区別でしかなく、実際のそのようなものは一切、自然界に見られない……自然はみずからの産物に、綱も、目も、科も、属も、恒常的な種も形成したことなどない。単に個体を形成してるだけ。そして個体はつぎつぎに生まれかわり、みずから生んだ個体に似るというだけだ。
……各個体は、多様化した種のいずれかに所属し、種族はどのような形態をとっても、どのような体制の段階にあっても、他と微妙な差異を見せ、なにかの変化の原因が作用しないかぎり、変異せずに自分を保っていく……」
種は、実は連続的だとしても、これまでに存在した全生物を含む生物界の知識に我々が乏しいために、ある種と種がはっきりした境界線で隔てられているかのような印象を受けてしまうと、ラマルクは指摘する。ただし新しい証拠が次々見つかっているとも。彼はどうも、カモノハシやハリモグラのような(つまり単孔目の)卵生哺乳類を、鳥類と哺乳類の間の生物中間的生物ではないかと推測したりもした。
 「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
意識と神経系の謎
神秘的に思えるような感性(すなわち精神?)とかも、唯物論的世界で定義しようというのなら、当然、物質システムとしての説明が必要となろう。
まず、生物の有する感性というものについて、ラマルクは観察データを参考に、そもそもそういうのが生じるためには「神経系の構成がすでにかなり進んでいる必要がある」と考えた。「知性という現象が生まれるためには、神経系がいっそう構成的になっていなければならないだろう」と。
今となっては、彼が導出した説以上に興味深いのはやはり彼の方法であろう。
「……観察によって、神経系がもっとも不完全な様態にあるとき、例えば神経系を最初にもちはじめた動物の場合、神経系は筋肉運動の刺激に働きかけるだけであるようだ。その際に神経系が感性を生みだすことはないと、私は確信できた。同じ様態でも、神経系が提供するのが髄質(ある器官の内層、内部を占める組織)の結節(骨などにみられる隆起)と、そこから発する神経繊維のみ、有節縦走神経索も、脊髄も、脳も示さない場合がある(ここで重要なのは神経系の各部の名称より、その各部が、ラマルクの言う不完全な神経系において不足している、という観察事実なのであろう)。神経系のもっと進んだ構成では、長くのびた形の主要髄質体を示すようになり、縦走神経索なり、脊髄なりも見られるようになる。脊髄の前端が脳を提供すると、これが感覚の中枢を含み、個々の感官の神経、すくなくともそのいくつかを生むのだと考えられる。だから、この様態の脳を所有する動物が、感覚する能力を有するのだろう」
進化理論を見出したのと似ている。
まず精神構造が唯物論的なものであるならば、そのハードウェアとしての実態が神経系であるということは、けっこう古くから有力な説であったようである。そして、普通にある種が少しずつ変化して、別のある種に変わることがあると考える場合、つまりその変化が神経系である場合、ある生物に感覚能力がない(でなくとも乏しい)のだとしたら、それが感覚能力を有する生物に変わる流れのどこかにおいて、確かに、感覚能力(を構成する要素群)が発生している段階があるはずだろう。
むしろここで(ここでも?)奇妙なのは、(たいていの場合、それを守るために進化論を嫌った節がある)生物世界の変化があまりない創造世界の場合かもしれない。
これはまた、よく考えてみれば、感覚能力が神経系のような物理的な構造から生じるものであるのなら、その事実も、不変構造の反対根拠になりうるのかもしれない。
少なくとも、人間が自分のことを理解する時、どうやって理解している? それが感覚によるものだとするなら、自分のことを理解するのに、感覚能力のための物理構造以外は必要ないとすら言えるかもしれない。はたして人間の構造がどこまで重要なのだろうか? もし感覚能力が完全に唯物論的であるとするなら、それを守って、しかし他の構造全てを変形させることもできるのでなかろうか。だとするとその時に、その感覚が認識しているのは人間なのか、あるいは作り変えられた全く別の何かであるのか。
古くはまた、我々が意識と呼ぶようなものを持ってるのは結局人間だけであって、他の動物は、たとえ感情を持っていることを示唆するような行動をするのだとしても、全ては機械的な反応であるという説、つまり、動物は実質的に全てロボットも同じという説もあった。生物構造の変化による、生物種の転移がありえない現象である世界観なら、あるいはそういうふうに考える方が理にかなっていたのかもしれない。
「私は、感覚が作動する機構の決定を試み、知性のための器官を欠いた個体の場合、感覚は知覚を生みだすだけで、個体になんらかの観念をあたえることはまったくできないこと、その特別の器官をそなえていても、感覚が認知されないときはやはり知覚だけであることも示した。感覚のこのような機構が、作動点から発する神経流動体の放出によるものか、この流動体内部の運動の単なる伝達によるものか、という問題については、私はまだ断定できない。ただ、ある種の感覚の持続時間は、それをひきおこす印象の持続時間に相関しているようなので、後者の見解に傾いている」
おそらく神経流動体が構造に与える影響などによる感覚能力のある発達段階までは、観念を持てないと推測している。つまり意識的に何かを認識できることは、不完全な神経系と完全な神経系の違いの1つなのだろう。
そしてこの段階的に発生するらしい、というデータを、ラマルクはさらに参考にした。
「……感性と被刺激性はまったく異なった2つの有機的現象なのだろう。この両者は、これまで考えられてきたような共通の源泉などもたないのだ。どうやら感性という現象は、ある種の動物に特殊な能力を構成し、これがおこるためには特別の器官系が要請されるようなもの。一方、被刺激性という現象は、なんら特殊な器官系を必要とせず、もっぱらすべての動物体制に固有のものらしい。これら異なる2つの現象が、その源泉と作用とにおいて混同されているかぎり、動物体制の大部分の現象の原因について試みられる説明は誤りやすいし、だいたい誤って当然だろう……」
ラマルクは、頭を切除された動物でも、その肉体に、刺激に対する反射反応がしばらく確認できるという実験報告にも注目している。どうも、そのこと(脳を切除されてしまった後の筋肉の反応)を根拠に、脳がなくなっても、体にしばらく感性が残る可能性を考える向きがけっこうあったらしい。
そして話題はさらに、内的感性とか表現される、つまり意識、心の動作に移る。ラマルクは、その考察からまた、特に彼が言う、感性というか神経系という構造自体を持たない「かなり不完全な生物」についての興味深い結論を引き出す。
「……内的感性、感覚する能力を享受する動物のみがもっている、あの存在感覚を考察し……既知の事実、および私自身の観察ももちいて、内的感性というものは必ず考慮に入れなければならない一つの威力であるという確信も生まれた。実際、人間、および内的感性を生みだしうる神経系を有する動物を考察するとき、いま問題としている感性ほどの重要性をつきつけるものは何もないように思われる。内的感性は身体的かつ心的な欲求によってひきおこされ、運動と活動がみずからの遂行手段をくみとる源泉となっている」
環境ごとの必要に応じた欲求が、特定の器官を強力にしうるという、つまり用不用説とも関連を思わせる話である。だが、そこに注目するまでもなくしっかり内的感性を有するレベルの神経系を持っている動物にとって、それが生物としての活動において最も重要なものでないかというような、ここでの考察は、むしろそれを持たない生物に対して疑問を持たせる。
ただ、今となっては、むしろ注目すべきは「私の知るかぎり、これ(完全か完全寄りな神経系を有する生物の内的感性の重要性?)に注意をむけた人はだれもいない。したがって、動物体制の主要現象のもっとも強力な原因の一つについての知識が欠落しているため、現象の説明に考えだされてきたことがらは、すべて不十分なものとならざるをえなかった」というような記述かもしれない。あるいはここでの、「注意を受けた人が誰もいなかった」というのは、用不用説から連想できるような、生物構造(またはその、従来考えられていたよりも柔軟である型)にも高い影響力があるような(まるで、誰もが持つ弱めの魔法みたいな)精神作用とかだろうか。
しかし、やはりラマルク自身もそうであったように、むしろその通り(意識を有する生物の生命活動にとって最も重要な)だとすれば、気になるのは、例えばそもそも神経系自体を持たないような生物(仮にもし、用不用説のみ用いて、あらゆる器官の発生を説明できるのだとしたら、神経系の発生という現象自体がとても興味深いものかもしれない)。
「……明らかなことだ、これまで知られている動物のすべてが神経系を所有しているわけではなく、また所有できるわけでもないから、したがって、すべての動物が問題の内的感性をそなえているとはかぎらず、内的感性を欠くもの、それらに見られる運動は別の起原をもつのだろう」
ラマルクは植物が「外部からの刺激がなければ生命は存在せず、活動を維持できない」ようだとして、多数の動物も同じような存在と考えていいのではないかとする。また自然が何かを行う手段を、その時々に変更するというのは、観察されている事実であるとも。
そしてまた1つの推測。
「私の考えでは、神経系を欠いている非常に不完全な動物は、外部から受容するさまざまの刺激にもっぱら助けられて生きているのであり、それは周囲の媒質に含まれているようなもの。つねに運動状態にある微細な流動体がたえず有機体に浸入し、有機体の様態が流動体に維持力をあたえて、生命を維持していくようだから……植物の生活がこれを明らかに証明していると思われる」
そしてここまでの考察を合わせ、ラマルクは、流動体による、いくらか各種の構造(例えば生命の構造)を壊さないようなわずかずつの(しかし長い時間それが積み重なることによって大きくもなる)変化をもたらすこの複雑な全世界の中での流動体の動作。そして、おそらくそのための様々な生物の環境ごとに変わっていく進化システムなどを確信した。「そしてただちに自然のこの手段、つまりあらたに生まれた個体において、それに生命を伝えた者たちの体制が生命と環境の結果として獲得してきたすべてのものを保持するという手段の重要性を認めた」。
彼のいう(物理的な)感性の原因、神経系の発生はどう考えるべきか。「動物の運動は他から伝達されるのでは決してなく、つねに刺激によってひきおこされることに私は気づいていた。自然は不完全な動物の生命運動と活動の刺激力を得るため、周囲の媒質を頼る必要があった」。明らかにここでは、運動と呼ばれるようなものが、別の運動とか、とにかく世界構造の中の様々な要素の相互作用によって、それぞれ発生しているという世界観を見いだせる。生命活動としての運動も例外ではないはずと。そして構成の複雑な生物の神経系とは、「(周囲の影響による動作の)その威力をまさに動物体内に移しいれるすべ、ついには、その威力を個体の自由にするため」の特殊器官なのではないかと、ラマルクは推測したようだ。
しかし、なぜ自然のまま生きているだけではダメだったのか。なぜ、内部に新しいシステムを作ってまで、自身の動作を自身で決めるような生物が生まれるのか。
複雑性自体が増していっても、それが何を生み出すかということはランダムだろうか。ラマルクは、完全と定義した、つまりその自身のエネルギーの利用法を自分で決めるような生物の構造は、おそらく必然的に生まれたと考えていた。
「……体制が構成的となるにつれて、生命の活力が増大するので、ある限界に達して、生命運動になくてはならない活動を十分におこなうために、自然は活動の手段を増加する必要に迫られた」という訳である。
ラマルク的には、循環系と神経系は、いわば生命体の原因である流動体の動作の加速装置であったようだ。
重要な器官は変化の歴史の手がかり
ラマルクにとって、感性の器官(神経系)は、動物において、(その利用頻度などから考えて)類縁関係を考察するのに重要と考えられる3つの特別な器官のうちの1つだった。
残りの2つは、肺、鰓、気管などの「呼吸の器官」と、動脈や静脈など「循環の器官」。
この中でも重要性という点で、循環の器官は少し劣るという。他の2つは自然界の中でより一般的に使用されているようだから。
そして感性の器官は価値が高い。動物の最も卓越した能力を生みだすから。
生物学は、植物も含めたもの。
植物の場合は「繁殖に欠くことのできない部位が類縁の決定に主要な形質を提供する唯一のものであり、それらの部位を価値あるいは重要性の順位にしたがって以下のように示しておきたい。
一、胚、その付属物(子葉、胚乳)、そして胚を含む種子。
二、花の性的部位。例えば雌しべと雄しべ。
三、性的部位をつつむもの。例えば花冠や萼。
四、種子をつつむもの、すなわち果皮。
五、受精を必要としない生殖体」とする。
全般的な分類については、おそらく完全な自然の秩序的なものに近づいていってる感じで、それはつまり「自然がその産物を存在させるためにたどる歩みを、人間が粗描したものに他ならない」と結論している。それはやはりラマルクとしては、自然界の絶対的な分類というよりも、変化の歴史の痕跡だったのだろう。
古い世界観。不変の形質
「動物哲学」は少なくともその著者(ラマルク)自身の見解としては、それまであまり注目もされなかった、新しい科学的学説を語った本だったと思われる。ラマルクは自身の考える世界観に合わせようとして、まだまだ未知であった様々な要素をいろいろ勝手に確信していたと批判もされてきた。だがそのような彼であるからこそ、打ち破るべき古い世界として持ち出しているものが、むしろ今は興味深いかもしれない。
「ほとんどすべての人たちに承認されている仮定がある。すなわち生物は不変の形質によって恒常的に区別される種を構成しており、これらの種の存在は自然そのものの存在と同じだけ古いものであるという仮定は、観察が十分におこなわれておらず、自然諸学がいまだなきに等しかった時代につくりあげられた。広い見聞を有する人々、長く自然の探究にたずさわった人々、また私たちの自然誌博物館の大量豊富の蒐集品を調査して成果をあげた人々の眼には、この仮定は日々ごとに、否認されつつある。
……ある種の個体が変異することなく世代をかさねるのは、それらの生存様式に影響をおよぼす環境が根本的な変化を見せないあいだに限られるということに注意をはらう人はおらず、世の偏見も似た個体がつぎつぎに生まれかわるという事態に合致していたから、それぞれの種は不変で、自然と同じだけ古く、そして、すべて存在するものの至高の創造者の手で個別に創造されたと思われてきた」
不変の形質とは、自然の生物の型のことであろう。
万物の創造者というものを、ラマルクが本気で信じていたかどうかはわからない。先に述べたように、少なくとも彼は、彼の理論において、それが関係ないような要素と考えていたと思われる。
そして進化システムを普通に想定できるような世界観が、新しいものとして語られる。なぜ、わずかな時間だけを記録してきたにすぎない人々が、現実とまるで違うシステムを思い描いてしまったのか、その理由も。
「……私たちの蒐集品が豊かになればなるほどすべて大なり小なり微妙な差異を示し、目立った相違は消え去り、自然が私たちにゆだねてくれるのは、たいていの場合取るに足りない、いわば幼稚な特質だけと考えるべき証拠に出会う。
……種の決定にながらく熱心にたずさわり、豊富な蒐集品の調査にあたってきた人々だけが、生物のあいだの種がおたがいにどれくらい融合しているかを知ることができる。ある部分に孤立した種が見られるのは、私たちの蒐集がいまだおよばないために、いっそう近い位置を占める他の種を欠いているから、そうなるにすぎないと確信することもできるだろう
……今日生存する動物が、きわめて単純な系列、いたるところで一様に微妙な差異の段階を示す系列を形成していると主張するつもりはない。そうではなく、それらは分岐し、不規則に段階づけられた系列をつくっていると言いたい。この系列は、その諸部分において非連続を示していない。あるいは、いくつか種が失われたために、どこかに非連続がおきるということがほんとうであるにしても、すくなくとも、つねに非連続を示すわけではない……
私は、この証明のために、いかなる仮説もいかなる仮定も必要としていない。観察を旨とするすべての博物学者がその証人である」
私たちが自然の中で見つけてきたものは、ごく一部にすぎないというような話は、それを化石証拠などの不足の言い訳と捉えるとするなら、後のダーウィンのそれとかなり似ている。
そして、適当なあちこちでは不規則な段階があって、しかし様々な部分だけならば連続的である種の系列。さらに、そういうことがあると確信しているわけではなさそうだが、(この時は、1つの仮説としてはあっても、誰もが同意するような歴史上の出来事では決してなかった。そもそもラマルク自身もその点には何度か触れているが、まだ地球には、未知の巨大生物すら普通に存在できるような、未開の地も結構あったから)絶滅という現象があるとするなら、それが種の非連続性の原因になるかもしれないという考え方など。ここにはすでに、現代でも結構普通であるような進化論的世界観が語られている。
ダーウィンの場合もそれは同じだが、現代的な考え方との相違点の原因の多くは、彼らの時代には、まだ誰も知らなかった、個体から個体への情報受け継ぎシステム、すなわち遺伝子のことを知らなかったことと思われる。
しかしながら、今から見ると、やはり本当に見事な考察と言えよう。
進化論と大絶滅説
絶滅現象に触れる時、ラマルクはかなり慎重に思えるが、最終的にはどう考えていたろうか。
 「絶滅」クレードはどのように進化し、そして消滅してきたのか
「絶滅」クレードはどのように進化し、そして消滅してきたのか
「……自然が種あるいは種族の保存を確実にするためにとった手段は、ある種族をそっくりほろぼし、消滅させてしまうほど、果たして不十分なものであったろうか……しかし、さまざまの場所で土地にうもれているところを発見された化石の破片……化石状態で見つかる種で、まったく類似した現存の個体がぜんぜん知られていないものはもはや自然界には存在していない、となんらかの根拠をもって結論できるかもしれない。
ただし、地表にはなお人の足をふみいれたことのない場所があまたあり……そこに棲む動物を知る手段がほとんどないようなところもあるから、私たちの知らない種がそこに隠されているかもしれない」
ところで、絶滅説を科学界において有名にしたのは、ラマルクの同僚であったキュヴィエとされている。ラマルクも当然、彼の提唱した説を持ち出してもいる。
「もし現実に消滅した種があるとすれば、それは疑いなく、地球の乾燥した部分に棲息する大型動物であろう。陸地では、人間が絶対的な支配力をふるって、保護することも家畜とすることも望まなかったいくつかの種の個体をすべて滅亡させることができたはず。そこでキュヴィエ氏が言うように、パレオテリウム、アノプロテリウム、メガロニクス、メガテリウム、マストドンのような属の動物とすでに知られている属の他のいくつかの種は、もう自然界には生存していないという可能性も生まれる」
それでも、それは単なる可能性でしかないともラマルクは言う。
キュヴィエが絶滅説を強く支持していて、ラマルクが懐疑的だというのは奇妙な話だろうか。少なくとも進化論に関しては完全に立場が逆であるはずだが。
ただ、そもそも進化システムが有効な世界における絶滅と、不変な各種の生物の型が存在する世界での絶滅とは、同じものではないと考えることもできるだろう。キュヴィエは確かに、生物の不変の型を信じていたとされる。もちろんラマルクの世界観はもっと自由に変化するもの。
そもそも変化の自由な世界観において、完全な意味での絶滅を想定するのは難しい。そのような世界観での絶滅とは、ラマルクが言う、部分として連続性を示しているある種の系統の途切れと思われる。絶滅の規模によって、ある系統を完全に宇宙から抹殺することもあれば、その連続的な流れに空白をあける可能性もある。ラマルクがそんな「可能性も」としているのは(あるいは確認が可能かもしれないと考えているのは)そのような空白と思われる。
生物の型があるとして、もしそれが創造によるものなら、ある種の方の生物が絶滅した場合に、再びそれと同じ生物がこの宇宙に出現するには、おそらく創造者がまた同じ生物を創造するしかない。この中にどれほどの時間があっても、システム的に内部の変化では不可能な再誕生ということになる。
一方で、生物の誕生と変化が、進化のような内部システムに関連しているなら、一度絶滅した生物も再び現れる可能性が、長い目で見れば、なくはないはず。ラマルクがその変化する世界をどれほど変幻自在と考えていたのかわからないが、もし同じ環境が同じ生物を誕生させる確率が、今の我々よりもずっと高いと考えていて(おそらく現在の我々や、もしかしたらダーウィンも、ラマルクに比べると、進化現象のあちこちの構成要素のランダム性が高いと考えている)、それに加えて、例えば大規模な絶滅現象をあまり信じていなかったのだとしたららほとんどの生物系統の消滅に、懐疑的なのも、無理なかったかもしれない。
ただし、ラマルクが同じような環境で、同じような性質を獲得はしたが、あくまでも別種と考えられるような生物系統を想定しいてた節もかなりある。
大型の動物だけじゃなく、あらゆる生物に対し、その絶滅させるような行いとして、人間の行動を考えているのはちょっと興味深い。自然の大災害はあまり考えず、生物の絶滅の多くは、人間の誕生以降に起こったものと考えていたのかもしれない。あるいは、大規模な絶滅があるとしたら、自然でなく人為的と考えていたのだろうか。
「……水中、とくに海水のなかで生活する動物、さらに地表に棲み、空気を呼吸するものでも、体軀が小さい種族はすべて、人間による種の滅亡をまぬがれている。これらの動物の繁殖力は大きく、また人間の追跡と罠を逃れる手段は大変なものだから、種をすっかり滅亡させることができるとは思えない」
変化したことで今の時代にはなくなってしまった生物種もあるだろうか?
ラマルクは「人が滅亡をもたらしえなかったのに、どういう理由で消滅したのであろうか」と疑問を持った、例えば現代に生きたサンプルが確認できない大量の化石貝類などは、変化することで消えたのでないかと推測した。
そして続いて、様々な環境の変化について語っているから、(言うなれば)変化パターンの型の存在を信じていなかったかはわからない。やはり同じ環境では、同じ生物が生まれると考えていたろうか。ただし現代でも、そう考えてあまり問題ないかもしれない。実際同じ環境というものがこの地球上の歴史の中のどこかであったかどうか、誰も確定できるなんて思えない。同じような環境であってもたいていどこかが違う。生物構造がそれほど複雑で、さらに変化可能性がほとんど無限の方向性を持っているとするなら、わずかな環境の違いでも重要になってくるだろう。
ラマルクが絶滅現象はともかく、大激変による大絶滅現象に懐疑的だったのはかなり明らかである。
「ほとんどの動物が時の推移とともに変化をこうむる立場にあることに気づかなかった博物学者たちは、観察された化石ならびに地表のさまざまの地点に認められる大変動に関する事実を説明しようとして、かつて地球に世界的規模の災害が発生して、すべてを変転させ、当時生存していた種の大部分をほろぼしたのだと仮定した。
遺憾ながら、この考えかたは、原因が把握できない自然の働きをなんとか説明しようとするとき、やっかいな問題をきりぬける便利な手段ではあるが、たんに人の想像が生んだもので、根拠をもたない……局地的な災害、たとえば地震、火山、その他特殊な原因がひきおこす災害については十分知られている。これをこうむった場所におきる混乱についても、観察がなされてきた。しかし自然の歩みがよりよく知られて、私たちがそのあらゆる部分に観察するあらゆる事実の理由を十分にときあかすことができるいま、なぜ、世界的規模の災害などというものを、証拠もないまま仮定しなければならないのか」
ようするに、大災害にはあまり根拠がなくて、それは「逃げ」のような認識だったのでなかろうか。説明できないことを説明するために持ち出した説と。実はラマルクもあちこちで似たような感じではある。しかし彼は進化システムが考えられる、生物が長い時間の中では変化する世界観を信じたわけだから、今は存在しない生物がかつて存在していたという事実は、それほど謎なことと思わなかったのだろう。だから、あまり強い根拠のない大災害を想定する必要などないと考えたのだろう。
ラマルクは1つの現象、1つの世界領域が、従来考えられていたよりもずっと複雑かもしれないと考えたのだろうが、実際には世界全体が、おそらく彼が考えていたよりもずっと複雑だったわけだと思う。
生物と無生物のそれぞれの定義
「私たちの観察できるすべての自然の産物は古くから博物学者によって三つの界、すなわち動物界、植物界、鉱物界に分けられている……私は以前から、もう一つ別の第一次区分をもちいるほうがよいと思っている。こちらのほうが、対象となるすべてのものを概してよりよく理解させるからである。そこで私は、いま述べた三つの界に含まれるすべての自然の産物を二つの主要部門に区別する。
一、生きている有機体。
二、生命のない無機体」
ラマルクは、生物の始まりも含めて、その全てのシステムをどうにか説明しようとした。だから彼は、決して変化による誕生では説明できない、彼の言う最も不完全な単純な生物の誕生の原因を、「自然発生」という現象に求めるしかなかった。それ以外を知らなかった(今でも、ほとんど誰もがそうだろう)
そうなると様々な生物の系統に関する彼の見解、実際には全て連続的な各系統(最終的には、枝分かれするかなり複雑な系統樹)と合わせて考えると、つまり実質全ての自然は連続的なものなのかもしれない。自然発生する寸前ではあるが生命のない無機物と、生命体として生じたばかりだが確かに生命を有する有機物の違いをどう考えるか。それは、ある種の生物種とすぐ隣の系統の生物種の違いと、どんな違いがあるのか。あるいは生物と非生物の間にだけは、何か重要なギャップがあると想定してたろうか。
想定していたかもしれない。
「動物と植物、すなわち生物は自然の産物の二つの部門のうちの第一……栄養摂取、発達、生殖の能力をそなえており、そして必然的に死をまぬがれない……ただし、人のそれほど知らないことは、生物が、器官の活動と能力との成果、ならびに有機的運動が体内にもたらす変化の成果として、みずから固有の物質と分泌物質を形成するということ。さらに知られていないのが、生物の遺骸が、自然界に観察される様々な無機的複合物質を生みだすこと。この物質のさまざまな種類は時の経過とともに、また場所の環境に応じて、いつのまにか変化をこうむるため、数を増し、物質はますます単純化され、ながい歳月ののちに、かつてみずからを構成していた諸原素の完全な分解を見るにいたる……
自然の産物の第二の部門を構成しているのは、あの生命をもない無機物、固体か液体かであり、大部分は鉱物という名で知られている。無機物と生物のあいだには、果てしない間隙があると言うことができる……」
まず、生物の遺骨は長い時間かけて周囲の物質とも徐々に同化して、構成的には単純化し、やがてすっかり消えてしまう(自然に還る)というような話。生物系の変化と合わせて、様々な構成要素があちこち循環するような世界観を考えやすいだろう。
そして「無機物と生物の間に、果てしない隙間」とある。
しかしラマルクは、全世界としての宇宙の(そうでないとしても、少なくても地球の)真の起源を除けば、創造主の手を想定する必要はないと考えていることがかなり明らかである。ようするに生物の世界も、完全に唯物論的に説明(解釈)しようとしている。だがそうなると「果てしない隙間」というのを、どういうふうに考えればいいのか。
無生物から生物が発生し、そして生物の変化が生物の様々な種を生み出す。生物が死んだ後は無生物物質に戻る。そのようなサイクルの中で実際に起こっているのは、物質の構成要素のあちこちへの移動や集合だろう。だが結局それは、無生物だろうが生物だろうが、その物質要素の組み合わせの違いにすぎない。その(要素群の)動きが時空間の中で連続的であるならば、やはり全てのものは連続的ということになろう。
だが、もしかすると、例えば非生物の要素として機能している時、生物の要素として機能している時とで、その要素自体に何か変化があるのだろうか。
ラマルクが言うように、まだ彼の時代に、三界という古い基本分類がまだまだ強い影響力を持っていたというのなら、どちらかというと興味深いのは、彼自身もよく別々に名称を出している、植物と動物との違いかもしれない。
「知られている一切の生物は、動物と植物とを区分する本質的相違に根拠をおいた、二つの特殊な界にはっきりわかれる。しかしこれまでの主張にも反し、私は、二つの界のあいだのいかなる点にもほんとうの移行は存在せず、したがって、植物的動物、つまり植虫類という語があらわすものも、動物的植物も存在しないと確信している。すべての部位あるいはいくつかの部位における被刺激性が動物のもっとも一般的な形質である。これは、意志的な運動の能力と感覚能力よりも、さらに消化能力よりも一般的である。ところで、植物はすべて被刺激性をまったくそなえていない。感覚のあると呼ばれている植物も例外ではない……」
ラマルクは植物の感覚能力に関して、その証拠とされるものもいくつか否定し、一方で動物についても、その全てに感覚能力がある可能性を拒否した。
「のちに述べる観察と、そこからとりだした帰結からすれば、動物が感覚能力のある生物であって、すべて例外なく、意志の行為を生みだす力をそなえ、したがって、意志的に運動する能力をもつとするのは、一般的には真実でないということになる。そのような、これまで、植物と区別するために、動物にあたえられてきた定義(感覚能力の有無?)はまったく不適切である」
さらに新たな、動物と植物それぞれの定義も提案する。
「動物の定義。動物は生命をもつ有機体であり、いつでも刺激を感受する部位をそなえており、ほとんど全部が、摂取する食物を消化し、あるものは、自由意志または従属的な意志の結果、またあるものは被刺激性の刺激の結果として、運動する。
植物の定義。植物は生命をもつ有機体であり、その諸部位において刺激を感受することは決してなく、消化をおこなわず、意志によっても、真の被刺激性によっても、運動しない」
アリストテレスの分類法
ラマルクの進化論は、どんどん複雑になって、最終的には枝分かれする系統樹になったとされている。
「動物哲学」は、まさに彼の生物研究の集大成である。その変化する世界が描く、種(系統)の地図自体の変化も結構読み取れる。
偏見があったことはほとんど確実だ。ある生物系統の並びは、一方の端が最も単純な生物で、一方の橋が最も複雑(構成的)な生物だとラマルクが考えたことに対した根拠はなかった。
そして植物と動物は分けた。
「自然的方法にのっとった、すなわち、類縁の考察にもとづいた既知の植物の全般的分類において、いま確実に知られているのは、秩序の一端だけであり、周知のとおり、隠花植物がこの端に位置するだろう。もう一方の端が同じ確実さをもって決定されていないのは、植物の体制についての私たちの知識が、知られている多数の動物の体制の知識にくらべてはるかに劣っていることによる……
動物については、そのような困難はない。全般的系列の両端はかなり決定的に定まっている。というのは、自然的方法、したがって類縁の考察になにほどかの注意をはらうかぎり、哺乳類は必ず秩序の一端を占めるであろうし、滴虫類がもう一方の端に置かれるであろう。
それゆえ、動物についても植物についても、一つの秩序が存在するこれは自然に所属するものであり、この秩序が存在させる対象と同じく、自然が万物の「至高の創造者」の手からうけとった手段に由来している。
自然それ自体は、崇高なる「創造者」が万物のうちに創造した一般的にして不動の秩序にすぎず、また、この秩序が服する一般ならびに特殊にわたる法則の総体にすぎない。これらの手段を変質させずにもちい続けることによって、自然はその産物を生みだしてきたし、いまもたえず生みだしている。自然はみずからの産物を変化させ、つねに更新し、いたるところで、実はこうした活動の結果である全秩序を維持している」
単純なものから構成的なものへというのが、必然的であるということを進化システムが考えられるような変化が多ような世界観で考えるならばおそらく環境の方もやや特殊なものにしなければならないつまり単純な構造の方が有利な環境というものが存在しないとするか、そのような環境自体が、生物の存在そのものに変えられてしまったりするとか。
古代の偉大な生物学者といえば、有名なのはアリストテレス。ラマルクの時代においても、多くの生物学者たちが彼を尊敬した。ラマルク自身も、彼に大きな影響を受けていると言われる。その見事な観察と集中したデータをまとめて考えて、アリストテレスは、おそらくは現代的な進化論にもある程度近づいていたと製作されることもある。
だが、アリストテレスの分類に関して、ラマルクが間違いを指摘する時、我々は別のことにも注目すべきだろう。
「……アリストテレスは、動物をはじめに二つの主要な区切り、彼によれば、二つの綱に区分した。すなわち、
一、血液をもつ動物(胎生四足類、卵生四足類、魚類、鳥類)
二、血液を欠く動物(軟体類、甲殼類、介殼類、昆虫類)
動物を二つの大きい区切りにわかつ、この第一区分は大変すぐれたものであるが、これを形成するのにアリストテレスがもちいた形質はよくなかった。彼は、血液という名を、動物の主要な流動体で色の赤いものにあたえた。そして第二の綱に配した動物はすべて、白あるいは白味がかった流動体しかもっていないと考え、それらを血液を欠くものとみなしたのだ。
これがおそらく動物の綱区分の最初の粗描であり、すくなくとも、私たちの知るもっとも古いものである。しかしこの綱区分は自然の秩序とは反対方向にある分類の最初の例をも提供した。ここには、非常に不完全とはいえ、もっとも構成的なものからもっとも単純なものへの進行が見られるからである。
このとき以来、動物の分類に関して、この誤った方向が一般に採用されてきた。これは明らかに自然の歩みについての私たちの知識をおくらせた。
……この形質はいかにも不備である。無脊椎動物のうちにも、赤い血液をもつものがある(例えば多くの環虫類)……
私の考えでは、動物に欠くことのできない流動体は、動脈と静脈の血管をもはや循環しないとき、血液という名に値しなくなる。このとき、これらの流動体は非常に汚損されていて、原素の結合がほとんど複合的でなく、つまり不完全なので、この原素の性質を、ほんとうの循環をおこなう流動体の性質と同一視するのは誤りであろう」
アリストテレスの分類を非常に古いものというより、ほとんど分類学の始まりのように語っているのも(実際そうかもしれないし)また興味深いが、「複雑なものから単純なものへの進行」はおかしいというような意見も。
ただし、このわりとすぐ後に、ラマルクは一応、生物構造の部分的な漸退もありうるとしている。単純にそれは、多様な環境によって、例えば水中から陸上への生息域の拡大時などに、水中では有利だが陸上では不利になるように要素に関して起こるだろうと。もちろん環境への適応のための変化というのは、どういうふうに考えるにせよ、たいていそのような世界観において、ある環境における機関や能力を失ってしまうような変化(つまりラマルクが考えたような後退)を認める必要があるだろう。実際にそうだったと思われるが、それこそまさに系統樹という概念の重要なヒントになりうる。
原理的に生命に必要な流動体に関しても、血液だけではないが、血液もその状態の1つというような理解だったようだ。
 「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの
「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの
リンネの分類の失敗
アリストテレスの分類に続いては、リンネの分類の話に移っている。
「1794年(共和暦2年)の春、博物館で最初の講義をおこなったとき、私は、知られている動物の全体を完全に区別された二つの区切りに区分した。すなわち、「脊椎をもつ動物」と、「脊椎のない動物」である。
……脊柱の存在は、これをそなえた動物が大なり小なり完成に達した骨格と、それにみあった計画の体制とを所有することを示している。これに対して、脊柱を欠く動物は前者とはっきり区別されるばかりでなく、みずからそれにもとづいて形成される体制計画すべて、脊椎動物の計画とはきわめて異なっている。
……前世紀に、もっとも才能ある博物学者たちが動物について、主として多数の無脊椎動物について、非常な数にのぼる特殊な観察をおこなった。
ある者は、解剖の知見を明らかにし、またある者は、変態や習性の正確かつ詳細な記述をものした。こうして、彼らの貴重な観察の結果、もっとも重要な多くの事実が私たちに知られるにいたった。
衆にすぐれた天分の人、これまで知られているもっとも偉大な博物学者のひとりと言えるリンネが、事実を蒐集し、また、あらゆる種類の形質の決定に正確さを要することを私たちに教えたうえで、動物のつぎのような分類を提示した。
彼は、既知の動物を六つの綱に分類。綱は三つの段階、すなわち体制の三つの形質に従属させられているとした。
第一段階=一、哺乳類。二、鳥類。「心臟二心室。赤くあたたかい血液」
第二段階=三、両生類類(爬虫類)。四、魚類「心臟一心室。赤くつめたい血液」
第三段階=五、昆虫類。六、蠕虫類。「つめたい血様液(血液にかわる液)」
この分類は、他のすべての分類と同じく、順序が逆であることを除けば、提示されたはじめの四つの区切りは、いまや決定的に定まっており、全般的系列における位置について、今後いつまでも動物学者の同意を得るであろう。
……残りの二つの分類が厄介だ。これらはかなり出来が悪いと言える。非常にまずい配置だ。知られている動物のもっとも多数を含み、またそれらの形質はもっとも多様なのだから、区切りの数をもっと多くするべきなのだ。
私はそれをつくりなおす必要があった……
……無脊椎動物に対して次のような分類を提示し、これを二つの綱ではなく、次の順序で五つに区分した。
一、軟体類。二、昆虫類。三、蠕虫類。四、棘皮類。五、水螅類。
これらの綱は、ブリュギュールがその蠕虫類の分類で提示した目のいくつかと、リンネが限界を定めたとおりの昆虫類の綱とで構成された。しかし、ブリュギエールの目の配置は採用していない。
そのうち、共和暦三年(一七九五年)のなかごろ、キュヴィエ氏がパリに到着し、動物の体制について動物学者の注意を喚起しつつ、軟体類が全般的系列に占めるべき順位に関して、この動物を昆虫類よりも優位に置かればならないという決定的証拠を提出したのを、私は非常な満足でもってながめた……」
ラマルクの無脊椎動物の研究とその報告は、進化論研究に関する評価と違って、一般的にほとんど不動な、彼の重要な功績である。
リンネはすでに膨大な数の(おそらく間違った認識ではない。地球上で最も数の多い多細胞生物)昆虫類はほぼ特別枠として残りの無脊椎動物は全長類という、よくわからない分類に放り込んだ。これは現在においては、ようするによくわからない生物種を詰め込む、分類のゴミ箱のようなものだったとも考えられている。だが、何がなんだかよくわからない生物はみんなそこに入れられていたために、当然中はむちゃくちゃになっていた。それを、かなり整理してくれたのがラマルクというわけだ。
不規則な複雑化の理由としての進化論
リンネの分類の上位種的な4種。つまり哺乳類、鳥類、(爬虫類を含む)両生類、魚類。ようするに脊椎動物と彼自身が定義した、特別な(と認識していたようである)動物種。
それらは、完全か、完全に近い体制を持っている動物群ということだったのだろう。
 「爬虫類」両生類からの進化、鳥類への進化。真ん中の大生物
「爬虫類」両生類からの進化、鳥類への進化。真ん中の大生物  「鳥類」絶滅しなかった恐竜の進化、大空への適応
「鳥類」絶滅しなかった恐竜の進化、大空への適応
ラマルクにとって、生物は基本的には複雑化(漸進性)の傾向があるが、環境による影響による変化のための部分的な単純化(漸退性)の傾向もあることは重要だった。それをしっかり区別して認識するべきと。
例えばヘビに足がないのは、そのような環境のための単純化の結果。だからそれを見て、それよりも下位種とされながら、足のある生物との関係を考え、それが自然の基本原理が、生物を劣化させることもあると考えてはならないと彼は指摘している。
もうこうなってくると、本当に、ただ生物はひたすら進歩するもの、複雑化するものとどうしても信じたいから、話を強引に解釈しているというな印象すら、今となっては受ける(実際そうかもしれないが)。
だが、ラマルクが進化論を考えたきっかけは、ある意味でその偏見のおかげであったと思われる。
「動物の階梯(段階)を、自然のそれとは反対の方向に考察するとき……生物の体制はしだいに単純化の度合を増し、これに比例して、能力の数の減少が見られることは、いまや争うことのできない事実である。この事実は十分に認められたものであり、自然が、みずから存在させたすべての動物を生みだすにあたって従った秩序そのものについて、もっとも大きい光を私たちにあたえてくれる。しかし動物の体制が、もっとも不完全なものからもっとも完全なものまで、構成が増大するにつれて、不規則な漸進しか示さず、その全域にわたって多くの異常、あるいは偏差が姿を現わし、その多様性にはなんの秩序もあるように思えないのはなぜであるか、この事実は明らかでなかった……構成の増大におけるこの奇妙な不規則性の理由。地球のあらゆる部分の多様な環境が、動物の一般的形態、諸部位、そして体制そのものにおよぼす影響の所産を考慮しさえすれば、すべては明瞭に説明できるのでなかろうか」
人間の進化。人間とサルの違い
「動物哲学」には、(理由はともかく)注目すべき推測や主張はいくつもあると思う。おそらく中でも、特に現代の人たちが強い興味を抱く1つが、まさに「人間の進化(というより他の種から人間への進化)」についての部分であろう。
ダーウィンは、人間の進化をテーマの1つとした本を1冊書いたことで知られているが、彼が自身の進化理論を初めてはっきりと語った『種の起源』においては、人間の進化については全然語っていない。
だが、生命そのものの起源の問題と同じく、ラマルクは、(特に当時は大きな問題を起こしたかもしれない)その点の考察も、避けなかった(ただ、実際それにどれほどの問題があったのだろうか? 例えばリンネはすでに、人間を動物分類の中で扱う時、最も近い生物としてサルを考えていた)。
ラマルクもたいていの場合、人間を特別な生物(彼の言い方で言うなら、最も完全と思われる生物)としていた。だがそれは、おそらくすごく優れた生物という以上の意味ではなかった。ラマルクは明らかに、生物世界の背景にあるシステムに神秘的な要素を考えていない。システムを作った何か自体は、確かに万能の力を持つ創造主とかかもしれないが、実際にこの世界に存在している生物自体は、あくまでも唯物論的なものだという信念を持っていた印象がかなり強い。そして、複雑な生物がいきなり現れることはない。彼が考えた自然の系列において、複雑な生物はもっと単純な生物からの段階的な変化の最終変化系である。つまり人間が、何か他の生物種から変化することで誕生した、とするのは当然の想定。
そしてもちろん彼は、単純に人間に似ていると考えられる、サル(ラマルクは当時一般的だったらしい「四手類」という分類名を使っている)に注目した。
後の時代に、人間に最も近い種どれなのかで論争があった、ゴリラ、チンパンジー、オランウータンの内、ゴリラに関しては、まだ未開の地で語られる噂程度の存在だったとされる。そこで当然、人間に最も近いサルはオランウータンかチンパンジーであると推測したようである。
「四手類(Quadrumanes)=ガラゴ(Galago)。メガネザル(Tarsier)。ノロマザル(Lori)。キツネザル(Maki)。アギトザル(Indri)。オナガザル(Guenon)。マンドリル(Babouin)。オマキザル(Sapajou)。ホエザル(Alouate)。ヒヒ(Magot)。テナガザル(Pongo)。ショウジョウ(Orang。オランウータン)。
……四手類の科は既知の動物のうちでもっとも完全なものを含むことになり、とりわけ、この科の最後の諸属がそうである。実際、類人猿(Pithecus)は、モナス属がこの秩序をはじめるように、秩序の全体をおえる。体制と諸能力とに関して、これら二属の動物のあいだに、なんという相違のあることであろう」
当時まだ発見されて間もなかったらしいチンパンジーについては、「アンゴラのショウジョウ(Simiatroglodytes,Lin。チンパンジー)は動物のうちでもっとも完成されたものであり、インド諸島のショウジョウ(SimiaSatyrus,Lin.)で、オランウータンと呼ばれているものよりもずっと完成されている」と書いている。
人間は、手と足をほとんど別のもののように扱うが、サルは全てを手のように扱う。その違いから、四手類のサルに対し、人間は二手類と呼ばれていた。
さらに人間の中の個別の種。これは後にダーウィンが指摘した問題だが、その人間の変種分類にさ、ものすごく幅広いパターンがあった。しかしラマルクは、あたかもそれが常識かのように6つの変種に触れる。
「博物学者たちは、ただ体制の面からのみ人間を考察する。そのため人間について、1つの特別な属を既知の6つの変種とともに形成し、この属だけで一科を構成した。その形質はつぎのように示される。
二手類(BIMANES)=四肢がわかれ、爪をそなえる哺乳類。歯が3種。親指は他にむきあうことができるが、手のみ=ヒト(Homme)。変種=コーカサス人。北方人。モンゴル人。アメリカ人。マレー人。エチオピア人または黒人。
……実際、人間では手のみが、他の指と分離して向きあえる親指を示し、四手類では、親指に関して手も足もこの形質を示す。
もし人間が他の動物と区別されるのはただ体制に関してのみであるとするなら、人間について特別の一科を、その変種とともに、形成するために使用される体制の形質は、ことごとく人間の活動の旧来の変化と、人間が身につけ、その種の個体に特有のものとなった習性との所産であることを論証するのは容易だ。実際、もし四手類のなにかの種族、とくにもっとも完成されたものが、環境のための必要により、木によじのぼって枝を手でつかむように足でつかんで懸垂するという習性を失うなら、そしてもしこの種族の個体が、何世代かひき続いて、足を歩行のためにだけもちいることを強いられ、手を足のように使用したくなるなら、まさに疑いなく、これらの四手類は、ついには二手類に変化するはず……」
人間が支配種族になれたのはなぜか
しかし最も重要なことは、人間があまりに特別である(つまり、最も近いはずの最も完全なサルに比べても、まるで別次元の存在。自分たちは、偉大なる神に選ばれた支配種族などと自惚れてしまっても仕方がないほどの特別性の)理由の推測であろう。
もっと普通に考えるなら、その特別性とは知的能力のことだろう。実際それは、今でも謎といえば謎の1つかもしれない。
「仮に四手類の1種族が、もっとも完成されたものとして、上述の構造と、直立姿勢をとり、直立して歩行するという能力とを、すべての個体にわたる不断の習性によって獲得し、ついで動物の他の種族を支配するようになったと想像していただきたい。そうすれば、つぎのことが理解されよう。
一、この種族は能力においてより完成されており、そのため他を圧倒するにいたり、この地上で、みずからに適した土地はすべてわがものとしたであろう。
二、この種族は、他のすぐれた種族と地上の富を争う場合には、これらを駆逐し、まだ占拠されていない土地に逃げこまざるをえなくさせたであろう。
三、この種族は、類緑上隣接する諸種族の盛んな繁殖を妨げ、これらを森林その他の荒地に放逐しつつ、これらの種族の能力の完成の進歩を停止させる一方、自身は自由にどこにでもひろがって、他の妨害なしに繁殖し、多数の群で生活することができるから、つぎつぎに新しい欲求を創造し、これがまた技能を刺激して、手段と能力を次第に完成させたであろう。
四、最後に、この卓越した種族は他のすべてに対して絶対の覇権を獲得したので、みずからと、もっとも完成された動物たちとのあいだに、一つの相違、いわば莫大な距離と言うべきものを置くにいたったであろう。
こうして、もっとも完成された四手類の種族は支配者となり……他の種族でもっとも完成されたものまで、すでに到達していた様態のまま押しとどめ、自分たちとの間にはっきりした区別を導入することもできたであろう」
ただし、この辺りですでに、「しかし直立姿勢が人間にはいっそう容易となったからといって、これは人間にまったく本来的なものと言えるであろうか」と、それが実際的には人間にとっても楽でなく、実際、歩くためにそうするしかないというような状態とも考えられると、疑問も発している。
では、人間は本当に完全であるのかどうか。
生物はなぜ個体なのか。なぜ死ぬのか
ラマルクが考察により導出した、生物と物質との違いには、現代人からすると確かに奇妙な部分もある。今でも謎の部分もある。
例えば「単なる物体は、要素分子の集合の総体としてしか、個体性をそなえていない。固体であれ、流動体であれ、気体であれ……物質の本性は、全体として、この物体の要素分子の本性のうちに存するからである。
逆に生物は、その総体、総量において個体性をそなえる。個体性はあるものでは単一で、またあるものでは複合的で、生物の複合分子の個体性に限定されることは決してない」
まず、個体性というものがよくわからないのでなかろうか。
また「物体は同質の総体を提供できる。異質である総体を構成することもできる……
だがすべての生物は、反対に、体制のもっとも単純なものさえ、必然的に全て異質……」
原子論的に全ての物質が構成されていると考えている印象がある。だがその構成分子(原子)のスケールをどのくらいと考えていたのだろう。異質性は、集合構造の多様なパターンでは、説明できない場合があるのか。
最後に挙げられるのが、死ぬことについての疑問。
「ただの物体が死ぬことはない。ただの物体は生命をそなえていないからであり、そして死は、必ず生命がある物体に存在することに結果する。有機的運動の完全な停止、その運動がなんらかの変調のために、以後不可能となってひきおこされるもの……生物は死を避けることができない。生命の特性、あるいは生命をある物体のうちに構成している運動の特性そのものが、一定の時間が経過すると、この物体の諸器官のうちに、器官が機能を果たすことをついには不可能とするような様態、したがって有機的運動を遂行する能力を消滅させるような様態をもたらす」
生物は生命を持っているから、それを失う。つまり死ぬことがあるというのは、その原理だけなら実に単純なものだ。だがそもそも、生命というのが何なのか? それが物質にないなら、なぜ(特に唯物論的世界観において)生物構造はそれを獲得できるのか。ラマルクにとってはなおさら不可解だったろう。最も単純な生物さえそれがあると思われることに。
「生命をある物体のうちに構成しているものは、みずからを、生命を欠いている一切のものから区別する本質的相違をつくりあげている。ある種の生物と無機物とのあいだに1つの関係、いわば微妙な差異の移行を見出そうとする人たちとしては、何とも不都合なことだ」
不可欠な起動者。最初のスイッチの謎
世界のどこが変化するにせよ、生物構造自体が相互作用しあって動作するというのは、その複雑な真の姿をとらえられなくとも、ある程度理解も納得もしやすい。
だが問題は、そのようなネットワーク的な総体運動の、最初のスイッチ、第一動作の原因。それは全くわからないが、非常に重要な問題だとラマルクも考えていた。
「……そのような不可欠の起動者は、今日まで、観察者たちの探究をまぬがれてきた」
興味深いことは、彼がそれを見つけたと、かなり自信を持って考えたらしいこと。
「……断言してさしつかえないが、動物の柔軟な含む部位に機能亢進と被刺激性をひきおこし、維持する特殊な原因がなければ、そしてこの原因は、植物にあっては、ただ漠然とした機能亢進を生むだけであり、含まれた流動体を直接に運動させるだけであるが、もしこの原因がなければ、循環系をもった動物の血液、および循環系をもっていない動物に見られる白みがかった透明な血液は休止の状態にとどまり、これらの流動体を含んでいる諸部位ともども、やがて分解してしまうだろう。
生命運動のこの刺激因がなければ、物体のうちに活動的生命を存在させるこの力、あるいは発条(バネ)がなければ、樹液と植物に固有の流動体は運動しないままとなり、変質し、消散して、ついにはこれらの生物の死と乾燥をもたらすであろう」
ラマルクは、まさにその原因を説明できることを喜ばしいと言う。それが自分の数々の発見の中でも特に重要なものと考えていた節がある。だからこそがかなり前置きも長い。そしてそこで、非唯物的な発想の否定も見られる。
「古代の哲学者たちも、ある特殊な刺激因が有機的運動に必要であることをさとっていた。だが自然をそれほど研究できてなかったから、刺激を自然の中に見つけられなかった。生命元質なるもの、死すべき動物の魂なるものを空想したのだ……
だが、有機的運動を刺激する原因を完璧に明らかにすることが、私たちの能力の限界を越えているとしても、その原因が存在すること、そして、これが物理的であることは確かに明白な事実のはずだ。私たちはこの原因の結果を現に観察しているのだから……自然の法則に服している対象は、どれ1つとして、絶対的な安定性など持っていない」
生物の世界のどこにでも広がっている流動体、媒質
それを知ることが人間の能力の限界を超えているかもしれないという考えを示してはいても、ラマルクは、そうではない希望を持った。
今の誰かが、同じことを言うよりも、それはずっと新しい学説であったのだろう。確かに、古代の哲学者たちにはよく理解できていなかったが、ラマルクの時代には、(少なくともそれまでの時代よりもずっと)かなり明らかにされつつあったものがあった。だからこそ彼は、現代の人が第一動作の原因として、例えば量子の動作を想像してみるように、「熱」や「電気」、「磁気」といった流動体を想定した。ただし、彼の語る電気と磁気はともかくとして、熱に関しては熱素(カロリック)またはフロギストンのことだったと思われる。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ  「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
実に拍子抜けの答かもしれない。
実際、ラマルクが説明している通りにそのような流動体が、この世界の中で絶えず運動し、そして生物の体内を含むあらゆる物質構造の中によく入り込み、特定の部位を膨張させたり、より深く浸透したりということがあるとして、それがなぜ生物の場合だけ、生物の動作を実現するための原理となりうるのか。まだ結構謎でなかろうか。
生命に固有の流動体が影響を受けて動作することになると考えるにしても(実際そういうふうな説明もある)、結局はその生命の流動体が構造であるのか、特殊な要素であるのかは謎。特殊な要素であるのはラマルクの考え方と反すると思う。だからそれも、何らかの構造か、あるいは構造の中で機能する性質の要素なのだろうが、結局、生物だけが特別であるような決定的な理由としては、それほど強い説得力を感じるのが難しい。
もちろん、生物がそもそもそれほど特別なものと考えないという考え方もあるだろうが、ラマルクは多分そうでなかった。
 「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち
「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち
だが、電気と熱が、生命システムの動作に重要というのは、現代的な観点から考えてもかなり正しい方向性に思われる。問題は根本的な物理世界観自体の捉え方がかなり大きく違ってしまっていることだろう。だから単純に現代的な考え方との考え方を比較するのは難しい。
ラマルクの説明からは、まるでそのような自然の流動体が、例えばエーテル的な全てと重なる媒質のような印象も受ける。興味深い世界観であるが、古い。実質的に全てが宇宙空間の中で、相互に作用しあうエネルギー体であるというような全体構造さえ、それほど奇妙と思われなくなっている現代的には(だからこそ多くの人は、SF小説の転送テクノロジーにさえ、それほどファンタジー性を感じない)。
 「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
単純な生物の自然発生
ラマルクの世界観の中で、用不用説を除けば、自然発生説の許容は有名な方と思う。実際、生物の世界を有限のものとして考える時、むしろ無限ではない創造者を想定する場合さえ、その問題を避けることなんて、おそらく不可能であろう。
「古来の哲学者たちも……生命が熱からみずからの支えと活動力をくみとること、そして熱の喪失はどこでも死を招くことには気づいていた。そして熱が単に生命の維持に不可欠であるのみならず、生命、ならびに体制の創造さえできることも正しく理解していた。だからこそ、彼らは、直接的生殖がおこなわれることを認めた。すなわち、自然が直接におこなう生殖(自然発生)……
古る人たちが自然に直接生殖能力を与えたことは正しい。しかし、この種の生殖に決してあずかりえない多数の生物にまで、この心証上の真理を適用したことこそ、彼らの明白な誤りだった」
ラマルクも指摘しているように、例えばアリストテレスのような高名な古代の生物学者でさえも、昆虫などの自然発生説をかなり真剣に考えていたことはよく知られている。
しかし彼が、自然に発生するものと考えたのは、とても単純な生物だけ。自然の系列の中で、最も単純な生物種のみだった。だが結局のところ、その過程は必ず必要だった。そうしなければ生物を生み出す自然システムだけでない。生物そのものも、何らかの創造の手によるものと考えるしかなかったろうから(今だってその状況は変わらないだろう)
「あらゆる自然物が実際に自然の産物であることを認めるなら、まったく明白なこととしなければならないことは、自然は、さまざまな生物を生みだすために、必ずすべての生物のうちでもっとも単純なものを形成することからはじめたこと。すなわち生命をそなえた有機体であることが、ぎりぎりやっと認められるような、単なる体制の粗描形でしかない生物を創造することからはじめたはずであること」
電気と生物電気。精神の物理的原理
ある意味、「動物哲学」は、生物現象の全てを唯物論的に説明しようとする試みとも言える。だがそうなると、起源問題の他、もう1つ重要と思われるのか、「精神とは何か」という問題。
「……精神と呼ばれている、あの特殊な存在は果たして何であるか……人の言うところによれば、脳の行為と関係し、そこでこの器官の機能は、個体の他の器官の機能とは別の秩序に属しているという……そんなの、私は、自然の法則を十分に研究しないために除きえなかった困難を解決するべく案出された一つの手段を見るだけである。つまり、あの世界的規模の災害(ノアの洪水?)とほぼ同じ類だ。こちらは、私たちを当感させるいくつかの地質学上の問題に答えを出すべくもちだされたものだ……
神経がどのように筋肉を活動させるかを、私たちはもっとよく知っているであろうか。けれども、神経の作用が筋肉運動の遂行に欠かせないものであることは疑えない」
実際に、ラマルクの時代に確認されてきた、脳の動作を考えると、ラマルクの推測はいくらかは当たっていると言える。
マクスウェルが、自身の方程式から電流と光の速度が同じであることを発見するのはまだ先の時代だが、ラマルクは、実際の知的生物の能力などを考慮し、神経機能のための流動体の速度は光と同じくらいは必要で、まさしくそのような高速の流動体として、電気を考えている。
ただし彼は、他の流動体との相互作用か、生命体のような特殊な構造における変化か、とにかく自然の電気と、生物の中で機能する電気を別ものみたいに考えていたようだ。明らかにガルヴァーニ(Luigi Galvani。1737~1798)の生物電気の理論に影響を受けていた。
「私は、神経系を所有するすべての動物体において、神経、および神経の達する髄質の中枢に……直接吟味する手段を欠くがゆえに、その本性がほとんど知られていない流動体が存在すること信じる。すなわち神経流動体である。
その流動体は驚くべき速度で、神経と脳との髄質のなかを動く……まさにこの微細な流動体を介し、神経は作動し、筋肉運動や感性が生みだされれ、さらには脳の両半球が発達に応じたレベルで生じさせるあらゆる知的行為をおこなう。
私たちは神経流動体を結果によってしか知りえない……しかしガルヴァーニ電気の発見以来、それが電気流動体にきわめてよく似ていることはますます確実である。
おそらく神経流動体は、動物組織のなかで変化をうけた電気流動体で、血液中に滞留することで、言ってしまえば動物質化されている……」
例えば想像力に関して、おそらくそれは人間しか持たず、人間しか持たないからこそ、様々な概念を新しく次々作ることができた。というような考察は興味深い。
だが最も重要なのは、ラマルクも言うように、おそらく記憶能力。現代の我々はコンピューターが身近にあるから、知的能力を機械的に考えることに慣れている。その点、想像力はシミュレーション能力と言っていいかもしれない。だが、原理を突き詰めた時、様々な要素が動作するためには、そもそも「どう動くか」や、または「今どんな状況か」、「これまでに何をしたか」などのパターンを保存するメモリーが絶対的に必要となろう。
「……記憶なしに、私たちは何をすることができようか。私たちの多様な欲求に、どう応じればよいでか……
記憶がなければ、あらゆる学問は人間にとってまったくの無であり、いかなる技芸も修得できず、観念を伝達するための言語、想像するための言語さえもつことができないであろう……」
記憶の重要性に関しては、おそらく哲学の世界では、十分語られ尽くしているようなものでなかろうか。だが、物理的原理として考える時、今でも我々は、情報という名称を与えた、世界というコンピューターのメモリーについて、多分あまり知らない。
これまでの多くのことでもそうだが、精神能力の、あるいはこの記憶能力の機構についての説明は、ラマルク自身は証明とさえ考えていた節もあるのだが、やはり空想的な印象がとても強い。
だが、これは結局のところ、今に至るまで、唯物論的に全てを考える場合の、ある種の限界を示しているように思える。少なくとも、人間がこれまで考えることができた限界。
「……いまとりあげている驚くべき能力の機構がどのようなものであるかを明らかにし、記憶の行為をひきおこす神経流動体の作用が、すでに獲得された、様々な観念の刻印された輪郭を通りながら、この観念にかかわる特殊な運動をひきうけ、その所産を個体の内的感性にもたらすことであることを証明したい。
……私たちが感覚を介して形成した観念、ついで思考行為によって獲得した観念は、私たちの知性の器官のなんらかの部位に彫りこまれた、すなわち刻印される。あるいは特徴的な輪郭を形成する。記憶は、私たちの神経流動体が内的感性によって興奮させられ、動揺しつつ、問題の像あるいは輪郭に出会うたびに、それらを喚起するのだろう。神経流動体がその成果を私たちの内的感性にもたらすと、ただちに、それらの観念はふたたび私たちに感覚できるものとなる。こうして、記憶の行為が遂行される」
そんなに複雑な原理じゃない。
ようするに、私たちの知的能力のための構造の中には、私たちが理解した様々な観念を何らかの形として用意できる領域がある。おそらく記憶領域は(その1つ1つの保存のための形に比べれば)かなり広い。我々が獲得できるあらゆる観念の量を考えると、結果的にそう考えるのが妥当だろう。
そして、神経流動体が記憶領域の特定の形に刺激を与えると、私たちの感覚的には、ある記憶が呼び覚まされるということになる。
ただ、神経流動体がどの形に触れるのかを決定づけているのが、私たちの内的感性とも語られるが、妙な話かもしれない。仮にラマルクの推測が正解なのだとして、では、そもそも内的感性は記憶を呼び覚ます前の段階で、どうやってどの記憶を呼び覚ますかを決定できるのか。私たちは必要な時に必要な記憶を思い出せないことがある。だがほとんどの場合、思い出したいものを思い出せる。だが内的感性は直接的に記憶をしないなら、いったいその時々で記憶の形の場にあるどの記憶を呼び覚ますかを、いったいどう判断するのか。
他にも、問題はいくつもあるだろう。
複雑な機械の場合の知性
しかし、単純な構造であるなら感覚能力は大したことなくていい。例えば機械的な反応だけするシステムだけあればいい。だが構造が複雑になるにつれて、そのコントロールには神経などが必要となってくる。複雑なコントロールの中でそれを操作できるのは精神のようなもののみのはず。
(おそらくラマルクの抱いていた)そのような考え方からして、もしも現在のAIの発展を、ラマルクが未来視で覗き見たり出来たならば、そしてそこに人間らしさでも見つけたなら、はっきり心が生じていると推測したかもしれない。つまり、複雑な機械が動作するためには神経系のようなものが必要。それほど複雑なものはつまり心の原因にもなるはずとか。
系統樹の発見。枝分かれしていく生物の世界
何度か、枝分かれする系統樹の話に触れたが、その点に関して重要な話は、「動物哲学」の本文より、追補での考察であろう。
ラマルクはまず、自身の最新の観察研究の成果から、収斂進化、すなわち、似たような環境で別種の生物がそれぞれ個別に進化したが、その環境が同じであったために、表面的な構造や能力が似たようなものになる、という現象などを提示する。
しかし、それはまた、同じ環境でも進化のたどり着く先が別種の生物になる可能性を明らかにしている。それは実際重要なヒントだったに違いない。
「……ここで、つぎのような省察、私がこれまでの研究において考察してきたすべての対象によって提起され、ますます確証されるように思われる省察を読者にお伝えしておきたい。
……私は、水が全動物界の真の揺籃であることをいささかも疑っていない。実際、もっとも完全でない動物は、これがいちばん数が多いけれども、水中でしか生活しない。体制のもっとも単純な極微動物の直接生殖、つまり自然が過去におこない、好適な環境であればいまもおこなっているかもしれない自然発生も、水中で起こるのだろう……
周知のように、滴虫類、水螅類、放射類は水のなかでしか生活せず、蠕虫類も、あるものは水中に、またあるものは湿潤な場所にのみ棲息する。
蠕虫類は動物の階梯の最初の分枝を形成するように思われ、それは滴虫類が、明らかに他の分枝を形成するのと同じであるが、蠕虫類のうちでまったく水棲であるもの、すなわち他の動物の体内に棲息しないもの、たとえばハリガネムシとその他、私たちにまだ知られていない多くのものはたしかに水中において多様化したと考えられる。そして、これらの水棲の蠕虫類のうちで、のちに大気にさらされることに慣れたものはたぶん、カ、カゲロウといった両棲の昆虫類を生みだし、これらがつぎつぎに、空気中に生活するすべての昆虫類を生みだしたと考えられる。さらに昆虫類のいくつかの種族は、そのうつされた環境によって習性を変化させ、孤立して隠れすむ習性を身につけて、蜘蛛類を生んだ。
そして蜘蛛類のうち、水に親しみ、しだいに水中生活に慣れ、とうとう空気に身をさらさなくなったものが、すべての甲殻類の存在をみちびいた。このことは、ムカデをヤスデに、ヤスデをワラジムシに、ワラジムシをミズムシ、トビムシ等につなぐ類緑が十分に示している。
また、空気に決して身をさらさなかった他の水の蠕虫類は、時とともに種族をふやし、多様化し、それに応じて体制の構成を進歩させ、環虫類、蔓脚類、軟体類の形成をもたらした。これらはともに動物階梯の一つの連続した部分を形づくる……
……軟体類が、まだ知られていない種類を仲介とし、魚類を生みだしたことは、魚類が爬虫類を生みだしたのと同じく明らかである。
さまざまな動物の確からしい起原をずっと調べていくと、爬虫類が、環境のもたらした2つの明瞭な分枝により、一方では鳥類を、他方では両棲哺乳類を形成し、後者が他のあらゆる哺乳類をつぎに形成したことも疑うことができない……」
進化論世界観としては、このような分岐分岐の流れは当たり前のもののように感じられるかもしれない。実際ここにたどり着くまでの道がどれくらい困難だったのかは、今となってはかなり想像も難しい。だがラマルクは到達していた。
「……私の考えでは、動物の階梯はすくなくとも2つの特殊な分枝からはじまり、そして、全体にひろがりながら、いくつかの個所では、さらに細かく枝分れをするように思われる。
この動物系列は、もっとも不完全な動物が見られる2つの分枝からはじまっているが、それぞれの分枝の最初の動物が生まれるのは、もっぱら直接生殖つまり自然発生によるのだろう。
1つの有力な理由のため、私たちは、既知の動物を多様化し、それらをいま私たちの観察する様態にまでみちびいてきた、順次おこなわれた変化を認識することができない。すなわち、私たちは決してこうした変化の証人たりえないからである。私たちは作用の結果を観察するが、作用が現におこなわれているところを眼にすることは決してないので、おのずから、事物はつねにいま見ているとおりであると信じるほうに傾き、それらがしだいに実現されてきたものであると信じようとはしない……
もしも人間の寿命が、1秒の長さしかないとし、ねじを巻かれ動くふつうの時計があるものとすれば、この時計の針を見つめる人は、だれにせよ、その一生のあいだに、針の位置が変化するのを見ることは決してないであろう。針は現実には停止してはいないけれども。30の世代を重ねた観察も、針の移動についてなんら明白なことを教えないはずである。その運動は30秒間になされるものにすぎず、はっきりと把握するには、あまりにわずかだからである。そしてもし、ずっと昔の観察が、針は実際に位置を変化させたことを教えたとしても、その記述に接した人たちは、各人がつねに文字盤の同一点に針を見ているので、それを信じないで、なにかの誤りとみなすに違いない」
どうして生物は未来を生きられないか
ラマルクは、記憶能力について考察する時に、結局全ての記憶はある時点での経験が保存されたものであるのだから、だからこそ未来の出来事は、直接的に知ることはできないのだろうとも語った。
未来のどこかで起こるだろう、ある出来事とかならわかる。例えば生物構造が死ぬことは、他の生物構造の変化の観察から予測できるから。
だが、まだ訪れていない未来を直に経験することはできないはずと。
そのようなところでも、一般的な偏見、今でさえ、そうでないかもしれないという可能性が(事実としたら)奇妙な世界観への偏見が見いだせよう。
つまり今の我々は、ラマルクよりもさらに後にウェルズが考えたタイムマシンの存在も、そこまでファンタジー的に考えてはいないはず。アインシュタインが時間の速度が一定とは限らないことを示して以来、時間というものがどれほどに自由に変化するかの議論がずっと続いている。どうにかすれば過去に進むことも可能であると真剣に考える者が、今はかなり普通にいるだろう。
 タイムマシン、宇宙戦争、透明人間、モロー博士の島「H・G・ウェルズ」
タイムマシン、宇宙戦争、透明人間、モロー博士の島「H・G・ウェルズ」  「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
そのような時空間の中で、生物の変化ネットワークはどのように動作するのか。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
例えば変化の速い生物を全て、記録することが永久にできないかもしれないという時、そこには、理解のための世界の容量、そういうシステムが利用できる範囲が常に変化しているから、しかもその変化が早すぎて、どうしても一瞬でも全て収めることができないというような、そういう世界観をイメージできるかもしれない。
しかし、例えばある瞬間を繰り返して、ある瞬間の保存容量をひたすらに増やすことが可能だったら……
我々が何かを学ぶたびに、どんどん世界は複雑になっているようにも思えるが。
複雑化の傾向は本当に幻想か
ラマルクは変化を促す自然の力として、2つを想定した。すなわち、生物構造が全く自然と単純なものから複雑になっていくというような段階的変化。そして環境による影響がもたらすほとんど無限の方向性があると思われる変化。
ラマルクの変化する生物世界において、まっすぐに近いか、かなり複雑に枝分かれしているのかという疑問は、実質的には2つの変化のどちらがより大きな影響力を持っているかということ。
明らかにラマルクは、自然が本来持っている複雑化傾向の方を最初は重要視していた。しかし観察データの増加のたびに疑問を抱き、最終的には、環境のための変化の方を重要視した。
「動物哲学」の追補で語られたもの。最後にたどり着いていた、2つの始まりの生物から始まる、分岐する生物の世界観。彼はさらに、その数年後に書いた心理学の本において、生物の分岐の話に1章を使い、ついにはたった1種類の生物から枝分かれしていった「地球生物の系統樹」という考え方もはっきり示していたとされる。
しかし結局、複雑化の傾向とは何だったのだろうか? 実際にはそれは、迷信とか幻想といった類のものだったのだろうか?
仮に生物が変化する連続体と考えられるなら、それが存在している様々な環境が連続しているこの世界をどう考えるべきか。環境に適応し、変化をひたすらに繰り返せるのなら、どこまでも生物は広がるのかもしれない。
実際には、環境のパターンはすごく小さくなってしまうこともありうるだろうし、あまり極端な変化に生物の変化は対応できないという見方も、別に奇妙な感じはない。
例えば今、いきなり魔法使いが、地球をすっかり原子スケールでバラバラにしたとする。それでも地球生物はバラバラ世界に適応して生き残るなんてことあるだろうか?
しかし、そのような極端な壊れ方はしない、という程度の安定した世界においては、確かに生物は、変化し、あちこち広がり、全体の生物系としては複雑化の傾向を見せるのでなかろうか。
あまりに複雑すぎる。
まだ誰も答を出せないだろうか?



