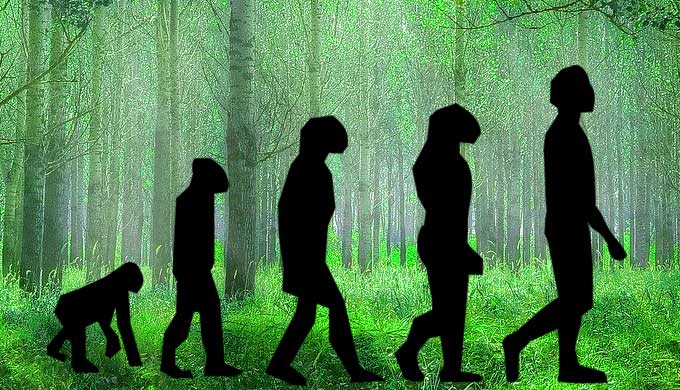ヒトはどれくらいに特別か
脊椎動物、無脊椎動物
地球の歴史の中で最初に誕生した『脊椎動物(vertebrate)』は魚だった。
 「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
脊椎動物とは、名前通りに「脊椎(Vertebrae)」を有する生物。脊椎とはつまり背骨のことだが、より正確には「頸椎(cervical spine。首の骨)」から、「尾椎(Coccyx。尻の辺りの骨)」までの連なっている構造のこと。また、脊椎動物でない生物は『無脊椎動物(Invertebrate)』と言うが、これはかなり広い範囲を含む分類である。
哺乳類は本当に高等な生物なのか
魚から、両生類が派生して、両生類から爬虫類と哺乳類、あるいは両生類から派生した爬虫類から、さらに哺乳類が生まれたと考えられている。
 「両生類」最初に陸上進出した脊椎動物。我らの祖先(?)
「両生類」最初に陸上進出した脊椎動物。我らの祖先(?)  「爬虫類」両生類からの進化、鳥類への進化。真ん中の大生物
「爬虫類」両生類からの進化、鳥類への進化。真ん中の大生物
たいていの人がこの流れを知っている。恐竜が好きな人などは特に、鳥類も爬虫類に実質的に含まれているということを知っているだろう。
 「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。  「鳥類」絶滅しなかった恐竜の進化、大空への適応
「鳥類」絶滅しなかった恐竜の進化、大空への適応
そして我々は哺乳類の人間である。
それは自惚れであるかもしれないが、確かに人間は他とは決定的に違う生物だろう。自分の意思で自然界からあえて外れようとする。そしてまるで、再びそちらに戻ることを拒否するかのように、自然を破壊しようとする。
時々は美しい木々に囲まれたりして、野性動物と触れ合ったりしようとするかもしれないが、それすらも、こちら側の気分次第のコントロールがある。安全を確保しようと、あらかじめ危険でない領域を見極める。危険に踏み込むのは、ただそのスリルを楽しむためにだ。我々は自然に帰ろうと考える時ですら、自然をコントロールしようとする傾向がある。少なくともそれが理想と思っている。
人の理想郷だ。
自然は好きな時にだけ好きなように現れる。人類の時代が長く続けば、おそらくそういう日は本当に来てしまうことだろう。
我々は哺乳類である。
 「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
人間はひとまず置いておくとしても、多くの生態系の頂点に哺乳類がいる。ネコ、イヌ、ゾウ、クジラ。まるで鳥が支配する空以外は全て哺乳類のものになってしまったかのようなイメージを持っている人すらいるのではなかろうか。
空ですら、鳥だけのものではない。夜はコウモリが飛ぶ。
 「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ
「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ
それで今は哺乳類の時代と呼ぶ場合がある。
同じように、ひとつ前は爬虫類の時代だったと言われる。6500万年前までの話だ。恐竜のほか、翼竜や首長竜などが繁栄していた時代。
 「翼竜」種類、飛行能力、進化史。恐竜との違いはどのくらいか
「翼竜」種類、飛行能力、進化史。恐竜との違いはどのくらいか  「首長竜」恐竜時代の海の覇者。種類、進化、化石の研究記録
「首長竜」恐竜時代の海の覇者。種類、進化、化石の研究記録
そして進化という言葉には、「低レベルから高レベルへの飛躍」というようなイメージが抱かれやすい。
というか実際、普通にそのようなニュアンスで、まったく問題なく使われる場合もある。例えば、宇宙の中でかなり孤立した系と言えるような恒星の始まりから、エネルギーの放出、そしてその終焉までの流れを「星の進化」と表現する時、そこにあるのは、確かに定まった方向性への流れという意味で、ある種(決まっている段階を進んでいくという意味で)進歩的と言えよう。
ただ、生物学の文脈で進化という言葉を使う場合は、そのような意味すっかりなくなるか、薄れるというわけだ。
ダーウィンは普通の理由を求めた
進化論によって我々がサルの仲間であることを示したダーウィンは、むしろ最初から「進化論が生物の進歩の理論である」と誤解されることを恐れていたような節もある。
ただしダーウィン自身も、ある生物が下等で、ある生物は高等というような認識は持っていた(例えば、あまり文明の中でテクノロジーを発達させていない田舎の島や大陸の住人(未開人)たちは、ヒトとしては下等だと表現していた)。しかしおそらく彼は、下等な存在から高等な存在への進化が起こる場合には、それが必然ではなく、自然淘汰がそういう方向に働いたから、つまり高等な生物の方が有利な環境がそこにあったから、というふうに理解しようとした。
 「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い
「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い  種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
恐竜人間という自惚れの象徴
進化というのは進歩であるということ。このイメージは非常に根深い。脊椎動物の中で、魚から両生類、両生類から爬虫類、爬虫類から哺乳類。まるで魚が一番下等で、哺乳類が一番優れた生物であるかのようなイメージは長く広く浸透してきた。
もっとひどいのは、無脊椎動物から脊椎動物が生まれたのだから、無脊椎動物はさらに古く、旧式的な、つまり劣った生物という認識。つまりあらゆる生物の(進化した)頂点に脊椎動物があり、その脊椎動物の頂点が哺乳類。さらに言うなら、哺乳類の頂点が素晴らしい人間という空想。
恐竜図鑑などには時々、「恐竜がもし絶滅していなかったら恐竜人間が生まれていたか?」というような話が載っている。まるで映画に出てくるエイリアンのような感じに描かれることが多い恐竜人間だが、あれこそまさに人間の自惚れの極みであろう。
つまり進化の先には人間のような形態があるという認識。直立二足歩行で、頭がよくて、言葉をしゃべる。
 「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か
「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か  「人間原理」宇宙論の人間中心主義。物理学的な神の謎と批判
「人間原理」宇宙論の人間中心主義。物理学的な神の謎と批判
ダーウィンは本当は何を言いたかったのか
進化(evolution)という言葉自体に、進歩と同じ意味があるのは、別に翻訳によるものではないという。この言葉を科学の世界に持ち込んだのは社会学者のハーバート・スペンサー(1820~1903)で、ダーウィンは彼に強い影響を受けていたようだ。
有名な『適者生存(survival of the fittest)』という言葉もスペンサーの開発とされる。
とにかくダーウィンは自分の生物学理論を説明するのに、幅広く浸透していた、スペンサーの進化という言葉を取り入れた(取り入れるしかなかったのかも)。しかしそうなるまでには葛藤もあったと言われる。なぜなら彼の進化論は、生物が変異していく中で、文字通りの進歩が必ず起こるという可能性など大して示唆していないから。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
しかしダーウィンはそれでも、人々の心の中に根付いた、人間の特別性、人間こそ最も高等な生物という自惚れを甘く考えていたのかもしれない。実際、彼の進化論を支持し、彼の擁護者になってくれた者たちすら、わりと進化論を進歩の理論と捉えてしまったらしいから。
自然淘汰とニッチの概念
進化論に反対する者たちは、素晴らしい生物である人間がサルから進化したなどということを認めたがらなかった。一方で、多くの進化論者たちは、生物は進化を重ね、優れた生物であるサルを生み、そしてそのサルからさらに優れた生物である人間を生んだと考えていたとされる。
ようするに生命体というものは、基本的には複雑化(進歩)する方向へと進化していくものという思想があった訳である。というか、あったというか、そのような進歩的発想の進化論は現在でもある。
ではそれとは違う、ダーウィンの進化論とはどのようなものであったのか
進化というのは、ダーウィンのそもそもの考えでは、ただの変異である。ただし彼はその変異のバリエーションの内、次世代に生き残る変異がどう選ばれるのか、その原因に関して『自然淘汰説(theory of natural selection)』というのを提唱した。それは、様々な生物が生まれる中で、その時々の環境に最も適応した生物の子孫が最も増えて、後の時代に繁栄するだろうというもの。
しかし自然環境の中では、個々の生物が存在できる環境ごとの(『ニッチ』と呼ばれる)容量は決まっていて、まるで椅子取りゲームのように、その容量が埋まってしまった場合、他の生物はそこで生きれない。そのため特に、大きな繁栄をした生物がいると、あまり環境に適応できなかった生物、変異体に関して『絶滅』という現象が起こる。
ただ、人間が複雑な生物であることは間違いない
現実問題。この地球の生命体の歴史において、生物は常に複雑化してきた傾向がかなり見れる。もし人間が、人間が考えているような生物だとするなら、今のところ知られているすべての生命体の中で、最も複雑な存在であることはほぼ間違いないだろう。
物理的な領域だけではない。例えば意識というものが神経系が作り出すまやかしにすぎないのだとしても、そのまやかしの制御が、独自の社会などの新たなシステムを構築していく。人間という存在がどこまで複雑な生物か、考えれば考えるほど、それだけでその(複雑性の)証明になろう。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で  「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
我々の力はどの程度なのか
ダーウィン的には、実際にこの地球で、常に複雑化が起こってきたのだとしても、それは地球上という環境が、複雑化した方が有利である環境だからにすぎない。だが生物が誕生する環境というのは、そもそもそういう環境なのではなかろうかという疑問はある。
だが環境は変わるものだ。地球と太陽が未来永劫に穏やかだったとしても、宇宙全体としてはそうではないだろう。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
実際に中生代の大量の生物がそれで絶滅したと考えられているように、巨大な隕石が地球に降ってくることはありうる。その衝突によって大異変が起きて、とても人間のような複雑な構造を持った生物では生きれないような環境になる可能性も常にある。単純な生物の明らかに重要な利点は、多くの環境に簡単に適用しやすいということだろうから。
 「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。
「恐竜絶滅の謎」隕石衝突説の根拠。火山説の理由。原因は場所か、生態系か。
そもそも今、人間はその気になればいつでも自分たちを滅ぼすことができると考えられている。世界中に存在する核兵器という核兵器をすべて起動させればいい。
実はもっと簡単な方法もある。単純に、誰も子供を産まないようにすればいい。そしたら、150年も経った頃には人類は絶滅しているだろう。それをしようと思ってもできないはずと考える人はあまりいないと思う。本当に、全人類が一致団結して、それをしようと思ったらできるはずだ。
なぜなら我々には意思というものがある。どういう機構でそれが生み出されたにせよ、我々は自分の意思で人類の時代を終わらせたいと考えたならば、終わらせることができるというわけだ。そうしたら、我々が最も複雑だと考えている生物がこの地球から消えることになる。
自己修復を伴う複雑なシステム
複雑なシステムは、それを構成する要素の少しが欠けただけでも、全体が修復困難なダメージを持ちやすい。このイメージは正しいだろうか。
これは正確には、失われた機能の再現が難しいというふうにも言えるかもしれない。またコピーも難しい(つまりバックアップが取りにくい)。
ただそのように機械的に考えることができるとするなら、あるコンピューターの中で別のコンピューターシステムを再現したりする技術(エミュレーター)のように、もっと複雑なシステムの中で、人間という生物を再現する、というようなことが可能だったりするだろうか。おそらく『宇宙プログラム説』のいくらかは、この観点に立っている。
もちろん、そもそも複雑な存在の維持について、普通に我々が使う複雑な機械のように、外部の手を使うメンテナンス(点検、整備、調整)やリペア(修理)をする誰かがいるのなら話は別かもしれないが。
人間はもしかしたら、人間自身の優れた修理屋にになろうとしているかもしれない。かなり「真の」と言えるような意味でそうなった場合、それこそ本当に人間の時代の始まりなのかもしれない。
意識というのは特別なのか
では、もし人類が消えたらどうなるか。生物全体としては頂点がやや下になってしまったということなのだろうか。
進化というのが常に進歩の方向に進むと考えている人でも、そういう事は起こりうると考えている人は多い。
だがそれは一時のことにすぎない。再び生命体は進歩の方向へと進むと考えられることもある。つまり次の時代の人間(でないとしても人間のような生物)が再び誕生することになりうると。
しかしそもそも、人間の工学技術や、意識による生物らしからぬ行動などは、本来自然に存在する流れへの抵抗であり、例えばそれによって進化が妨げられたりとかしても、自然法則の範疇に入らないのではないかという説もある。これも単に、意識というものを特別と考えるか、考えないかだけの話だろうか。
例えば意識というものが、人間と生物の機構の中にある、生きるための道具に過ぎないのだとしたら、我々が遺伝子操作したり、自ら絶滅を受け入れたりすることすらも、自然界の出来事の範囲から完全に脱却しているとは言えないだろう。
微生物。この世界で最も繁栄している者たち
もう1つ重要なことは、我々は目に見える生物しか長い間知らなかったということだ。だが今ではよく知られているように、この地球上において、繁栄度という基準で優劣を決めるなら、最も成功している生物は我々の目には見えないくらい小さな微生物たちである。
目に見える生物に限定したとしても、そもそも脊椎動物よりも(主に昆虫などの)節足動物(Arthropod)の方がはるかに数が多い。
 「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
節足動物ですら怪しいのだが、微生物となると、もう完全に、我々がその気になろうが滅ぼすことは不可能だろうとされている。
しかし我々が勝手に滅ぶことはできる
深く考えると、我々はごく一部の狭い世界の中の、さらに狭い世界の中しか知らなかった井の中の蛙だった。そしてようやく外の世界の存在を知れたにもかかわらず、それを認めたがっていない。という状況なのかもしれない。
人間とは結局どのような存在か
比率から考えるに、目に見える領域というのもそもそも1つのニッチとして考えることができる。そしてそのニッチの中で最も繁栄しているのは節足動物に思える。
目に見える領域内でも、様々なニッチを設定できる。それはいわばニッチの中のニッチ。
人間も何かのニッチを占めるなら、それはなんだろうか。多分、略奪者だろう。生態系の頂点の頂点とでも言おうか。
略奪という行為を行うために必要なのは力だけではない。
逃げる者や隠れている者を捕まえる知恵がいる。そもそも、「自分で何かを生産できないならば誰かから奪えばいい」という発想に至る知能がいる。家畜や養殖など、人間というのは搾取のスペシャリストと言えるだろう。
ただし、「計画的な略奪」というような表現を使ったりする場合ですら、知能を進化させるような構造とかけ離れている寄生虫などをどういうふうに説明すべきか、結構難しいかもしれない。しかしこう考えてはどうだろうか。効率的な略奪に関しては、自然淘汰でもそれを生み出すことがある。しかしそのために強大な力を蓄え、そしてその力を意図的に使うことで略奪を実行できるのは、知能がなければかなり厳しいだろうと。つまり複雑なシステムを保ったままで、効率よく略奪を行うには知能が必要だと。
とにかく我々は、目に見える生態系の頂点というニッチを占める存在と言える。そして実際には極一部でしかないそのニッチが、全ての生態系の中でも重要だという思想が、進化というものが進歩であるという決めつけに繋がったのだろう。生命は常に複雑化する道を辿ってきたということすら、我々の視野の狭さが引き起こした錯覚だったのかもしれない。
つまり我々が存在しているニッチが、複雑さが有利に働く領域だったというだけの話というわけだ。少なくともその可能性が多分にある。
ヒト型であることの意味
普通、今の我々が人間らしいとイメージするような人間に必要なのは(少なくとも今現在、人間が持っているとされてる要素の中で)大きな脳みそだけではないと思う。
今は電子コンピューターとか、飛行機や宇宙船、粒子加速機とかみたいなすごいものを開発してる人類であるが、今の我々、つまりホモ・サピエンスの歴史の時間のほとんどにおいて、それらは(おそらくは空想の世界にすら)なかった。我々は長い時間、せいぜい石造りの道具とかで満足していたと考えられている。
昔ながらの解剖学的な観点から見たとしても、現代的な遺伝学的の観点から見たとしても、進化の速度はヒトの時代の長さと比べた場合は非常に遅い。つまりは、ホモ・サピエンスは登場した時から今にいたるまで大して変わっていないと言える。だから例えば、原始時代の子供を現代に連れてきたとして、しっかり教育すれば今の子供と同じように育ってくれることだろうと普通は考えられている。
だがもしそうだとするなら、逆に我々は高度なテクノロジーを得る可能性を秘めた高度な知能を有しながらも、長い間そのような開発を行わなかったということになる。
何が必要だったのだろうか。
確実に必要だったのは、情報の世代ごとの上手い伝達であろう。世代ごとに学んだ知識を受け継いでいけるなら、たくさんの世代の賢い人たちが、テクノロジーを開発していくことも可能になる。
だが、そのような伝達システムには、言葉とか文字とかが欠けてはならない。まずは言葉をしゃべる機能が必要だろう。もっと極端に言えば、色々な感知能力が。どれほど高性能なコンピューターであったとしても、外部からの入力がなければ、メモリー内のデータ、パターンを増やすことはできないはず。
考えてみれば、知能を持ったと言えるだけでなく、知能を活用できる生物を想定するならば、その構造には少しばかりの制限がかかってくるであろう。突き詰めて考えてみたとき、それがまさしくヒトみたいな姿をした生物になるということも考えられないことではない。
しかし、仮にそういう推測が真実であるとしても、それはヒト型が、テクノロジーを発達させることが可能な生物であるということ以外には、神秘的な特別性もないように思われる。
コープの法則。大型化の傾向は本当にあるか
『真核生物(Eukaryota)』の中で、『菌界(Fungi)』、『植物界(Plantae)』、『動物界(Animalia)』のいずれにも属さない生物の総称として『原生生物(Protist)』というのがある。
単細胞の原生動物である有孔虫類(Foraminifera)は、自らの周囲に殻を形成するという性質のために、化石として残りやすい。
海生有孔虫類はほとんど、海底堆積物内に生息するベントス(Benthos。底生生物)である。
ベントスとは、底質(bottom material)、つまり水域の底を構成する表層に生息する生物のこと。
しかし少数ながら、浅いところで浮遊生活するプランクトンもいて、浮遊は移動にもなり、そういう種は分布も大きくなりやすく、過去の環境における水塊の動きの復元などや、異なった場所の堆積物の比較などにも使える。
そして、プランクトン性有孔虫の進化史もよく知られてる方で、絶滅と変化について考えやすい。まずそれらは白亜紀に生じ、ところが白亜期末、それに新生代に大量の種が絶滅してしまっている。しかし、数をを減らした後には、毎回進化劇があり、現在にいたっている。
白亜紀、新生代初期(古第三紀)、新生代後期(新第三紀)のどの時代においても、この生物の進化パターンは、普通似たような感じとされている。
基本的には、毎回の進化パターンが、種の平均サイズを大きくしていく傾向を見せている。
変異幅の制限
『コープの法則』とも呼ばれる、増大化の傾向は、進化という現象の一般性と考えられるだろうか。実際、化石記録は、たいていの系統が、増大化進化の歴史を辿ることを示しているともされる。
しかし実際のところ、確かに時間と共に大きくなるのは、最大種と平均のサイズにすぎない可能性もある。例えばたいていの種が、全体を見た場合、そのほとんどが小型種であるということもかなり確かな事実である。大きな種はいつでも少数派。
簡単に考えられる。単純に小さな種が多いから、大量絶滅の際には、生き残る種は小さい種の可能性が高い(実際その傾向がある)。そして新しい生態系の様々なニッチを埋めるために、サイズも含めた多様性が増やされていく。つまり、少数ながらも体を大きくする種が現れる。いつも最初に小さなもの、小さな種ばかりで始まって、後から大きい種も現れるようになるというのなら、平均サイズの増大化傾向の理由は簡単に実感できよう。
この場合、サイズが大きくなる傾向があるというよりも、サイズ幅(変異幅)が広がる。ようは大きさも含めた多様性が広がるだけということになる。
生物の大型化の進化はあっても、小型化の進化がそれほどないように思える理由も明らかであろう。(元々の数が多いだろうし)生き残るのは最小の種である可能性が高い。そうでないにしても、化石として残ることができる最小の大きさ、我々が気づくことのできる最小の大きさ、生物が物理的に生物として存在できる最小の大きさというものが存在するのなら、それが変異幅の制限の壁として立ちはだかっているのかもしれない。
モード(最頻値)で見る
プランクトン性有孔虫類に関しては、伝統的な採集方法は、堆積物を篩にかけるもの。目の大きさ順に段を重ねた装置に入れ、水洗いする。そしたら当然、殻の大きさと篩の目の粗さに応じ、様々なサイズの有孔虫が回収できる。しかし、篩の目のサイズの最小をもすり抜けるようなサイズの種はかなり採取されにくくなろう。そうした人為的な、観察範囲の限界のための壁も考えられる。
ところである数値サンプル群の平均の手がかりとしては、全サンプル合計の数値を、サンプル数で割った『平均値(arithmetic mean)』の他、全サンプルに順位をつけた場合の真ん中の順位サンプルの数値を抽出した『メジアン(median。中央値)』、サンプル数値の中で最も多い数を抽出した『モード(mode。最頻値)』。
例えば(1、1、2、3、4、5、6、7、20、167、45673591)という数値群があったとして、平均値は「4152164.272727273」、中央値は「5」、最頻値は「1」である。
特に平均値の増大化傾向は、サンプル群に、極端に大きなサイズがあった場合、結果が奇妙になりやすい。
生物の多様性の中で、有利な形質の基準を繁栄度であると考えるなら、もっとも重要なのは最頻値であろう(歪んだ分布における平均を探るのに、最頻値は有効ともされる)。中央値も、平均値ほど極端な怪物に引っ張られることはないが、やはり、実際には大して繁栄していない大きなサイズが抽出されてしまう可能性は高い。
スティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould。1941~2002)によれば、少なくともプランクトン性有孔虫の進化史においては、最頻値を指標にすると、それほど変化が見られないという。
 ダーウィン以来、ワンダフルライフ、人間の測りまちがい「グールド著作」
ダーウィン以来、ワンダフルライフ、人間の測りまちがい「グールド著作」
全体平均よりも、はっきりと大型化傾向を証明するには、直接的につながっている子孫種と祖先種を比べてみて、子孫種の方が大きくなる場合が普通であることを確かめるのもよい。
実際、中生代のプランクトン性有孔虫の、祖先種と子孫種の関係がほぼ確定されてる300以上の種のデータを使い、サイズの変化具合を調べた研究もある。そういうのによると、やはりそもそも大型、小型、どちらへの方向性も進化史の中には見いだせないらしい。
複雑性の増大化はそれでも考えられる
しかし今でも、何らかの意味での増大化傾向を信じることは全然可能と思う。
例えば生物の進化の最小の壁を考える時、逆に最大の壁はあるかと考えれたならどうか。 例えば生物種の基盤となる細胞構造が、複雑化限界の壁を動かしてきたならば、各区切りごとの生物群の最大に複雑な種の複雑度は結果的に上がっていくかもしれない。
しかし、グールド的な非進歩なトレンドが正しいとして、そしてもしかしたら、生物進化の系が、ある程度複雑だったり、大きな生物から始まったとしたら、進化傾向として単純な生物へ向かったり、小型化傾向も発生するだろうか。
今の段階では、突拍子もない空想科学的な考え方かもしれないが、人間が複雑である程度大きな動物とするなら、たとえば仮に、この生物が滅びゆく地球を見捨ててどこか他の星に移住したとするならどうか。その星にもともと生物がいなかったとして、人間がそこに生きるようになったならば、そしてその星をテラフォーミングのテクノロジーで、つまり他の地球生物を使うことによる改造をしないのだとしたら、その惑星の生命系は、人間(つまり複雑で大きな生物)を祖先種として始めることになるだろう。
また、人間社会というものを、自然の世界から外れた、いわば独立した世界系と考えるとするなら、テクノロジーの進歩によって人間は堕落してきているというような仮説も時々囁かれている。何事も単純なことが好きな子どもたちが増えていると。こういうことも何か、上記のような話と関連付けて考えることはできるだろうか。できるかもしれない。 だがこの場合、複雑化が発生させたテクノロジーというものが何なのかをしっかり定義する必要もあるかもしれない。
もしかして、それが生物の複雑化を止めるとか言えるだろうか。はたしてそんなことありえるのか。
適応主義的な進歩
特定の系統を特別視した場合、例えば動物、脊椎動物、哺乳類や人間を基準としても、顕著な増大化傾向は特に見られないとされる。また、単に数では少数派であるとしても、意識を有する特別な系統、すなわち人間も、今そのような複雑さの頂点のニッチに存在できる事は、単なる幸運の結果で、生態系の中で、複雑さの頂点がどんな生物になるのか決まっていると考える根拠など何もないとされている。
それにもかかわらず、絶滅時期の区切りを越えた後に発生する、いわば各区切りごとの時代の、生物群全体を見た場合の最大種に関しては、ひたすらに強化と言えるような進化を続けているのではないか、と推測することはまだ可能かもしれない。それは単に、体の大きさというようなものではなく、生物としてのあらゆる要素の複雑性の増大化とか。
ただしそのようなことが真実として、生物世界全体の複雑性(多様性)が、増大していくということを示しているだけかもしれない。全体の幅が広がるなら、当然、最大の部分の領域はそれまでの最大よりも大きくなるだろうから。実際、適応主義的と言えるような進歩の定義として「系統に有益な特徴パターンを、全体の傾向として蓄積していくことで(そのパターンを生き残る生物が保存することで)、より広い環境に適応する構造可能性を増やしていく傾向」というようなのが示されることもある。
微生物は生物設計図を保存してきたのか
地球生物の区切りは、いくつかの大絶滅であると考えたとして、しかしどの大絶滅でも当然、全ての生物が滅んだわけではない。微生物はどの絶滅の時でもかなりの数生き残ったと考えられている(むしろ影響がなかった可能性すら示唆されている)。長く、この地球で最も繁栄してきた微生物群が、我々のような巨大生物の領域においても強い影響力を今でも持っていると考える人は多い。そう考えると、区切りごとの次の巨大生物領域に発生する多様性の可能性については、微生物群が絶滅の度に普通に保存してきたと考えれるかもしれない。微生物群は複雑な生物の設計図を持っていて、そしてその設計図はどんどん付け足しがされ、複雑になっていっている。例え巨大生物が大量に滅んだとしても、次は初めから複雑な設計図を使えるから、結果的には前の時よりも全体の複雑性を高くすることができるのかもしれない。
しかしこの場合、1つだけかなり気になるところがある。つまり、設計図の複雑性の限界はあるのだろうか。
宇宙国家でどんな大絶滅の可能性があるか
やはり、ある惑星の終焉の時よりも前に、複雑な知的生物がその生息域を宇宙に広げていく場合も考えられよう。その場合、もしも複雑な生物も、結局は微生物のネットワークによってつながっているようなものならば、結局は微生物群のネットワークが宇宙中に広がっていくことを意味しているかも。だがそうなった場合、自らのネットワーク規模も大きくしていく微生物群は、さらに複雑な生物の設計図を得られるのだろうか。
複雑な設計図の限界がないとしても、それをいつまでも実用的に限界まで使い続けることができるだろうか。大絶滅がなければ、今の地球生物もここまで複雑になれただろうか。そうでないとすると、宇宙に生息域を広げた場合は、また別の問題が生じるかもしれない。つまり、宇宙のかなり広範囲に生息域を持っている生物群が、そのような全体的に壊滅的な大絶滅に見舞われるということなど考えられるのだろうかと。
いずれにしろ、複雑化への可能性を保存するための各区切りごとの複雑化傾向は、その保存性が安定していることを前提としているから、そこにまで打撃を与えるような大絶滅があった場合は、それが終了のお知らせとなろう。
そもそも誰にとっての進歩なのか
そもそも進歩とはどういうことなのだろう。それについて、複雑化が進歩だという考え自体が、人間至上主義的だと考える向きもある。
例えば、もしも進歩が、より単純な方向へ向かうと定義できるとしたら。(こういうのも適応主義的な進歩といえるような考え方であろう)それよりも何より、常に最も適用したものの適応度を上げることが進歩と考えれるのだとしたら、進化論的な世界はそれについてどのように受け止めるであろうか。
進歩のよく言われる定義の1つは、「望ましい方向へと変わっていくこと」であるが、だとするとその望ましいとはいったい何者にとってなのだろう。例えばもし、この世界に神様がいるとして、その彼がより単純で美しいような世界を目指しているのだとしたら、複雑への歩みは、望ましくない方向、退化と言えるかもしれない。