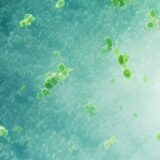国家という巨大な怪物の理論
トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes。1588~1679)は、機械論的、または唯物論的な世界観の研究に影響を与えたとされる哲学者。
『リヴァイアサン』は代表作。
ただ確かに、当時の神学的な立場からは、かなり異端的に世界要素を捉えていた印象はあるが、はっきり無神論者とわかるような記述は、(意外と?)あまりないようにも思う。ただし、彼は物質とか生物とかが存在する、この宇宙を単体で見るならば、それは完全に唯物論的なものであると考えていた節がある(おそらく、ただ、外部の神秘的な存在を否定していないというだけの(よくある)話)
それはともかく、この書で語られる、国家、人間の共同体を巨大な生物として考える理論などは、なかなか興味深く思う。
〔自然(神)が世界を作り給い、統治し給う技は、人間の技術によって、他の多くのばあいと同じように、人工的動物を作りうるという点においても模倣される。生命とは四肢の運動にほかならず、その運動にある内部の中心部分からはじまる、ということを考えると、すべての自動機械(時計のようにぜんまいと歯車で自動的に動く機械装置)は、人工的生命をもつといってならない道理があろうか。すなわち、心臓はなにかといえば、それはぜんまいにほかならず、神経はそれだけの数の細い線、関節はそれだけの数の歯車にほかならないのであって、それらは、神が意図し給うたような運動を全身に与えるものではないだろうか。技術は、さらに進んで、自然のうちで、理性的でもっともすぐれた作品、すなわち人間を模倣するに至る。というのは、技術は、コモンーウェルスあるいは国家と呼ばれるかの偉大なリヴァイアサンを創造するが、それは、人工的人間にほかならない……〕
人間という複雑構造
ホッブズは、社会の中にある様々な要素を、生物の部分に例える。そこには概念的なものもある。例えば、社会の構成員の全員が共有する約束ごとなどは、神が創造時に人間に与えた命令のようなものだとか。
ポッブスは本の最初の章で、国家(社会)そのものの重要な構成要素でもある、(固有構造としては最も優れたものであるかのように彼も認識していた節がある)人間というのが、いかなるものか考察している。
そこでは、複雑な精神を作る物理構造と、その精神が理解する恣意的な世界観との複雑な関係、今の時代で言うなら「実は全てが実質的にバーチャル現実」であるかのような理論、とかも語られている。
国家という生物、あるいは巨大人間、怪物(リヴァイアサン)が実在のものとして、この世界で最も自然的には、そのモデル要素的な人間は、どのように構築されているか。
 「VR(バーチャル・リアリティ)」人工の現実、偽物の宇宙の背景情報の謎
「VR(バーチャル・リアリティ)」人工の現実、偽物の宇宙の背景情報の謎  「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
現実世界の動作の、再現映像の精度はどれくらいか
〔個別的にみると、思考とは、それぞれわれわれの外部の物体の、ある質あるいはその他の偶有性の表象ないしは現象である。このような物体は普通、対象と呼ばれる。そして、この対象は、目・耳その他の人体の諸器官に作用し、そのさまざまな作用によってさまざまな現像を生みだすのである〕
そして思考は、感覚と呼ばれるものから生まれるのだろうと、 ホッブズは推測する。
確かに、目や耳というような感覚器官が、生物という構造体(個体)の一部であるとして、それらは外部環境からの影響を(吸収とか、変化とか、方法はともかくとして)捉えるものでしかないように思われる。そして、そのような感覚器官がとらえた情報を整理して、自らの意識的な領域の中で理解することが、我々にはできる。そのようなシステムが明らかにある。
本当にそうだとするなら、我々が心の中で浮かべる概念というものは、実際の世界に存在する何かではなく、物事の分類のための記号のようなものでしかないかもしれない。
そして、もしかしたら我々は、本当に何かを理解するということが、できないのかもしれない。
我々の感覚と、想像と、現にこの世界に存在する物質群。それらの、(どうやらあちこちで起きてるらしい)相互作用に関しては、少なくとも ホッブズは、かなり唯物的に理解しようと努める。
彼は、相互作用している物質同士を単体で見た場合に、個々には何が起きているか、ということに1つの答も提案する。
つまりそれは動作、運動であろうと。
それで色や音というのはどのように伝わるか。そのようなもの(音や色)が、(つまり、昔の唯物論者が考えたような)何らかの塊なら、感覚器官でそれを感知している時、その色とか音の物質は移動していることになる。だが、構造体がそのような色とか音とかを持っているとしても、それが誰かの感知のたびに、その構造体から離れているはずがないと、ホッブズは考えたようである。(彼曰く、彼の時代の少し前からキリスト教社会における主流だったとされるスコラ学派には、感覚とか理解の背景に、かなり直接的な物理的やり取りがあるとする考えが、普通だったらしい)
それはなぜであるのか。
 「ルクレティウスの唯物論」物の本質について。無神論者の、全てを原子で説明する試み。
「ルクレティウスの唯物論」物の本質について。無神論者の、全てを原子で説明する試み。
もしもある構造体の内部に、無限に何かが生成するような仕組みがないのなら、感覚に捉えられているということは、何かを取られ続けているようなものであって、どこかでその要素が失われたりすることもあるのかもしれない。
ホッブズはそのような世界観を考察したのだろうか。
いずれにしろ彼は、基本的に知性が理解する、つまり我々が見たり聞いたりしていると感じているもの自体は、ある種の映像みたいなものであろうと推測した。と、そこまではいいのだが、それでは少し、現に存在しているこの世界と我々の妄想との区別がかなり曖昧になってしまう気がする。
どうすればよいのか。
実際、ある構造体と構造体は、この世界の中でどのように情報をやり取りしているか。音は2つの構造体の間の分子群に与えられた振動波。色は(目のような)光を捉える感覚器官の方向へと向かってきた光の波長に関連している。というのが、今の一般的な考え方であろう。そしてそのような現象がある時、我々はまさに、砂を固めたみたいな物質の塊を投げ合っているとは言いがたいだろう。
だが確かに、物理的などんな振動も波も、ある種の動作だ。それが我々のこの精神が、それを色とか音として理解するまでの過程で、おそらく何かの変化はある。多分ホッブズは、それを想像とした。
映像からは読み取りにくい力学、動作
その昔、アリストテレスは、物質の最も自然的な状態は静止状態であって、動いてる状態というのは(何かの影響を受けるこで)自然から離れた状態だという仮説を語り、これが長く支持された。
ところがガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei。1564~1642)は、どういうのが自然なのかはともかくとして、何らかの力とかみたいな影響がなければ、変化しないのは物事の状態だろうと考えた。つまり、動いている状態の物質に何もしなければ、その”動いている”という状態は変わらないというような、そういう考え方を提唱した。
そしてこれは、現代の力学の基礎的な見方にもなっている。
ガリレオの考えに影響を受けていたのか、自分なりに同じ結論に達したのか、明らかにホッブズは、そのような(静止している物質に何もしなければ静止したままなだけでなく、動いてる物質に何もしなければ動いているままである)力学の世界観を想定していた。
〔物体が静止しているばあいには、なにか他のものがそれを動かさないかぎり、それは永久に静止したままの状態にあるだろう、ということはだれしも疑わぬ真理である。しかし、物体が運動しているばあいには、なにか他のものがそれを阻止しないかぎり、永遠に運動し続けているであろう、ということも、その理由はまえと同じこと(すなわち、いかなるものも、それ自体では変化しえない)なのであるが、なかなか簡単には容認されない。人間というものは、自分以外の人間だけではなく、すべての他の物体についても、自分自身を基準にして判断するものだからである〕
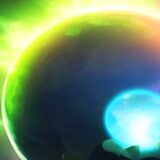 「古代ギリシアの物理学」万物の起源を探った哲学。遠い現象の原理
「古代ギリシアの物理学」万物の起源を探った哲学。遠い現象の原理  「ガリレオ・ガリレイ」望遠鏡と地動説の証明。科学界に誰よりも業績を残した男
「ガリレオ・ガリレイ」望遠鏡と地動説の証明。科学界に誰よりも業績を残した男
なぜ、何も影響がなければ動いているものは止まりたがる、と考えるのか。この誤解が生まれる理由の1つとして、ホッブズは、我々が何か運動をした時とかに感じる疲労感を持ち出す。自分を基準にしてしまうと、動くと疲れるために、万物は静止を望む。しかしホッブズは〔人びとが、自分たちのなかにみいだす休息への意欲は、なにか他の運動に原因があるのではないか〕と考えてもよいだろうと指摘する。
そんな疑問は当然だと思う。 ホッブズはまさに、国家が巨大人間だと考えたように、すでに人間というものは、様々な要素を含んだ複雑な構造体だと考えていたのだろうから。
人間は完全に個の物質というだけのものではないのだ。たとえ各物質が、他から影響を受けなければ全く何も変化しないというようなものであるとしても、構造体である人間の各要素は、常に内部、外部から様々な影響を受けている。そして複雑に絡み合うネットワークの1つの帰結が、人間という存在なのだ。そしてこれは、おそらくは動作をした場合に、疲労と定義できるような現象を起こす、システム。
〔……水について、風が止んでもなおその後、長いあいだ波がそのうねりを止めないのをみるように、人間の内的部分に生じさせられた運動についても、すなわち人間がみたり夢みたり等々するときにも、同じことが起こるだろう〕などといった推測はどういうことか。
ホッブズの考えでは、我々が何かを見ている時、我々は直接にそれを見ているのではなく、得られた情報から映像(またそれは実は記憶でもあるという)を作っている。この作られた映像というもの自体はどのようなものであるか。目を閉じてみて、それでも目を閉じるその時まで寸前に見ていた光景が、脳裏に焼き付いているような感覚。そういうのも、ある種の動作が、その動作を起こすための影響がなくなった後もしばらく継続する現象、と同じようなものでないかと彼は考えていたらしい。この場合、映像という世界の部分の動作の原因は、それを構築した我々の神経(すなわち精神の)システムであろう。
どのくらい意識していたかわからないが、ここにはやはり、かなりはっきりとした唯物論的な見方があるように思うが。
夢はなぜ夢と気づけないか
”夢”というのは、眠っている人間が作る映像だという。ただし、(目覚めている時に行うような)感覚が得た情報を参考にして理解しやすいように再現している、とかではなく(ホッブズは、寝ている時は、様々な感覚器官や神経系が不活発になるはずと考えていた)、〔人体の内的部分の精神的興奮によって生じるもの〕としている。
内的部分は頭脳その他の諸器官と連結してるが、通常の感覚システムの不活発は、理性的な意識を失わせていて、だからこそ夢の映像は強烈な印象を与え、それが夢である(完全に妄想でしかない)こと自体を気づきにくくさせているのだろう、とか。
ホッブズにとって、夢という現象は、我々が、我々の作った映像を、映像と気づかずに体験することが容易であることを示唆する、1つの重要な例だったろう。
ホッブズは、そのような強い想像こそが、そしてそのような強烈な偽の世界観についての無知が、様々な妖怪とか魔女とか幽霊とかを生んだ可能性にも言及している。
そこはさすがに〔神のみが超自然的な幻を作りうることは疑いのないところだが〕とか、けっこう慎重であったが、しかし唯一の神についての話、あるいはイエス・キリストのような人物の霊感自体が、すでに単なる妄想であるという仮説も、ホッブズの文からは連想しやすい。ホッブズが警戒に値する人物だと、宗教の信者や教祖たちが考えたとしても、特におかしくはなかった。
人間の特別性。唯物論と平等主義
人間は、他の動物と比べて、何か特別だろうか。
たとえこの世界が完全に唯物論的な世界だったとしても、これ(人間)が少なくとも確認されている生物の中で最も複雑な生物、と考える向きは多い。
ただ、その特殊性は、どのような特殊性か。
〔……人間のみに固有なもののようにみえるところの、多くの能力は、後天的なもの、研究と努力によって増大されるものであって、それらはたいていの人において指導と訓練の結果習得されたものである〕
認識される世界は、(現に存在している世界とどれくらい似ているか、どれくらい完璧に再現されているかにも関係なく)あくまでも自身の精神が用意した映像にすぎない。本当にそのように考えていたとしたら、人間の精神と関連する様々な独自要素(?)が、この複雑機械(人間、というか知的生物)の作用による後天的なもの、という発想も当然かもしれない。
(自然から離れていると言われることもある)人間の世界の多くの要素が、この知性体の知的活動によって、後天的に作られたという説を支持する立場上では、”言葉”というものがよく重要視される。ホッブズの場合も、その例に漏れない。
〔……これらはすべて話と言葉の発明から生じたのである。というのは、人間の心には、感覚、思考、思考系列のほかにはなんらの運動もないからである。ただ、同じような能力があって、言葉と方法の助けによって、人間を他のすべての生物から区別するほどの高次の段階にまで進歩させることができる。というにすぎない〕
ホッブズは、うまく機能した理想的な国家を怪物扱いしていても、もちろんそれを恐れてばかりとかではなかった。むしろ、とてもポジティブな印象が強い。
重要なことは、彼は人種や性別に関して、同じ人間という種として、生まれつきの決定的な差はないとしていた(ような記述が普通にいくらかある)ことかもしれない(ホッブズを唯物論者として想定するならば、それほど驚きではないが、単純に時代だけを考えると、なかなか興味深い平等主義かもしれない)。
人は言葉で色々学んで、人間世界の中で優れた存在になれるが、それはあくまでも学びの結果。そのような考え方と、言葉というものの知的生物システムへの(驚くべきほどの)影響力を合わせるなら、必然的に、言葉による情報(知識)の共有というものがもたらす、素晴らしい結果を連想したくならないだろうか。
ホッブズは多分、実際にそれを考えた。彼にとって、様々な法律とか宗教とか、そのような社会の者たちの心理的側面を管理するための概念群は、全体としてのその巨大人間が安定して機能するための優れた歯車でしかない。最も重要なことは、その巨大人間が持つことのできる、まさに人間が持てるような知識量の単純な増大、その膨大な知識量を利用した世界そのものの変革、というような考えがあったのでなかろうか。
聖書の記述に関する疑問は何だったか
ホッブズの記述の中に、明確にキリスト教の神を否定しているようなものはないと思う。ただし、懐疑的な見方を促すようなものはある。
特に、「聖書の権威についての問題の提示」としている一節は興味深い。
〔キリストの宗教のさまざまな宗派のあいだで、おおいに論談されている問題は、聖書はその権威をどこからひきだすかということである。この問題はまた、ときには他の用語で、われわれはどのようにしてそれらが神の言葉であることをしるか、あるいは、われわれはなぜそれらを、そういうものだと信じるか、という問題として提出される〕
 「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説
「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説  「新約聖書」神の子イエス・キリストの生涯。最後の審判の日の警告
「新約聖書」神の子イエス・キリストの生涯。最後の審判の日の警告
実際それは難しい問題だろう。答が出せてるとも思えない。
何か、神の教えがあったと、誰かが言ったとして、それがなぜ、ある種の妄想でないと自信を持てるのか。
案外、明確に書いていないだけで、聖書とか教会の権威に対する疑問の、穏やかな表明だったりしたのかもしれない。