ピュシオロゴイたち
アリストテレス(Aristotelēs。紀元前384~紀元前322)は、自分より以前の自然哲学者たちのことを『ピュシオロゴイ(physiologoi。自然を論ずる者たち)』と呼んだとされる。
ちょうど彼が生まれたくらいの頃でも、アナトリア(小アジア)やイタリアの沿岸地方では、自然を研究する哲学者たちのいろいろな学派が、この宇宙に関する思想を共有し、次々と(例えば世界がいかにして形成されたかとか。どのように現在の安定状態を保っているのかとか)大胆な理論を提唱していたらしい。
創造論。第一原理の謎
ピュシオロゴイの中には、もっと実用的な視点を持つ経験主義者たちもいた。 そういう者たちはすでに、例えば数学をいかに利用できるのかをよく理解していて、地球や天空の大きさを測ることさえ試みた。さらには、原始的な知識の上では実体として捉えることも難しいと思われる音などに関しても、数学的法則を見出したり、定義付けようとした。
しかし結局のところ、彼らが特に重要視していた理論の多くは、彼らにとっては実証できないような、つまりは説得力のある空想程度のものにすぎなかったと考える向きは多い。結果的にそうなったことも、技術的制約のためというよりも、彼らのある種の思い込みが原因だったと考えられる節すらある。
古代ギリシアの多くの哲学書は、自然の様々な現象を説明するのに、多くに機械的説明を付けながらも、例えば第一原理に関しては、不可知的な、あるいは超越的な神なる存在を無条件で想定している感じのものも多い。
世界がどう動いているかを考える時、なぜそのような動きをしているのかに関しては考える必要性が薄かったのかもしれない。それは人間にはわからない超越的存在の特別な技があるのだから、というように。
神か、愛の力か。唯物論の限界
古代ギリシアの他その思想を受け継いだローマの哲学者の中にも、時には唯物論者がいた。しかしたいてい彼らの理論は、普通は神を想定しないといけないと思われるような不可思議な現象に関して、その説明になかなか無理が感じれる。
原因を推測できても、それを確かめる術がなかった、あるいは確認できるとは思われなかった時代において(つまりいくつもの現象をただ謎で終わらせるしかない中で)は、唯物論というのは、理性的でなく、感情的なものだったかもしれない。
もっとはっきり、神学と科学の違いもかなり曖昧だったと言ってもいいかもしれない。我々が、神など想定しなくてもよい物質世界に対して考えるのと同じような意味で、第一原理に神が存在している神秘的な世界が、科学的に考えるべき対象だったとか。
 「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン
「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン
それでもピュシオロゴイは、それまではほとんど神の力で片付けられていた問題の多くを、あくまでも自然の原理として説明しようとした。
例えば地震という現象に関して、神話を記録したヘシオドス(Hēsíodos。紀元前700年頃)が、 その原因を神の怒りと関連付けた。しかしミレトスの哲学者タレス(Thalēs。紀元前624~紀元前546年)は、大量の水の上に浮かぶ大地が、波に揺さぶられることによって地震が起こると考えたという。
また、世界の始まりなどに関しては、神が世界を創造したというようなもののほか、根源的な愛の力などといった、ある種、世界に備わる魔法的な力によって、自己的に発生したかのような仮説も人気だったみたいだが、それもまた、もともと、どうしても想像するしかない第一原理に関して説明しようとした結果だったのかもしれない。
提唱者が誰か問題
タレスの水に浮かぶ世界観のような、特定の哲学者が提唱したとされる様々な仮説が、現代まで多く伝わっている。しかし実際のところ、古代ギリシア哲学におけるある仮説の提唱者が、誰だったのかを示す根拠は、別の誰かの引用がほとんどである。『ドクソグラフィ(Doxography。学説誌)』頼りとも言われる。ドクソグラフィというのは、 つまりは過去の思想家の学説を紹介する書物のこと。
例えばタレスに関して、 彼は最初の哲学者ともいわれるほど、広く影響を与えていたようなのだが、彼自身の著作は1冊も現存していない。
真の歴史を考える時は、後世の研究所の都合よい解釈とか、断片的な捏造などの可能性も考慮しないといけないだろう。
それに、少なくともそのような提唱者がはっきりとどこかで示されている仮説の場合、その提唱者がそういうことを考えてもおかしくないというようなイメージが、少なくとも知識人たちの間で共有されていた。というように考えていいかすら少し怪しい。なぜなら、そのような仮説の提唱者が示されているテキストが、当の提唱者の死後から数百年経っているもの、ということもそう珍しい話ではないから。
当時よりもずっと文字による記録が多く残されてきているであろう現代においても、数百年前ともなると、怪しい記録が非常に多いでないか。
今時はどんなふうに考えてるか
しかし第一原理とかに関して、現代の科学はどう考えているだろうか。事実上何も考えてないと言えるだろう。現代的なサイエンス(科学)は反証可能でないものは基本的に対象外として扱う傾向にある。ようするに古代ギリシア(のものにも限らないだろうが)哲学に比べると、かなり保守的な考え方が普通なのである。
例えば宇宙のどこかで発生した(おそらく地球だろうが)地球生物に関して、最も初めの共通祖先までは考えるが、あるいはその共通祖先が生まれた化学反応とかは考えるかもしれないが、そのような化学反応が、この宇宙になぜありえるのか、という根本的な理由に関しては、ほとんど無視する。宇宙の始まりに関しても、ビッグバン理論を唱えて、その証拠をいくつも提示はするが、しかしビッグバン以前の(というより、最初のビッグバンが最初に起こるような状態がいかにして生まれるのか)宇宙のことに関してはあまり気にしない。
 「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要
「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要
もっとも、様々な科学分野で、考えなければいけない範囲が思っていたよりも広いかもしれないという可能性が最近は多く示されていて、例えばパラレルワールド宇宙に関しての可能性を考える時、それは反証可能という意味での科学なのかどうかの議論の原因になったりもする。
しかし反証可能かどうかというのはやはり重要で、例えば「世界を作った神がいるかどうか」というのが科学の問題外とされるのは、そのような超越的な神がいるとしても、いないとしても、その反対のことを証明する術を誰も知らないから、と言えば普通、話は終わる。
プラトンの宇宙観。創造者デミウルゴス
プラトンが、その著書「ティマイオス」で語る宇宙観は、弟子であったアリストテレスにも痛烈に批判されていたとされる。
しかし確かに宗教色が強くはあるが、それもおそらく、宇宙の創造者デミウルゴス(Demiourgos)を含め、万物の原因に関してどうにか説明しようとした結果ではあった。
しかしプラトンが読み取り、理解しようとしたデミウルゴスが世界を作った理由というのは、つまり世界の第一原因がいかなるものだったか、という謎だろうか。
プラトンのティマイオスという本は、時々は、世界の物理的原因を数学的分析によって明らかにしようとした最初の試みとされることもある。それは過大評価であるとしても、おそらくこの本は、数字を用いた物理法則を語った、現存する最初期の本であろう。
その世界観も、プラトンの幾何学への興味ゆえだろう。プラトンは物質原因としての4元素(火、水、土、空気)に関して、それぞれが幾何学的形(正多面体)を持ち、 どんな形も、もっとも単純な幾何学的形である三角形が基礎になるというように語った。
ただし、何かの証明になっているかと言うとかなり微妙なところである。例えば「火の原子は尖っているから、刺激が強い」とかそういう話である。もっとも、 面の数と面の数を足し合わせた物質と物質の変化の説明など、例えばエネルギー保存則を思わせるような発想も見られはするが。
アナクサゴラス。第一原理の原理の問題
クラゾメナイのアナクサゴラス(紀元前500~428)は、全物質が無秩序に混じり合う混沌状態から始まった、宇宙創成理論を展開した。
混沌の中に秩序ある形を与えたのは、それ自体がどのように生じたのかはよくわからないが、とにかく『ヌース(知性)』と呼ばれる要素だった。
ヌースにより、混合されていた全物質が、部分的に分離し、独自集合体となり、それら各集合体が、数々の固有の物質となっていった。
問題は、ソクラテス(Socrates。紀元前470~紀元前399)がすでに指摘していたとされるように、アナクサラゴスは、あらゆる物質の原因がヌースと言っているだけで、そのヌースなるものが どこからどのように生じたのかを全く語っていないこと。これでは、神が全てを創ったという物語と、本質的には変わりないだろう。
仮にソクラテスのこのがっかりしたという話が、いくらかでも真実なら、彼の弟子プラトンが最終的に「第一原理は人に理解できないようなもの(神)だから、考えるだけ無駄なのだろう。我々が理解できることは、神の魔法の上に成り立ったこの世界のシステムだけだ」というようなスタンスになったのも、仕方がないと言えば仕方がないのかもしれない。
哲学は科学と何が違っていたのか
現在の人が科学史を見てみる時。
万物の根源を探究した古代ギリシャの哲学者たちについて、その思想が現代の科学までもかなり先取りしていたことを讃える者は多い。一方で時には、例えば理論の証明という過程に対して、彼らがかなり無頓着だったと思われることは愚かと見る向きもある。
ようするに彼らは、様々な世界観の理論を提唱はしたが、それらのどれが正しいのかを具体的に確かめようとはしなかったという考え方である。現在の我々は、彼らが提唱したいくつもの世界観のうちのどれが、今我々が考えているような世界観に近いか、ということを考えることはできる。しかし、当時の彼らには、どれが正しいのか客観的には理解できていなかったのではないか、というような疑いがあると言ってもいい。つまり彼らにとって自説は、論理的に正しくありそうとかではなく、単なる願望的なものだったと。
時に、(特に前8~6世紀くらいであるアルカイック期、前5世紀~4世紀くらいの古典期と呼ばれる時代の)古代ギリシャ哲学のほとんどの理論はポエム(物語詩)にすぎないというような評価もあるが、実際何の根拠もなくそうあってほしい、というような世界観を語りまくっていただけならば、的外れとも言えないだろう。
物理学者スティーヴン・ワインバーグ(Steven Weinberg, 1933~2021)などは、タレスからプラトンまでの哲学者たちの系譜の中で、ゼノンを除けば、自説の論証すら試みていないことに注目し、彼らの過大評価を指摘した。彼らは「どうやってそれを知ったのか」をまるで気にしていないと。
誰のために書いた本だったか
ただし現代の科学者でも、何か説明の文章を書く時そうであると思われるように、哲学者たちも、その説明のベクトル(矢印)を最も多く向けていたのは、同時代の人たちだったと思われる。それも文字を読むことができるような知識人か、そうなろうとする学者の卵である。
それに今でも、専門家が専門家向けに書く物が(無駄だからというよりも、おそらくその先の多くの情報をなるべく含めるために)、 その意味も説明もなく(つまりその読者なら意味を知っているはずと暗に了解している)大量の専門用語であふれていることは珍しくない。 一方で、誰が書いたにせよ、一般向けに書かれた本とかには、理論だけ紹介されてたりとかして、 特定の雪を断言するするのに何故そうなのかを語っていないものもまた珍しくない(重要なこととして、そういうもの、つまり答だけ書いてあり問題の解き方が書いていないような本は、妙に詳しく説明しているものよりも、人気になることもある。特に理解が難しいとされている理論は、なぜそうなのかにあまり関心を持たない(というかはなから理解を諦めているから、答だけ、というような)人は多いと思う)
それに言うまでもなく、どの高名な哲学者でも、その著作が全て残っているとは考えにくい。そして後世に残りやすいものが何かを考えてみた時、「なぜそうなのか」を説明したものが書かれていたとしても、全然残らなかったことを理解するのは容易いと思う(ただしもちろん、本当にそういう類いのものが一切書かれなかったという可能性もあるが)
そもそも、それほどまだ科学と遠くなかった宗教の様々な書物においても、歴史上の中で高い評価を受けてきたのは、なぜそうなのかではなく、単に神に選ばれたものとかの奇跡の物語というような髪髪の毛神と神に選ばれたものの奇跡の物語的なものばかりである。
ワインバーグは、プラトンが自身の元素幾何学の理論について「批判は受け入れるが、現状我々は、他の考え方は考慮に入れていない。だが理由をしっかり書くと長くなるだろうからやめておく」とティマイオスに書いたのを見て呆れている。確かに彼の言う通り、現代の科学者は論文でこんなことを書けないだろう。
ティマイオスが、本来どんな読者を想定して書いたものだったのか、なかなか気になるところである。
確かに数学遊びや、それ自体哲学的色合いのある理性のみから提唱された(しかし自然の観察、測定、実験にも基づいていない)物理理論には、(たとえどれほど興味深くとも)現代的な意味での価値はほぼないと言える。
例えば、基本的には反証可能なものを扱うとする現代科学よりずっと、ギリシャ哲学は広い領域の謎に挑戦していた。現代科学の枠組み内で、そういう哲学をどう評価するかというのは実質かなり難しい。
逆にはどうだろうか。現代の科学を、そういう時代の哲学者たちはどういうふうに見るだろうか。
原子論。元素集合体としての物質世界
哲学に原子の概念を定着させたのは、ミレトスのレウキッポス(Leucippus of Miletus。紀元前5世紀)と伝わっている。この物質世界の最小構成要素、いわば最小ブロックに、「分割できない」という意味のAtom(原子)という名前を提案したのも、レウキッポスの弟子であったデモクリトス(Democritus。紀元前460~紀元前370)らしい。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
デモクリトス。実在か幻想か、その中間理論として
デモクリトスは、原子は「均一な固体であり、硬く、非圧縮性で、破壊もできない、停止するまで空間を無限に移動するようなもの」と考えたようである。そして全物質は原子の集合体であり、 そうした集合体の大きさなどの違い(つまりは原子の組み合わせ)によって、物質のさまざまな性質が決定すると。
デモクリトスは、単に物質世界の構造だけでなく、知覚とか、その原因(?)であるとされる魂などに関しても、この原子論で説明しようとしたという。 後に多くの原子論者によって語られる、きつい味はざらついた原子群、無味なものは滑らかな原始群というような理論も、彼はすでに語っていたとされる。
デモクリトスらの時代のギリシャ哲学界では、この世界全体に関して、対立する主要な2つの説があった。つまりは、この世界にはただすべて物質だけがあるという説と、全ては(それが何かはともかくとして)意識の原因だけがあり、そうして知覚されるものすべては幻想にすぎないというような説。
デモクリトス流の原子論は、全ての物質はそのままでは確かに幻想(見たまま、あるがままの存在とは言えない)といえるようなものだが、その原因は決して分割することのできない基本構成要素(つまりはマクロな幻想を演出しているものも、あくまで物質的なもの)というように、2つの理論の中間的なものだったとする見方もある。
エピクロス。唯物論は迷信を砕くか
唯物論者であったと思われるエピクロス(Epicurus of Samos。紀元前 341 ~紀元前270)は、デモクリトスの原子論を支持し、それを持って迷信の恐怖を破壊しようともしたらしい。
エピクロスの唯物論的哲学の世界観では、例えば神々のような存在がいるのだとしても、結局そのような神々すら(この空虚の中に大量の原子が溢れているだけの宇宙においては)原子の集合にすぎない訳であるから、この宇宙の本質的性質に逆らうことはできない。つまりは、まず世界があって、その上にすべての存在というようなものだったとか。
一方でエピクロスより少し前。プラトンとアリストテレスは、部分的には原子論を取り入れていたが、唯物論的に世界を考えたわけではなかった。彼らはおそらく、物質世界と別の重なっている世界観も考えていた。
プラトンは善や美といった属性は「物質原子の機械的演出」ではないとした。
アリストテレスは、ただ原子が動く場となる真空というものを否定したとされる。
原子の幾何学的構造
エンペドクレスは、万物は「地、水、火、風」の4元素から成ると考えた。
プラトンは、その四元素を取り入れた上で、さらに自身の強い興味の対象であった幾何学も手に、まさに幾何学元素論というようなものを提案した。
つまりプラトンは、この三次元世界において、四元素は5種存在する正多面体(すべてが同一の正多角形で構成され、頂点で接する面の数が等しい多面体)の4つと考えた。
火原子は正四面体、土原子は正六面体(立方体)、風原子は正八面体 、水原子は正二十面体。
しかし、正多面体は5種で、この場合は正十二面体が余っている。プラトンは、その正十二面体こそ、コスモス(宇宙の形?)と考えたらしい。
プラトンの理論の興味深い点は、原子の形を設定したことより、その組み替え自由性のシステムであろう。 例えば各原子の形(正多面体)は、さらに基本的な形である二次元の三角形の組み合わせである。
例えばいくらかの火原子と風原子をデタラメに混ぜたとする。
この時混ざり合った多面体群の三角形の数の中で、立方体を作れる数が揃った時、そこに土原子ができるというような(代わりに、火と風原子群から、立方体分の三角形が減る)。ある系の中で現れる素材は、その中にある物理量を決して変えないという考え方(エネルギー保存則)が、明らかにここに見られる訳である。
しかし、この原子の多面体を構成する三角形こそが真の原子なのだとしたら、それが造る正多面体原子4種は、内部が空洞なのだろうか。
またアリストテレスは、地上世界と天上世界の物理を別物として、四元素は地上の元素であるとした。そして天空は第5の元素エーテルあるいはクインテッセンスが支配するのだと。しかし彼が、エーテルを正十二面体と考えたかどうかは謎である。
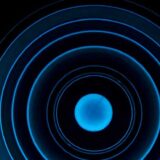 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
運動法則。日常的感覚の罠
ニュートン(Isaac Newton。1642~1727)の偉大な著作『プリンキピア(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica。自然哲学の数学的諸原理)』で語られた『ニュートン力学(Newtonian mechanics)』の基礎となる運動の法則は、アリストテレスの運動論と対立する。
 「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
ニュートンの運動法則とは、つまり以下のようなもの。
『第一法則。慣性法則』
静止している物体は力を加えない限り止まり続け、動いている物体は力を加えない限り動き続ける。
『第二法則。運動方程式』
物体に力がかかる時、物体には力と同じ向きの加速度が生じるが、その加速度は、物体の力の大きさに比例し、物体の質量に反比例する。
『第三法則。作用反作用の法則』
力を加えられた物体は、その作用と反対向きで同じ値の力(反作用)を発生させる
ただし日常的な視点では上記運動法則は奇妙とされた。力を加えて物体を動かす時、力に比例するのは(加速度なんてものでなく)単純に速度であるように思える。それはアリストテレスの考え方でもあった。
アリストテレスはなぜ真空を否定したのか
アリストテレスは、様々な物質はその中心に落ち行くものと考えた。そしてその中心の点こそ地球の中心であり、それが地上の物体が落下する原因であるのだと。
しかし、落下ではなく水平方向の動きをどう考えればいいのか。
ある物体を投げる時、その投げられる物体には、投げた誰かの腕の動きに押されているはず。では投げた誰かを離れた後に物体はすぐに落ちるかというと、そうとは限らない。
アリストテレスは、押す物がないようでも、物体がしばらく飛び続けられるのは、空中を飛ぶ物体は、さらに(物体を投げる手の勢いに一緒に押された)空気に押されているからとしたらしい(普通、この考え方はかなり強引とされる。つまりは、投げられた物体がすぐに落ちない事は、アリストテレスの力学が間違っているという重要な手がかりとされるのが普通)
またアリストテレスは、投げられた物体を投げた手を動かしている別の何かの動きも必ずあり、それが例えば筋肉の収縮ならば筋肉を収縮させている何かもある、というような運動の連鎖を考えた。そして、そのような連鎖が無限であるとは考えず、最初に動かし始めた何かが存在するというような考え方をした。
不動の運動者、それ自体が運動を開始することなく運動を開始できる存在。言うなれば、アリストテレス哲学世界における神がそこに現れる訳である。
そしてまた、このような原因論を突き詰めた彼は、『真空(vacuum)』というものを否定するに至った。
現在の一般的な(あるいはニュートン力学的な)理解では、投げられた物体に対し、空気はむしろ抵抗する形となり、物体が勢いを弱める原因となる。
また真空に関しては、例えばアリストテレスは「自然が真空を許さないからこそ、ポンプは水を吸い上げられる。つまりは空気が抜かれたためのポンプ内真空を水が埋めようとするから」というように説明したが、液体が容器内を埋めようとしない状態は作れる。エヴァンジェリスタ・トリチェリ(Evangelista Torricelli。1608~1647)はそれに成功もした。彼は、ガラス菅を液体の水銀で満たし、さらに大きな容器に入った水銀に突っ込んでから、ガラス菅の塞いでいた口を開いた。水銀につかった開口部を下に、ガラス菅を真っ直ぐ立てると、ガラス菅内の水銀はいくらか流れ出るものの、それはガラス菅と容器の水銀の高さが同じになるより早く止まった。この時、容器内に見られるものは、まさしくアリストテレスがないと断言したものと同じ意味での真空と思われた(このトリチェリの真空の発見から、大気圧の研究などが進んでいくことになる)
アレクサンドリアで進んだこと
ヘレニズム期(紀元前323~紀元前33)、哲学(科学)の中心地となったエジプト、アレクサンドリアの学者たちは、それ以前の時代の偉大な哲学者たちに比べると、より身近で実用的な問題を好むようになっていたとされる。
彼らは、万物の根源のような壮大な問題の優先度を低くして、現実に実験的成果を上げることが可能と思われる現象を見いだしていった。
身近な世界の動きを理解しようとして、結果的に光学や流体静力学(流体の変形や力を扱う流体力学の分野)などがよく発展したとされる。
 「流体とは何か」物理的に自由な状態。レイノルズ数とフルード数
「流体とは何か」物理的に自由な状態。レイノルズ数とフルード数
また、ある意味それまでの伝統的なギリシャ哲学は、人工によって乱された自然を、つまり不純物の紛れ込んだようなものとみなして、哲学的対象として低く考える傾向があったとされる。しかしアレクサンドリアでは、その傾向も少し弱まっていたらしい。結果、科学研究が技術の発展に直接結びつくことも珍しくなかった節がある。
光学。光はどこからどう進むのか
エンペドクレスなどは、視覚システムが光を利用していたことに注目した初期の人とされる。 彼は彼の唯物論的世界観において、知覚システムを光を媒介としたものとして説明した。つまりは、生物のそうした機能(視覚)を実現する原子構成が光を発した場合、対応する外部要素と結びつくことによって、何かを見るというような認識過程が発生しうる。というような。
一方で、光という物理要素自体の性質に関しては、アレクサンドリアで活躍したとされるエウクレイデス(Euclīdēs。紀元前3世紀)の研究(あるいは先人の研究をまとめた記録)が伝わっている。
 なぜ数学を学ぶのか?「エウクレイデスと原論の謎」
なぜ数学を学ぶのか?「エウクレイデスと原論の謎」
エウクレイデス。反射はなぜあるのか
エウクレイデスもまた、目から光が発すると(現在の一般的な理解と逆に)考えていたが、彼は特に『反射(reflection)』という現象に注目した。
目が光を捉えるにせよ、目から光が発せられるにせよ、ある物体が鏡に映る時に起きていることは、まさに光の反射であろうが、そうすると、鏡への、あるいは鏡からの光の経路をどう考えればよいか。ある物体から鏡面上のさまざまな点を経由し、目に返ってくる光の道は何通りも考えられる。しかし鏡に映る像は鏡一杯には広がらない。鏡が常に、何か特殊な原理により、特定パターンの光と相互作用する点群を対象(?)の形に合わせているとかでないなら、おそらくは鏡像が現れる原因の光が通る経路は1本でなければならない。
エウクレイデスは答を得ていたとされる。つまり「光線が鏡面と成す角度は、光線が鏡面にぶつかるときと、それが反射するときとで等しい」という法則(この条件を満たす光の道は1本だけ)。
ヘロン。最短ルートの法則
後のローマ時代、紀元後60年頃にはヘロン(Heron of Alexandria。10~70)という人が、光線の道筋の法則(等角度の法則)を、「物体から鏡面にぶつかって、観察者の目に返ってくる光線は、常に可能な最短ルートを選ぶ」という仮説に基として、数学的に証明もした。ただし、光線がなぜ最短ルートを選ぶのかも、ヘロン(あるいは他の誰か)が証明したかは定かでない。ただヘロンは、「自然は無駄なことをしない」という信念を抱いていたらしい。
紀元後15年頃には、クラウディオス・プトレマイオス(Claudius Ptolemæus。83~168)が、等角度の法則を目盛り付き装置などを利用して測定も試みたそうである。
ずっと後、17世紀には、フェルマー(Pierre de Fermat。1601~1665)がヘロンの反射法則を「物体から目に至る光線の経路は、距離でなく通過時間が最短となるコース」と修正。
そしてホイヘンス(Christiaan Huygens。1629~1695)が、光の波動説から、反射を含む、光線現象の原因(光の波がどのように物理空間を伝わるか)の原理を見いだし、光線の道筋の実用的解析も可能となった。
流体力学。機械のためのいくつか
アレクサンドリアには、エジプト王プトレマイオス1世(紀元前367~紀元前282)に招かれ、王子たちの教育係を任されていたこともあるというストラトン(Stratōn。紀元前3世紀)は、特に光や熱が物体を通過することから考えを展開し、真空を存在しないとするアリストテレスの考えを拒否したことが知られている。
またストラトンは水滴群の落下運動の観察研究により、「落体は下向きに加速する」と結論した。
紀元前250年頃にアレクサンドリアに滞在していたらしいフィロン(Philon of Byzantium。紀元前280~紀元前220)は、機械工学について書いた本で、空気の力学について記述している。
彼の理論はおそらくかなり実用的で、実験に基づいていた。例えば彼は、空ビンを逆さまにして水に沈めたら、ビン内の空気の圧のために、水はビンの中に入ってこないが、ビンに穴を開けて空気を抜くと、水は流れ込んでくる。というような説明をした。
また、残念ながら現存していないが、技術者だった彼の成果の中には、人間型の機械のための理論もあったらしい。
アルキメデス。浮力の法則
しかしヘレニズム期において、最も重要とされる学者は、おそらくアルキメデス(Archimedes。紀元前287~紀元前212)。
技術者としても優れていた彼は、 てこの原理を応用して海岸付近の船を拿捕させる機械とか、集めた太陽光の熱を利用する兵器などを造ったという伝説まで伝わっている。
そのアルキメデスの実際的な研究成果として、最もよく知られているものはやはり、静止流体における浮力の法則であろう。
つまりは、流体(気体または液体)に完全または部分的に沈められた物体には、上向きの力(浮力)が作用する。そしてその浮力の大きさは、物体が押しのけた液体の重量に等しいというもの。
情報。世界存在のパラドックスはあるか
現代の科学者も、物質世界を考える時に、直接的な観察ができない要素を想定することはある(もちろん間接的に実験などで示されることは重要とされる。例えば電子の存在に関して、電子なるものを直接は見れなくとも、それが存在することで説明できる現象を見つけたり、意図的に発生させたりとかいうような実例がないと、大した支持はされないと思う)。
間接的な証拠がどのくらい重視されていたかはいまいち不明なところもあるが、古代ギリシャの哲学者たちも万物の最小構成要素として、直接確かめられたことのない原子を想定したりした。
ようするに、現代の我々が、おそらくそういうことなのだろうと推測しているように、古代ギリシャの哲学者たちも、我々に(特殊なテクノロジーや魔法なしでも)知覚できるものだけが世界の全てではないことは理解していた(あるいはそのつもりだった)。
ゼノン。あらゆる運動は不可能か
パルメニデス(Parmenides of Elea。紀元前520~紀元前450)は「自然界において、人に観察可能な変化は幻想」とした。そうした仮説に傾いた彼だが、目指していたものは世界に存在しているものが存在可能としている根本原理であったようである。そういうことを考える哲学を『存在論(ontology)』と言うが、彼はその分野の創始者ともされる。
師の思想を継いだパルメニデスの弟子ゼノン(Zeno of Elea。紀元前490~紀元前430)は、 例えば運動という概念が実際にこの世界に存在しないことを示すために、1つの逆説(パラドックス)を提案。
つまりは、ある人がある特定位置から別の位置へと進む場合、まずはその距離の半分を走り、次には残り距離の半分、さらに次にはまた残り半分というように、いつまでも距離の半分を走り続けることになってしまって、目的地には永久に着かないと考えられると。
それでゼノンは「つまりあらゆる運動は不可能」と主張したのだという。
肯定するにせよ否定するにせよ、ゼノンのパラドックス、あるいは論法を拾い、それぞれが考える世界観で考えてみた哲学者たちは多い。
特にアリストテレスはよく知られる。彼は、ゼノンの論法が運動を否定することを否定した。
例えば距離の各段階、つまりは半分の距離ごとに、必要時間が充分な速さで減少していくなら、無限分割された距離であっても、有限の時間で遂行できるだろうと。
これは例えば、1/2 + 1/4 + 1/8 +……というような無限級数、つまりは無限に足し合わせていく数列の和でも、有限の場合があると言っているに近い(実際にそうである)
 「数列の基礎」和の公式。極限と無限。単純な増加、減少
「数列の基礎」和の公式。極限と無限。単純な増加、減少
より現代的に考えるなら、ゼノンの考え方は、運動の空間的な位置関係でしか捉えていないのが、間違い(というか勘違い)の原因と思われる。
つまりは、時空間の中に敷かれた線上を、例えば一定以上の速度で進む場合、ある時間に進む距離は一定だから、例えば時速5メートルの物体が5メートルの距離を進もうという場合に、ゼノンの論法を適用したいならば、時間経過を常に半分にしていくなどの工夫が必要となる。
逆に、例えばある程度以上、無限に減速し続ける速度の物体とかなら、例えば無限の時間の中ですらゼノンの考え通り、目的地に着かないような状況を、有限距離で実現できる。
一般にアリストテレスは、「有限線距を進むのに無限な時間を使うことは不可能」と断定していたとされるから、その点では彼も間違っていたと言える。
 「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
見かけの世界を下に見ていたか
しかし、パルメニアスやゼノンどころか、彼らの仮説を支持した古代ギリシャのどの哲学者も、(仮に運動が不可能なのだとして)なぜ物体が動いているように見えるのか、どういう立場にせよ重要と思われるその点には妙に無関心だったとも言われる。
つまり真の世界がどのようになっているのかを説明する者は多かったが、見かけ上の世界の説明はあまりなされなかったと。
我々の知覚しているものが見せかけの世界にすぎないならば、そこに大した意味が見いだされなかった理由は何か。ここに、古代ギリシャの哲学者たちの「単に見かけ上の世界を低いとする」知的スノビズムを推測する向きもある。
スノビズムというのは、ある種のものが、別の種類のものよりも優れているとして、その他の(劣っている)ものを見下すような(つまり絶対的に価値の低いものとして扱うような)、そういうものの見方のことであるが、そうしたものは科学の領域においてもそれほど珍しいものではない。
例えば、たくさんの生物の中で複雑構造の多細胞の(あるいは脊椎動物とか、哺乳類とか、人間といった)生物を高等としたりとか。または、還元至上主義と言えるような立場に立ち、最も基本的な素粒子による構造の説明を、もっと上の段階の化学分子などによる構造説明よりも本質的なものと考えたりなど(あるいは、化学分子では素粒子レベルのことで説明しきれないこともあるだろうが、素粒子においては化学変化も全て説明できるだろうと推測したりとか)。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ  「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
ただし現代科学におけるスノビズム的思想はあくまでも、ある分野の科学者たち、あるいは個人の科学者限定というのが基本と思われる。
実は、古代ギリシャの哲学者たちのどの書物においても、見せかけの世界を価値の低いものと考えていた影響が強かったという訳ではなく、それは単に、後世に残るほど人気の高かったジャンルにおける傾向だったかもしれない。




