日本と中国のカラクリの起源
『日本書紀』には、第35代皇極天皇でもある第37代斉明天皇(594~661)の治世(655~661)。唐(中国。618~907)より帰化した智踰という僧が『指南車』を造ったという記述がある。彼はさらに8年後には、第38代天智天皇(626~672)にそれを献上したという。
 「歴代天皇」実在する神から、偉大なる人へ
「歴代天皇」実在する神から、偉大なる人へ
指南車は、人形が乗っている車であり、その走ってる方向に関係なく、人形が常に南を指差すという機械で、その仕組みには磁石が用いられていたという説もあるが、それはただの羅針盤であり、むしろ磁石を使っていなかったからこそ、このカラクリは優れていたという説もある。
ところで日本のカラクリ技術は中国からもたらされたものだとされている。
そもそも指南車の人形が常に南を指差すのは、中国皇帝の玉座が南に向かって据えられていたことに由来しているようである。
しかし中国におけるカラクリ技術の発明時期に関しては、よくわかっていない。沈約(Shen Yue。441~513)が編纂したとされる『宋書』によると、指南車はすでに紀元前1000年ぐらい、周(紀元前1046年頃~紀元前256年)の政治家であった周公旦(Zhōugōng Dàn)に造られているようだが、こういう周が起源の話というのはたいてい怪しい。
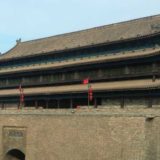 「周王朝」青銅器。漢字の広まり。春秋時代、戦国時代、後の記録
「周王朝」青銅器。漢字の広まり。春秋時代、戦国時代、後の記録
張衡。水力渾天儀、候風地動儀。木雕
後漢(25年~220年)の頃の科学者、発明家、文人であった張衡(Zhang Heng。78~139)は、117年頃に、水力で自動回転する『渾天儀』を造ったとされる。渾天儀は、天球上の天体の動きを模した機器で、ギリシアで似たような『アーミラリ天球儀(Armillary sphere)』というものが独自に開発されている。しかし水力式は、おそらく彼のが初めてであると思われる。
132年には、『候風地動儀(地動儀)』というものを造った。これは8方向に龍が付けられた巨大な瓶みたいなもののすぐ周囲に、8つの龍の口を見上げているようなカエルが置かれているというようなもの。ある方向のどこかで地震が起こった場合、その方向の龍の口の中にある球が、下のカエルの口のなかに落ちて、大きな音を発するというもの。つまり震源地の方向がわかる地震感知装置、(やはり世界最古と思われる)地震計である。
他にも、よりシンプルな、球面上に諸々の恒星の天球上位置を示した(つまり天球を、完全に模型外側から眺めるタイプの)模型である『天球儀(celestial globe)』。
通常は、いくつかの容器に水が流入(流出)するようになっていて、その水面の高さの変化で時間を確認できる『水時計(漏刻)』。
自力で飛ぶことができたという木製の鳥『木雕』。
それに指南車も造ったとされている。
 「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
張衡は多才な人だった。
普通、小説などのように、なんらかの形式や規則にとらわれずに書かれる文章を『散文(prose)』。一方で俳句とか連句のように、主に聴覚に一定の形象を感知させうる一定規則(韻律)に則って書かれる文章を『韻文(verse)』と言うが、古代中国には、『賦(fù)』という韻文形式があった。張衡は賦の名手で、彼が書いた、漢王朝の東西の首都(西京長安、東京洛陽)を比較して、漢王朝の繁栄を称賛しながら、人々の生活を描写したという『二京賦(Èr jīng)』は大傑作として知られる。また『七言詩』という形式の最初のものであるという、『四愁詩(Sì chóu shī)』なる作品も書いた。
「算網論」なる彼の数学書では、すでに円周率πが「3.16」くらいと算出されているとも。
天文の分野では、『渾天説』を深く研究、2500個の星々を記録し、月と太陽の関係も研究した。
渾天説とは、古代中国における宇宙構造論の1つで、大きな天は鳥の卵殻のように球形、小さな地は卵黄のように内部にあり、天地共々気に支えられて、その状態に定まっている。さらに、天の表裏の面には水があり、天地は水にのって運行。天の半分は地上を覆われ、半分は地下を囲んでいるが、そのために天球の二十八宿(28のエリア)の半分は常に隠れて見えない。天の両端の両極(南極北極)は、回転する天の軸となっている。というようなもの。
『霊憲』、『霊憲図』、『渾天儀図注』などの天文学書を書いていて、霊憲では、月は球形で、その輝きは太陽の反射光している。『月食(lunar eclipse)』の原理も理解していたとされる。
渾天説以外に、古代中国で主流だったらしい宇宙論として、『蓋天説』や『宣夜説』というのもある。
蓋天説は、天は広げられた円形の傘のようなドーム状であるという世界観。地は方形(正方形)の碁盤とか、ひっくり返した皿みたい形など意見が割れやすい。天は「蓋笠」、地が「覆槃」と書かれることもある。天は左に回転しており、右へ向かおうとする太陽や月も、回転に引っぱる形で左回転させているとも。蓋天説の大きな特徴として、天と地の平行状態があり、夜の暗闇は太陽が観察者から一時的に離れるためとされる。
宣夜説は、天にはそもそも果てなく、形質などというものもないとする世界観。天体というのは、形ある天にくっついているとかではなく、虚空の中に各自浮かんでいる。天体ごとに動く速度が異なるのは、それらを縛る繋がりなど存在しないため。
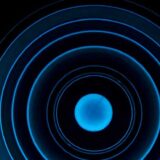 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
馬鈞。指南車はすでに古い伝説だったか
三国の時代、魏(220~265)の科学者、発明家であった馬鈞にもまた、指南車を造った記録がある。
 「魏呉蜀の成立」曹操、孫権、劉備。三国時代を始めた人達の戦い
「魏呉蜀の成立」曹操、孫権、劉備。三国時代を始めた人達の戦い
若い頃は遊んでばかりだったが、彼は博士に任じられる。そして生活費を稼ぐために機織り機の改良をしたことで、本人も自覚していなかったというその才能を周囲に知られることとなった。
興味深いことに、彼の時代には指南車というのは、古書にその記述があるだけのやや伝説的な機械だったらしい。ある時に馬鈞は、政治家の高堂隆、武将の秦朗らと、いろいろ議論をして、指南車の話題も出た。高堂隆と秦朗は「指南車は実在しなかったろう」と主張したが、馬鈞は「実在した。今の人は工夫をしてみようともしないな」と反対意見を返した。後に馬鈞は、本当に指南車を造る訳である。
馬鈞の発明として、他にも、田畑に水を引くための(当時の水準としてはかなり強力な)足踏み式水車などが知られるが、彼は既存の機械を改良するのも得意だった。
例えば、魏の皇帝(明帝曹叡に機械人形を献上する者があったが、帝はその人形の動きに不満があった。そこで改造を命じられた馬鈞は、それが水力を原動力に、さらに動くようにする。その機械人形は『水転百戯』とも呼ばれた。
中大兄皇子の漏刻
智踰が日本に指南車をもたらしたのは658年くらいとされるが、その2年後の660年には、中大兄皇子(天智天皇)が、漏刻を造っているという。
一般的な漏刻は、階段上に何段も積んだ器をそれぞれ『サイフォン(siphon)』で繋ぎ、最後の器に浮かべている浮きの高さの変化などで時刻を表示する装置だったとされる。
サイフォンとは、隙間のない管を利用し、液体をある地点から別の地点まで運ぶのだが、特に途中で、出発地点より高い地点を通るようになっている装置。
これは、『サイフォンの原理』というものを利用している。
例えば真空(内部空間が、通常大気圧より低い圧力の気体で満たされている状態)の管を(大気に対してむき出しの)水のような液体に浸けた場合、菅が通じていない部分の水面にかかっている通常大気圧と、菅内との圧力差のために、水は菅内を上昇する。どのくらい高く上昇するのかは、大気と菅内との圧力差、液体の密度などにより変わるが、その上昇する高さが、 水の入ってる桶などと水面の高さの差より大きいのなら、それを利用して水を外に運ぶことができる。サイフォンの原理とはそのようなものである。
もっとシンプルな砂時計のような構造は、あまり好まれなかったとされるが、例えばそのようなものだと、上の器の水量変化のために、水が垂れるスピードが変わりやすく、時計としての信頼性が低かったからである。
とにかく、天智天皇となった中大兄皇子は、漏刻を目安にして、鐘や太鼓を打ち、人々に時を知らせたという。
平安時代後期に、どのようなハイテク時計があったか
平安時代の算博士(数学者)である三善為康(1049~1139)が編纂したとされる文書集的な書である『朝野群載』には、日覚という僧が造った漏刻に関する記述が見られる。それは、時刻に合わせて12種類の鳥獣の像が現れ、装置の中央に立っている童子人形が音を発して時刻を示すというものだったらしい。また、季節による時間の長短も表示されていた(表現されていた?)という。
天智天皇の頃からずいぶん進歩したと考えるべきか、それとも、時間を考えると、やはり当時の技術の変化は遅いものだと思うべきか。
和時計。不定時法の機械時計
1549年に鹿児島に上陸したイエズス会宣教師のフランシスコ・ザビエル(Francisco de Xavier。1506~1552)は、後奈良天皇(1497~1557)に会おうと京都にも向かうが、戦乱の世にあって、それは簡単なことではなかった。
結局天皇に会うことはちゃんと彼は、周防国(山口県東南部分)山口で宣教し、そこの大名である大内義隆(1507~1551)にも謁見。様々な贈り物の中でも、特に座の人々を驚かせたのが、ヨーロッパ製の機械時計であった。
戦国時代の頃の日本は、時間に関して、季節によってそれぞれの時間が変化する昼と夜というものを明確に分けて、それぞれを6等分する『十二刻』という考え方が普通であった。西洋の機械時計は、普通1日を24時間、でないとしても、太陽が出てる時間に関係なく、決まったいくつかの時間に分ける『定時方式』が前提となっていた。しかし時計があまり出回っていない時代には、十二刻のような不定時法は、感覚的に時間を共有しやすいために便利であった。政府が時計を頼りに、定期的に金を鳴らしていたとされる平安京においては、定時法が基本であったとも。
いつから造られるようになったのか
大内義隆は、家臣であった陶隆房(晴賢。1521~1555)の謀反(大寧寺の変)により自害に追い込まれる。そして大内氏の滅亡と共に、彼がザビエルからもらった機械時計も失われてしまった。
しかし機械時計の日本への流入はその後も続き、後に、日本独自の『和時計』という、カラクリ時計の開発につながっていく。和時計は不定時法の時間を表示する機械時計であったが、定時法とも併用できるようなものも開発されるようになっていく。
西洋時計にしろ、和時計にしろ、機械式時計には、ある時間を音で知らせる機能がよく備わっていたから『自鳴鐘』とも呼ばれた。そもそも和時計というのは明治以降に使われるようになった呼び方のようで、江戸時代においては自鳴鐘の他、『自鳴盤』や『時辰儀』と呼ばれていたという。時計という言葉もけっこう古くからあったようだが、その漢字は「時計」の他、「土圭」、「斗景」、「斗鶏」、「図景」などが使われていたとされる。
1598年には、津田助左衛門という人が、徳川家康(1542~1616)が所有していた(朝鮮から献上されていたらしい)時計の修理を任された。助左衛門はそれを修理した後、同じものを造り、あるいは改造したものをさらに献上した。それは和時計であったという説があり、そうだとすると、その開発史は、その頃にすでに始まっていたということになる。
いかにして十二刻を刻んだのか
和時計の文字盤の針は基本的に1つだけで、 それは1日(24時間)ごとに一回転する。 文字盤は『十二支』と、それに対応しているような9から4までの数字の2ループ(987654987654)で、12等分されていた。つまり、1日の十二刻を表していた訳である。
和時計の多くは、錘によって駆動していたが、 初期の頃は柱にかける『掛け時計』、機構の下に台をつけている『櫓時計』や『台時計』が主流だったと考えられている。 それらの上部には『棒テンプ(foliot balance)』という天秤型の『調速機(Governor)』、つまり時計が機能する速度を調整する部分があった。棒テンプに掛かっている錘の位置を朝夜ごと、時期ごとに変えて、季節ごとに変わる昼の時間、夜の時間に対応した訳である。
棒テンプの錘切り替えによる調整は、最初の方は全て人手によっていた。しかしそのうちに、昼用のテンプと夜用のテンプが用意され、それらが自動的に切り替わるという二丁テンプ和時計が開発される。
また、棒テンプは使わず、文字盤の各数字を書いたプレート(各文字盤)を個々に独立させて、プレートの間隔を変化させることで不定時法を表現する『割駒式』の和時計も開発されたが、これも最初は手動だったものが、だんだんと自動になっていった。
他に、落下する錘に時針をつけた『尺時計』、ゼンマイ式の置時計である『枕時計』などもあった。
しかし実用的な和時計は基本的に高価なもので、所有者は大名などに限られていた。ただ、公共施設などに和時計が置かれることもあり、庶民がそれで時間を確かめれることもあったかもしれない。
もっとも普通に考えるなら、庶民にもたらされた和時計に関する知識は、ほぼ錦絵や文学を通じてだったろう。
 「江戸のカラクリ」人形浄瑠璃、飛行機械計画、玩具黒船の伝記
「江戸のカラクリ」人形浄瑠璃、飛行機械計画、玩具黒船の伝記
デウスエクスマキナ。機械仕掛けの神は夢か
アイスキュロス(Aischylos。紀元前525~紀元前456)、ソポクレス(Sophoklēs。紀元前497~紀元前406)と共に、古代ギリシア都市国家アテナイの三大悲劇詩人とされるエウリピデス(Euripídēs。紀元前480~紀元前406)は、『デウス・エクス・マキナ(deus ex machina。機械仕掛けの神)』という演出技法を好んだとされる。
伏線が複雑に入り組みすぎて回収しきれそうにないとか、どう考えても解決法などないような困難な局面に陥った劇において、絶対的な力を持つ存在(例えば神)が現れて、その全能によって全てを収束させ、終わらせるという手法。転じて、現在は、全能な存在などが出てこないでも、単に偶発的要因とかで複雑に広がった伏線などを一気に回収して物語を終わらせる方法自体が(たいてい悪いニュアンスで)デウスエクスマキナと呼ばれたりもする。
エウリピデスの劇においては、その最終段階、つまり神が現れる段階で、神に扮した役者(あるいは像)が舞台の上空にドラマチックに出現したとされる。デウス・エクス・マキナ(ἀπὸ μηχανῆς θεός。アポ・メーカネース・テオス。機械仕掛けの神)という名称は、 物語の展開よりも、劇での演出を由来としている。神はクレーンのような機械を用いて空中に維持されたそうである。
ヘロンの自動人形芝居
デウスエクスマキナは、機械仕掛けと呼ばれながらも、あくまでも舞台裏での人のコントロールが必要な仕掛けだったとされている。しかしエウリピデスよりもずっと後の人である、おそらく紀元1世紀か2世紀ぐらいのアレクサンドリアのヘロン(Hero of Alexandria)は、全てがマキナ(機械式)である自動人形劇を考案した。正確には、それを開始するために、最初は人がヒモを引っ張るのだが、それ以外は全マキナ(自動)。
ヘロン自身の著作から読み取れる彼の自動人形劇『ナウプリオス(Nauplius)』とは以下のような流れだったらしい。
まず第1シーン。十数人のアカイア人(ギリシア人)たちが船を修理し。進水させようと動く。
第2シーン。船が進水。
第3シーン。海を進む船、しかし海は荒れていく。時折、イルカが出没する。
第4シーン。暴風の中で、ノープリウスが偽りの烽火(狼煙)を上げる。
第5シーン。船は難破し、アイアス(ロクリス王オイレウスの子)はなんとか陸に逃れようとする。しかし女神アテナ(デウス・エクス・マキナ)が現れ、稲妻(雷音)を発生させ、アイアスは海に消える。
上記すべて自動装置により演出されるわけだが、その装置は、砂時計内を一定のペースで下降する錘を動力源とし、滑車とそれと連動する車輪のみで動作したそうである。雷の音などは、隠された打楽器にタイミングよく落ちるようにしていた金属ボールによって実現されていたようだ。
ヘロンのナウプリオスは、史上最初のカラクリ人形芝居の記録ともされる。
しかしこの自動人形という存在が、初期の頃から宗教や娯楽と結びついていたということは注目に値するだろうか。実用的な場では、生きた人間の奴隷たちの方がよっぽど役に立ったろうから、当然といえば当然のことなのかもしれないが。
アイオロスの球は、史上最初の蒸気機関か
ヘロンはカラクリ人形以外にも様々な発明をしていて、工学史上の重要人物である。
やはり初の蒸気機関と呼ばれることもある、『アイオロスの球(aeolipile。風の神の球)』などは特に有名。
先端(噴出口)が回転方向の逆に曲がっている、2つか複数の『ノズル(nozzle)』が付いている、回転可能球体か円柱の形の容器が、『ボイラー(boiler)』となる水容器と繋がっているというもの。
ノズルとは、流体が流れる方向を定めるため、つまり経路とするためのパイプ状部品。場合によっては流量、流速、圧力などの調整にも使われる。
ボイラーは、水を熱して蒸気を発生させる装置。
とにかく、水容器(ボイラー)を加熱してその内部に蒸気を発生させると、それが球体(あるいは円柱)容器、つまりアイオロスの球に流れ込み、さらにノズルから噴出する蒸気の勢いがロケット的な効果(反作用)を生み、球を回転させる。アイオロスの球とは、熱して回転させられる『タービン(turbine)』のようなもので、動作システム的には『チップジェット(Tip jet)』のような装置という訳である。
タービンとは、流体が有するエネルギーを、回転動力(回転エネルギー)に変換する機械のこと。
チップジェットは、主回転翼(メインローター)の各羽根(ブレード)ごとが噴射口を持っている、回転翼機構。
古代のオートメーションスペース
ヘロンが考案した、あるいは実現したか、実現しようとしたとされる機械仕掛けの話は、見事なオートメーションスペース(自動化された空間)を思わせる。
彼は祭壇に火をつけると、自動で開き、火を消したら閉じるという扉を、神殿の祭壇につけたという。それは火の点滅によって、密閉した器の空気が膨張、収縮し、それによって移動した水が扉の軸のバランスを変えて、回転させるという仕組みであったとされる。
上部の細長い穴(スロット)にコインを投入すると、一定量の聖水が分配されるという装置もあった。投入されたコインが、レバーの取り付けられた皿に落ちて、傾きすぎて皿からコインがさらに落ちるまでの一定時間、レバーがバルブを開き、水を流出させるという仕掛けだったようだ。これはいわば、てこの原理を利用した古代の自動販売機である。
他にも、風車と繋げて自動演奏をするようにしたオルガン。サイフォンの原理を応用した消火ポンプなど、夢の玩具のようでもある発明が多く知られている。
アレクサンドリア・ムセイオンの最初の人
ヘロンは、紀元前3世紀ぐらいの人とされるクテシビオス(Κτησίβιος ὁ Ἀλεξανδρεύς)の著作に影響を受けていたとされる。2人は師弟関係であったという説もあるが、年代的にはおかしい。
現存する記録のみを頼りにして考える場合、アイオロスの球、つまり史上初の蒸気タービンを考案したのは、このクテシビオスの可能性も高いようだ。
クテシビオスは、気体力学の父と称されるほど、空気に関して深く研究した人で、圧縮空気によるポンプや『空気砲』を考案したともされる。
彼はまた、エジプト、アレクサンドリアにおいて、設立されたという学術機関『ムセイオン(Μουσείον。Mouseion)』の、最初の館長ともされる。
サイフォン式の水時計は、このクテシビオスが発明したという説がある。
アラビア世界の水力カラクリ時計
ヘロンのオートメーションの夢は、後に、ビザンツやイスラムの技術者たちに受けつがれ、発展し、ヨーロッパにおいてルネサンスが起こった時に、時計技術と結びつくことで、近世以降の自動人形(オートマタ)に繋がっていった。とされる。
機械装置の工夫に関する知識の書
6世紀くらい。
パレスチナ出身のプロコピオス(Procopios)という歴史家は、都市ガザにて、無名の技師が造ったカラクリ時計のことを記録している。
市場に設計されていたという、その大きな時計堂の屋根にはメデューサの首の像がついていて、その下には、12枚ずつの扉が上下2列に並んでいる。上の扉群は夜の時刻を知らせるもので、夜間の時刻ごとに左から右へと扉が1枚ずつ開き、ランプがついていく。下の扉群は昼間の時間を知らせるもので、やはり左から右へ、扉の上のワシが翼を広げると共にその扉は開き、英雄ヘラクレスの像が現れ、有名な12の試練(功業)を、各時間ごとに演じる。さらに各時間ごとに、一番下にあるヘラクレス像がシンバルを鳴らしたり、その下僕たちの人形が、時間に合わせた仕草を見せたりもする。
この時計の原理は、はっきり記憶に残ってはいないが、基本は水力を原動力としていて(つまり水時計の応用で)、歯車などは扱っていなかったと考えられている。
そしてもっと後、アラビアの科学者、発明家のアル=ジャザリー(Al-Jazarī。1136~1206)は、『機械装置の工夫に関する知識の書(Kitāb fī Ma’rifat al-Ḥiyal al-Handasiyya)』という書を書いたが、その中で、噴水や自動人形と共に記述されている水時計は、明らかに、ガザのヘラクレス時計の流れを汲んでいるという。
その屋根は、黄道十二宮をアーチ構造に描いていて、太陽と月を象っている2つの円盤が、季節に応じた各十二宮のすぐ下を動いていく。さらにアーチ構造の下には、2列に並んでいるそれぞれ12の扉があり、上の扉群は時間ごとに開いて中の人形が姿を見せ、下の扉群は時間ごとに回転して色を変えて三日月を表示する。さらに時間ごとに、扉群の下の壁についたタカの像が、さらに下の壺に玉を落として音を立てる。6時9時12時の時には、一番下の人形たちがラッパやシンバルなどの楽器を奏でもする。
 「アラビア科学の誕生」天文学、物理光学、医学、イスラム世界に継承されたもの
「アラビア科学の誕生」天文学、物理光学、医学、イスラム世界に継承されたもの
ジャイルンの水時計
時計職人の息子のリドワン(Ridwan ibn al-Sa’ati。~1230)は、ジャザリーと同時代くらいの人だが、その父親が制作し、彼自身が修理したらしいカラクリ時計の設計図を後世に残した。
12、3世紀くらいに、シリアの辺りを支配していた『ザンギー朝(Zengid Dynasty)』の第2代君主であるヌールッディーン・マフムード(Nūr al-Dīn Maḥmūd b. Senkī。1118~1174)の命を受けて、リドワンの父であるムハンマド(Muḥammad)は、『ダマスカスのウマイヤドモスク(Umayyad Mosque in Damascus)』の入り口である『ジャイルン門(Jayrūn Gate)』に時計を造った。
『ジャイルンの水時計(Jayrun Water Clock)』と呼ばれているように、この時計もまた水力を利用していて、歯車は使っていないとされる。
リドワン自身が書いたとされる『時計の構造とその使用について(Ktab ‘Amal al-sa’at wa-l-amal biha。On the Construction of Clocks and their Use)』という論文によると、「文字盤の幅は約4.23メートル、高さ2.78メートルの大きさで、木材で構成されている。画面には一列のドアがあり、その両端にはハヤブサの姿。日中、小さな三日月がドアの前を一定の速度で動き、1時間ごとにドアが回転させて異なる色を示す、ハヤブサは前かがみになり、小さな塊をシンバルにぶつけ、定位置に戻る。ドアの上では、黄道十二宮の円が一定の速度で回転。それらの上の12個の円形の穴の1つずつが、1時間ごとに照らされる。時計はアルキメデス(Archimedes。紀元前287~紀元前212)の水機械により操作され、その動きは滑車とロープによって作動機構に伝達される」
歯車機構はいつからあったか
いかなる自動装置であっても、連鎖する動作ネットワークシステムの最初のスイッチ(動力源)は必ず必要である。もちろん複雑な機構、大きな動きを装置に実現させるためには、多くのスイッチか、または強力な動力が必要にもなる。装置の動作安定のためには、調速機のような自動制御装置も必須だ。
初期の頃の機械は、基本的にその動力源が、水力か風力、あるいは家畜の力だったとされているが、それらだとどうしても場所的に縛られる。そこで錘がよく動力源として使われたわけだが、やがてそれはゼンマイへと変わっていく。ただしそれは15世紀以降くらい、実用的なゼンマイの材料となる強靭で均質な金属を、かなり自由に作れるようになってから。
ちなみに江戸時代の日本においては、クジラのヒゲが、ゼンマイの材料として主流であったという。
そしてゼンマイ式の機械において、連動する機構の中でも、特に重要となる部品、要素は、やはり『歯車(gear)』
現存する最も古い歯車機構の装置は、有名な『アンティキティラ島の機械(Mechanismós ton Antikythíron)』とされるが、これは歴史記録的に、オーパーツ扱いされるほどのレベルで複雑な機構。天体運行を計算するために使われていたと考えられる歯車式計算機らしいこの機械は、紀元前2世紀ぐらいのギリシャ製だとされているが、 それ以降の1000年ほど、機械工学の歴史はミッシングリング状態である。
歯車が当時なかった訳ではない。アリストテレス(Aristotelēs。紀元前384~紀元前322)の『機械学(Μηχανικά)』などに、歯車についてとされる記述もある。また、ヘロンやアルキメデスも『ウォームギヤ(worm drive)』、つまりネジ歯車と、普通の円状歯車を組み合わせた機構を記録しているようだ。
しかし特に注目すべきは、紀元前一世紀ぐらいのローマの建築家、ウィトルウィウス(Marcus Vitruvius Pollio)が書いたとされる『建築について(De architectura)』に記述されている、水車を利用した歯車装置であろう。
歯車と組み合わせ、運動方向を変換したりして、より複雑な機構を構成するのに役立つ『カム(cam)』や『クランク(crank)』といった機械部品も15世紀ぐらいに登場したものとされているが、むしろこれらの登場がそこまで遅れた理由に関しては謎とも言われる。
カムは、様々な形が、任意の機械部品に接触することで、その動きに影響を与える機構。システム動作の高速化に役立つとされている。
クランクは、ピストンなどによる直線往復運動などを、連結している『クランク軸(アーム)』などを介して、ギアの回転などに変換、あるいはその逆を行なう機構。これは特に機械全体の扱いやすさなどを変えやすい。



