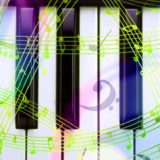戦火の時代に生まれた大オペラ作曲家
1806年。
ナポレオン1世ことナポレオン・ボナパルト(1769~1821)により、1806年8月に、神聖ローマ帝国は解体された。
そして同年末に、ザクセンは公国(貴族の領地)から王国へと格上げとなる。
後にドイツの一部となる、そのザクセンのライプツィヒに、ヴィルヘルム・リヒャルト・ワーグナー(1813~1883)は生まれた。
1813年5月22日のこと。
 「ドイツの成立過程」フランク王国、神聖ローマ帝国、叙任権闘争。文明開化
「ドイツの成立過程」フランク王国、神聖ローマ帝国、叙任権闘争。文明開化
時々ヴァーグナーとも書かれる彼の生まれた時期は、フランスの第一執政期、第一帝政期と呼ばれている時期(1799~1815)のナポレオン戦争と呼ばれる一連の戦火の最中だった。
リヒャルトの母であるヨハンナ・ロジーネ・ワーグナー(1774~1848)は、家の窓越しに、馬に乗って走るナポレオンその人を見たとも伝えられている。
二人の父。カール・フリードリヒとルートヴィヒ・ガイヤー
リヒャルトの父とされるカール・フリードリヒ・ワーグナー(1770~1813)は警察書記であった。
フランス軍に占領されたライプツィヒにおいて、フランス語に通じていた彼は忙しく、過労もあってか、流行っていたチフスに感染し、妻と幼いリヒャルトを残して世を去った。
ヨハンナは夫の死の翌年には、夫の親友でもあった俳優のルートヴィヒ・ハインリヒ・クリスチャン・ガイヤー(1779~1821)と結婚している。
ガイヤーの活動拠点の関係から、彼が生きてる間は、ワーグナー一家はドレスデンに暮らした。
またヨハンナとガイヤーは、カールの生前から通じていて、実はリヒャルトの父はガイヤーの方という説もある。
真の父がカールとルートヴィヒのどちらであったかという謎は、リヒャルト本人含め、普通に議論されてたようだが、結局ヨハンナも亡くなって以降、完全に確信を持てた者はいなかったようだ。
作品のキャラクターへの自己投影
1848年から制作をはじめ、1874年にようやく完成した四部作の壮大な「オペラ(歌劇)」である、『ニーベルングの指環(Der Ring des Nibelungen)』。
序夜(第一部)『ラインの黄金(Das Rheingold)』。
第1日(第二部)『ワルキューレ(Die Walküre)』。
第2日(第三部)『ジークフリート(Siegfried)』。
第3日(第四部)『神々の黄昏(Götterdämmerung)』。
この内の第三部ジークフリートの主人公は、自分の真の父親を知らないで、義父に育てられた。
そんなふうに、ワーグナーの作品には、作者自身の自己の投影といえるような要素が現れていることが多かったとされている。
生前のワーグナーと親交のあったフリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ(1844~1900)が述べたとされるように、ワーグナーは、「生まれから定められているような、芸術の神童」ではなかった。
そういう存在になれるような環境に、生まれついたわけではなかった。
しかし彼は芸術の道を歩き、そこに自分の生きる場を常に見いだしていた。
彼にとって自作品への自己投影は、現実で壊れないための逃げの手段であったと言われることもある。
芸術家志望の少年時代
ディレッタントな義父
ワーグナーの批判者は、時に彼のことを『ディレッタント(dilettante。好事家)』と呼んだ。
ようするに、プロの芸術家というよりも、趣味の人だと。
彼自身はともかく、彼の義父に関しては、まさにディレッタントという呼び名は合っていた。
ルートヴィヒ・ガイヤーは、舞台俳優という本業の傍らで、絵を描き、劇作(脚本作り)を試みたりもしていたとされる。
そのルートヴィヒは、リヒャルトを画家にしようと考えていたらしい。
しかし、晩年には、彼が向いているのは音楽かもしれないと考えるようにもなっていたという。
いずれにしても、母を通して伝えられた、「お前を特別な存在にしてやりたかった」というような、ルートヴィヒの臨終の言葉は、少年ワーグナーに強烈な影響を残したと考えられている。
憧れの音楽家ウェーバー
ワーグナー一家は、そもそも音楽好きな演劇一家だった。
リヒャルトの兄アルベルトは歌手。
四人の姉の内の一人も歌手になり、二人は俳優となったという。
そういう一家であるから、ワーグナー家には、舞台関係者の知人友人も多かったようだ。
そんな一家の交友関係の中に、作曲家のカール・マリア・フリードリヒ・エルンスト・フォン・ウェーバー(1786~1826)がいた。
はっきりと音楽の道を志す以前から、リヒャルトはウェーバーに憧れを抱いていたとされる。
そしてリヒャルトが9歳の頃。
「君も音楽家を目指すかね?」と問われ、リヒャルトは何も返さず、母が代わりにこう答えた。
「この子に音楽の才能があるとは思えません」
不良少年と音楽の先生
実際の才能の有無はともかく、リヒャルトが幼少の頃に、正規の音楽教育を受けなかったのは事実である。
作曲家として知られるようになってからも、彼がまともに弾けた楽器はピアノぐらいだったという話もある。
ただし、ガイヤーが亡くなって数年経って、ライプツィヒに帰ってきてから、リヒャルトは、音楽学生として大学に通う機会があった。
そしてトーマス教会の「カントル(Cantor。教会音楽家)」のクリスティアン・テオドール・ヴァインリッヒ(1780-1842)から作曲の指南を受けたりもした。
また、それ以前からも、よく独学で作曲の勉強をしていたという。
大学生のリヒャルトは、不良な少年であったともされている。
ヴァインリッヒも、最初は彼を門前払いしたりもしたようだが、後にその才能に気づき、彼の母に「彼のような才能あるお子様を育てることができたことが、私にとって何よりもの報酬でした」などと感謝を伝えたりもしたそうだ。
偉大なアマチュア学者の叔父
リヒャルトの叔父にあたる、フリードリヒの弟アードルフ(1774~1835)は一家内の変わり者で、騒がしい演劇よりも文学を好んだ。
アマチュア学者でもあったアードルフは、ソポクレース(紀元前497~紀元前406)や、ベンジャミン・フランクリン(1705~1790)の翻訳などもしていた。
また、シラー(1759~1805)やフィヒテ(1762~1814)やティーク(1773~1853)などとも交友があったとされる。
アードルフは少年ワーグナーに、言葉で紡がれる芸術を伝授した。
ワーグナーは、アードルフにこそもっとも強い影響を受けたと自分でも考え、生涯にわたり彼を、最も自慢できる身内として尊敬し続けたという。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン
少年ワーグナーは、兄姉たちのような俳優でなく、詩人を目指そうと決めた。
しかし、15歳くらいの頃に、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770~1827)が、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749~1832)の戯曲「エグモント」のために書いた曲に強い感銘を受けて、自分が目指す表現には音楽が必要なのだと悟る。
また、ベートーヴェンの「交響曲第九」は、ワーグナーの生涯において、 最も重要な音楽の手本であった。
 「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」簡単に悲劇な運命と向き合う
「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」簡単に悲劇な運命と向き合う
ヴィルヘルミーネ・シュレーダー・デフリーント
俳優の演技へに関しては、身内以上に、ヴィルヘルミーネ・シュレーダー・デフリーント(1804~1860)に強い影響を受けたようである。
ベートーヴェンの音楽との出会いから間もない頃。
そのベートーヴェンの唯一のオペラ「フィデリオ」に出演する彼女を見たリヒャルトは、すぐさまファンレターを書いたそうだ。
それには、「いつか僕が芸術の世界で人気になれた時は、そういう存在になろうと僕に決心させた存在が、あなたであったことを思い出してください」というように書かれていたされる。
後にデフリーントは、ワーグナーのオペラにも出演するようになる。
おそらく彼女は、ワーグナーが初めて出会った、理想の「ディーヴァ(diva。歌姫)」だった。
またワーグナーが、デフリーントが出演するフィデリオを見たというのは、嘘か妄想であるという説もある。
実際には、ワーグナーが初めて彼女を見た舞台は、ヴィンチェンツォ・ベッリーニ(1801~1835)のオペラ「カプレーティとモンテッキ(I Capuleti e i Montecchi)」だったとも言われているが、この辺りははっきりしない。
歌劇王としての軌跡
初期のオペラ作品
ワーグナーは、環境が悪かったとも言われるが、しかし決して恵まれていないわけではなかったろう。
芸術家として表舞台に出るにあたり、家族のコネは明らかに役にたった。
1833年。
長兄アルベルトを頼りヴュルツブルクに来た彼は、そこで、市立劇場の「合唱指揮者(Choir conductor)」としての職を得た。
しかし、ただの安定した暮らしには、彼は満足しないで、ラウフシュテット、マクデブルク、ケーニヒスベルク、リガと、遍歴を重ねていく。
青年ワーグナーは、各地の劇場で音楽監督をしたが、まったく人気は出なかった。
マクデブルクでは、自作の「恋愛禁制(Das Liebesverbot)」を二度上演したが、二度目の公演の時の客はわずか3人だったという。
恋愛禁制は、未完成に終わった初のオペラ「婚礼(Die Hochzeit)」と、初めて完全に完成させたオペラ「妖精(Die Feen)」に続く、三作目とされている。
最初の論文と、恋する借金王
ワーグナーは生前に、多くの論文を書いたが、遍歴時代の1834年に、ハインリッヒ・ラウベ(1806~1884)主宰の「エレガントな世界のための新聞(zeitung für die elegante welt)」に寄稿した「ドイツのオペラ」は、その最初のものだという。
女優のウィルヘルミーヌ・ミンナ・プラーナー(1809~1866)と恋仲になったのも、遍歴途中であったとされる。
ミンナとはもともと、行きずりの(一時だけの)恋のつもりであったともされていて、結局結婚まですることになる二人の間には、対立も多かったようだ。
また、当然売れないために借金も増えていったし、売れる作品を作ってもあまり意味はなかった。
当時のドイツは、作曲家が印税をもらえるのは劇場での初演だけで、ある曲が人気になっているにもかかわらず、その作曲家は借金取りに追われるということは珍しい話でもなかったとされる。
浪費癖なども合わせて、ワーグナーは特に有名だから、借金王などと呼ばれることもある。
さまよえるオランダ人の体験
1839年に、ワーグナー夫妻は、イギリスを経由した海の道から、フランスのパリへとやってきた。
その公開途中、嵐に見舞われて、オペラ「さまよえるオランダ人(Der fliegende Holländer」のヒントになったともされる。
パリは、ワーグナーにとっては憧れの都市だったようだが、台本の形体に厳しかったり、作曲家自身は初演に指揮をしてはならないといった、そこでの制約は窮屈であった。
ドイツでは叶わなかった一攫千金などもなく、ワーグナーは失望し、パリに憎しみさえ抱くようになっていったという。
パリは後年のワーグナーにとっては、不幸の象徴であった。
リエンティの成功
1842年に、ワーグナーは、今度はドレスデンへと移住してきた。
パリでは拒否された「リエンツィ、最後の護民官』(Rienzi, der letzte der Tribunen)」や、「さまよえるオランダ人」がドレスデン宮廷歌劇場で上演されることになったからだ。
後に公演されたオランダ人こそ、それほど好評でなかったが、先のリエンツィは、大好評であり、ワーグナーは、ようやくオペラ作曲家として、その名を広く知られるようになった。
また、借金まみれの貧乏生活の中でも、(何度か逃げたりはしたが)夫を見捨てなかったミンナは、むしろ当人である夫以上に喜んだという。
三月革命への参加と、反ユダヤの始まり
ワーグナーのライフワークと称されることもある大作「ニーベルングの指環」の構想に、彼が取りかかり始めたのは1848年ともされる。
その頃に勃発した、三月革命(Märzrevolution)に積極的に参加した彼は、1849年には指名手配となり、スイスのチューリッヒに逃げてきた。
当時、スイスという国は、亡命者に寛容な国土地柄だったらしい。
ワーグナーのパトロンや、芸術家仲間の中にはユダヤ系の人もいたが、この頃、1950年くらいから、明らかに彼は反ユダヤ主義になっているという。
その根源には、彼の父親かもしれないルートヴィヒ・ガイヤーが、ユダヤ人かもしれないという事実があったという説がある。
つまり、ワーグナーにとっての反ユダヤは、ある種の自己嫌悪、同族嫌悪だったという説である。
 「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
ヴェーゼンドンク夫妻と隠れ家
パトロンとなり、隠れ家まで提供してくれることになるオットー・ヴェーゼンドンク(1819~1890)との1852年の出会いは、ワーグナーにとって幸運であった。
オットーの援助は1953年に始まり、隠れ家にワーグナーが暮らしだしたのは1857年から。
隠れ家時代にワーグナーは、オットーの妻マティルデ・ヴェーゼンドンク(1828~1902)と親密になり、男女関係を持っていたという説もある。
少なくとも、夫を追ってスイスへとやってきていたミンナは、マティルデとワーグナーの関係を浮気と見なしていた節があったようだ。
結局ミンナとは別居することになる。
1862年の恩赦によって、ザクセンの地をまた踏めるようになったワーグナーは、ドレスデンでミンナとも再会できたという話もあるが、二人が寄りを戻すことはなかった。
最大のパトロン、ルートヴィヒ2世
バイエルン王ルートヴィヒ2世(1845~1886)からの誘いは急で、彼はまさしく貧相に苦しむ芸術家の救世主となった。
若きバイエルン王は、当時ワーグナーの大ファンであり、即位するや、ワーグナーの借金もすべて肩代わりして、消してやった。
さらには年金を支給してやり、結果的には彼の生涯の最大のパトロンとなった。
しかし、王と芸術家のパートナーシップも、それほど強固なものとはならなかった。
ワーグナーはだんだんと調子にのったのか、政治にまで口出ししてくるようになる。
また彼が、彼自身の弟子のハンス・ギードー・フォン・ビューロー(1830~1894)の別居中の妻コジマ(1837~1930)と関係を深めていたことも、王にとってはあまり良い印象ではなかった。
また、ルートヴィヒの方も、自分を単なるパトロンではなく、芸術家との共同事業者のような関係と考えていたという。
そして、指輪のオペラの分割上映を強行した時、ワーグナーは凄まじい怒りを見せたという。
二度目の妻コジマの日記
ワーグナーの最初の妻ミンナは、献身的に夫を支えたにも関わらず、非情な芸術家に裏切られた、哀れな淑女などと称されることもある。
これはワーグナーが、コジマをよく前妻と比べて持ち上げるような発言をしたことが多く知られているからなようだ。
例えば、「子供のできない結婚は茶番だ」とか(コジマはワーグナーの子を身ごもったが、ミンナとの間には子供が生まれなかった)。
「よい結婚の条件は知性が対等であること」とか(知性というか、少なくとも作品に関しては、コジマの方がワーグナーに理解を示していた)。
そんなふうなことを言ってたという。
結局コジマはワーグナーの二番目の妻となり、その最期まで付き合っていくことになる。
また、コジマが書いていた日記は、ワーグナーという人物に関する貴重な記録資料ともなっているという。
とりあえずコジマが、ワーグナーの最後の拠り所であったのはほぼ間違いない。
臨終のワーグナーは、コジマに対して告げたという。
「私たちのような仲は、5000年に1度くらいのものだろう」