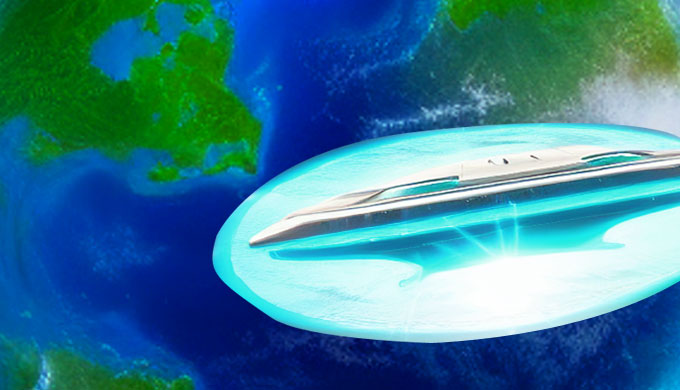サイバーパンク的世界観への影響
荒廃系未来、異常現実SFの大家とも言えそうなフィリップ・K・ディック(Philip Kindred Dick。1928~1982)は、今でも、SF作家の間では影響力強い人と思う。特にサイバーパンクと呼ばれるジャンルとか。
サイバーパンクSFと言えば、コンピューターテクノロジーがコントロールする現実とか、電脳空間のリアリティ性などを描いたジャンルというイメージもある。しかし個人的には、科学が発達する前はそう考えにくかったような、例えば精神とか、空想世界とかいうようなものを、現実的な枠組みで理解したり、解釈しようとしたりする創作の試みというような印象がある。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
そういう面的には、ディック作品の多くで、ガジェットとしてある(コンピューターとリンクさせたりした上での直接的なものだけでなく、例えばドラッグによる影響など)神経系のコントロールシステムや、超能力(サイ能力)のような精神の物理的利用などは、彼が考えていた世界のシステムとして「あっておかしくないようなもの」だったのかもしれない。
 「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか  「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
ディックの作品の中でも、おそらく最もタイトルが有名なものでないだろうか。
タイトルからは哲学的な感じを思わせるが、作中ではあまり(アンドロイドに限らず)特定の哲学的テーマについて直接的な議論とかはあまりない。ただ作中のキャラのやりとりから、読者は様々な生命という哲学テーマについて考えさせられるかもしれない。
そういう構成になっている。そしてそういう構成はディック作品ではよくあるが、これはかなり顕著に思う。
科学技術は進歩してるのに、荒廃した世界
世界観は、人間たちの幾度の争いの末に、もうほとんど自然というものが地球から失われてしまった未来。この世界観は、1982年にこの作品が映画化されると、SF小説をあまり読まない層にも衝撃を与えたらしい。
そういう、「未来でしっかり科学技術も進歩してるのに、妙に荒廃してしまってる雰囲気の世界観」というのは、当時は珍しかったそうだ。
この作品の世界観は、単に病んでいるというより、何か、アンドロイドでなく、人らしい何かを、誰もが忘れてるような雰囲気。
だからこそアンドロイドは、人になれない。
むしろ人らしさを、人すら忘れているような。
そんな世界が構築されている。
ディックの短編でよくある作風を、そのまま長編にした感じ
主人公のリック・デッカードは、地球に不法に移住してきた指名手配中のアンドロイドを、賞金目当てに破棄する仕事をしている。
彼の作中での主な目的は金である。
誰しもが、動物を飼っているのだが、彼の飼っているのは電気羊、つまりはアンドロイドの羊で、それは恥ずかしい事とされる。
それで彼は、本物の羊を買いたい、というわけで金がほしい。
ディック作品は基本、キャラに青臭さというか、そういうリアルな未熟さが感じれて、多くの人にとって共感しやすい面がある。
この作品に関しては、本物の動物が社会的ステータス。何が真実かもわかってない者たちの真相の探りあい。欠落した者とアンドロイドとの交流。それに独特な印象の宗教と、ディックが好んでたと思われるようなガジェットが、”わかりやすく”溢れているから、この作家の入門書としてもよいかもしれない。
自らを生命体と認識するアンドロイド
この話に出てくるアンドロイドの中には、自分をまるでアンドロイドと自覚出来ていないような描写をされる者がいる。
人間に近く作られているのに、人間についていくつかを理解出来ない者も出てくる。
主人公のリック・デッカードは、そんなアンドロイドたちを追う内に、そして殺す度に、だんだんと彼ら(それら?)についての考えを変化させていく。
ただ、最新のアンドロイドである”ネクサス6型”についての、「二兆個の構成素子を備え、脳活動の組合せの選択範囲は一千万種類におよんでいる。この型式の脳を備えたアンドロイドは、わずか〇・四五秒で、十四種の基本的反応態度のいずれかに入ることができる」というような説明などからして、この作品に登場するアンドロイドは、「もし」と「それなら」などを組み合わせた、いわゆるエキスパートシステム系と思われるから、それも考慮すると、感情についての問題などはより興味深くなるかもしれない。
 「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
アンドロイドは人間と同じように考えられるのか?
自ら知能を持ち、自己を持ち、そして死を恐れるアンドロイドたち。
ディックはこの小説を通し、読者に明らかに問う。
本当に人間は人間であるのかを。(もしかしたら)あなたは間違いなく人間であるのかも。
 「オートポイエーシスな生命システム」物質の私たち。時空間の中の私たち
「オートポイエーシスな生命システム」物質の私たち。時空間の中の私たち
アンドロイドを認識するテスト
しかし、人間社会に紛れ込んだ、人間そっくりなアンドロイドを見分けるためにどうするか。
もちろん、そのための特別なテストがある。作中でリックが使うのは、フォークト=カンプフ感情移入度測定法というもの。単純な知能テストではアンドロイドは非常に優れた成績も出せるが、感情を測定すると、たちまちボロが出てしまうと。
この作品では、感情というものが、知能から生じるものというよりも、人間という種に特有の性質というように扱われている。人間以外にも、それなりに知能の高い生物はいるが、感情を持っている、感情移入ができるのは人間だけと。そしてアンドロイドも、そうした感情移入がどうしてもできないと。
ただ、感情移入能力は共同体、社会を安定させるための要素であり、一方で肉食の生物には、この感情移入が(獲物に対して同情してしまったりと)障壁になることがあるというような考察もある。
そこで感情移入能力は、雑食の生物か、草食の生物にしかまず芽生えないのではないかとか。
実際に食用動物の殺されるところを見た人が、その動物の肉を食べられなくなるというような話は、現実で聞くこともある。しかし、1つ重要と思われることは、おそらく感情移入という現象が、まず相手の立場になって考えることができるような、そういう知的能力が必要ということだろう。そうでないはずがないだろう(普通に考えて)。
だから、それ(感情移入)に知能が必要不可欠な要素ということはほぼ間違いないのでなかろうか。だが相手の立場になって考えることができて、しかし感情移入がどうしてもできないというような、それはどういうことだろう。
もちろんアンドロイドが、完全に機械的なエキスパートシステムなら、相手の立場になって考えることが実際にはできないことは当たり前(?)であるが。ディックもそんな風に考えてたのだろうか。
あるいはより重要な問題は、アンドロイドに感情が芽生えるかどうかよりも、人間がそれに感情移入してしまうこと。つまり、偽りの感情を本物の感情と勘違いしてしまう可能性なのかもしれない。
少なくともリックは、アンドロイドに感情移入してしまった、というような描写が結構はっきりあると思う。
 「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か
「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か
バカ、欠陥品
作中で特殊者、スペシャルと呼ばれる存在であるイシドアは、プリスという変わり者な女性と関わる内に、自分にもちゃんと価値があるんだと認識し、物語が進む度に、自信を手にしていく。
特殊者というのはつまりバカの事。
低い知能。脳に欠陥を抱える人。現実の人間社会でもそういう人は「役立たず」とか「使えない」とか散々に言われる。
役立たずと、言われなくたって思われるだろう。この社会では。
イシドアはこの小説の物語に、絶対必要なキャラというわけではない。しかしディックは彼を使い、人間だけが持つはずの感情をいくつか描いている(個人的に映画版の大きな不満の1つは、彼の存在をカットしたこと)
「お願いだ。かたわにしないでやってくれ」
あるシーンで彼が放つこのセリフは、あまりにも考えさせられる。
それは同情だろうか? それは人間だからこそなのだろうか?
ディックは多分そう考えてたんだと思う。
アンドロイドは確かに(そういうふうに作れば)人間のような知能を持ち、自己を持ち、もしかしたら電気羊の夢だって見るだろう。
でも人間のように、他人との間には何も生じさせられない。
友達になっても、恋をしたって、おそらくは同じ気持ちを共有する事は出来ない。
その機構は人工的には作れない。
この小説の描きたかった事って、そういう事じゃないかなとも思う。
そういう主張。
 人はなぜ恋をするのか?「恋愛の心理学」
人はなぜ恋をするのか?「恋愛の心理学」
また、イシドアが独自に考えたのだと思われる「キップルの法則」、あるいは理論というのは、なかなか面白いかもしれない
「キップルってのは、ダイレクト・メールとか、からっぽのマッチ箱とか、ガムの包み紙とか、きのうの新聞とか、そういった役に立たないもののことさ。だれも見ていないと、キップルはどんどん子供を産みはじめる。たとえば、きみの部屋になにかキップルを置きっぱなしで寝てごらん、あしたの朝目がさめると、そいつが倍にもふえているよ。ほっとくと、ぐんぐん大きくなっていく」
高い城の男
ディックの作品の中でも特に高い評価をされがちな作品(理由が、プロットが破綻していないからとか、わりとものすごかったりもする)
この作品は、第二次世界対戦に、日本、ドイツの二大国家が勝利したif世界を描いている。
このような設定は、いわゆる歴史改変ものという、SFではわりとメジャーな小ジャンルであり、第二次対戦の勝敗逆転も、人気な設定。
ただ、この『高い城の男』という小説の個性的なところは、その日本とドイツに支配された世界において、さらにアメリカ、イギリスが勝利したという歴史改変小説、「イナゴ身重たく横たわる」が登場する事であろう。
なぜか流行っている易教という、変わったガジェット
この小説の世界では、どういうわけか易教(占術をテーマとした中国の古典)が大流行しており、各キャラは度々迷った時の答を易教に書かれた占いに頼る。
実はこの小説の作者であるディック自身、これを書いてた時期、易教にハマっていたらしい。物語終盤、メインキャラのひとりジュリアナがある選択を迫られた時、彼女がどういう選択をするのかを(作中のキャラが、とかではなく、作者当人が)占いで決めたのだという。
つまりこの小説は、まさに易教に導かれて書かれたものなの、とも言えよう。
これは大切な事なのでもう一度言っておいてよいと思う。「この小説は易教に導かれて書かれた」
この作中世界自体がどのようなものなのか。
「何が真実なのか」を考えたくもなるかもしれない。
日本人描写はステレオタイプ
ある意味、日本人は完全なステレオタイプで描かれる。
作中で、日本人はとにかく真似をするのが上手いと皮肉られる。易教も、しっかり中国由来だと作中でツッコまれている(なのでそこに関してはディックの勘違いではない)
ただし、日本人は紳士的に描きすぎてる感じを、日本人なら抱くと思う。まさに「勤勉で真面目な日本人たち」という、典型的なイメージのような感じ。
ifのifのif
大まかな話は、起こる前から失敗した花嫁略奪。計画はよかったかもしれないが、見事にから回る商売活劇などと、ありきたりなエピソードが多い。
ただこの小説の本領は、やはりSFらしい、作中キャラたちの議論であろう。
まさにifの中でのifの議論である。
日本とドイツが世界侵略を成し遂げた世界で、「どうすればアメリカやイギリスは、日本やドイツに勝てたのか」という議論が繰り広げられる。
現実の第二次対戦について知ってても、知ってなくても、その辺りは楽しみやすいと思う。
また、作中では、ユダヤ人は根絶やしにされているのが、世間の認識となっている。実際には、ひっそりと容姿などを変えて生き延びているという設定。
ただ実際に、枢軸側(日本とドイツ)が勝ってたとして、ユダヤ人全滅させられてただろうか?
なんにせよ、ifのifのifを想定する楽しさを、まさに小説の形で、表面化させたのが、この小説の素晴らしいとこであろう。
ただ、アフリカを熱心に開拓する呑気な日本に対し、ドイツは早くも太陽系惑星開拓を始めているという話が出てくるのだが、こうした宇宙開発関連は、ちょっと場違い設定感もあるか。
イナゴ身重たく横たわるの作者
タイトルにもなっているが、この高い城の男の描写は、正直微妙だった。
しかし、彼自身の人物設定はべつとして、エンタメ的な恋愛描写は、彼の意思なのか、ちょっとディックに聞いてみたい。
日本人には「イナゴ身重たく横たわる」は普通に人気という設定はよかったと思う。
流れよ我が涙、と警官は言った
管理、あるいは監視社会的な世界観は、ディックのお得意ぽいが、これはそのような管理システムに対して、ある日突然に透明になってしまった(つまりありゆる管理システムからデータが消えた。事実上、社会的に存在を消された)男を描く、少しミステリー色ある作品。
なのだが(作者本人もそう言っていたらしいように)総合的に見てみると、追われる身として逃げる中で、主人公と、出会った女性たちとの様々な関係を描く、恋愛小説的な印象がむしろ強いかもしれない。
ディックの書いたSFの中でも、SFさは薄いぽいので、人によっては逆にとっつきやすいと思う。
愛とは、生存本能に打ち勝つようなものか
確かに、「愛がテーマ」と考えていいくらいには、そういうものに関する議論がよくある。
例えば、愛は自身の生存本能に打ち勝つかもしれない。他者のための自分に繋がる(いわゆる利己的な遺伝子論などとは関係ないと思う)、というような話。
ただしそのこと(愛は自己保存本能を打ち負かすものかどうかの)自体より、「なぜ本能に逆らうことがよきことのように考えられるのか」という疑問が重要そうである。
ただ、女は語る。「保存本能が試みたことはけっして達成できない。愛を失えば、結局は死に屈服させられて終わるだろう」とか。
しかしもちろん、愛を知っている誰かが、いつまででも死なないとか、そういうことではない。自分が死んでも、愛するものを見守り続けられる。あるいはそういうふうな気でいられて、安心して死ねるというような。
そして主人公の反論。「でも彼らだって死ぬんだ」
 「利己的な遺伝子論」進化の要約、恋愛と浮気、生存機械の領域
「利己的な遺伝子論」進化の要約、恋愛と浮気、生存機械の領域
脳機能としての認識とパラレルワールド
結局SFとしてのこの話は、並行世界(パラレルワールド)、どこかで分岐した別の現実を描いた話な訳だ、注目すべきはやはり、別の世界へ迷い込んでしまった、その原因。
原因はある薬物の効果、ある知性体の背景プログラム、コンピューター的な脳と関連する、宇宙システムのバグかのような。
ようするに、脳の働き、機能として『時間保存(タイム・バインディング)』、あるいは「知覚と定位力の体系化」がある。その保存情報を脳が受け入れることで、認識というのもある。しかし、脳は、空間を保存できなければ、上手く機能しなくなることがある。
なぜ時間や空間の保存情報が、脳の機能を停止か、弱めてしまうのか。おそらくは「時間と呼ばれる前後関係が整えられるような形で、現実を固定させようという本能と関連がある」とか推測される。
 「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去  「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
空間の概念。「ある一定の単位の空間は、その他のすべての一定単位の空間を排除する」というもの。1つの存在の場には、1つのものしか存在できない。1つの存在の場とは、ある瞬間での存在の場も同じ。だからこそ、1つの時間で、同じ場に別の出来事は起きない。そういうことだろうか。
しかし脳はどう関係するか。認識されるある出来事は、脳の働きによって、つまりその働きによる空間の排他性のために、”起きた”と認識される。
そして重要なことは、空間は排他的なものではない。だからこそ、脳の機能の一部停止は、あらゆる空間ベクトル、すなわち、いくつものパラレルの空間が混同して認識される。ただし、結局のところ、脳の総合的な機能の限界として、何かを理解している時に、やはり一つを選んでいることになる。そこでパラレルの空間群から、最も身近なものが選ばれる。それが、以前と異なる宇宙の場合、結果的にパラレル宇宙に入り込むということになる。そう認識される。
 「ベクトル空間」基底、次元の定義。線形結合、従属、独立。n次元の写像
「ベクトル空間」基底、次元の定義。線形結合、従属、独立。n次元の写像
しかも、そうした時空変換の影響は、他人を巻き込むこともある。もし認識が宇宙を存在させているのだとして、例えば一緒に何かを見たりとか、共有する時に、何かネットワークがそこに生じてたりするためだろうか。
暗闇のスキャナー
ディックの他の作品でも、神経に、つまり認識とか理解される世界に影響を与える薬(ドラッグ)が度々出てくるが、この作品ではそれがメインな感じ。
この作について、ディック自身は、リスクの大きい薬を快楽目的や興味本位で使ったり、中毒になってしまったり、犯罪に利用されたりするような現実を批判する目的で書いたらしいが、実際は逆効果だったのではないか、とも言われている。
ただドラッグに批判的な小説といえば、内容的には確かにそうと思う。ここで描かれているのは、神経系に影響を与える薬がもたらす、幻想の世界観というよりも、そこにのめり込んだり、戻ることが難しくなってしまって、結果として個人や社会が破滅していく、そういう物語。
SF要素は「流れよ……」よりもさらに薄めと思う。徹底的に排除されているという感じではないが、必要最低限というような印象。
スクランブルスーツ。知覚機能に対する透明化
わかりやすいSF要素としては、覆面麻薬捜査官の『スクランブル・スーツ』なるものが出てくる。
例えば声紋(音声を波形、グラフとして表した場合の、その形状に定義される特徴)とか外見などを、かなり透明化、ようするに実際の物理的情報を隠してしまう、特別なスーツ。
スクランブル・スーツは、神経組織に影響のある脱抑制物質の実験をしていたS・A・パワーズという人の事故がきっかけで発明されたもの。
一応は、安全量を計算した上で、自らに注射した脱抑制性の成分。しかしそれにより、おそらく予想以上のレベルで体験してしまった、「毒々しい眼内閃光活動」、「現代抽象絵画と思われた映像がモンタージュされ、めまぐるしく……」というような。
そしてこの事故が、視覚による認識を狂わせるスーツというアイデアに繋がったとか。
小説ならではだろう、テーマに縛られていた感じもあるか。
スクランブル・スーツ自体の原理としては、接続された小型コンピュータのメモリ・バンクに蓄えられた、断片化された容姿データを外部(超薄膜)に投影する多面水晶レンズ。
ドラッグが狂わせる認識世界と合わせて考えると、物質世界に生きている中で、物理的現象としての神経系、認識能力を直接的に、あるいは間接的に変化させることの違い。直接的な変化がどのくらいに危険なのかとか、いろいろ考えやすい。
統合されている2つの意識。離された2つの意識
作中で重要となるのが、その出所も1つのミステリーになっている、『物質D』というドラッグ。
その影響、(作中で否定されているものの)中毒性などを調べるためと思われるテストと関連して、ジョセフ・E・ボーゲン(JosephE.Bogen,M.D。1926~2005)の実際の研究に関する話が出てくる。
その研究とは分裂脳(Split-brain)に関するもので、この作品においても、各脳半球、つまり右脳と左脳のそれぞれが精神を有している(本質的に誰もが二重、または多重人格?)というような解釈がされてるように思う。
そして、物質Dとはつまり、左脳半球と右脳半球の統合的環境を壊すようなもの、のようである。
また、脳機能の認識と、認識される世界観の実在性について、「流れよ……」の「脳機能の異常が歪ませる、大量のパラレルワールドの存在性」というようなアイデアに近いぽいが、別バージョンのような説もある。
あちらが、”認識宇宙論”というような印象に対して、こちらのは、宇宙そのものは(認識とも関係なく?)実体としてあって、その上で成り立っているシステムというような。
宇宙を幾何学的に理解した場合
世界をトポロジー(作中で「幾何学的物体か、その他の集合において、いかなる一対一対応の連続写像によっても変化しないような性質を研究する分野」と簡潔に説明されているもの)的に見る時、脳の両半球の統合性が失われた状態で認識される世界観は、どう表現されるか。
つまり「世界を表裏逆転させて見ている」
 「写像とはどういうものか」ベクトル、スカラー、線形、非線形の定義
「写像とはどういうものか」ベクトル、スカラー、線形、非線形の定義
この辺りの設定はかなりわかりにくいと思われるが、重要なことの1つは、「世界を本質的に幾何学的に考えてみる」ということかもしれない。
そこからこの話では、「ループする時間の永遠」というような説にも繋げられている。もし時間が地球のよいな、つまり球体みたいなものならまっすぐ進めばやかでたどり着く場所は1周回った同じ場所。
おそらくディックの、好みのモチーフの1つであったろう、キリストの伝説との関連付けもなかなか興味深い。「キリストの最初の到来と再来は、同じ出来事だったんだ。時間がエンドレステープになっていたから。みんなが再来を確信していたのも無理はない」と。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
ただし、なぜその時の誰もが、時間、時空間、宇宙の真実を、後の人々よりも理解できていたのだろうか。世界がループする時、折り返し地点はどこ(いつ)なのであろう? 仮にループの中で、ある程度科学が発展し、人々の知識が増えたところで、キリストの登場があって、そこから知識が失われる、という過程があるというような世界観だったのだとする。では人類以前の時代の痕跡はどういうふうに考えるべきだろうか(作中で、こういう疑問に関しては触れられていないが、SF的に素直に解釈するなら、例えばある時に時空が丸まって、球体になって、そこからは人類の時代がひたすらループしているというような感じかもしれない。そうすると神の創造とかの話も、あまり奇妙でないような形に解釈しやすいと思う)
生物と無生物の違い
この現実より(?)の世界観の作品においてディックは、単に生物を(その心とか精神とか呼ばれるようなものまで含めて)物質的に解釈する、あるいは解釈できる可能性を示しているだけでなく、「では生物は、無生物と比べて何が特別なのか」というような話にも少し踏み込んでいる感じがする。この辺は「アンドロイドは……」とも近いが、「活動は必ずしも生命の証拠ではない。クェーサーは活動する。瞑想する僧は無生物ではない」というように、単に機械と生物、人間の違いというより、もっと広い領域での境界線をどう決定すべきか、みたいな話。
タイタンのゲームプレイヤー
ディックの作品の中でも、個人的には特に世界観が興味深いと思う作品。
ディックの作品にはよく、楽しげなボードゲームのようなものが登場するが、これは、そうしたゲームが重要なガジェットとなっている。
タイタン(土星の衛星)の種族との星間戦争に敗れ、太陽系世界において、ずいぶん肩身が狭くなってしまった地球人たち。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
また無痛兵器による自爆というか、子供がほとんど生まれなくなってしまった世界。
そして、地球で土地を所有している者たちは、土地を賭けてのゲームを楽しんでばかり。
最終的には、ゲーム好きなタイタンの権力者たちに、地球のゲーマー(?)たちが、ゲームでの第2ラウンドを挑むことになる。というような話。
ゲームのルール
作中の〈ゲーム〉は、どんなゲームか。
完全にルールが説明されてるわけではないが、結構細かく描写されているところもあるので、大まかなルールは読み取れる。
基本は、スゴロク(というか人生ゲーム)みたいなものなのだと思う。お互いのターンでカードを引き、そのカードに書かれた数字分、自分のコマを進める。そしてコマのたどり着いたマスに書かれたアクションを実行する(例えば、お金をいくつ儲けたとか、損失したとか)。ただし、カードの数は対戦相手には見せる必要がなく、嘘の数字分コマを進めることもできる。だが数字が嘘だと思ったなら、それを相手は指摘(ようするにダウト)できる。もちろんその場合、嘘を見破られたもの、あるいは嘘でないのに指摘してしまった者には、ゲーム内罰が与えられる。
冷静に考えなくても、こんな単純なアナログゲームが未来の世界で人気というのは、時代を感じさせるかもしれない。もっとも、シンプルイザベストというやつかもしれないが。
タイタン人が恐れるもの
炭素型生物の地球人に対して、タイタン人は、ケイ素(シリコン)型とされる。つまり代謝速度が遅く、酸素のかわりにメタンを代謝触媒にしているという、SFでは結構一般的な宇宙種。しかし、そうした物理タイプの違いは、物語上はわりとどうでもいいような設定。
また、両性具有。(これはたいていの宇宙生物種の出てくるSFで言えることだろうが)性別をどう考えるべきか、ちょっと興味深い。
 「特殊領域の生物」高熱低温の極限環境、右利き分子、現実内の仮想
「特殊領域の生物」高熱低温の極限環境、右利き分子、現実内の仮想
作中では、インチキを交えたゲームも描かれるものの、そうでない純粋なゲームにおいて重要なものは運であって、そしてゲームが強い、つまり運の強い者が(可能性が低くても子供を産めるかもしれないから)、好戦的なタイタン人にとっては脅威というのも、ゲームと絡めた、いい設定と思う。
超能力者を相手に、どうやってゲームで勝つか
他のディック作品でも、人間の精神能力、超能力(サイ能力)への関心は明らかだが、そうした特殊能力もまた、この話で重要なガジェット。
それが一番かはわからないが、ディックとしてもこの話における重要なアイデアだったと思う。つまりサイ能力者が〈ゲーム〉にどう影響を与えるか。
特に作中では、ブラフ(はったり)が重要なゲームにおいて、心を読むことができたり、未来の可能性を覗き見れる相手、それどころか引いたカードの数字をいつでも好きに変更できるような能力を有する相手にどう立ち向かうか。というのが、大問題として提示される。
 超能力の種類研究。一覧と考察「超感覚的知覚とサイコキネシス」
超能力の種類研究。一覧と考察「超感覚的知覚とサイコキネシス」
もっとも、単純な答は、超能力者に対しては超能力者に対抗させる、というものだが。
フロリクス8から来た友人
個人的にはディックの長編で、最も好きな作。
テクノロジーによる調整のために生まれた〈新人〉と、超能力を使える〈異人〉が、知能の劣る〈旧人〉を支配している未来の地球社会。
この不平等をどうにか解決してくれる宇宙生物を求めて、太陽系を出て行ったプロヴォーニという英雄的な男が、実際に地球生物よりもはるかに優れたテクノロジーを有する生物を連れて戻ってくる。というだけの話なのだが、この連れてきた宇宙生物のお友達モルゴの設定が興味深く、そのキャラクターもいい感じで、プロヴォーニとのやりとりがとても楽しい。
ある意味キャラクター小説。
しかしそういうわけなので、これは純粋にストーリーを期待する人には微妙かもしれない。
賢き新人類と、謎の理論の効果
〈新人〉と〈旧人〉の設定は、人種主義や差別問題などに関して、いろいろ考えさせられるところあると思う。
この作中では、〈新人〉の発明した『中立論理学』と呼ばれる、〈旧人〉にはまず難解すぎて理解できない知的方法が出てきたりする。理解できないほど賢いものに支配される恐怖、というような、人間の枠組みを超えた生物種同士の関係性まで、踏み込めるかもしれない。
また、二〇一九年に、アルファ星のそばの宇宙空間で、人間より数千倍進化した有機生命体の死体。つまりは、他の生命体を作ることができるほどのテクノロジーを有すると思われる生命体が見つかって、神かもしれないと噂されてたりする。
知能が高い生物が優れている。より高度な生物、という考えが普通に見える。
しかし、もしそれが真実なら、確かにこの宇宙の中で、進んでいる者と遅れている者との出会いは、遅れている者にとって恐ろしいものでしかないのかも。
最強の宇宙スライム
フロリクス星系から、プロヴォーニが連れてきた宇宙生物モルゴは、不死であり、どんな物質分子でも飲み込んで成長の糧にできる、巨大な生きた液体(スライム)のような生物と思われる。
その種に決まったかたちはなく、歴史的には、他の物もしくは他の生物をまねて、生きてきた。他の生物を吸収して、必要なエネルギーを全て奪うと、後は残った抜け殻を捨てられる。そういう生物。
フロリクス生物は、基本的には支配者と定義できるような知的生物が存在する星には関わりを持とうとしない。しかし恒星間ドライブを開発できた(つまり宇宙探索が可能なテクノロジーを得た)文明には、通常は平和を与えるために関わる。
つまりは、フロリクス生物にも及ぶかもしれない、潜在的な危険性を持ってしまった文明に、先手を打つというような。
実用的な理由以外に、モルゴは、(どの惑星世界にもそういうものがあるという)地球に独特の文化品も報酬的なものとして求める。「真空掃除機、タイプライター、3Dヴィデオ、二十年耐用電池、コンピューター」とか。
昔は、フロリクス星系にも、地球にいるような動物とかが結構いた。という設定も合わせて考えるなら、この生物もまた、〈新人〉と同じように、テクノロジーがある種の生物を変えた結果なのでないかと、推測したくもなるが。