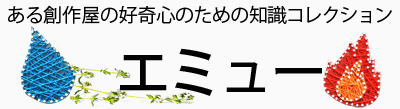眼はどんなふうに物を見ているか
レンズと絞り
頭骨の「眼窩」に収まっている『眼球(Eyeball)』、いわゆる目玉にはまず、焦点距離を調節、いわゆるピント合わせのための『水晶体(Lens。レンズ)』がついている。
さらに光量などを調節するための『瞳孔(pupil)』もつく。
瞳孔は、『虹彩(Iris)』という膜に囲まれ、この虹彩は瞳孔の開きを調節する。
カメラでいうと、虹彩は「絞り(Diaphragm)」である。
 「カメラの仕組み」歴史。進化。種類。初心者の為の基礎知識
「カメラの仕組み」歴史。進化。種類。初心者の為の基礎知識
人の目を普通に見た場合、瞳が虹彩で、瞳の中の黒目が瞳孔。
「視野(Field of view)」、つまりは目に見える範囲の光学的情報は、水晶体を介して、眼球の後ろの、層状を成している『網膜(retina)』という膜に与えられる。
明暗を感知する杆状体、色を認識する錐状体
網膜の層のひとつには、そこに入ってきた光(光子)に反応する 4種類の光受容器が存在する。
すなわち1種類の『杆状体(retinal rod)』と3種類の『錐状体(retinal cones)』である。
杆状体は、通常、人間のひとつの目に1億個以上存在するとされ、弱い光に反応し、明暗の判断に利用される。
一方で、明るく強い光に反応する錐状体は700万個ほどあり、種類ごとに違った光の波長に反応することで、色の感知に使われているとされる。
錐状体が種類ごとに反応する(あるいはしやすい)波長は、我々が認識するような色で定義するのなら、典型的な『三原色(three primary colors)』、つまり、青、赤、緑になるとされる。
例えば青色の波長に反応する錐状体が少ない人は、青色(あるいは青色と何かを混ぜた色)に対する『色盲(Color blindness)』になるのだという。
実のところ、我々のほとんどは、極端に言えば、三原色の波長以外全ての色に対する色盲である。
そして誰であれ、薄暗い場所では、錐状体があまり反応しないために、色を認識しにくくなる。
視覚情報が最初に処理されるのは網膜であるようだから、網膜は実質的に脳の一部であるとする意見もある。
網膜は、脳の他の部分に比べると研究もしやすいとされているので、おそらく最初に完全理解される脳の部分になるという推測もある。
基本的には錐状体は、我々が明るい所で物を見る時。
杆状体は、暗いところで物を見る時に、特に使われるとされる。
錐状体は主に「中心窩(central fossa)」、 つまり眼底(眼球の眼窩内部の方)のほぼ中央に集中的に存在している。
一方で杆状体は、目の端の方に多くあるという。
そういうわけで、我々は明るいところで物をはっきり見ようとする場合はそれを凝視しようとし、暗いところではどちらかというと目の端に映る物体がよく見えるのだとされる。
意識とは何か
人間という存在を、我々はどういうふうに考えているだろうか。
我々が人型というような形をした多細胞生物。
言葉を喋り、生化学的な原理に頼らずとも、定義と論理的思考でコミュニケーションできる生物。
つまり、 物事を自分たちの言葉で定義して、それを理解し、教え合うことができる、この、それぞれという意識こそ人間だと、我々はよく考えるのでなかろうか。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
では人間というのを、 単なる物質的な原理だけで説明することは可能だろうか。
思考、意識、心が大きな問題であるが、これはおそらく単に、大量のニューロン(神経細胞)の相互作用による結果だと考える者も、今はけっこう多い。
単純に自分の頭を吹っ飛ばしたらと想定してみよう。
そこに自分の意識が残っているだろうか。
残っていないと思える人はおそらく、意識とかいうのを単に物質的な産物として考えている。
もしかしたら我々の意識は、ニューロンの相互作用に影響を与えたり、多少コントロールすらできるのかもしれない(それが我々が言うような自由意思というものの正体なのかもしれない)。
しかし、意識はニューロンの相互作用が作りだしたもの。
そういうことがありうるだろうか。
ニューロンは何をしているのか
生物の体のあちこちは様々な変換器の機能を備えている。
光や音や圧力など様々な物理化学的効果を電磁気的信号に変換し、それを情報として神経系(脳)に伝えている。
 「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈
「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈
光や音や圧力などは外界からの情報であるが、我々を構成する細胞のいくらかは内部状態に反応する。
例えば血液の成分が少々異常な状態となっているとか。
 「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
一般的な多細胞生物は、基本的には、外界をモニターする細胞よりも、内部をモニターする細胞の方が多いと考えられている。
体を構成する細胞というのは基本的に受信機で、その受信機で捉えた情報を処理して扱っているのが神経系。
つまりニューロンというわけである。
還元主義と地球スケール
ところで20世紀というのは、物理学の世紀と呼ばれた。
21世紀になった今日でも、科学のあらゆる分野で物理学というのは幅を利かせている。
そして20世紀以降の物理学はずっと、物事の構成要素を理解すれば、それが構成する物事自体も理解できるはず、というように考える『還元主義(Reductionism)』がブーム状態である。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
神経系(というより人間という存在)が、完全に物質的なだけのシステムなのだとして、それも還元主義で説明するのは可能だろうか。
このような疑問は、(素粒子物理学者が時々例にするような)原子(あるいは素粒子)の集団の振る舞いや相互作用のみで竜巻を説明できるか、という疑問に近いだろう。
 「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
そもそも還元主義というのは、最初の要素が存在することを前提としている。
そうでないと、例えば、脳を説明する場合、まず神経細胞同士の多くの相互作用を知り、さらに神経細胞を構成する分子の動きを知り、さらにその分子を構成する陽子、中性子、電子などの作用を知り、さらに……。
というような感じで、無限の思考に陥ってしまう。
 「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か  「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
ただ最小のものがあるにせよないにせよ、生物の脳の働きのような、地球上のスケールの現象に関してだけなら、実質停止してよい段階があると考える向きが普通である。
まずここで言う生物とは安定した環境で生きている生物のことである。
宇宙の中で生物というのはおそらく結構繊細でちょっとした変化に耐えきれない。
極端な話、 超巨大隕石とか見たいな強大な圧力がかかって地球がぶっ壊れたら我々は生きられない。
生物の脳の動きを、地球上のスケールの現象としてのみ考えるのは、かなり理にかなっている。
原子の内部には、プラス電荷を持った重い原子核があり、その周囲をマイナス電荷を持った電子の雲が取り巻いている。
そして原子の化学的性質は、基本的には原子核の電荷によって決定される。
我らの地球環境では、原子核の質量や電荷が変化することなど基本的にほぼないから、その内部構造を考慮する必要はあまり無いと考えられる。
重要なのは核の持つ電荷のみである。
 「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係  「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道
「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道
ただ放射性崩壊など、核の変換に関係する現象が地球の自然界に存在しないわけではない。
それでも神経系というシステムが、放射性崩壊を重要なこととして利用しているような兆候は、これまでぜんぜん確認されていないので、普通はあまり気にすることではないと考えられている。
要素の総和以上の現象
通常、分子と呼ばれるものは、複数の原子が特定の形を成すようにくっつきあった状態のものである。
そのようなくっつき状態を実現している力は、電磁気学的なものと考えられているが、 それらがなぜくっついているのかは今はどうでもいいことである。
重要なことは、たいてい分子は、それを構成する原子1個1個が持っている力、というより影響力の総和以上の影響力を有していること。
あるいは原子1個1個が持っていた以上の情報力を有しているということ。
おそらく還元主義が世界の全てを説明できるか否かというような議論は、ある要素の組み合わせ、相互作用によって発生する総和以上の現象を、実際に試してみないで推測できるものなのかどうか、という議論に近い。
要素が集合した場合に、その要素の総和以上の影響力を発揮するというのは、まず間違いなく確かな事実であろう。
ある1個の物質を考えてほしい。
それ1個だけなら、そこに存在する情報力はその空間をどれだけ占めているかという程度のものと考えられる。
ところが、近くにもう1つ物質を置いたとしたらどうなるだろうか。
各物質が占有している空間量だけではない。
物質と物質の引き合っている力、それによって乱れる周囲の様々な 変数がそこにいくらでも発生しうるようになる。
組み合わせの数が増えれば増えるほど、情報はさらに膨大になっていくだろうことを想像することもたやすい。
そして、かなり明らかなことであろうが、適当な人の神経細胞のひとつを取り出して確認してみたとする。
その神経細胞に意識というものが宿っていないことは、かなり確実なことであろう。
それどころか我々が心と呼ぶものの要素たる、どの機能も備えていないはずである。
記憶しないし、想像しないし、理解をしない。
見もしないし、聞きもしないし、読みもしない。
生物の定義は、細胞か、細胞の集合体であることとされるが、別に意識を持っていることではない。
思考することではない。
実のところ、単細胞生物の世界でも、我々が狩りと呼ぶようなものとか、交尾(遺伝子情報の交換、やりとり)と呼ぶようなものですら存在するとされるが、それらを意識的に行っていると考えるのは、少なくとも今の我々の知見的には少々厳しい。
そしてもしも神経細胞1個が、確かに意識の要素を備えていないとするなら、 少なくとも心(意識)は、複数の神経細胞の相互作用があって初めて生成されるものだということになろう。
これは当たり前のようだが、かなり重要な事実とされることが多い。
意識というのは、神経細胞の相互作用が生み出した、その総和以上の何かなのであると考えられるから。
我々はどの段階で、本当に認識しているのか
意識が相互作用によって新たに生成されたものであるとして、 それでも、それを神経細胞の相互作用だけで説明できるのだろうか。
まず、我々は神経系というシステムを理解するために使っているのか。
それとも神経系が我々に理解させているのか。
もしもこの意識というものが完全に物質的、つまり神経系が生成したものだというのなら、まず間違いなく後者と言っていいだろう。
仮に我々の意識が神経系の動きに何らかの動きを与えるのだとしても、その神経系に影響を与える我々の意識というものを作ったのは結局神経系なのだから、やはり還元主義的に考えるのが妥当なのかもしれない。
我々という意識は、それを意識なのだとと理解させられているAIみたいなものと考えられるかもしれない。
 「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで  「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
意識は消滅と再生を繰り返すか
どういう原理にしろ、脳が意識を作っていると考えるならば、逆に脳が意識を作っていない時、それはそこに存在していないことになる。
我々は少なくとも感覚的には意識を失い、その後にばっちり目覚める時がある。
夢を見ている時、そこに意識があるのだとしても、寝ている時、常に夢を見ているわけではないと、今は考えられている。
意識がない時、本当に意識がないというのなら、目覚めた時に、脳は再び意識を作っているということになる。
つまり脳は、一時的に意識を消し、そしておそらくは保存しておいたその意識を、後で再現することができる。
意識を神秘的なものだと解釈できるなら、単に我々が意識がないような感覚に陥ってる時それは意識が眠っていると考えたりすることで問題はなくなるかもしれない。
我々自身が意識を感知するためには、例えば記憶が必要なのだという可能性はある。
つまり我々の意識というもの自体は常にそこに維持され続けているのであるが、記憶のスイッチを切られたりして、そのことを覚えていられない場合がある、というふうに考えることもできるかもしれない。
仮に誰か友達が死んだとする。
その友達とまったく同じ体、神経系を持つ、究極的な意味でのクローンを誰かが作ったとする。
あなたは、そのクローンの友達を以前の友達とまったく同じ存在なのだと考えることができるだろうか。
もしも意識というものを我々が失うたびにら本当に失っているとするのなら、おそらく今の意識と、前日のあなたの意識は、友達とクローンくらいには違うかもしれない。
 「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
もし、意識こそ人間だとするなら、例えば永遠の愛を誓い合った二人が一緒にいれるのは、次に眠る時までの間だけなのかもしれない。
目覚めた時そこにあるのは、そっくりな他人の意識。
また、本当に意識が、神経系が作った産物であるというなら、それはつまり物質的に作れるということだから、死んだ人を本当の意味で蘇らせることも可能なのだと考えられる。
 「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験
「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験
機能は局在化しているか
脳の一部に損傷を受けた人は、特定の事が出来なくなったりする。
例えば長期的な記憶ができなくなったり、言葉を上手く喋れなくなったりとかだ。
こういうことは、脳の中での機能が局在化しているからだろうか。
つまり我々の正常な精神というものを成り立たせるための様々な機能は、脳の特定の部分ごとが担っているものなのだろうか。
脳はどのくらいコンピューター的か
脳システム(神経系)はよく、コンピューターにたとえられるが、本当にそれほど近いものだろうか。
どちらも物理的に、電気的信号に変換された様々な情報を処理しているということは同じである。
概念的に言えば、記号や数を操作しているという部分が同じというわけだ。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
神経系をコンピューターに例える場合一つ一つのニューロンはコンピューターの素子にあたることになろう。
しかし、現在の平均的なコンピューターに比べ、神経系の各素子(ニューロン)の発火速度(毎秒発火する頻度)は明らかに遅いとされている。
高性能な脳の秘密は、 その驚異的な並列計算能力にあるという説がある。
各システムにおいて、通常我々は 両方の目から得た情報を100万本もの『軸索(axon)』、すなわち神経細胞の反応を伝達する突起を介して脳に伝える。
そして脳は、意識として、見た情報を認識させるような、内部ネットワークを働かせる。
人工知能はドラゴンを認識できるか
我々が当たり前にできることのいくつかをコンピューターは行うことができない、ということは確かである。
だからこそ、人間と同じような頭脳を目指しているAI研究は苦労してきた。
 「機械学習とは何か」 簡単に人工知能は作れないのか。学ぶ事の意味
「機械学習とは何か」 簡単に人工知能は作れないのか。学ぶ事の意味  「ディープラーニング。深層学習」 画像認識する仕組み、原理
「ディープラーニング。深層学習」 画像認識する仕組み、原理
例えばコンピューターは、赤色が何かを認識することはできても、どの生物がドラゴンなのかを認識することはできないとされている。
 「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
モニターに写っているドラゴンを、我々はそういうふうに認識できるが、それは実際には波長が異なる光を発する、ただの点の集まりである。
そしてコンピューターにとってはそれはそういう点の集まり以上の何物でもないのである。
それとまったく同じ点の並びや、近い並びのものをドラゴンだと認識することはできるだろう。
ただ、例えば色を大きく変えただけでも、それはもうドラゴンでなくなるかもしれない。
まだ知らないメカニズムの可能性
コンピューター素子に比べて、ニューロンは可変的で、やや信頼性が低いとされている。
あるニューロンの集団が演算処理をしている最中に、新たに与えられた信号が、演算中のニューロンの性質を変化させることもありうるとされる。
我々が何事もコンピューターほど正確に計算できない理由はここにあるかもしれない。
しかしだからこそ我々は、コンピューターにはできない理解を可能にしているのだろうか?
脳はどの部分もCPUとして扱えるとか、ハードウェアとソフトウェアが真の形で一体化しているような構成のコンピューターとか、いろいろ意味がわかりにくいような説もある。
たとえ話で使ったりするのはともかく、本当の意味でコンピューターと同じ類のものと考えるのは、コンピューターが意識を持つようになるまで慎重であった方がいいのだろうか。
少なくとも心というものを作る上では、我々がまだ知らないメカニズムの方が重要なのかもしれない。
道具もシステムの二次作用なのか
コンピューターは、そのひとつを構成するあらゆる要素が、すべて総合的な存在として、汎用的な動作を行うことができる。
対して脳は、各部分は相互作用しつつも、それぞれの部分が多少異なった特別な仕事をするよう、発達しているという説もある。
だが、意識的に喋ることができなくなってしまった人と、音を鳴らせなくなったコンピューターでは、実際的に何がどのくらい違うのだろうか。
少なくとも脳が自己修復プログラムを要しているのはかなり確かなことのようである。
神経系に関して、あるひとつの機能の部位を失っても、他の部位がその働きを補うことは明らかにあるからだ。
単純には、例えば目が見えなくなってしまった場合でも、我々はその状況に慣れることができなくはない。
しかし、仮に目が見えなくなってしまって、それでも普通に生活できるように杖を開発した人がいたとする。
この場合、その人が意識的に考えて発明した、その杖という道具も神経系システムの二次的作用と言えるだろうか?
神経系は本当に非線形か
数学的には、ある入力をして、必ずそれに対応した決まった出力がされるものを『線形』。
入力に対して 出力されるものが必ずしも決まっていないことを『非線形』という。
 「写像とはどういうものか」ベクトル、スカラー、線形、非線形の定義
「写像とはどういうものか」ベクトル、スカラー、線形、非線形の定義
一般に神経系の入出力システムは完全に非線形。
コンピューターはおそらく線形であるとされる。
同じ何かを見ても、神経系は時と場合によって、あっさり別の答えを出すことがある。
一方コンピューターが出力するものというのは、そこにかなり複雑なプロセスがいくらあろうと、入力された時点で決まっている。
真にランダムに出力するためのプログラムというものは、現在は知られていないともされる。
そこにあるのは擬似的なランダムだけ。
だが擬似的な非線形は、まだ線形なのであろうか。
そもそも神経系は普通に非線形なのであろうか。
3人の健常者たちにリンゴを見せたとして、3人のうちの2人はそれをリンゴというのに、1人は(大真面目に)ドラゴンと言ったりはしないと考えられる。
現実に気づく場合
我々の脳は、量子コンピューターよりは電子コンピューターに近いのかもしれない。
だがそれが、我々が知っているような電子コンピュータじゃないことだけは確かといえよう。
 「量子コンピュータとは何か」仕組み、宇宙の原理、実用化したらどうなるか
「量子コンピュータとは何か」仕組み、宇宙の原理、実用化したらどうなるか
コンピューターはそもそも本当にドラゴンを認識できないだろうか。
これがドラゴンだという点の集合パターンすべてを記憶しているコンピューターならば、実質的にはドラゴンを認識できないだろうか。
我々と違って、そのコンピューターの趣向は究極的に一貫していると考えられる。
我々が(例えばドラゴンだと考えていたものを、単にでかいトカゲと考えるようになったり)思想とかを変えたりすることがあるのは、神経系の構成や、時にはニューロンの性質が変化するからではないのだろうか。
つまり、ある程度一定の法則に従って、我々の神経系は変化するが、その二次的な副作用として、基準やら信念とかみたいなものも、意識的に変化する。
また、例えば、緑色という概念を持っていない人の神経系は、 おそらくコンピューターに例えるなら緑色という色のデータがないコンピューターということになろう。
緑を知らない人が緑を見た場合、とりあえず人は、(例えば青とか)緑に近いと思われる色を想定できる。
コンピューターにそういう考えはできないだろうか。
これは青っぽいから青に違いないと我々は発想している。
実際には波長が近いものだから、そうだろうと発想しているのかもしれない、
そしてそれならコンピューターにもできることかもしれない。
視覚システムの重大な謎
我々が自分の目で物を見る仕組みは、カメラの原理に似ているとされている。
水晶体というレンズで取り込んだ光に、網膜の光受容器が反応し、 それが情報として脳に送られ、脳がその情報を処理することで、我々は物を見る(と自分で認識する)。
上記のような『視覚システム(vision system)』は、かなり明らかで、真実に近い説明だろうと一般的には考えられている。
だが大きな問題がひとつ。
この視覚システムも、ニューロンの相互作用の結果にすぎないと考える。
すると結局のところ、その相互作用が意識というものをどうやって生み出しているのかが謎なのだから、我々が意識的に見ることができているということも、かなり説明できない。
このことは、我々がそうだと考える視覚のメカニズムが、間違っているか、あるいは単純化しすぎているがゆえの問題なのだとされている。
仮に魂とかみたいな、物質的なものではない神秘的な要素を想定するのだとしても、その神秘的な要素というものがどういうものなのか、おそらく誰もわかってないから、結局謎も同然。
我々はまぶしい光を見ることができるか
そもそも認識という現象がどの段階で起こっているのかも謎である。
我々はあまりに眩しい光を目がキャッチした時に、眩しいと思うだろう。
光量が多すぎて、受容機が一気に反応しすぎた(あるいは損傷を受けた)ために、処理が混乱したりしたのだろうと考えるのは容易い。
我々がその時に眩しいと認識しているのは、単に刺激の解釈なのだろうか。
それとも眩しすぎる光を見たのだろうか。
視覚に関する損傷の謎
なぜ見えていると思うのか
『アントン症候群(Anton-Babinski syndrome)』というのは、常識的にちょっとありえなさそうなことなので、ヒステリーだと勘違いされる場合もあるとされる神経障害である。
これは簡単に言うと、見えていないものを見えていると認識する症状。
つまり視覚を失ってるにも関わらず、それをまったく自然と信じないという症状である。
例えばアントン症候群にかかった患者は、(ネクタイなどしていない)医者に、「私はどのようなネクタイをしていますか?」と尋ねられると、水色のネクタイをしています、などと平然という。
アントン症候群は、脳の視覚システムに関係する部分とともに、見えていないものを見えていないと認めるための領域がダメージを負っているのだろうと推測される。
普通に健康体の人でも、声を聞いた人や、あるいはその人に関する話だけ聞いた人とかが、どういう人か勝手に想像する場合があるだろう。
アントン症候群の人が何かを勝手に想像するのは、そういう類のことなのではないか、と考える人もいる。
もしかしたら自分の勝手な想像と現実とを区別するための領域も欠けているのかもしれない。
我々が普通に勝手な想像をしてしまうことはまず間違いない事実である。
後ろ姿だけ見えている人がいるとしよう。
そいつが振り向いた時にのっぺらぼうだったらびっくりするだろう。
それこそまさに、後ろ姿を見ただけで我々がそこには顔があるのだと勝手に想像してしまっているからこその驚きなのではなかろうか。
なぜ見えていないと思うのか
『盲視(Blindsight)』は、アントン症候群の逆みたいな現象である。
つまり患者は、ある程度物体を指差したり、区別したりもできるのに、その物質を見えていることを否定する。
この現象においては、多くの場合、患者の損傷は脳の片側だけであり、患者は視野の半分だけ盲目状態になっている。
しかし患者は視野の半分は見えないと自分で感じつつも、光が点灯する場所を指差すことができたり、簡単な形を識別できる患者もいるのだという。
この現象は「盲点(blind spot)」に当たる部分、つまり、光受容器がない部分に光を放っても、患者は反応することがないことから、おそらくは、患者の光受容器がある程度無事なための現象だと思われる。
つまり光を受信してはいるのだが、それを意識のレベルにまで情報処理できていないという考え方である。
ようするに、何か健康な人に比べて、特異な視覚(第六感?)というのが発生しているわけではないということだろう。
ちなみに盲点は、網膜上の、視神経と繋がる部分の点らしい。