ネルソン・グッドマンの哲学入門書
哲学者ネルソン・グッドマン(Nelson Goodman。1906~1998)の『世界制作の方法(Ways of worldmaking)』は、 タイトル通りに世界を作るための手引書(マニュアル)というよりは、この世界の本質の考察のパターンである。
いくつかの事情から、この本におけるグッドマンの関心は、世界全体の始まり、あるいは必然的な始まりの探求というよりも、ある世界を他の世界から構築する際のプロセスとしている。
はじまりについては、『神学(theology)』に任せればいい、というように、少し諦めを感じる。
 「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか
「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか
世界というものに関する、いくつかの疑問
グッドマンは、世界(ワールド)というものについて、素朴な謎をいくつか提示する。
多くの世界があるというのは正確にはどういう意味でなのか。
本物の世界というものはありうるか、あるならば偽りの世界といかにして区別されうるか。
世界が現に存在しているというのなら、最も基本の『要素(element)』はあるのか。
最も基本の要素があるのだとして、それで世界はどのようにして作られているのか。
そして世界の制作時に、記号(言語、哲学)はどのような役割を果たすのか。
世界制作は『知識(knowledge)』や『認識(perception。recognition)』と関連しているか。
完全無欠で最終的な答えははるか先だとしても、それでもグッドマンは、世界を考える以上は、上記の問いを正面から取り上げる必要があるとする。
明らかにいくつもの世界が存在しているということ
世界が1つとしても、その中では対立する様々な側面がある。多くの世界があるのだとしても、それらをまとめて1つの世界と表現することもできる。だからこそ、なぜ多数の世界を強調するのか、ということがまず重要な点として取り上げられる。
万物の統一理論は、芸術的感性が生み出した世界まで含むか
しかし数多くの世界、つまり異なった世界のバージョンが存在しているのだとしても、それらのバージョンを全て還元できる、ただひとつの真理の法則があるというのなら、それこそ唯一の世界に関する唯一の真理とみなされるものであろうともされる。
例えばこの世界の全ての現象の説明が、ある物理学法則で説明できるとする。それはいわゆる『統一理論(Unified theory)』とか、『万物の理論(Theory of Everything。ToE)』と呼ばれるものだが、そういうものがあるなら、確かに他の見方によるいくつもの説明は全て、『便宜的(For convenience)』に部分のみを対象とした『偽物理論(Fake theory)』と定義可能かもしれない。
グッドマン自身は、少なくとも真理の法則(統一理論)に関して、最も有力とされる物理学すらも、候補として説得力のある考え方ではない。そもそも何らかの真理があって、全ての世界をそこに還元できるという考え方自体が、あまり説得力がないとしている。
わかりやすく、芸術的感性が生み出した、文学や絵画の世界(ヴィジョン)を、どのような物理法則に還元するというのか、という疑問を出してもいる。
しかし仮に、強引にでも還元させてみるとするなら、どういうふうになるのだろう。
芸術家の感性が、物理的な神経系というシステムから生み出されているものだとしよう。それを考えて作り出し、そこから何らかの『インスピレーション(inspiration)』を得たりするのも、全て神経系システムの仕事という解釈は、それほど難しくはないかもしれない。そうすると芸術というものが生み出す世界の中で、物理的現象として還元できないものは、むしろ何か残るだろうか。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
ある座標系から見た世界
「太陽は常に動いている」と「太陽は決して動かない」がどちらも真であるなら、それは別々の真理を持つ2つの世界があるのか、というような疑問もあったりする。
このような場合には、理性的な人はたいてい、「それはある座標系Aのもとでは、太陽は常に動いている。しかし別のある座標系Bからは動かないということなのでなかろうか」と、つまり同じ世界の中での別々の領域から解釈された内容にすぎないと捉えたい気持ちに傾きがちと、グッドマンは指摘する。
だが問題は、尋ね人が、「どんな座標系からも離れて、世界はどのようなものなのかを語ってほしい」と言ってきた場合に、どのように説明すればよいかであると。
 「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史 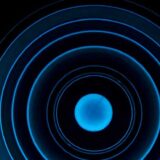 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
世界が記述されるなら、それが何であれ、我々は記述方法に縛られてしまう。我々の宇宙は方法からなり、それ自体が最初から存在していた世界ではないという。
しかし、本の全体を通して、絶対的に存在しているもの、という可能性は、あまり語られていないようにも思う。
 「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
科学者がある法則を発見する研究において
グッドマンは、真理は厳格な主人でなく、素直な召使いにすぎないでないかとも。
自分が、真理を探求していると考える科学者は、自分を欺いている。実際、科学者はたいてい、些細な真理になど関心を持たない、それより、そんなものはどこまでも「自分でも作り出せる」。
もう、誰かが物事を考えるたびに、新しい世界が誕生していると考えてもいいのじゃないかとも思えてくる。
しかしそうして、それまでなかったような新しい世界観が誕生する時というのは、世界の『進化論(theory of evolution)』における、『系統樹(phylogenetic tree)』の枝が増えた瞬間なのだろうか。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
グッドマンはさらに、いくつもの不規則な観察結果は、全体の構造や、わかりやすい一般化の参考として注目されることはあるが、たいてい最終的にそれは重要視されなくなる。真理を探そうとする者たちが関心があるのは、体系、単純さ、広い射程を探求することだとする。
科学者は、上記のような点で満足な結果が得られると、後は真理をそれに合うよう裁断(自分なりに断定)するのが普通。明らかとなった法則は、その科学者が発見したものだが、しかし見方を変えるとその人が制作した法則でもあると。
そして、ある物理法則が存在する時、それが適用される(例えば、現実(?)の世界よりもずっと単純化された)世界もそこにあるのだろうか。
科学論文における真理。創作作品における真理
つまり真理とは何か。
それは語られたものの中にのみ属しているだろうとも。文字通りの真理というのは、文字通りに語られたものの中にのみ。
だが、世界をつくるものは文字通りに語られたものだけではない。
それに、科学論文では文字通りの真理が最も重要とされるが、詩や小説においては、『隠喩的(metaphorical)』な真理、『寓意的(allegorical)』な真理とかがより重要になることもある、というような例も挙げられている。
『隠喩(metaphor)』も『寓意(Allegory)』も、『修辞技法(figure of speech。rhetorical device)』とされる。つまりは、文章の表現を豊かにするための技法である。
隠喩は、「のごとし」とか「のようだ」みたいな、一般的な例えの形式を使わずに、例えとなっているような表現。寓意は、直接的に表現しているものにかこつけ、別のことをほのめかしたりすること。
そして、知られているどんな体系化も究極的なものとは言えない。唯一の世界が存在しないように、様々な世界からなる唯一の世界も存在しない。
だが我々は世界を制作できる。
分割し、組み合わせ、強調し、順序付け、削除し、充填し、肉付けし、歪曲する自由もある。それらの自由に制約はあるか、世界制作には、何かの評価基準とかがあるのか。
引用。絵は音楽を含むことができるか
この本での世界政策という表現が、実際にどのようなものであれ、その行いは言葉で表現される。
そして、『引用(citation。quotation)』という行為を、つまりどのように考えるべきかについて、1章が使われている。
引用という言葉を使う時は、普通、言語的な引用を意味していることが多い。だが他の種類の引用というものがあるか。ある言葉が、別の言葉を引用できるように、ある絵が別の絵を、ある音楽が別の音楽を、身振りを引用することはできるだろうか。そういう引用は、真似とは違うのだろうか。基本的にはそういう疑問が問題とされている。
何かを引用したものは、その引用したはずの何かを含んだもの。とすると、含むという概念が重要だが、それがかなり意味的に拡張された場合にしか、絵が音楽を含んだりはできないだろう。
実際にそのような意図で書かれているかはわからないが、いくつかの結論に関しては、現に存在する情報を重視しているようにも思う。
例えば、あるベートーベンの第九の演奏を描いた絵画があるとする。そこからある人は、第九の楽譜を心に用意することができる。それを実際に紙にでも書き記した場合、そこでは音楽を記号的表現として表した楽譜というものの引用が、ほぼ確実に発生していることになる。しかしその音楽(楽譜)の引用は直接的に行われているのではなく、それを引用(?)した絵画を通して間接的に行われている。その場合、情報の流れ方的に、やはり絵の時点で、すでに音楽は引用されているのかもしれないというような。
 「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」簡単に悲劇な運命と向き合う
「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン」簡単に悲劇な運命と向き合う
もっと単純に、ベートーベンの音楽を鼻歌で奏でた場合、それはすでに、音楽を言葉で引用しているし、その楽譜をも実質的に引用していると言える。というような示唆もある。
記号。存在しない怪物、存在している芸術
記号というものをどのように考えるべきかということについても、しっかり1章使われている。
『記号(sign。symbol)』というのは普通、情報伝達を行うための(単純化か、一般化されたような)表現物を意味するだろう。
記号というのは常に外部の何かを表現するものではない。
実際に、外部ではないものを意味している例として、自らを指し示す場合の「この言葉」、11文字である「十一文字で書かれている」などが挙げられる。
このような言葉はまれだが、例えば自らの絵であるような絵、描写の中に自らが含まれているような絵は、さらにまれだとも。
だが実際に、とんでもなくまれでもいい。たったひとつでも、明らかにそれ自身を意味している記号が存在するというのなら、「記号というものをどのように考えればよいのか」という問題は、難易度を急激に上げるかもしれない。
また存在しない怪物という記号などをどのように解釈すべきか。
他に、記号というものがどれくらいに万能かが語られているような感じも受ける。どんな芸術作品もガラクタに変えられるか、道端の石ころとかを芸術として定義できるか、というような。
 「幻獣のまとめ」ファンタジーの魔物一覧。特に興味深いモンスターの分類
「幻獣のまとめ」ファンタジーの魔物一覧。特に興味深いモンスターの分類
「芸術は、いったいいつ芸術なのか」と問われるが、深く考えると、世界をデジタルで表現する場合、アナログで表現する場合それぞれに、変化というものをどのように考えるべきか。というような疑問とかにも通じるような気がする。




