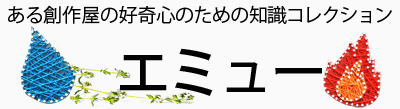泡の研究と、理解されていること
『泡(bubble)』というのは普通は、完全に液体でも、完全に気体でもないと考えられる。
たいていの『泡の塊(foam)』はすぐに壊れる。しかしそういう泡の塊に関して、以下のような観察事実がある。
まず基本的に、液体や固体の中には気体の泡が含まれていることがある。液体の泡の塊はたいてい白く、普通は短命で、純粋な気体や液体とは違う動きをする。個体の中に生じた泡の塊も、最初は液体の泡として作られている。
ペットボトルの中の泡の変化
透明なペットボトルに普通の水道水を半分くらい入れて振ると、そこに泡ができると思われるが、しかしその泡は不安定で、振るのをやめた途端にすぐ消えてしまう。
しかし少しだけ液体石鹸を加えてからよく振ると、振るのをやめた後でも、泡はある程度長続きする。この泡は、振られることで、透明な空気や水が転換したものと考えられる。そして泡は、最初は液体に近くても、空気と混ざるにつれて、振ってもあまり動かないようになっていく。
最初は気体よりも液体が多い湿った泡でも、泡同士の間の水が重力に引かれて下に落ちていくので、だんだんと気体の比率が多い乾いた泡に変化する。泡を隔てている膜も薄く、互いに押し合う。そして、壁が破れて2つの泡が合体したり、小さな泡に含まれる圧力の高い空気が膜を通って大きな泡に入ったりする。そうした事象によって、泡の塊のキメ(表面の凸凹)はどんどん荒くなり、大きな泡ばかりになり、形も変化していく。さらに隣り合う泡同士が互いを歪めあうことで、泡は、孤立したものがたいていそうなるような球状でなく、多面体の形となる。
 「カヴァリエリの原理」錐体、球体の体積。半球と円錐の関係
「カヴァリエリの原理」錐体、球体の体積。半球と円錐の関係  「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
ここまでの手順で作ったペットボトルの多面体泡塊は、結構長く続くともされるが、それでも数日程度で普通は消えて、ボトルには石鹸水のみが残る。泡の膜は薄くとも、その中で光の波が干渉しあうことで 、全体的には虹色に光ったりもする。
液体を多く含んでいる泡は、光線がそらされ、白く見えることが多い。
泡の正体。表面張力と界面活性剤
一般的な泡の正体は、気体を内部に含んだ液体、あるいは個体である。または内部の気体によって膨らんだ液体や固体とも言える。
気体を閉じ込めている泡の膜は、物質を構成する分子間に働く、なるべく表面積を小さくしようとする力、すなわち『表面張力(surface tension)』によるものとされている。単独の泡が球体となるのは、それが表面積が最も小さくなる三次元の形だからである。
 「四次元空間」イメージ不可能、認識不可能、でも近くにある
「四次元空間」イメージ不可能、認識不可能、でも近くにある
また、石鹸のような物体は『界面活性剤(surface active agent。surfactant)』と呼ばれる類いのもので、それを少量溶かした液体などの表面張力を低下させる効果を持っている。
そうした界面活性剤の分子が、泡の膜の表面張力を変化させ、結果的に重力などの力に適応できるようにもなり、壊れにくくなったりする訳である。
海水の泡はある程度壊れにくいとされるが、それも、海水に含まれている様々な分子が、界面活性剤の役割を果たすからである。
スフレやホイップクリームといった食べる泡も、卵白や乳製品の分子などが界面活性剤になっている。
 海はなぜ塩水なのか?地球の水分循環システム「海洋」
海はなぜ塩水なのか?地球の水分循環システム「海洋」
プラトーの法則。多面体の泡の構造
ジョゼフ・プラトー(Joseph Antoine Ferdinand Plateau。1801~1883)は、石鹸水が発生させる泡の膜構造に関して観察研究をし、『プラトーの法則(Plateau’s laws)』というのを発見した。
彼は研究途中に、光学研究がたたって失明したが、身内や同僚の助けを借りながら研究を続けたという。
プラトーの法則は、多面体の泡は、以下のような構造以外は不安定であるというもの。
稜(多面体のとなりあった2つの面が交わってなす直線)ができるのは、3つの膜が出会った時のみ。3つの膜の、隣り合うどの2つも、常に120°の角度で交わる。稜が複数交わるのは、その数がちょうど4本の時のみなど。
プラトーの法則は、1973年、表面張力のための『極小曲面(minimal surface)』、つまりは平均曲率が曲面上のどこでも0になるような曲面になるような物理系の法則と関連した、数学的証明が、ジーン・テイラー(Jean Ellen Taylor)によってなされた。
ケルヴィン構造。最小面積の問題の最適解
複数の泡が集合している場合、それぞれの泡の薄い膜同士が押しあい、 複雑な形になるわけだが、しかしその場合に形成される形のパターンは、数学的にかなり複雑とされる。
そのような泡構造は、泡が全て同じ大きさという単純化をした場合には、ある空間を等しい体積の部分に分割する際に境界面積を最小にするパターン、とも言えるという。
ケルヴィン卿(William Thomson。1st Baron Kelvin。1824~1907)は、1887年、この空間構造パターンの問題に取り込んだ。
そのためか、この問題は基本的に『ケルヴィン問題(Kelvin problem)』と呼ばれるようにもなった。
そして、鉄の結晶の形などを研究したケルヴィンは、その問題の解、 つまり泡構造の最適パターン(表面積が最小の泡構造)は、正方形の面を6つで六角形の面が8つの『十四面体(Tetradecahedron)』であると推測。それは、『ケルヴィン構造(Kelvin structure)』と呼ばれ、長らくこの問題の、もっとも妥当らしい解答とされた。
ケルヴィン構造は、『切頂八面体(truncated octahedron)』による『空間充填(Space-filling)』を模したものとされるが、実際には14面体の六角形の面はわずかに曲率を持っているともされている。
切頂八面体、または『切頭八面体』、『切隅八面体、『角切り八面体』は、正八面体の各頂点を切り落とした立体。
空間充填、または『空間分割』は、空間内を図形で隙間なく埋め尽くす操作。ユークリッド的二次元空間の『テセレーション (tessellation)』、つまりは平面充填の高次元版ともされる。
ウィア=フェラン構造。コンピューターシミュが導き出したもの
1993年には、ダブリン大学トリニティ・カレッジのデニス・ウィーア(Denis Lawrence Weaire)と、ロバート・フェラン(Robert Phelan)が、コンピューターシミュレーションを利用して、ケルヴィン問題の最適解として、ケルヴィン構造より優れているようである『ウィア=フェラン構造(Weaire–Phelan structure)』というのを発見した。
利用されたコンピューターシミュレーションは、『サーフェス・エヴォルバー(Surface Evolver)』と呼ばれるもので、主に、表面張力が影響した液状物質の形状変化をシミュレーションするためのソフトウェアである。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
方法としては、三角形のタイルで望み通りの形の三次元面を作って、面積が最小になるように、面の形を変えていったそうである。
ウィア=フェラン構造は、体積の等しい2種類の基本形が組み合わさっているもの。基本形は、五角形の(正ではない)十二面体と、五角形の12面と六角形の2面が合わさった十四面体。
この形はケルヴィン構造よりも面積の小さな構造であることは確からしかったが、これが最小構造だという証明はされなかった。
そのため、ケルヴィン問題は今も、問題のままである。
個体の泡と、その利用
人は古くから、『軽石(pumice)』のような、天然素材の泡の特性を利用していた。これは個体の泡でもある。
また、『海綿(sponge)』や『コルク(cork)』も、ある種の泡構造(個体の泡の天然素材)とされる場合は多い。
軽石。水に浮かぶような石
軽石とは、浮石とも呼ばれ、水に浮くような石。基本的には火山から噴出する『火山砕屑物(pyroclastic material)』である。
名前の通りに軽い(水に浮く場合も多い)のは、多孔質が基本のためとされる。ようするに、気体で満たされた空洞(泡)が中にたくさんあるため、水よりも密度が低くなるわけである
熱く溶けた溶岩の中に閉じ込められた気体が膨張した泡を作り、溶岩が冷えて固まると、泡が凝固することで、軽石はできる。
軽石を割ると、断面は気泡の縁(へり)で、ギザギザになっているので、物を磨いたり、汚れなどを落とすために使いやすいともされる。
海綿。内部通路にて水を動かす多細胞生物
海綿は、わりと古くからある型の多細胞生物とされる。 基本的な細胞間の結合がゆるめで、器官の分化があまり明確ではないのだ。
世界中のあらゆる海や、時には淡水にも様々な種が生息していて、壺、扇、杯状など、いろいろな形態は、単に種の違いだけでなく、生息環境にもけっこう影響されたりするようである。通常、動かない生物のために、古くは植物と考えられていたこともあるらしい。
海綿の骨格構造は、多数の通路が互いにつながった複雑なものになっている。海綿はその通路を使って、吸い込んだ水から栄養を摂取している。典型的には、外側面積の60倍くらいともされる、その内部面積内に、大量に備えられた『鞭毛(flagellum)』という小器官で、内部の大量の水を動かす。
死んだ海綿の柔らかく、液体を溜め込みやすい骨格は、古代ローマの時代などにブラシとして使われたりもした。現在、人工的に作られるスポンジという道具も、元々は海綿の構造を参考としている。
コルク。とても弾力性に富む素材
コルクは、『コルクガシ(Quercus suber)』という木の樹皮の組織を剥離、つまり剥がしたそれを加工して造る。
ビンなどの飲み口などから、中身を溢さないようにするためのフタとして、ようするに『栓(bung。cock。plug。spill。stopper)』としての用途がよく知られているこの素材は、内部に気泡構造があるために、弾力性に富む。
コルクはその気泡構造のために軽く、水も染み込みにくいので、救命具としても使われてきた。また、コルクの気泡構造は音をよく吸収するともされ、防音材として使われたりすることもある。
ロバート・フック(Robert Hooke。1635~1703)が、コルクの断面を顕微鏡で観察して、多数の小部屋構造を発見し、細胞(cell)の名前を与えたことも、有名であろう。
発泡プラスチック。かなり自由な調整
普通『プラスチック』なるものには、『ポリ~』と呼ばれるものが多い。そのポリは、プラスチックという物質が、『モノマー(単量体。monomer)』という分子単位が集まった高分子『ポリマー(集合体)』であることからきている。
プラスチックを作る過程で、液体の形のモノマーが混ぜ合わせれたりする時に、意図的に気体を加えたりすることで、『発泡プラスチック(Foamed plastics)』というものを作ることができる。
通常のプラスチックの時点でも、モノマーをどのような幾何学的構造として結びつけるかで、いろいろその性質などを調整できる。発泡プラスチックともなると、内部の気体の量などを変化させて、さらに自由に、いろいろな性質を与えることができる。
例えば熱の空気の遮断性を高めたり、踏み心地をよくしたり、虫に食われにくくしたりとか。
炭酸飲料という発明
自然に湧き出た、泡立つ水には、治療効果があるという発想はかなり昔からあったようである。
そのような湧き水の泡が、溶け込んだ二酸化炭素によるものだと、科学者たちが気づいた時から、人工的な泡飲料水、いわゆる『炭酸飲料(carbonated drink)』を作る研究は始まったのだとされる。
脱フロギストン空気として、酸素を発見した功績で有名なジョゼフ・プリーストリ(Joseph Priestley。1733~1804)は、炭酸飲料(炭酸水)の開発に、最初に成功した人としても知られている。
最初は、醸造(発酵により造る)過程のビールから生じる二酸化炭素が、掲げた容器に溶け込むように水を入れ、くみ出すという行為を繰り返したのだという。
1772年には、もっと簡単に炭酸水を生成する装置も開発したらしい。
水に含まれている二酸化炭素がもたらす酸味は、クセになるという人も多い。しかし、プリーストリの開発した装置にいちはやく目をつけた、時計職人で宝石商だったヤコブ・シュウェッペ(Johann Jacob Schweppe(1740~1821)は最初、炭酸水を売り出すにあたり、薬効ある飲料水という点を強調していたようである。
1792年に、シュウェッペはロンドンに移り、炭酸水ビジネスに乗り出すが、最初はあまり成功できなかったとされる。
その新しい飲み物について語ることで、人気の火付け役になったのは、進化論で有名なチャールズ・ダーウィン(Charles Robert Darwin。1809~1882)の祖父、エラズマス・ダーウィン(Erasmus Darwin。1731~1802)とも。
消火泡は、以下にして火を消すのか
炭酸水が、実際に治癒効果とかを持っているかに関しては、怪しいと言えるかもしれない。
しかしもっとはっきりわかりやすく、泡が誰かを救うためのテクノロジーに利用されている例も多い。
真っ先に思いつきそうなのは、やはり消火器であろう。通常、泡消火器の消火泡は、それが水を適切に火に運ぶことで、高い消火効果を実現するとされる。
直接的に火に水をかけた場合は、燃えている燃料の下に水が沈んだりして、かえってそれを広げてしまったりする場合もある。しかし消火泡の場合は、泡が炎の上に乗るような形になり、冷却のための水を火に直接的に押し当てる。しかも、火に覆いかぶさったような泡が、火という現象に不可欠な酸素を遮断する訳である。
音ルミネセンス。泡は小さな核融合炉になりうるか
泡と光学には様々な関連がある。
光は電気でもあるが、普通さまざまな化学物質が混ぜこまれている海水には電気がよく通る。しかし、空気は電気を通しにくいので、 空気の泡がたくさんの海水中では電気伝導率が悪くなったりもする。それで、特定場の泡の量を調べたりもできるとされる。
 「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
またクリーンエネルギー、つまりは、二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)といった有害物質の排出量を抑えたハイテクエネルギーテクノロジーに繋がるかもしれない、泡の現象として、『ソノルミネッセンス(sonoluminescence。SL)』というのも知られている。
液体中の気泡が、超音波を受けた際に光を発するこの現象は、『音ルミネセンス』とも呼ばれる。
意図的に音ルミネセンスを起こそうとする場合、気泡にぶつける超音波は、人間の耳には聞こえない周波数が使われるのが普通。だが、実際的にはかなりうるさいものらしい。
とにかく、そのような音波をぶつけられた液体の中では、圧力のパルス(急激な変化の繰り返し)が作り出され、泡も同じリズムで収縮、膨張をする。泡が十分に小さいと、外向きの圧力もほとんどないために、周囲の圧力によって、泡は激しく内側に押されることとなり、急激に縮む。すると泡は、おそらくは高温となった場の分子の化学変化などにより、光を発するのである。
発せられる光は、音波のサイクルごとに繰り返されるようで、かなり規則的なため、例えば光速に近い速さで動く素粒子の運動時間を測ったりするのに、この音ルミネセンスが利用されたりもするという。
音ルミネセンスに関する有力な説として、それが起こる時、高圧領域の移動が生じる中で、泡の中の気体が激しく圧縮されるため、温度が著しく上昇するというものがある。セス・パターマン(Seth Putterman)は実験室での測定では、この現象時の、泡の収縮速度は、音速の4倍以上だったとも。さらに圧縮の後の膨張も、その加速度はすさまじいようで、これが熱核融合に使えるのでないかと考える向きするあるらしい。
普通に、音ルミネセンスを起こす泡は、微小な熱核融合炉のようになっているかもしれない、という推測もある。適切に音波を利用することで、そこに凄まじい高熱を実現させることも可能かもしれない訳である。
液体の流れの中で、圧力差などのために泡の発生や消滅が短いスパンで繰り返される物理現象を『キャビテーション(cavitation)』、または、『空洞現象』という。
音ルミネセンスの過程とされる、気泡の膨張や収縮変化も、このキャビテーションと言える。
インチキとされた、バブル核融合
2002年には、アメリカ、オークリッジ国立研究所のルーシ・タリヤーカン(Rusi P. Taleyarkhan)が、『バブル核融合(Bubble fusion)』なる、新しい原子核融合の一種に関する論文を発表したが、再現性がなかったためにあまり信用されなかった。そして2008年、パデュー大学の審査委員会が、タリヤーカンの研究は『不正研究(Scientific misconduct)』だったと断定した。
タリヤーカンは、重水素を含んだアセトンに超音波を当て、生成された泡が壊れる際に、中性子が飛び出るのを確認。それは高温高圧下で、重水素同士の熱核融合が起きたものと推測したそうである。