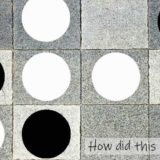十字軍の時代。キリストのヨーロッパ、イスラムの中東
騎士社会の誕生。グレゴリウス改革により変わる教会
11世紀から、農業の発達や、それによる「飢饉(famine)」や「伝染病(Infectious disease)」の減少から、ヨーロッパの人口は増え始めた。
また、王の代理人として、地方領主たちが実質的な支配者として力を振るうようになってきていた。
この時期に、戦いのための道具も改善される。
「鎖帷子(Chain lion)」や「鉄兜(steel helmet)」を身につけて、馬に乗り戦う『騎士(Knight)』という姿は この時期に誕生したとも言われる。
騎士は幼い頃から特別な訓練を積んでいる。
それにそもそも戦いの装備にも金がいるから、基本的に騎士は貴族が多かった。
また、騎士の社会は血筋を重んじ、武勇が好まれたが、教養は心を弱くするとして嫌われた。
11世紀の後半には、教会を世間のその他から明確に切り離した領域とする『グレゴリウス改革(Gregorian Reform)』があった。
教会の中には、平和の重要性を唱えて、戦争を消し去ろうとする動きもあったが、そんなことは不可能とみなが悟った後は、騎士による戦いをキリスト教的に解釈するという方法が主流となっていく。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
騎士道を立派なものとして、聖職者や社会的弱者を守ることを、騎士の目的とした。
ビザンティン帝国
一般的にローマ帝国は4世紀末頃に東西に明確に別れたとされている。
その東側の方、いわゆる『東ローマ帝国(Eastern Roman Empire)』は、『ビザンティン帝国』という名前でも知られている。
中世の交差点とも呼ばれる、帝国の首都『コンスタンティノープル』もかなり有名である。
11世紀前半頃。
ビザンティン帝国は「小アジア(アナトリア半島)」から「南イタリア」の一部までの領土を有していて、ビザンティン皇帝は絶大な権力を持っていた。
しかし11世紀後半。
西からイタリアのノルマン人、東からトルクメン人が侵入してきて、多くの領土を奪われてしまう。
そこで、1081年に即位したアレクシオス1世コムネノス(1048or1056~1118)は、ローマ教皇ウルバヌス二世(1042~1099)に、兵士の増援を要請する。
クレルモン教会会議。ウルバヌス二世の呼びかけ
アレクシオスとしては、単に兵力を増強したかっただけなのだが、ウルバヌス二世はこれを好機として、大規模な遠征隊を東側へと送ることにする。
「騎士道精神にのっとり、仲間を苦しめる異教徒と戦うため」というような発想であったとも言われる。
そして1095年。
フランスのクレルモンで行われた「クレルモン教会会議」にて、ウルバヌス二世は、騎士の力により、異教徒たちの脅威からキリスト教徒の仲間たちを救うための『十字軍(Crusader)』という思想を語った。
それが「十字軍遠征(Crusade Expedition)」の、決定的な契機となったとされている。
ウルバヌスは、十字軍に参加する者は、訴訟などを起こされている場合でも、それを停止することを約束。
さらに聖地奪還が果たされたならば、十字軍兵士たちには罪の許しがあるだろうと説いた
聖地奪還か、政治的な思惑か。十字軍の目的
当時イスラム世界にあったパレスチナは、イエス・キリストが生涯を過ごした地。
特に聖地『エルサレム』は、『キリスト教徒』の人にとっては重要な場所とされている。
ある説では、最後の審判の時、地上のエルサレムは天上のエルサレムとつながり、イエス・キリストはそこに現れる。
つまりエルサレムは、運命のその時に、キリストが再降臨する地でもあるわけだ。
イスラムの者も、8世紀末ぐらいから、キリスト教徒によるエルサレムへの巡礼を許していて、その近場には巡礼者たち用の宿泊施設もあったようである。
しかし許されているといっても、そこはイスラムの土地であり、巡礼者たちの安全が常に保障されているというわけでもない。
 「イスラム教」アッラーの最後の教え、最後の約束
「イスラム教」アッラーの最後の教え、最後の約束
十字軍の目的の中には、聖地奪還もあったのはほぼ間違いないとされている。
一方で十字軍には、不安定になりつつあったヨーロッパ社会の人々の心を一つにまとめるため、という政治的思惑もあったと考えられている。
隠者ピエールの民衆十字軍
フランス王フィリップ1世の弟など、様々な貴族も十字軍参加を表明した。
そういう者たちは宗教的な動機以上に、征服した土地で自分の国を築きたいという野望を持っていた。
一方で、教皇としても予想以上の数だったとされる、貧しい民の参加者たちは本気で、聖地エルサレムで死ぬつもりであったされている。
最後の審判の時にキリストの側にいるためだ。
信仰深い民衆たちの背景には、彼らを先導した宣教師たちがいた。
特に隠者ピエール(?~1115)は 十字軍が発足される数年前に聖地エルサレムを訪れていて、帰還してからは、聖地の奪還の重要性を民衆たちによく訴えかけた。
そしてピエールは、『民衆十字軍(People’s Crusade)』と 呼ばれる一団を率い、十字軍本隊に先駆け、東へと向かったという。
騎士道とは程遠い
民衆十字軍は騎士道とは程遠い野蛮な連中だったようである。
ライン地方でユダヤ人を虐殺し、ハンガリーでは略奪行為を行った。
ビザンティン皇帝アレクシオスも恐れを抱き、「ボスポラス海峡」を渡らせてほしいという、彼らの要求に素直に従うしかなかったとされる。
しかしトルコにて、民衆十字軍は二度も敗北。
アレクシオスは生存者たちをヨーロッパへと返そうとしたが、信仰心だけは相当に強い彼らは、決して帰ろうとしなかった。
おそらく、立派な信仰心というものと、野蛮な攻撃性というものは、両立できるものなのだろう。
第一回十字軍の戦い
アレクシオス二世が憲兵とした十字軍
十字軍本隊が来ると、アレクシオスは騎士たちに忠誠を誓わせた。
さらに、ビザンティンの領土であった土地を奪還した場合は、皇帝に返すこと。
その他の征服した土地の「宗主権(内政や外交を管理する権利)」も、皇帝に帰する事を認めさせる。
十字軍は、アレクシオスの思惑通り、憲兵として役に立ってくれた。
1907年6月の、ビザンティン帝国によるニカイア奪還は、十字軍の功績とされている。
正教会と、エデッサ伯国
トルコ南部タウルス山脈などには、「アルメニア正教会」や「シリア正教会」のような「正教会派(Orthodox church)」の者たちもいた。
正教会とは、「ギリシャ正教」をはじめとする、キリスト教初期の教会の思想を受け継いでいると称する、キリスト教内の派閥である。
正教の者たちは、イスラム帝国はもちろん、教会会議の決議を押し付けてくるビザンティン帝国にも、よい感情は抱いていなかった。
そんな彼らにとっても、十字軍は救世主的な一団だったとされている。
エデッサの君主トロスは、十字軍に参加していた貴族、ボードゥアン・ド・ブローニュ(1065~1118)を養子にして、トルコ軍を追い払う。
トロスが死んだ後、ボードゥアンはエデッサ伯を名乗り、オスロヘナ地方の都市の多くを我が物とした。
1098年より始まる、ボードゥアンのエデッサ伯国は、オリエント最初のラテン(ローマ系)国家ともされる。
アンティオキアでの対立
アンティオキアに対しての十字軍の包囲戦は、半年以上の長期に及んだ。
この戦いはギリギリの勝利だったとも言われる。
モースルから、アター・ベク・カルブーカーが率いる大軍が、アンティオキア防衛のために迫ってきていて、十字軍が街の中に攻め込んだのは、その大軍が到着するわずか二日前だったのである。
アンティオキアはビザンティンの領土だったこともあるので、ビザンティン皇帝に返す契約のはず。
しかし、勝利に貢献したボヘモンド(1054~1111)という貴族は、この街を自分で支配しようとして、それに賛成する者も多かった。
だがレーモン・ド・サン=ジル(1052~1105)など、ボヘモンドに反対する者もいて、十字軍内部でも明確な対立が生じてしまう。
恐ろしきタフール軍
ボヘモンドら名だたる諸侯たちが支配権をめぐって対立する一方で、彼らの強欲さを目の当たりにした一般兵士たちの間では、「赤貧(何も持たるほどの貧乏)こそが救済条件」という考えも芽生え始める。
そうした思想の者たちが結成した『タフール軍』は、 十字軍の先鋒部隊として活躍した。
タフール軍は、 槍も剣も盾も持たないで、 ただがむしゃらに棍棒を振り回したという。
彼らはイスラム教徒の者とみるや、問答無用に虐殺して、倒した者の死体を自分たちの糧とした。
当然のことだろうが、イスラムの者たちは彼らに恐怖し、仲間であるはずの他の騎士団員達も、彼らには嫌悪感を抱いていたという。
一方でタフール軍は、必要以上の破壊を行うことで、土地の所有権争いばかりに時間を使う上の者たちに抗議した、という見方もある。
エルサレム征服
十字軍がついにエルサレムに到着したのは、1099年6月のことだったという。
日光に照らされたその地の輝きは、十字軍たちを膝まづかせ、神の奇跡を信じさせた。
そうして、ろくな準備もせぬままに、神の加護だけを信じた彼らの襲撃はあっさり失敗する。
しかし運よく(あるいは本当に神の助けか)、ジェノヴァとイギリスの船が、近場であるヤッファの港に到着し、十字軍は不足していた物資を仕入れる。
そして7月。
再びの襲撃で、ついにエルサレムを征服した。
十字軍の蛮行。極悪非道な征服者たち
十字軍のエルサレムの征服。
この時の十字軍(キリスト教徒)の残酷な振る舞いは、中東世界に長く残る、深い傷跡を残したとされている。
エルサレムのイスラム教とユダヤ教の者たちは、次々と剣で刺され、火で焼かれ、殺戮は数日にわたって続けられた。
生き延びた者たちの多くも奴隷として売られたそうである。
 「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
極悪非道な振る舞いに関しては、「エルサレムは、その地を間違った信仰で汚した、異教徒たち自身の血で浄化されるだろう」というような発想に基づいていたと考えられている(エッセー)。
(エッセー) 神様を信じているのだとしても、神様が何者かは考えるべきか
十字軍のエルサレムでの所業のように、今の我々から見れば残酷だと思えるような行いは、時代背景や、当時の思想を考慮すべき、という人もいるかもしれない。
そんなもの考慮するまでもなく、人間の残虐な振る舞いというのは残虐なものである。
つまり人間は本質的にそういうもの、と考える人もいるかもしれない。
全てを宗教と、 それを信じる者たちのせいにする人もいる。
個人的には、何かの宗教を信じ、その理念に基づいて残虐な行為を行うということに関しては、その宗教自体を悪いとは思わない。
それよりも「もしかしたら神様は悪なのかもしれない」という、ごく普通にありえそう、かつシンプルな発想も抱けないような短絡的な思考回路が原因だと思う。
「神様が望んでるからやった」のだとしたら、その神様はつまり悪党なんだと思う。
一番偉い奴が悪党だなんて話、別に珍しくもなんともないし。
「そんなことを考えてたり、言ってたりすると地獄に落とされるんじゃないか」と恐れる者もいるかもしれないが、たかがそんなことで地獄に落とすようなやつが善人なわけがない。
この宇宙が暴君の恐怖政治だと想像するのも、個人的には結構恐い。
 「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
こんな話、無神論者には関係ない話と思うかもしれない。
しかし無神論者の人であっても、実際に何かの宗教の信者になったつもりで、こういう問題を考えるのは大事なことと思う。
歴史の中で、宗教が大きな力を持ってきたことは事実である。
エルサレム王国の栄光
王でなく聖地の守護者
エルサレム征服後。
やはり諸侯たちの間で、いったい誰がこの聖地を統治するべきかという問題が発生した。
最終的には、エデッサ伯国のボードゥアンの兄、ゴドフロワ・ド・ブイヨン(1060~1100)に任されることが決定。
彼自身は王でなく「聖地の守護者」を名乗り、彼の死後は、弟のボードゥアンが後継となり、彼はしっかりエルサレム王を名乗った。
そうして1100年。
聖地は、エルサレム王国になったのだった。
ボードゥアン一世、二世の治世
ヨーロッパでは十字軍の呼びかけが続けられていて、いくらかの新軍団が再び出発していたが、最初の十字軍との戦いで団結を学んだイスラムの者たちに、次々と返り討ちにされていた。
一方で、イタリア艦隊や巡礼者兵士の活躍もあって、エルサレム王国は、ボードゥアン一世、二世、合わせて30年ほどの治世の間に、それなりに広い土地を獲得したとされる。
もちろん、孤軍奮闘を余儀なくされていたエルサレム王国は、 イスラム勢力の抵抗に対して、いつも完勝していたわけではない。
ただ、イスラム側の内部争いや、重装備のヨーロッパ側兵士が正面きっての防衛戦に長けていたことなど、様々な要素がエルサレム王国を有利にしていた。
イスラム勢力の反撃。エデッサの奪還
イスラムがなかなか団結しなかった理由として、十字軍のキリスト教への信仰を甘く見ていたという説がある。
つまり彼らは十字軍の征服を大局的には重要なものと思っていなかった。
イスラムの世界は侵略されても、その度、結局はイスラムに取り込まれ、征服者たち自身がイスラムに帰するのである。
しかし、数十年もの時間をかけて、だんだんとイスラムの人たちの意識も変わり、十字軍を自分たちの世界の脅威と見なすようになっていく。
そしてイスラム勢力の反撃が始まり、1144年にエデッサは征服された。
今度はイスラム教の者たちが、キリスト教徒の血の雨を降らせる番だったが、一般的に十字軍側の所業ほど酷くはなかったろうとされている。
ただし十字軍の記録に関しては、「キリスト教側がどうしようもない悪の征服者だった」というような図式が浸透しきっていて、キリスト側が大げさに、イスラム側が控えめに伝えられている可能性はある(注釈)。
善悪に関する東西の思想の伝統?
伝統的にヨーロッパ側は善悪を明確にするのが好きで、アジアは善悪を曖昧にするのが好きという説もある。
「正義は必ず悪を倒す」か「敵と味方のどちらにも正義がある」か、というような思想の違いである。
これは確かに、様々な歴史の本などでよく見られる傾向かもしれない。
例えば、何か科学の発見に関する歴史の話があるとして、日本人の本では淡々といろいろな人の業績が述べられていたりするのに、同じテーマの欧米人の本では、最もその発展に貢献した人を誉め称えて、その人の業績を奪おうとした人たちへの批判を書いてたりもする。
その後の十字軍。敗北ばかりの歴史
フランス王の誤算。第二回
エデッサ没落の知らせを受けたヨーロッパでは、公式に二度目の十字軍の召集が決定された。
軍隊を率いていたのはフランス国王ルイ七世(1120~1180)と、ドイツ皇帝コンラート三世(1093~1152)で、呼びかけにおいては聖ベルナルド(1090~1153)が大きな役割を担ったとされている。
第二回十字軍は1147年に出発したが、シリアに着くまでのイスラムの攻撃によって、大半の兵士が死亡。
さらにルイ七世は、「まずオロンテス川より東を攻めるのがいい」という、アンティオキアのレーモン・ド・ポワティエ(1099~1149)の アドバイスを無視して、ダマスクスへと侵攻。
結局ダマスクス攻略に失敗した、第二回十字軍は、ヨーロッパへと逃げ帰ることになった。
そして第二回十字軍が去った後、1149年に、アンティオキアもイスラムに敗北した。
イスラムの英雄サラディンとの戦い。第三回
レーモンが要注意人物として考え、アンティオキアの征服も果たしたヌール・アッディーン(1118~1174)の後継者とされた、英雄サラディン(1137or1138~1193)は、1186年までに、イスラム世界のラテン国家全てを攻略した。
サラディンの活躍による、エルサレム王国の敗北により、ヨーロッパは再び立ち上がろうとする。
そうして、第三回の十字軍が結成された。
今度は「尊厳王」ことフランス王フィリップ二世(1165~1223)と、「獅子心王」ことイングランド王リチャード一世(1157~1199)が軍団を率いた。
 「イギリスの歴史」王がまとめ、議会が強くしてきた帝国の物語
「イギリスの歴史」王がまとめ、議会が強くしてきた帝国の物語
基本的にサラディンと第三回十字軍との戦いは、サラディンの勝利ということになっている。
実際にその通りであろうが、少なくとも第三回十字軍の者たちは、サラディンと戦いの末に停戦協定を結び、一部の領土をラテン国家として扱うことを認めさせた。
さらにキリスト教徒がエルサレムを訪れる自由も再び取り手に入れたのだ。
しかし、もはやイスラム世界を奪い、そこに新たなラテン国家を建設するなどという野望は、ほとんど完全に死んでいた。
キリスト教史上最大の恥晒し事件。第四回
はっきりと成功したと言える十字軍遠征は、第一回のみと言われている。
第三回においても、東の地におけるラテン国家滅亡を食い止めたという業績以外に見るべきところはないと言ってもいい。
しかし、特に第四回の遠征に関しては、文字通りに、本当にひどい。
1202年~1204年の、第四回十字軍は、あろうことか、曲がりなりにもキリスト教側であるはずのビザンティン帝国の内紛に乗じ、コンスタンティノープルを占領し、ビザンティン皇帝を追い出して、そこに自分たちのラテン国家を新たに建設したのだ。
いったい何が起こったのか、よくわからないが、この事件はビザンティン帝国崩壊の直接的なきっかけとされ、 キリスト教全体の歴史においても、最も恥晒しな事件の一つとされている。
ただ侵略に成功したという意味では、第四回十字軍は成功だったと言えなくもない。
あるいはイスラム側は、何もせずとも勝ったのだと言えるかもしれない。
調子に乗りすぎた者たち。第五回
1210年から1219年までの第五回十字軍はエジプトへの遠征だった。
サラディンが創始したとされる「アイユーブ王朝」の中心部が、エジプトとされていたからである。
そこを抑えることで、やがてはエルサレムも取り返せるかもしれないという希望もなくはなかった。
実は考えとしては正しかった。
アイユーブ朝は、和平の条件として、旧エルサレム王国の領土を返そうと言ってきたのだ。
しかし、図に乗って、エジプトをまるまる征服しようとした第五回十字軍は、その条件を退けて戦いを続け、そして負けた。
戦わずしてエルサレム奪還。第六回
1228年から1229年の、フリードリヒ2世(1194~1250)の第六回十字軍は、 エルサレムを取り戻した十字軍として有名であるがその背景には、モンゴルのチンギス・ハン(1162~1227)の勢力拡大があった。
チンギスハンの侵略に恐怖していたイスラム側に、フリードリヒ二世は和平を持ちかけ、結果的に、十字「軍」とは名ばかりに、第六回十字軍はほとんど戦いを行うことなく、エルサレムを取り戻したのだった。
しかしこの、異教徒と妥協しあうやり方は、教皇庁から非難を浴び、結局エルサレム自体も、フリードリヒが交渉したイスラム側のアル・カーミル(1180~1238)が亡くなると、すぐに再びイスラムのものになった。
ラテン国家の最期の足掻き。第七回、八回、九回
1248年から1254年の、第七回十字軍は、またアイユーブ朝のエジプトを攻めるも敗北。
軍を率いていたフランス王ルイ九世(1214~1270)は、仲間達と共に捕虜となったが、莫大な身代金と引き換えに釈放されたという。
ルイ九世は、しかしヨーロッパには帰らず、1270年に、再び十字軍を立ち上げ、キリスト教の領土拡大を図る。
しかしルイ九世は志半ばで死亡。
イングランド王太子エドワード一世(1239~1307)が後を継いだが、十字軍内部での対立が激しいこともあり、結局イスラム側には勝てず、1291年に、最後の砦となっていたアッコも没落し、十字軍の歴史は終わりを迎えた。
ルイ九世の十字軍を第八回、エドワード一世が後を継いでからを第九回とすることもあるが、これらはひとまとめに第八回十字軍と言われもする。
いずれにしても、十字軍という存在に、歴史を動かすような力はもう残ってなかったとされている。