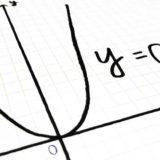紀元前のブリテン島
ストーンヘンジに立った人々
紀元前7000~6000年くらいの事。
ユーラシア大陸の西端。
大陸から切り離された、後に『ブリテン諸島』と呼ばれるようになる島々には、すでに多くの人が住み着いていた。
この島々で、農耕や牧畜が始まったのは紀元前4000年頃。
さらに『ビーカー人』という人たちが、『青銅器』を伝えたのが紀元前2000年頃の事だとされている。
そして紀元前1700年頃。
島々の中で最も大きな『ブリテン島』の東南部に位置するソールズベリー平原には、巨石を信仰していたと思われる文化があった。
どのくらいの規模であったかはわかっていない。
ただ彼らが残した巨石の遺跡『ストーンヘンジ』は、毎夜、火の明かりに照らされた巨石を崇めた人々を想像させる。
あるいは、空にありながら、巨石によって見え隠れする星の謎に、考えふける誰かたちを。
 「ストーンヘンジ」謎解きの歴史。真実のマーリン。最重要のメガリス
「ストーンヘンジ」謎解きの歴史。真実のマーリン。最重要のメガリス
ローマと、ケルトのブリタニア
紀元前2000年くらいのアルプス山脈で起こったとされているケルト文明の諸部族たちは、それから1000年以上にかけてヨーロッパの多くに広がっていく。
 「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
そのケルト系の部族が、ブリテンに住み着いたのは紀元前500年くらいの事とされている。
彼らは新しく強力な鉄器の文化を持って、青銅器までしか知らなかった当時のブリテン先住民から土地を奪っていった。
そして紀元前58年。
後に初代皇帝となる、ローマ帝国将軍ユリウス・カエサルは、アルプス北に幅を利かせていたケルト部族『ガリア』の地の征服を開始。
当然ガリア人は反抗し、戦いが始まったが、この時、ガリアはブリテン島を実質支配していたケルト部族『ベルガエ人』に支援されていた。
ベルガエ人はローマでは『ブリタンニ』とも呼ばれていて、カエサルは、そのブリタンニ共が支配している島を『ブリタニア』と名付け、それがブリテンという名の由来となった。
カエサルの時代にはブリタニア征服はそれほど上手くいかず、一応、紀元前54年頃には諸部族を屈服させるも、支配は長く続かなかった。
しかしほぼ100年後の紀元43年。
4代目皇帝クラウディウスは、改めてブリタニアを侵略。
カエサルの頃に比べ、強化された装備のローマ軍は、あっさり征服を成功させた。
さらに年月と共にローマの勢力は拡大し、紀元100年頃には、ブリタニアはすっかりローマの島となっていた。
イングランド統一まで
帝国による発展と、支配の終わり
ブリタニアはローマ人の手により、紀元200年頃までに、商業の地として発展していく。
また、街道や砦、闘技場や劇場や公衆浴場など、都市としても開発されていった。
しかし帝国の支配地域の拡大により、逆に各地域への帝国の影響は弱まっていく。
そこでローマは、地域を4分割し、それぞれを、それぞれの帝が治めるという四分統治体制(テトラルキア)を採用。
紀元300年頃の事である。
ブリタニアは、ガリアと共に改めて統治された。
そして紀元400年頃。
元々スカンジナビアの原住民であったようである『ゲルマン人』がガリアへ侵攻してきたのに乗じて、ブリタニアで結成された軍も、ローマの統治者たちを攻撃、追放に追い込んだ。
そうしてブリタニアのローマ時代も終わりを迎えたのだった。
アングロ・サクソンにより分けられた領域
ローマから解放されたブリタニアを待っていたのは、新たな勢力の侵略であった。
アングル人、サクソン人、ジュード人と、ゲルマン系の部族たちが、ブリタニアにも侵攻してきたのである。
紀元400年から500年にかけて、ゲルマン人たちは、ブリタニアの住人たちの住居を奪い、定住を始めた。
3つの名前を合わせ『アングロ・サクソン』と呼ばれるゲルマン系部族により、西に追われたブリタニア人たちは、その内に『ウェアルフ』と呼ばれるようになった。
ウェアルフとはアングロ・サクソンの言葉で異邦人の意であり、この呼び名から、後に『ウェールズ』という地名が生まれる。
北に追われた人たちの中には、元々アイルランド島に住まい、隣のブリタニア島の西海岸地域を、海賊行為により脅かしていた『スコット人』の姿もあった。
後に彼らは、共に追われた他のブリタニア人たちと、北の地に新しい王国の建設に着手していく。
アングロ・サクソンの中で、最も有力な部族はアングル人だったのだろうか?
やがて彼らゲルマン系部族が支配した、ブリテンの中央地帯は『イングランド(アングル人の地)』と呼ばれるようになっていった。
七王国時代
イングランドはすぐに一個の国として機能したわけではない。
アングロ・サクソンとまとめられてはいても、元々はいくつもに別れた部族団体である。
イングランドに定住してからはある程度まとまりだしたが、特に強力であった七つの王国はすぐにまとまらなかった。
『ケント』、『サセックス』、『ウェセックス』、『イーストアングリア』、『エセックス』、『マーシア』、『ノーサンブリア』という七王国は、数世紀の間、互いに覇権をかけて長く争う事となった。
このイングランド戦国時代とも言うべき時期は、歴史学者から『七王国時代(ヘプターキー)』と呼ばれている。
紀元757年から796年の間にマーシアの王を務めたオファや、825年の戦いでマーシアに勝利したウェセックス王、エグバートなど、実質的にブリテン統一に成功する王もあった。
しかし彼らの統一支配は、軍事力による強引なものにすぎず、長続きするものではなかった。
しかしいつまでも内輪揉めをしてる場合ではなかった。
ブリテン島は外部からの新たな驚異にさらされつつあったのだ。
ヴァイキング
紀元800年以降。
スカンジナビアから発った『ヴァイキング(入り江に住む人々)』と呼ばれた海賊たちが、ヨーロッパを海から制覇しようとしていた。
彼らを代表する部族とも言える『デーン人』は、ブリテンの島にも、その船を上陸させる。
紀元865年。
デーン人はその圧倒的な武力で、当時ブリテンに残っていた4つの国の内、イーストアングリアとノーサンブリアを次々に制圧。
やがてデーン人がウェセックスに到達した時、そんな時期にアルフレッドは王となった。
アルフレッド王は、恐ろしい敵を前にある決心をする。
それまで幾度も戦ってきたマーシア国と手を結んだのである。
そしてウェセックスとマーシアの連合軍は、ついにデーン人の撃退に成功したのだった。
アルフレッド王
デーン人との戦いを終えて、ブリテンにかつてと同じ規模で残っていた国はウェセックスだけだった。
そしてアルフレッド王は、歴代の王たちとは違っていた。
彼は単に武力による支配に満足して終わる事なく、今や七王国でもなく、ウェセックスでもなく、もっと強大な一個になりつつあった国の改革に努めたのである。
新しい法典。
それに各地方に地方官を起く事で、個別の州として機能させた。
そしてアルフレッドの孫、アゼルスタンの時代にさらに基盤は整い、曾孫エドガーの時代に、ウェセックスはついにイングランドとなるのである。
イングランドの誕生
イングランド中に広く通用する単一の硬貨を、最初に作ったのはオファ王だが、アゼルスタンは、彼の頃にはすっかり失われていた、この単一硬貨を復活させる。
さらに姉妹を、新聖ローマ皇帝やフランス王に嫁がせ、他の国とも関係を深めていく。
何より、アゼルスタンは深く立法に関わり、有力者たちと定期的な会議を開き、その習慣を次代以降にも引き継がせたのである。
このような習慣は、議会などのシステムの起源とされている。
そしてアゼルスタンの甥、エドガー王の時代。
熱心なキリシタンでもあったエドガー。
彼はブリテンにて、司教に王冠(おうかん)を授与される事で、キリストの祝福の元に王となる『戴冠式(コロネーション)』を初めて受けた王となる。
同じく真聖ローマ帝国のオットー1世の戴冠式(962年)より後、フランス王ユーグ・カペーの戴冠式(987年)より前となる973年の事であった。
主の大いなる愛に包まれる事で、エドガーは名実共に最初のイングランド王となったのである。
そして、それはついにイングランドが完全に統一された事を意味していた。
ウェールズ王子誕生まで
無思慮王とデンマーク
なぜだか、よき王というのは何世代も連続するものではない。
エドガー王の死後、次代の王に選ばれたのは、長男のエドワードだったが、彼は即位から3年ばかりで暗殺されてしまう。
そして当時10歳の次男エゼルレッドが急遽王になるのだが、彼にその才はなかった。
紀元1000年くらい。
『無思慮王(アンレディ)』と呼ばれたエゼルレッドは、無能な政治で、貴族たちを呆れさせた。
さらに再び攻めてきたデーン人たちへの必要以上の報復で、スカンジナビアはデンマークの王スヴェンの怒りを買ってしまう。
スヴェンは軍を、イングランドに送り、哀れエゼルレッドは、平和条約の為に多額の銀貨をヴァイキングたちに差し出す事となった。
それからイングランドの貴族たちは、無能なエゼルレッドに代わり、スヴェンを王として迎え入れる。
しかしそうなった1013年からわずか1年後の1014年にスヴェンは急死する。
フランス北西部を侵略したヴァイキングの『ノルマン人』が築いた国ノルマンディ。
そのノルマンディに亡命していたエゼルレッドが、スヴェンの死後、再び王に返り咲くも、1016年に彼もまた世を去った。
エゼルレッドの後を継いだのは、彼の長男エドマンド2世だった。
だが彼はすぐさま、スヴェン王の次男カヌートに親子2世代にわたっての敗北を喫し、イングランド王はカヌートに、つまり再びデンマーク人となる。
ふたつの国の王
カヌートはデンマーク王家の血筋であったが、イングランドの伝統や習慣を重んじ、ちゃんとイングランド王になろうとした。
 「デンマーク」王室の船、神話に書かれた起源、世界最古の遊園地
「デンマーク」王室の船、神話に書かれた起源、世界最古の遊園地
しかし1019年に、デンマークで王位についていた兄ハーラルが急死し、彼は海を跨いだふたつの王国を一手に担わなければならなくなった。
イングランドとデンマークを両方の王として行き来しなければならなくなったカヌートは、自分が不在の時のイングランドの統治をなんとかする為に、新たな階級を作る。
イーストアングリア、ノーサンブリア、マーシア、ウェセックスの4地域を、伯領として、それぞれの地域を統治する最有力者を『伯』としたのである。
だが、王の不在を担う伯たちの権力は次第に強くなり、カヌートの後を継いだ王たちは、『強すぎる家臣たち』と称される有力貴族たちとの、政治的な内戦に悩まされる事となる。
ノルマンディのウィリアム1世
カヌートの次の王は、エゼルレッドの子であるエドワードとなった。
彼は強すぎる家臣たちを抱えながらも、即位まで25年もノルマンディに亡命するなどして、暗殺も追放も一応免れ、即位後は、それなりには上手く王として生きた。
そして紀元1050年半ば。
50歳を越えたエドワードは、跡継ぎに、自身と関わりの深いノルマンディの当主ギョームを指名した。
しかし1066年1月に、実際にエドワードが死んだ後、貴族や聖職者たちに新たな王として選ばれたのはウェセックス伯ハロルド2世だった。
だがハロルド2世の即位に、エドワードに選ばれていたはずのギョームは異を唱えた。
また、スヴェンやカヌートと同じくデーンの血筋である、ノルウェー王ハーラルも、加わり、三つ巴の抗争が勃発する。
一年も経たぬ間に、抗争を制して新たなイングランド王となったのはギョームだった。
彼は自身の名前ギョームを英語読みして『ウィリアム1世』を名乗り、戴冠式にはノルマンディの貴族たちも大勢招待した。
ここに『ノルマン王朝』の時代が幕を開けたのである。
征服王と息子たち
かつて無能な自国王に代わる存在として、貴族たちから迎え入れたデーン人のスヴェンとは違い、ウィリアムは『征服王(コンカラー)』と呼ばれ、完全に異国人の征服者であった。
だから彼が王となってからしばらくはイングランド各地で反乱が絶えなかったが、彼はそれら全てを上手く押さえつけた。
しかしノルマンディと、イングランド。
カヌートのように、ふたつの国を一手に持つという状況は、ウィリアムを苦労させる。
また、ノルマンディは強国であるフランスの隣にある為に、その防衛にも気を配らなければならない。
そして有力貴族に後押しされた、長男のロベールが反旗を翻し、フランス王と共にノルマンディを攻撃してきた時、ウィリアムの命運は尽きた。
1087年9月。
落馬事故によりウィリアム1世は戦死して、父子の対決は終わった。
すると今度は兄弟喧嘩が始まる事となった。
ノルマンディを継いだロベールと、イングランドを継いだ三男のウィリアム2世との間で、国の権利を巡る新たな争いが勃発したのである。
十字軍とヘンリー1世
1096年。
ローマ教皇ウルバヌス2世が、異教徒イスラムに奪われた聖地イェルサレムを取り戻す為に、大規模な遠征を画策。
ヨーロッパ中を巻き込んだこの『十字軍』の遠征に、ロベールも参加する事となり、ウィリアム2世は、チャンスとばかりに兄が不在のノルマンディ貴族に取り入ろうとする。
しかし手応えなくウィリアム2世がだらだらしてる間に、時間だけは過ぎていった。
そしてとうとう1099年に見事イェルサレム王国を建設した十字軍は、1100年に帰還。
 「十字軍遠征」エルサレムを巡る戦い。国家の目的。世界史への影響
「十字軍遠征」エルサレムを巡る戦い。国家の目的。世界史への影響
ロベールは英雄的立場となり、ウィリアム2世は焦りを感じ始める。
それから現実逃避か、狂ったのか、趣味のハンティングに出かけたウィリアム2世は、事故により急死。
その死に誰より強く反応したのは、イングランドを欲しがっていたロベールではなく、自分の国すら父に与えられなかったウィリアム1世の四男ヘンリであった。
彼はすぐさま戴冠式を行い、『ヘンリー1世』として、新たにイングランドの王となったのだった。
しかし当然身の程知らずの弟にロベールは激怒し、国を巻き込んだ兄弟喧嘩は、片方の役者を変えた第二幕に突入する。
結局これは1106年9月に、タンシュブレーという地にて、ヘンリーの方が勝利して、イングランドとノルマンディは再び同じ王を有する事となった(注釈1)
(注釈1)キングでなくデューク
ノルマンディは公国だから、最高権力者の称号は、王でなく公(デューク)が正しい。
女王になれなかった女マティルダ
ヘンリーの子は、息子ウィリアムと娘マティルダ以外は、みな早くに世を去り、ウィリアムも成人する事なく海難事故で死んでしまった。
そこでヘンリーは1127年1月に、娘マティルダを王位継承者に指名し、評議会にもそれを納得させた。
だが1135年12月にヘンリーが死ぬと、いつかのエドワードの時と同じく、王の意とは違った人物が、次王として選ばれる。
選ばれたのはフランス貴族のエティエンヌである。
彼はヘンリーの甥であり、イングランドの貴族たちともそれなりに良好な関係を築いていたので、あっさりと受け入れられ、英語名である『スティーヴン』として、王の座についた。
だがマティルダは、気性が荒く、黙って涙を飲むようなおとしやかな女ではなかった。
彼女は最初は、教会などに、自分の正当な王位継承を訴えたが、聞き入れられず、武力による王座奪回を決意する。
彼女はスティーヴンがイングランドばかりに居座った為に、彼への忠義を弱めたノルマンディ側の貴族たちを味方につけ、イングランドを攻撃。
戦いは長引き、その間に情熱の覚めてしまった母の後を継いだのが、マティルダの息子ヘンリーだった。
そして1153年12月に、彼は「スティーヴンは死ぬまで王だが、彼の死後は自分が王位を継ぐ」という条約を、イングランド側に受け入れさせ、戦いは終わった。
また家族戦争
1154年にスティーヴンは亡くなり、その年の12月にヘンリーは戴冠式を受け、新たな王ヘンリー2世となった。
ヘンリー2世は、母マティルダ派閥の貴族が多かったノルマンディ。
またそのマティルダの夫、つまり父ジョフロワが有していたアンジュー伯の地位も受け継いでいる。
さらに、フランス王ルイ7世の元妃でもある自身の妻、アリエノールが相続していたアキテーヌ領。
そしてもちろんイングランドと、それまでの中でも、最も広大な地域を支配下に置いた王であった。
しかもヘンリー2世は、満足という言葉を知らず、支配の手を隣国スコットランドの所有地域や、海を隔てたアイルランドにまで伸ばそうとした。
しかしこのような領地の更なる拡大はあまり上手くいかず、しかも欲張った広範囲の独占支配は、結果的に息子たちの反乱に誘発してしまう。
結局最終的には家族をみな敵にしてしまい、1189年7月にヘンリー2世は憎しみを身に感じながら死んだ。
獅子心王と腰抜け王
ヘンリー2世の死後は、三男のリチャードが王座を継いだ。
リチャードは騎士道を重んじ、十字軍で武功を上げるなどして、軍事に優れし王として、ヨーロッパにその名を轟かせた。 しかし、その武勇から『獅子心王(クール・ド・リオン)』と呼ばれた彼も、1199年に死に、今度はヘンリー2世の五男ジョンが王となった。
だがこのジョン王は、フランス国王フィリップ2世と揉めてしまい、ノルマンディをあっさり侵略されてしまう。
いつしか彼にも兄のような呼び名がついた。
『腰抜け王(ソフト・スウォード)』と。
マグナ・カルタ
ジョン王は、その後も外交や戦で何度も失敗したが、挑戦心だけは強く、貴族たちに支援を何度も要求し、無駄にした。
そういうわけで貴族たちの反発は強まり、ついには内戦に発展する。
そして1215年6月、戦況が悪いとみるや、ジョンは、貴族たちが提示した、後に『大憲章(マグナ・カルタ)』と呼ばれ、憲法の基礎となる文書を承諾した。
せざるを得なかった。
だがマグナ・カルタには、税や援助金の制限、教会の特権などについての要求が書かれていて、ジョンにとっては決して本心から認めたくはないもの。
結局彼はすぐに承諾を撤回し、1215年8月から、内戦は再開した。
そして、鎮圧も、再度のマグナ・カルタもなく、1216年10月に腰抜け王は死んだ。
だがジョンの死後に、軍は反乱の鎮圧に成功。
新たな王には息子であるヘンリー3世が選ばれる。
議会政治の始まり
即位した時、ヘンリー3世はまだ9歳で、幼い彼に変わって、いくらか政治を成した、有力貴族や聖職者たちの大会議は、後の議会の原型となった。
60年近くも続いたヘンリー3世の治世の大半、これまでの何人かの王と同じく、王と有力貴族たちは、互いの利をかけて争った。
ヘンリー3世は、父ジョン王が失った大陸の領地を取り戻したいと願っていたが、それは結局叶わなかった。
そして幾度もの内輪揉めの末に、ヘンリー3世は、妥協の道を選ぶ事となった。
大陸を諦め、それは王と並ぶものだとし、議会の重要性を認めたのである。
こうしてイングランドの議会政治は始まったのである。
王国の問題は共通問題
1272年にヘンリー3世は死に、33歳の息子エドワードが後を継いだ。
エドワード王は議会システムをさらに一般化させる。
議会は重要であり、「王国の問題は我々の共通問題であり、いかなる場合でも話し合いはしなければならぬ」と貴族たちにも告げた。
ただしその治世も、後半は、スコットランド、フランスとの戦争に、ウェールズの反乱と、度重なる戦いの影響下で、エドワードは議会と何度も衝突しなければならなかった。
プリンス・オブ・ウェールズ
ウェールズ人は反抗心が強く、実は明確にイングランドの支配する土地というわけでなかった。
しかしなんだかんだでイングランドの力は増していた事もあり、エドワードはウェールズを征服。
しかしウェールズ人は、「ウェールズ生まれで、英語を喋れず、罪を置かした事がない者」でないと王とは認めないとしたから、とりあえずエドワードは王とは認められない。
そこで王は、1284年4月26日に、ウェールズのカーナヴォン城で生まれたばかりの我が子エドワード2世を、『プリンス・オブ・ウェールズ(ウェールズの王子)』とした。
生まれたてのエドワード2世はまさしくウェールズ王の条件全てを満たしていたのである。
そして以降、イングランドの王位継承権第一位の者は、このプリンス・オブ・ウェールズの称号を授かるのが伝統となった。
百年戦争と薔薇戦争
スクーンの石
エドワード王の時代には、これまでも時折あったスコットランドとの対立もかなり表面化した。
しかし本格的な戦争となると、規模が小さいスコットランドは不利である。
1296年。
当然のように勝利したイングランドは、スコットランド王が戴冠式に使う特別な石を戦利品として奪った。
『スクーンの石』、あるいは『運命の石』と呼ばれるそれを、エドワードはイングランド王が戴冠式に使うウェストミンスター寺院の玉座に埋め込んだ(注釈2)
スコットランド人の反発は強かったが、こうしてイングランド王は、同時にスコットランド王のようにもなった。
(注釈2)700年後の返却
かなり後になったが、1996年に、スクーンの石はスコットランドに返却された。
王座の剥奪
1307年7月にエドワードが死ぬと、スコットランドは実質解放された。
エドワード2世はスコットランドにあまり興味を示さず、石なしではあったが、新たなスコットランド王も誕生した。
この事は、スコットランドに新たな土地を獲得した有力貴族たちの反感を買う。
さらに一部の側近を優遇するなど、彼には王としての配慮が明らかに欠けていた。
結局、最終的にエドワード2世は議会による王位を剥奪されてしまう。
1327年の事であった。
スコットランド、フランスとの確執
全王と違い、14歳で新たな王となったエドワード3世は、それなりに有能な王とされた。
しかし王位継承から10年ほどしてから起きた、フランスとの長い戦争には非常に悩まされる事となる。
1329年にスコットランド王ロバート1世が急死した隙をつき、エドワード3世は、1世が手にいれたスコットランドを再びイングランドのものにしようと画策、
しかしフランスがスコットランド側の肩を持った事から、新たな対立が発生。
そしてフランスが、自国内のイングランド王領であるアキテーヌとポンティエの没収を宣言した事を直接のきっかけに、両国は開戦。
これが後の世に語り継がれる『英仏百年戦争』の始まりであった。
 「英仏百年戦争」王家と英雄、原因と意味。領地と王位を賭けた連続の戦い
「英仏百年戦争」王家と英雄、原因と意味。領地と王位を賭けた連続の戦い
ブラック・プリンス
1339年9月。
エドワード3世は、フランスへの進軍を開始。
戦いは長引くも、たいていイングランド有利に進んだ。
しかしその勢いのままイングランドが勝利するより前に、予期せぬ事態が、戦いを泥沼化させる。
1348年頃からヨーロッパ全土で、『黒死病』、あるいは『ペスト』という伝染病が猛威を奮い、多くの命が失われたのである。
だが病気という共通の敵に苦しめられながらも、両国は戦いを止めなかった。
1356年には、黒い甲冑を好んだ事から『黒太子(ブラック・プリンス)』と呼ばれたエドワード皇太子が、フランス王ジャン2世と激突。
華々しく勝利した彼は、未来を期待されるも、しかしエドワード4世にはなれなかった。
1376年に彼は赤痢により死んでしまう。
強いショックを受けたエドワード3世も1977年にその生涯を終えた。
ふたりの少年王
新たな王は黒太子の子であるリチャード2世がついた。
この10歳の少年王の誕生から、3年後には、何の因果か、フランスの王も11才のシャルル6世がついた。
そして1394年に、リチャード2世が、シャルル6世の娘イサベルを妻として迎えた事から、イングランドとフランスの間に28年もの休戦条約が結ばれる。
しかしこのつかの間の休戦対策が、いくつかの有力貴族の反感を買ってしまう。
そこで1397年、リチャード2世は、危険分子となりうる、有力者たちをみな処刑か追放したが、その中には従兄のダービー伯ヘンリもいた。
ランカスター家の財産
1398年。
ダービー伯ヘンリは、父であるランカスター公爵ジョンが亡くなったので、その権利や土地の継承の為に、追放の免除を王に申し出た。
しかし王は、ヘンリの願いを聞き入れなかった。
イングランドでも特に裕福であったランカスター家の財産に目が眩んだ為とも言われている。
何にしてもこれは失策であった。
権力を持って土地を奪われるかもしれないという恐怖と、権力の乱用という王座剥奪の正当な理由を、有力貴族たちに同時に与えてしまったからだ。
1399年にリチャード2世は王座を剥奪され、ダービー伯ヘンリが、5代前のヘンリー3世の正答な後継として、新たな王ヘンリー4世となった。
フランス戦線
ヘンリー4世は、財政的な問題を考慮し、フランスとの戦いには消極的な立場だったが、息子のヘンリー5世は違った。
1413年に死んだ父から王位を継いだヘンリー5世は、熱心なキリスト教徒であり、自分は神に守られているからと、何事にも強気だった。
そして1415年。
かつてジョン王によって失われたフランスの領地を取り戻すために、ヘンリー5世は、フランスに軍を送った。
それからヘンリー5世は、何度もフランスを打ち負かしたのだが、戦争には勝っても、病気には勝てず、1422年に病死した。
薔薇戦争
早くに死にすぎた父を持つヘンリー6世は、王位を継いだ時、まだほんの赤ん坊であり、その為か、大人になってからも、政治にはいまいち疎かった。
精神的にも脆く、1453年7月に、カスティヨンという地で、イングランド軍が大敗したとの報を聞いた時、彼は重い精神病を患ってしまう。
そこで、エドワード3世の血筋であるヨーク公爵リチャードが台頭する。
彼は精神的に崩れたヘンリー6世から、王座を奪おうとしたのだ。
しかしヘンリー6世の妻、王妃マーガレットは、それを許すまいとして、今度は内戦が始まった。
それは赤バラを印とするヘンリー6世のランカスター家と、白バラを印としたヨーク家の、戦いであり、『薔薇戦争』と呼ばれるようになる。
百年戦争終結
内戦は、結果的にはヨーク家の勝利に終わったが、戦いの中でヨーク公リチャードは死んだ。
そこで、一時的なヘンリーの王座奪還などの試練を越えて、1471年、新たな王には白バラ派閥の中でも有力な、ウェールズ辺境伯エドワードが就く事になる。
エドワード4世を謳った彼は、内戦に決着が着いたとみるや、すぐフランスに目を向けた。
しかし特に戦果は上げられず、両国はにらみ合いの末に、結局1475年に和平を結び、百年戦争は幕を閉じたのだった。
赤薔薇の逆転劇
エドワード4世はロマンチストだったようで、あまり身分の高くないウッドヴィル家のエリザベスと結婚した。
そのおかげでウッドヴィル家は成り上がったわけだが、そのせいで元々の有力貴族たちからの嫉妬や憎しみにもさらされる事となる。
1438年にエドワード4世が死ぬと、エリザベスとの息子エドワード5世が王となったが、その時、既に彼と、成り上がりのウッドヴィル家の周りは敵だらけであった。
すぐにエドワード5世の王位は剥奪されて、エドワード4世の弟であるグロウスターが、リチャード3世として代わりの王となった。
ところがリチャード3世はあまり政治の腕には優れておらず、国内はあっさり混乱をきたした。
この混乱の隙を、ヘンリー6世の血をひくヘンリー・チューダーが突く事になる。
フランスに亡命しながら、ランカスター家再興を夢見ていた彼は、1485年8月に、イングランドに攻めいった。
そしてヘンリーは戦いに勝利し、薔薇戦争もこれにて終結となったのだった。
グレートブリテン連合王国への歩み
計算高き王
1485年10月30日。
戴冠式を終えて、ヘンリー・チューダーはヘンリー7世として、正式に王となった。
彼はその治世の間、白バラ派閥の生き残りによる反乱や、百年戦争と薔薇戦争で弱った国力など、苦難にさらされ続ける。
しかし持ち前の計算高さで、新興の強国スペインに取り入るなど、彼は王として上手く機能した。
そして1509年4月。
ヘンリー7世は世を去ったが、生前の根回しのおかげで、皇太子ヘンリー8世の即位はスムーズにいった。
イングランド教会と女王の誕生
ヘンリー8世は男の子になかなか恵まれなかった。
別にイングランドは法的に女王を禁止してはなかったが、過去に例はなく、また戦場に王自らが出向くような時代である。
女王の存在には不安があった。
そしてヘンリー8世は、妻キャサリンが40歳を越えた時に離婚を決意するが、教会はそれを認めてくれなかった。
そこでヘンリー8世は、チューダー家の血筋を守るために、大陸の教会と決別し、イングランドに独自の『イングランド教会』を作り、自分の離婚を認めさせた。
しかしそれでもなかなか男子は生まれず、ヘンリー8世は次々に新しい妻を迎えた。
捨てられた妻は単に離婚でなく、罪を着せられ処刑されたりもした。
そこまでして無事に生まれた男子は病弱なエドワードのみであった。
そして1547年にヘンリー8世が死んだ後、少年王として王座を引き継いだエドワード6世は、早くも1553年に病死してしまう。
そこで王位を継いだのが、エドワードの姉メアリーであり、彼女は最初のイングランド女王となった。
付き合い上手なエリザベス
メアリーは熱心なカトリック教徒であり、父が自国に勝手に作った教会を好ましく思っていなかった。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
しかし既にイングランド教会という思想は国民たちの心に根付いており、イングランド教会の信者を異端として処刑も辞さなかったメアリーは『ブラッディ(血まみれ)メアリー』と呼ばれ、恐れられた。
その彼女も1558年11月に死に、次世代はまたしても女王の治世となった。
ヘンリー8世の子で唯一王位継承権の残っていた、メアリーの妹エリザベスが新たに女王となったのである。
エリザベスは外国語に通じて、外交自体も上手く、しっかりと地に足をつけ、現実を見る事の出来る女王であった。
権力を奪われる可能性から生涯結婚もせず、姉によって失われかけたイングランド教会を建て直し、それでいてイングランドの財政状況を出来る限りで改善したのだ。
そして1603年3月に、彼女も世を去った。
連合王国の夢
正統な跡継ぎを残さなかったエリザベスだが、生前に継承者をしっかり指名していた。
スコットランド王ジェームズ6世である。
これまで何度も敵として争ってきたイングランドとスコットランドだが、この両国が同じ王を有したのは見事に転機となった。
ジェームズはイングランドとスコットランドだけではない。
それにもうひとつ、海で分けられたアイルランド王国をも取り込んだ『連合王国(ユニオン・キングダム)』を夢見ていたのである。
 アイルランドがイギリスの植民地として支配された経緯「中世のアイレ」
アイルランドがイギリスの植民地として支配された経緯「中世のアイレ」
だが宗教上の対立や、民族間の劣等感も邪魔して、この夢は夢に終わった。
革命と虐殺と
1625年。
ジェームズが死ぬと、息子チャールズが王となった。
彼はあまり争いを好まず、『平和王』と呼ばれた父に比べるとずいぶん強引なやり方を好み、イングランドの歴史において、久々に議会を無視した絶対王政的な政治を繰り広げた。
だが、そんなやり方が、革命派と王の戦いという内戦を招き、スコットランドとアイルランドもそれに関わった。
結局チャールズは革命軍に捕らえられ、1649年1月に処刑された。
しかし革命派を支持する者も多かったスコットランド、アイルランド両国は、この処刑に関して一切の相談をされなかった事に激怒した。
両国はチャールズの長男をチャールズ2世としたが、これに納得できなかったイングランドの革命軍は、スコットランド、アイルランドとも戦いを決意。
この戦いに敗れたスコットランドは、1654年4月にイングランドと合併した。
悲惨だったのはアイルランドで、一般市民も含め大虐殺された挙げ句、国土の半分近くを植民地化されてしまう。
それからしばらくは王不在であったイングランドだが、結局チャールズ2世が王座に帰還する形で、王国に戻った。
実は他国でカトリックに改宗していた彼だが、1685年2月に世を去るその寸前まで、その事を口外しなかったという。
あるいはイギリスの誕生
チャールズ2世は非常に懸命であった。
次代のジェームズ2世もカトリックであったのだが、その事を隠しはせず、それが常に争いの火種を蒔いていた。
そんなだから、ジェームズ2世は1688年に追放され、次の王には、長女メアリーのオランダ人の夫ウィレムがなった。
だがふたりの間に子が育たず、さらに次に王位を継いだメアリーの妹アンも、跡継ぎを育てる事が出来なかった。
 「オランダ」低地国ならではの習慣と特徴。水と風車と倹約家主義
「オランダ」低地国ならではの習慣と特徴。水と風車と倹約家主義
アン女王はその治世(1702~1714年)の間に、今だ完全に成されてなかったイングランドとスコットランドの完全合併の話を推し進め、これは1707年5月に実現。
ここにウェールズ、アイルランドの半分ほど、それにスコットランドにイングランドを含む『グレート・ブリテン連合王国』がついに誕生したというわけである。
暗黒時代と黄金時代
ドイツ人王と初代首相
1714年にアン女王が死ぬ少し前。
本た来の王位継承者であるジェームズ1世の孫娘ゾフィーも死んでいた為に、彼女の長男、ドイツ北のハノーファー候ゲオルグ。
彼がジョージ1世として次の王となった。
英国最初の首相と呼ばれるロバート・ウォルポールもこの時代の人である。
1720年、スペイン領の南アメリカとの貿易失敗により、大暴落したロンドンの金融市場を、上手くカバーした事で、彼は立場を強めた。
ウォルポールは、ジョージ1世と、その次の2世とも良好な関係を築き、21年に渡って、政治の場を取り仕切ったのである。
ウォルポールの21年は、彼にまとめられた政治家たちにも、彼に頼る事で政治の表舞台には出なくなった王にも、首相という存在を認識させるに十分であった。
及びアイルランド連合王国
1760年10月に、王は、ジョージ2世から3世となった。
もう彼の時代からは、王は戦場に姿を見せる事が一切なくなり、「スピーチが王の仕事」と言われるような時代も近づいてきていた。
変化もいくつもあった。
1760年代から、イギリスでは世界に先駆けた産業革命が起こり、この国は農業国から、産業国へと姿を変えつつあった。
また1783年には、遠く、アメリカが独立して、イギリスは実質的に多くの領地を失ってしまう。
そして1792年、フランスにて起きた革命戦争の影響はヨーロッパ中にあった。
 「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
アメリカ独立と同じ1783年に、24歳という若さで首相となったウィリアム・ピットは、カトリック国フランスが、同じくカトリック教徒の多いアイルランドを取り込む事を恐れ、先手を打つ。
つまりまだ独立状態にあったアイルランドを、グレートブリテンに合併したのだ。
1801年1月の事。
グレートブリテンは、『グレート・ブリテン及びアイルランド連合王国』となったのである。
ヨーロッパの危機
1804年5月。
フランスで、ナポレオン・ボナパルトというカリスマが、圧倒的な支持を受けて皇帝となった。
ナポレオンはその野心を持ってヨーロッパ征服に乗り出すが、最終的には敗北。
1815年2月。
ナポレオンはイギリス領のセント・ヘレナ島に流され、ヨーロッパ全土の危機は去った。
イギリスはこのナポレオン危機を乗り越える上での最大の功労者として、各国の称賛を受ける。
一方でこの時代は、産業拡大と同時に、黒い企業も増えて、労働者たちのストライキや暴動が相次いだ。
つまりかなり不況な時代であった。
派手好きの嫌われ者とカトリック
1820年から10年間、王座についたジョージ4世は派手好きで、その豪華な戴冠式は、不況に嘆く国民たちには非常に不評だった。
また、不仲であった王妃キャロラインへの扱いも、国民を刺激した。
彼はイングランドに独自の教会まで作って妻と離婚した、いつかの王と同じように、でっち上げた罪を根拠に、王妃と離婚しようとするが、世論という圧力がそれを許さなかった。
かつてと比べて、民衆の声や意識はずいぶんと強くなっていたらしい。
それに首相を中心として、独立し始めた政治。
1829年には、王が頑なに反対していた、弾圧されるカトリックの解放も、政治家たちの働きにより実現した。
王がメインに国をコントロールする時代は終わりつつあったのである。
妖精女王ヴィクトリア
ジョージ4世の死後、弟がウィリアム4世として後を継ぐが、彼の治世も7年ほどで終わり、さらなる跡継ぎは、1837年、ウィリアムの姪であるヴィクトリア姫が選ばれた。
国民は、即位当時、まだ18歳のこの少女王を『妖精女王(フェアリー・クイーン)』と称して、大歓迎した。
そしてこの妖精女王の治世はまた、イギリスという国が、最も栄え、大帝国と呼ばれるようになった、黄金時代でもあった。
経済改革と領土拡大
ヴィクトリアが女王となった時点では、イギリスの経済状況はドン底だった。
だが、1830年代から40年代にかけて、活躍し、首相にもなったロバート・ピールの、国益優先の政治改革などが功を奏する。
産業界出身であるピールは、貧乏人にまで課せられていた曖昧な税を廃止し、個々人の収入によって額が上がる所得税の導入など、金の巡りを見直し、悲惨な経済状況を回復に向かわせた。
また、1840年から2年にわたり繰り広げられたアヘン戦争などにより、この時代、イギリスは中国との交易も広げていく。
インドなどはまるごと植民地にしてしまい、アジアに帝国領土を広げていった。
順調に、永遠のような帝国が築かれつつあった。
そう考える人も大勢いた。
世界対戦と帝国の解体
1901年にヴィクトリア女王が死ぬ頃には、大英帝国は繁栄の極みにあり、地球の陸地の2割ほどを支配していた。
しかし1904年に起きた日本とロシアの戦争が、日本が善戦の末、ロシアに大打撃を与える、という劇的な結末を迎える。
このアジアのちっぽけな国の大勝利は、世界中で白人の強国に支配される国々に勇気を与え、大英帝国の植民地でも独立運動が加熱する。
そうした中で、1914年6月28日、オーストリア大公フランツ・フェルディナンドがバルカン半島のボスニアで射殺された事件をきっかけに第一次世界対戦が勃発。
さらに1939年から1945年にかけての第二次世界対戦と会わせ、2度の世界対戦での各地の戦いは、各地の独立心を高めた。
そして1947年8月に、イスラム教徒中心のパキスタン、ヒンドゥー教中心のインドの2国に別れる形で、インド帝国が独立。
さらに翌年1948年には、ミャンマーとスリランカも独立。
1949年には、北を除くアイルランドの大半も『アイルランド共和国』として独立。
グレートブリテン及びアイルランドは、『グレートブリテン及び北アイルランド』になってしまう。
 「イギリス」グレートブリテン及び北アイルランド連合王国について
「イギリス」グレートブリテン及び北アイルランド連合王国について
結局、世界征服?
インド独立以降、世界中で植民地の独立は続き、現在のイギリスは、地図の上ではずいぶん小さくなってしまった。
単純な大きさだけなら、ヨーロッパが世界だった時代より上かもしれないけど、そのくらいの時代にも、多分世界全土からの比率で考えるなら負けている。
しかしある意味で、イギリス、というかイングランドは、世界征服を果たして、それは今も続いているとも言える。
現代人ならたいてい知っているが、この世界の共通語は英語。
そして今は科学とコンピューターの時代である。
科学論文は英語で書かれる。
そうしなければ、いかに優れた発見があっても世に広くは知られない。
そしてコンピューターを操る為のプログラム言語はたいてい英語基準である。
共通語としての英語は、まさに大英帝国の最大の功績であろう。
英語がわかる人たちにとってはだけど。