天竺とは明らかに異なる領域である震旦
今昔物語は全体として、天竺(インド)、震旦(中国。Cīnasthāna。チーナスターナ)、本朝(日本)の話に別れているとされるが、ここでは、震旦編の興味深い物語を取り上げる。
多くの話が、仏教(佛教。Fójiào)に関するものだが、仏教に関するものであっても、中国古来の道教などの要素が入っているものも多い。
 「道教」老子の教えと解釈。タオとは何か、神仙道とはどのようなものか
「道教」老子の教えと解釈。タオとは何か、神仙道とはどのようなものか
似たような話であっても、明らかにインドのそれとは傾向が違っている感じもあり、国ごとの世界観の違いが表れている。
一例として、天竺の物語では功徳を積むことで生まれ変わった後の成功が約束されたりするが、今の世でさっさと救われるということはあまりない感じがある。しかし震旦においては、生まれ変わるまでもなく、今の世の中で救われるという話が多いように思う。
書かれた当時に知られていた世界中の物語を集めたと思われるこの説話集だが、あまり世界観の統一はできていないと言える。当時の人は、それぞれの国、それぞれの世界をどのように感じていて、どういう繋がりがあると考えていたのだろうか。
震旦の仏教伝来秘話
仏教の伝来を邪魔した、秦の始皇帝
(ここから6巻の話)
──秦(紀元前221年~紀元前206年)の始皇帝(秦始皇。Qínshǐhuáng)の時代に、天竺から1人の僧がやってきた。18人の賢者を一緒に連れていた彼の名は釈利房。
国王は彼に尋ねた。「お前はどういう者なんだ? どこの国から来た? 見たところ実に奇怪な姿をしているではないか、頭髪なく丸坊主で、着ているものも人と違っている」
 「秦王朝」始皇帝政の父母、性格、政治政策、最期。統一国家、中華の誕生
「秦王朝」始皇帝政の父母、性格、政治政策、最期。統一国家、中華の誕生
釈利房は答えた。「西方の国に浄飯王(纯米王。Chún mǐ wáng)という大王がおられました。その方に1人の太子がおられ、その名を悉達太子といいました」
その太子が、家を出て、6年間の苦行の末に、無上道(悟り)を得て仏となったこと。彼が80歳でついに入滅(生死を超越)したこと。そして自分が、その教えを伝えようがためにやってきたことを話した。
だが国王は言った。「わしは仏なるものは知らないが、とにかくお前のその姿は実に不快だ。追放すべきだが、ただ追い返すわけにもゆかぬ。牢獄に入れて、処罰しよう。今後かような奇怪なことを口にする連中への見せしめにするためだ」
そうして釈利房は、いくつもの鍵付き扉で閉ざされている、重罪人を収容する牢に入れられてしまった。
 「釈迦の生涯」実在したブッダ、仏教の教えの歴史の始まり
「釈迦の生涯」実在したブッダ、仏教の教えの歴史の始まり  「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
牢の中で、釈利房は嘆き悲しみながらも祈る。「私は仏の教えを伝えようとこの国にやってきたが、ここの悪王ときたら仏法を知らぬ。そのために私は重罪まで被ってしまった。なんと悲しいことか。我が大師、釈迦牟尼如来(释迦如来。Shì jiā rúlái)よ。あなたが入滅されてから長い月日は経っていますが、その神通力によってこの私の苦難はご存知でしょう。どうか私のこの苦しみをお助けください」
するとその夜、虚空より、釈迦如来が黄金の光を放つ仏像姿で現れて、 牢の扉を踏み破り、中の釈利房を連れ去った。そしてその時に、18人の賢者たちも逃げ去った。 ついでに騒ぎに紛れて同じ道路に捕らわれていた多くの出会いにたちもそれぞれに逃げ去ったという。
この出来事を目撃した牢の役人から話を聞いた国王は、かなり恐れた。
こういう訳で、この時代に天竺から渡来してくるはずだった仏法は、渡来せず終わった。
実のところ、周の時代に、仏典はこの国(震旦)に渡来していた。また阿育王(アショーカ王。Āyù wáng)の造った塔もあった。
秦の始皇帝は多くの書物を焼いたのだが、その中には仏典もあったという。
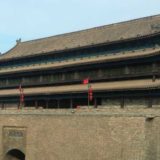 「周王朝」青銅器。漢字の広まり。春秋時代、戦国時代、後の記録
「周王朝」青銅器。漢字の広まり。春秋時代、戦国時代、後の記録
秦の時代の仏教が伝来、しそうだったがしなかったという伝説の話。始皇帝が普通に悪王扱いだが、この当時も、そういうイメージが強かったのだろうか。
始皇帝が、僧の容姿を不快としていたのはなぜたろうか。坊主頭というのは、それほどにおかしな髪型だったのだろうか。
また釈迦は、地上からいなくなってからでさえ、その神通力によって、弟子たちのことを知っているようである。
法師と道士の術競べ
震旦において、後漢(25年~220年)の明帝(28~75)の頃(57~75)。この帝が、夢の中にて、金色に輝く何者かを見た。
目覚めた皇帝が、知恵ある大臣に夢について尋ねると、大臣は「それは他国から、尊い聖人がやってくるということでありましょう」と答えた。
しばらくして天竺から、摩騰迦(kāśyapa mātaṅga)と、竺法蘭という2人の僧がやって来た。彼らは持参していた仏舎利と経典をそっくり皇帝に献上。皇帝は、期待通りに僧たちがやってきたことを心から喜び、深く帰依した。
だがそのことを承服できない大臣、公卿は多くいた。さらに数多いる五岳(Wǔ Yuè)の道士たちは、「我々が奉ずる道教(Dàojiào)を、国内の者たち、上中下のことごとく、昔から国をあげて尊んできたのに。突如外国からやってきた、容貌も衣服も異なる、訳わからない者たちがつまらぬ書物を持ってきたのを、皇帝が喜ばれるとは、実に面白くない」と嘆いた。
ここではしかし、摩騰法師を深く尊んでいて、仏舎利と経典を納める寺を作って、彼を住まわせてやった。
ある道士はそれを見て、皇帝に対して提案する。「外国から坊主頭の怪しい奴が、つまらないことを書いた書物や、仙人の骸骨など持って渡来しましたが、そんなことを尊ばれるとは奇怪なことです。あんな坊主頭、どれほどのこともありますまい。我らの奉じております道教は、過去未来のことをよく占い知り、人の将来に起こる善悪のことを相し、その誤りないこと神のごとき教えです。しかし今まさにそれが廃棄されようとしているように見受けられます。ここでその坊主頭と、力量競べをさせてください。それで、勝った方を尊び、負けた方を破棄したらよろしかろうと思いますが」
まだ外国からやってきた僧の力量の程を知らない皇帝は不安になったが、当の摩騰法師はわりと余裕であった。「私の信仰するところの仏法は、昔っから術競べをして、人にあがめられてきました。この際対決して、勝ち負けのほどをご覧になるのもよろしかろうと存じます」と。
 「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
術競べの当日。
ただ1人だけの大臣が寄っていただけである摩騰法師と向かい合うは、老人から血気盛んな若者まで、2000人ほどの道士たち。その道士たちの各々が、その道の学識を十分に磨き抜き、昔の達人に恥じぬ者たちである。多くの大臣や公卿たちも、百官を引き連れて、道士たち側の席に寄り集まっていた。
摩騰法師は、仏舎利を入れた瑠璃の壺と、経典を入れた箱を持ってきていた。
そして2つの陣営のそれぞれは、術を仕掛ける時を待っていたが、やがて道士の方がまず、「そちらの方から我々の経典に火をつけてみよ」と言った。
すると摩騰法師の方から、1人の弟子が出てきて、道士たちの経典に火をつけた。続いて道士たちの方からも、代表が1人出てきて、摩騰法師の持ってきていた経典に火をつける。瞬く間に周囲に黒煙が溢れた。
そのうちに、仏舎利が光を放って空に昇っていく。経典もそれに続くように空に昇り、虚空にとどまった。摩騰法師は、香炉を手にしたままで、しばらくもそれから目を放たずにいる。
一方、道士の方の経典はあっという間にみんな燃えつきて灰となった。
道士たちの中には、血の涙を流す者、鼻血を出す者、気絶してしまう者、席を立って走り出す者、法師の方にやってきて弟子入りを志願する者、悶え苦しみ正気を失う者もいた。あるいは舌を噛み切って死ぬ者すらいた。
そして、そのような様子を見た皇帝は、涙を流して席から立ち上がり、法師を礼拝した。
その後、諸経典は漢の地に広まって、仏法は今に至るまで栄えている。
震旦への、仏教の伝来話。
釈迦や、その後を継いだ者たちが、その術の力を持って、天竺により古くから存在しているバラモンたちの術を打ち負かす話の、震旦版とも言えよう。震旦という異国の地に仏教を伝えようとしてやってきた摩騰法師は、道教の達人たちと術を競いあい、勝利する。
ただ、嵐を起こしたりとか、そういう派手なものではなく、術競べというか、経典比べと言ってもいいくらいかもしれない。
道士たちが言う五岳というのは、道教の聖地である5つの山。すなわち、山東省の東岳泰山(东岳泰山。Dōng yuè tàishān)、陝西省の西岳華山(西岳华山。Xīyuè huàshān)、湖南省の南岳衡山(Nányuè guāngshān)、山西省の北岳恒山(Běiyuè héngshān)、河南省の中岳嵩山(Zhōngyuè sōngshān)のこと。
祈りによって出現する仏舎利
天竺に康僧会三蔵という聖人がいて、仏法を広めようと、震旦の呉の国にやってきた。しかし三宝(仏、法、僧)にまだ知られていなかったその国で、三蔵は怪しまれる。
 「魏呉蜀の成立」曹操、孫権、劉備。三国時代を始めた人達の戦い
「魏呉蜀の成立」曹操、孫権、劉備。三国時代を始めた人達の戦い
三蔵は国王に「私は西の国の釈迦仏の弟子ですが、衆生のため、多くを説き置かれてご入滅になられた、その仏の教えを伝えるために、ここに来ました」と言った。
王は「釈迦仏がすでに入滅されているとすれば、そなたは誰を師と仰いでいるというのじゃ」と返す。
「仏はすでに入滅なさったとはいえ、仏舎利を残して、それにより衆生を導いておられます」と答えた三蔵に対し、当然、王は「その仏舎利はどこか」と聞くが、三蔵は「天竺にです。持ってきてはいません」とさらに答えた。
そして、仏舎利の実物がないために、話をあまり信じようとしない王に対し、三蔵は告げる。「例えここに仏舎利がなくとも、祈念し、奉ったならば、それは出現します」
王は、「ならばここで、仏舎利を、祈り出現させてみるがいい」と言った。
そうして、「仏舎利が祈りによって出現しなかったならば、この首をお取りになればいいです」と自信満々な三蔵に対し、「7日の期限内で仏舎利を出現させよ」という勅命が下された。
紺瑠璃の壺を机に置き、花を散らし、香を焚き、三蔵は祈った。
やがて期限の7日が経った後、三蔵はもう7日延長してもらって、それでも舎利は出現しないので、さらに7日延期してもらう。そして2度目の延長期間の6日目の夜に、瑠璃の壺の底に、光輝く大きな仏舎利が一粒出現した。
その仏舎利が本物かどうかを怪しむ王に対し、三蔵は「本当の仏舎利は、火で焼かれず、金剛杵でも砕けません」と説明。実際にそうだったため、王は心から信服。「1つの寺を建立して、この仏舎利を安置なさるがよろしかろうと思います」という三蔵の言葉に従って、王は寺を建て、『建初寺』と名付けた。
三国時代の呉の国への仏教伝来話。
この話の康僧会のように、『三蔵(Tipiṭaka。ティピタカ)』という僧は多いが、三蔵とは、仏教の3種の聖典の総称。すなわち、仏の説法を集成した『経蔵(Sutta pitaka。スッタ・ピタカ)』、仏徒の戒律を集成した『律蔵(Vinayapiṭaka。ヴィナヤピタカ)』、経典の注釈集で研究書である『論蔵(Abhidhamma piṭaka。アビダンマ・ピタカ)』。
また、三蔵を翻訳する者、それらの教えによく通じている者も、三蔵と呼ばれる訳である。
仏舎利に関して、もしも全部釈迦が死んだ時のものなのだとすれば、あまりにも世界中で多すぎるのではないか、という疑問がある。しかし、このように祈りとかで出現するものならば、どんどん増えていくものなのかもしれない。
玄奘三蔵の物語
震旦の唐(618~907)の玄宗という皇帝の代に、玄奘法師という聖人がいた。
玄奘は天竺へと向かっていたが、広々とした野を通っているとき、日が暮れてしまった。宿を取るところもなく、足の向くまま歩いていると、はるか遠くから多くの火を灯した松明を持った者が500人ほどやってきた。
「人に会えた」と玄奘は喜んで近寄ったが、しかしそれは人ではなく、なんと異様な姿をした恐ろしい鬼たち。玄奘はとにかく、天竺へ向かう道中で授けられた経典である『般若心経』を唱えた。そして、このお経の声を聞いた鬼どもは、四方八方に一目散に逃げ去ったという。
玄奘が般若心経を得た経緯は、以下のようなものである。
どこかの深山を通っている時。いつしか鳥も獣もやって来ないような場所へと玄奘は迷い込んだ。そして、どうにも耐え難いような臭さに気づき、それの発する場所に近寄ってみた。
そこでは、獣もいないどころか、草木も枯れていた。それに死体が1つ横たわっているようだった。「これが臭いのもとなのだろう」と思いながら見ていると、かすかに死体が動いている。「では生きてるのか」と考え、玄奘は事情を聞いてみようと傍に寄ってみた。
「そなたはどういう人なのです? どんな病気にかかってこのように倒れているのですか?」と声をかけると、病人は「私は女ですが、瘡(腫れ物)の病にかかり、頭から足の裏まで隙間なく瘡ができて、全身がただれ、耐え難いほどの生臭い臭いを発してしまうのです。父母も嫌がって、このような深山に私を捨ててしまったのです。けれども、寿命もまだ尽きず、こうして息も絶えずにいるのです」
彼女に心から同情した玄奘は「そなたが家にいる時、本当に誰もその病気の薬を教えてくれなかったのですか?」と聞いた。
女は「1人の医者は、「頭から足の裏まで膿汁を舐め吸ってもらえれば、即座に治るだろう」と言っていましたが、この耐え難い臭さのために私のそばに近寄る者もありません。まして舐め吸ってくれるなんてあろうはずもありません」と語った。
玄奘は涙しながら「そなたの身はまさに不浄のものとなっている。私の身は見たところでは不浄ではないが、思えばこれも不浄です。それゆえ、同様に不浄の身である私が、自分だけは清浄と思い、他の者を汚く思うなど極めて愚かなこと。だから私が、あなたの体を舐め吸ってその病を治してあげましょう」と言ったが、それを聞いた女は非常に喜び、自らの身を彼に任せた。
その泥のような皮膚から発する臭さを、玄奘は深い慈悲の心から、臭いと思いもしないで、膿んでいるところから膿汁を次々吸って、吐き捨てていった。すると、舌の跡がついた女の部分は、普通の皮膚に変わっていき、ついにはその病気もすっかり消えた。
喜ぶ玄奘の前で、その病人だった女は光り輝く観自在菩薩(Avalokiteśvara)に姿を変えた。玄奘は思わず膝を地につけて掌を合わせて拝む。菩薩は言った。「そなたは真の清浄、誠実な聖人だ。わしはそなたの心を試すために病人の姿で現れたのだ。そなたは実に尊い。ところで、わしには日頃から信奉している経があるのだが、それを今そなたに譲り与えよう。これを受け取って、はるか後の世まで広め、衆生を導くがよい」
そうして、玄奘は般若心経を与えられたのである。
やがて玄奘は、『摩訶陀国(Magadha)』に着いて、『世無厭寺(Nalanda。ナーランダー大学。那爛陀寺』という寺に入って、正法蔵とも称される戒賢論師(Śīlabhadra。シーラバドラ。529~645)の弟子となった。
その後、さらの他の国に行こうとした玄奘は、『恒迦河(ガンジス川)』を下る船に乗っている時に、盗賊たちに捕らえられてしまう。
その盗賊たちは突伽天神(Durgā。ドゥルガー)に仕えていて、毎年の秋頃に、1人の美しい人間を生け贄としていたが、そのために彼らは、美しい法師を見つけて喜んだ。
だがまさに、彼の処刑の時、真っ黒な風が四方から吹いてきて、川の水が高く逆立ち、盗賊たちは仰天する。そして他の船客から、 自分たちが今殺そうとしている法師が「支那の国から仏法を求めてやってきた人」と聞き、風や波が荒れるのは、天人が激怒したためだと悟る。
そして、盗賊たちは奪ったものを全て返して、「悪行はもうきっぱりやめます」と、法師に誓った。するとようやく風波はおさまった。
様々な霊場に参詣した後、帰国しようという玄奘は、彼に帰依していた天竺の戒日王(Harsha Vardhana。ハルシャ・ヴァルダナ。590~647)から多くの財宝を与えられたが、その中に1個の不思議な鍋があった。それは、その中に入ってるものをいくら取っても尽きることがなく、また入っているものを食べた人は病気にかからないという、王家に代々伝わる財宝であった。
そして帰りの旅の途中。『信度河(インダス川)』という川を下っていた時に、乗っていた船が突如傾き、多くの教典が水中に没してしまいそうになった。
玄奘は言った。「この船が傾くのは、何か理由があるのだろう。もしやこの船に竜王の欲しがるものがあるというのか? それならば、その証拠が見たい」
すると川の中から翁が顔を出して、「鍋が欲しい」と言った。玄奘は、多くの経典を失ってしまうよりはと、鍋を川に投げ入れた。
それから、震旦に帰ってきた玄奘が伝えた『法相大乗宗』の教えは、今も絶えることなく栄えている。
これはもちろん、西遊記の主人公(?)、三蔵法師として有名な玄奘法師の話。
天竺への旅、天竺での修行、そして帰りの旅までしっかり描かれ、この説話集の中でも長めな話となっている。
ナーランダー大学は、東洋世界最古の大学ともされ、玄奘の時代には、天竺における、学問の聖地だったようだ。
震旦の仏話
釈迦如来像製作に手を貸したために生き返った人
唐の時代。幽州の地に、虞安良という人がいて、長年にわたって鳥獣の殺生を仕事としていた。殺した生き物の数は莫大。そんな彼だが、37歳の時に、ウマ(馬、学名: Equus ferus caballus)から転落して気を失い、そのまま死んでしまった。
しかし半日ほど経つと生き返った彼は、親族たちに涙ながらに語った。
「最初落馬したかと思った時、ウマの頭をした鬼と、ウシ(牛。Bos taurus)の頭をした鬼が大きな車をひいてやってきた。そして俺を掴んで、その車に投げ入れた。車の中は炎が燃えていて、俺の体を焼いたが、とんでもない熱さだった。そしてすぐに、閻魔王(阎王。Yánwáng)のところまでやってきた。
すると突然、1人の尊げな僧が現れました。
閻魔大王はその僧をご覧になるや、即座に手を合わせ、「なぜここにおいでになったのですか」と尋ねた。
僧は答えた。「この罪人は、実はわしの信者である。わしはこの罪人の命を、しばらくの間もらい受けようと思ってきたのだ」
閻魔王はさらに「この男は非常に罪の重い罪人ですが、大師がわざわざここにおいでなさったからには、放免にしないわけにもいかないでしょう」と言い、解放された俺はその僧に連れられ、帰れることになったのです。
それで、「あなたは誰なのでしょうか?」と聞くと、彼は答えました。「そなたは知らぬか。わしはそなたの兄が信仰心を起こして造った、釈迦如来の像なのだ。そなたも銭30枚を出すことで、その像の制作に協力した。そのことのために、わしは今、ここに来てそなたを救った訳だ」
そして彼は姿を消し、俺は生き返れたのだ。今は、これまでの殺生を後悔している」
地上に教えを求めてくる天人
(ここから7巻の話)
ある山寺の比丘は、長年にわたって、『大品般若経』を読誦(お経の音読)し続けていた。
そうしてる間、夜には必ず天人がやってきて、天の『甘露(Gānlù)』を降らして供養した。ある時に、比丘は天人に尋ねた。「天人界にも般若経はあるのですか?」
「ある」と答えた天人に、比丘はさらに聞く。「それならばなぜ、毎度ここにやってきて供養するのですか?」
天人は答えた。「仏法を敬うために来るのです。天上界の般若経は、もろもろの天人たちが伝えてきた言葉なのですが、人間界の般若経は、まさに仏のお言葉を正しく述べたもの。そういうわけで、私はここに来て供養するわけです」
比丘はまた「では天上界では、般若経を常に身から離さないで信仰している者はおりますか?」と聞いたが、天人は「天上界の者は楽しみに執着しているために、身に添えて信仰する者はありませんし、他の『洲』にもありません。ただこの『閻浮提(Jambudvīpa。南贍部洲)』の人は、大乗の機根(仏の教えを聞く才)が十分に熟しているために、よく般若経を信仰して、苦を逃れることができるのです」と答えた。
比丘は「般若経を信仰する人を守護する天人は、あなただけなのですか?」とも聞き、天人は、「信仰する人を守護する天人は80億あります。それらがみな人間界に下ってきて、般若経を信仰する人を守護するのです。1句でも聞く人を敬うことは、仏を敬い奉るごとくです。だから、あなたの守護をやめたり怠ったりすることは決してありません」と答えた。
般若経を信仰して身から離さず、読誦したり、書写したりするならば、その場には必ず天人が来て守護していると知るべきである。という話。
天人が、地上の経典を毎度供養しに来るという、ここまでからするとちょっと妙な印象の話。
供養される甘露というのは、めでたい時とかに天が降らせる甘い雨。
また、天人の言う閻浮提と他の国とは、古代インドにおける、須弥山(sumeru)という山を中心とした世界観における各地域。須弥山を中心として、東西南北に4つの大洲。特に仏教では、東が『勝身洲(毘提訶洲。弗婆提。videha-dvīpa)』、西が『牛貨洲(godānīya-dvīpa)』、北が『倶盧洲(kuru-dvīpa)』、そして南が贍部洲。
仏を恐れて逃げる神々
上定林寺という寺に、普明という僧がいた。
幼い時に出家してから、ずっと清らかな心を持ち続け、常に懺悔の行法を行うことを務めとしていた。余念なく法華経を読誦しては、六牙の白像に乗った普賢菩薩がその場に現れる。『ruby>維摩経 (Vimalakīrti-nirdeśa Sūtra。ヴィマラキールティ・ニルデーシャ・スートラ)』を読誦すれば、伎楽と歌詠が大空を満たした。
ある時に普明が道を歩いていると、誰かが水のほとりで神を祀っていた。そしてそこにいた巫が、普明を見て言った。「神があなたを見て、みんな逃げてしまった」
仏教の世界観では、異教の神々というのが、仏よりも下の存在であるということは確かだが、この話においては、恐れられているような印象がある。
仏の思想の影響を受けた中国世界の昔物語
隋(581~618)の頃、1人の僧が仏法を修行するためにあちこち巡り歩いていたが、やがて『大山廟』という建物に行き着いた。
僧は宿を借りようと思っていたのだが、そこに廟守りが現れて、「ここには廟以外の建物はないから、廟堂の廊下で寝るしかない。だが、ここにきて宿を取った人は必ず死んでいるのだ」と言ってきた。
僧はしかし、「人間が誰しも最後に到達する道であります。私は死など気にしません」と余裕だった。
そうした結局廟内に泊まった僧が、夜にお経を読誦していた時、玉が触れ合うような音と共に、気高く尊げな人が現れ、僧を礼拝してきた。
僧は聞いた。「この廟に宿を取った者は死んでしまうと聞いたのですが、神が人を殺害なさることなどあるはずもないですよね。神よ、何卒私をお守りください」
神は言った。「私は決して人を殺すことはない。ただわしが出てくると、人はわしが身につけている玉の鳴る音を聞いて、その恐怖心から自然に死んでしまうのだ。だから師よ、どうか私を恐れないでほしい」
神といっても、近くで話をすると、それはまるで人と変わらない。
僧はまた聞いてみた。「世間の人々は、大山府君(泰山府君)が人の魂を支配なさる神だと噂していますが、それは事実なのでしょうか?」
神は答えた。「それは事実だ。あなたは以前死んだ人で、会ってみたいと思う人がいますか」
僧は、以前に死んだ同学の2人の僧を見たい、と願う。泰山府君は、「2人のうちの1人はすでに生まれ変わっているが、もう1人は重い罪のために地獄にいる」と告げる。
その後、僧は泰山府君に連れられて地獄へとやってきたが、炎が燃え盛る中、1人の人が火の中にいて、ひたすら叫び声をあげていた。誰とも見分けがつかず、ただただ血みどろ。そして神はそれを指差して「これがあなたの同学の1人だ」と言った。
現世に帰ってきて、「地獄で苦しむ彼を助けたい」という僧に、泰山府君は、「そうしてやるがよい。あなたが彼のために法華経を書写し奉れば、彼も罪を免れることができよう」と説明。
 「隋王朝」賢き皇帝、愚かな皇帝。あまりに早かった滅亡
「隋王朝」賢き皇帝、愚かな皇帝。あまりに早かった滅亡
それからしばらく。言われた通りに法華経を書写し奉った僧が、 その報告をしに再び廟に来ると、また夜に神が現れ、「地獄の空も苦しみから救われた」と教えてくれた。
僧は「ではこの経を、この廟に安置して奉りましょう」と言ったが、神は「ここは正常なところでなく、経を安置するような場所ではない。師よ、どうか故郷に帰って、それは寺にお納めください」と返した。
僧は言われた通りにした。
僧が地獄に行く話であるが、その案内役は閻魔王でも、釈迦でもなく、道教において死を司る神とされる泰山府君。
前世で夫だった老人との再会
隋の時代の頃。
魏州の長官である雀産武(崔彦武)は、ある村に来た時に、いきなり驚き、喜びもした。「わしは昔、前世でこの村に女として生まれ、人の妻となっていた。そしてその家のあった場所も思い出した」
実際にその家の老主人も、読誦し奉った法華経や金の簪を隠した場所など、亡き妻しか知らないはずの話を武がいくらか語ったので、信じるしかなかった。
そして2人は今後の深い関わりを約束し、仲良く語り合った。さらに武は、多くの財産を主人に与えて帰って行った。
雀産武は多分男であろう。
説話集には、多くの前世譚があるが、男の前世が女であるというパターンは結構珍しい。
木像の母
(8巻は欠本。ここから9巻の話)
漢の頃。河内に、丁蘭という人がいた。彼は15歳の時に、自分が幼い時に死んだ母の姿を慕って、彫工に亡き母の姿に似せた木像を造ってもらった。丁蘭は、その木像を本当の母のように敬い、朝も夜も食事をお供えし、外出する時も帰ってきた時もしっかり挨拶した。
しかし丁蘭の妻は性悪で、夫のそういう態度が妬ましくて憎いと思っていた。そしてある時彼女は、その木像の顔を火で焼いた。夢の中に現れた母からその事実を聞いた丁蘭は、以降はその妻を憎み続け、愛情を示すことがなくなった。
それから別のある時。「斧を貸してほしい」と言ってきた隣人に対し、木像の母が反対しているように思えたことから、貸すのを断った丁蘭。しかし激怒した隣人は、後でこっそり家に忍び込んで、木像に斬りつけた。丁蘭が後でそれを見た時、その床には木像から流れた赤い血が染み込んでいた。丁蘭は復讐として、 その隣人を殺して 首を母の墓前に添えた。国王も、その殺害の罪を「孝行のためにしたことだ」と許してくれて、しかも褒美の品と官位まで与えてくれた。
ただの木であっても、母と思って孝行の誠を尽くせば、天地も感動して、赤い血が宿る。という話。
木像の母を敬い、それを斬った相手を復讐に殺す、というのは、血の描写を抜きにして考えると、かなり気が狂っている誰かを描いた話のようにも思える。
この辺りの話は、孝行話が多いのだが、その中でもこの話は、なかなかの残虐性が要素としてあり、霊的な印象も強めな内容。
馬となり、子に飼われる母
隋の頃、洛陽に兄妹がいて、兄はウマを飼っていた。
ある冬の寒い日。墓参りへの道中、川を渡ろうとした時に、このウマがどうしても渡ろうとしないために、兄は鞭を打って馬を叩いた。
一方、家で留守番してた妹のもとに、もうすでに死んでいるはずの母親が、傷だらけの姿で現れて、告げた。「私は生前、お前の兄さんの米を少しばかり盗んでお前に与えた。その罪の報いで、今ウマの身に生まれてしまい、すでに5年の間、お前の兄に対して罪の償いをしているのです。ところが今日、川を渡ろうとしたが、少しばかり水が深いので恐怖で立ちすくんでいた時、お前の兄が鞭で私を叩きました。そうして頭や顔が血だらけになりました。そこで私はお前に訴えます、私の償いはもう終わりに来ているというのに、なぜ何の理由もない苦痛を受ける必要があるのでしょうかと」
娘は驚きながらも、とりあえず母が傷が受けたという部分を書き留めておいた。
そのうちに帰ってきた兄に実際につけられていたウマの傷の部分と、母の語った傷の場所は全く一致していた。それでさっきのことが夢でなかったということを完全に悟った妹は、ウマにすがり泣きじゃくった。兄も事情を聞くと、一緒にウマを抱いて泣き悲しむ。ウマの方もまた涙を流した。
その後、ウマが死んだ時に兄妹は手厚く葬ったが、それはまるで本当の母が死んだ時と変わりなかった。
人が飼っている動物は、みな前世にした事の償いをしようとして家に来ているのではないか、と考えて、あまり酷い仕打ちは加えるべきではないだろう、という話。
イヌたちの怒り
兗州の都督(総司令)であった遂安公の李寿は、若い頃から狩猟が好きで、よくイヌ(犬。Canis)を殺しては、タカ(鷹。Accipitridae)の餌にすることを仕事のようにしていた。
そしてある時、重い病によって死にかけた李寿は、おそらくは夢の中で5匹のイヌと会い、「命をよこせ」と迫られた。
李寿は「お前らを殺したのは、わしの従者たちだ。わしの罪ではない」と言い訳したが、イヌたちは「何で下の者が自分1人の考えでそんなことするものか。我々は人の食い物など盗んだりしていない。建物の前を通り過ぎただけなのに、無体に殺したではないか。この敵はきっととってやるぞ」とさらに怒る。
李寿は必死に「わしの罪はお詫びし、お前たちのために追善供養しよう」と言い、それで4匹は納得してくれたが、1匹の白いイヌだけは「俺は罪もないのに殺された。その上まだ息があるのに、お前は俺の肉を裂いたのだ。その苦しみ、痛みは例えようもなかった。その恨みは忘れることができない。許すことなどできるものか」と、なかなか納得してくれない。
その時、1人の人が現れ、怒りを鎮めぬ白いイヌに言った。「そなたたちは敵を撃ってこの人を殺したからとて、そなたたちのためにいいことなどあるまい。許してやればよい。この人がそなたたちのために追善供養をしたなら、その方が良いことだ」
それで、白いイヌもようやく納得した。
それから李寿は生き返ったが、五体はあまり自由でなく、気分も優れない。以降、彼はイヌたちのために追善供養を営んだが、病気はついに全快しなかった。
殺生の罪がいかに重いかを語る話。このような話が連続する訳だが、 この話のように、作中での殺生が動物に対するものも結構多い。
生まれ変わった存在であるとか、そういうことでもなく、畜生は人間よりも下の存在と考えるのだとしても、とにかく殺すというのはいけないこと、と考えられていたのだろう。
別の話では、タカ狩りを趣味としていた人の妻が、タカのくちばしそっくりの口を持った男の子を産んだという話もある。その子は、すぐさま忌み子と判断され、さっさと捨てられてしまったというが、それは父に対する罰と言えるのか、あるいは母、または子に対する罰と言えるのか。
死者の裁判所
魏郡に馬嘉運という、学識広い人がいた。
ある時に彼の家を、ウマを連れた2人が訪ねてきて、「東海公の使者であり、あなたを迎えに来た」と語った。
それから嘉運が、用意されたウマに乗ろうとした時、彼は死んでしまって、同時にどこかの役所の前に来ていた。大きな門があって、多くの人が何かを訴えるようにそこに並んでいた。1人、すでに死んでいる知り合いの女性がいて、そのために自分も死んだということにも気づけた。
嘉運を門内に連れて入った使者たちは、そのことを東海公に報告するが、公は眠っていて尋問などしようとしない。
次に司刑(刑を司る役人)の前に連れてこられたが、それがなんて、益州の行台朗中であった霍璋だった。
霍璋は嘉運に、「この役所は、書記が欠員になっているのですが、東海公があなたの学識を聞き、ぜひともその役についていただこうと、お呼びしたのです」と告げた。
嘉運は言った。「私は家が貧しく、妻子を養うことさえ難しい状況です。だからあなたがなんとか、私が放免されるようお取り計らい下さいませんか。そうしていただければ幸いです」
すると霍璋も、「そういうことなら、あなた自身が、「私は学識が浅く何の知識もない」と陳述してください。そうしたら私が、わきからそのことを説明しますから」と言ってくれた。
やがて公は目覚め、裁判官の席に座っていた、太って背が低く色黒の彼の前に呼ばれた嘉運。
しかし、霍璋の嘘の証言もあって、彼は無知ということになり、また生き返ることになった。
だが、蘇ってしばらくしてから、嘉運はまた東海公の使者と会った。返された嘉運の代わりに、連れられてきた者の証言によって、霍璋の嘘がバレてしまったのである。彼は責められ、嘉運もまた再び死ぬはずだったが、昔、魚の命を助けてやった功徳のために免れたのだという。
死んだ者の裁判所は、学識ある死者がそれぞれの役目を務めているかのようである。この話の東海公というのは、泰山府君だという説がある。
仏教との関わりをあまり感じさせない話
莫耶の2つの宝剣と、眉間尺の復讐譚
春秋時代(?)に、莫耶という鍛治の工匠がいた。
彼の時代に、国王の后が、夏の暑さに耐えられず、鉄の柱を抱いてばかりいた。そして彼女が懐妊して出産したのは、鉄の玉であった。不思議なことではあったが、とりあえず国王夫妻は莫耶を召しだし、その生まれた鉄から宝剣を造らせた。
剣は2つ造られたのだが、莫耶はその1つを国王に奉り、もう1つは密かに隠しておいた。
ところが国王が持っていた方の剣は、いつも鳴り続けていた。大臣は「この剣が鳴るのには理由があるはず。思うにこの剣は、きっと夫婦二振り造られたものであり、その一方がもう一方を恋い慕って鳴っているのでしょう」と告げた。国王は、もう1本の剣を隠していた莫耶に対して激怒。彼に罰を与えようとした。
一方で莫耶は、夢のお告げにより、自分がおそらく死罪に処せられることに気づいていた。そこで妻に対し言い残しておいた。「今、身ごもっている子供がもし男子だったなら、それが成人した時に、「南の山の松の中を見よ」と伝えてくれ」
その後、生まれた男の子が15歳になった時、その眉間が1尺(30センチメートル)ほどもあったことから、彼は眉間尺という名を受けた。 そして彼は、母から伝えられた父の遺言通りに、南の山を探してみて、そこで1つの剣を見つけた。
その頃、今度は国王の方が、眉間が1尺ある誰かが謀反を起こし、自分を殺そうとしている、という夢を見て、恐れた。
そして、眉間1尺の者の首に懸賞金までかけられた。眉間尺はそのことを知って、深い山中に隠れていたが、勅命を受けた者たちについに見つけられてしまう。
「我々はあなたの首と、持っている剣を探し求めている。そういう勅命を受けた」と言われ、眉間尺はその場で自ら剣を抜いて、自分の首を切り落とした。首を手に入れた彼らは、それを国王に届け、国王は大喜び。
それから眉間尺の首は大釜で煮られることになったが、いくら煮てもその形は全然崩れない。怪しく思った王は、自らその釜の中の様子を見た。するとそのうちに国王の首も自然に落ちて、釜の中に入った。2つの首は、釜の中で上になり下になり互いに食いあって戦った。臣下の者は、それを見て奇異の念を抱きながらも、眉間尺の首を弱らせようと、剣を釜の中に投げ込んだ。途端に、2つの首は形が崩れた。さらに臣下の者も、鍋の中を見ているうちに自然に首が落ちて、釜の中に入った。そこで3つの首が入り交じり、どれがどれかわからなくなった。そのため、3つの首は1つの墓に葬られたという。
おそらく結構なアレンジがあるものの、元から有名な話とされる。時代的に、仏教伝来以前の話でもあるだろう。
刀鍛冶の息子の復讐譚であるのだが、 そもそもの最初から、色々と奇妙な展開が連続する。
始皇帝と巨大な魚
(ここから10巻の話)
秦の始皇帝は、知恵に優れ、剛毅(何事にも屈しないような強い意志と気力)な心で世を治めていた。
彼は前代に行われていたことを全て破棄し、自分独自の政治をしようとした。前代の書籍を集めて焼き捨て、自らの書籍ばかりを世に残してやろうとした。しかし孔子の弟子たちは、前代の書籍の特に重要なものは、そっと隠し、壁の中に塗りこんでおいた。
始皇帝には、とても寵愛している、左驂馬というウマがいた。その体軀(体躯)は竜とそっくりであったという。
ある時に始皇帝は、海で体を洗っていたこの左驂馬が、高大魚(大鮫魚)という、 突如現れた大きな魚に食いつかれ、海に引きずり込まれる。という夢を見た。
それで怒りを抱いた皇帝は、「大海に高大魚という魚がいるが、それを射殺したものには、どんな褒美でも与えよう」と勅命を下した。それで多くの人々がこの巨大な魚を殺そうとしたが、ことごとく失敗。引き返してきた者たちは王に報告した。「海に船を出して、この魚を探しましたが、発見してめ殺すことができません。竜王によって邪魔されるためです」
始皇帝はその後、まずは死の恐れを取り除こうと考え、方士という者を、不死の薬があるという、蓬萊の山(仙境)に向かわせた。しかし数ヶ月ほどで帰ってきた方士は告げた。「蓬莱山に行くことはさして難儀ではありません。が大海に高大魚という大きな魚がいて、これが恐ろしく、蓬莱に行き着くことができません」
始皇帝は「あの高大魚とかいう魚、わしに対して何かと悪を働く奴だ。どうやっても殺さねばならぬらしい」と、またそれを殺すように勅命を下したが、今度は挑戦者もなかなか現れなかった。
始皇帝はついに、自らその魚を殺そうと、大海に船を出した。そして探し出して、その魚を矢で射殺したが、満足して帰る途中に、天の責めを受けたのか、重い病にかかってしまう。
そして始皇帝が死んだ後、息子がその地位を継いだが、大臣に謀反を起こされ死ぬ。さらに後を継いだ孫も、味方を得られないまま46日帝位についていただけで、殺されてしまい、秦は滅亡した。
5色の竜王の子
漢の高祖という人の、母は卑しい素性の者であったが、父は竜王であった。
昔、高祖の母となる女が、池の堤を通っていた時。雷が鳴って、周囲は闇のように真っ暗となった。彼女は恐れてうつ伏せに付したが、雷は突如彼女の上に落ちかかって、その身を汚した。そして彼女は男子を産み、その後に女子も産んだ。
それから数年した後、この母が田植えをしていると、1人の老人がやってきて告げた。「そなたにはとりわけ優れた相があるな。必ず国母となるであろう」
彼女は、「私には決してそのような相があるはずもありませんよ。私は貧しく卑しい素性の者です。どうして国母の相などありましょうか」と答えたが、その時、彼女の2人の子供たちが姿を見せた。
老人はまた、「そなたはこの2人の子のために国母の相を備えているのだ。兄は必ず国王となろう、妹は必ず皇后になるであろう」と告げた。
母を通して聞かされていた老人の言葉を信じ、高祖は「自分はそのうち国王になるのだ」と期待していたのだが、結局世の人に知られることもなく、『芒崵山(芒碭山)』という山に隠れ住むことになった。
そして、その山に常に5色の雲がかかっていることが気に入らなかった秦の始皇帝は、「どのような人物がそこに住んでいるのか。もしも人が住んでいるなら、それを殺せ」という勅命を下したが、高祖は毎回上手く逃げた。
芒崵山の、高祖が隠れ住んでいた木の上には、常に5色の竜王が姿を見せていたともされる。
漢の高祖とは、つまりは、後に秦を滅ぼして、漢という国を建国した劉邦(紀元前256~紀元前195)その人である。
仏教関連の話を終えて、歴史上人物の伝承が多くなってくるが、その最初の方は王族のものばかりである。
楊貴妃の悲劇
唐の時代の、玄宗(685~762年)という皇帝は色を好む人だったが、寵愛していた后と女御が亡くなった後、世にたぐいまれなる美しさを持っていた楊貴妃(719~756)という女に、新しく夢中となった。
帝の楊貴妃への寵愛ぶりは凄まじく、すっかり政治を放っておくくらいであった。そこで政務いっさいは、楊貴妃の親族である楊国忠が行った。
世の人々は、「この世で生きていくには、男の子より女の子の方がよい」と陰口を叩き、嘆いた。
一方、安禄山(703~757)という賢明な大臣がいて、女のために天下が乱れてはならぬと、ひそかに軍勢を集め、王宮に押し入る。帝と楊貴妃は逃げたが、一緒に逃げた楊国忠は陳玄礼という人に殺された。
帝は、「この女を愛するあまりあなたは政務をお執りになられなくなりました。そのため天下が乱れました。この楊貴妃を殺して、天下の怒りを和らげるべきかと存じます」という玄礼の説得にも耳を貸そうとしなかったが、ついに玄礼は楊貴妃も殺した。
帝は、 楊貴妃の亡骸を見てとても悲しいんだが、しかしこうなるのは道理でもあるとわかっていたので、怒りはしなかった。
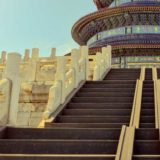 「唐王朝」最も安定していたとされる治世、中国唯一の女帝の影
「唐王朝」最も安定していたとされる治世、中国唯一の女帝の影
それから、安禄山は自ら王宮に入って天下を治めたが、すぐに死んだ。玄宗は御子に位を譲って、自分は太政天皇となった。しかし楊貴妃のことはずっと忘れられず、いつまでも悲しんでいた。
そんなある時、方士という蓬莱を行き通うことができる人がいて、玄宗に言った。「私が帝の御遣いとして、楊貴妃のおられる所を尋ねてきましょうか」
帝は言った。「ならばそちは、楊貴妃の居場所を探し出して、その様子をわしに聞かせてくれ」
方士は了承し、上は空の果てから、下は地の底の国まで探し求めたが、彼女は見つからない。しかしある人が「蓬莱の島の上に大きな宮殿があり、その中に玉妃の大真院というが御殿があり、そこに楊貴妃がいる」と教えてくれた。
そうして方士は楊貴妃と会えて、帝がいつでも彼女を思い出せるように、玉の簪を与えられる。彼女自身と出会えたという証拠にもなる思い出話と共に帰ってきた方士の報告を受けて、しかし帝はさらに悲しみ、少しして亡くなった。
ところで、安禄山が楊貴妃を殺すことになった時も、世の中を正そうがためであったから、帝もそれを対して非難しなかった。昔は、帝も大臣も、道理を心得ていたのである。
玄宗と楊貴妃の有名なエピソードであるが、おそらく非常に重要なのは、この話を説話集の中に記述した者の見解。その美しさのあまり帝に愛され、しかし最後には殺されてしまった楊貴妃。その話を単に悲劇で終わらせず、安禄山や陳玄礼の行いを道理だとしている。つまりは政治的行いとして肯定しているようなのである。
また、「昔の人は~だった」というような記述は、他の話にも多い。
マヌケな孔子
世に賢人として知られる柳下恵という人がいたが、彼の弟である盗跖は 獰猛な連中を配下とし、人の物を奪い取っては自分のものに、行く先々の家を荒らして人々を苦しめていた
ある時、道でばったり出会った孔子が、柳下恵に聞いた。「あなたの弟の悪事はひどいものです。なぜあなたは兄として忠告してやらぬのですか」
「あれは私の忠告に従うような人間ではないのです」と言う柳下恵に、「ならば私が彼のところに行って忠告してやろうと思います」と孔子は言った。
柳下恵は止めたが、孔子は「あれも人の子。正しい道を説いてやれば、あるいは善道に赴くこともあるでしょう。初めから忠告を聞かぬと思って教えもしないなど、実によろしくない」と聞いてはくれない。
そうして盗跖に会いに来た孔子を、盗跖の方も知ってはいた。
「お前は世に名高い人間と聞いているが、なぜここにやってきたのか。お前が様々なところで人にものを教えているとは聞いているが、もし俺を教えようがために来たのかならば、来て教えればよい。俺の心にかなったならば言う事を聞いてやろう。だが叶わぬのなら、お前の肝を引き裂いて膾にしてやる」
孔子は「こんな恐ろしい男とは思っていなかった。姿形を見て、その声を聞くと、人間と思われない」とすでに恐怖で体を震わせていたが、しかし我慢して、いつものように説き始めた。「人がこの世に生きていくには、すべて道理をもって身の装いとし、心の掟としなくてはならぬものです。しかしあなたときたら心の赴くままに悪事ばかりなさるという。悪事というのはその時は満足した気持ちになるが、結局はよくないことに終わるものです」
盗跖はせせら笑う。「何1つ当たっていないな。お前の弟子を始め 、お前が言う賢人というやつらは、みんなろくに領地を得られず、裕福な生活も出来ず、短命で終わっている。だが俺は、悪事ばかり好んでしているが、この身に災いは起きておらぬ。さっさとここから消え失せろ、お前の言う事など何の役にも立たない」
孔子は言い返す言葉も思いつかず、逃げるしかなかった。しかしよほど怖かったのか、馬の轡を2度も取り損なって、鐙を踏み外したという。世間ではこれを「孔子倒れなさる」と言った。
孔子の話はいくつかあるが、結構マヌケなものもある。これは特にそう。
他にも、仏教の関係なくなったところの話では、結構悪人が、その知恵で成功するというような話がある。こういうところは、何か教訓とかそういうのよりも、単純な物語の面白さを優先している感が強い。
青い竜の恩返し
あるところに1人の猟師がいた。
彼は海岸に山が突き出している辺りで、シカ(鹿。Cervidae)が出てくるのを待ち受けていたのだが、ふと見てみると海の中から2匹の竜が現れた。片方は青く、もう片方は赤い。2竜はお互いに噛み合って戦っている。猟師は不思議なこともあるものだと見ていたが、2時間ほどの戦いの後は青い竜は負けて逃げて行った。
翌日にも同じ時刻に2匹の竜が海から現れて、やはり戦い、青い竜が負けて逃げていった。3日目にもまた2竜は出てきて、また青い竜は負けそうになった。猟師はそれを見ていて可哀想だと思い、青い竜を助けてやろうと、矢を赤い竜に向けて放った。するとそれは見事に命中して、赤い竜は海の中に逃げていった。青い竜の方も海に戻ったが、しばらくしてからまた出てきた。玉をくわえて、陸へと。
猟師は「青い竜は、敵である赤い竜が矢で射られたために勝つことができた。これは俺の恩によるもの。だからその恩に報いようと、宝珠を持ってきて、俺にくれようというのだな」とか合点し、海岸に近寄っていく。青い竜も、猟師を見てますます近づいてくる。そして玉を陸の上に置いたまま、海中へと戻っていった。猟師は玉を取って家に帰った。
以降、この猟師は、多くの財宝を思うまま手に入れられるようになり、何1つ不自由することがなかったという。
わりと唐突な竜の話。





