レオポルト・モーツァルト
ヨーハン・ゲオルク・レオポルト・モーツァルト(Johann Georg Leopold Mozart。1719~1787)は、製本職人の家の子だった。
幼い頃より聖歌隊(Choirboys)で歌うことで、音楽は身近だった。
演者として舞台作品に出演することもあり、バイオリンやオルガンも学んだ。
地元のイエズス会の学校、聖サルヴァトール校(St. Salvator)で、論理学、科学、神学を学び、よい成績を収めた上で、1735年に卒業。
しかし次に入学した、聖サルヴァトール高等学校(St. Salvator Lyzeum)は、1年も経たないうちに中退。
レオポルドの両親は、息子に関して、カトリック司祭としてのキャリアを望んでいたとされる。
だが息子の方は、それを望んではいなかった。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
1737年。
オーストリアは、ザルツブルクの大学に入学した彼は、 哲学と法律を専攻したが、1年も経つ頃には、学業に対してやる気をすっかり失ってしまっていた。
代わりに熱中したのは音楽だった。
レオポルドは、バイオリンの名手で、作曲も嗜んだ。
 「オーストリア」アルプス、温泉、カフェ、辻馬車。音楽が習慣な貴族
「オーストリア」アルプス、温泉、カフェ、辻馬車。音楽が習慣な貴族
カトリック信仰の雰囲気の中、ザルツブルクでは、学問よりも芸術趣味が横行していたのだと考える者もいる。
それこそ、若者たちが気を惹かれないではいられないほどに。
1739年。
学業を疎かにしたので当たり前だが、レオポルドは大学から除籍処分を受ける。
そして翌年の1740年から、彼は、ザルツブルグの名門貴族であるトゥルン=ヴァルサッシナ・タクシス伯爵家(Count of Thurn-Valsassina and Taxis)の従者楽士となり、音楽家としての道を歩み始める。
レオポルドの時代のヨーロッパにおいて、普通に音楽家といえば、自由な芸術家でなく、使用人身分として、雇用主や注文主の意向に沿った曲ばかりを作る職人であったとされる。
レオポルドもそうだった。
1743年には、宮廷楽団のバイオリン奏者となり、音楽家としての職も安定した。
忠実な職人として注文主が望む曲を作る中に、子供みたいな遊び心をいれることもあった。
代表的とされるのが、数匹の犬をオーケストラに参加させたという「狩りの交響曲(Jagdsinfonie)」であろう。
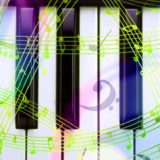 「音楽の基礎知識」大事なこと、楽譜の読み方、音楽用語だいたい一覧
「音楽の基礎知識」大事なこと、楽譜の読み方、音楽用語だいたい一覧
レオポルドは、音楽教育者として非常に優れていたとよく言われる。
豊かな教養に裏付けされた、合理的な指導法や、的確な指摘は評判であった。
1747年。
レオポルドは、1つ下らしいアンナ・マリア(Anna Maria Pertl。1720~1778)と結婚。
1755年も末頃。
アンナは7人目の子の出産を間近にひかえていた。
そして、それまで生まれた6人の子のうちで、その時までに生きていたのは、三女のマリア・アンナ(ナンネル)だけ。
また次の子も、早くに死んでしまうのではないかという不安はあったろう。
そして、レオポルドの名を後に残すことになった、彼自身の功績である「バイオリン教程(Versuch einer gründlichen Violinschule。A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing)」という本が完成した1756年。
1月27日に、彼の7人目の子、ヴォルフガング・アマデウス(Wolfgang Amadeus Mozart。1756~1791)は生まれた。
ザルツブルクという街に、最も偉大な音楽家の1人とされる天才児が、満を持して登場したわけである。
神童と家族演奏旅行
5歳上のナンネルは、『クラビーア(Klavier)』、いわゆる鍵盤楽器の才能が早くから開化していたそうである。
ヴォルフガングの方もそれは同じだった。
彼が生まれた時点での、姉と同じ年齢になる頃には、彼はもう、多くのクラビーア曲をマスターしていた。
のみならず、驚くべきことに、特に教えも受けてはいないはずなのに 、いつの間にやらバイオリンを弾けるようにもなっていたらしい。
作曲を始めたのも、このくらいの頃からとされる。
怖いもの知らずの少年
それは愛ゆえか、それとも教育者としての使命感か、名誉心か。
父レオポルドは、神から大いなる才を与えられた自分の子を連れて、 家族旅行という名目の演奏旅行によく出かけたという。
ヴォルフガングは、バイエルンのミュンヘンに滞在中に、6歳の誕生日を迎えた。
ここでは姉と一緒に、選帝侯(Kurfürst)の御前で演する。
選帝侯とは、神聖ローマ帝国君主(ドイツ王)に対する選定権を与えられていた諸侯(臣下の貴族)。
さらにミュンヘンでの演奏披露会と同じ年の9月に今度はウィーンへ。
一家がその地に到着する時には、すでに神童の噂は都市に広まっていて、多くの貴族が彼らを招待した。
そして一週間後には、ハプスブルク王朝君主のお気に入りとされたシェーンブルン宮殿において、 当時の神聖ローマ皇帝であるフランツ1世(Franz I。1708~1765)と、女帝マリア・テレジア(Maria Teresia。1717~1780)は、一家を歓迎した。
 「ハプスブルク家の王室の人達」ルドルフ、マリー。最後の皇帝まで。代表者9人
「ハプスブルク家の王室の人達」ルドルフ、マリー。最後の皇帝まで。代表者9人
恐れ多いことに、無邪気なヴォルフガングは、女帝の膝に乗り、首に何度もキスをした。
また、転んだ時に起こしてくれた、同世代のマリー・アントワネット(Marie-Antoinette。1755~1793)と、その場ですぐに結婚の約束をしたという伝説は有名である。
また、シェーンブルンにおける演奏会にて、怖いもの知らずなモーツァルト少年は、有名な作曲家であるヴァーゲンザイル(Georg Christoph Wagenseil。1715~1777)に譜めくりを頼んだが、その理由について以下のように語ったとされる。
「あの人は音楽をわかってるからね」
自作曲の初めての出版
モーツァルト一家は1763年11月にパリにやってくるが、ここに来るまでの馬車の旅の道中でも、立ち寄ったあちこちで演奏会を行った。
フランクフルトの演奏会には、後に有名な詩人となるゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe。1749~1832)も、父に連れられて来ていたらしい。
パリではヴェルサイユ宮殿(Palais de Versailles)にも招待され、ヴォルフガングとナンネルの演奏会は、そこでも王族たちに好評だったという。
そしてパリに滞在中、モーツァルトは初めて、自身が作曲した作品、『クラビアとバイオリンのためのソナタ集(Four sonatas for keyboard and violin)』を自費出版によって世に出した。
それらはパリにおいて、世話になった2人の貴婦人に捧げられたとされる。
ちなみに、上記に限らず、モーツァルト少年の初期の作品は、実はレオポルドの作と考える人はけっこういる。
クリスティアン・バッハとの出会い
少年モーツァルトの評判は、海を越えてイギリスにも伝わった。
パリに5ヶ月滞在した後に、一家は今度はロンドンへと渡ったが、そこでまた彼らは大歓迎され、一週間たたないうちに、宮廷での御前演奏をすることになった。
ロンドンでは、音楽史上において非常に有名な大バッハ(Johann Sebastian Bach。1685~1750)の息子で、父同様に音楽家として活躍していたヨハン・クリスティアン・バッハ(Johann Christian Bach。1735~1782)との出会いもあった。
クリスティアン・バッハは、天才少年をとても気に入り、イタリア音楽の模式などを教授したという。
2人が即興的に奏でたクラヴィアの連弾は、実にぴったり息が合っていたとも伝えられている。
 「 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」何より貪欲に。音楽一族出身の大作曲家
「 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」何より貪欲に。音楽一族出身の大作曲家
ジョーク作品、ガリマチアス・ムジクム
レオポルドが病気で寝込んだこともあって、ロンドン滞在は予定よりもかなり長くなった。
少年モーツァルトはその間に、最初の交響曲、クラヴィア小曲集、イタリア語によるアリアなどを作曲したとされている。
1765年の夏に、一家はロンドンを発った。
帰路の途中でオランダに訪れたが、ここで今度は子供たちが腸チフスにかかり、一時期はかなり危ない状態にもなったそうである。
また、モーツァルトはジョーク好きな人としても知られているが、オランダでは『ガリマチアス・ムジクム(Galimathias Musicum。無意味な音楽)』という、初のジョーク作品と呼ばれるような曲も作っているという。
オペラ作曲家を目指して
ヨーロッパのあちこちを3年以上旅して、ザルツブルクに帰ってきたモーツァルト一家は、まだ1年も経たないうちに、再び旅立つ。
1768年。
ウィーンで新皇帝ヨーゼフ2世(1741~1790)にも会い、 彼の意向もあって、12歳のモーツァルトは、宮廷劇場のための喜歌劇『ラ・ファンタ・センプリチェ(La finta semplice。偽物な無垢)』を作曲する。
しかし、結局これは、ウィーンでは上映されずに終わってしまったらしい。
上映されなかった理由に関して、すでに神童というより、一人前の作曲家として、多くの人が認めるところであったモーツァルトに対し、ライバル心を抱く者たちの妨害工作があった、という説もある。
モーツァルトはまた、この時期に、『バスティアンとバスティエンヌ(Bastien und Bastienne)』という歌劇も仕上げている。
父レオポルトも、息子がオペラ作曲家として成功することを望んでいたようである。
ローマ教皇から送られた栄光
18世紀のヨーロッパでは、イタリア音楽が特に人気だったとされている。
そしてここはオペラが盛んであり、本気でオペラ作曲家を目指すなら、避けては絶対通れない、いわば本場であった。
そのイタリアの地に、満を持して、レオポルドとヴォルフガングの父子が訪れたのは、1769年の末のこと。
この時は家族全員旅行ではなく、2人だけだったとされる。
そして、モーツァルトの天才ぶりは相変わらずであった。
やはり行く先々で、各地の王族や貴族たちに歓迎されもした。
都市ミラノでは、謝肉祭のためにオペラを作曲する契約を結ぶことができた。
ボローニャにおいては、少年モーツァルトは音楽理論の大家であったマルティーニ神父から、複数の旋律を調和させる高度な作曲手法である「対位法(counterpoint)」を学んだ。
彼があまりにもあっさりと、何もかもすぐ覚えていってしまうので、神父は非常に驚かされたという。
また、帰りの旅の際に再度ボローニャを訪れた時は、本来は20歳以上という条件がある、音楽家団体「アカデミア・フィラルモニカ」の会員に、少年モーツァルトは例外的に選ばれた。
カトリックの総本山であるローマにももちろん訪れた。
そして少年モーツァルトは、教皇クレメンス14世(Papa Clement XIV。1705~1774)から、音楽家として最高の名誉とされた『黄金拍車勲章(Order of the Golden Spur)』を授けられもする。
マリア・テレジアの判断
1771年の3月頃に、イタリア旅行から、ザルツブルクへと帰ってきた父子。
それからそんなに時間の経たないうちに、彼らは2回、イタリアをまた訪れている。
その2回の1度目は、ミラノでフェルディナント大公(Archduke Ferdinand Karl of Austria-Este。1754~1806))の結婚式が行われた時のこと。
モーツァルトは、大公の母であるマリア・テレジアの依頼で、『アルバのアスカーニョ(Ascanio in Alba)』という祝典用セレナータ(セレナーデ)
もう1回の時には、 モーツァルトがミラノの街自体のために、作曲したというオペラ『ルーチョ・シッラ(Lucio Silla)』が上演され、それを大公も楽しまれた。
この時の滞在をレオポルドはかなり伸ばしたが、それは大公が、息子を、宮廷音楽家として雇ってくれることを期待してのことだった。
しかし結局、その期待はむなしく終わった。
レオポルドは知らなかったが、実のところマリア・テレジアその人が大公に対して、手紙で、「無用な人間を雇わないように。乞食のごとく世の中を渡り歩いてるような人たちなど、家臣たちに悪い影響を与えます」などと、忠告していたそうである。
ザルツブルクの宮廷音楽家
もちろん教師である父親から、しっかりと教育は受けていただろうが、学校に通うことはなく、旅ばかりしていた少年時代。
その特殊なあるいは贅沢な経験は、モーツァルトの才能をよく開花させた。
1773年。
モーツァルトは、故郷ザルツブルクで、ヒエロムニス司教(Hieronymus Joseph Franz de Paula Graf Colloredo von Wallsee und Melz。1732~1812)に、 宮廷音楽家として雇われる。
モーツァルト自身が様々なところを旅することは、(自分のような才能ある者にとって)よい刺激になると考えていたとされている。
だから、結局は父親と同様に、ザルツブルグという小さな故郷の宮廷音楽家になった時、もう旅ができなくなってしまったというのは残念であったろう。
ただ、ザルツブルクなど、せっかくの才能を無駄にしてしまうと、モーツァルト自身も、父も、意見を同じくしていた。
最終的に父親は、ザルツブルグにとどまることを決心したが、21歳のモーツァルトは、1777年夏、故郷での職を辞して、母と一緒に、職を求めて旅立っていった。
初恋への情熱
旅先で、貴族の友人ができることもあったが、たいていの場合、自分を売り込んでも、空席がないという理由で断られた。
御前演奏を行って、それがとても好評なことは多いが、最も求めている現金が謝礼として渡されることはなかった。
多くの場合、渡されるのは時計だったそうである。
父の生まれ故郷で、親戚たちが多くいるアウクスブルクにもやってきた。
従妹にあたるマリア・アンナ・テクラ・モーツァルト(1758~1841)は、 なかなか陽気で、お行儀悪い娘らしく、モーツァルトとよく気があったという。
ふたりはダジャレや語呂合わせ、悪口や、下品な言葉で、存分にふざけて楽しみあったとされる。
ただ、アウクスブルクには、就職場所として求めているような宮殿もないため、あまり長く留まっているわけにもいかなかった。
マンハイムでも、就職できそうにない状況はそれまでと同じであったが、モーツァルトはそこからはなかなか離れなかった。
手紙を通した次のアドバイスもあって多くの音楽家たちと親しくなって楽しい日々だったし、それにもう1つ、彼は恋をしていた。
マンハイムの宮廷で、バス歌手と写譜係をしていたフランツ・フリードリン・ウェーバーの娘アロイジア(1760~1839)に。
アロイジアは、当時、16歳になったばかりのソプラノ歌手で、歌だけでなくピアノも上手かったという。
モーツァルトは情熱に駆られるまま、彼女らの一家と一緒になり、 一緒にイタリアに行って力になってやりたいと考えた。
しかしそれを知った父レオポルドはめいっぱいに反対した。
「 その真の才能を発揮し、後世にまで名前が残る音楽家になれるかは、全てお前自身の分別にかかっているのだ」と手紙に書き、天分を持った人々の評判と名声が広がる場となるだろう、パリにこそ、お前は行くべきだ、と伝えた。
モーツァルトは大人しくそれに従った。
母の死、パリにて
パリは、思い出にある素敵な街ではなくなっているようにモーツァルトは感じた。
みんなお世辞ばかりで、よそよそしい感じも受けた。
しかし、変わらず親切にしてくれる人はいたし、何よりこの街は、音楽の面でかなり刺激的であったようである。
そして、この街において大きな不幸が彼を襲う。
1778年の7月。
旅の連れであった最愛の母を、病気によって、永遠に失ってしまったのだった。
大きな挫折
1778年の9月の末。
結局モーツァルトは、ザルツブルグに戻ることに決める。
父親の願いもあり、すでに司教の雇われとして、復職も認められていた。
帰りの道中には、愛した人がいたミュンヘンに立ち寄った。
そして彼女アロイジアに、彼女のためのアリアを送り、結婚を申し込んだのだが、冷たくフラれてしまう。
この実現は大きな挫折であった。
久しぶりの吉報
彼自身にとって、もはや今の人生は不幸であった。
音楽的な刺激に乏しい田舎町で、ろくに芸術的教養ももたない人たちのためにばかり作曲しなければならない。
それに加えて、旅行によって積み重なった借金の返済にも苦労した。
その上、いつでも優しかった母はもういない。
1780年のミュンヘンからの依頼は久々の吉報であった。
それは、新しくバイエルン選帝侯となっていたカール・テオドール(1724~1799)からの、翌年の謝肉祭シーズンのオペラの作曲依頼。
この時に作曲された『イドメネオ(Idomeneo, re di Creta ossia Ilia e Idamante)』というオペラが、 実際どのくらいの人気を得ることができたのかは資料に乏しいらしい。
これは当時としては先進的すぎると言っていいくらい難解なものともされ、理解できる者がどれほどいたかは怪しい、という推測もある。
ただ、とりあえず、練習中の風景を見学した選帝侯は、「このオペラは必ずやあなたの名誉となろう」と言ってくれたようだ。
失望と決別
ミュンヘンでの一仕事の後。
ヒエロムニス司教はウィーンに滞在していて、モーツァルトはお抱え楽師として、直接そこへと呼ばれた。
彼にとっては、ザルツブルグに比べれば、ウィーンの方がずいぶんマシだったから、それはそれで喜ぶべきことだった。
しかし、場所は変わっても、結局その暮らしぶりは以前と変わらない。
召使たちと一緒に食事を食べ、ただただ命令に従って演奏したり、作曲したりするだけで、大した報酬も支払ってくれない。
それどころか、自ら進んだ活動をしようとすると妨害にあう。
モーツァルトには皇帝の前で演奏する機会すらあったのに、身内の演奏会のために、それを逃してしまった。
以前から、というよりはおそらく最初からあった、司教との確執が、ここでかなり決定的なものとなってしまう。
口論の末に二人は決別する。
さらに、息子の怒りに任せた行動に対し、今度は父が怒りを見せて、それにもモーツァルトは失望させられる。
「名誉を重んじた、よき父としてのあなたなど、もういない」と、息子は手紙に書いた。
司教は悪者であったか
ヒエロムニス司教に関しては、モーツァルトの才能を無駄にするところだった悪人かのように紹介されることもあるが、実際そうだったのかは疑問なところもある。
モーツァルトは、自分が並の従僕と似たような待遇ということが我慢ならなかったようだが、多少優れていようと、音楽家が従僕の待遇というのは、当たり前の時代だ。
それにモーツァルトは、幼少時代から天才天才と周囲に崇められ、すっかり天狗な自信家だったともされるから、確実に扱いにくい音楽家でもあったろう。
それでも司教は、1度辞めた彼の復職を認めてもいる。
また、その音楽家としての才能を十分に理解できていなかったというのは事実かもしれないが、そもそもモーツァルトの作風は、かなり先進的で、実際問題、理解できると自信を持って言えるような人がどのくらいいたのかも疑問である。
フリーメイソン所属の自由作曲家
司教と完全に決別し、今や自由な音楽家となったモーツァルトは、ウィーンではまた、ウェーバー家の下宿の世話になった。
かつて愛したアロイジアは、すでに別の人の妻となっていたが、モーツァルトは彼女の妹であるコンスタンツェ(Constanze Mozart。1762~1842)と恋に落ちる。
この辺りは未亡人となっていた、アロイジアたちの母の策略だったという説がある。
今やウィーンでそれなりに人気のモーツァルトは、単純に娘の結婚相手としては、申し分ない相手であった。
最終的には結局折れたものの、父レオポルドはこの付き合いに関して、やはりまた、かなり反対の意を示していたそうである。
彼は、人のいい息子が、したたかなウェーバー夫人に踊らされているのだろうと考えていたそうだが、それはあながち間違いでなかったかもしれない。
とにもかくにも、精力的な活動により、 職業音楽家として多忙を極めたモーツァルトだったが、それでも今回は、コンスタンツェとじっくり愛を育んだ。
そして1782年8月4日。
聖シュテファン大聖堂で、2人は結婚する。
裏の真相はどうあれ、少なくともモーツァルト自身にとっては、これは幸福な結婚だったようだ。
最初の息子の死
結婚の翌年、1782年の6月には長男も誕生し、ライムント・レオポルドという名前を与えられた。
モーツァルトは、この子供を、乳母に預けると、故郷ザルツブルグに帰って、 気まずくなっていた父と姉に妻を紹介したが、結局、彼女はあまり歓迎されず、親子の間でも、以前の親密さを取り戻すことはできなかったという。
そして4か月の後に、ウィーンに戻ってきた夫婦を待っていたのは、わずか2ヶ月しか生きれなかった、息子の死の知らせであった。
父との仲直り
1785年の2月。
モーツァルトは父をウィーンに招待した。
もちろん、自分の、音楽家としての立派な活躍を見てもらうためだ。
モーツァルトは今や、ピアノ曲の作曲家としてかなりの権威にもなっていて、父子の関係は、ここに至ってようやく、元通りになりつつあったようである。
当時のウィーンでは、秘密結社のフリーメーソンが流行していたようで、すでに入会していたモーツァルトは、父にも入会を進めている。
また、ウィーンにおいて、24歳年上のハイドン(Franz Joseph Haydn。1732~1809)と親しかったが、彼もまたフリーメイソンだった。
 「フリーメイソン」秘密結社じゃない?職人達から魔術師達となった友愛団体
「フリーメイソン」秘密結社じゃない?職人達から魔術師達となった友愛団体
フィガロの結婚
1786年に作曲したオペラ『フィガロの結婚(Die Hochzeit des Figaro)』は、ウィーンではそれほど好評ではなかったともされる。
賢い従僕の活躍で、貴族が笑いものにされるというポールマシェ(Pierre-Augustin Caron。1732~1799)の原作からして、 ウィーンではかなり問題視されていたそうである。
しかしこの喜劇はプラハでは大人気となり、1787年の1月、当地の音楽団体はモーツァルトを招待した。
その人気ぶりは、やってきたモーツァルト自身が驚くべきものであった。
今、オペラといえばフィガロ、朝も夜もひたすらフィガロの話題ばかりであったという。
プラハの街は、モーツァルトの音楽をしっかりと聞いてくれて、しっかりと評価してくれ、多額の報酬まで与えてくれる、素晴らしい場であった。
死を恐れる必要なんてない。それは友達
もちろん、いつでも幸運なことばかりではない。
プラハに訪問した、同じ年の5月28日。
ザルツブルグにて、父レオポルトは、母を追うことになった。
死の2ヶ月ほど前に、モーツァルトが、病気で倒れた父に宛てた手紙は有名である。
「死ぬということは、生きる者たちにとっての本当の最終目標と思います。私は、ここ数年ほど、この真実の友ともすっかり仲良くなりました。ですから、死を恐れる必要などないと思います。むしろそれは心を安らかにし、慰めてくれるものなのです」
彼はそんなふうに書いていたとされる。
もう、すっかり売れなくなっていた
1787年の末頃に、モーツァルトはウィーンに帰ってきた。
そして、ちょうどその頃に亡くなった作曲家グルックの代わりのように、彼は宮廷作曲家の称号を得たが、本人的に期待していたような待遇ではなかった。
フィガロ以降、ウィーンにおいては、モーツァルトは落ち目だった。
彼のオペラが上演されることは明らかに少なくなり、曲の買い手も激減した。
もうモーツァルトのブームは終わっていたわけである。
もっともモーツァルトは音楽家としてまるきり仕事を失ってしまったわけではない。
貧乏暮らしは、夫婦そろっての浪費癖のせいだったとする説が有力。
また旅に出て、しかし現実は厳しく
1789年。
フランス革命が始まり、ヨーロッパ全体が激動の兆しを見せる中、モーツァルトは知り合いの貴族カール・リヒノフスキー(Karl Alois Johann Nepomuk Vinzenz Fürst von Lichnowsky。1761~1814)の誘いを受けて、また旅に出た。
苦しい経済状況で、いよいよ創作意欲も失いかけていた中、打開策を思いつくための気分転換には、ちょうどよかったろう。
 「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
「フランス革命」野蛮で残酷なひどい文化か、自由を求めた戦いか
しかしこの頃には、コンスタンツェが病気がちになっていて、モーツァルトは情けなくも、フリーメーソン仲間のプフベルク(Johann Michael Puchberg。1741~1822)宛てに、返すあてもない借金嘆願の手紙を書きまくっている。
晩年の製作活動
1791年は、モーツァルトの人生における最後の年である。
1月5日には、最後のピアノ狂想曲も完成した。
3月に、フリーメイソン仲間で、ウィーンの町外れの、ヴィーデン劇場の支配人をしていたエマヌエル・シカネーダー(Emanuel Schikaneder。1751~1812)からの作曲依頼があった。
劇場の興行不振を何とかするために、大衆受けしそうなドイツ語オペラを書いてくれないか、という依頼。
モーツァルトはこれを引き受け、そうして、神秘主義と道化芝居、 子供のような悪戯心と、スペクタクルな仕掛けが混じりあった、自由自在な破天荒オペラ『魔笛(Die Zauberflöte)』は誕生した。
また、最後の夏には、気味悪い注文もあったという。
注文の名前を明かそうとしない、使いの者が、結構な前金だけを置いて依頼してきた、レクイエム(死者に捧げるミサ曲)である。
この真相は、ヴァルゼック・シュトゥパパなる貴族が、亡き妻に捧げる曲を、こっそりと調達する必要にかられていた、というものらしい。
そんなことを知る由もないモーツァルト本人にとっては、かなり不気味な依頼だったかもしれない。
最期。魔笛の熱狂の中にて
ヴィーデン劇場における魔笛の初演は、最後の年の9月30日。
客たちは最初こそ静かだったが、段々と熱狂していった。
そこでは、明らかにこれまでとは違う手応えがあった。
貴族中心の宮廷劇場とは違い、シカネーダーの劇場はもっと下の大衆のためのもので、本当に楽しいものを見たいと思っている人たちが大勢やってきたわけである。
音楽が、御大層な飾りである時代は、終わりつつあった。
そして、音楽は楽しむものだという考えは、ユーモラスな性格だったモーツァルトが、少年時代から持ち続けていた信念だったともされる。
彼が相手にするべきは、もしかしたら貴族でなかったのかもしれない。
だがそうだとしても、それに気づいた時にはもう遅すぎたろう。
10月にはすっかり病気で弱ったモーツァルト。
そして彼は寝たきりとなって、12月5日に、世を去った。




