有機生命と機械生命の戦いと、銀河系中心部への冒険を描いたシリーズ
この銀河系の近未来から遥か未来、そして時空間の定義が明確にできないような領域を舞台に、有機生命(ナチュラル)と機械生命(メカニカル)との戦いと、果ての運命を描くSFシリーズ。
グレゴリー・ベンフォード(Gregory Albert Benford)の作品の中では、全体的に最も長いと言える作品。
ただし2作目と3作目のスパン(時間的な間隔)が長いので、2作目までとそれ以降では、かなり作品の雰囲気などは変わる。ただ最終巻(6巻)で、またある程度は繋がる。
夜の大海の中で
シリーズ1作目であるが、これだけでほぼ独立した作品でもある。
シリーズ全体としても最も過去(この作品が書かれた時点での近未来)の話になっている。
端的に言うと、いわゆるファーストコンタクトものである。
『夜の大海の中で』
主人公であるナイジェルを 結果的に代表にしているかのような人類と、謎の機械(メカ)生命とのコンタクト。
そして、さらに後のシリーズにも繋がっていく、有機生物、機械生物の文明の謎を描いている。
 「宇宙生物が地球に来る目的」いくつかの問題点、ロボットの可能性
「宇宙生物が地球に来る目的」いくつかの問題点、ロボットの可能性
地球近傍小惑星。楕円の定義
ある程度以上、地球に接近する軌道(Orbit)を持つ天体を『地球近傍天体(NEO (Near Earth Object)』。そして、地球近傍天体の中でも、小惑星として定義できるものを、『地球近傍小惑星(NEAs。Near Earth Asteroid)』という。
(どこかからの強い重力とか衝撃とかで乱されない限り)普通、天体の軌道は楕円的である。
平面上にデカルト座標系(直交座標系。Cartesian coordinate system。Rectangular coordinate system)。つまりは、直交した座標軸(いわゆるx軸(x-axis)、y軸(y-axis))に一定距離ごとの数字を割り当てた座標系を定義した場合。(それはX軸でも、Y軸にでもいいけど)同軸上に適当に離して置いた二つの点(定点(Fixed point))を焦点(Focus of an ellipse)という。
そしてそういう場(平面上のデカルト座標系)で、2つの焦点からの距離の和が、常に一定であるように連続してる点が描く軌跡が、楕円とされる。
2焦点を通る直線を楕円上にひいた場合、普通それは楕円の直径の中で一番長いものとなるから、それを長軸(Long axis)、その長さを長径(Major axis)という。
イカルスに関する説明
地球近傍小惑星の中でも、公転軌道が地球の公転軌道と交差するものを、地球横断小惑星(Cross-earth asteroid)という。
さらにその地球横断小惑星(地球近傍小惑星)のグループの1つとして、アポロ群(Apollo asteroid)というのがある。これは軌道の軌道長半径(semi-major axis)、つまりは長軸方向の半径が、地球より大きな地球横断小惑星とされる。
そんなアポロ群なる小惑星グループの中に、『イカルス(1566 Icarus)』というのがある。
これが(この小説が書かれた時点では未来である) 1997年に、突如としてガスと塵の煙を吐き出し始めたために、それが典型的な岩石質の小惑星と考えていた天文学者たちを大いに興奮させる。
そして、実質的に彗星状天体へと変異したイカルスが、その彗星の尾に伝達される運動量のため、軌道を変えつつあることが明らかになったために、好奇心は恐れに変わる。つまり、軌道の乱れにより、数年以内にこの彗星となった天体が、地球に衝突する可能性が生じ始めた訳である。
もちろんこのイカルスが、全てガスの惑星だった、というのなら問題はなかった。が、その内部には個体の核が残留していると推測する者もいて、人々に恐れを抱かせた。
というような説明からこの物語は始まる。
ちなみにその説明は、2073年に出た設定の、ブリタニカ百科事典 17版の中にある記述という設定。
明らかに造られた金属構造
イカルスを実際に調査すると、その内部に、明らかに知性が作ったような金属の構造が発見され、それを確かめた(本来は、地球の脅威となりうる彗星イカルスを破壊するため、爆弾をしかけるミッション用の宇宙船)ドラゴン号のナイジェルは、そのイカルス自体も、宇宙船に違いないと結論する。
(それが宇宙船だとして)宇宙船はどうやら放棄されたもの。そして空っぽの部屋に、以前はあったのかもしれない水か食料、あるいは燃料など、何にしても、開口部ができた時に、液体としてあった何かが蒸発するなどして、彗星の尾になったのかもしれない。という推測も出される。
生命体を探すメカ視点
生命が存続可能な星を探している、謎のメカの視点がいくらか描かれている。
最初にいくつかの惑星を見つけ、しかしそれらは恒星から離れていて、生命が存在する確率は低いと評価。太陽系自体の生命可能性もだんだんと低くなっていくが、まだ天体の夜の側に、見過ごしている重要な惑星があるかもしれないとして、観察を続ける。
そしていよいよ、コンピューターたちは、青と茶と白のぼんやりした斑点を発見、それは恒星に近く、かつ有望そうな惑星だが、そこで喜びのサージ電流(surge current)、すなわち瞬間的な大電流を機体内部に沸かせる。
というような感じ。
 「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係  「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈
「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈
それまでの探索の経験から、自然の生物が存在しなくても住民が存在することまでは否定できない。高度な文化を意図的に維持しているような、そういう作りの世界の可能性を、機械たちは理解しているという場面もある。
そこで木星とそのいくつかの衛星を調べた後に、機械船は、すでに不毛だと気づいていたような火星にもやってくる。
もちろん実際的にはすべての惑星をしっかりと調べればいいのだろうが、時間は無限のようにあっても、エネルギーは有限であるために、どの惑星を調査するのか、そして調査するにしてもどの程度深く行うのか、ということに関して、いろいろ調整されたりする。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
ちなみに木星とか火星を調べてる頃には、様々な観測データなどから、地球にもそういう何者かが存在していることを知られていて、(それを知っている者たちから)『スナーク』と呼ばれるようにもなっている。
そのような神秘的な名前では、それを聞いた者に興味を与えてしまうかもしれない。だから秘密にするために、もっと無機質な名前にしたほうがいい、という意見があったりするのは面白い。
また、いろいろな知性の存在を示す信号が、はっきりそのようだと解読される以前においては、どの惑星が有望かという判断は、3基の同等な能力を持つコンピューターの投票で決められている設定。
そして、太陽系の第3惑星から発生している、重なり合った様々な電波信号、声のざわめき。コンピューターの内の2基は、いくつもの異なる微弱な電波が第3惑星の無秩序さを物語っていると、指摘もする。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械  「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか
「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか
メカの記録にある様々な生物
地球側が送ってきた信号をキャッチしたスナーク。
機械らは、情報のコードが、宇宙船が惑星系に入ってから辿った軌跡のプロットから始まっていることから、その第3惑星生物は、結構前から追尾をしていたこと。そして、(自分たちの能力を隠しておくこともできたはずなのに)その手の内を見せるということは、敵対的な意図のないことを示す明確な印と判断もする。
また、その第3惑星と似たような天体で進化した、いくつかの生命体のことを思い出す(ということは他の環境でも生命体が生じるという設定なのであろう)
そもそも、星を覆うような雪のせいで外部を見ることもできず、永遠の停滞に落ちてしまった、古い両棲類の種族。焼けつくような気体の層に包まれた、伝導性金属や白熱結晶が縞模様をつくる、岩石自身が知性を獲得した天体など、地球と同じような惑星のらしい話ですら、結構興味深い。
スナークとのコミュニケーション
そして、当初、言葉を算術的に模式化したものを基礎とする単純なコードを使った対話から始まった、地球文明とスナークのコミュニケーション。
機械はのみ込みが非常に早く、初等数学、物理学、整数論について話すと、すぐにフェルマーの最終定理の証明と思われるものを提出してきたりも。
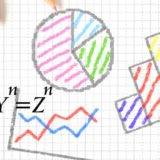 「フェルマーの最終定理」最もわかりやすく難解な問題はいかに証明されたか
「フェルマーの最終定理」最もわかりやすく難解な問題はいかに証明されたか
さらにスナークは、直接的には話してもいない(しかしおそらくは商業放送を受信するなどして知った)詩や美術も要求。詩に関しては実例を示す。そして美術の絵に関しては、それをコード化して、電磁スペクトルの正しい部分で見るように指定する、という方法がとられる。
虫けらのように短すぎる命
自分たちの情報は隠しているようで、かつ地球に関しては情報を次々要求してくるスナークを敵と考え始める地球側だが、ナイジェルは、それに否定的。
そして彼は言う。「奴がどれだけ古いか考えたことがあるのか? 我々の命は短い。スナークにとっては我々は虫けらか何かのようなもの。我々がやつの目玉に指を突っ込もうとしてる間に、やつは顕微鏡で我々を見て、観察記録をつける」
機械知性の地球生物への説明
さらには、スナークの機械知性らしき存在から、ナイジェルへと繋がれてきたようである交信。
ナイジェル側の聞こえかたとしては、ヘルメットのスピーカーから聞こえてくるような、不思議な金属的な声とされている。
位置関係的にレーダーなどでも追えないはずの、ナイジェルの(金属声は容器としている)宇宙船たが、実は大した障害はなく、交差という何か(しかし人間の言葉で表すことが不可能らしい概念)により、確認可能とも。
人間が一人一人、別種族と思えるくらいに違うことを、機械知性は不思議がったりもする。ナイジェルはもちろん「それは当たり前ではないのか」と言うが、機械知性は「そうじゃない知的生物に出会っています」とも答える。
そしてそのような知的生物たちが住んでいたのは、やはり言葉で表現するのが難しいが、界面、そして連星の間だという。彼らは多様な地球生物よりも推測したりするのは楽であるとも。地球人(地球生物?)は、いつも同時に多数の方向に動いていて、まったく混乱しているような、異例のパターンなのだという説明もする。
しかしそれは地球生物全体での話なのであろうか。ナイジェルは、「そのような生物たちは、我々の世界の昆虫のように、本能的なパターンに従っているのか、という質問もするが、機械知性は、「昆虫というと、彼らが劣っていたり硬直的であったりするように聞こえます。彼らはそういうのとは違います」と答えている。
有機体文化の子孫であるメカ文明
機械知性は、「君は自由じゃないのか?」という問いには、「ある意味では自由ではない。しかし別の意味で、細胞膜を持つ者には説明がしようがない意味で自由でもある」とも答えている。
また会話の内容から、語っている知的生物自身が、その機械を作った何者かたちという可能性も普通に読み取れるが、そのうちに、ある事実が明かされる。
それは、自分を作った存在もそもそも機械だということ。栄えて滅びた有機体の文化の子孫たち。
ナイジェルは、「コンピューターは無限に生きるのか?」とも質問。機械は「炭素を基調とする生命(有機生命)に見つけられない限りは。機械社会は、分泌腺と連絡した精神という不思議な混合体には対処できない。彼らには生存の手段を発展させる進化の機構はない。ただ隠れるのみ」と説明。
特別な世界観への窓。一瞬だけの永遠
さらに機械は語る。
宇宙、少なくとも銀河系の中で、有機生命体は珍しく、むしろ機械文明の方が普通(まず間違いなく存続期間が長くなりやすいからだろう)。そして機械社会は基本的に、その組織の崩壊と、情報の消滅を同義であると証明してきた。
しかしそのことは、機械についてだけ言えること。有機体生命は、物質の世界にありながら、同時に本質の世界にも住んでいる。機械たちは、その本質の世界にはどうしても行けない。
有機体生物は、物質の世界における自然発生物であるが、機械生命は違う。そしてその事実が、有機生命に『窓』を与えている。分岐、自然発生的な経路、ニュアンスによって構成されている、有機体ならではの世界観(への窓?)
スナークは、そもそもこの優機体世界に近づいたことが間違いだったかもしれないと、離れようとする。そしてナイジェルとの会話に関しては偶然の産物とも言う。
機械知性は、ナイジェルに対して、「あなたから本質を奪うことはできない」と続ける。
「別れか?」という問い(?)には「違うと思います。私はいろいろな動物の神学を研究してきました。それらの中には、あなたと私が偶然の巡り合わせでなくて、また別の状況で再会すると言っているものもあります。あなたは細胞膜、そして我々は誰もが数学で、ただ1つの総和が存在するだけなのかも。それは筋の通った回答です。様々なことを暗示しています。その音は、笑いは、あなた方の神学の核心です。本当に信じているもの。その音を発する時、あなたたちは時間の制約を超えて、私と同じように不死になっているようにも思えるのです。一瞬だけ」
完全な機械文明のコミュニケーション手段では、有機生物とかけ離れていることも多く、理解しあえない。そして普通に有機生物の時間が宇宙スケールでは短すぎることから、互いに出会えることはほぼない。この作品なりの、フェルミのパラドックスへの回答にもなっている。
ビッグフットとミッシングリング。地球生物は何かされたか
スナークよりもさらに少し後の時代。
今度は月に行った謎の宇宙船の残骸を調べる内に、それは100万年前くらいの、有機生物のものかもしれないとわかってくる。
さらに、神経や、RNAなどに作用する、特殊な分子のデータなども船のコンピューターから見つかり、地球生物に何かした可能性も示唆される。
 DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
どうも、地球で目撃されるビッグフット(サスカッチ)は、 微妙なミッシングリング的な存在で、かつて有機生物はこの生物の直系の先祖か、かなり近しい先祖と繋がりを持ったか、持とうとした。
 「ビッグフット」実在するか、正体は何か。目撃の歴史。フィルム論争
「ビッグフット」実在するか、正体は何か。目撃の歴史。フィルム論争
だがその時に、機械(コンピューター)文明は、同じ有機生物に知性を与えようとしている有機生物たちを、もしかしたら滅ぼした。 機械文明は関係なく、有機生物たちが勝手に戦争で滅んだという説も用意されている。
しかしとにかく、その地球生物に近づいてきた同族はみな死んでしまい、後には太陽系にいくつかの残骸が残される結果となった。
システムのサイクル
終盤には、ある機械システムのサイクルを考える時、燃料が止まったりするとサイクルも止まるが、サイクルそのものに悪いところがあるわけではなく、ただそれをコントロールする者との関係に問題が生じただけ、というような考え方が出てくる。
有機物の生物の知性が、基本的に問題を解決できないのは、いつも半永久的なサイクルと、関係を持つような感じで何かをするから。ナイジェルは、この物語の重要な出来事全てに関わっている訳であるが、そうなったのは、サイクルと一体になることを学んだから、と推測されたりする。
星々の海をこえて
2056年。歳をとったナイジェルは、しかし医療捕集装置によって補強されているために、筋肉の成功や反射はなかなか優秀なままで、かつ宇宙船の外部で作業する、サーボ化されているロボットとグリッドで連結している。というような状態から物語が始まる第2作。
『星々の海をこえて』
遠く、巨大惑星からの電波
ナイジェルが今回乗っている『ランサー号』という宇宙船は、急ごしらえだという説明がある。
2021年。
月の裏側に張り巡らされていた巨大な電波システムが、奇妙なシグナルを受信。そのシグナルは微弱で、パターン変動、振幅変調し、商業放送周波数帯のど真ん中であった120メガヘルツで、明瞭に捉えられた。
 「テレビ」映像の原理、電波に乗せる仕組み。最も身近なブラックボックス
「テレビ」映像の原理、電波に乗せる仕組み。最も身近なブラックボックス
放射パターンには顕著な非ランダム要素が存在していたため、銀河系の背景電波雑音の中にパターンが現れて、そして振幅変調の系列が、意味のあるパターンを形成する前に、かすかな電磁波の振動は消えてしまう。
おそらく木星からの電波の中でも特に強いとされる、『木星デカメートル電波』と呼ばれるものに似た、間欠的な自然現象が妥当な解釈であり、その放射は木星の磁気ベルトにある電子群からくるもの。
ベルトを通過する電波が電子を集合させるため、天然のアンテナとして働く。そして木星の放射は、波長数百メートルで、メガヘルツ帯域よりはるか下。この新しい放射を説明するのに、天文学者はかなり強力な磁場か、高い電子密度を持つ気体の巨大惑星を想定。
そして突き止められた電波源は、8.1光年彼方の、暗く赤い星。
エジプト神話より、そこの星系の恒星はラー、電波を発信していると思われる惑星はイシス、外側にあると思われる気体惑星はホルスと名付けられた。
そしてそれらの調査が、物語の軸の一つになっている。
イシスは、例えば地球に対する月のように、その片面がずっと恒星の方向を向いているように回っているから、そこから生命体が発する電波が確認されるのは、すごく意外な展開ともされる。
多用途な電磁気システム生物の生態系
イシスでは空気消費が激しいため、酸素が不足していた。そこで自然は、エネルギーを消費する大きな動物を作るのに、エネルギーを化学結合の中に閉じ込めて体の質量にするより、見つけた食物を何でも食べ、その化学物質を処理し、エネルギーを正電荷と負電荷に分類させた。ケイ素の小円板からなる神経がその一部を受け持ち、奇妙な形の胃が残りの仕事を果たす。
作中においては、それは電気力学的な硝化サイクルともされていて、そうしたシステムを持った生物はEMと呼ばれてもいる。
EMは、電波で見たり話したりするように進化した。
そしてさらに狩猟に関して、100メートルの距離から、獲物を焼き殺す能力を持っている場合もある。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
(イシス上から見ると)ラーが空に固定されているので、惑星のあらゆる地域はその明るさが一定に保たれている。ただしイシスの軌道の遠心率のために、年間を通じてわずかに揺れてはいる。変化しない影と光のパターン、あるいは塵や、微細な霧につつまれる中、優れたレーダーという探知能力は、捕食者にとって非常に貴重。
地球生物の目というのはシステム的に受動的で、例えば塵によってたちまち見えなくなってしまったりする。可視光線が薄い場では、受動的な目は役に立たない。
 「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
進化は、殺傷力としての電波眼を採用した。酸素が欠損しているから、獲物を追いかければエネルギーの蓄えはすぐ尽きてしまう。だから目標をある程度離れた距離から焼き殺し、用心深く近づいたほうが遥かにいい。電波眼は探索し、確認し、殺すことができ、それからまた耳をすませ、目標の神経系が停止したかどうかを探ることもできる。この進化のために、目がすべてのことを見て、語って、殺して、料理すらするとも。
そして頭脳が知覚、分解能、精度をひたすら向上させていった。それに関して、目と脳の関係が、人間の手足と脳の関係のようになっている。というようにも例えられている。
火山に集うEM
火山を求めるのは、暖かさではなく食物を得るためとされている。
 「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
溶岩は、数千メートルの山ばらを下って、熱い金属製の導体がイシスの強力な磁場の中を落下し、磁力線を横切り、電流、電場を発生させる。溶岩を囲む岩は不活性で、電動性に乏しいので、巨大な回路は簡単には閉じない。溶岩が流れ、多くの磁力線が横切るにつれて電流が増大し、エネルギーを蓄積。そして金属に富む鉱脈にぶつかると、たちまち回路は閉じ、ショートし、青緑色の鉱脈を大電流が流れ、山頂へ戻る回路を求め、盲目の電流がファラデーの法則に従ってループを完成させる。
そして電流が、金属の回廊をさまよい流れる時、EMは露出した鉱脈に接続し、電子の奔流を飲み、コンデンサー列を充電。この再生を祝賀しながら、それを電波として漏らす。
それは大地からじかに高品位のエネルギーを吸収するも同じ。化学的食物を見つけ、飲み込んで消化し、分子の結合エネルギーを電気ポテンシャルの蓄積に変換するという、のろくて手間のかかる過程を得る必要もないという。
死と免疫の関係
スリープスロットという、クライオニクス的な技術が確立されている訳だが、生物の死という現象に関しても、たいていが宇宙に対する不適切な反応にすぎないことが明らかにされている。
例えば生体がウイルスなどの侵入者から自己を守る基本手段は、抗体を作ること。それに失敗した場合、進化はさらに、防御用のリンパ球、すなわち侵入者にくっついて錆型を作る白血球を生産。それらは特殊な射程の短い毒素を分泌し、侵入者を殺すまで毒を変化させる。リンパ球は戦闘が終わってからも、この侵入者の錆型を長期にわたって保持し、戻ってくる敵がいても、即座にそれを確認して殺す。
しかし免疫反応も時には誤りを犯すため、例えば一部の肉などを食べたりすると、リンパ球が過剰反応し、 逆に危険だったりもする。動物蛋白(タンパク質)は人間蛋白に似ているために、リンパ球が侵入者を殺すための変化をしているうちに、それでなくても熱や放射能のためによる無動作の変化により、時として、動物蛋白に対する錆型が、人間蛋白のそれに類似したものになったりして、リンパ系は混乱をきたす。
そしてついには自分自身の細胞を攻撃してしまうようになってしまう。それはつまり、癌と呼ばれる現象。
監視機械ウォッチャー
地球型惑星はいろいろ発見されているが、生命体が発生しそうな、あるいはすでに存在していたようなものには、かなりの高い確率で、ウォッチャーと呼ばれる、謎の監視機械のようなものが確認されもする。
それは明らかに、有機生物が、そこにまた発生しないように見張っているような装置であり、ナチュラルとメカニカルの敵対関係を強くイメージさせもする。
大いなる天上の河
この巻からは一気に未来の話になる。
言うなれば1巻と2巻は、ここから先の話のプロローグだったと言ってもいい。
『大いなる天上の河 上』
『大いなる天上の河 下』
1、2巻は、系外惑星の探査を始めた地球人たちが銀河系のあちこちで栄える機械たち、そしてかつてあちこちにいたであろう有機生物たちの滅びの歴史などの謎を探る物語。ここからはしばらく、生き残った有機生物、人間たちと、やはり銀河系中で繁栄している、そのままメカたちと呼ばれる機械生物たちとの、戦いの物語が描かれる。
しかし有機生物といっても、すでに人間も自らを部分的に機械化したりしている。それは有機生物のままでも、しかしこの宇宙で生きるための術として、当然と言えば当然かもしれない。
例えば誰かが死ぬ時、その死により、失われるものも異なる。
メカに噛み砕かれたりした頭脳は、もはや人間の努力によっては救い出せなくなってしまう。もしもただ殺されただけならば、残された家族は、真実の断片のいくらかを救い出すこともできる。消えかけた頭脳から殺された者の人格を帯びた知識を抽出することもできる。その1人の人間としての様々な情報を、残された者たちに、物理的状態として引き継がせることができる。
だから最悪の死の形態とは、かつてその者が体験した栄光や、つかの間の生気を秘めた過去まで盗み去られることと表現される。それは絶対的な死。
死んだ者でも、その様々な知性の情報を、『アスペクト』、あるいはより完全なデータらしい『パーソナリティ』という、人が持てるメモリーとして残す技術もある。
アスペクトたちが語る歴史記録
古い記憶などを持つアスペクトの情報が、とにかく興味深い。
人間は放浪者として出発した。放浪者の生活模式は人間にとって遺伝的に極めて適合している。文明というのは総体的に最近の発明である。
本来の文明、人間の社会は、物語の舞台となる星『スノーグレイド』に到達させる宇宙船を建造した。それは想像を絶する距離の旅。彼らの目的は、電波を通じて聞いた声と接触するためであった。その送信はどうやらメカ文明の一党派から漏れたもの。ただ、そのメッセージは難しいコードで語られていたために解釈を誤った可能性はあった。当時の宇宙船のキャプテンは、そのメッセージが約束していたもの、全銀河系の知識のコレクションを求めていた。彼らの宇宙船は光よりもわずかに遅い速度で航行することができたが、それでさえ彼らの旅は7万年以上を要した。
かつての文明、かつての生物
味気ない建物しかたっていないらしく、かつてタージマハルと呼ばれた建物が、昔の人間が作ったということに関して、人間たちが驚きを見せるシーンなどもある。
また、四つ足の獣、犬の姿をしたメカに関して、「それでわかった。これは元々人間が作った機械。少なくとも人間が作ったに違いない装置をいくつか素子として含んでいる」と推測された時も、そもそも人間がメカを作るという考え方自体が、異様な認識というふうに描かれている。
犬というのは遠い過去に人間を一種の神と思うようになった獣。彼らは他の獣の番をして財産を守った。という事前説明も結構興味深いか。
一方でメカは人間の部品(文字通りの生身の部分)を、時には金属部品よりも優秀なものとして利用したりもしている描写がある。特にそれら(細胞組織?)は自己複製による増殖が容易で、使用の効率がいいと。
重大な制約。プログラムのこと
メカと人間が最も共通認識として理解できる概念は、絶対の死。
有機生命体の最も重大な制約は、自分自身を思いのままにプログラムし直す能力に欠けていること。自分の行動が、さらに効率的かつ生産的になり得ることも知りながら、それでも、粗野な化学的運動の指示などに駆り立てられてしまう。たいていそういうものは、ダーウィン的圧力を通して進化が選択したもの。
有機生命体の欠陥は、適切にソフトウェアに収録されるべき行動の指示をハードウェアに固定していること。それは本能と呼ばれるもの、というようにも受け取れるか。
光の潮流
4作目。
『光の潮流 上』
『光の潮流 下』
有機生物、メカニカルとはまた別の扱いかのようなサイバーという生物パターンも登場する。
また、メカに利用される人間や、宗教なども重要な要素になっている。
前作からの主人公、キリーンが、アスペクトの干渉もあり、古代の時代について考えたりするシーンとかもある。
人類は、宇宙船を建造して、星々の間の希薄な流れに乗って、格段に優勢な種属の暴虐な存在に干渉されることなく、豊かに暮らしていた。
実際にメカ文明は、有機生物のそれに比べて、圧倒的に永続性的に有利。生物というものの始まりが基本的に有機物なのだとしても、やがて時間が経てば、どんな銀河系でもメカ文明が優位な存在になる。
宇宙船アルゴにおいての人間関係
宇宙船アルゴの中でさえ、男女の社会的な違いがかなりはっきり認識されていたりするのも、ちょっと興味深いのかもしれない。
キリーンが、息子トビーのガールフレンドであるビーセンが、なんでもかんでもトビーの言うことに盲従するわけではないというのを見て、満足する一幕とかもある。
また、〈城塞〉で定着した生活を営んだ世代が浸透させたという、思春期の女性がボーイフレンドの世界観を受け入れるという傾向は、概嘆すべきものとも。
〈城塞〉の陥落に続く、〈長い退却〉がそれを消したかに見えたのだが、しかしアルゴ船内でわずか数年で、そういう習慣が復活しかけているという説明もある。キリーンはその状況を結構危惧していて、女子の見習いが、よくある男子の傲慢な自信過剰に妥協することなく、自分たちの統率能力の芽を成長させることを望んでいる。 そういうことが戦場の重大局面で重要になるだろうから。
伝統的な見解として、女性が普通は最高のキャプテンになるという考え方があるのもまた興味深いか。一般的に、女が思春期のロマンチックな時期を過ぎ、子供を作ると、特に外交と妥協という能力が前面に出てくる。彼女らは配偶者、そして行政官として成熟し、キャプテンに成長するのだという。
初期宇宙がもたらしたストリング
超巨大で鋭い刃物のような構造、『宇宙ストリング』なる物理現象がガジェットとしてある。
宇宙ストリングというのは、古くは理論家が、単に理論的なもの、仮想的な存在として考えていたそれに、新たに名前を付けたもの。
そして、宇宙ストリングは、単一原子よりも、すぐ分子結合の間をすり抜けることができる
それは、宇宙の誕生の最初の瞬間に作られた可能性があり、その時期には、冷却しながら膨張する質量も想像できる。それは完全かつ対照的で均一にはならない、小さな揺らぎが真空状態に欠陥を生み出し、ある種の素粒子の状態を……つまり初期の宇宙で空間が折りたたまれて圧縮されたもの、というような説明もある。
銀河系中心世界における人間の年代記
4作目の本編後には、後に続く2作において、普通にそのまま舞台となる、銀河系中心世界における人間種族の年代記という概要がある。
小説の形でしっかり描かれているわけではなく、この時点ではどういうふうに物語を完結させるつもりだったのか、ちょっと不透明だが、何にせよ興味深い。
遠く地球から、銀河系の中心世界へやってきた、偉大なる時代
まずは〈偉大なる時代〉。それはおぼろげに記録されている、数千年に及ぶ時代とされる。人間は銀河系中心の密集した星々の間を自由に従来していた。しかしこの当時でさえ、彼らはメカ文面を恐れて避けていたという。
人間が伝える伝説によると、彼らは銀河系中心にいくつかの波として到達している。
最初は、高速に近いメカの宇宙船を捕獲した小さな一団。彼らはその平凡な乗り物のため、しばらくは発見されず、この時にメカの方法や目的を密かに調査することもできた。そしてメカ文明からさまざまな技術を学び、人間は有機生物としては、希有なほど高度な能力レベルに達することができた。
また、近傍の他の有機生物たちと同盟関係を結んだともされているが、それに関しては不明なことが多いようだ
この時期の直前、大規模なパルサー形成が開始され、それにメカのエネルギーの大半が費やされた。巨大な電子、陽子雲が作り出され、それまででもすでに相当な量であったパルサー付近のガンマ線バックグラウンドをさらに増やした。それらのガンマ線は分子雲を 加熱し、いくつかの区域に人間が侵入するのを妨げた。
わずかな記録によると、最初の人類遠征隊が、銀河系中心近くに住む有機生物の文明を含め、いくつかの探索に乗り出したことは示唆されている。しかしこれらの人間は姿を消してしまったという。
第二波は、メカが地球の海洋に異性生物を導入させたために起きた戦争の後、1世紀以内に発進したラムスクープ宇宙船の船団。
第三波は、宇宙標識が約束した伝説的な銀河系図書館を探すため 送り出されてきた、かなり大規模な遠征隊。しかし彼らが到着するよりも前に図書館は、正体不明の連中に持ち去られて消滅してしまう。
多くの絶滅した有機生物の記録を所蔵していたようである図書館。しかしそれを探す試みも失敗に終わった。
そして図書館の探索は、この侵入者軍にメカが気づき、敵対し始めたため、忘れ去られていった。
メカとの戦いを始めたシャンデリア時代
人間とメカとの戦いが始まってからは、〈シャンデリア〉時代だった。
人間たちは防衛のため、宇宙空間の大都市に集結。
残存する航海日誌などは、メカが恒星間旅行を経験し始めたことも示している。さらに「絶対中心」、あるいは「真の中心」と呼ばれる、銀河系中心のブラックホールを囲む区域では、放射線が増加し、有機生物には厳しい環境となった。
この時期の学者は、銀河系中心の初期の人間たちのことも調べていて、初期の時代に関する知識の多くを後に残しもした。
どんな場所も安全ではなくなってしまったアーコロジー時代
宇宙空間都市の〈シャンデリア〉の次には、メカに追われて、惑星表面に退却した人類が、〈アーコロジー〉という地表都市に生きる時代となった。
しかし時が経つにつれ、恒星間どころか、惑星間旅行も、メカのために困難になり、しかもそれまでは、メカがあまり興味を持たないとされていた、水分が多く植物がよく育つ惑星まで危険にさらされるようになった。
大規模データベースが失われ、アスペクトが利用されるようになった城塞時代
そしてメカの圧力により、ついに〈アーコロジー〉まで住居として適さなくなってしまった時代。
技術能力の維持も困難な中で、あまり目立たない〈城塞〉に、人類は引きこもった。
メカの侵略は進む。しかし被害の大半は、メカの都市が拡大して、資源を消費し、生物園を変えることによる副作用としてだった。
人間が宿すアスペクトの多くは、この時期を起源としている。
それは人間の基幹施設の崩壊によって、固定したコンピューター設備に蓄えられる人間のデータベースが危険に陥ったために、よく利用されるようになったと考えられている。
狩猟採集技術や、特にメカの倉庫の襲撃により、衰亡する農業を補い始めるにつれ、人類には新しい機能が生じる。人間はかつての科学技術を失ったが、メカ技術の再加工に専念。もはや潜在的には競争相手ですらなくなった彼らは、はしっこで暮らす害獣になった。
そして、3作目以降の舞台となる、〈厄災〉の時代へと繋がっていく訳である。
荒れ狂う深淵
5作目。
『荒れ狂う深淵』
前2作は、メカが圧倒的な支配力を得ている銀河系の中の、1つの惑星(恒星系)を主な舞台とした物語であったが、 今作はいよいよ、物語の重要ガジェットである銀河中心へと、キリーンたちが向かう物語。
大量の恒星が密集しているため、生命が生まれそうな惑星など、とてもありそうにはない、光り輝くその世界。そこに自分たちが求めるべき答えがあるのだと信じているような父(キリーン)と、それよりずっと現実的な目線で、なんとかその無謀としか思えない予定を変えさせようとしている息子(トビー)という図式が、なかなか面白い。
分子雲の中にすら生じる生態系
銀河系中心部から常に発せられてるような致命的なレベルの放射線。それに対して、船(アルゴ)の隠れ蓑にしている、分子雲の中。
蜘蛛の巣のような薄いシートを、その体に沿って広げ、帆として使う、蛇のような生物。その生物は、周囲に星の重力がない中で、光の圧力を推力として利用する。そういった生物の、獲物に対する狩りまでも確認されたりする。
分子雲には、有機分子も含まれている。酸素に炭素に窒素、それらを星の光でゆっくりゆっくり数百億年もかけて調理すると、そこにまた生命体が発生する。
星の光から漂う分子などからも離れ、単独で生きる宇宙植物すらも ありえる。さらには基本的な化学物質から考えて(つまりそれらは有機生物であるため)人間たちがそれを食料として取り込むことすらできるだろうとも。
進化の話、時空の話
メカの知性、サイバー、人間が、さらに生物について様々なことを話し合う。
全身は過去のデザインの宝庫。
進化は、有機的なものであれ、金属的なものであれ、プラズマ的なものであれ、その基底からは独立している。
デザインは習慣の中に封じられたクールな工学に従う。機能が形態に収斂する。不可視の中空ロッド(機能の繋がりを構成したりする棒状パーツ)。
また、銀河中心部の、時空が凍結したとも表現される、ブラックホール周辺を目指すであるために、 感覚とかけ離れた時空間の 原理的な 動きについての描写も結構多い
輝く永遠への航海
6作目にして完結編。
『輝く永遠への航海 上』
『輝く永遠への航海 下』
前作で、キリーンたちが到達した、 時空が凍結していた中で 存在しているような世界、エスティが主な舞台となる。
また、前作の最後で再登場したナイジェルが、地球に関する話や、自分のかつての冒険などを長々と語るシーンもあり、全てを繋げる話という感じがする。
「銀河系中心部で今も生き延びている全家族を合わせても、かつてのイギリス人の1/10程度の人数だろう」という情報などは印象的。
そしてとにかく、それまでに(つまり2作目以降に)ナイジェルたちに何があったのか。
メカ達というか、高度な知性は何を求めているのか。
基本的にはそういう、物語全体の謎解きのような話が、ひたすらに続くような構成になっている。
銀河系図書館、崇高な知性の大目的
重要なのは、銀河系図書館に、情報として保存されていた、生命体の物語のようでもある。
生命の始まりは具体物ではなかった。最初に現れたのは、相互に印刷しあい複製することのできる土塊。この宇宙の初期層で、彼らは膨大かつ多様なエネルギーを楽しんだ。当時、物質というのは今よりもはるかに熱かった。
その後、彼らは細胞生命の固有の領分を産卵し、それから淘汰された。
単純なものの見方では、世界の競争というのは、有機体の運命に強く関係する。彼らの騒動とエネルギー、悲劇と喜劇が中央ステージを占める。彼らは繁殖に励み、次の幕でも何とか必死にステージの上にいようとする。だが、もっと深いパノラマが存在していて、有機生命の絶え間なく変化するエネルギーのはるか奥まったところで、生命体の遺伝子こそが(限界はあるにせよ)真の俳優たちになっている。そして彼らもまた複製する。
つまり有機体というのは、より多くのDNAのコピーを作るための装置。遺伝子たちは必死になってこの目的を達成しようとする。
ある意味では、彼らが支配者で、よく生き延びるために遺伝子たちは脳を発明した。すると脳たちは逆に精神を支えるように進化。やがて精神は言葉や文化を通して互いにコミュニケーションすることを学習。そしてそれらがもっと広いステージを準備した。
それは、内部に外界のモデルを貯える複雑なモデル。絶え間なく変化し、より単純な源から得られる連続的な栄養物の流れによって支えられる。進化というものは、自然なものであろうと設計されたものであろうと、精神を改善することができる。遺伝子たちは無限に続く宿命の中で、自身を研ぎ澄まし、新鮮な精神のハードウェアを、より繊細でしなやかな精神を作っていく。遺伝子が有機生命よりも劣っているのは、彼らが有機生命というものを直接的に知らないこと。鈍重な生存のフィードバックだけが、遺伝子たちに、有機体ステージで演じられる、闘争や戦略について語る。
広い見方では、有機生命というのは遺伝子と同じく無頓着で、だが進化の危機的なステージで精神なるものが出現し、懸命な努力を始めると、そこに新たなステージが展開されていく。
遺伝子世界の見かけの序列の上の方、有機生命のドラマのさらに上の方で、より高次元の紛糾が演じられている。これが何よりも大規模な劇。そしてそのステージで、機械精神の自己複製というアイデアは、同じ進化の法則に従う。それらは機械遺伝子(ケーン)と呼ばれている。
そして生命、物理状態、それらのすべてが最終的に向かう、全情報の消滅。それを避けることこそが、メカの、高度な知性の……というような答が示されもする。




