ドゴンは本当に特別なのか
西アフリカといえば、マリのドゴン族の神話は、おそらく(エジプトを除けば)アフリカの神話の中でも最も有名だが、もちろんこの広い地域の国々に生きている部族は、ドゴンだけではないし、語り継がれ、記録されてきた神話も、彼らのものだけではない。
ドゴンは、アフリカ全土(時には全世界)において、驚くべき神話エリート部族と見られることがあり、実際に彼らの神話の世界観の壮大さ、複雑さには目を見張るものがあると思う。いわゆる、超古代文明の伝説についての話においても、よく取り上げられるほどだ。
それでも、 ドゴンの神話もあくまでも、それぞれに影響を与え合う東アフリカの諸部族の神話群の1つの例にすぎないと考えることが できる、という見方もある。
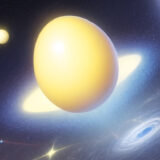 「ドゴン神話」創造神アンマ、世界の卵、ノンモと祖先たちの箱舟
「ドゴン神話」創造神アンマ、世界の卵、ノンモと祖先たちの箱舟  「シリウスミステリー」フランスか、宇宙生物か。謎の天文学的知識
「シリウスミステリー」フランスか、宇宙生物か。謎の天文学的知識
そもそも、今日でもまだまだ知られていない、あるいは(残念なことに)もうほとんど失われてしまったアフリカの伝統的な神話世界はいくらでもあるだろう。その中で、ドゴン神話は特別であるのだとしても、それはいくつかの特別の1つ、という可能性もあるだろう。
 「アフリカ大陸の神話基礎」四つの力、天空神、大地の精霊、秘密結社
「アフリカ大陸の神話基礎」四つの力、天空神、大地の精霊、秘密結社
アシャンティ。創造神とトリックスターの関わり
17世紀後半くらいからガーナのアシャンティ族(Ashanti)の人が始めたアシャンティ帝国(Asante Empire)は、広範囲に大きな影響力を持っていたという。
1900年頃、ガーナがイギリスの植民地になる時に、実質的に消滅したが、国が独立してからは、法的に準国家とされるようになった。
アシャンティの神話のキャラクターや物語は、ガーナやコートジヴォアールの他の部族たちと共有されている部分も多いようだ。
ニヤンコポンとアサセヤ
アシャンティ神話において、創造者である天空の至高神はニヤンコポン(Nyankopon。Onyankopon)という。ニャメ(Nyame)という別名も知られるが、別の人格的に語られる場合もあるという。
嵐の動きはニヤンコポンであり、雷は「神の斧」とされる。
ニヤンコポンには大地の女神アサセヤ(Asase Ya)という妻がいるが、アシャンティ族は、木曜日が大地にとって神聖な日と考える。だから地上の者が木曜日に働くのはタブーとされる。
春に農夫たちは、ニワトリを生贄として捧げ、土を掘り起こす許可と、それによる実りを祈る。大地は死者たちの墓でもあるから、酒を注ぐことで、彼らの許可も求める。
タノとビア、ヤギの策
タノ河(Tano)の神、あるいはその河自体が、重要な神タノ・アコラ(Tano Akora。Tando)として語られてきたとされる。アシャンティ神話においては、それは天空神ニヤンコポンと地の女神アサセヤの次男。
多くの話で、兄弟は対立する関係である。
天空と大地の長男はビア河(Bia)で、ビアは従順な子であったが、タノはわがままな子だった。子供たちが成人に達した時、神はビアに肥えた地を、タノには痩せた地を与える。
神は息子たちへの使いとしてヤギを送ったが、そのヤギはタノの友人だったから、彼にビアに変装するように言い、そして先に神のところへ行かせた。一方ビアには「神は忙しいからあまり急がない方がいい」と言った。
ビアのふりをしたタノは、肥えた土地を受け取った。後に本物のビアが来た時に、神を間違いに気づいたが、もう取り返しはつかなかった。
湖の精霊の子
湖は精霊たち、あるいは精霊たちが住まう領域。
ガーナのボソントウェ湖(Bosomtwe)は、死者の霊が集まるとか、その集まった霊たちが女神アサセヤの祝福を受けるとか、語られてきた。不漁の時、神の怒りを鎮めるために生贄を捧げたとも。
昔(1648年という説があるらしい)、アシャンティの狩人のアコラ・ボンペ(Akora Bompe)が、故郷であるアサマンの方から、獲物のレイヨウを追いかけ、この湖に来たが、湖でそのレイヨウは消えてしまった。それはまるで湖の意思が、哀れなレイヨウを救ったかのようだった。
そこで彼は、その湖を「ボソントウェ(レイヨウの神)」と名付けた。
別の説、あるいは別の時代の話として、ハンセン病にかかったために、夫も子供もいなかった老婆が、その湖の神トウェに出会った話がある。彼は老婆と交わろうとしたが、彼女は拒んだ。「自分は一人で暮らしてきて何も持っていない。もし子を生んでしまったら、ちゃんと育ててやることもできない」と。
トウェは言った。「もし何かを欲しくなったら、この湖の水面を叩けばよい。そうすればいくらでも魚が集まり、あなたはそれらを、とって食うことができる」
そして二人の間に、トウェ・アドド(湖神の子)と呼ばれる子供が生まれた。その子は、湖の精霊を守護者と称する氏族の創始者となったという。
鍛冶師の助手はアナンシか
アシャンティ族の天地創造神話では、たいてい鍛冶師が重要な役割を占めているらしい。
鍛冶師は天地創造において、天空神の助手として活躍したとされる。しかし、鍛冶師と天空神は別々の存在ではないという説もある。
天空神は通常ニヤンコポンであるが、「オドウマクマ」とか「オニヤメ・パンイン」、「アナンシ・クロコン」などとも呼ばれる。そしてそうした名前のいくつかは、アシャンティの間でよく知られたトリックスター(あるいは文化英雄)のアナンシ(Anansi)の呼び名と解釈されることもあるという。しかし多くの物語のパターンの中で、どちらかというとアナンシは、天空神の助手である鍛冶師
アナンシは「クモ(蜘蛛)」を指す名称であるが、神話の中で、これが本当のクモとして語られているかは、議論の的。
「アナンシはニヤンコポンと関係が深い」という者もいれば、「アナンシは諸部族の始祖で、かつては人間であった」とも。
 「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
創造の仕事の失敗
ある時、至高神ニヤンコポンは、彼に属する鍛冶師ムブソに、人間と動物を2ダースずつ造るように命じた。
しかし人間は動物より難しかったから、 ムブソは人間は1ダースしか造らなかった。それでも、ニヤンコポンが考えていたより、創造の仕事には時間がかかった。
待ちくたびれたニヤンコポンは、伝令長のイフ(黒猿)に、鍛冶師の様子を見てくるように命じた。
イフは出発したが、途中で彼の友たちがオダンサムという戦争踊りを踊っているのに遭遇。あまりに楽しそうだったので、与えられた任務も忘れて、一緒に踊った。
ムブソもイフも帰らないので、ニヤンコポンは自分で様子を見に行くことに。
途中、踊りに夢中になっているイフを見つけ、ニヤンコポンは尋ねた。「お前はいったい何をしている?」
必死に頭を下げるイフをとりあえずは許してやり、ニヤンコポンはさらに進む。
ムブソは、やってきた神を歓迎し、彼の作品を見せた。
ニヤンコポンは人間が予定よりも少ないことに気づいたが、ムブソはもう、完全に仕事をやり終えたふうだった。
ムブソは、まだ生命を持たない人や動物を神に差し出す。
ニヤンコポンは、緑の葉を右手で擦り合わせ、液汁を1ダースの人間たちの眼にたらし、彼らの顔に吹きかけた。さらに左手でも葉をを擦り、同じように液汁を2ダースの動物たちの眼にかけた。すると、人も動物たちも、立ち上って原野へと走り去った。
ムブソは神に、動物たちの数が人間よりかなり多いので、いくらかを人間に変えてください、と頼んだ。
ニヤンコポンは承知し、ムブソに集めさせたいくらかの動物たちに、また右手で葉の液をかけて、それらの野獣を人間にした。
別の説では、鍛冶師が造った人間や動物たちは、どの道ものすごい駄作だったので、仕方なく、神は創造の仕事を全て自分で行ったという。
ヘビと精霊とスズメバチとヒョウ
文化英雄としてのアナンシの話には、他の精霊が関わる話も多いという。
ある時にクワク・アナンシは、天空神ニヤンコポンのところに来て、物語を手に入れようと思った。
ニヤンコポンは聞いた「どうしてお前は私から物語を買うことができると考えたのか?」。
アナンシは言う「私ができると確信していますから」。
「ここには人間たちもやって来たが、彼らは物語を買いとることに失敗した。お前などちっぽけな存在なのに」とニヤンコポンは言うが、アナンシは気にしないで「それより物語の値段はいくらですか?」と聞く。
ニヤンコポンは言う「金では買えない。大ヘビ(オニニ)、精霊(ムモアテイア。フェアリー)、スズメバチ(ムモボロ)、ヒョウと交換だ」。
それを聞くと、アナンシは自信満々に宣言した。 「私はそれらの者たちばかりか、老母のスシアと6番目の息子をも連れて来ましょう」
アナンシは家に戻って母親と妻に事情を話し、必要なものを手に入れるためにどうすればよいかを教えてもらう。
それからアナンシは大ヘビを見つけると、「私はお前よりも長いものを知っているけど、本当か疑わしいと思っている。だから体の長さを測らせて欲しい」と、その体を伸ばしてもらった。そして隙をついて縛った。
 「ヘビ」大嫌いとされる哀れな爬虫類の進化と生態
「ヘビ」大嫌いとされる哀れな爬虫類の進化と生態
アナンシは次に、スズメバチの巣にヒョウタン(瓢箪)にいれた水のいくらかをかけた後、残りを葉の帽子をかぶった自分にかけてからスズメバチたちに言った。「これから大雨になるらしいけど、この瓢箪の中に入ったら雨宿りができると思うよ。僕を見てみなよ、もう葉で水を防ぐ準備も万端さ」。スズメバチたちは、これはありがたいとヒョウタンの中に入って来たが、当然アナンシは、すぐにそのフタを閉めた。
それからヒョウも、罠をしかけて捕まえた。
最後は精霊。アナンシは、「アクア」と呼ばれる、小さく平たい木偶(木ぼりの人形)を造り、精霊たちが好む樹液を採取し、アクアに塗りつけた。さらにヤム芋のエトという食物を用意し、アクアの手に置き、いくらかはタライの中に入れた。アクアは、オーダムという樹の下に立てかけられたが、やがて精霊たちが現れて、木偶に語りかける「アクアよ、食物をいただいてもいいかい?」。アナンシは糸で木偶を操作し、うなずいているように見せた。精霊は一緒にいた妹に「アクアは食べてよいといっているよ」と食べ始めた。食べ終ると彼女はアクアにお礼をいったが返事はない。妹が「痛がるようなところを叩いてみたらどうかな」と言った。言われた通りに精霊は叩いてみたが、すると手がくっついた。彼女は言った「手が離れなくなったわ」。妹は「ではもうひとつの手で叩いてみたら」と提案。もちろんその手も離れなくなった。彼女は妹に言う「あなたのおなかで押してみて」。しかし妹の身体も木偶にくっつく。こうしてアナンシは精霊まで手に入れた。
 「妖精」実在しているか。天使との関係。由来、種類。ある幻想動物の系譜
「妖精」実在しているか。天使との関係。由来、種類。ある幻想動物の系譜
宣言通りのことをやってのけたアナンシに、ニヤンコポンは言った。「よろしい、クワク・アナンシよ。今日から私の話はお前のものだ。コセコセ(祝福の言葉)はもう私のものでなく、蜘蛛の話と呼ばれることになるだろう」
三色の汚い精霊たち
昔、飢饉の時。アナンシとその息子アナヌテは、草原で食物を探している時にシュロ(棕櫚)の実を見つけた。
アナヌテがまさに実を割って食べ始めようとすると、それは手から落ちて、ネズミの穴の中に入ってしまう。
アナヌテは穴に入り、やがて黒、赤、白の三色の精霊の居る場所にたどりついた。それらの精霊は天地創造の時以来、顔を洗ったことも髭を剃ったこともないものたちであるから、とても汚かった。
汚い精霊たちは、アナヌテがたった1個のシュロの実に苦労させられていると知って驚き、同情した。
それで彼らは、自分たちの畑のヤム芋をいくらか取ってアナヌテに与えて、言った「芋の皮をむいたら、よい部分を捨て、皮の部分のみ料理しないといけない」。
アナヌテが教えられた通りにすると、皮はとても美味しい芋となった。そして三日間、そこで美味しい芋を食べたアナヌテは、四日日には帰ることを決める。精霊たちは、大きな籠いっぱいのヤム芋をくれて、さらに途中まで見送りながら、歌を教えてくれた。
「(独唱)
白い精霊、ホ、ホ
赤い精霊、ホ、ホ
黒い精霊、ホ、ホ
(合唱)
この頭がいうことをきかないなら
何が私に起るかな?
彼が捨てさった頭
彼が捨てさった脚
汝は、偉大な呪物神を怒らせた」
それは、絶対に1人でいる時にしか歌ってはならない、とも教えられた。
アナヌテがヤム芋を大量持って帰宅してくれたおかげで、人々は食糧危機を乗り越えることができた。そしてまた芋がなくなっても、彼は例の場所に行けば、教えられたことをよく守っている彼に、精霊たちはいくらでも芋をくれた。
アナヌテの父、すなわちアナンシはあまり良い気分ではなかった。しかし、父の悪い部分をよく知っている息子は、一緒に行きたいという彼の希望を承諾しなかった。
そこでアナンシは、真夜中、息子の袋にこっそり灰をつめ込んでおいた。さらには、精霊たちの所へ向かう彼より先回りして、息子が代役を頼まざるをえないように仕向けた。
そして、精霊たちの所にやってきたアナンシは、息子から事前に受けていた様々な注意を全て無視して、精霊たちの嫌がることばかりした。
彼は精霊たちを「汚い奴ら」とからかい、偉そうにヤム芋を要求し、皮に関する忠告も「ばかばかしい」と無視した。ただ、勝手な方法では芋が炊けないということを知ったから、その後はちゃんと言われた通りにして、すると芋は美味しくできた。
別れ際に、精霊たちはやはり、人前で歌ってはいけない歌をアナンシに教えたが、彼は精霊たちの姿が見えなくなるや、周囲を気にせずその歌を大声で歌う。すると彼の体は頭から裂け、ひっくり返って、歌いながら死んだ。さすがに精霊たちは哀れに思い、彼を蘇らせてやったが、復活すると、また彼は感謝もしないで、好き勝手に歌った。
それでさすがに精霊たちも相当に怒って、アナンシから、与えたヤム芋を1つ残らず取りあげた。
後で、帰還した彼がしでかしたことを知った人たちも、怒って、彼を村から追い出した。
大地から現れた人間たち
アシャンティには、 人間たち、少なくとも現在生きている人間たちの起源を、創造神の仕事でなく、自然発生的なものとして捉えているような神話もいくらかある。あるいはいくらかの人間たちは、創造された後、今のように地上にはいなかったが、何かのきっかけで現れたと。
例えばある説話では、始祖たちは地中の穴から表に出てきたされる。
部族のあるグループには、月曜日というのが特別な曜日らしい。なぜなら、昔、ミミズが大地に道を通した時に、7人の男と、数人の女と、1匹のイヌと1匹のヒョウが現れたのは月曜日。
そして地上に出てきたばかりの時、男たちも女たちも見慣れない風景に驚いたが、リーダーのアジュ・オギーネーだけは恐れなかった。ところが水曜日、家造りの最中、木が倒れてきて彼は死んだ。
その後、イヌがどこかで見つけた火をもち帰った。
創造の神は、いろいろな物を造りながら、世界中を旅していたが、この大地から現れた人たちと出会うと、そのうちの1人を自分の助手として、また自分の意思を人々に伝えるメッセンジャーとして働かせることにした。その人は神の身内として、永く特別な導き手であった。
今も年中行事には、その最初の人々を偲んで催されるものがあるが、彼らが神に捧げてきた酒の壺が、森のなかにあるという。
別の説では、昔、一組の男女が天空から来たが、もう一組の男女が大地から来た。
天空の王はまた、無毒のヘビであるパイソンを地に送った。パイソンは河に住処を作る。人々は生殖や生誕のプロセスを知らなかったから、パイソンはそういうことを教えてやった。
パイソンは、それぞれの夫婦を向かい合わせ、それぞれに腹に水をかけて、「クスクス」 と、今でも氏族の儀式に使われる言葉を言い、後は帰って一緒に寝るようにと言った。
すると、女たちは妊娠して子供を生めるようになった。だから、彼らの子孫の氏族の間には、パイソンが神聖な動物であると伝わっている。
クラチ。星々の出会い、死との出会い
ガーナ(あるいはトーゴ)のクラチ族(Krachi)は、太陽と月が夫婦で、その子供たちを星々と考えるという。
星々の戦い
ある時に月は、夫に飽きて愛人を持った。それで太陽は怒って妻と別居。彼らは財産を分け、子供たちのあるものは彼と留まり、他のものは月と共に去った。
しかし月は不満で、夫の領域に踏み込み、その時に太陽と子供たちと、月と星たちとの戦いが嵐となった。
ただ月は、子供たちがいつまでも戦うことは望まず、多色の布を使者にたなびかせてもらうことで、彼らを仲直りさせようとした。その多色の布というのが虹である。
時に太陽は、月を捕まえて食ってしまおうとするが、それが月食で、人々は大きな声や太鼓の音を響かせて、太陽を驚かせて、月を助けようとする。
死の巨人
昔、飢饉の時に、食物を探して森をさ迷っていた男が、見知らぬ土地に着いた。彼はそこで、非常に髪の長い巨人と出会う。その巨人の名前は「死」だった。
男が空腹であることを知った巨人は、「召使いになれば、食物をやろう」と提案。男は了承し、しばらくは巨人に仕えたが、だんだんとホームシックになってきて、暇が欲しいと巨人に伝えた。巨人は「交替の召使いをよこしてくれるなら、よい」と言った。
それで、男は弟を巨人のところに連れてきて、自分は家に帰った。
それからまた、飢えが酷くなってきた時に、彼は巨人のところに戻り、また働いた。ところが、弟の姿を見なかった。巨人に聞いてみたが、所用で出かけているとのこと。
次に男が休みを望んだ時には、巨人は結婚相手の娘を要求し、男は妹を巨人に紹介。
さらに、再び彼が巨人のところに来た時には、妹もいない。そして男は、美味しい肉が用意されていた家の中で、妹のものである骨を見つけしまう。
逃げた男は、村の人々と共に森の巨人のところに来たが、恐ろしいから直接的には攻撃できない。そこで彼らは、巨人の遠くまで伸びている長い髪に火をつけた。やがて、巨人の所にまで流れてきた火は、ついにそれを殺した。
その後、人々は、巨人の髪の付け根に魔法の粉薬を見つけた。巨人の家の骨にその薬をかけると、男の弟と妹は蘇った。
反対する者も多かったが、男は魔法の粉薬を、少しだけ巨人にもかけてみた。すると倒れている巨人の目が開き、人々はすぐに逃げ出した
そうして、死は今も地上にある。死が、目を開けたり閉じたりするたびに誰かが死ぬとされる。
フォン。悠久なる創造の連鎖
ベナンのフォン族は、ギニア湾岸の方の地域に特異な政治体制の植民国家を樹立していた。そのダホメ王国(Dahomey)は、かなり中央集権化した国で、すべての官吏の任命権が王の手中だったとされる。王以外は、王族の者も、ある程度の特権があるくらいで、国の政治に介入することはできない。
また王は七人の高級官吏を任命し、彼らの妻は「母」と呼ばれ、宮廷においては夫より高い地位を占めていた。そして形式的には、母后(王の母)の方が、王様より立場が上であった。
王国の社会は、かなり厳格な階層制に支えられていた。官吏や祭司が上位で、下に農耕を行なう平民階層、さらに最下層の奴隷たち。
親族集団、父系クランも社会単位としてあって、最年長の男が小集団の長となった。基本的に一夫多妻で、家屋敷内、各妻はそれぞれの小屋に子供たちと住む。
信仰や儀式関連でもかなり分化があり、神ごとに、その神だけを祀る祭祀集団があった。『ヴォドゥ(vodoun)』と総称される、その集団ごとの神々は、起源を辿れば全て創造神から生まれた存在(例えば、ある神様を生んだ神様を生んだ神様が創造神)
ヴォドゥ教義における下級の神、あるいは精霊の総称として『ルワス(Lwas)』というのもある。ルワスはたいてい、石とか木といった自然の中の無生物物体に宿るか、それらが実体化した存在。
ほか、神格化された死者は『トヴォドゥ』と呼ばれ、生者と神々の間の仲介者としての機能を果たすという説もある。
王は至高神と特別のつながりがあるか、あるいは王自身が最も偉大なる神の象徴とされ、各地での下位の神々の信仰が、王国のイデオロギー(社会思想)を形成していたとも考えられている。
マウ・リサ。月と太陽
通常、フォンに伝わる至高神は、創造神マウ・リサ(Mawu-Lisa)とされる。マウとリサというのは2柱の神とされることもあるが、1柱の神の2つの側面として語られることも多い。
実は世界の創造は1回限りでなく。現存する世界が創造される以前にも世界は存在し、創造者は世界の度に異なるとされるようだ。創造神マウリサも、より古い世界の神々に創造された存在。そして現存するヴォドゥ(神々)はマウリサから生まれた。そしてマウリサは、すでに存在している素材を用いて世界をつくった。
マウリサを生んだのは、両性具有の神ナナ・バルク(Nana-Buluku)ともされているが、経緯などはかなり不明。
マウとリサが別の神とされる場合、マウは西に住む月、リサは東に住む太陽。そして、日食や月食のときはいつでも、マウとリサが交わっているのだとされる。
球体世界の内部
フォンの間では、カラバッシュ(Calabash)というヒョウタンは、 実用的によく使われてきた。柔らかいなかみをきれいに取ったら、固い皮は入れ物としてかなり有用になる。水を蓄えたり、固い種を入れてガラガラ(楽器)にしたり。礼拝所に、水平に2つに切った丸いカラバッシュが置かれる場合があるが、その場合は供物や、象徴的な品が入れられる。カラバッシュの上下それぞれの殻にしばしば彫刻が施されるが、その模様は多様。
カラバッシュが象徴としてよく使われるのは、それが宇宙の形に似ていると考えられているからである。宇宙は丸みの強いヒョウタンのような球体で、分割されている上と下の緑が合うところが水平線。それは、空と海が混じり合うところ。
地球は、大きな球体の内部の水域に浮かんだ平坦な大地と考えられている。どうも、地を掘ったら、水が発見されるという経験から想像された世界観らしい。
太陽、月、星は、球体の上の方の部分を移動するもの。
死者たちの場所は不確かだが、大地の上空領域、大地の底の場所の2説が一般的だという。
神々の役割とそれぞれの言葉
サグバタ(Sagbata)は大地の存在で、マウとリサの子供たちだった。マウは1柱の神だが2つの側面を有する。つまり月の眼の女性の半身マウと、太陽の眼の男性の半身リサである。
マウリサは両性具有の神なので自ら身籠る。最初に男女一組の双子が生まれ、男の子はダダ・ゾジ(Dada Zodji)、女の子はニオウェ・アナウ(Nyohwe Ananu)と名づけられた。二番目に生まれたソグボ(Sogbo)は両性具有のひとり。三番目に生まれたのはまた男女の双子で、男の子はアグベ(Agbe)、女の子はナエテ(Naete)と名付けられた。四番目は男の子アジェ(Age)。五番目は男の子グー(Gu)だが、この子には頭がなく、首から大きな剣がはえていた。六番目に生まれたのは神でなくジョ(Djo。空気)だったが、空気は人間を創造するために必ず必要な存在だった。そして七番目にレグバ(Legba)が生まれた。
ある日、マウリサは子供たちを集めて、各自が支配すべき領域を教えた。
最初に生まれた双子にはすべての富を与えられ、地上を領域とする。ソグボにはマウと似ていたから、天上に残る。アグベとナエテは海で水を支配する。アジェは狩人として藪に住み、獣と鳥を支配する。グーは、はなからマウの力、あるいは道具としての役割であり、頭が与えられていなかったのはそのためだった。
最初の頃の地上は、そのすべてが藪で覆われ、何もかも閉ざされていたのだが、グーの働きのおかげで、地上から藪がいくらか切り取られ、開けた部分ができた。そうして人間が幸福に生きるための場所を与えてくれたのは彼である。
ジョは天地の間の空間に住むことになる。彼には人間の生命が委ねられた。
マウリサは地上へと降りる神々にはそれぞれに異なる言語を与え、天上で用いていた言葉の記憶は奪った。ジョに与えられたのが人間の言葉であった。
最後に残っていたレグバに、マウは言った「お前は末子だから、私はお前をとても甘やしてばかりだった。だから、他の子供たちと同じように扱うわけにはいくまい。お前はこれからも私のそばに住ませよう。お前の役目は、時々兄たちが治める領域を訪れては、そこで起こっていることを私に報告することだ」
その役目のために、レグバは兄たちが用いる言葉も、天上のマウリサの言葉もすべて知っているという。だから、地上の人たちが、マウやその子供たちに何か言いたいことがある時、必ずレグバを通す必要がある。
火と水。宇宙で最も重要な二つ
創造神マウは、世界を創造した後は、もうそれに関与することを止めて、息子のサクバタ(大地)とソグボ(嵐)に世界の支配を委ねた。
しかしある時にこの兄弟は喧嘩して、兄のサグバタは怒って天上を去り、地上に住むことにした。長男だった彼は、母の財産も含め、相続すべきもの全てを持って、天を去った。
母のマウは兄弟の間に入り、言った「お前たちは一体となって、その中に世界が入るべきだ。そして兄のサグバタは下の大きい部分に、弟のソグボは上の部分になるべきだ」
しかしソグボは母の言うことを聞かないで、いつまでも母と共にあろうとした。
一方サグバタは、地上へと降りはじめると、もう天にも戻れなくなり、やがて地上で暮らし始める。
天上にとどまったソグボは、やがて母や彼女をとりまく他の神々の信頼を得た。そしてある日、彼は地上に注ぐ雨を止めてしまった。それで地上はきびしい干魃に見舞われた。サグバタは、地上の人々の国の王になっていたが、雨が降らない日が続き、民からの不満も募ってきた。
その頃、天から降りてきた2人がいて、占いのための運命文字『ファ(fa)』、あるいは『イファ(Ifa)』のことを人々に教えていた。噂は聞いたサグバタは2人を招き、雨が降らない理由を聞いた。彼らにはわからなかったが、イファについては教えてくれた。それと、少し前まで天にいた彼らは、天のソグボが怒っているということは知っていた。
サグバタ自身も、イファの占いにより、弟の怒りを直接確認する。天の2人からはソグボをなだめるように勧められたが、サグバタにはもはや、あまりに遠くなってしまった天空に帰る術がなかった。
天のソグボが、今や完全に支配下に置いてるのは水であった。実はサグバタは地上に降りる時、母の与えてくれた富を全て持っていく権利を持っていたが、水は袋に入れることが出来なかったから、天に残してきたのである。
サグバタは、地上にいて雨を降らせる方法がないか、天の2人に聞いた。2人は答えた「雨乞いの儀式で犠牲を捧げる際ごとに、地上の富の一片を、ソグボの親友であるウトゥトゥ鳥に与えるようにするのがよい。そしたらウトゥトゥ鳥が、直接ソグボに雨を願ってくれるだろう。
サグバタは教えられた通りにして、ウトゥトゥに弟への伝言も伝える「世界の支配権を彼に譲るつもりでいることを伝えてくれ」と。そして伝言を聞いたソグボも、ウトゥトゥに返事を持たせる「兄に伝えてくれ。お前は長男だから母の富を全部相続したのに、愚か者で、宇宙における重要な2つの力を残してしまった。そして、私は弟だけれど、その2つを使って、結局はお前が与えられた全ての富を支配するのだ」。2つの重要なものとは火と水である。
地上を目指すウトゥトゥが天と地の中間くらいに来た時には大雨が降り、サグバタはその鳥を殺すことを禁じた。そして兄弟はついに和解した。それは、毎年かならず雷が地上を訪れるようになった理由でもある。
金属で地上を開拓
マウが男か女かを誰も知らないのに、多くの人はマウを神々の母と考える。
マウは世界を創造した後は地上を去って、天に住居を定めた。それからは二度と地上に戻ろうとしなかった。
人間たちは知らないことばかりで、マウが去ってからの地上は何一つうまくいかない。
マウは、人間たちを導くためにリサを地上へおくった。マウは事前に、リサにグー(金属)を与えて、グーの力により藪を切り開くことで耕地をつくることを、人間たちに教えるように頼んだ。
そうして、地上に現れたリサは、グーの力を借りて、人々が何をするのにも邪魔になっていた、地上を覆っていた藪を切り開き、焼払い、人間たちが住む村や、その周囲の耕地のための空き地を用意してやった。
リサは、人間に家を建てることも教え、後は「時に立ちはだかる障害を克服するためには、金属が必要であることをよく知っておけ」と人間たちに伝えてから、天上に帰った。
リサの仕事はマウの心に適ったので、リサは太陽に棲むことを許された。そしてリサは、今でも家である太陽から世界中を見ている。
王様と王様の子
誰にでも親切なレグバは、マウのそばでいたから、彼が何かよい事をする度に、人々はマウにお礼を言った。レグバは最初は、マウの命じることを忠実に行なっていた。
しかしある時に、レグバはちょっとばかし失敗をして、人々の怒りを買ってしまった。そして人々に抗議されたマウは「それはレグバのやったことだ」と答えた。それで人々はレグバを憎むようになった。
ある夜に、レグバはマウに聞いた「なにかよくないことが起こると、なぜ私のせいにするのですか?」。マウは答えた「どんな国でも、首長(王)は常に正しく、悪いのは臣下なのだと思われないといけない」
その後またしばらくして、レグバは「あなたの大切なヤム芋畑を、盗人たちが狙っているようです」とマウに忠告した。真に受けたマウは、王国の住民全員を集め、「最初に私の畑にヤム芋を盗みに入った者は死刑」と申し渡した。
そしてまた夜に、雨降りの中、レグバは盗んだマウのぞうりを畑の中に置き、ヤム芋を全部持ち去った。翌朝には、「自分のものを盗む者がいるとは」と人々は呆れたり、怒ったり。マウは「すべてレグバの陰謀だ」と弁解しなければならなかった。
そしてマウは、地上を去った。しかし天空はこの時代、地上からわずか2メートルくらいの高さにあったとされる。ところが、レグバのその悪戯以来、マウはレグバを見る度毎に叱るので、その内に面倒くさくなったレグバは、また一計を案じる。
レグバは、1人の老婆を唆して、天のマウがいるあたりに水をかけさした。その水は、皿や壺を洗ったあとの汚いものだったから、マウは怒って言った「こんなところ、わずらわしいことが多すぎる。私はもっと遠くへ行こう」
こうしてマウは自らの暮らす天空を高くして、レグバは地上に残った。
神聖なるヘビたち
集めた土を固めて大地を作り、水の境界を決めて、現在のような球体世界は創造神が造った。球体は上下の部分でくっついてるわけだが、それをくっつけているのは神聖なるヘビたち。そのヘビたちは、地球の周りではとぐろを巻き、あちこちに神を運び、完全な行動によってあらゆるものを支えるそうである。
ある説では、世界が創られた時に、土を集めて、人間の住むための場所(つまり大地)を与えたのはヘビたちであった。そして、今もヘビたちは世界を支え、創造されたものたちが分解しないように、とぐろでくっつけている。
大地の上下には3500ずつのとぐろがあるとか。別の説では、ヘビは天を支えるための東西南北の4本の柱をまっすぐに保つために、それらの柱の周りに体を巻いている。
黒、白、赤という天の三原色は、ヘビたちが夜、昼、夕方に着る着物の色とも。ヘビたちは完全にじっとしている訳でなく、地球の周囲を動き、天体はその影響を受けて運行している。また地震も、大地を支えるヘビの動きのためと解釈されてきたようだ。
大海に浮かぶ大地
創造の段階においても、ヘビたちが重要な役割を果たしたという説がある。
(地上全てが藪に囲まれているために、切り開いて空き地を用意する話のパターンと比べてみると興味深いかもしれない)最初の頃の大地は水ばかりだったので、ヘビたちは、川などの水域のための溝を設計した。それで生命が享受できる渇いた大地ができた。
また造物者が最初に創ったのは巨大な(「Da」という名前が設定されていることもある)ヘビで、造物者(創造神)を口にくわえて運ぶ役割が与えられた、という説もある。ヘビが造物者を運んでいた時、立ち止まったところに山が現出した。山は、ヘビの糞が固まったものともされるが、(ヘビたちは原初にいろいろな宝物を与えられて、それらを食べていたとかだろうか)人々が山を掘り進むと宝が見つかるのは、その現れた経緯に関係しているとも。
造物主は仕事を終えた後、大地(地球)にはあまりにも山や川や大きな動物が多すぎて(重たいから?)、ほっておいたら周囲の海に地球が沈みそうなのをどうにかしようとした。それで彼は大地を支えてもらおうと、尾を口にくわえてとぐろを巻くようにヘビに頼んだ。ヘビは、物の運搬用の丸い詰め物のようになった。
ヘビは暑さを嫌うが、常に触れている海により冷やされてもいる。神は、海に住まう赤いサルたちに、ヘビが飢えた時に食料となる鉄の棒を造ってやるように命じた。サルたちも鉄の餌をやるのを忘れてしまう時があり、そのたびにヘビは飢えをしのごうと、自分の尾を食べて、結果、自分の体を小さくする。さらには、大地に生きる人々はどんどん増えて、さらに彼らが造った家などのために、全体の重みも増した。もしいつかヘビが、重くなった大地を支えきれなくなってしまったなら、その時、大地は海に沈んでいく。つまり世界の終わりである。
二重の虹
その神話での役割から、ヘビは神聖視されることが多い。そしてヘビの象徴の代表的なものとして、『二重の虹(dual rainbow)』というのがあるともされる。
ヘビは時に虹に見いだされ、赤い部分が男、青い部分が女の部分という二重性も語られる。それはマウリサや、ヒョウタン宇宙の二重性と同じとも。
大地を支えるヘビは、芸術の中ではよく2匹の姿で描かれ、1匹は大地を巻き、もう1匹は空に現れる。
『虹のふもと』に財宝が発見されるという伝説もあって、その財宝とは、装飾用のビーズとも、あるいは山から掘り出されるというヘビの金ともされる。
ヨルバ。始源の宇宙より
ナイジェリアのヨルバ族(Yoruba)の神話世界には、フォン族のと強く関連するものも多いようだが、そもそもベナンに起源があるというヴォドゥ信仰は、フォンとヨルバの宗教が混ぜ合わせることで誕生したとも考えられている。
例えば、ヨルバの神話世界観においてオグン(Ogun)とよばれる、金属や戦争の神は、フォン神話のグーと同じ神(ルワス)とされる。
全知全能の創造神にして、全ての源
オロドゥマレ(Olodumare)は、人間の活動や自然の力すべて、善と悪の両方、宇宙の進化のための全ての要素(つまり万物)を創造したとされている、全知全能の創造神。
これは全ての源でありながら、空間、時間の次元に縛られない神聖なる存在ともされる。
ただし、この至高神が直接的に崇拝されるということはあまりない。他の全ての神はこれの一部が現れたものという説があるが、普通、人々はそうした他の神々をオリシャ(Orisha)と呼び、個々のオリシャを通じて、間接的にオロドゥマレと繋がろうとする。
創造神としてのオロドゥマレは、2柱の神とも語られる。
空の神オロルン(Olorun)と海の神オロクン(Olokun)である。オロクンの方は、女神であるというイメージも一般的だという。
オリシャ・ンラの創造の仕事
最初、世界は水だらけの荒れた土地であった。 その頃から上には空があって、空の所有者オロルンが他の神々と一緒に暮らしていた。
ある日、神々は荒れ地で遊ぼうと、クモの巣を伝って天から降りて来た。固い地面もないので、人間はまだいなかった。
オロルンは、神々の首長であるオリシャ・ンラ(Orisha Nla。大きな神)、すなわちオバタラ(Obatala)を呼び、固い地面を造ってくれと頼んだ。別の説では、その仕事を頼まれたのは神託の神。
オリシャ・ンラは、ばらばらの土を入れたカタツムリの殻と、ハト(鳩)と、5本の足指をもつメス鳥を与えられる。彼は湿地にカタツムリ殻の土をまいた。地に足つけたニワトリと雌鳥が、それらの土をさらにちらばらせる。そして湿地の大半を覆った土が固まって、人も住めるような地面が完成した。
地面完成の知らせを聞いた至高神は、そのできを確かめてもらおうとカメレオンを派遣する。
カメレオンは一度は、大地がまだ乾き切っていないのを確認したが、再度検査した時に、もうそれが広く乾いていることを確認。
創生がはじまった場所は『イフェ(Ifẹ。広い場)』と呼ばれたが、いつからか、「イレ(家)」という言葉が付け加えられ、『イレ・イフェ(Ilé-Ifẹ̀)』となった。それは、その場所で、全ての家の建築が始まったことも意味している。イレ・イフェと呼ばれる場所は、ヨルバ族の最も神聖な都市である。
大地の創造には4日かかったが、5日目は大神を崇拝するための日とされたから、働くの週(全5日)の4日で、1日は神を祀る日となった。
造物主は人間の食物を与えようと、オリシャ・ンラにいくらかの植物の種を撒かせた。しかしヤシの木以外(あるいはヤシの木も)、大雨の時にどこかへと流されてしまう。
最初の部族は天国で創られてから、地上に送られた。人間創出の一部を任されていたオリシャ・ンラは、人間を土から造った。だが、彼が許されていたのは形を整えるまでで、命を吹き込む役目はあくまで造物主の仕事。彼はそのことが不満だった。
そこで、いかにして命なきものに命が吹き込まれるのか、その方法を盗み見てやろうと、オリシャ・ンラはこっそり、自分の作った土人形の1つにその身を隠した。だが全てを把握していた造物主は、いつもの作業を始める前に彼を眠らせて、彼が目覚めた時にはすでに人形たちには生命が宿っていた。
オリシャ・ンラは今でも命の形だけを作るが、時々不満の印であるアザを刻むのである。
天空神と海神の対立
ある説では、始源の宇宙は、空と湿地の水だけで構成されていたが、オロルン(あるいはオロドゥマレ)が空を支配し、オロクンが下の広大な湿地帯を支配することになった。
オロクンは最初は、彼女の水中の王国に満足していたが、オバタラという小さな神が、オロクンの王国について改善のアイデアを持っていた。
それでオバタラは、至高神(オロドゥマレ?)に、畑や森や丘や谷など、さまざまな陸の生き物が住みやすい堅固な土地の作成を提案。至高神はそれは良いことだと同意し、彼に土地作りの許可を与えた。
オバタラは、オロドゥマレの最初の子ともされるオルンミラ(Ọrunmila)に、自分の計画を実行するのに、どんなよい方法があるかを聞いた。
オルンミラは、金を集めて、空から下の海に降ろすことができる鎖を作るようにオバタラに言った。そして鎖が完成すると、オルンミラはさらに、砂で満たされたカタツムリの殻、白いニワトリ、黒いネコに、ヤシの実を与えた。
オバタラは鎖に身をかがめ、砂を水に注ぐ。そしてやはり鳥が砂を散らばらせる。砂が落ちたところが乾燥した土地になった。
オバタラは、イフェという土地に家を建て、ヤシの木を育て、黒ネコを仲間として暮らした。
やがて、オバタラは孤独をどうにかしようと、粘土で人形を作り、オロルンが、それらに生命を吹き込み、人間が誕生した。多くの神々が空から降りてきて地球に住んでいたが、オロドゥマレは彼ら全てに、人間の祈りに耳を傾けて、彼らを守ることを命じた。
しかし水の国の女神オロクンだけは、地上で行われた創造行為に不満を見せていた。乾燥した土地ができたために彼女の世界は小さくなったから。それで彼女は、失った自らの領域を取り戻すために、大洪水を起こし、全ての土地を沈めようとした。
だがオルンミラが、その力により水を後退させる。
天空のオロルンの子に負かされて、ますます腹を立てたオロクンは、造物者たる至高神を、今度は力でなく名声で負かしてやろうと考える。それでオロクンはオロルンに、「互いに最も美しい着物を着て、お披露目し、公衆の賞賛を受けた者が勝利」という勝負を持ちかける。
しかし対決の日にまずやってきたのは、オロルンの使いのカメレオンであった。ところがその使いからして、オロクンと同じような、とても豪華な衣装を着けていた。それでオロクンは海の宮殿に一旦戻って、さらに美しい衣装を仕立てた。ところが再び出て見ると、カメレオンはまた同じ衣装。 そしてこういうことが何度か繰り返された末に、「神の使いですら、私と同じくらいに美しい衣装なのだから、天空神はもっとすごいに違いない。私に勝ち目はない」と、戦う前に諦めてしまった。
鉄と狩猟の神
オリシャ・ンラが大地を固めた後、彼は密生した森を見つけたが、道具が青銅のものばかりだったために、邪魔な木々を切ることもできなかった。
しかし鉄の斧をもっていたオグンは道を開くことがてきた。
それから、彼らが聖なる都市イレ・イフェを建設した時、他の神々は道を切り開いてくれたお礼として、鉄の神オグンに王冠を送った。
ところがオグンは、狩りと戦いが大好きで、地上でそれをもっと楽しみたいと願い、仲間を支配することは好まなかった。それで長きにわたって、ひとりで(獲物を見つけやすい)見晴らしのよい丘の上に住んだ。
オグンがついに神々のところに戻った時、彼の服は血の染みだらけだったから、神々は彼をなかへ入れようとしなかった。彼は、ヤシの木の皮で着物を作ってから、どこかへと去った。
かつて人間だった嵐の神
雨は恵みになることもあれば、強風と共に、暴風雨をもたらすこともある。落雷も伴って、人里に大きな被害を与えることもある。だから嵐の神(精霊)は、たいていどこの土地でも重要な存在と考えられている。
ヨルバの嵐の神シャンゴ(Shango)は、元々は広大な領土を有する王国の 4代目の王、つまり人間であったという。彼は絶対的な権力を持つ王であり、偉大な医者であり、しかし、口から火を吐くこともできる、恐ろしい暴君でもあった。
ある時、この王に対し、2人の大臣が反逆を企てたが、王は彼ら同士を戦わせることで同士討ちさせようとする。しかし、本来は味方同士の2人のその戦いで、片方は死んだが、生き残ったもう片方はさらに怒りを増して、王に攻撃をしかけてきた。それで王は、3人の妻と、いくらかの忠実な家来たちを連れて森へと逃げた。
その後の長い逃亡生活で、ついに、側にいてくれるのが最愛の妻だけになって、絶望した王はコソという土地で、木に首をくくって自殺した。
旅の者により王の死が知られるや、彼の敵だった者たちは、 勝利の喜びに浸って、それでも王への忠誠を忘れない者たちを嘲笑った。王のかつての友たちは、敵どもの家を燃やしてやりたいと、呪術師たちに相談。呪術師たちは、天から火を落とす方法や、嵐の日に火薬を詰めたヒョウタンを屋根に投げるという策を、彼らに授けた。
そうしてあちこちで火事が起こり、王の忠実な家来たちは、「王は今だに健在」と語った。彼は死してなお、天から怒りの火を送ってきてるのだと。彼をなだめるには犠牲が必要となる。
コソには礼拝所が建てられた。そこの祭司は代々、王であったシャンゴが、地上を去った本当の経緯を語り継いできたという。
つまりシャンゴ(王)は、情けない逃亡生活に不満を持ち始めた家来たちにも怒って、森のなかへひとり消えた。捜索隊が後を追いかけたが、乗っていたウマが見つかっただけ。と、その時、空から声が聞こえてきた。
すなわちシャンゴは首吊り自殺をしたのではなく、縄(あるいは鎖)を使って天に昇ったのだ。そして天に登ってからは、ずっと雷を支配しているのだという。
スプーンと鞭、オロクンの海の宮殿
昔、ヨルバ族の地が大飢饉の時、アジャイという男が、食物を求め旅に出た。
そのうちにアジャイは、1本のパーマヤシの実が、川の上にぶら下がっているのを発見したが、彼が木に登ってその実に手を伸ばした時に、それは落ちてしまった。浮き沈みしながら流れていくその実を追いかけ、彼は走ったが、ついにそれは海に流れ出てしまう。 彼はそれでも諦めず、服を脱いで海に飛び込んだ。そして歪む実を追って潜った。
やがて彼は水中の宮殿にたどり着いた。そこにいた海神オロクンは彼に聞いた「アジャイ、お前はなぜ私の宮殿にやってきたのか?」
アジャイが事情を説明すると、オロクンは「ここなら、食物の心配などいらない」と言った。
しかしアジャイは、自分のためだけに実を追いかけていたわけではない。「故郷では家族が飢えているのです」 と彼は言う。するとオロクンは、奇妙な形の(おそらく木製の)スプーンを用意してくれた。
「このスプーンを持って、家族のところに戻りなさい。これを大事に使えば、お前さんの家族が飢えることももうないはずだから。お前のなすべきことは、スプーンに「その務めは何か」と訊ねることだけだよ」とオロクンは教えてくれた。
故郷に帰ったアジャイは、家族の者にまず食わせてから、王のところへ行き、住民全部を養うよう申し出た。またアジャイは、国中の動物にも食物を与えることを提案。
そして動物の饗宴の時に、1匹のカメがアジャイに、 スプーンをどうやって手に入れたのかを聞いてきた。アジャイは事情を話し、カメはスプーンの力を確かめようとする。カメがスプーンに、「お前の務めは何かいな」と聞くと、スプーンは 「食物を出すこと」と答える。カメが「パームヤシの実を1つ頼む」 とお願いすると、すくまさまパーム椰子の実が転がり出た。
その後、カメは川に行って、水中に投げたヤシの実を追い、同じように海神オロクンのところへ来て、アジャイの時と同じような問答をした。
オロクンは「ここまで来たのは、何かほしいものがあるからだろう」 見抜いた。そこでカメは正直に「スプーンがほしい」と言った。そしてオロクンは、「スプーンはもうないが、しかしこのムチをやろう。これはお前にもお前の家族にも役に立つだろうよ」とムチを1つ、カメに与えてやった。
家へ帰ったカメは、家族を呼び集めた。「私もアジャイと同じく、よいものを手に入れたんだ」、そさて問いかける「さあさあムチよ、お前の務めは何か」。するとムチは、「ぶちのめすことだ」と言って、カメの一族のぼこぼこにした。
翌日、カメは腹いせに、ムチを王に献呈した。もちろん王が「お前の務めは何か」と聞くと、ムチは王や周囲の重臣たちも打ちまくった。
ムチが静まると、だんだんと何者かが笑っている声が目立ってきた。結局その声は、隠れてムチで打たれる者たちの不幸を笑っていたカメのもので、そうだと気づかれるや、カメは引っ張り出されて、今度はムチでなく人々に打ちのめされた。
エシェはトリックスターか、炎の悪魔か
ヨルバ族神話のトリックスターとして、エシュ(Eshu)という神が知られている。地方によってはエレグバ(Ẹlẹ́gbára)とも呼ばれるため、それをエシュ・エレグバと呼ぶ者もいるという。そしてこの神はまた、フォン族の間に伝わるレグバ神と同一視されることもある。
エシュの祭祀は、イファ(神託)と直接的に結びつき、複雑化したヨルバの神話体系の中でも、重要な位置を占めているとも。
エシュは特に北方ヨルバの間では、悪意の権化、不平や争いの煽動者と考えられていたという。エシュの悪戯は神々まで争わせ、月蝕や日蝕は、そうした天空の神々の争いの結果という説もある。
こんなだから十九世紀、キリスト教会は、エシュを悪魔と解釈したらしい。
今世紀初頭のヨルバ族出身の牧師で、最初のヨルバ学者の1人とされるサミュエル・ ジョンソン(Samuel Johnson。1846~1901)は、自らの著書(The history of the Yorubas )の中で、エシュを「サタン、邪悪なる者、諸悪の根源」と定義した。
そして、おそらくそうした、キリスト教的な悪魔と関連づけられる以前からと思われるが、復讐したい相手の名を呼びながら、エシュの像にピーナッツ油を注ぐことで、この悪神に報復を願う呪術が古くから語り継がれているとか。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束  「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
エシェの本性は焔で、火事の時に、火が広がるのはエシュの仕業と考えられることもあったようだ。
彼は、火種を大量に隠している山の洞穴を本拠にしているという説もある。エシュは老人のような姿で、時に岩窟を聞いて、この世に現れる。エシュの祭祀には火が不可欠で、エシュを祀る祠の近傍は常に灰で浄めている必要があるとも。
ただし、エシュの行いが必ず悪い結果をもたらすわけでもないようだ。例えば今、畑の植物たちが元気よく育ってくれるのは、もともと彼の悪戯が原因と語られるたりもするという。恵みの太陽からして、彼が用意したものという説もある。
イファの神託がもたらされた話
昔、人々が16のヨルバの主神の存在を忘却し、供物をしなくなったことがあり、神々は飢えた。神々は協議の結果、人々がまた神々を崇拝してくれるよう仕向ける役目をエシュに与えた。
エシュは物知りなオルンミラに相談。オルンミラは彼に言った「十六神はみな飢えているが、彼らは人間の関心を惹くのに役立つ物もまだ持っているだろう。私はそれが何かを知ってもいる。つまりそれは16のシュロの実で出来ている素晴しい物だ。お前は神々にそれを思い出させればよい」
それから、シュロヤシの樹の所にやってきたのはよかったが、結局そこからどうすればいいのか、エシュにはわからなかった。
だが、樹の上のサルたちが実を16取ってくれて、さらには「これらの実を持って、世界の16の場所を巡る。そしたら各場所でその場所ごとの答が得られるだろうさ。後は十六神に、その答を教えてやりな。そしたら、人間たちは再びお前さんらを怖れるようになるはず」とも教えてくれた。
そしてエシュは教えられた通りにし、神々は彼を通じて、忘れていた知識を思い出せた。その知識とは、すなわちイファであり、それはまた人間にも与えられることになった。
人々もイファを用いれば、将来の危機を事前に予測して、それを避けるため、事前に神々に祈りや供物を捧げることができる。供物が捧げられるわけだから、神々も飢えなくなる。
こうして、イファ(神託)はもたらされた。
ジュクン。野兎がもたらすもの
ナイジェリアの多くの部族は起源的にジュクン(Jukun)で繋がるともされる。
このジュクン族の説話には、トリックスター的な役割のウサギ(野兎)を主人公としているものが多いらしい。
スプーンとムチのウサギVer
これはヨルバの、アジャイとオロクンの話に似ている。
ある時、籠(カゴ)を編むため森にて入ったウサギは、休憩中に食べていたピーナッツの最後の一粒を池に落としてしまう。彼はすぐに池の水の底を手探りしたが、ピーナッツは見つけられず、代わりに籠が見つかった。そしてその籠の中には1本の木製スプーン。
「お前は何ものか?」とウサギが聞くと「お前こそ何者だ?」とスプーンは聞き返してくる。「俺は木の葉で寝床をしつらえるウサギだ」とウサギ。「私はあらゆる食物を創り出すものだ」とスプーン。
そして実際そのスプーンは、様々な食物を出現させることができた。
ウサギは家に帰ると、妻や子供達にもそのスプーンの業を見せてやり、村の者たちは、食物の心配がいらなくなったと、畑も壊して放置した。
それから、噂を聞いたゾウがウサギの家を訪ねた。ウサギは留守だったが、子供たちに例のスプーンを見せてもらえた。しかしゾウは、食物を出してもらって食べたが、勢いよくかじりすぎたためにスプーンを壊してしまった。
夕方に帰ったウサギは、事情を聞いて怒ったが、とにかく次の日にまた、ピーナッツを持って池に向かった。そしてスプーンの時と同じように、最後の一粒を落として、水中から木製の物を拾う。
今度の品は「私は誰もが恐れるものだ」と言った。それはムチでウサギを打ちまくった。必死に助けを求めるウサギ。すると「アンギャ。貴方の権威に並ぶものはありませぬ」といえば助かる、と教えられたので、なんとかウサギは助かった。
それからウサギは家に帰って、わざとムチに子供たちを打たせてお仕置きした。さらに後からまたやってきたゾウには、助かるための言葉も教えなかったから、打たれ続けた彼は死んだ。
ウサギはゾウの肉を食べた後は、「こんなものは、俺には荷が重い。首都のウカリの王に献上しよう」と決めた。
ウカリの王が代々受け継いできたムチはこれである。また、王にムチで打たれた臣下が「アンギャ」というと、王がムチ打つ手を止めるという決まりは、この話が由来。
妖術師の起源
ある時、町の住民が次々に死んだが、原因不明だった。
そしてある占い師が王に助力を申し出る。占い師と王は、妖術使いたちを見つけ、全員焼き殺したが、1人の妊婦だけは叢林に逃げた。
彼女は自分の産んだと夫婦となり、さらに近親相姦で生まれた子たちが、また妖術使いとなった。
叢林の中でひそかに、再び数を増した妖術使いたちの家を見つけたウサギは、すぐに王に報告。王に命じられ、ウサギは町に連れて来るために一計を案じる。
ウサギは夜に妖術使い達の家に来て、近くの樹の上から笛を吹いた。妖術使いたちの母はこれを聴くと、子供たちにドラムを用意させ、笛の音に合わせ、みなで一晩中踊った。
朝になって、妖術使いの1人が樹に登って、笛を吹いていたのがウサギであることをたしかめる。妖術使いたちはうさぎを歓迎し、 再び彼の笛で踊った そしてウサギはそのまま少しずつ町の方へと彼らを進ませる。
最終的には、一番大きな家にまできて、彼らを閉じ込めてから、ウサギは王に報告。王は妖術使いたちごと家を燃やしたが、またしても妊婦の1人が脱出し、逃げる時には憎しみこもった言葉を吐いたという。
「そのうち王妃にでもなって、さもなくば奴隷になってでも王宮に入り込んでやる」
もちろん今日の妖術師は、彼女の子孫と考えられる。
ハウサ。風の精霊たち
ハウサ族(Hausa)は西アフリカで最大級とも考えられる民族グループで、ナイジェリアにおいて存在感も大きいという。
(現在彼らの多くを占めるらしい、イスラム教徒が区別のために呼び始めたのかもしれないが、謎)ハウサの伝統的宗教は『ボリ(Bori)』、それを信仰する者は『マグザワ(Maguzawa)』と呼ばれているとも。
ただし、異教とイスラム教の境界線はかなり曖昧(ハウサに限った話でもなく、現在のアフリカの多くの信仰形態がそうだが(つまりよく普及しているキリスト教と混ざってる部分が多い))
 「イスラム教」アッラーの最後の教え、最後の約束
「イスラム教」アッラーの最後の教え、最後の約束
マグザワは、イソキ(Isoki)という精霊たちを かなり特別視してきた。それは風の霊、あるいは風そのものとされる。これはイスラム教におけるジンと同一視されることも多い。
 「ジンの種類とイスラム世界のいくつか」アラビアの怪物たち
「ジンの種類とイスラム世界のいくつか」アラビアの怪物たち
ジャンガレ。精霊たちの国
イソキは主に2つのカテゴリーに分けられるという。つまり、飼いならされ従わせること容易な農園の精霊ゴナ(Gona)と、接触がまず難しい叢林の精霊ダジ(Daji)。
ゴナはイスラム教、ダジはボリとより密接に結びついているとも。
至高神ともされる、最も偉大な精霊サルキン・アルジャン(Sarkin Aljan。ジンの主)、あるいはツンブルブラ(Tsumburbura)も、イスラムの影響を強いと見る向きがある。
ハウサの神話では、『ジャンガレ(Jangare)』という精霊たち(イソキ)の都市世界が語られることがある。そして、「風のように移動する王国」ともされるその領域の絶対的な王が、サルキン・アルジャン。
死は精霊たちの誘いであり、死すべき者に積極的に介入しようという時にこの都市は動く、という説もある。
また、ジャンガレは12の家、あるいは一族に分かれ、それぞれが、サルキン・アルジャンに仕える、特別な精霊に率いられているとか。
それとジャンガレは、広い世界を旅した旅人に見つけられることもあるらしい。しかし勇気をだしてその中に入っていった者が帰ってきた例は、ただの一度もないそうだ。
 「妖精の国」夢の楽園か。時空間次元の異なる領域か
「妖精の国」夢の楽園か。時空間次元の異なる領域か
危険な魔女
ハウサ族の説話には、恐ろしい魔女が登場するものがある。
 「黒魔術と魔女」悪魔と交わる人達の魔法。なぜほうきで空を飛べるのか
「黒魔術と魔女」悪魔と交わる人達の魔法。なぜほうきで空を飛べるのか
ある所に、3人の妻をもった男がいた。彼女たちはよく森で踊っていたが、他の2人が妖術踊りを誘ってきたことで、3番目の妻は、彼女らが魔女であることを知る。 彼女らは夫にした男を、踊りの儀式のための生贄にするつもりでいたのだ。
その事を聞いた夫は、出かけたふりをして、女たちの「あいつの心臓を食べたい」とか「肝を食べたい」といった会話を盗み聞き、しっかり真相を確認してから、2人の妻を追い出し、あとは忠実な妻と平和に暮らしたという。
少なくともいくらかの話は、単に妖術を使う危険人物というより、怪物的である。
別の説話では、ある男の妻が、夫とその父のためスープを作ったのだが、 スープに口をつけるより前に、スープを入れた壺が男たちに警告する。「蓋を閉めないと死んじまうぞ」と。
夫が2つの壺を妻に投げつけると。実は魔女であった彼女は、隠していた9つの口を露にして、逃げ去った。
コノ。人間と動物たち
シエラ・レオネのコノ族(Kono)は、礼儀正しく親切な人たちであり、異郷から来た見知らぬ人でも、けっこう歓迎してくれたりしたそうだ。
コウモリがなぜ夜に飛ぶか
コノの説話によると、創造神が造ったばかりの世界は、暗くなることも寒くなることもなかった。昼は太陽、夜は月が照らし、すべてのものがはっきり見えていた。
しかしある日、太陽はコウモリに、月に渡すための籠を持たせた。その籠には闇が入っていたのだが、神も、月がそれで何をすべきか言わず、説明を後回しにした。
コウモリが月のところに向かう途中、疲れたから休もうと、背負っていた籠を下ろして食物を取りに行った時、他の動物たちが籠を見つけ、中に食べ物があるのだろうと考えて開けてしまう。コウモリが戻ってきた時には、闇はもうどこかに去ってしまっていた。
それからは、コウモリは昼に眠り、暗くなってから、逃げた闇を捕まえるために飛び回る。
最初の人間たち
初期世界に関する別の説は、死の起源についても語る。以下の話はまた、植物や動物よりも先行して、人間が存在していたというパターンが、アフリカ神話の中でも、おそらく珍しい。
最初、世界には光も植物も動物もなかった。
色もない世界で、生命ある者たち(あるいは人間たち)は、ちゃんと生きることも難しく、ひたすらに疲れていた。
唯一の人々は、サ(Sa)と、彼の妻と、そしてサが魔法の力で造ったという彼らの娘、つまり泥の海に住んでいた死だった。
彼らは、ひどく乱雑で不潔な世界に住んでいた。
ある時にアラタンガナ(Alatangana)というものが彼らを訪ねてきた。 ちょうどその頃には、サたちも汚物の世界に住むことが難しくなってきていた。
そこでサとアラタンガナは泥を固い大地に変え、さらにアラタンガナが新たに造った植物や動物も住まわせた。
アルタナガナは、サの娘(つまり死)を欲して、(サは反対したともされるが)、彼女と一緒になった。
それから彼らの子孫、つまり現在の人間は死を有している。
ヘビが盗んだ新しい皮膚
死についての別の説話。
昔、最初の男と女と彼らの男の子がいて、至高神は彼らに「3人とも死ぬことはないのだが、年を取ったら体に合わせた新しい皮膚を付けた方がよいよ」と言った。
そして神は新しい皮膚を包んだものを、人間のところへもって行くようイヌに頼んだ。ところがイヌは途中で、米とカボチャを食べる他の(最初の)動物たちと出会う。食事中に包みの中身が何か聞かれ、人間の皮膚の話をしたが、横からこっそり話を聞いていたヘビが、それを盗んでしまう。
イヌは人間たちに、皮膚が盗まれてしまったことを誤り、神のところにも行ったが、ヘビは皮膚を決して離そうとしなかった。
だから人間は死ぬようになった。
ヘビは町から追放された。さらに人間は、ヘビを見つけたら殺そうとする。
メンデ。神の忠告
シエラ・レオネにおいて最大級の民族グループ、メンデ族(Mende)の伝統的神話世界観では、ンゲウォ(Ngewo)という創造神が知られている。
人々にうんざりした神
ンゲウォは最初に大地を造り、地上に他の全てを造ってから、最後に一組の人間、すなわち1人の男と1人の女を造った。ンゲウォは彼らに「何か欲しいものがあるなら、何でも与えよう」と約束。
しかし、彼らはなんでもかんでもンゲウォに頼んでばかりで、いい加減にうんざりしたンゲウォは、遥か高いところに、自分の新しい住居を造って、地上を去ってしまった。
後で、人々が見上げると、神(天空?)が全方位に広がっているのが見えたので、「神はなんと偉大か」と彼らは言った。
神は別れの時、人間たちに伝えたとされる「みな仲良く暮らすように造ったのだから、お互いに悪いことをしてはいけないよ」と。
遅すぎた伝言
メンデ族の死の起源の話も、イヌが失敗したためとか語っている。
ある時に神は、人間たちへの伝言係として、イヌとヒキガエルを派遣した。それは死の伝言である。イヌは「人間は死なない」と伝え、ヒキガエルは「人間は死ぬ」と伝えることになっていた。
ふたりはそろって出発したが、イヌは途中で、子供の食事を作っている女と遇い、おこぼれをもらうために時間は消費した。
結果的に、人々が住む町まで先にやってきたヒキガエルが、「死が来たぞ」と先に叫んだ。イヌも後からやってきて「生が来たぞ」 と叫んだが、もう手遅れだった。
ソンガイ。精霊たちの危険な領域
ソンガイ族(Songhai)は、ギニア、マリ、ニジェールなどに流れるニジェール河沿いで生きてきたという。
伝統的な宗教は、祖先崇拝やアニミズム的要素を含む多神教だったと考えられるが、今はイスラム教の影響も強いと見られる。
ソンガイの宇宙は、下の大地『ガンダ(Ganda)』と上の空『ベネ(Bene)』で構成される。ガンダは、未開の森林と、人が住む土地に分けられている円盤。すべての叢林は川で繋がっているとも(サハラ以南の多くのアフリカ文化の世界観で適用されている、未開の森林と人里という二分法は、危険な荒野と、文明化された安全な領域との隔たりというイメージからとされる)
天国は7つの層に分かれているともされ、創造神はその最上層に住む。アッラー以外の彼の呼び名として、イリコイ(Irikoy)というのが知られる。
天の他の層には、アブラハムの天使たちが住むとか、あるいは精霊が住むともされる。そうした精霊とはつまりジンであるとも。
雷神と、嵐を避ける祈り
空の精霊のひとり(雷神とされる)ドンゴ(Dongo)は斧をもっていたが、ある時にそれを試してみようと空を飛んだ。そして仲間が造った火花と共にドンゴが斧を投げるや、電光が閃き、下界の男たちが何人か死んだ。
ドンゴは驚き、損害を修復するにはどうしたらいいかを母に聞いた。彼女はまた祖父に相談し、祖父は水が入った土製の壺をドンゴに与えた。
ドンゴが壺から吸った水を、死んだ者たちに吹くと、彼らは蘇った。ドンゴは、「そもそも彼らが死んでしまったのは、おれを讃える歌を歌わなかったからだ」と言って、さらに嵐を避けるための祈りを彼らに教えてやった。
風の精霊のいたずら
ある時、若い男が市場へ行く途中の林の中で、 不思議な生き物のような旋風が、砂埃を巻き上げながら向かってくるのに気づき、とっさに持っていた槍を投げつけた。それで風は消え去ったが、槍も失ってしまった。
それからしばらくたったある日に、若者は市場で、前に失ったのと同じと思われる槍を持った男を見つけ、それをいったいどこで見つけたのかを聞いた。
すると男は、楽しげな笑みを見せて言った。
「お前、忘れぽいな。いつかお前がこの市場に来る途中に、風に邪魔されたことを覚えていないか?」
つまり男は、旋風の精霊だったわけである。
水の精霊の家
水の精霊である、あるいはかつて水の精霊だったヘビが支配している湖があった。
ある日、日光浴をしていた女を見初めたヘビは、彼女との結婚を望むが、女の両親は支度金として湖の所有権を要求してきた。ヘビは了承して、女の両親が支配者となった湖からは離れて、妻と一緒に暮らし始めた。
しかし時々ヘビは湖の底の家に帰って、そこから魚やワニやカバを支配した。ヘビが死んでからは、彼の場所は息子に継承され、その息子が今でも湖を護っている。だが彼は、鉄の道具をもって湖に入り込んでくる人間たちを快く思っていない。
人間たちのせいで、カバも湖から去ってしまった。
水の精霊に関する別の説話は、ある村の酋長が夜に魚を取りに来たが、その際、河の真んなか、水中の丸い小屋の中にいたヒツジと出会う。
その明らかに異常な存在に恐怖した酋長は、呪文を唱えたが、すると、ヒツジは小さな赤ん坊に姿を変える。酋長は、赤ん坊の正体は、変身した河のヘビにちがいないと考え、カヌーの底に這いつくばって助けを求めた。
だが、村の兄弟たちが彼の声を聞いて助けに来た時には、もう彼は死んでいた。彼はジンを見てしまったが、それは人間に禁じられていることだから。
大地の精霊の教え
大地の精霊は森に属している。彼はまた狩人の後援者でもあるという。彼はあちこちさまよう旅人で、地上のあらゆることを学んでいる。
例えば、水を利用して粘土を好きな形に固めて土器を造ったり、綿の茎を集めて編むこととか、もともとは動物のものだった技術を覚えては、人々にそれを伝えたりもしたと語られる場合もある。
森の事情に通じ、12本の特別な木をも人々に教えた。それらの樹皮を砕いて粉にして水に混ぜたもので洗ったものは、何でも、誰でも、森の動物たちから見えなくなる。
マンデ。ドゴンの影響
ポロ(Poro)とサンデ(Sande)という宗教的秘密結社が有名なマンデ族(Mande)は、西アフリカのかなり広い地域に分布している民族グループ。
特にマリ南部の集団が語り継いできた創世神話が知られているが、これにはドゴンの影響が見られる。
世界卵と方舟に関する創世神話
創造神マンガラ(Mangala)が最初に造ったのはバラザ(balaza。シロアカシア?)の種子だったが、それは酷い駄作だったので捨てられた。
次には一組のエルージン(Eleusine。オヒシバ)の種子が造られ、ファニベレレとファニバと呼ばれる。このことは「神は世界卵を自ら生殖できるよう2つの部分から造られた」と表現される。
そして神はさらに6つの種子を造り、それら8種に四元素と方位を結びつけ、世界構造とその広がりの指標とした。すなわち西にファニベレレとファニバ、東にサニョとケニング、北にソとケンデ、南にカバとマロが置かれたのである。それらのすべてはまた、むくげの種子の中に入っていた。
つまりは、最初の種子は互いに性の異なる双児であって、世界の卵、世界の胎盤の中にあった。同じ世界卵の中には、未来の人間の原型である2組の双子もいた。男児の1人はペンバ(Pemba)は創造過程を支配したいと考えて、月満ちる前に生まれ、胎盤の一部を切り離して、虚空を下った。その時に切られた胎盤の一片は大地となったが、それは干からびてもいた。
ペンバはそこで、卵(天)に戻ろうとしたが、彼が前にいた位置にはすでに太陽が置かれていたから、彼はもう戻れなかった。
ペンバは神から8つの雄の種子を盗んで、それらを大地に撒いた。それからファニベレレだけが芽を表し、他の種子は水不足で枯れ、生まれないで死んだ。
ペンバの盗みと近親相姦 (母の子宮に種子を入れた)ために、大地は汚れ、エルージンの種子は赤くなってしまった。
最初のもう1組の双子の男児で、魚の姿であったファロ(Faro)は、ペンバの罪のために汚れた大地を浄化するために、天で生け贄にされ、その体は切りきざまれて、ばらまかれ、それらの切片が大地に落ちると、その場所から木々が実った。
神はファロを天で生きかえらせ、人間の姿を与え、彼を包んでいた胎盤から造った箱舟に乗せ、地上に向かわせた。箱舟はコウロウラという山に着いたが、雪の多い空から彼は地上での生命を得たともされる。
箱舟にはファロと、彼の胎児からつくられた8人の始祖たち(男女の双子四組)と、地上に生きるべきあらゆる植物と動物が乗っていた。 その時、それら全ての動物たち植物たちはファロと共に生命力に満ち溢れていたという。そして彼らは雨乞いによって、大洪水を起こすまで雨を降らせて、大地の不浄を完全に洗い流した。




