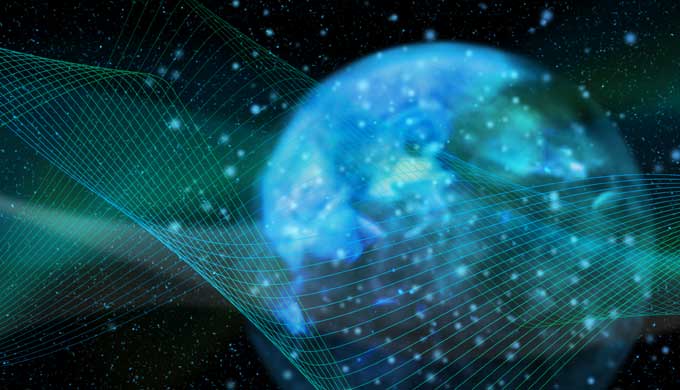原子論と場の理論の起源
最小物質か、空間性質の状態変化か
紀元前の古代ギリシャの時代から、 この世界が、どのようなもので、どのように構成されているのか、ということは賢人たちの強い興味の対象であった。
レウキッポスや、彼の弟子のデモクリトス(紀元前460~紀元前370)は、不生不滅な最小物質単位『原子(atom)』があると考えていた。
それら(無数の数の)原子が、単体では(大きさや向きや形などもない)空虚な空間の中で、様々な結合や分離パターンを構築し、それらのパターンの組み合わせがあらゆる現象を演出しているという思想である。
一方でアリストテレス(紀元前384~紀元前322)は、原子論を拒否した。
彼は空間そのものが、(例えば熱いとか冷たいとかの)性質を持ち、 そこに連続的に広がる基本要素が、様々に組み合わさったりするという考えを提案。
今風に言うと、デモクリトスの理論は、『原子論(atomism)』で、アリストテレスのは『場の理論(Field Theory)』である。
量子論への思想の変化
だいたい、我々の想像力では、どちらかと考えるのが妥当のように思える。
ようするに、空間に様々な最小物質があって、それらがいろいろ組み合わさって、いろいろな物質ができるという考え方(原子論)
もしくは、空間は何かに満たされたものか(つまり物が発生するとともに、初めてそこに空間が生じるというのか)、その空間というやつそのものが何かであって、それらが様々に変化することで、この世界が成り立つという考え方(場の理論)。
どちらか。
エヴァンジェリスタ・トリチェリ(1608~1647)やブレーズ・パスカル(1623~1662)の「真空(vacuum)」や「流体(fluid)」の研究以降、20世紀までは、原子論が正しかったということで議論は落ち着いていた。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
しかし20世紀に、『量子力学(Quantum mechanics)』、 原子以下の領域の現象の研究が進み、単純な原子論的発想で、世界のあらゆる現象を説明することは難しくなってしまった。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
波動と素粒子
真の原子とはどのようなものか。
かつては、水素やヘリウムといった、あるスケールで物質を構成しているものが、そうと考えられていた。(それらは今でも原子とは呼ばれている)
では現在、有力とされている最小のものとは何か。
それは『素粒子(Elementary particles)』と呼ばれている。
多くの場合において、この言葉には今、基本要素という意味以上のことはあまりない。
つまり「粒子」という名前であるが、それが小さな粒のようなもの(粒子)とは限らないわけだ。
そうだと(つまり素粒子だと) 考えられているものが実際に何なのかはわかっていないが、それがこの世界でどのように振る舞うのかを、数学的に記述することはできる。
そのような記述も、言うなればそういう振る舞いがありえるという推測以上のものではないのだが、実際の実験データなどとの矛盾が生じていないことから、正解(あるいは少なくとも近似的に正解)である可能性は高いと見られている。
しかし、問題は素粒子を記述するのに、「波動(Wave)」を記述する手法が有効になる場合もあることであった。
これは20世紀の物理学会における大きなパラダイムシフトの一つであったとされる。
つまり素粒子は少なくとも、(数学的には)素粒子のように振る舞う場合と、波のように振る舞う場合があるのである。
どう解釈するべきか、どう解釈されるのか
では、素粒子は波でもあるのだろうか。
重要なことは、我々は実際には、その素粒子というものがどのような存在であるのかを知らないことだ。
しかし、波動に関連する数式でそれを表現できることに関して、代表的な説(解釈)が三つある。
素粒子は、文字通りに粒子(ごく小さな基本物質)であり、 それはまるで、波のような振る舞いをすることもある(むしろそういう降るまいが実は自然的)という説。(1)
実は素粒子の実態は空間に広がる波動(だから波動を記述する数式で表現できるのは当然)であり、状況によっては、波が素粒子のように振る舞うという説。(2)
素粒子は波でも粒子でもなく、我々には認識できないような何かであって、それを状況ごとに、近似的に扱うのにあたって、波と想定できる場合、粒子と想定できる場合があるというだけ(3)
(1)は現在は少数派であるが、(19世紀までの)原子論的な発想に近く、馴染みやすい。
しかし、波のように振る舞うということなどを深く考えていくと、意味不明にもなりやすいとされている。
(2)は奇妙と捉えられやすい量子論的な現象を、おそらくもっとも理解しやすい。
量子力学の思想の方向性を嫌っていたらしいアインシュタイン(1879~1955)やシュレーディンガー(1887~1961)は、(1)か(2)が答と考えていたのでなかろうか。
 「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家
「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家
(3)は、量子研究の歴史においては最も伝統的な解釈ではあるとされる。
極端な言い方をすれば、この世界を構成する何かを言葉で定義することはおそらく不可能であり、その振る舞いというか、原理を数学によって(近似的に)記述することのみができるという考え方。
本当にすべてを知ることはできないのか
この世界がなんらかのシステムの上に成り立っているのだとして、今、物理学的に考えるなら、素粒子論がそのシステムということになるだろう。
だが、それの振る舞い(そしていかにこの世界を作っているのか)を複雑奇怪な数式によって、どのようにでも表してしまえる物理学者であっても、実際にその素粒子とやらが、具体的にどのようなものであるのかを知ってはいない。
個人個人の解釈があるだけだ。
しかし本当に我々にはそれが認識できないのであろうか。
現に、この世界はあるし、この世界に我々は生きているというのに。
もし、(1)か(2)の説が正しいのだとしたら、いつか、実際に何が起こっているのかを言葉で説明できる日も来るかもしれない。
場の量子論の世界観
エーテルと相対性理論
古く、光(電磁波)が波であるか粒子であるかという議論があり、ある時期から波であるのが有力とされるようになった。
波(波動)というのは、 物理学的には何らかの空間分布(何かの振動)のパターンが伝わっていく現象である。
何かの振動パターンが実態として現れるには、『媒質(medium)』と呼ばれるものが必要とされる。
例えば、地震波という波は、大地の揺れの振動が伝わっていく。
 「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
音波は、空気の振動が伝わっていくもの。
光が波なら、何か伝わっていくもの(媒質)があるだろうか。
もちろんあるはずで、それは『エーテル』と言われていた。
エーテルは馴染みやすい物質として定義されていた。
ようするに空気みたいなものだ。
10立方メートルの空間があるとして、その中の1立方メートルを埋めたり、3立方メートルに広がったりする。
そこでアインシュタインは、 何もない空間の中で単体で存在しているものが、自分は動いているとか止まっているとか判断するためには、他に動いているものや止まっているもの(つまり相対的に比べることができる他のもの)が一つでも必要であるのを基本原理とし、エーテル(注釈)に関してもその基本が当てはまるとした。
これがよく知られた相対性理論の基礎である。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
以降は、エーテルは物質のように、空間から離して考えるということができないものと考えられるようになって、物質名的なその名称はあまり使われなくなった。
現在では一般的に、空間と相対的に分離不可能な、光が伝わる場は、まさしく場として考えられている。
その光の流れる場が『電磁場(Electromagnetic field)』である。
粒子と波の二重性
相対性理論が発表された時。
場の概念が適用されるのは光のみであった。
また、アインシュタインは、物質に光を当てた時に、電子を放出する「光電効果(photoelectric effect)」を説明するために、光が粒子かのように振る舞うことがあるとした。
そのような場合に想定できる光の粒子は、『光子(photon)』と呼ばれる。
おそらくは、粒子と波の二重性がはっきり明らかとされたのは、これが最初であった。
やがて波動を捉えるように、素粒子の振る舞いを示せるということがわかってくると、そこから、そもそも素粒子に対し、場の概念が適用できるのでないか、という推測がでてきた。
『場の量子論(Quantum field theory)』というのは、そのように考え出された。
そもそも場とは何か
素粒子でなくとも、波動と考えることができる何かに対する媒質ではある。
しかし、例えば音波の媒質である空気は、それ自体が物質であり、空間の中を移動しない。
だが(例えば電磁場のような)場と定義されるものには、空間を単体で移動するという性質はない。
空間に対して移動できないとも言える。
また、当然だが、空気も素粒子でできている。
現在の我々の一般的な知見的には、どう考えても空気分子(原子)は実体であり、波と想定するのは難しい。
素粒子が、場に存在するのだとしたら、あらゆる物質が存在している時、そこは素粒子の場の中と考えられる。
それは空間そのものだろうか。
それより素粒子こそ、空間に広がっている場そのものと考える方が妥当である。
物質的なものではない。
少なくとも、あらゆる状況において、物質的な状態を維持するわけではない。
ところで、アインシュタインが見つけた『E = mc^2』という数式は、基本的に正しいとされているが、これは質量というものが実はエネルギーでもあるということも意味する。
場の量子論的に考えるなら、おそらく場のエネルギーが十分に『励起状態(excited state。エネルギーが高まっている状態)』にある時、それは質量という形(実体の形)で現れる。
つまり質量がエネルギーというより、質量(実体)はエネルギーのひとつの状態なのである。
真に空っぽの空間の中に
素粒子そのものが場と考え、粒子(物質)の状態は、その場の空間での特定の位置がエネルギーを持ち、(我々の認識的に)実体として現れたもの。
例えば真に空っぽの空間があるとしよう。
それが水のようなもので満たされた状態を想定する。
この水は特殊で、何者も触れたりはできない。
しかし適当な場所にエネルギーが集められると、そこは実体ある氷となるとする。
このようなイメージにおける特殊水が「素粒子の場」で、実体氷が「素粒子」である。
本当に二重の性質か
量子ゆらぎは打ち消されてるか
光が波であるなら(でなくとも波のように振る舞うとしたら)、それはどのように伝わるのか。
仮にa地点から光を発生させるとする。
光がまぎれもなく粒子だとすると、光は様々な方向に打ち出されるに等しいだろう。
そしてb地点には、aから様々な方向に飛んだうちの、b地点の方向に飛んだ光子が到達する。
では光が波ならばどうか(しかもその媒質は空間と一体である場)。
するとa地点から、まるで全方向に放たれた光の波は、振動が伝わるように、例えばx地点やy地点でもまた、全方向に放たれるということを何度も繰り返す。
そうなると、b地点(だけでもなくあらゆる地点)に届く光の量は、かなり大きくなるだろうが、実際には、まるで光は粒子であるかのように、a地点からb地点方向に飛んだものだけがb地点に到達したかのように観測される。
これは、最短ルートであるa→b以外のルートの光の波が打ち消しあうことで起こる。
このために光は、まるで必ず最短ルートを進むかのように考えることができる。
空間を素粒子が進む場合にも、同じようなことが起きていると考えれば、波(場)でありながら、ある地点から、ある地点まで粒子の移動かのように考えることは可能だろう。
最短ルートが現実に観測される素粒子として、打ち消しあった他のルートが『量子ゆらぎ』というやつだとも定義できる。
エネルギーの粒子状態
問題はある範囲内に波を閉じ込めた場合である。
仮に波を閉鎖空間内で泳がせたとしたら、往復する波は、やはり大半打ち消しあうが、一部は安定して繰り返す波として残る。
そのような安定した波は、実質的に移動なく、振動をただ繰り返すような波となり、そういうのは『定常波(stationary wave)』と呼ばれる。
ある領域に閉じ込められた素粒子の定常波状態において、降り幅が最大になる地点は、エネルギーが高まりやすく、一般的には「存在確率が高い」と表現される。
完全に特定空間に閉じ込められているもの(素粒子)が、実際にはどういうものであれ、その全エネルギー量だけは、変化をしないと考えられている。
『エネルギー保存の法則(Law of conservation of energy)』というやつだ。
場の波動は、場におけるエネルギーの移動と解釈すると、素粒子の状態というのを、ある特定の部分にエネルギーが固まった状態と考えることもできる。
あるいは安定状態で一部固まったような状態だ。
しかしそのような安定した状態となるためには、そこに加えられる様々な作用が、ある程度以上少ない必要があるだろう。
素粒子はひとつだけあるわけでもなく、実際の空間では、たいてい場は複数が重なり合わさり、相互作用しあう。
これが更に広がった空間でなくごく狭い空間内でのみのことであれば安定した波の状態は生まれない。
つまり粒子の状態としての素粒子が現れない。
例えば電磁波の粒子状態が光子とされる。
電磁場にエネルギーを加えると光子が放たれる。
これは、場の波動に加えられたエネルギーによる高まりが生じ、波立った箇所が粒子として振る舞うと考えると、理解もしやすい。
物質を構成する素粒子
二つの大分類
素粒子の大分類として、『フェルミオン』と『ボソン』がある。
これらは、場の性質が異なる。
粒子には『スピン』と呼ばれる(実態はやはり不明ながら、実際的に磁気力として描けるような)ステータスがあり、フェルミオンは数式上におけるそのスピンの数値が「半整数(half-integer)」となるもの。
その半端な数値のために、フェルミオンは、「スピノル場(Spinor field)」という空間的概念を設定することが必須であり、そのために、その性質には、ボソンにないいくらかの制約が発生する。
複合粒子ではあるが、例えば陽子や中性子はフェルミオン、「中間子」はボソンとして扱える。
 「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道
「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道
フェルミオンは対でしか存在しないか
通常、フェルミオンは、単独では生成や消滅もできない(粒子状態が崩れにくい)。
必ず、粒子ひとつに対して、電荷の符号が逆な反粒子ひとつがセットで、『対消滅(annihilation)』、あるいは『対生成(Pair production)』される。
フェルミオンに属する素粒子、反素粒子は、変換されることもあるが、あくまで単体での生成、消滅が基本的にないので、ある領域のフェルミオンの粒子、反粒子の比は必ず一定である。
変換とはどういうことか。
例えばフェルミオンのダウンクォークは、場の作用を受けて、アップクォークに変わることがある。
これも、クォーク場において、状態が異なっている粒子同士にすぎず、単に状態変化があったと考えられる。
場の中での、波の振動の方向変換とされる場合もある。
対消滅には反粒子がいるが、反粒子は我々が知る限りの宇宙の領域内にはあまりにも数が少ないことから、自然なフェルミオンの消滅はほぼありえない。
また対生成も、必要なエネルギーがあまりに高く、そう頻繁に起こるものではない。
そこでフェルミオンは「物質粒子」と呼ばれている。
陽子や中性子を構成するアップクォーク、ダウンクォークなどの「クォーク族」や、「電子」や「ニュートリノ」などの「レプトン族」が、フェルミオンである。
ちなみに、反粒子と粒子が本当に完全に対でしか生成や消滅をしないというなら、この宇宙はおそらくありえない。
 「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか?
「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか?
ボソンの役割
ボソンは力を媒介する素粒子と言われることがある。
フェルミオンよりも簡単に消えたり現れたりするボソンは、その影響により、フェルミオン同士の間に引力や斥力を生じさせることがある。
電磁気力の光子、弱い相互作用のウィークボソン、強い相互作用のグルーオン。
それに、もとは質量を想定するのが不自然な単体のフェルミオンに質量をもたらしたと考えられている「ヒッグス場」などが、ボソンである。
 「ヒッグス粒子とは何か」質量を与える素粒子。その発見は何をもたらしたか
「ヒッグス粒子とは何か」質量を与える素粒子。その発見は何をもたらしたか