初期の原子論
タレスの水、アナクシメネスの空気。万物の基礎物質はあるか
偉大なギリシャ哲学の元祖とされるタレス(紀元前640~546)は、あらゆる物質の根源は「水」だと考えた。
タレスと故郷(ミレトス市)を同じくする、アナクシメネス(紀元前585~525)は、別の説を考えた。
彼は万物は「空気」から成るのだと主張した。
事実はどうあれ、タレスやアナクシメネスの説は、この世界のあらゆる物質が、最小構成要素『原子(Atom)』から成るという、『原子論(Atomism)』の始まりであったとされる。
エンペドクレスの四元素説
エンペドクレス(紀元前495~435)は、政治家であり、技師であり、医者であり、科学者だった。
彼はタレスやアナクシメネスの説を発展させ、万物は「地」「水」「空気」「火」の『四元素(Four elements)』から成るのだと考えた。
四元素こそが原子である。
個々の物質の違いとは、四元素の組み合わせの違い。
というのがエンペドクレスの出した結論であった。
 「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
体系化された原子論。デモクリトスとエピクロス
原子論を明確に、体系化した学説へと押し上げたのはデモクリトス(紀元前460~370)とエピクロス(紀元前341~270)だったと言われる。
彼らは四元素という、複数原子説は誤りだとし、原子はたったひとつだとした。
そのたったひとつの原子の形や運動の違いが、物質の個性を作るとしたのである。
驚くべき事に、彼らは原子論によって、感覚というものまで説明しようとした。
これは、現代の物理学者、生物学者が、「量子論」で感覚の仕組みを解き明かそうとする試みにかなり似ている。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
アリストテレスの思想。真空などありえないという反論
アリストテレス(384~322)は原子論を否定した。
彼は、
「自然に『真空(Emptiness)』などというものはありえない」
 「インフレーション理論」ビッグバンをわかりやすくした宇宙論
「インフレーション理論」ビッグバンをわかりやすくした宇宙論
また「物体は力を加えられなければ動かない」
だから原子など存在するはずがないと述べた。
アリストテレスの主張は、つまりこういう事だ。
原子論者は、あらゆるものは原子で構成されていて、個々の独立した原子が移動し、組み合わせを変える事で、物質の性質が生まれると述べる。
しかしそれなら、原子同士が動く向きなどにより、それらに距離が空く事があるはず。
、そうすると何もない空間が原子同士の隙間に生じる事となる。
何もないなら力もない。
そうなると、原子が動く事もなくなる。
 「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見
「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見  「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
つまり動き回る原子などというものはありえない。
原子論者の冬
原子に限らず、アリストテレスの考えは、今となっては間違いだらけである。
しかし少なくとも当時の水準で言えば、彼の考えはかなり理にかなっていて、説得力があった。
その影響力は大きく、しかも長く続き、少数派の原子論者たちは、ずっと後に復活するまで、冬の時代を過ごす事となった(注釈1)
(注釈1)原子の位置交換の発想
相対性理論や量子論的な発想が、当時まともに受け入れられたなら、原子論は消えなかったろう。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
仮にアリストテレスの言うように、真空がありえないのだとしても、生じるはずの真空がなくなるように、時空間が膨張するものなら。
そして原子がある位置を移動する際は、真空が生じないよう、
不連続的に移動するものなら。
アリストテレスの反論を覆せたかもしれない。
なぜ人は神や奇跡はあんなに信じるのに、奇妙な現実は信じにくいのだろう?
真空と空気の研究
パラケルススの万物理論。錬金術師の原子論
アリストテレス以降、かなり長い間、原子論は科学というより、魔術の理論だった。
特に、スイス出身の錬金術師、パラケルスス・ホーエンハイム(1493~1541)が打ち立てた理論は有名である。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎  「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊
「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊
パラケルススは、原子は『硫黄(sulfur)』、『水銀(mercury)』、『塩(salt)』の3つだと考えた。
そしてそれら根本の第一原子が組合わさり、「地、水、火、空気」という4つの第二原子となる。
万物は、第二原子の組み合わせというわけである。
魔術というのは、科学ほど厳密なものではない。
真っ当な科学者に原子論がなかなか受け入れられなかったのは、もちろん原子というのが直接確認出来ないからだ。
しかしそれと同じくらい、真空というものが何か、全然誰にも定義できてなかったせいでもある。
科学的な原子論構築の為には、真空とはいったい何かを知る必要があった。
ブレーズ・パスカルの実験。トリチェリの真空
フランスのブレーズ・パスカル(1623~1662)が、父の友人から、イタリアのエヴァンジェリスタ・トリチェリ(1608~1647)の水銀の実験の話を聞いたのは23歳の頃だった。
その実験とは以下のようなものだ。
まず、一端の閉じた細長いガラス菅を、濾過(不純物を取り除く作業)した(液体の)水銀で満たす。
そして鉢や桶などの容器に入った水銀に、ガラス菅の開口部を突っ込む。
もちろん突っ込むまでは、水銀が溢れぬように、指などで開口部は塞いでおく。
ガラス菅をそのまま真っ直ぐ立てて、ガラス官の開口部を解放してやるとどうなるか?
通常、ガラス菅の水銀はいくらか流れ出るが、それはガラス菅と容器の水銀の高さが同じになるよりも早く止まるのである。
普通はそうなる事を知らない現代人が、この実験を目の当たりにして驚くとするなら、水銀が流れ出るのが途中で止まってしまう事にだろう。
だがパスカルらの時代の人たちが驚いたのは別の理由だった。
アリストテレスの思想が幅を効かせていた当時は、ガラス菅の水銀は、当然流れ出るわけがないと考えられていたのである。
なぜなら自然は、真空を作るようには動かない、動けるはずがないからだ。
しかし現にそこに真空らしき空は現れてしまった。
もちろん反論は多かったが、それを間違いなく真空だと考える者たちは、そのガラス官に出来る真空を『トリチェリの真空(Torricelli’s emptiness)』と呼ぶようになった。
ならなぜ止まるのか?大気圧の力
トリチェリの真空が現れた後に、水銀の容器に水を加える。
すると、同じ液体でも、水は水銀より軽いために浮く。
それからガラス菅の開口部を、水の部分まで持ち上げると、水銀とは逆に、水は容器へと流れ入る。
もちろん十分な量があればだが、水は水銀と混じりながら菅を上昇し、最終的には水銀を追い出して、菅を満たし、トリチェリの真空すら消してしまう。
この現象は、トリチェリの真空が、やはり真空なのだという事の証拠にも思えた。
しかし真空が出来るとしても、なぜガラス菅は完全な真空にはならないのか?
パスカルは水銀以外にも、普通の水やその他様々な液体でトリチェリの実験を何度も試みた。
やはり真空は出来る。
しかしなぜ水銀なら76cm、水なら10mもの柱を菅の中に作るのか?
トリチェリはその答が、大気の圧力、すなわち『大気圧(Atmospheric pressure)』に関連しているのではないかと考え、パスカルにもその説の情報は届いた。
そういうわけで、パスカルの関心は大気に向いたのだった。
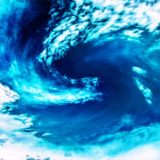 「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差
「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差  「気温の原因」温室効果の仕組み。空はなぜ青いのか。地球寒冷化。地球温暖化
「気温の原因」温室効果の仕組み。空はなぜ青いのか。地球寒冷化。地球温暖化
空気の重み。水銀柱が示す事
パスカルは、液体が流れ出るのを止めるのは、空気の重みが、容器側の液体を下に押しているからだと推測した。
そこでパスカルは、高い山の頂上と、地上で、トリチェリの実験をそれぞれ行い、ガラス菅に出来る水銀柱の長さを比べてみる事にする。
結果は予想通り、空気が薄い山頂では、水銀柱の長さは短くなったのである。
これは明らかに、空気の重みの圧力の低下で、水銀が多く容器に流れ出たからであろう。
この結果は単に、ガラス菅から流れ出る液体が、止まる理由を明らかにしただけではない。
空気というものに重さがある事を証明してしまったのである。
パスカルの原理
例えば空のガラス菅を、水銀の容器に突っ込み、蓋で容器の水銀に圧力をかけるなど、トリチェリの実験から発展させた、真空に関する様々な実験の結果から、パスカルはある法則を導きだした。
「水や水銀などの流体の1ヶ所に圧力がかかると、その流体のあらゆる場所の圧力が同じだけ増える」
 「流体とは何か」物理的に自由な状態。レイノルズ数とフルード数
「流体とは何か」物理的に自由な状態。レイノルズ数とフルード数
これは『パスカルの原理(Pascal’s principle)』と呼ばれるものである。
そしてこれは、考えてみれば経験的、感覚的に当たり前の事である。
開口部が3ヶ所ある巨大な箱を水で満たすとする。
開口部のひとつに圧力をかけたら、他の2つの開口部から水が押され出てくるだろう。
凄まじく強い圧力をかけようものなら、もちろん箱はぶっ壊れる。
そういうふうになっているのだという主張が、パスカルの原理なのである。
オットー・フォン・ゲーリケ。マクデブルクの半球
ドイツのオットー・フォン・ゲーリケ(1602~1686)は、密閉空間内の気体を吸い込む為の装置である『真空ポンプ(vacuum pump)』の発明者である。
 「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
1654年。
ゲーリケは、皇帝や国会議員達の前、ある公開実験を行った。
ゲーリケがマクデブルク市の市長であった為、『マクデブルクの半球(Magdeburg hemisphere)』と呼ばれるその実験の内容は以下のようなもの。
銅製の半球を2つ密着させ、完全な球体にする。
球体内の空気を、真空ポンプで抜く。
すると半球は強くくっつきあい、剥がすのがかなり困難となる。
実権に使われた半球の直径は37cm程度、つまり球体の半径は18.5cmくらいという事になる。
この程度の大きさであるのに、球体の両側を馬8頭ずつで引っ張らせて、ようやく半球は離れたという。
ゲーリケは、半球がそれほど強固にくっついていたのは、空気の圧力が原因であろうと主張した。
これは、トリチェリの実験の結果よりもさらに確実的な、空気の重みの証明であった。
ロバート・ボイル。J字型ガラス菅の実験
アイルランドのロバート・ボイル(1627~1691)は、ゲーリケに影響を受け、より高性能な真空ポンプの開発を試みた。
その真空ポンプは多くの人達の間で話題となり、「ボイルの真空」という言葉が生まれたほどだった。
 「アイルランド」伝統的なパブの特徴、ジャガイモ、ハープ、競走馬
「アイルランド」伝統的なパブの特徴、ジャガイモ、ハープ、競走馬
そのボイルは1660年頃に、4mくらいのJ字型のガラス菅を入手し、ある実験を行った。
J字型ガラス菅の開口部は、長い方の先にある。
そこから水銀を注ぐのだが、途中で、菅を傾けるなどして、J字の左右の水銀の高さが同じになるよう調整。
この状態では、短い方の上部に出来た隙間には空気が詰まっているはず。
それからさらに水銀を注ぐと、短い方の水銀も少しは上昇するが、長い方の水銀がより高くなる。
J字菅の短い方、長い方の水銀の高さの差は、最終的には2m以上になったという。
ボイルは助手に、菅の開口部から空気を吸わせた。
すると左右の水銀の高さの差はさらに大きくなった。
この実験は元々、「トリチェリの真空の原因は、神が垂らした見えないヒモに、水銀などが引っ張られているからである」というような説に反論するためのものだった。
だがボイルは、聖職者への嫌みよりも、ずっと重要だろう事実を得る事になった。
神のヒモは説得力がない
ボイルは、J字菅の左右で水銀の高さに差が生じたのは、官の短い方に閉じ込められた、圧縮された空気の圧力によるものであろうと結論。
長い方の空気を吸い込むと、差が大きくなったのは、空気が吸われた事で、短い方の圧縮空気に対抗する、長い方の空気の圧力が減少したからだと考えたのだ。
これは神のヒモよりずっと説得力がある説明と言えよう。
ボイルは次に、目盛りを用意したうえで、J字菅の実験を再び行ってみた。
左右の水銀の高さを同じにした時、短い方に出来た空気は、長さにして12インチ(約30cm)ほど。
J字菅の長い方の開口部から水銀をゆっくり注いでいく。
J字菅の短い方の空気の長さをvとして、
v=6インチ
つまり最初の半分にまでvが圧縮された段階での、左右の水銀の高さの差hは、29インチ(約74cm)になっていた。
「なんと74cmである」
それは地上で、トリチェリの真空を作った際の、水銀の高さとほぼ同じだったのだ。
最初h(J字菅の水銀の高さの差)は0だったのだから、v(短い方の空気の圧力)は大気圧とつり合っていたに違いない。
そしてhを74cmくらいに伸ばした圧力も、地上での大気圧と同じだけの圧力に違いなかった。
するとvは半分の大きさに圧縮された事で、ちょうど倍の圧力に変化したのだと考えられる。
つまり空気の圧縮度と、それに必要な圧力の強さは反比例の関係になっているのだ。
ある空気の束を1/2に圧縮するには2倍の圧力が必要になる。
1/3にするには3倍、1/10なら10倍である。
ボイルの法則。ボイル・シャルルの法則
J字菅において、一定量の気体の圧力をpとして、その強さは水銀の高さvに比例する。
という事はpv(p×v)は常に一定のはず。
v=12インチの時、pの圧力は29インチらしいので、その時、pv=29×12=348。
という事はvを右辺に移動させて、p=348/vという結論を出せる。
インチでなくcmなら、p=2220/vとなる。
ボイルはこのような考えにより、vのある値の時のpの強さを次々と予測。
それらは実測値とかなり高い精度で一致。
彼は自分の推測は正しかったのだと確信した。
ボイルは、空気の熱を高めたり、冷やしたりする場合にもその圧力は変わるだろうか?
そういう疑問も持ったが、熱を冷ますのは難しいし、あまり熱するのはガラス管が壊れそうで恐ろしいので、その問題は棚上げとなったようである。
そこで彼は「一定量の気体の体積(圧縮度)と(外部からの)圧力は反比例する」と主張した。
これは『ボイルの法則(Boyle’s law)』と呼ばれるものである。
後にシャルルの法則というのと組み合わさり、体積と圧力に、温度の関係も加えた「ボイル・シャルルの法則」というのも出来る。
つまりボイルは恐ろしくて確かめるのをやめてしまったが、彼の予想した通り、熱はしっかり圧力に関係していたわけである。
 エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
アイザック・ニュートン。プリンキピアの原子
アイザック・ニュートン(1642~1727)の『自然哲学の数学的諸原理(Mathematical Principles of Natural Philosophy)』、通称「プリンキピア」が出版されたのは1687年の事。
 「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
その本には、彼が自ら考案した微積分などの数学的手法を駆使して、導き出された力学に関連する様々な原理が書き記されていた。
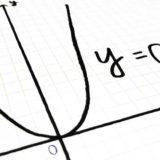 「微積分とはどのような方法か?」瞬間を切り取る
「微積分とはどのような方法か?」瞬間を切り取る  「微分積分の関係」なぜ逆か。基本公式いくつか。指数対数関数とネイピア数
「微分積分の関係」なぜ逆か。基本公式いくつか。指数対数関数とネイピア数
プリンキピアにはボイルの法則に影響を受けたかのような、ある定理が導き出されている。
例えば何らかの気体の塊を用意しよう。
簡単のために、その塊は立方体だという事にしておく。
これを仮に1/8の体積に圧縮すると、立方体を構成する各線の長さは、1/8の立方根である1/2となる。(1/8=1/2×1/2×1/2)
気体の体積を1/8に圧縮すれば、気体の各方向への圧力は1/2に圧縮される事で2倍になる。
体積が小さくなるに際し、個々の圧力がかかる面積も小さくなっているだろう。
1/8なら、面積はその平方根である1/4になる。(1/4=(1/8)/(1/2))
という事は全体として1/8に圧縮された気体の圧力は、1/8(1/2×1/4)となる。
この考えは、ボイルの法則のほとんど言い換えにすぎない。
ただ重要なのは、ニュートンは気体全体の圧力を、個々の圧力の合計と考え、この結果を導いた事である。
気体の塊の形は体積に影響なく変える事が出来る。
だがどんな形にしようと、計算が面倒になるだけで、気体のあらゆる部分、個々の部分に加わる圧力は同じ。
そう考えると、この考え方、計算は上手くいく。
個々の圧力とは、普通に考えるなら個々の微粒子の圧力になろう。
つまりボイルの法則のような計算が上手くいくならば、気体は微粒子の集合体の可能性が高まるのである。
ではその気体を構成する微粒子とは何か?
当然それこそ原子なのではないだろうか?
四大元素狩り
酸素の発見。見つからなかったフロギストン
燃焼を引き超す火の元素として「フロギストン」なんてものが考えられていた時代もあった。
金属を燃やしたら、煙が立ち込めた後に、灰が残される。
煙や炎が金属から出ていくフロギストンで、後に残された灰が、フロギストンが抜けた後の抜け殻金属だと考えられていたのだ。
残された灰は、燃やす前の金属より重くなっていたりして、それはフロギストン説の間違いを示唆していた。
だが人々は、火や煙は天へと昇る。
つまりフロギストンはマイナスの重さを持っているのだという説すらあったという。
ジョセフ・プリーストリ(1733~1804)は水銀灰(水銀を加熱して出来る灰)をトリチェリの真空内に置いて、熱してみた。
すると水銀灰からは気体が出てきたが、彼はその気体を集めてみた。
集めたその気体は水に溶けにくく、吸うと心地よかった。
そして木やロウソクをその気体にあてるとたちまちに燃え上がった。
そこでプリーストリは、その気体にはフロギストンが含まれておらず、だからこそフロギストンを含む(例えば木などの)物質に触れた時に、そのフロギストンを奪い、結果燃え上がったのだと推測した。
彼はその気体に、フロギストンが含まれないという事で「脱フロギストン空気」という名を付けた。
プリーストリは全然気づいてなかったらしい。
実は彼が見つけたその気体は、現在では誰しもによく知られている『酸素(oxygen)』だったのである。
アントワーヌ・ラヴォアジエ。空気の解体
化学や錬金術の実験によく使われる『レトルト(retort)』というガラス製の器具がある。
これは、球状のボディに、斜め下に向かって伸びる管がついているという容器である。
アントワーヌ・ラヴォアジエ(1743~1794)は、あらかじめ重さ計っておいた『錫(Tin)』を、レトルトに入れて密閉した。
さらに錫入りレトルトの重さを計ってから、内部の錫が灰になるまで加熱し、再びその重さを計った。
錫入りレトルトの重さRWは、中の錫が灰になろうが変わらなかった。
続いてラヴォアジエはレトルトに穴を開けて空気を流入させた。
当然流れ込んだ空気の分の重さAWだけ、レトルトの重さは増加した。
最後にラヴォアジエは灰になった錫を取り出し、その重さを計ってみた。
すると錫は灰になって、重さがUW増えていたのだが、面白いことに、AW=UWだった。
ラヴォアジエは実に上手い解釈をした。
密閉された空気のいくらかが、錫が灰になる際に取り込まれ、レトルトに穴を開けた時は、その消費された空間内の空気分だけ、外部から新たな空気が流入したのである。
灰になるとは、つまり空気、あるいは空気の一部との結合なのだと彼は述べたわけである。
ラヴォアジエはさらにプリーストリの方法をヒントに、水銀を密閉した容器内で灰化させてみた。
そして水銀の灰化に空気のいくらかが消費された後に、残された気体の性質を調べてみたのである。
その残された気体は、火を消し、動物を窒息させた。
さらにプリーストリのように、再び密閉された容器の中で水銀灰を加熱し、脱フロギストン空気とやらを取り出す。
もちろんこれは燃えやすく、動物も呼吸に使えるようだった。
最初の容器内で失われた空気と、脱フロギストン空気の量を比べると、かなり一致していたので、ラヴォアジエは、それらの気体が同じものなのだと結論。
そしてそれは、空気と言うのが、少なくとも燃えやすい気体物質と、燃えにくい気体物質の混合物である事の証明でもあった。
現在では燃えやすい方が酸素、燃えにくい方は『窒素(nitrogen)』と呼ばれている。
ヘンリー・キャヴェンディッシュ。水の分解
ラヴォアジエはいくつかの結論を出した。
(1)空気とは酸素と窒素の混合物。
(2)灰化とは、物質と酸素の結合。
(3)空気中で燃えたり、呼吸が出来るのは酸素のおかげで、窒素のみでは、燃える事も呼吸も出来ない。
(4)現代の知見において、フロギストンを想定する必要はない。
空気は原子ではなかった。
つまりこの時点で四大元素という考え方は間違っていた事になるわけである。
ついでみたいに火も消えた。
フロギストンを想定しなくても、フロギストンのせいにされていた様々な現象は説明できるからである。
そして同じくらいの時期に、水もヘンリー・キャヴェンディッシュ(1731~1810)によって原子の地位を剥奪された。
 「ヘンリー・キャベンディッシュ」最も風変わりな化学者の生涯と謎。
「ヘンリー・キャベンディッシュ」最も風変わりな化学者の生涯と謎。
彼もまたプリーストリに触発されて、『水素(hydrogen)』と空気を容器内で混ぜて、電気を浴びせた。
すると容器内に水滴が出来たのである。
キャヴェンディッシュは水素と酸素が、必ず体積比2:1で結合する事すら見出したが、彼はフロギストン説の支持者だったので、水の素材としてフロギストンも想定していた。
一方、すでにフロギストンと縁を切っていたラヴォアジエは、冷静にキャヴェンディッシュの研究結果を解釈した。
つまり水とは単に水素と酸素の混合物だったのである。
さらに彼は、逆に水を分解し、水素と酸素を得る事にも成功したされている。
見つかった原子
ゲイ・リュサック。気体反応の法則。整数比という発見
水が必ず体積比2:1で結合するらしいという事実は、原子という見えない領域に挑む科学者たちにとって、大いに希望であった。
もしかすると計算により、原子というものの性質を決定できるかもしれない。
フランスのゲイ・リュサック(1778~1850)は、気体の結合と分解を繰り返し、その体積比を多く割り出し末に確信した。
 「フランス」芸術、映画のファッションの都パリ。漫画、音楽、星
「フランス」芸術、映画のファッションの都パリ。漫画、音楽、星
「ふたつの気体が結合する時、その体積比は整数の比となる」
この事は『気体反応の法則(law of combining volumes)』と呼ばれるようになる。
そしてその気体反応の法則に関する話に衝撃を受けた者の中に、イタリアのアメデオ・アヴォガドロ(1776~1856)がいた。
アヴォガドロは、どの気体でも同じ体積比なら同じ数の分子を含むに違いない、と考えた。
ちなみに彼は、原子と、複数の原子の集まりである『分子(molecule)』を区別せず、まとめて分子と呼んでいたようである。
 「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
アメデオ・アヴォガドロ。原子量の決定
アヴォガドロは、自ら考えた仮定より、原子の相対的な質量を計算する事にした。
同じ体積なら同じ数の原子が含まれてるのだから、その相対的な質量は、同じ温度、気圧、体積における重さを比べればよい。
そうして原子の重さを比べると、例えば水素が1gの時は、窒素は14g、酸素は16gとなる。
とすると窒素の質量は水素の14倍、酸素は16倍という事になる。
この相対的な質量の値は『原子量(Atomic weight)』と呼ばれるようになる。
また原子量は化合物にも適用できる。
例えば、酸素と窒素が1:1で結びついた一酸化窒素は原子量30。
酸素と窒素が2:1で結びついた二酸化窒素は原子量46
原子量が23の『ナトリウム(sodium)』と35.5の『塩素(chlorine)』が1:1で結びついた塩化ナトリウムは原子量58.5というわけである。
ジェームズ・ジュール。見えなくても計算出来る
結合しようと分解しようと、単体の原子がどういうものなのか、どういった性質を持つのかは確かめようもないだろうか?
原子量という概念の成立以降、ここまで明らかになった原子を深く理解する事を、やはり見えないからと諦める人などかなり少なくなっていた。
科学者の間では、自然は理解できるものだという考えが当たり前になってきていたのである。
ジェームズ・ジュール(1818~1889)は1857年に「気体分子の速度について」という論文を発表した。
それは原子の速度の数値化に成功した最初期の例とされる。
 「ジュール」電流、熱、羽根車の巧妙な実験。金持ち素人学者の研究人生
「ジュール」電流、熱、羽根車の巧妙な実験。金持ち素人学者の研究人生
すでに原子を信じる人たちの間では、気体の圧力が、大量の原子の運動により生じるものだというのは通説になっていた。
そこで彼は以下のように考える。
まず立方体の箱の中に閉じ込められた気体分子を想定する。
立方体の各綾の長さをL、まだ知られてなかった個々の気体原子の質量をm、数をNとする。
そして箱にかかる気体の圧力は、分子がぶつかる事で生じるものとする。
箱内部でぶつかった個々の原子は、ぶつかると、こんどは反対に飛んで、反対側の壁にぶつかるだろう。
仮にx方向に飛ぶある単体原子の速度をVxとして、その単体原子の壁にぶつかり、一往復してくるまでの時間は、2L/Vxとなる。
とするとその原子が1秒間に一方の壁を叩く回数はVx/2Lとなろう。
分子が一回の衝突で壁に与える運動量はmVx(m×Vx)。
一秒間の合計運動量は、mVx×(Vx/2L)=mVx^2/2Lとなる。
箱の中の原子は全部でNだから、気体原子全体が1秒間に一方の壁に与える運動量は、(mVx^2/2L)×Nとなる。
これはつまり1秒間における原子の壁に与える総力であるから、後は壁の面積で、割ってやれば、単位面積辺りの圧力が出てくる。
つまり、((mVx^2/2L)×N)/L^2=(mN/2L^3)×Vx^2となる。
この(mN/2L^3)×Vx^2は、すなわち気体の圧力。
そしてその気体の圧力の式(mN/2L^3)×Vx^2の中で未知の数字はmとNとVx。
しかしmN(質量×数)とはつまり気体の全質量であるので、それなら余裕で測れる。
こうして未知数は原子の速度Vxだけという数式が出てきたわけである。
そうして速度が導き出されたのちも、科学者達による原子を計る計算は続き、現在知られる原子の大きさなどのデータも知られていく事になったのだ。
それでもそれは見えない
ロバート・ブラウン。分子
1828年、ロバート・ブラウン(1773~1858)は、花粉を『顕微鏡(microscope)』で観察し、その内部で起きていた微粒子の驚くべき動きの記録を、論文の形で世に放った。
微粒子には、特に水につけたらデタラメに動くような球形のものがあり、ブラウンはそれを『分子(molecul)』と名付けた。
ブラウンは観察対象を広げ、やがて分子は様々なものから出てくる事を確認していった。
生きている者ばかりでない。
死後1年以上は経っている標本や、石炭や化石にまで、ただちょっと傷をつけるだけで、分子が確認出来たのである。
 「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
当時、科学に携わる者たちの間では、ある噂がまことしやかに囁かれていた。
それはあらゆる生物は、共通の微粒子で構成されているという生命の原子論である。
ブラウンは自分が見つけた、この分子こそが、まさに原子なのではないかと考えたのだった。
ブラウン運動
だが生命の原子というのは間違いだった。
ブラウンは観察を繰り返す内に、分子には明らかに生物由来でないものがある。
つまり原子は、生物の構成要素でなく、生きてない物も含めた万物の構成要素なのであろう。
だが、そう考えるのは奇妙な事に思えた。
ブラウンは、水中で個々の分子が、まるでみな生きているかのように、それぞれ勝手に動き回るのを観察していたからだ。
ブラウンは、分子というか、どんな物質でも砕いて粉にすればデタラメに動くとした。
そうした微粒子のデタラメな運動は、後に水中でない環境でも確認され、『ブラウン運動(Brownian motion)』と呼ばれるようにかる。
より小さな要素
ブラウン運動は現実に観察されてる例である。
すると原子というのは勝手にデタラメに動くものなのだろうか?
まあ実際、統計学的には、原子がデタラメに動くこと自体は、あまり深刻な問題でもないらしい。
ちなみに原子の運動は、熱運動とされてるので温度が下がると運動は緩やかになっていく。
究極に熱いと、原子は原子の状態でいれなくなるのだと知ったら、この記事で名前の出てきた方達はどんな顔するだろうか?
しかし、存在すら危うくする量子論のせいで、現代人はマヒしているが、最小の構成要素が、単体ではめちゃくちゃに動くというのは奇妙な話かもしれない。
今でも人は本当の意味での原子を見れてないし、見ることは不可能だと考えられている。
現にそこに見えないものをどうして信じられよう?
原子論を信じなかった昔の人たちは、ある意味我々より真っ当な考え方をしてるのかもしれない。
たいてい気になるのは、どちらが真実に近いかという事だろうけど。




