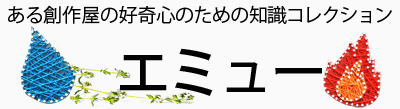量子論の始まり
物質を混ぜ合わせた時、分解した時の反応などから、『原子(atom)』が発見された。
ずいぶんと種数が多いのが困りものだが、それはしばらく物質の最小の構成要素のように考えられていた。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち  「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
20世紀初期に、より小さな粒子を原子にぶつける実験などから、物理学者は原子の内部構造を明らかにした。
プラスの『電荷(electrical charge)』を持つ『陽子(Proton)』と、電荷を持たない『中性子(Neutron)』からなる『原子核(Nucleus)』。
その原子核の周囲を、マイナスの電荷を持つ『電子(Electron)』が巡る。
その発見は、『量子論(Quantum Theory)』という試みの始まりであった。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ  「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
クォーク
陽子、中性子、電子
ひとつの陽子はe(ある決まった数)の電荷を持つ。
中性子の電荷は0だから、陽子がZ個含まれた原子核はZe(Z × e)となる。
そして、ひとつの原子は、Zeの電荷を持つ原子核とZ個の電子から成る。
ひとつの電子は-e(陽子ひとつの電荷の、符号が逆になってる数)の電荷を持つ。
つまりひとつの原子の電荷は、Zeと-Ze(Z × -e)が足し合わされるので、0(Ze-Ze)となる
陽子、中性子は、電子より圧倒的に軽く、原子の重さである『質量数(Mass number)』とは、中性子の数をNとして、ほぼZ+Nである。
そして『原子番号(Atomic number)』というのはZの数である。
ちなみに原子番号は同じだが、中性子の数が異なる原子を『同位体(Isotope)』。
電子がZより多いか少ないために、電荷を帯びた状態の原子を『イオン(ion)』と言う。
それと、もちろん複数の原子の集まりを分子と言い、我々という存在も、かなり大規模な分子である。
更なる構成要素
陽子、中性子、電子を違いを電荷で考えるなら、陽子がe、中性子が0、電子が-eとバランスが取れてるように見える。
しかし質量に関しては、陽子と中性子がかなり近い(もしかすると同じ)。
そして電子だけかなり軽い。
この観点から見ると陽子と中性子は、まるで電荷が違うだけの同じものであり、そのさらなる内部構造を予感させる。
例えば陽子、中性子の構成が、3つの最小粒子の組み合わせなら、その電荷がe2/3の粒子と-e/3の粒子と考えれば上手くいく。
電荷的に、陽子の組み合わせはe2/3+e2/3-e/3(e)。
中性子の組み合わせはe2/3-e/3-e/3(0)。
となるわけである。
つまり電荷がe2/3や-e/3の粒子を発見できれば、それは陽子、中性子を構成する要素の候補になりうる。
その内に、その陽子や中性子を構成する粒子は、『クォーク(quark)』と呼ばれるようになった。
通常、e2/3の電荷のクォークを『アップ(up quark)』。
-e/3の電荷のクォークを『ダウン(down quark)』と言う。
粒子の見つけ方
そもそもクォークのようなものがあるとして、単体の原子の時点で、すでに目に見えないほど小さいのに、さらに小さなそれをどうやって見つければよいというのか?
そこで、物理学者は、秘密アイテム、『霧箱(cloud chamber)』や『泡箱(bubble chamber)』を使う。
霧箱で軌跡を捉える
チャールズ・ウィルソン(1869~1959)により、1897年に発明された霧箱は、人工的に『過飽和(supersaturation)』な(例えば水の)蒸気で満たされた空間である。
蒸気というのは冷やすと、水滴など、液体化してしまう。
ある温度で、水滴にならず存在できる蒸気の量を『飽和蒸気量(Saturated vapor amount)』と言う。
しかし水滴化するには、その中心に核が必要である。
空間内に塵などの核になりうる物がなければ、蒸気は水滴になれず、飽和蒸気量を越えても存在出来る。
そのような蒸気の状態を「過飽和状態」と言う。
霧箱に、電荷を帯びた『荷電粒子(Charged particles)』、あるいは空気などをイオン化する『放射線(radiation)』などを突っ込む。
すると、『極性分子(Polar molecule)』である水などは、荷電粒子や、イオン化した空気に引き付けられ、それらが核となり、それらの進む経路に沿って水滴が発生する。
その軌跡のサイズや影響から、本来は見えないはずの(放射線などの)粒子に関する、電荷量など情報を知る事が出来る。
極性分子とは、内部のプラス電荷とマイナス電荷の「重心(働く力の中心)」が一致していない分子である。
そのために電気力的な隔たり、『極性(polarity)』が発生し、電荷の影響を受けやすいのだ。
泡箱で捉えられたニュートリノ
泡箱は、1952年に、ドナルド・グレーザー(1926~2013)によって発明された。
こちらは『過熱状態(Overheating state)』の、『液体水素(Liquid hydrogen)』などの液体で満たされた空間。
過熱状態とは、『融点(Melting points)』や『沸点Bboiling point)』を越えてるのに、状態変化してない状態である。
泡箱内を粒子が通る時に、水素は気化され、やはり泡の軌跡として観測出来る。
1970年に、謎の粒子『ニュートリノ(Neutrino)』を捉えたのは、アメリカアルゴンヌ国立研究所の泡箱。
また、日本の『カミオカンデ』、あるいはそのヴァージョンアップ版の『スーパーカミオカンデ』は、言ってしまえば「超泡箱」みたいな装置である。
そして霧箱や、泡箱のようなものに、電荷e2/3や-e/3のような粒子が捉えられたから、それはクォークと考えられるわけである。
単体のクォークの影響
ある空間に単体のクォークを放り込む事ができればどうなるか?
ある空間には普通、大量の陽子と中性子がある事だろう。
仮にひとつの陽子の電荷を1とする。
中性子はもちろん0である。
ある空間内の合計質量は、空間内の物質がどういうふうに変化しようが変わらないようである。
同じように電荷の合計も変わらない。
もし空間内にクォークがないなら、その総電荷は、陽子の数(と電子の数)に応じて、整数の値になるであろう。
だが、クォークがひとつあれば、総電荷には、必ず分数の値が現れるはず。
かつてロバート・ミリカン(1868~1953)が、行ったある実験がある。
液体の中に油を落とすと、油は緩やかに動く。
その過程で油は電子を液体と交換しあい、電荷を変化させる。
そこで外部から『電圧(Voltage)』をかけておくと、油は電荷量に応じた電気力由来の動きも見せる。
その動きの測定から、ミリカンは電荷の最小の値eを見つけたのである。
ではミリカンが行ったような実験を、クォーク1個(あるいは3の倍数でない個数)が含まれた油で行ったならどうか?
当然、電荷に分数が見つかる事になるだろう。
するとそれは、クォークのかなり確かな証拠となる。
湯川博士と中間子
何の力か?
原子核が陽子と中性子からなる。
だがこれは、『重力(gravity)』と『電磁気力(Electromagnetic force)』しか知られてなかった時代の人たちからしてみれば、かなり奇妙な事だった。
電磁気力は符号が逆の電荷同士が引き合う力。
だから、プラス電荷を持つ陽子などは、電磁気力的には離れようとするはずである。
では重力が核を繋ぎ止めるのではないか、というと、これはありえない。
重力というのは、電磁気力に比べるとあまりに弱すぎるからだ。
適当に磁石で、適当な磁性体を上に引っ張らせてくっつけてみればいい。
その手に持てるくらいのサイズの磁石に、地球サイズで負けてしまう程度の力が重力なのだ。
湯川秀樹(1907~1981)が『中間子(Meson)』というアイデアを思いついたのは、1934年の秋だったという。
相対性理論的な、量子論
電磁気の力が及ぶ『電磁場(Electromagnetic field)』というものを想定し、マックスウェル(1831~1879)は、電磁気力の体系を数学的に記述したマックスウェル方程式を書いた。
 「マクスウェル」電磁気学の方程式、土星の輪、色彩、口下手な大物理学者の人生
「マクスウェル」電磁気学の方程式、土星の輪、色彩、口下手な大物理学者の人生
マックスウェル方程式から導き出される事実の中に、光速度が空間的な位置関係に関わらず不変であるというのがあった。
アインシュタインはその不変の光速度という事実から出発し、『特殊相対性理論(Special theory of relativity)』に到達した。
特殊相対性理論は、あらゆる粒子に適用される、時空間の基本的性質である。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙  「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家
「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家
しかし量子論によれば、ひとつの粒子とは、実は波動でもある。
シュレーディンガー(1887~1961)は、その波動を、『波動関数(Wave function)』として、数学的に記述したシュレーディンガー方程式を考案。
だがシュレーディンガー方程式は、特殊相対性理論が示す時空の性質を考慮には入れていない。
そこでディラック(1902~1984)が、電子の波動関数を決定する為のディラック方程式を書いた。
ディラック方程式は、特殊相対性理論をしっかりと想定したものであり、シュレーディンガー方程式にはなかった新たな要素がいくつかあった。
そのひとつが、すでに一部の物理学者たちに、存在が示唆されていた『スピン』という粒子の性質。
スピンとは、粒子が持つ固有の(回転力らしき)運動量である。
このスピンがディラック方程式から自然と導かれる要素だった事は、この考え方が正しい方向なのだと感じさせるに十分であったろう。
反粒子、0の粒子
スピンとはまた別の、ディラック方程式から導かれる要素として『反電子(Anti-electron)』というのがあった。
これはディラック方程式の解として、時にマイナスのエネルギーが出てきてしまうという問題を解決する為に、導入された概念である。
『陽電子(positron)』とも言われる、この反電子は、電子と全く同じものだが、電荷の符号だけ逆という粒子。
つまりeの電荷を持つ電子である。
 「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか?
「反物質」CP対称性の破れ。ビッグバンの瞬間からこれまでに何があったのか?
実は量子論的観点から見れば、マックスウェル方程式も、相対性理論的なものとなる。
かつて物理学者が想定した、電磁場という場も、量子論的には粒子的性質を持つのだ。
 「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
電子や光の粒子である『光子(photon)』などの粒子は、基本的な性質として、質量、電荷、スピンを持つ。
ある粒子のそれらのステータスの値がわかれば、後は適当な波動方程式で、その粒子の運動を記述出来る。
ディラック方程式から、あらゆる粒子が電荷逆(0の場合は電荷も同じ)の反粒子を持つ事が予測される。
さらに、質量0の粒子は、常に光速で動く事が推測出来るという。
光子は典型的な質量0の粒子である。
 「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見
「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見
スピン
電子などのスピンには、上向き(プラス)と下向き(マイナス)の状態があるとされる。
数量的に光子は1というスピンを持つ。
電子は1/2である。
基本的にスピンjの粒子が質量を持つなら、2j+1個の状態が存在するという。
それらの状態は数値的にj、j-1、j-2、j-3……、となる。
つまり、1/2のスピンを持つ電子は2個の状態を持つ(2×(1/2)+1=2)。
そしてその状態は「1/2、-1/2」となる。
同じように計算するとスピン1の粒子は、「1、0、-1」となる。
また、質量のない粒子は+jと-jの2個だけらしい。
フェルミオンとボソン
ヴォルフガング・パウリ(1900~1958)は、スピンが半整数の粒子は、複数の粒子が同じ状態を取れないという『フェルミ統計(Fermi statistics)』に従うこと。
そして、スピンが整数の粒子は、複数の粒子が同じ状態を取れる『ボース統計(Bose statistics)』に従うことを示した。
そこでスピンが半整数の粒子は『フェルミオン(Fermion)』。
スピンが整数の粒子は『ボソン(Boson)』と名付けられた。
フェルミオンの同じ状態をとれないというのは実にわかりやすい。
つまり位置aに何かが存在するなら、もう位置aには何も存在出来ないという事。
一方で、位置aに重なって存在出来るのがボソンである。
光子はボソンだが、それが同一状態で大量に重なったものが、いわゆるレーザービームだとされる。
中間子の予言
フェルミオンは、陽子や中性子や電子のような、物質の粒子である。
一方でボソンは、何らかの力を伝える場としても存在しうる粒子。
光子は電磁場となり、電磁気力を伝えるわけである。
そこで当然沸き上がる疑問が、光子以外にもボソンはあるのだろうか?
という疑問である。
もしあるならば、それは何らかの力の場にもなりうる粒子のはず。
光子は質量0だが、別にボソンが質量を持ってはいけない訳ではないだろう。
そういうのを想定した波動方程式のひとつが、クライン・ゴルドンの方程式。
それは質量を持ち、スピンが0のボソンに対応した方程式である。
それから導き出せるのは、ごく短い範囲限定で伝わる力の場の粒子であった。
そしてもし、陽子と中性子を繋ぎ止める、いわば『核力(Nuclear forces)』があるならば、それはごく短い範囲限定の強力な力に違いない。
湯川はそういう発想で、核力の場になりうる、質量を持ったボソンを予測したのである。
パイオンの発見
湯川は、調べられていた原子核の大きさ(核力の及ぶ範囲)から、その未発見のボソンの質量(電子の200倍くらい)すら推測出来た。
そこで陽子や中性子よりは(1/10くらいに)小さく、電子よりは大きいその未知の粒子を、湯川は『中間子』と名付けたのだった。
電磁気力に電荷という整数倍出来る力の源が存在するように、中間子にも存在するであろう。
その力の源、整数倍される最小の力の数を『結合定数(Coupling constant)』と言うが、核力が強いのは、この結合定数がすでに大きな値だからと考えられる。
実際、1947年に、核力を伝える中間子『パイオン(pion)』が見つかったので、湯川氏は日本人初のノーベル賞受賞者となった。
クォークモデルの始まり
また、予想外の展開
実際には全然見られない粒子を、実際に見つける試みとして、加速させた粒子同士を衝突させるという方法がある。
そうして崩壊した粒子の(粒子よりさらに小さな素材)は、偶然に別の粒子になったりする。
パイオンもそんなふうに作る事が可能だが、その寿命は短く0.1秒よりずっ僅かな時間で崩壊してしまう。
我々が、パイオンを全然見つけられないのは、ある意味で当然と言えよう。
問題はそんな事でなく、パイオン以降、次々と見つかった、パイオンとは違う中間子である。
まったく想定外に、中間子というのはいっぱいあったのである。
新しい冒険
パイオンの発見のすぐ後に、『V粒子(V particles)』というのが発見された。
この粒子は必ず対発生するらしいから、それは電荷のような、何らかの保存量を持っているのかもしれないと考えられる。
マレー・ゲルマンは、その保存量に『ストレンジネス(strangeness)』という名をつけた。
ストレンジネスのような何らかの量は、やはり発見される粒子の内部構造を予感させる。
やがて、次々と見つかった中間子、それに陽子と中性子は、やがて『ハドロン(hadron)』と呼ばれるようになる。
そしてそのハドロンを構成する、さらに基本の粒子として、クォークは考え出されたのである。
クォークという名前を考案したのはゲルマンだが、それはジェームズ・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」という小説の一句から取ったものだという。
原子の発見は、この世界の最も基本的な構成要素を探す冒険の第一幕の始まりであり、量子論によってそれは終幕した。
そして、原子の内部、中間子、そして物理学者たちが、クォークがあると想定した時から、冒険の第二幕は始まり、今もそれは続いているわけである。