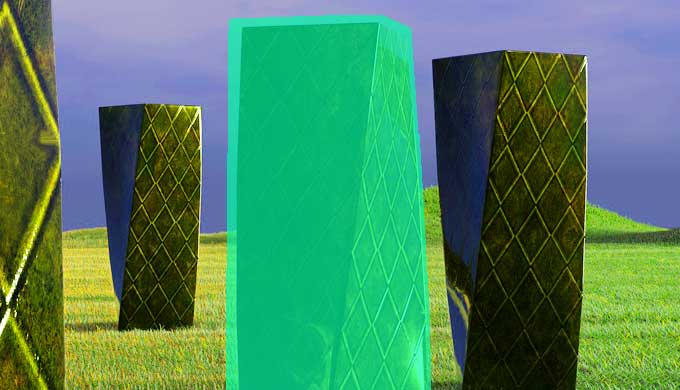2001年宇宙の旅
「これは、この広大な宇宙に多くいるだろう地球外生物と、我々地球生物との接触が、いまだに起こっていないのはなぜなのか、という疑問に対する回答の1つである(ただしもちろんフィクションでもある)」と結論する前書きからすでに、(とてもシンプルで、かつ古くさいながら)興味深いテーマの尽きない、名作SFである。
『2001年宇宙の旅』
小説の執筆と同時に製作されたという、スタンリー・キューブリック監督の「映画版」もまた有名であるが、 個人的には原作(というか小説版)のこちらの方が好き。
とりあえず映画版は、説明をほとんど映像のみですませているために、けっこう退屈だと感じた人でも、こちらは面白い可能性はある。一方で映画版は、おそらくは意図的に説明を極力省いていて、それはそれで様々な解釈が可能な作りになっていて、いい感じかもしれない。
リアルなSFは難しい
非常に重要なこととして、この作品は、「地球生物と地球外生物が接触していないのはなぜか」というより、実質的に「ある惑星の知的生物が、別のある惑星の知的生物と接触しないのはなぜか」を前提としている。
明らかに作者であるアーサー・C・クラークは、地球的な化学特性、知性、意識、進化論を適用できるような生物を、他に数多く存在するであろう宇宙生物としても描こうとしている。
 「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用  「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
ただクラークが、それが唯一の可能性と考えていたのかどうかは、この小説からは読み取れない。
クラークは明らかに、(執筆の時点で最大限の)リアリティにも拘っているみたいだから、生物のパターンを唯一のサンプルである地球生物型に絞るのは(というか絞らざるをえないのは)、当然といえば当然の話だろう。
もちろんそもそも、それは決しておかしなアプローチではない。少なくとも観測可能な宇宙の観測からは、宇宙のあちこちでの物理法則の決定的な違いなどは見つけられていない。
また、地球以外に生物は見つかっていない(他のサンプルがない)。こんな状況では、少なくとも地球生物のような存在を探そうとする地球外知的生物がどこかにいるなら、それは地球生物のような生物と考えるのはかなり妥当だろう。
 「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎  「宇宙生物が地球に来る目的」いくつかの問題点、ロボットの可能性
「宇宙生物が地球に来る目的」いくつかの問題点、ロボットの可能性
気になることがあり最新科学の本とかを読むと、「結局我々は何もわかっていないのではないか」と途方に暮れる場合が時々ある。それは、このようなリアリティを描こうとしたSFの方でも同じかもしれない。我々の知見ごときで、リアル感のある地球外SFを描くなんて、未知の世界への適当な大冒険も同じなのである。
もしもの2001年の物語
まずこの小説の物語を簡単に要約すると、以下のような感じ。
20世紀末期。
明らかに知的生物が残したような直立石、モノリスが月で発見され、 しかもそれは太陽光線を浴びると、何かの合図かのようなエネルギー波を発した。そして、おそらくは土星の衛星ヤペタス(イアペトゥス)に、 そのエネルギーに反応する、また別の何かがあるはずという事実を踏まえ、探査船ディスカバリー号が送られる。
いくつかの困難をこえ、仲間たちを失いながらも、1人、ヤペタスの巨大モノリスに到達した、宇宙飛行士のボーマン。
そして彼は、そのモノリスが発生させたのだろう、時空の通り穴を越えて、自分の知らない宇宙のどこかの領域にまでもたどり着く。それから彼は、おそらくは永遠の存在となっているエネルギー体の謎の生命体たちによって、自身もそのような段階へと変化させられる。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
月への有人飛行寸前の、月のイメージ
この小説が書かれたのは1960年代の後半、まさしく、初めて月への有人旅行に成功したとされるアポロ計画の時代である。当時はアポロ計画がどのような結果になるとしても、人類が月の地を踏むのは時間の問題だと考えられていた。そして、その後は太陽系の地球以外の惑星への有人旅行や、月に人が住むようなエリアの設立なども、数十年以内くらいには行われるだろうと考えてる人は多かったという。そのような、今となっては儚く聞こえる希望的観測が、この小説の設定の背景にもあると思われる。
この話はタイトル通り2001年前後くらいの時代の物語という設定であるが、そこで描かれている2001年は、人が住むようになったどころか、月生まれの子供がすでに存在しているような時代である。
ちなみに多くのSFで、月は低重力環境のために子供の成長が早く、また肌にシワなどがあまりできないとされているが、この作品でもそうである。
月面の岩の分析調査により、月が地球から分離したものでないことが証明されたという記述もなかなか興味深いか。実際のところ、アポロ計画で採取された月の石は、地球の岩石との(化学組成や発生年代の)類似性が多く発見されたために、 無関係説の否定につながっている。
月への有人飛行ももちろんだが、この小説が書かれた当時は、原始の地球に巨大天体が激突した結果、月が形成されたとする、ジャイアント・インパクト説がなかったことも重要であろう。(地球や月に関する話とは全く別の文脈ではあるが)この小説でも指摘されている通り、物体の運動量(エネルギー)は保存されるために、分離したら、個々の運動量は減ることになる。古くは、激突天体なしの分離に関しては、原始地球が後の地球と月の合計の運動量を持っていたとは考えにくい、という指摘が結構多かったようで、クラークもそう考えていたのかもしれない。
ディスカバリーはまるで有人版ボイジャー
ディスカバリー号は、木星の重力を利用した加速、 いわゆるスイングバイを行って、さらに先の土星の衛星へ向かうが、 その辺りの描写は宇宙船が有人であるということを除けばかなり、1977年に打ち上げられた無人探査機ボイジャーをイメージさせられる。(年代的に)そうじゃないのは確実なのだが。
それと、木星の衛星が新しく発見されているという設定だが、その発見が、月に設置されている望遠鏡からなされた、というのも時代を感じさせる(実際、この小説以降にも、木星の衛星は多く発見されているが、その発見は月の望遠鏡ではなく、ボイジャーや地球の望遠鏡によるものである)
他に、長い時間かけて宇宙を旅するための1つの手段にもなりうる技術として、人工冬眠が実用化されている。
 「クライオニクス」冷凍保存された死体は生き返ることができるか
「クライオニクス」冷凍保存された死体は生き返ることができるか
インターネットは存在していないが……
現実の21世紀と比較した場合に、進みすぎているものばかりではない。
例えば、様々なニュース情報をリアルタイムで取得し、更新して、表示する『ニュースパッド』という装置が出てくるわけだが、描写的には、インターネットの劣化版のような感じである。また、紙による情報発信が、もうすでに過去のものと言っていいくらいに時代遅れになっている点が、現実と比較して、なかなか面白いかもしれない。
そのニュースパッドの操作に、コード入力を行ったりする描写もあるから、MacとかWindowsのような、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)も開発されていないのだと思われる。
 「OSとは何か」直感的なGUI、仮想の領域。アプリケーションの裏で起きてること
「OSとは何か」直感的なGUI、仮想の領域。アプリケーションの裏で起きてること
ある意味、インターネットとかGUIが、どれほどに衝撃的な発明だったのかがよくわかる。
ただしAIを介した、声の命令によるコンピューターのコントロールは実用化されている。
 「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
「人工知能の基礎知識」ロボットとの違い。基礎理論。思考プロセスの問題点まで
知性の進化
序盤には、やがて知性を持つようになる人間の祖先たるヒトザルたちの物語が描かれている。そこでは、たとえ感情が生じようとも、それを理解して、記憶していくだけの知性はないように描かれている。
やがてヒトザルの〈月を見るもの〉は、地球外の別の知性がもたらした人工のモノリス(直立石)とも接触する。結局はそのモノリスは、ヒトザルたちを、賢き存在への進化に導く道具でもあるようにも描かれている。
つまりそこでの「知性の誕生」は、他の知性から与えられた、少なくとも影響を受けたためによる誕生である。
確かに進化論が適用できるような生物、つまりは変化するような生物であるならば、別の知性が意図的に、それらの生物が知性を持つような変化(進化)を促すことも可能と思われる。
この辺りの描写は、デイヴィッド・ブリンの「知性化シリーズ」などにも影響を与えているかもしれない。
HAL。まるで本当に生きているAI
微妙にあまり必要なさそうな気もするが、生命体の定義の問題を浮き彫りにするためにか、ただの演出か、ディスカバリー号の船員の1人は、ハル(HAL)というコンピューターとされている。
ハルは単に、宇宙の旅を安定させるためのサポートを行う高度なコンピューターでなく、チューリングテスト(ある機械がとる反応、行動が、どれほど人間的かどうかを診断するためのテスト)にも 普通に合格しうるAI(人工知能)として描かれている。
命令に従うだけでなく、自分で意思を持っているかのように、対話の相手となったり、勝手な行動を行おうとしたりする。
(そして終盤、その自我、あるいは(少なくとも人類的には)プログラムバグが、大きな問題を引き起こすことになる)
コンピューターの半分架空の歴史
コンピューターの革命は20年ごとに起こるとして、その発展の歴史が簡単に語られてもいるが、半分は(この小説が書かれた時点での)未来の話なので、架空である。
20年ごとの革命は、1940年代のENIAC(最初期のものとされるコンピューター)開発を最初。
 コンピューターゲームの誕生「ゲーム機以前のゲーム機の歴史」
コンピューターゲームの誕生「ゲーム機以前のゲーム機の歴史」
そして、1960年代の集積回路(IC)などの開発によるコンピューターの小型化を第二次としている。
 「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械
そして史実に沿っているのはここまでである。
1980年代には、ミンスキーとグッドという2人が、学習プログラムに従い、神経ネットワークを自動的に発生(自己複製)する方法を発見したという設定となっている。
21世紀以降にも大いに発展し続けている現実の人工知能と比べると結構興味深いだろう。
現実でも、学習方法はともかくとして、実際の人間のように振る舞う人工頭脳は、1つの大きな目標とされている。ここではすでに、その成長プロセスの原理の時点から、人間の神経系と実質同じというような感じの人工知能が描かれているみたいである。
 「機械学習とは何か」 簡単に人工知能は作れないのか。学ぶ事の意味
「機械学習とは何か」 簡単に人工知能は作れないのか。学ぶ事の意味  「ディープラーニング。深層学習」 画像認識する仕組み、原理
「ディープラーニング。深層学習」 画像認識する仕組み、原理
我々に理解できる限界
神経系や意識の原理が完全に解明されたわけではなく、利用できるようになっているだけ、再現できるようになっているだけというのもポイントかも。細かい仕組みの解明はまだできそうにもないし、おそらく真実は、人間が理解できるレベルの100万倍以上複雑であろう、というような記述もあったりする。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で  「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
実際そうなのかもしれないが、この世界の原子以下の原理を利用した様々なシステムは、そのうち再現できるようになるだろうと考えている人は多い。しかし、そういう人であってもたいていは、それらの原理自体を知識的に理解することは、結局不可能かもしれないと考えていることは多い。多くのSFで、そこは悲観的な点である。
これのような、知性というものをテーマに含んだSFですら、理解できる限界がはっきり示唆されることが多いというのは、多くの人が、そういうものがあると信じているからだろうか。
普通にかなりすごそうな5割勝率プログラム
それと個人的に興味深いのが、退屈しのぎのために、ハルにはゲームの相手をしてくれるという機能も備わっているが、あまりに強すぎるとそれはそれで面白くないために、あえて5割の勝率を維持するようなプログラムを組まれているということ。
そんなプログラム、実際問題組めるであろうか。
はっきりそのあたりの説明はないが、まさか5割を超えそうなら、あからさまにわざと負けるというようなシステムではないだろう。おそらくは、対戦相手と同じくらいのゲームの実力を、ごく自然な形で発揮するというようなプログラムに違いない。だが、そんなものどうすれば作れるものか。
地球外生物についての議論
やはり終盤に、地球外生物(ET)についての議論があるが、今となっては、古くさいというより、ワンパターン的なイメージがある。
ようするに、知的生物は人間的なフォルムをしているかしていないか。進化の結果は、人間とは似ても似つかない知的生物を生み出す可能性があるのかどうか。我々のような有機物(炭素化合物)の生命体は、もっと頑丈な機械の体を持った存在に、自分たちの知能を移す進化もするのか。
いずれにしても、進化論が適用できないような、あるいは有機物が最初からまったくいらないような生命体は、ここでは仮定されない。
「地球外にも知的生物がいるなら、知的生物としてこの上なく理想のフォルムである人型に違いない」という考えは、過去に囚われた偏見的なもの。
「我々のような形は、長い年月の進化が選択した偶然のものにすぎない。発生学のサイコロは別の結果を示すこともあり、単純に良いか悪いかで言っても、もっと良い形体もあるかもしれない」という考えが、宇宙時代のスタンダード。
そして「科学知識が進歩すると、遅かれ早かれ生物は、自然が与えた肉体というもろい住みかを逃れ、実質的な不死の体、つまり機械の体を得るはず」というのが、やや異様な見解とされている。
この辺りも、けっこう時代を感じる。
精霊か神か、エネルギー生命体
さらに、神秘主義に傾く少数の生物学者の意見として、「そもそも精神はいつか物質の束縛をもがれるはずだ。それこそ我々の理想だろうから」というようなものも語られる。それは多分、我々が精霊と呼ぶようなもので、もしもその先があるのなら、それこそ様々な宗教で語られる神のような存在であろう、ともされる。
 「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか
「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか
物語の最後に登場する、あるいはそうではないかと示唆されている、謎のエネルギー生命体は、まず間違いなくそのような進化をたどった生物という設定なのだろう。
しかしこのエネルギー生命体、 あるいは精霊、または神たるその存在は、簡単に言ってくれるが、人間と実質的に同じような意識を有する機械とかの、それこそ100万倍も奇妙な存在でなかろうか。
おそらく映画版と最も重要な相違点であろう、かつて地球生命のためにモノリスを残した知的生物の視点での歴史の描写は、個人的には最も興味深くもある。
「地球に生命を見つけ、進化の実験のためにモノリスを残した時はまだ、彼らは地球の生物と同じように、しっかり血と肉からなる(ただし見た目は、人間とはまったく似ていない)生命体だった。それがやがて機械の肉体を持つようになり、さらにその段階もある時急に終わった。
休みない実験を続けるうちに、空間構造というものを理解した彼らは、 放射されるエネルギーに思考を保存する仕組みすらも学び、純粋エネルギーの生物に変貌していった」
そういう感じに説明されているが、この時空間に置かれたエネルギー自体に、意識(思考) を保存する方法とは、いったいどのようなものであるというのか。
まずエネルギーをどう考えるべきなのか。それは粒子の塊と考えてよいのだろうか。少なくとも現在の知見的にはそれでよいような気はする。
 「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
我々のような存在に限らず、何かの情報を保存するには、たったひとつだけの粒子が単体では、無理だと考えるのが普通ではある。だから、それがたとえ、はっきり我々が物質と定義するような状態でなくとも、エネルギー生命体とやらが、何かの形をとっているのは間違いなさそうな感じがする。結局、状況によってそれが崩れるということはないのだろうか。
例えば、ブラックホールに入ってその特異点の極限状態に追いやられた時に、エネルギー生命体は結局消滅せざるを得ないのではないのだろうか。つまり真の意味の不死身ではありえないのでなかろうか。特異点のような極端なものでなくても、銀河系内を好き勝手動き回ってるうちに、唐突な悲劇に出くわしたりしそうなイメージはある。
 「ブラックホール」時間と空間の限界。最も観測不可能な天体の謎
「ブラックホール」時間と空間の限界。最も観測不可能な天体の謎
明らかにこのエネルギー生命体は、有機生命体が、さらに機械生命体を経ての最終進化形態のように描かれていることも興味深い。
生物が時々知能を生み、知能は、生物をより高度な段階へと進化させていく、というような感じか。
宇宙という世界は、知能を作り、そして知能は、この世界を作り替えることができる、と言い換えてもいいかもしれない。
だがそうだとすると、知能は何者なのだろうか。
純粋にリアル志向なSFとして考えると、クラークは、この辺りの事に関しては、ちょっとファンタジー的に描きすぎな気がしないでもない。
2010年宇宙の旅
前書きなどによると、これは前作『2001年宇宙の旅』の正当な続編というよりも、映画の要素も踏まえて、ちょっと平行世界的にしたif続編のようである。
しかし前作の船ディスカバリー号の話は出てくる。
『2010年宇宙の旅』
木星とイオを結ぶ線上の、ラグランジュ点(影響の大きい天体同士の重力の釣り合いが取れて、安定しているとされる点)に止まっていたはずの、ディスカバリー号が、なぜかイオに向かって急加速し始めたという話が出た時。
「天文学じゃ、そういうことってありえないと思っていたわ。天文学って精密科学なんでしょう。進歩が遅い私たち生物学者は、いつもそう聞かされてるんだけど」
「精密な科学さ。何もかも計算にいれることができればだが。イオの周辺では奇妙なことなんて常時起きてるんだ。火山活動はともかく、放電現象。それに木星の電磁場は10時間周期で回転しているし」
すべてを物理学的に考えるなら、結局のところ同じことではなかろうか。つまり何もかも計算にいれることができるなら、すべての科学が精密科学と言えるはずだろう。しかしここでは、対比に使われているのが生物学というところが、重要なポイントかもしれない。
仮にすべてを計算にいれることができるならという考えは、あるいはすべてを計算する科学だと考えているがゆえの思い込みの可能性もある。特に生物学に関しては、生物というものを物理数理的にだけ考えることは、実際にはできない可能性もよく示唆されている。魂のようなオカルト的なものを考慮しないとしてもだ。
ボイジャーの最初のフライバイから
エウロパの全表面は氷に覆われていて、見渡す限りには平坦。氷を奇怪な形に掘り上げる風雨もなければ、幾重にも積もって徐々に位置を変える丘となる粉雪も存在しない。大気のないエウロパに隕石が落下しても、雪が舞い落ちることはないから。その表面に作用する力は、あらゆる高地を同一面に引きずり込もうとする重力の働きと、他の衛星が付近を通過しながら引き起こす地震だけ。木星は、その桁外れの質量にも関わらず、大した影響は及ぼさない。木星の潮汐作用は、はるかな過去にその仕事をもう終えていて、エウロパは巨大な主人に、永遠に片面を向けたまま運行しているから。
こうした事実はすべて、1970年代のボイジャーの接近、80年代のガリレオの探査、90年代のケプラーの着陸以来、すでに周知のことである。
これからの話ももちろんのこと、この話が書かれた時点で現実に飛んでいる探査機も、普通に存在している世界観。 それでもこの世界では、モノリスというものが見つかっていて、高性能なコンピューターを積んだディスカバリー号が、謎の現象に遭遇している。
しかし物語は2010年ごろ。「ボイジャーの最初のフライバイからすでに30年あまり」というような文も見られるが、太陽系有人探査の進み具合からして、すでにというよりも、「まだ30年で~」と言うべき場面でなかろうかと思わなくもない。それともやはり、この頃といえば、まだまだ宇宙開発の速度はどんどん上がっていくだろう、とか考えられていた時期だったのだろうか。
液体の水の世界エウロパ
エウロパに関する知見は、小説執筆当時の、かなりの最新情報であったといえるだろう。この小説の中でも、やはり水があるということで、非常に興味深い衛星として扱われている。現実と同じだ。
エウロパに水生生物がいることになっているが、その情報が出てくる場面は、やはりSF小説としてはワクワクする。
この水生生物に関しては、モノリスとの関係性も含めて、作中で議論の模様が語られている。中国の探査船のチャンという人物が遭遇し、報告したこの水生生物は、チャンの報告の限りでは、 少なくとも人間のようなで表現できるような知的生物ではない。
また、エウロパ生物の議論の中で、熱水噴出孔の生態系が根拠として挙げられたりもしている。地球上で1度でも起こったことは、この銀河系の中では100万回は起こると考えた方がいい、生命の誕生だってそうなのかもしれない。
水はエウロパに、他の木星の衛星にも氷が発見されたりしている。イオには噴火する火山がある、つまりは活動している。エウロパ上の生命の存在は可能というよりもむしろ必然。後知恵を働かせた時に自然の脅威のほとんどがまさしくそうであるかの如く。
さらに議論は、知性に関する問題へと続く。海中で高度な知性は発達しうるのか。温和で変化に乏しい環境の中、試練そのものの数が足りないのではないか。
さらに海洋生物は火を使わない。火を使わないで、どのようにテクノロジーを発達させようというのか。
だが人間の道が唯一だという保証もどこにもないとも語られる。海に高度な文明が存在しないと誰が断言できようかと。だがこれは、生命がそもそも、我々の一般的想定以上に特別であるという可能性まで、夢によって覆っているようでもある。
とはいえ、海中世界に知的文明が発生しうるか、という問題自体はかなり興味深いと思われる。
知的文明の形は我々のものだけか否か、というような疑問が提示されたすぐ後に、「宇宙に乗り出すような文明がかつてエウロパにあったなら、建物や、それでなくても何らかの人工物の形でどこかに痕跡が残っているはず」という推測があって、それもなかなか考えさせられるところか。
もっと後の場面。エウロパで発見される生物のオアシスは、地球の古生代の海と比べても安定した環境とは言えず、進化が急速に進行し、突拍子もない形体を無数に生み出しているとされている。生命の泉は遅かれ早かれ弱まり、背後にあった力は他の場所に移っていくと。生態系そのものの移動と言えるだろうか。
収斂進化による、魚と似た水生生物の存在も示される。地球の生物との明らかな相違点はエラがないこと。彼らが泳ぐ水の中に酸素はほぼないから。地球の熱水鉱床に群がる生物のように、代謝機能は火山付近の環境に豊富に含まれる、硫黄化合物に基づくと書かれている。目を持っているものもほとんどいない。めったにない溶岩の噴出と生殖の相手や、獲物を求める生物が、時折発する光を除けば、闇の世界。ここで進化論のみならず、地球生物的な遺伝子の譲り渡しシステムもあるのが当たり前にされている。
生物をどのように考えるべきであろうか。
UFOの半世紀
近未来の起こった出来事として、アメリカ航空宇宙工学協会(AIAA)の『UFOの半世紀』という報告書がある。1997年、つまり1947年のアーノルド事件から半世紀ということで出されたもの。
 「ケネス・アーノルド事件」空飛ぶ円盤、UFO神話の始まりとされる目撃譚
「ケネス・アーノルド事件」空飛ぶ円盤、UFO神話の始まりとされる目撃譚
ここでUFO伝説の歴史について軽く語られるわけだが、「AIAAが報告書を発表する頃には、名のある科学者で、UFOと、地球外生命や知性の関連を信じる者など皆無になっていた」とされている。
ある知性の話
かなり昔に地球を見つけたこともある、ある知性の話がまたしても語られる。そこはやはり、特に興味深いところかも。
実験にとりかかった生物は人間ではない。人間に似ているところはどこにもない、しかし彼らもまた、血と肉からなる生き物。宇宙の深淵を見る時には、畏怖と脅威と孤独を感じる。
彼らは様々な生命形体、千の世界で進化システムを見た。宇宙の闇の中、知性の最初のかすかな光がきらめいては消えるのを何度も目にした。
銀河系全域で精神以上に貴重なものを見出すことはできなかった。彼らは星々の畑に種を蒔くようにもなるり、時には収穫、時には除草した。
彼らは(恐竜の時代よりは後の)地球を見つけ、そこに生命の世界を見出した時、研究を十分に行った後、修正にかかった。様々な種の運命に干渉し、しかしそれらの実験のどれが成功するかを見るには100万年以上は必要。不死ではなかった彼らは、他にしなければならない多くのことを成すために、地球生物の運命を知らないままに去る。
銀河系の文明も移り変わっていく。銀河国も起こっては滅び、後を継ぐ者に知識を残した。星々の世界で、進化は必然かのように神を目指した。太古の地球を訪れた生物たちは肉を捨て、機械の体になり、脳の構造から思考そのものまで金属にそのありかを移した。宇宙を動くのに船ももういらない、彼ら自身が宇宙船と同じだから。
やがて機械生命の時代すらも終わる。絶え間ない実験のはてに、彼らは空間構造そのものに知識を蓄え、凍りついた光の格子の中に思考を永遠に保存する仕組みまでを学んだから。物質そのものから逃れて、放射線の生物になった。彼らは純粋エネルギーの生物にまで変わった。
多くの世界で打ち捨てられた脱け殻は、どこの世界でも朽ち果てて塵にかえっていった。
彼らは時すら超越した銀河系の覇者。それでも彼らは、遠い先祖が始めた実験の様子を、神のような存在として見守り続けている。
真の宇宙全体からしたら一部にすぎないだろう銀河系の中ですら、あまりにも広大であるために、「そういうことになっているだろう」というような想像がここでは語られている。
つまり生物が相当に珍しい現象であるのだとしても、それがいくつも起こっているほどに、この領域は広いだろうと。
生身の生物から機械生物へ。そして、物質をも超越した存在へと変わっていく進化の過程は、SFではよく見られるが、基本的には、まるでそれが進化の必然かのような印象を与えるものが多い。この話でももちろんそうである。
しかしこれは、時間的スケール的にどうなのだろうか。実際に銀河系は広くて、珍しい現象の生命が、わりと誕生しているのだとする。だとしても、例えば地球生物は、人間という知的生物を誕生させるために40億年ほどかかったともされている。そもそも生命の歴史と言われるものは、ほとんどが、他の恒星系になど気づけることもないような、微生物の時代だったはず。地球生物の知性の発展が遅すぎる可能性もあるが、これが早すぎる可能性だってある。
そもそも進化は、必然的にある方向に向かうのだろうか。例えば地球においても、知性を獲得する存在は人間でなかったかもしれない。だが、機械生物や、さらにその上の段階の生物への進化は、また少し次元が違う話のような気もする。
よく機械生物が生き残るとされているのは、それの寿命が圧倒的に長いはずだからだろう。だが、有機生物の寿命というのを、そもそもどう考えるべきかという疑問もある。
仮に生物の本質を遺伝子とするなら、入れ物としての我々が大量のバックアップを待たされている遺伝子なる存在の生存時間は、かなり長いと言えるかもしれないのだ。
地球生物をどう考えるべきか。生物と知性の繋がりを、いったいどう考えるべきか。
太陽系自体の変化
終盤の展開のスケールは、前作よりも本質的には小さいと思われるが、しかし実質的には大きいものとも言えるかもしれない。少なくとも架空の物語的には大きいと思われる。木星における大きな変化、さらには地球生物すべてに関連する、太陽系自体の重要な変化。これが近未来を描いた小説ということを考えると、相当に大胆な展開を持ってきたものだと思う。
また、エウロパの特別性も、最後の最後でかなり強調される。
2061年宇宙の旅
やはりif設定多めなパラレル続編。
『2061年宇宙の旅』
前作において、神的な高次元生物に恒星ルシファーへと改造された木星。実質、恒星系の中のミニ恒星系みたいになった木星系(ルシファー系)の調査の話とも言えよう。
人工冬眠の効果
老化の原因の一端として重力を挙げるSFはよくあるが、さらに人工冬眠についての若返りに関しても触れられている。
病院の地球の1/6という重力が、生物時計を遅らせただけではなかった。生物時計は逆行もさせられた。人工冬眠が老化の過程を停止させるに止まらないことは今や広く信じられている。若返りを促進するのである。
ルシファー系
ルシファーから受けるエネルギーのために、表面温度を数百度上げて、金星以上の灼熱世界となったイオ。このような灼熱世界においては、表面温度による大地の融解などが、短期間で地形を変え続けてしまう。 そこで惑星学者も地図作成の企てを完全に放棄したとされるが、ゆっくりとはいえ、地球の地形とかだって変化することがある。時間的スケールと地図を合わせて考えた時に、どうにか変わり続ける地形の地図に、意味を与えられないか、と考えたくなってしまうような話である。
ガニメデとエウロパに関しては地球に似た温度を持っている。もちろんエウロパに関しては生命があり、ついでに表面の氷が溶けている設定。
ルシファーの寿命の推定値が1000~100万年ぐらいの幅があるとされているが、いずれにしても、このルシファー系は、太陽系よりも早くに死を迎えると思われる。その後にどうなるかも気になるところではあろう。
恒星系の環境次第によっては、生物の進化、というより知性を持つという変化が起こりやすかったりするだろうか。地球では目に見えるような生物から、知的生物が誕生するまでに数億年ほど時間をかけたとされているが。
エウロパの水生生物は、見かけなどはともかくとして、本質的にどのように考えられているのか。
この作中においては、サメのような生物が宇宙船に近寄ってこないことから、何か高度な通信システムを備えているのではないか、という仮説が出たりもしている。
エウロパに関しては、厚い雲に覆われた中にある、新しいエウロパ。40億年前の生まれたての地球もそうだったかもしれないように、陸地と海が果てしない戦いを始める準備をしているような。
ルシファーが誕生したことによるその変化の過程は、ダイナミックかつドラマチックである。
50年前までは陸地も海もない、氷しかなかった。今ルシファーに向いている半球においては、氷が溶けて、沸騰して空に昇った水は、夜側の永久冷凍庫に堆積していく。そうして、半球から、もう片方の半球へと、数十億トンもの液体が移動し、それまでは太陽の青白い光さえも知らなかった太古の海底が露出することになった。
そして先。いつかその捻れた大地も、植生の広がりに覆われ、和らげられるはずとされる。
かつて、木星とイオのラグランジュ点であった、巨大な黒いモノリスが置かれていた『L1点』。 ルシファーの誕生日光速に近づくのは危険となった 元々木星と内側の衛星との間にあった電気エネルギーの流れ、イオの電磁束管の強度が数百倍に増したからとされる。このエネルギーの流れは電離したナトリウムの光で黄色く輝き、肉眼に見えることすらある。
ペネトロメーター(土に打ち込んだりして、大物質の情報を得たりするための器具)が、突き刺さってから5秒間ほど機能して、イオの化学的、物理的、レオロジー(流動的性質)的な様々な計測値を研究者たちにもたらした。などの探査シーンも、わりと興味深いところかもしれない。
エンデュアランス号漂流記の時代
少し前の、世界が狭かった頃の話。
アーネスト・シャクルトン(Ernest Henry Shackleton。1874~1922)の『エンデュアランス号漂流記』のような、旧時代の極探検の記録。それに比べると、たとえ絶望的な漂流をしたって、それでも太陽系天体の探検隊は恵まれている。
同じ地球にいるのに、他の人類から完全に遮断されてしまい、半年、1年と、連絡などできなかった、少し過去の時代。
それと比べて、リアルタイムで仲間たちと話せないとか、地球から返事が来るのに数時間かかるとか、そういうことに文句言うのは恥じるべきことでもあるとも。
近代において、どれくらい急激に世界が狭くなったのか、あるいは広くなったのか。そういうことは、今にしか生きていない我々には実感しにくい事だ。逆に昔の人たちは、未来の情報世界をどのくらい正確に想像できたろうか
モノリスの生物選択。木星の生物
装置としてのモノリスに関して、言及されるシーンが終盤にある。ついでに木星生物に関しての情報もある。
それを、まだ人間だろうフロイド博士に語るのは、 高次元生物、になっていないにしても、それに近づいているだろうボーマン。それになんと、機械知能であるハルも。
彼ら(ボーマンとハル)は、ハルが調べたモノリスの内部システムをいくらか利用することすらできる。それは一部にすぎないが、しかしそれがさらに多くの目的を果たすための道具ということもはっきりしている。
そして、生物園の中に影響を及ぼし、知的能力を発達させるというモノリスは、それ自身が高い知性を持っているが、それでもなお生物ではないとされている。自意識を持たず、それを有している生物に比べれば、下の存在にすぎないと。
400万年前には、アフリカで、猿の部族に知的生物にいたる運命を与えた。モノリスのそれは多くの犠牲を払う実験。木星を改造し、恒星としてのその潜在能力を発揮させたのも、もちろんエウロパの生物の知性の発展のためであるが、そのための犠牲もあった。
大陸のような雲が渦巻く中で、メートルの波長の周波帯で(単純なものだが)意思疎通をしあう、生きた気球のような生物群。それらの間を飛び交っているような、生きた飛行機のような生物たち。
地球の海のイカを思わせるようなジェット推進をする魚雷型生物は、巨大な気球生物を獲物とする捕食者。気球生物たちも、触手や電撃によって抵抗を試みたりする。
半透明で、様々な形態を有する、大気圏の中の、やはり巨大なプランクトン。上昇気流に浮かび、繁殖するまでの時間は生きる。そして深みへ押し流されると炭化して、新しい世代に再利用される。
そしてここには知能の兆候など見られない。最も有機生命体として発展していると考えられるだろう捕食獣でさえ、頭脳など持たない自動機械(サメのようなと表現されているのは気になる)
木星生物のそのダイナミックな世界は、しかし基本的には脆弱とされている。霧と泡、上層大気の稲妻で形成される薄っぺらい石油物質の世界。
モノリスは、エウロパに比べた場合、その世界には価値がないと判断し、ルシファーを形成した訳である。
3001年終局への旅
シリーズ完結編扱いであるこれは、特に大きく未来の話であるため、そういう意味ではちょっと異色的でもあるかもしれない。
『3001年終局への旅』
1000年分if歴史
これまでのような、近未来を舞台に創作したものでなくて、1000年分if歴史の組み立てがある。
土星のリングから氷を集めて、金星や水星などに押していく作業は、2700年頃から始まった。そしてこの計画の前後の、素人目には違いらしい違いが見分けられないような映像が、環境破壊という罪の強い根拠とする、太陽系環境保護論者たちがけっこういたりもする。一般大衆は過去の多くのエコロジー災害に過敏になっていて、「土星に手を出すな」との風潮はかなり強まっている。そこで、チャンドラーというキャラクターは、リング泥棒をあきらめ、カイパーベルト領域で活躍する彗星カウボーイに転向した。
ようするにするに水の豊富な領域から、それらを運ぶことで、金星や水星を開発しようと計画されているわけである。
十分に発達したテクノロジーは魔法と見分けがつかない
1000年間、宇宙空間を冬眠状態でさまよっていた後で目覚めた、『2001年、宇宙の旅』の(死んだはずだった)フランク・ブールの視点での驚異の未来が描かれる。
作者本人の言葉と考えるとやはり、「十分に発達したテクノロジーは魔法と見分けがつかない。誰が言ったか、そんな言葉がある」とかそのあたりの表現はなかなか楽しいか。
「2001年の時代に投げ込まれた11世紀人ではなくてよかった」とも彼は言うが、実際はどうであろう。
もちろん彼はエウロパの生命や、ルシファーのことなども知らない訳である。
そして、これもまだ、2010年の終盤とエピローグの間の時代の話ということを考えると、パラレル的にどんなふうになっているのかも、また気になるところであろう。
遺伝子調整で大人しくさせた肉食恐竜がベビーシッターとして優秀というのは、まさしくファンタジーであろう。26世紀ぐらいに流行ったというジョークが面白い。
「あなたはお子様を恐竜に任せて安心ですか? とんでもない、子供たちが怪我をさせたら大変」
真空エネルギー利用のリスク
原子炉の暴走という、かつてのテクノロジーの恐れがさらにバージョンアップしている。
蠍座新星の話は、SF的にはかなり興味深いと思う。
もちろん超新星爆発というのは、多くの恒星系で起こりうることだろうが、オートマチックの新星パトロールが追いかけた爆発の模様。その始まりは、なんと恒星ではなく惑星だったのである。
惑星の1つが最初に爆発し、それが恒星に飛び火したのだ。だが惑星の超新星爆発など、普通に考えてありえるわけがない。そして、「誰かが真空エネルギーを理由していて、その制御が効かなくなってしまった」というのが広く認められる説となった。超ド級のメルトダウンである。
また、「熱核兵器ら、ありふれた原料を使い、作りが単純だから簡単。それよりもっと高級なもの、例えば反物質爆弾とか、ミニブラックホールが欲しい場合は2、3ヶ月はかかるかも」というようなセリフもあったりする。
アインシュタイン宇宙のゼロ
モノリス(ボーマンとハル)が重要な情報を、ブールに伝えようとした場面。
さすがのモノリスも、何もかも完璧にお見通しというわけではないのか、彼の身元を確かめるために、かつての自分たちの軌道力学の先生の名前を言ってもらっている。
そしてそういうやりとりは、モノリスの存在があると思われるルシファーから、50光分の(つまり光で通信するには1時間ほどかかるはずの)距離でのこと。
そのメッセージは1時間前に発射されているはずなのだが、しかし少なくとも、ブールが、証拠となる軌道力学の先生の名前を告げてから、すぐにそれを理解するなど、リアルタイム感がかなりある。
この点に関して、「おそらくは正確にアドレス指定されたパッケージに詰め込んだ、知的な仲介プログラム」を使っているのかもと、推測はされる。
ただ、この時代において、脳に直接様々な情報をダウンロードできる『ブレインキャップ』というシステムを利用して、必要な情報を(もちろん1時間なんて待たせずに)ダウンロードさせる芸当などに関しては、「こんなことどうやったらできるのか」の疑問だけですまされる。
そしてモノリス、その装置を用意した何者かに、今作の時代の時点で、最後に伝わった情報は、人類の時代においてもっとも最悪の時期とされた20世紀。
この二度の世界大戦が起こった世紀は、人類史の中でも最悪の時代だとされることも多いが、実際はどうであろうか