昆虫とはどんな生物か?
節足動物。最も成功した多細胞生物
昆虫(Insecta)は、分類学上、節足動物門(Arthropoda)の六脚類(Hexapoda)に属する動物のグループ。
その単純な数や、多様性において、節足動物はこの地球上で最も繁栄した多細胞生物群として知られる。そして昆虫と呼ばれる生物群は、節足動物の中でも特に繁栄している。
具体的には、知られている地球生物の85%ほどが節足動物で、その節足動物の90%くらいが昆虫。
また、昆虫以外の節足動物としては、甲殻類、クモ類、ムカデ類などは有名と思う。
 「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
節足動物の一般的な特徴としては、多数の『体節(somite)』が繋がった形状の体。その体を覆う、キチン質とタンパク質から成る『クチクラ(Cuticle)』という成分の外骨格など。
キチンとは水素、炭素、窒素、酸素で構成された高分子(原子量が多い分子)のこと。
また、節足動物という名前の由来は、体節についた『付属肢(appendage)』と呼ばれる足である。
 「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
昆虫の体は、頭部、胸部、腹部の3つの体節で構成され、普通、付属肢は全三対、つまり6本であり、胸部についている。
通常、頭部には脳と、目や触覚などの感覚器官が揃い、口もある。胸部には、足以外に、二対の翅(羽)を持つ。腹部には消化器官、排泄器官、生殖器官がある。
ちなみに、哺乳類が所属する門はもちろん脊椎動物門(正確には、脊索動物門の脊椎動物亜門)である。それには哺乳類以外に、爬虫類(鳥類)、両生類、魚類が含まれる。
繁栄の度合いは節足動物に余裕で負けてるかもしれないが、知能の高さと、図体のでかさは我々の勝ちと言えよう。化石種を含めても、おそらく昆虫で1メートルを超える生物はまだ知られていない。
 「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
昆虫はなぜ、地球においてこれほどに最強か
昆虫の形態や機能、習性(生態)などを、 他の生物種と比べた場合、 その多様性は驚くべきものがある。すでに発見されている種数はもちろん、発見されていない種数に関しても、他の生物を圧倒しているという見方が一般的だ。
その種数、多様性の高さを見るだけでも、そのままこの昆虫という生物種のあらゆる環境への適応性の強さも明らかと思う。だがなぜ、この種は、これほどまでに生物として強いのか。
これは単に見方の問題であるかもしれない。我々、人間という生物は、自分たちそのもの(人間)を生物の標準として考えがちなところがある。他の様々な生物を、(時には擬人化してまで)いろいろ人間と比べて考えたがる傾向がある。
しかし、ヒトは分類学的には、1属1種という、構造的な幅の狭い 生物である。 少なくとも地球のような環境の生態系において、人間は、おそらく発生する確率が低い生物種なのだろう。昆虫はあらゆる環境で安定しやすく、だからこそ様々な環境に適応することで、結果的に幅広い多様性を獲得している。
しかし結局は、「では昆虫はなぜ地球生態系の中でこれほどに強力な存在か」という、実質同じ疑問に戻ってくるだろう。
昆虫はそれぞれの種ごとに異なった習性を持ち、様々な生き方を実践している。中には、やはり地球の生態系に溢れた植物群と深い関わりを持った種もけっこういる。他の生物に『寄生(parasitism)』するという生存戦略を取った種も少なくない。
また、この地球上で最も繁栄していると思われる動物群が、基本的に陸上生物であるということは、注目すべき点であろうか。つまり普通は、地中、地表、植物体、さらに空が、昆虫類の主な住みかである。
ただし、水生昆虫と呼ばれる昆虫も(比率的には少ないとはいえ、絶対的な全体数が多いので)わりといる。水面や水中に生きる種、生涯水から出ないものもいるし、それはさすがに珍しいようだが、海生種も一応はいるとされる。
哺乳類には全く使われていない生存戦略であるが、多くの昆虫は、『変態(transformation)』という技を使う。 つまり、生涯のある時期に、全く見かけも内部構造も異なっているような(何も知らない者が見たら、別の生物だと考えておかしくないような)『幼虫(Larva)』から『成虫(Imago)』の変化(移行)過程がある。
地球のほとんどの動物である昆虫のほとんどのが、この変態を行うということから、明らかにこれは、種の技として優秀なのだろう。
これは時間線上の役割分担の方法と考えられることが 一般的と思われる。
つまり、 成長のための幼虫時代と、生息域の移動や生殖などに特化した成虫時代を、明確に分けるという方法。これは例えば、効率のよいエネルギーの使い方に繋がるかもしれない。
もちろん役割だけでなく、その構造に合わせて生活環境なども変える場合も多い。親世代と子世代の競争を避けるという意味でも重要だろうか。
そもそも節足動物のクチクラという生体構造、つまり外骨格というもの自体が地球環境の中で有利な特性なのだと考える向きもある(しかし実際問題、昆虫は動物の中で圧倒的に繁栄しすぎている。昆虫に広く見られる特徴は、つまり地球の生物環境において優れている、という結論にしかならないかもしれない)。
クチクラというのは、皮膚に付属するように形成される外骨格であるが、他の外骨格としては、例えば貝殻などが有名と思う。
一方で、内骨格というのは、もちろん構造内部にある骨系。 少なくとも普通の外骨格とは区別すべきとは思うが、一応、亀の甲羅のような、基本的には内骨格の生物が露出させている、一部の骨部分に関して、”外骨格”という言葉が使われる場合もあるようだ。
昆虫の形体、構造
昆虫の体制はかなり合理的とされ、その繁栄の理由として挙げられることもある。
昆虫の3つの体節、すなわち頭部、胸部、 腹部は、それぞれに独自の機能を備える。
頭部は感覚器官(脳、眼。触角、口など)。
胸部は運動関連(2対の翅、3対の脚)。
腹部は、生理機能関連(消化、排泄器官、生殖器官)。
生息環境に適応する種ごとの脚は、基節(coxa)、転節(trochanter)、腿節(femur)、脛節(tibia)、跗節(tarsus)の各部分からなり、 跗節の先端に爪がある。
脚には体の支え、歩く、跳ぶ、泳ぐ、掘るなど、特に種にとって重要な役割に特化していることもある。また、昆虫の中には音でコミュニケーションする種もいるが、たいてい脚で音を出している。
胸部はさらに、前胸(prothorax)、中胸(mesothorax)、後胸(metathorax)の3部分に分かれるが、前脚、中脚、後脚がそれぞれにつく。
ちなみに前翅は中胸、後翅は後胸についている。
腹部は、10~11節に分かれ、どの節にも脚はない。
ただし、二次的に翅や脚がなくなった種もいるので、それら(翅や脚)に関しては、昆虫に完全に普遍的な特徴というわけではない。
進化史的には、同規的体節制(ほぼ同じ体節が繰り返されるような)生物(現生する生物として例えばムカデ)が先にいて、昆虫のような異規体節制(各体節に分化が見られる)生物は後から生まれたと考えられている。
まず各節に脚を持つようになり、胸部の脚が発達と腹部の脚が退化したグループが、昆虫になったのだろうと。
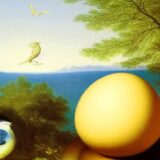 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
前翅と後翅の古いもの、新しいもの
昆虫は通常、二対、計4枚の翅を持つが、普通に飛行する種であっても、前か後かの一対の翅は、羽としての機能を失っている場合がけっこう知られる。
例えば、昆虫類で最も繁栄しているとされる『甲虫類(Coleoptera)』からして、前翅(forewings)が硬化していて、それは『鞘翅(elytron)と呼ばれる。羽としての機能は失われ、さながら鎧のようになっている訳である。
ハエの後翅(hind wings)はかなり小さくなっていて、それは『平均棍(haltere)と呼ばれる。
平均棍は一見、飛行には役立ってないが、これを消去してしまうとハエは飛べなくなるそうなので、結局何らかの役に立っているのだろう。
翅は薄い膜でできているのだが、普通それだけでは強度が足りず、飛翔に使うのは厳しい。しかし昆虫の翅には、『翅脈(vein)』という支えの骨的なものがあり、翅の構造を安定させている。
さらに、翅脈は凹凸気味で、飛翔時の空気抵抗を減らしてくれるとも。
原始的な昆虫は、翅脈を多く備えているとされ、進化の中で、ほとんどは融合したり消失したりしたと思われる。
卵に寄生するハチ類や小型のガ類など、微小化した種には、翅脈がほとんど消失し、翅の周辺部にある縁毛というのが発達しているらしい。
多くの昆虫は、翅を腹部の上に折りたたむことができるが、例えばトンボやカゲロウはそれができない。普通そのような折りたためない翅の方が古い構造とされていて、腹部上に折りたためない翅の種を旧翅類、折りたたむことができる種を新翅類とする分類もある。
口器。噛むか、吸うか
昆虫の頭部についた口は、『口器(mouth-parts)』という。
口器は、上唇(じょうしん。labrum)』、『大顎(おおあご。mandible)』、『小顎(maxilla)』、『下唇(labium)』、『下咽頭(hypopharynx)』などのパーツで構成されていてる。
大顎、小顎は、もともと付属肢だったのが、変形したものだと考えられている。
当たり前だが、口器の形状は、多種多様な昆虫の節食方法によって、かなり見た目が違ってくる。ただ、基本は噛むのに適したものであるようで、補食性の種はもちろん、原始的なグループはこのタイプだという。
しかし、血液を吸うカとか、花の蜜を吸う蝶とかのような細長い 口も結構有名であろう。
 「蚊」人間同士を、生態系を血と病気で繋ぐ小さな怪物
「蚊」人間同士を、生態系を血と病気で繋ぐ小さな怪物
口器の形成に関しては、頭部そのものの構造が重要と思われる。
昆虫は、胸部が3節、腹部が10~11節からなる訳だが、頭部は1つの塊かのようだ。しかし実は胚発生の観察研究などの結果、この塊(頭部)は、先節と6節が融合したものだという説が有力。
口器を形成する大顎や小顎などは、付属肢が変化したものと考えられている。胚発生において、最終的には口器となる部分が、胸部の脚部分の形と似ている段階があるから。
触角は匂いの感知器
昆虫の頭部の正面か側面には1対の触角(antenna)があることもよく知られているだろう。これは基本的に、匂いと関連する器官のようである。
触角もさらに細かく第1節の柄節(scape)、第2節の梗節( pedicel)。第3節以降の鞭節(flagellum)と部分的に呼び分けられたりする。
口器と同じく、触角も、付属肢が変化したものと考えられている。 そういう意味でこれらは、すごく特殊化した脚と考えていいかもしれない。
消化と排泄。マルビーギ管は一般的か
昆虫の消化管は、前腸(foregut)、中腸(midgut)、後腸(hindgut)の3つの部分に分けられる。そして前腸はさらに、口から、咽頭(pharynx)、食道(oesophagus)、嗉嚢(crop)。前胃(proventriculus)に分けられる。後腸は、結腸(colon)と直腸(rectum)、あるいは回腸(小腸)と結腸(大腸)と直腸に分けられるという。
消化のための仕組みも種によっていろいろ。ゴキブリの前胃には歯があり。カメムシは胃が4つの部分に分かれていたりと。
節足動物の排泄器官といえば『マルビーギ管(Malpigian tube)』 が有名であろう。それは、中腸と後腸の間付近から体腔内に出ている細長い管で、体液から吸収した老廃物を尿酸に変えて排出するというもの。昆虫ではかなり一般的なものだが、一部これを持たない種もいるらしい。
単眼、複眼の解像度
昆虫の視覚器官、目として、『単眼(ocellus)』と『複眼(compound eyes)』が知られる。
単眼は3つで、三角の形に並ぶ。単眼は、またクチクラのレンズに覆われてるが、あまり解像度はよくないという。
複眼は、頭部の両側面についているもので、多くの人が、昆虫の目と聞いて、思い浮かべるような目。思い浮かべられなくても、実際に昆虫を見てみて、「多分これが目だろう」と思えるような目である。
複眼は、多数の小さな『個眼(omatidia)』の集合で、昆虫の視覚は、主にこの複眼による。
複眼の個眼の数は種によってかなり差がある。
トンボは1~3万くらいあるようだが、これはかなり多いという。
イエバエ(Muscidae)で4000ほど。
ミツバチ(Apidae)の働きバチで4500ほどらしい。
当然だろうが、地中生の昆虫などはかなり少なく、そもそもひとつも持たなくなった種もいるという。
モグラが目を失ったのと同じ理屈であろう。
呼吸器官。気管かエラか
昆虫には陸生の種が多いが、肺は持たない。皮膚呼吸を行う種も少ない。
『気管(trachea)』という、管状の機構が、昆虫の呼吸系である。脊椎動物の体内で、空気の通り道として存在する気管とは違い、昆虫のはそれ自体が、そのまま、呼吸器官として機能している。
水生の昆虫も、多くは気管で呼吸し、ずっと潜ってはいられないが、一部の幼虫などは、魚のようにエラ呼吸をする。
一般的な陸生昆虫や呼吸管を持つ水生昆虫は、気門や呼吸管の構造的に、気管が体外に開いているが、これを『開放系』という。一方、水生昆虫や寄生性の種の幼虫などにみられるような、気管が体内に閉じた構造は『閉鎖系』。
普通、開放系の気管は、体の側面の気門から体内に伸び、複雑に枝分かれした毛細気管が体内に広がる。
また、昆虫の循環系は血管を持たない開放血管系で、体液が体内を満たす。体液循環には、体の背面中央を走る『背脈管(dorsal vessel)』の働きが重要。
背脈管も前後部に分けられて考えられる。前部は細い管の大動脈に相当し、後部は心臓に相当する。昆虫の血液には、 人の血液においてあの赤色の原因とされる(ヘモグロビンを含む)赤血球に相当するものはない。
生殖器。精子をどう扱うか
一般的に、オスは、挿入器である陰茎(penis)が発達している。その基部を支える陰茎基(phalobase)から、1対の陰茎側片(parameres)が出ている。陰茎側片は、交尾をする際に、メスの腹端部などを適切に捉えるための把握器(clasper)にもなる。
把握器もまた付属肢の変形説が有力らしい。
オス交尾器の陰茎と把握器は、種ごとに特徴的で、形質分類において重要視される。
 「性の進化」有性生殖のメリット、デメリット。オスとメスの戦い
「性の進化」有性生殖のメリット、デメリット。オスとメスの戦い
メスの生殖口(gonopore)は、通常は腹部第8節か第9節に開口するようである。ハエやガの仲間のように、腹部の末端で、必要に応じて伸長するものもある。
一部のチョウ目では、産卵口と交尾口が分かれ、精子が移動する受精管でつながっているもの(二門式)も知られる。
また原始的な種では、交尾口と産卵口だけでなく、肛門も同じ場所に開口する総排出口(単門式)。
コウモリガなどは例外的に、交尾口と産卵口が分かれているのに、それらを繋げる受精管がなく、精子は体腔外の溝を伝って移動させられるという(外溝式)。
昆虫の性と繁殖
昆虫の多くは一般に両性生殖する。つまりメスとオスという性別があり、それらが交尾することで、つまりオスの精子が、メスの体内に注入され、それがメスの体内の卵と混じることで、子が発生する。
精子はまず、メスの中の受精嚢にたくわえられて、受精は産卵時期となる。つまり普通は、媒精(insemination)、 つまりメスの体内に精子が注入されてから、受精までにタイムラグがある。そもそも受精のタイミングをメスがコントロール可能であり、それは(例えば脊椎動物などと比べての)昆虫の両性生殖の特徴とされる。
 「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
普通それは繁殖目的であるから、子のできない異種との交配は意味がない。なので、多くの種において、固有の配偶行動が見られる。
ホタルの発光や、セミやコオロギの鳴き声、ガの性フェロモンなど、視覚、聴覚、嗅覚と、いろいろ利用されている。
多くの種では、オスは生涯に複数回交尾する。しかしメスは1回しか交尾しない種もけっこういる(もちろん複数回交尾する種もいる)。
オスの精子なしで、メスが生殖(単為生殖)できる種も知られる。この場合、受精するか否かが、子の性別に関わる場合もある。オスと交尾した場合でも受精させずに、必要に応じて、未交尾の場合の性別の子を選択できることもあるようだ。 特に真社会性の種(例えば女王を中心とした集団の巣を作るハチやアリ)などでは有名であろう。
しかし、性決定様式について、(従来はそうだと考えられていた種についても)単純に受精卵がメスになるわけではないという研究報告もあるという。
また、『世代交番(heterogony。alternation of generations。cyclical parthenogenesis。周期的単為生殖)』というパターンがある。
これはつまり、両性生殖をする世代と、単性生殖をする世代が生活環の中に現れる現象。昆虫ではタマバチ科アブラムシ上科、タマバエ科、チビナガヒラタムシ科などで知られているという。
世代交番は昆虫でも珍しいが、昆虫以外でも、ワムシやミジンコや吸虫くらいにしかみられないとも。
世代交番する昆虫では、同一種でも、両性世代と単性世代成虫の形態が異なっていることもあり、別の種として(間違われて)記載されてしまう場合も珍しくないようだ。
一部の昆虫には、1個の卵から、発生過程で複数の胚が生じ、それぞれ別個体になる(多胚生殖)、というような現象も知られる。
例えばこの多胚生殖をするハチ目のトビコバチでは、古くから幼虫に2型あることは知られていた。頑丈な大顎を持った細長い幼虫と、ウジ状の幼虫。前者は蛹になならずに死ぬが、ウジ幼虫の方は、ちゃんと蛹になり羽化し、繁殖する。
普通に考えるなら、先に生まれた方は兵隊カースト(護衛)なのだろう。
かなり例外的だが、胎生の昆虫も一部知られている。
アブラムシはメスを生む性単為生殖が胎生で、さらには、その体内の胚には、さはに次世代の卵母細胞も生じているとか。
ツェツエバエ(Glossina spp)など、幼虫が、メス成虫の体内でかなり育ち、産出された後すぐに蛹化する種も。
直接繋がり合う交尾でなく、精包という、精子を包んだ塊を雌に渡すという種もけっこう知られる。これは古い方法という説が有力らしい。
変態は、魔法の変身かのよう
基本的に昆虫の変態は、以下の3パターンに分けられる。
幼虫から成虫になる間に『蛹(pupa)』の段階を挟む『完全変態(holometaboly)』。
蛹期がなく、幼虫から直接、成虫へと変わる『不完全変態(heterometaboly)』。
幼虫から成虫への変化がかなり少ない『無変態(without metamorphosis)』(これは実質変態しない種なのかもだが)。
主流は明らかに完全変態型である。現生する昆虫の80%くらいが完全変態型だとされるから。つまり、蛹の段階を通す事で変化がかなり大きいというのは、実質的に昆虫という種の特徴と言っていい。
そしてほぼ例外なく、幼虫と成虫は、別の生物と間違えてしまうくらいに変わる。
一部の完全変態昆虫は、幼虫期に体型の異なる複数の発育段階を経るが、これは過変態と呼ばれる現象。
不完全変態型としては、バッタ(Grasshopper)やトンボが有名。
また、不完全変態昆虫の幼虫は『苦虫(nymph)』と呼ばれる。
トンボやカゲロウ、カワゲラなどの若虫は水生で、成虫は陸生となり、変化も大きい。しかしバッタなどは、若虫と成虫の主な違いは、翅と生殖器くらいとも言われる。
無変態型は本当に少数派で、シミ(Thysanura)やイシノミ(Archaeognatha)など、翅を持たない種に多いという。
完全変態する昆虫の場合、翅芽(翅の原基)は幼虫の体の内部にあって外からみえないので、完全変態昆虫は内翅群とよばれることもある。一方で、不完全変態昆虫の場合、つまり若虫はたいてい、成長により翅が外からみえるようになるから、外翅群。
昆虫の分類。六脚類の各系統
まず、 この地球で非常に繁栄した昆虫の中でも、特にその種数が多いのが、コウチュウ類(甲虫類)。 だいたい世界中で40万種ぐらいが知られているとされていて、次に多いチョウ・ガ(鱗翅類)とハエ類も、約16万種くらいだという。
植物を含めた生物界全体においても1/4ぐらいが昆虫らしいが、この比率は、昆虫よりもさらに驚くべき多様性を持っているとも言われる、あの微生物群は考慮していない数だろう。
節足動物内における昆虫(六脚類)の系統位置については、最近は、甲殻類に近縁という説が有力らしい。
六脚類はようするに胸部に3対6本の脚を持つ節足動物のグループだが、その全てが昆虫というわけではない。
かつて、昆虫綱の伝統的な大分類として無翅類(Apterygota)と有翅類(Pterygota)、つまり、翅の有無を基準としたものがあった(獲得したことあるかどうかが重要視されていて、二次的に退化した種は有翅類)。しかし大顎と頭蓋の関節状態を基準とした、単丘亜綱(Monocodylia)、双丘亜綱(Dicondylia)という分類の方が今はより一般的とも。
昆虫でないとされる内顎綱
内顎綱(トビムシ目、カマアシムシ目、コムシ目)は、かつては昆虫綱に含まれていたが、今は分けるのが厳密とされる。内顎綱は、頭蓋と下唇が癒着して口器を包み、複眼やマルビーギ管が退化している。
トビムシ目は体長1~3ミリメートル(最大10ミリメートル)。
視覚器官は、複眼が消失するか、8個以下の眼斑とよばれる個眼。腹部が6節で、これは六脚類の中で最も少ない。
腹部腹面、第1節に常に湿った腹管というのがあり、滑らかな面の歩行時の安定や水分調節に役立つ。第4 節の跳躍器は、普段は腹面に折りたたまれ、緊急時には後方に伸ばされ、跳躍する。
気管を持たず、皮膚呼吸する。
無変態。
カマアシムシ目は体長0.5~2ミリメートル、細長い円筒形の見た目。頭部は円錐形で、複眼と単眼を欠くが、偽眼というのを持つ。触角を欠くが、代わりなのか、前脚が感覚器としてかなり発達しているようだ。
コムシ目はほぼ体長2~5ミリメートルだが、50ミリメートルの大型種も知られる。細長く、円筒状もしくは背腹方向に扁平で、体色は一般に淡く半透明。触角が数珠状で長い。複眼と単眼は欠くが、大顎と小顎が発達さている。
無変態で、生涯脱皮を繰り返す。
比較的マイナーと思われる目
イシノミ目は体長7~25ミリメートル。体型は円筒型だが、胸部が高く盛り上がる。小さい頭部で、複眼が大きい。
無変態で、生涯脱皮を繰り返す。
主に夜行性。
シミ目はたいてい10~20ミリメートルだが、1ミリメートルの微小種も、50ミリメートルの大型種もいる。
背腹方向に扁平で、多くの種が灰銀色の鱗片(と呼ばれる、ウロコ的構造)で覆われる。
複眼が小さい。
ジュズヒゲムシ目は、体長1.5~3ミリメートル。
成虫には有翅と無翅の2型。有翅でも、飛翔分散後に翅を自ら落とすが、それはシロアリやアリの女王と同様だという。
有翅型は複眼と3個の単眼を持つが、無翅型は眼を欠く。
不完全変態で、若虫は成虫と似ている。
シロアリモドキ目は、体長6~20ミリメートル。
体が細長く円筒状。単眼を欠く。口器はかみ型。
発達した脚の跗節第1節が大きく発達し、内部に絹糸腺を持ち、シルクを分泌する。
翅はオスのみだが、一部はオスも無翅。オスの尾角は左右非対称だが、これは交尾時にメスを捉えるのに役立つとも。
不完全変態で。翅が未発達だが、若虫は成虫とよく似る。
名前通りにシロアリに似ているが、特に昆虫の中で、系統的に両者が近縁という訳ではないとも(この種は、ナナフシやカワゲラに近いとされる)
ガロアムシ目は、体長14~35ミリメートル。
体はやや扁平。翅と単眼を欠く。口器はかみ型。複眼は痕跡的か退化している。
オスの交尾器は非対称で、交尾時に反転する嚢状部を持ち、メスは剣状の産卵管を持つ。
他の昆虫を捕食するし、死体も食べるようだが、飼育下では死体ばかり食べるとも。
交尾後にメスがオスを食べることもある。
現生種はマイナーだが、古生代石炭紀から中生代白亜紀にかけてけっこう繁栄したようで、化石種が多く知られる。
カカトアルキ目は21世紀になってから記載された種。化石種としてまず知られ、ベルリン自然史博物館に所蔵された標本が、その化石種と同じ種だと確認された。
体長20ミリメートル前後。糸状の長い触角。複眼は発達し、単眼は欠く。無翅。
飼育下の観察で、オスは交尾後、メスに食べられることがあるという。
ラクダムシ目は、現生種は少ないが、化石研究から、中生代にはけっこう繁栄したと考えられている。幼虫が、トビムシやシロアリを食べるという。
ヘビトンボ目もまた、絶滅した科が多いと考えられている。
大型の種が多く、開張が150ミリメートル に達するものもある。
大顎がよく発達する。前翅と後翅の大きさがほぼ同じ。
ヘビトンボ Protohermes grandisのオスは、交尾時にゼリー状の精包をメスに与える、婚姻贈呈を行うことが有名。
ネジレバネ目は、体長0.5~6ミリメートル。メスとオスで形態がかなり異なる。ほとんどのメスは無翅無脚のウジ虫状で、生涯を寄主の体内で過ごす。
オスは有翅の自由生活者。頭部は横に長い。完全変態。
すべての種が他の昆虫に内部寄生する。オス成虫は寄主を離れるが、メスはその一生を寄主の体内で過ごす。しかし例外的にシミネジレバネ科Mengenillidaeのメスは、成虫になると脚が生じて、寄主から離脱する。
シリアゲムシ目の、シリアゲムシ科とシリアゲモドキ科のオスは、腹端に大きく発達した把握器を持つ。
成虫は、細長い口吻と糸状の長い触角を持ち、前翅と後翅が膜質で細長い。
この目の多くの種で、求愛行動時にオスがメスに、栄養に富むプレゼントを渡す婚姻贈呈を行うことが有名。
ハサミムシ
体長4~30ミリメートル。大きいものは80ミリメートルに達する。
細長く、背腹に扁平。口器はかみ型。単眼を持たない。
前翅に翅脈がみられず、革質化して短い。後翅は膜質で、肛部が扇上に大きく発達し、不明瞭な翅脈が放射状に配列される。
不完全変態。翅が未発達だが、若虫は成虫とよく似た形態をしている。
湿った場所を好む。夜行性で、日中は土壌中や樹皮下などに潜む。
特徴的な尾鋏(尾のハサミ)は、闘争や交尾などいろいろ利用される。
交尾後、メスは腹部に精包をつけたまましばらく活動する。メスは卵と幼虫を保護し、若虫はある程度育つと、メス親の体を食べる。
カワゲラ
体長4~50ミリメートル。
背腹に扁平で、柔らかい。頭部が幅広く三角状。触角が細長い。複眼がよく発達している。
オスが外部生殖器を持たないが、肛上板が補助的な交接器官として機能する。メスは産卵管を欠く。
不完全変態。若虫は成虫と似てるが、気管鰓があり、翅が未発達。
一般的に溶存酸素の多い冷たい水を好むので、水場の水質評価における指標生物。
カゲロウ
大分類として、ヒラタカゲロウ亜目とマダラカゲロウ亜目のがある。
成虫の体長が2~30ミリメートル。
不完全変態。
亜成虫(subimago)という生育ステージが知られる。亜成虫は、2対の翅を持ち陸上に生きるが、成虫より色が暗いとも。亜成虫が脱皮すると、普通の成虫となる。
成虫は口器が退化していて、摂食ができない。
成虫が短命であることがかなり有名で、確かにヒメカゲロウなどは羽化してから数時間で死ぬらしいが、ヒラタカゲロウでは1週間生きた記録もあるようだ。
トンボ
前翅と後翅の形がほぼ同形で、腹部が細長い。
大分類として、イトトンボ亜目とトンボ亜目がある。
イトトンボは、オス成虫腹部末端の付属器が上下に各2本ある。
トンボは、後翅の基部が幅広く、前翅と後翅の形が異型、オス成虫腹部末端の付属器が上に2本、下に1本ある。
中間的な特徴(前、後翅が同形で、付属器が上2本、下1本)のムカシトンボ類は、トンボ亜目に含まれる説が有力らしい。
成虫の口器が、大顎が発達したかみ型。
また、オスは腹部末端の交尾器の構造のため、交尾の形がハート型みたいとも。
幼虫はほとんど淡水または汽水域で水生生活する。
バッタ
大分類として、キリギリス亜目とバッタ亜目がある。
キリギリスは、触角が長く、右の前翅をこすって発音する。バッタは、触角が短く、前翅と、後脚と後翅をこすり合わせて発音する。
つまりバッタ目は、鳴き声を出す昆虫として有名。
普通、声は生殖などと関係していて、オスが出すとされているが、一部メスも音を出す種が確認されている。
聴覚器官は、キリギリス類は前脚の脛節、バッタ類は胸部側面にある。
キリギリス類であり、肉食で知られるコロギス科は前翅に発音器を持たず、後脛節を地面などに素早く打ちつけて打音を奏でるという。
同じくキリギリス系のコオロギ科は、オスが右前翅を上にして発音し、聴覚器官は前脚の脛節にのみ存在。
多くの種は、生息環境に隠蔽しやすい色彩をしている。
ナナフシ
体長35~350ミリメートル。棒状で細長いナナフシ系と、扁平か肉厚で葉状のコノハムシ系が知られる。
頭部が小さく、単眼は欠くものが多いが、有翅型ではみられもする。
前翅がやや革質化していて、飛翔には後翅が使われる。
翅を欠く種が多く、メスに限るならほぼ無翅。
不完全変態で、未発達な翅以外、若虫と成虫は似る。
たいてい植物そっくりで、紛れているとかなりわかりにくい。いわゆる擬態をする昆虫の代表格。
両性生殖が基本だが、単為生殖する種もいる。
カマキリ
大型の肉食昆虫で、特に交尾後に、メスがオスを食ってしまうというのが有名であろう。しかし、オスがうまく逃げる場合もあるようだ。
前脚は鎌状で、これは獲物の捕獲用とされる。複眼がよく発達し、口器はかみ型。
普通は有翅だが、種によって短翅や無翅のもいる。
オスの交尾器が左右非対称で、メスの産卵器は短く、腹部に隠れている場合が多い。
通常、カマキリはゴキブリ目に近縁と考えられている。
ゴキブリ
人の家の中で見るような害虫のゴキブリは、大量に存在する ゴキブリ類のごくごく一部である。
シロアリは、今は同じゴキブリ類として扱われるが、昔は単独の目として扱われていたという。
成虫は、体が小判形で扁平。頭部が小さく、触角が長い。複眼が発達し、口器がかみ型。
発達した前胸背板が頭部を覆っていることが多い。胸脚は走行に適し、各脚は同じような構造。
前翅は革質化していて、革翅とよばれる。
ほとんどの種は森林に生息する。
 「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
シロアリ類は真社会性、つまり生殖女王と非繁殖個体の兵隊などのカーストを含む、 1つの巨大な存在として機能するような つながりの深い社会を形成する。
他のゴキブリに関しても、そうした社会性に近いものは獲得している、と考える向きもある。
カジリムシ
大分類として、自由生活するチャタテムシ系と、寄生性のシラミとハジラミ系がある。これらも昔は、別の種として扱われていたという。
いずれにしろ不完全変態。
チャタテムシ類の頭部は比較的大きく、複眼が発達している。単眼は、有翅の種では3個、無翅の種では欠く。
ハジラミ類とシラミ類の複眼は、縮小してるか欠如している。ハジラミ類の口器はかみ型だが、シラミ類の口器は吸汁型。
シラミ類は、哺乳類の血液を吸う外部寄生者で、寄主をかなり選り好みするようだが、ハジラミ類は適当な種も多いとされる。
アザミウマ
大分類としてアザミウマ亜目とクダアザミウマ亜日がある。
小さめで、成虫の体長は1~2ミリメートルばかり。口器は、大顎と 小顎が針状に細長く変化した吸汁式。翅は前後ともに細長く、翅脈は退化し膜になっている。翅の周縁には多数の長い毛が生えている。
不完全変態のカメムシ目と近縁なようだが、この種は完全変態。しかし蛹期が、やや不完全変態的で、つまり摂食しないが、動き回れる。
オスメスともに卵塊の保護的随伴行動を行うことが有名である。特にオスが随伴行動を行うことは昆虫ではかなり珍しい。
しかしオスは、メスが再産卵に訪れた場合に反応がよく、少なくともオス的には交尾戦略という説が有力。
カメムシ
カメムシは不完全変態の種の中では、多様性が最大の種とされている。世界中で約145科10万種以上知られる。
最大の特徴は口器の形態。大顎と小顎が合わさって細長い中空の針状構造となり、鞘状の下唇に覆われている。さらに口吻に2種類の中空構造があり、1つは唾液を抽出し、もう1つは液体状の餌を吸汁するの使われる。
祖先的な摂食様式は、植物からの吸汁であるという説が有力。
発達した唾液腺に、吸汁した液体を効率よく吸収するのに特化した消化管がかなり普遍的なようだ。
また、大量の師管液を吸汁するアブラムシ類は甘露を排泄し、アリと共生する例も知られる。
アミメカゲロウ
ヘビトンボ目に近縁な種とされる。
大顎が発達し、獲物にかみつき、体液のみを吸収する。
前翅と後翅の大きさはほぼ同じで、網目状の翅脈相となっている。
成虫だけでなく、卵、幼虫の形態が特徴的とされる。
クサカゲロウ類は糸状の柄の先に卵を産み、その卵が十数個くらいまとまっている卵塊は「ウドンゲの花」とよばれる。
またアリジゴク (蟻地獄)ともよばれるウスバカゲロウ類の一部の幼虫は、砂にすり鉢状の穴を掘り、餌が落ちてくるのを待ち伏せする。
カゲロウの名がついているものの、成虫は数週間は生きるようだ。
コウチュウ
一部の巨大種、ヘラクレスオオカブトムシDynastes herculesやタイタンオオウスバカミキリTitanus giganteus、それにもちろん日本のカブトムシがよく知られる。
 「カブトムシ」生態と不思議。集合する幼虫とサナギ
「カブトムシ」生態と不思議。集合する幼虫とサナギ
形態は多様だが、一般によく硬化した強固な外骨格を有する。特にゾウムシや、一部のゴミムシダマシなどでは外骨格が非常に硬い。しかしホタルなど、けっこう柔らかい種もいる。
複眼はよく発達するが、洞窟や土中に生息する種では退化、消失している。
口器はかみ型、大顎が発達する。前胸が大きく、中胸、後胸、腹部が密着して一体化する。前翅は角質化し翅脈がほぼない。
完全変態。幼虫は普通、頭蓋が固い。幼虫期を水中で過ごす種には、気管鰓のような特殊な呼吸器官がみられる。
寄生性や社会性を発達させた種が少ない。
ハエ
最大の特徴は、後翅が平均棍(飛翔機能が退化、変化した可動器官)に変化していること。慣習的に多等節の触角と主に3~4節の小顎鬚を持つカ亜目と、不等節の触角と1~2節の小顎鬚を持つハエ亜目に大別される。
害虫としてではあるが、カもハエも人間には馴染み深いと思われる。
キイロショウジョウバエは、遺伝子研究などのモデル生物として有名。
カは細長い体に長い脚、ハエはがっしりした体に短い脚を持つものが多い。
口器は吸う口か、あるいは舐める口だが、成虫期に摂食しないものでは退化縮小する。
幼虫は脚を持たない。
ノミ
この目もまた、寄生生物としてではあるが、馴染み深いのでなかろうか。哺乳類や鳥類に外部寄生し、吸血するが、特化した独特の形態と生態を有する、
二次的に翅を退化させていると考えられている。体が左右に扁平で、跳躍に適した発達した後脚を持ち、体長の100倍の高さまで跳ねることもできる。
腹部第9節の背面に20~40本ほどの感覚毛のある盤状の感覚器があり、動物の体から発散する二酸化炭素を感知し、寄主を認知する。
寄主特異性はさほど高くないという。例えばヒトノミPurex irritansも、人間だけでなく、他の哺乳類や鳥類も吸血する。
トビケラ
シマトビケラ上科とナガレトビケラ上科(とトビケラ上科)に大別される。
成虫が翅や体が毛で覆われ、原始的なガのようとも。止まるときは翅を屋根型にたたむ。
大顎が退化してるのが多い。かみ型の口器は特化し、下唇が下咽頭と融合して液状の食べ物を摂取しやすい吸器を形成する。
卵が球形か円形で、水中の石の表面などに並べて産みつける平面卵塊と、ゼラチン状の物質の中に多数の卵が入ったゼラチン卵塊が知られる。幼虫はほとんど淡水に生息する。
チョウ、ガ
チョウ目の特徴と言えば、やはり翅や体を覆う『鱗粉』。この名前通りに粉みたいな、平たくなった体毛か、あるいはウロコ的なものである。
翅が2対で、原始的なコバネガ科以外は、特に形状が多様。
トビケラに近縁とされ、鱗粉は毛が変化したものと考えられている。
ストロー状の口吻 (吸管)もまた特徴的。これは小顎の外葉が変化したものとされる。ただし、コバネガ類などは、口吻でなく、かみつく大顎。
チョウの大グループである二門類Ditrysiaは、メスの生殖器が交尾口と産卵口に分かれ、交尾口から注入された精子が受精管を通じて総輪卵管へ移動して受精する。
しかし二門類以外で、特に原始的とされる種グループは、交尾口と産卵口、さらに消化管の末端も合一した総排出口生殖器(単門式)。
ハチ
腹部第1節と第2節の間で強くくびれるもの(細腰亜目)と、くびれが微妙なもの(広腰亜目) に大別される。
複眼が発達し、口器はかみ型。前翅が後翅より大きいが、翅はよく退化もする。
細腰亜目の祖先はおそらく寄生蜂で、くびれにより、後休節の運動性が高まり、寄生や産卵行動に特化したと考えられる。
産卵管の構造や機能が多様だが、広腰亜目ではのこぎり状になっていて、産卵基質である植物を切り裂ける。さらに有剣下目では獲物の麻酔とか護身用毒針としても機能する。
コウチュウの次くらい、チョウと同じくらいに多様な種とされるが、特に寄生とか真社会性とか、特殊な生き方が有名。
昆虫の起源
最古の昆虫(?)リニオグナタ
かなり微妙だが、昆虫は、最初に陸上に進出した生物の可能性もある。
発見されている最古の昆虫であるリニオグナタ・ヒルスティ(Rhyniognatha hirsti)は、デボン紀(4億1600万年前~3億5920万)初期の地層から見つかっている。
リニオグナタは陸上生物だから、昆虫は陸上で誕生したか、より古い水生昆虫はもっと以前に存在したかのいずれかと考えられる。
発見されている頭部化石は、デボン紀初期の堆積物であるRhynie Chert(リィニー・チャート)の破片に保存されていた。それは最初、1926年に、トビムシ目のリニエラ・プラエクルソル(Rhyniella praecursor)として報告されている。トビムシは、六脚類グループだが、正確にはあくまで昆虫ではない。
しかし昆虫学者のロビン・J・ティルヤードRobin J. Tillyardが、1928年に、リニエラとされたその化石の中に混じる別の化石に気づく。それは昆虫化石で、リニオグナタと改名された訳である。
飛行能力の獲得
飛ぶ、という技術を最初にものにした生物は昆虫だと考えられている。
2004年、 マイケル・S・エンゲルとデイビッド・グリマルディの2人は、リニオグナタが、飛行性の昆虫に非常に近い特徴を持っていると発表した(実はこの生物が記載されたばかりの頃にも、そういう指摘はあったようだが、無視されていたという)
つまりリニオグナタは、すでに飛んでいた可能性がある。
ほぼ確実に翅を持っていた昆虫化石で、最古のものはデボン紀後期のストルディエラ・デボニカ(Strudiella devonica)という種で、原始的な口の形質が、雑食生であった事を示しているという。
いずれにしても、昆虫がいつからか手にいれた、この素晴らしい技は、まず間違いなく昆虫の大繁栄の原因のひとつであろう。
また、分子遺伝学的な解析結果が、昆虫の翅の獲得は、これまでにたった一度だけ起こった進化である事を示唆しているらしい。
巨大トンボ、メガネウラ
石炭紀(3億5920万年前~2億9900万年前)の地層からは、開張(羽を広げた場合の大きさ)が60cmほどもある、巨大トンボ(dragonfly)のメガネウラ(Meganeura)や、ゴキブリ(cockroach)の化石も発見されている。
メガネウラは、史上最大の昆虫であり、史上最大の飛翔性節足動物でもある。異常に大きいトンボだが、この時代の昆虫は基本、現生種より大きかったのかもしれない。
他、カブトムシやクワガタが属する甲虫(beetle)はペルム紀(2億9,900万年前~約2億5,100万年前)。
蝶(butterfly)や蛾(moth)、ハチ(bee)、ハエ(fly)は、三畳紀(2億5100万年前~1億9960万年前)に出現したと考えられている。
現生する昆虫の目(哺乳類で言うなら霊長類とか、食肉類とかの分類)は、全て白亜紀(1億4500万年前~6600万年前)末の大絶滅を乗り越えた種である。
昆虫と植物
被子植物のような高等植物が多様化を始めるのは恐竜が滅んだ約6500万年前といわれている。そして以降、昆虫は植物との間に、花粉の媒介など、密接な関係を持つようになり、双方の多様化も進んだとされている。
また、アリなどの、一般的に強力とされている昆虫と、特定の植物の間には、植物が体内を住処として提供し、アリが防衛などを行う、というような関係もある。
植物が先か、動物が先か
陸上植物は光合成をする緑藻類から進化し、苔類や蘚類といった維管束のない植物がシルル紀の前後にまず出現したあとに、シダなどの原始的な維管束植物が出現したとされる。さらに、伝統的には植物が先に陸上に現れ、陸に新しい環境を作って、そこに動物たちが後から現れた、という流れが一般的(この物語を支持する大きな理由としてよく言われるのが、陸上動物には普通、酸素が必要である事実。もちろん酸素を大気中に増やしたのは陸上に進出した植物)
一方で、実は陸上生物としては、節足動物が植物より優れているという見方がある。硬い外骨格という構造がまず強い。また、動けるので、例えばちゃんとオゾン層が形成されていない時代でも、有害な太陽光が眩しい日中は避けて、夜だけ陸に上がるというような行動も可能だったと思われる。
潜孔とゴール
昆虫には、主に幼虫が葉に潜る習性を持つものが知られ、「潜葉性昆虫」 とか「絵かき虫」 とよばれる(主にチョウ目、ハエ目、コウチュウ目、ハチ目の種)。
幼虫が潜った跡は『潜孔(mine)』とよばれ、それぞれの種やグループで特徴的である場合が多い。
潜孔は、幼虫が葉内部をどう食べ進むか、葉のどの組織を食べるか、潜孔内に糞を残すかどうか、糞を残すとしてどんな糞かなどによって、種ごとに特徴的となる。
しかしなぜ葉に潜るのか。
普通は、菌類やバクテリア、ウイルスに感染対策とか、潜孔内部の微気象が温度や湿度的に安定してるからと考えられる。もちろん、捕食者などから身を守るためにも役立つかもしれない。
では、昆虫がつくる潜孔に、種ごとの様々なパターンに意味はあるだろうか。
潜孔バターンに影響を与える要因としては、例えば「糞処理仮説」がある。つまり、幼虫が糞をどこに排出するかが潜孔の形を決めるというもの。また、寄生蜂の寄生から逃れるために、複雑な潜孔パターンを利用しているという説などある。
また、ゴール (gall)と呼ばれるものがある。昆虫が出す何らかの刺激により、植物体の一部を変形(あるいは植物細胞を外部から調整)させたもの(たいていコブみたいなもの)。
ゴールは、普通は、注入された唾液とかの分泌物により形成されると考えられている。
しかし分泌物と、植物とのどんな相互作用がゴールを形成するのか、謎が多い。
タマバチでは、共生しているウイルスがゴールを形成する説がある。つまりこの場合、タマバチ自体は形成者(ウイルス)の媒介にすぎない。
 「植物細胞」構造の特徴。葉緑体、細胞壁、大きな液胞、
「植物細胞」構造の特徴。葉緑体、細胞壁、大きな液胞、 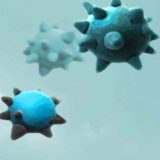 「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
ゴールの中に昆虫がいても、それが形成者とは限らない。形成者以外に、寄生者や同居者、再利用者や捕食者などの場合もあるから。
ゴールは、昆虫にとって有用なのは、ほぼ間違いない(例えば、栄養の効率よい蓄積や、やはり安定した環境、天敵への防御)。しかし、植物側にも何か利益があるのか、という議論がある。
ただ、一般的には、これは昆虫の、植物に対する寄生的な関係だと考えられている。
花粉を運ぶ昆虫と花の共生
多くの昆虫が、被子植物の花を訪れる。そして昆虫は植物から蜜などの報酬を得る代わりに、花粉を運ぶことで植物の繁殖を助ける。
この有名な共生関係について、やはり特に注目すべきは、ある植物に完全に適応して、一方である昆虫に完全に適応した植物という一対一の関係になっているパターンであろう。それは『絶対送粉共生系(obligate pollination mutualism)とよばれるものだ。
イチジクとイチジクコバチ、ユッカとユッカガ、カンコノキとハナホソガなど。
それらはもう、深い共生関係とか、依存関係とかいうよりも、まとめて1つのシステム的関係と言っていいのかもしれない。
イチジク類は、雌花が開花する時期(メス性期)と、雄花が開花する時期(オス性期)がずれている。花粉をつけたイチジクコバチ類のメスは、メス性期にイチジクに飛来し、花嚢に潜り込んで授粉し、さらに雌花に産卵。
卵の産まれた雌花はゴールとなり、幼虫はそこで育つ。さらにイチジクには花柱の短い雌花と、花柱の長い雌花があり、イチジクコバチは花柱の短い雌花だけに産卵可能。一方で、花柱の長い雌花は種子を生産する。雄花が開花するオス性期に虫こぶからオス・メスともに羽化し、交尾後に、オスは花嚢の中で死亡する。
ユッカガ類の各種は、ユッカ類の決まった各種の花粉を媒介するとも。
メスのユッカガは、ユッカの雌花の子房に産卵後、メスのみの特殊な口器(小顎の触肢) を使い、授粉し、孵化した幼虫はユッカの種子を食べる。
ユッカを寄主植物とし、幼虫もユッカの花茎や果実などを食べるが、特殊な口器がなく、受粉はしない、ニセユッカガなる詐欺師的な種も知られている。
コミカンソウ科のカンコノキ属Glochidionとホソガ科のハナホソガ属Epicephalaの一対一関係は、21世紀になってから発見されたもので、習性的にはユッカガがと似ているらしい。
昆虫は昆虫に寄生する
普通、寄生というのは、生物がその栄養分を他の生物から取り、特に宿主側にはメリットのないようなもの。似たような意味の言葉として、片利共生というのもあるが、違いはけっこう曖昧。それは世界をどう考えるかによるかもしれない。
基本的には、片利共生は、共生している片方の種だけが利益を得ている関係。寄生は生理的な繋がり、その宿主(寄主)というエネルギー体が、活動によって高めた自身のエネルギーを奪い取るというような。
ある生物(寄主)上で生活環の一部があり、その終わりに寄主を殺す場合を『捕食寄生(parasitoid)』。傷つけはするが寄主を死なす訳ではないものが単に寄生、あるいは真の寄生とされる。
ただ、一般的には捕食寄生者の発育は1匹の寄主のみで完了する。したがって、捕食寄生者が複数の寄主を殺すことはない。
寄生昆虫は、昆虫に寄生する場合が多いのが特徴とも言われるが。地球上で昆虫がそもそも圧倒的に多いのだから、それも当前なのかもしれない。
いつ空を飛んだのか
昆虫は、イシノミやシミなどの一部(一般に原始的だとされる)グループを除いて、基本的に4枚 (2対) の翅を持っている。 翅を持つ昆虫 (有翅昆虫) の化石は石炭紀などから出ているが、その起源はデボン紀にさかのぼるとされる。
翅の起源には、有名なものとして、側背板仮説と鰓仮説がある。
側背板仮説は、古生代の石炭紀などに繁栄したムカシアミバネ目の化石には、前胸の側面に翅のような張り出しがあり、このような器官が翅へ変化したとする説である。
一方、鰓仮説は、昆虫が陸上から水中へ進出した際に発達した呼吸の補助器官(鰓)が、空中を飛ぶための翅に変化したとする説である。
翅の獲得は、分子系統樹の研究から、1回の進化的変化によるものという説が有力。
しかしどのように獲得したのかはともかく、なぜ羽を必要としたのか(というより、それが多くの種に広がるほど有効だったのか)。
まず、発達した植物の胞子や種子、軟らかい光合成組織を食べるためという説がある。つまり高いところにある植物組織を食べたいから、空を飛ぶようになったというもの。実際のところ、植物組織はたいてい落ちてくると思われるが、早い者勝ちな競争が起きてたりしたのだろうか。
あるいは、もともと翅は温度調整に使われていたという説もある。現在の昆虫でもそのような使われ方は結構一般的なようだが、空を飛ぶための翅というよりは、体温調節のための広い膜とする方が、確かに、それのない生物が進化で獲得した流れを想像しやすいと思う。




