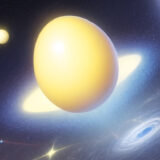ダーウィンにとっても古い説
ダーウィンはその著書『種の起源』のなかで、おそらく自身の進化論的世界観と対立すると思われた創造論的世界観を、複数回否定している。そのような文のうちの、特に感情的な印象の1つは以下のようなものだ。
 種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
「ウマ属各種は個々に創造されたと信じる人たちが主張することなんて簡単に予想できる。通常、個々の種に同じ属の他種と同じような縞模様が現れるのは、こういう変異の傾向を持つような存在として創造されているためと言うのだろう。それに個々の種は、世界の離れた場所に住む種と交雑すると、自分の親と同じ毛色でなく、同属の他種と同じ縞模様に似た雑種を生む強い傾向を示すよう創造されているとも。私から見れば、こんな意見受け入れるのは、非現実的原因、少なくとも未知の原因を受け入れるために、真の原因を拒絶することだ。それは神の御業を単なる模倣や欺きにしてしまうことだ。それくらいならむしろ、昔の無知な宇宙創生論者たちのように、貝の化石はかつて生きていた貝の遺骸ではなく、現代の海に生息する貝を模倣した石が創造されたものだと信じるほうがましだ」
今注目したいのは、「それくらいなら」より後。
ダーウィンはその前に、(おそらく)遺伝に関する問題を創造論で無理やり説明することは愚かなこととする。そしてそんなのよりは、その問題について無知な者が、無知なりに(その誰かよりいくらかは、それに関する知識のある者からすると)提案する妙な理論の方がまだよいとする訳である。創造という現象があるとして、ややこしい設定よりは、単純な設定の方がまだ信じやすいというような考えもあったろうか。
それはともかくとして、ダーウィンは明らかに、「化石が生物を模倣した(またはされた。そのように創造された)石」という説を、(主に生物学、地質学的なものだろう)現代の知見的に、もう真面目に考えれるようなものでもない古い説として持ち出している。
現在では、化石というものが、昔に生きていた生物の痕跡だということは、ダーウィンの時代より、もっと広く一般に知られているだろう。だが、そもそもなぜ化石は生物の痕跡と考えられるようになったのか? そしてそのような考え方が普通になる以前の時代、人々は化石(明らかに人に描かれた訳でもない、まるで自然に刻まれた生物の(たいていは部分的な)画)に何を見いだしていたろうか。
古代ギリシャの哲学者たちの化石研究
そもそも一般的に、化石が古生物の痕跡と認識されるようになったのは、ここ数百年くらいの話と考えられているが、本当にそうなのだろうか。
もちろん石化しているとはいえ、これはたいてい生物の骨なのだから、そのまま朽ち果てた生物の骨だと想像されることはあったと思う。龍とかドラゴンといった生物は、恐竜の化石から連想されたのでないかと推測する向きも結構ある。だが重要な事として、もう1つ、ここ数百年でようやく一般的に認識されたとよく言われている概念がある。それはつまり「生物の絶滅」である。
 「東洋の龍」特徴、種類、一覧。中国の伝説の最も強き神獣
「東洋の龍」特徴、種類、一覧。中国の伝説の最も強き神獣  「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
ようするに普通は、これまで、ほんの数百年前まで、化石という痕跡だけ残している絶滅動物がかつて大量に存在していた、というような現代的な地球世界観は、あったとしてもかなりマイナーだったのだとされている訳だ。
アリストテレスに不足していたもの
紀元前4世紀ぐらいのギリシャ。類まれな哲学者アリストテレスの興味は、非常に広い範囲に及んでいたが、少なくとも彼が最も得意としていたのは生物学であったと考えられている。
だが彼は、彼なりの変異や遺伝の理論(と解釈できそうな発想)まで提案しながら、ついに進化理論を思いつくことはなかったらしい。
アリストテレスには、それまでの人たちが集めた生物学の話の様々な証拠がまず不足していた。神話とか伝説とかでも、信頼できそうな話のみをピックアップして参考にしたりもした。そうするしかなかったわけである(だからこそ彼は、生物学の創始者と呼ばれることもある)
アリストテレスの時代において、明らかに不足していた証拠の1つこそ化石記録。
この時代にはまた、大陸移動説などもなかったろうから、ある生物の乏しい地域でも「かつては違う環境で、もっと様々な生物が生きていた」というような可能性を思いつくことも困難だったろう。古生物学や地質学で重要な、お互いに関わり合う概念(化石、絶滅、変異、大陸移動や形成など)のどれも、アリストテレスの時代には(あったとしても)たくさんの適当な説のひとつだったのだ。
 「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
ただそれをどのように考えたにしろ(そしてその考えたであろうことは記録に残っていないが)、彼はおそらく、化石を見たこともないわけではなかったろう。
単に大した興味がなかった可能性もある。砂漠や山で貝が見つかったと報告を受けただけでは、怪しい類の話と考えたのかもしれない。
アリストテレスはまた「気象学」の中で「oryktos」について語った。このoryktosというのは、英語の「fossil(化石)」の語源であるラテン語の「fossile」を、訳としてあてた語。しかし「oryktos(fossile)」は元々、「掘り出されたもの」というような意味で、(現代的な)化石の意味でこの語が使われだしたのは近代のこと。
 「アリストテレスの形而上学」第一原因を探求。哲学者の偉大なる挑戦
「アリストテレスの形而上学」第一原因を探求。哲学者の偉大なる挑戦
大地の動きと、太古の怪物
そもそもアリストテレスが、『ピュシオロゴイ(physiologoi。自然について語る者)』などと呼んだ、彼以前の自然哲学者たちにも、動物を思わせる石質を調べた記録があるという。
紀元前6世紀頃の(おそらく、万物の構成要素要素を「土」と提案したことがある)クセノパネス(Xenophanes)は、山の上の方でも、時たま(まず化石だろう)岩に埋めこまれた貝が見つかると報告した。
クセノパネスは、貝殻を作る陸の生物というものを想像することもできたかもしれないが、彼は人間が知らないのは隠れた生物種でなく、大地の動きだと考えたらしい。ようするに彼は、山がかつて水没していたのかもしれないと推測した。
紀元前5世紀頃の、リュディアのクサントスも、陸上の岩の貝を(おそらくいくつも)発見し、いくつかの島はかつて海底に存在していたのかもしれないと考えたとされる。
彼らの他にも、(アリストテレスの後の者たちも含めて)多くの哲学者が、山や砂漠で発見される貝に頭を悩ませ、たいてい最終的に、陸地のいくらかはかつて海に沈んでいたという結論に達したが、その原因に関しては全く意見の一致を見なかった(紀元後、聖書の物語が広く受けられるようになると、長きにわたって洪水伝説が一般的な説明となった)
貝だけでなく、大型動物の化石に関しても、例えば特定の神を信仰する教団の神殿などに飾られていたことを思わせる、地方記録などもあるらしい。
例えばサモス島には古代に、ネアデス(Neades)なる巨大生物が生息していたという伝説があって、この地震を引き起こす咆哮を発するという怪物の正体は、恐竜の化石という説がある。
紀元前七世紀の祭壇近くで掘り出された骨は、どうも絶滅したキリン科のサモテリウム(Samotherium)のものだったとか。
レスボスの化石の森
アリストテレスの弟子で、よき友人であったとされる(そして「動物学の祖」と呼ばれる師に対して、「植物学の祖」と呼ばれている)テオプラストスは、「植物原因論」の中で、インド洋の海岸の「石化した(おそらく)植物」について述べているともされるが、それ以外に「石化したもの」をテーマにした本も書いていたらしい(現存していないし、燃えやすい石についての本だった可能性もある)。
レスボス島は、2000万年前くらいに火山活動によって形成された化石の森があることで有名だが、アリストテレスもテオプラストスも、この島で暮らしていた時期がある。テオプラストスは、その化石の森に関して書いていたのでないかという説もある。
また、いくらか残っている(とされる)テオプラストスの生物石に関しての見解はまちまちなようで、化石の魚を動物の残骸とみなす一方で、例えばゾウのものと思われる骨を地球の創造物と見なし、化石の魚を実際の動物の残骸と見なした節があるという。
子宮石を巡る論争
コペルニクス(Nicolaus Copernicus。1473~1543)の地動説が大きな影響を残すことになった16世紀のヨーロッパ。化石、その起源に関して、様々な伝説が普通に語られていた時代。
鉱物学者、生物学者の間で、『子宮石(hysterical stones)』というのが知られていたという。
腕足動物の雌型
子宮石の正体は、主に、ある種の腕足動物(見た目が軟体動物の二枚貝に似た種の多いが、それらとは独立した門を形成するグループ)の、殻の内部で形成された『雌型(mold)』の化石だったとされる。
化石は堆積物で埋まった生物の遺骸が、痕跡として残ったものであるが、普通、(特に遺骸と堆積物の型の一致率が高い場合に)遺骸を埋めた堆積物に型どられた形を雌型、生物遺骸の本体の(もちろん元の生体部分が文字通りそのまま保存されていることなんて、かなりないが)形を『雄型(cast)』という。
雄型はさらに、体内部に空間のある生物の,外側の型と、内側の型とを『外形雄型』、『内形雄型』と分けることがある。また雌型があるなら、石膏を流し込んで固めて、『石膏雄型』を造れる。
子宮石は、基本的に内形雄型。腕足動物は、二枚貝と同じような2枚の殻を形成するが、閉じた殻の中に石膏を流し込めば、雌型は殻の凸面の度合いに応じた扁平度をもつ(ようするにちょっと平べったい)球形となるが、かつて、特定グループのそれが、見る人に女性器を思わせたらしい。また、ある種の、(それ自体が化石化することはほぼないとされる)摂食用の骨格を内部に収納するための筒状の溝の雌型が、男性器の突起を連想させることもあった。
子宮石が腕足動物の型であることは、18世紀頃には、もうかなり、生物学者の間で一般的であったようだが、 16世紀には、それは(そもそもそれが生物の痕跡であるという話自体)仮説の1つでしかなかった。
それはまだ、岩石の有する特殊な力により変質、形成された(生物の関与していない)生物型という仮説。あるいは、さまざまな古代の聖なる動物が発生させた、人の性的要素と関連する特異的な物質というような説とかと比べ、扱い的に大差なかったかもしれない。
博物誌から、掘り出されたものの研究へ
ローマ時代の博物学者、大プリニウスが書いた博物学の書は、(おそらくアジアより遅れて)ヨーロッパで活版印刷術が(15世紀中頃に)発明されてから、数十年ほど経った頃には、いくつも失われたのだろう古代人の研究を(時代はまさに、そのような古代の知恵の再発見を目指したルネサンス期であったから)参考にしようとしていた博物学者たちの間に、かなり普及していた。そうした研究者たちの中にゲオルギウス・アグリコラ(Georgius Agricola。1494~1555)とコンラート・ゲスナー(Conrad Gesner。1516~1565)がいた。
まず、博物学者の仕事は、手元の標本を、『博物誌』で言及されている(はずの)カテゴリーに帰属させる作業。『博物誌』の最終巻(37巻)、ある鉱物に関して「二形、白と黒、男と女という特徴を有する」という項目があり、これこそ子宮石に関する最初の言及でないかと考えられることになる。注目すべきは、男と女の二形という表現。つまり、時に男性器、時に女性器の石(つまり子宮石)のことと推測されるのは、奇妙なことではない。
アグリコラは、フォッシリウムというのを「掘り出されるもの」の意味としてタイトルに用いた『デ・ナチュラ・フォッシリウム(De Natura Fossilium)』を1546年に出版。これを世界最初の古生物学研究書とする人もいる。
著作で、プリニウスの記述を取り上げたアグリコラは、エーレンブライトシュタインの要塞付近で発見された化石の一部をディファイエス(二形)と命名した。
そして後、1565年、ゲスナーが著作で、プリニウスの二形石と、アグリコラの化石をあらためて関連づけて、それらをまとめて「子宮石」と総称した。そしてこの名は定着し、それが腕足動物の雌型化石であることが完全に認知されるまで、使い続けられることになる。
俗的な代物でもあったか
子宮石の図版をはじめて出版物で公表したのは、オラウス・ウォルム(Ole Worm。1588~1654)のようだが、彼はそれに関して、「その形状が女性器と似ているための名称」と紹介した。
現在のような写真とか動画などがないのはもちろん、禁欲的な考え方が現在よりもずっと一般的だったかもしれない社会において、そこに(当時なりの)性的願望のはけ口を想像する向きもある(もし本当にそうなら、根底にあるのは、現代で、普通には18歳未満に禁止されているような性的演出を一般作品などに紛れ込ませたりする理由と近いのかもしれない)
最初に分類された時
フォッシルが、掘り出されたもの全てでなく、ただ「化石」という意味で使われるのが普通になったのは、ようやく19世紀以降のこととされる。
しかし18世紀には、とにもかくにも、単なる岩石と、生物のただの遺骸と、動物や植物(たいていはそれらの一部の器官)に似ている「岩石中のもの」は別個のカテゴリーとして認識されるようになっていた。
1つの説として、鉱物界という領域に、他の界(おそらく生物界ではなく、動物界と植物界)の影響により現れたものがあり、それを『外来化石』、そうでない普通の鉱物は『内在化石』とするような発想もあったという。
子宮石がほぼ確実に生物の痕跡であろうと考えられるようになってからも、それがどのような生物に由来するものなのかということで論争があった。
つまり、そもそもこれは生物の雌型なのか、あるいは、何らか生物の本体か、備えていた器官なのか。当然いくつもの、適当なんだか、実は深く考えてるんだかわからないような大量の仮説が提唱されたことは、想像に難くないだろう。実際にそうだった。ただ、これが生物の痕跡という考えが合意に達してから、それが植物なのか動物なのかという(最初にまずくるだろう)問題に関しては、わりとすぐに決着がついたという。その正体はともかくとして、それが動物らしいことは、当時の専門家の目にも明らかだったようだ
最後まで対立していた2つの意見は、正しい答(腕足動物の雌型)と、現在でも素人は間違えてしまうかもしれない罠(子宮石は二枚貝)。そして、論争に終止符を打ったのは、ただ普通に観察。
たいてい深海生物で、浅瀬の種でも暗い隙間を好むのが多い腕足動物の、生きた状態での観察は難しい。一方で化石の方も、殻の内側を調べれる物は珍しい。しかし、決して不可能ではなかったろうし、どうにか腕足動物の殻の内部を調べれたなら、問題は解決した。
分類学の父として有名なカール・フォン・リンネ(Carl von Linné。1707~1778)も、コレクションカタログに、子宮石がある時、それを他の腕足動物類と一緒に並べたという。以前は人間の性器との類似性から神秘的なものと推測されることすらあった子宮石だが、リンネが彼流の(つまりほぼ現代流の)分類学を始めた頃から、それはすでに生物学的に正しく分類されていたわけである。
山猫アカデミーの化石樹
たった四人で始めた科学の結社
フェデリコ・チェシ(Federico Angelo Cesi。1585~1630)なるイタリアの貴族が設立した「山猫アカデミー(アッカデミア・デイ・リンチェイ。Accademia(Nazionale)dei Lincei。オオヤマネコ学会)」は、近世のヨーロッパにおける(少なくとも影響力の強かった)最初期の科学アカデミーとされる(その名は、古くから、鋭い視覚能力を持つとよく語られていたオオヤマネコにちなむ。実際オオヤマネコは視力がよいとされるが、この頃は、プルタルコスなどが伝えていたとされる、非常に鋭い眼光で、見えないものすら見ることができるというような伝説がまだ一般的であったらしい)。
設立年は1603年説が有力らしいから、チェシはまだ10代と若く、学会の初期メンバーの中でも最年少である。
チェシ以外の初期メンバーは、アナスタシオ・デ・フィリス(Anastasio De Filiis (1577~1608)、フランチェスコ・ステルッティ(Francesco Stelluti。1577~1652)、ヨハネス・ファン・ヘーク(Johannes van Heeck。1579~1620年頃)の人とされる。みな天文学や博物学畑の人で、特にヘークは占星術や錬金術のような今日的な視点で見れば怪しげな科学の専門家でもあった(もちろん当時は、化学と錬金術、天文学や医学と占星術との違いがまだかなり曖昧な時代)
 「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊
「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊  「ノストラダムス」医師か占星術師か。大予言とは何だったのか。
「ノストラダムス」医師か占星術師か。大予言とは何だったのか。
たった4人の若者が始めたアカデミーには、(文字通り結成された瞬間。むしろ結成が決定した時からだったかもしれない)最初から、チェシの父親という敵がいた。青臭くばかげた情熱を阻止しようという彼の妨害のため、4人はそれぞれの出身都市から、離ればなれのまま、(もちろんインターネットの時代まで400年ほど待つなんて不可能だったろうから)郵便と伝言という古いメディアだけを頼りに、しかしどうにかアカデミーを存続させた。
チェシが、資産を相続し、貴族として権威を高めていくと、必然的なアカデミーの影響力も大きくなっていく。
当時、カトリックの改革や、台頭したプロテスタントのために揺れていたローマ。市民、政治家、聖職者が入り乱れる政争の中、チェシは有能な調整役の立場に立つようになっていった。彼は、教皇や枢機卿たちの疑念を寄せ付けないよう上手く画策し、(彼なりの基準で)科学を(最低限と言えるような妥協で)自由にしていたのである。
哲学者と科学者
チェシは、その社交性を活かして、山猫アカデミーにさらに影響力のある人物を加入させていった。チェシは、1610年に、ナポリで、哲学魔術師として高名だったジャンバティスタ・デラ・ポルタ(Giambattista della Porta。1535~1615)と会って、当時75歳の彼を、アカデミーに誘い、説き伏せた。そして1611年には、当時の時代にあって最高の科学者であったとされる(ちょうど、月の表面や木星の衛星などの新情報で広く衝撃をもたらした『星界の報告(Sidereus Nuncius)』の出版から間もなかった)ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei。1564~1642)を、6番目の会員として迎える。
それからも、名高い思想家や活動家たち、最終的には30人ほどがアカデミー会員となった。
当時は、神秘思想を基盤とした哲学が、近代的な科学へと移り変わろうとしていた時代。ポルタが前者の大権威で、一方ガリレオは新しい科学の時代を始めた最初の1人として、今ではあまりに有名であろう。初期の山猫アカデミー自体は、気高くも無茶な理想と、いくらか遊んでるような秘密主義で飾られていたが、それは神秘的な調和を示す記号体系の奥義を隠し持った魔術師の秘密結社と近いところもあったろう。だが最初に外部からスカウトされた、正反対の立場とも思える2人の会員は、この組織が伝統と新思想との間で揺れていたことをよく物語っている(またこの2人は、ガリレオはその装置の改良者として、ポルタはその光学の原理を定式化した者として、望遠鏡関連の先取権のライバルでもあったらしい)
しかし1615年にポルタが死んで、その後も高まり続ける学者としてのガリレオの名声の影響か、アカデミーは次第に、実験と観察を重んじる、当時の基準で言えば最大級であろう、開かれた純粋科学の組織になった。
宗教とのジレンマと崩壊
だが、望遠鏡をはじめとした科学のための装置の発明がもたらしたいくつもの発見は、宗教改革運動に悩まされていたローマ・カトリック教会、その中央行政機関である教皇庁にとって、やはり危険な思想の種を思わせる側面も強かった。教会は1616年に、コペルニクスの教義は誤りであると公式声明を出して、ガリレオも、物理学的真理として地動説を語ることを禁止された。太陽の周囲を惑星が回っているという世界観は、数学的な遊びから生じる空想の中でだけ許されることになった。
チェシが1630年に、若くして病に倒れ、亡くなってしまったのは、アカデミーにとっも、彼の政治的庇護のもとで多くの発見をしてきた会員たちににとっても大きな不幸だった。
もしチェシが生きていたら、1632年のガリレオの無謀な挑戦(あるいは勝ち目のないゲーム)を止めたかもしれない。彼は、対話形式とはいえ、コペルニクス体系をしっかり論じた本を書いて、旧友であった当時の教皇ともひどく仲違いしてしまう。彼は異端審問にまでかけられた。
ガリレオの学を称賛していたステルッティは山猫アカデミーの創立メンバーの最後の1人となった。彼は、チェシのいなくなった山猫アカデミーをそれでもなんとか続けようとした。しかし新たなパトロン探しも上手くいかず、結局ステルッティ自身も1652年に失くなって、それからすぐ、アカデミーも終焉を迎えた。
錬金術師の石と、化石の樹
教会の機嫌を大きく損ねたために、幽閉の身にあった晩年のガリレオ。1635年11月3日、彼を励ますために、ステルッティは科学界の様々な最新ニュースを報告する手紙を書いた。そこには山猫アカデミーのある長期プロジェクトに関する話もあった。それは、以前、チェシの領内で見つかった、化石化したように思われていた樹木の話。
その出所と成因は、山猫アカデミーの会員たちの間で、長く議論の的になっていたらしい。
1611年、ガリレオは、チェシたちアカデミーの者たちとの面会時に、自身の望遠鏡と、それによって得られた知識から組み立てた自分なりの宇宙論で、みなを驚かせた。
彼はもう1つ、サプライズの品として、ボローニャの錬金術師が発見したらしい、太陽の光を吸収する(その後に反射する)奇妙な石も用意していた。チェシは(今は失われてしまって完全に正体不明な)その謎の石の標本に大きな興味を抱いたという。
ガリレオの方は、それ以上にチェシ自身が発見していた化石樹に興味を抱いていたようだ。もちろんチェシも、 それに関心がなかったわけでは決してなく、いろいろ研究記録をまとめていたが、生前にそれを公表することはなかった。しかしガリレオと、それへの興味を共有していたステルッティが、チェシの残していた図や文章をまとめて、1637年に出版した。
植物界と鉱物界を繋げるもの
もちろんガリレオも間違うことがあったが、ステルッティはそうした間違っていた理論を自分の目で確かめる事ができる人だったらしい(別に珍しくもないだろう)。化石樹に関しても彼は、チェシの明らかに間違っていた理論に関して、自分の目で確かに確認したことと論じた。
チェシとステルッティが共に観察研究から得たという理論は、(少なくとも自分たちが発見した類の)化石樹は、土や泥が、植物に似た形状に変化すること生成されたというもの。
この理論は、いわゆる、世界の全てのもの(その中でも、段階的、階層的に隣のもの同士)の互い同士の影響の連続が「大いなる連鎖構造」をなしているという、やはり古くからの哲学的世界観の影響下にある典型的なもの。
つまりチェシは、その化石の樹木こそが、鉱物界と植物界の中間にあって、知識的に溝になっていた連結部なのだと考えた訳である。
そしてチェシは、鉱物界にも、植物界にも属するとも言えそうなその中間の存在(化石樹)のために、『メタロファイト』なる新領域を創設した。
チェシの見解を支持したステルッティは、メタロファイトの生成は、すで植物界にある植物の種子や根に由来せず、泥から少しずつ生じ、少しずつ樹木に変わったもの、あるいはその途中段階のものとした。そして、この変化のための原因、自然の動作として、彼は特定地域の地中に(多く?)含まれる火に由来する熱だろうと推測した。
さらには、それ(化石樹)が普通の植物と明らかに異なる点として、「土から生じた段階では幹の形状しか見られず、一般的な植物器官がない」、「幹が、普通の樹木のそれのような円形でなく、(おそらく生成途中にも、積み重なった堆積物の重みを大きく受けるため)楕円形」、「(やはり生成過程で、堆積物の重みゆえの制約を受けるために)かなり不規則な内部構造」などの特徴を見いだしもした。
泥から植物を生成させた実験
ステルッティははたして、何を”実際に”見たのだろうか。
彼は、化石樹のいろいろな情報の中には、いくつも変形途中と思われるパターンが見られるとも語ったという。形状がまだ固まりきっていない土の部分と、すっかり化石化した樹木部分の、いわば(生物と無生物の)キメラがいくつもあると。
用水路から、泥まみれの樹木を発見し、それこそ素材となる泥と、すでに樹木と化したところが混ざり合った状態のものであり、そういうものは、『泥樹(クレタ・レーニョ)』と呼ぶべきかもしれないと。
(真実ならば確かに)決定的であるのが、ステルッティ自身がチェシの生前に行なったという、 化石標本の内部から取り出した一塊の泥を、チェシの所有していた宮殿の1室に置いて、何ヶ月か放置してから、確認したらしい実験。(泥だったはずの)それは確かに、数ヶ月で完全な樹木に変わっていた(そしてステルッティとチェシの他にも、何人かが確認者は複数人いた)らしい。
ステルッティは化石樹に関する推測を、化石と呼ばれるもの全般に拡張し、「すべての化石は鉱物界に属し、岩の内部で成長する」と主張したという。
そして彼の化石樹と泥の実験は、 化石が生物由来とは限らないという考えを抱く人たちに(そうした考えがほぼ完全に否定されるようになる18世紀中頃までずっと)長きにわたって、引用されることで、つまり間違った仮説の最有力根拠として、化石研究の歴史の中で重要な役割を担った。
ベリンガーの贋化石
リトグラフィエ・ヴィルセブルゲンシス
ヴュルツブルクの博物学者で医学教授であったヨハン・ベリンガー(Johann Bartholomew Adam Beringer。1670~1740)は、18世紀において、 一大センセーションを呼んだ、まさしく「リューゲンシュタイン(贋化石)」と呼ばれた贋作化石の事件の被害者だった。
彼は1726年に、ヴァルツブルクに隣接する山で自ら発見した一連の化石群の図と、文章での報告をまとめた『リトグラフィエ・ヴィルセブルゲンシス(Lithographiæ Wirceburgensis。ヴュルツブルクのリトグラフ)』という書物を出版した。
リトグラフィエ・ヴィルセブルゲンシスで扱われた化石群は、その形は多様で、(それが本物の化石だとすると)非常に保存状態のよいものだった。トカゲ、クモ、カタツムリ、ハチ、カエルといった、いろいろな生物の完全な形があり、トカゲには皮膚、クモには網、カタツムリには卵が一緒にあり、ハチは花から蜜を吸ってる最中で、カエルは交尾中の姿。 そしてその化石群は生物だけでもなかった。人の顔を映してるような太陽に、三日月、彗星などの天体の他、「YHWH」、つまり聖書の神の名を示す文字表現まであった。
それらは、平らな石版の表面に明瞭なレリーフとして残されていたという。
200年不明だった犯人
ベリンガーが、最初どのくらいに怪しめたかはわからない。少なくとも最初は、詐欺目的や、反宗教関連の目的で用意された、人工的な贋作という説は退けていた。しかし、すでにそれについて書いた本を出版してから、ベリンガーは自分が騙されていたことに気づいた(自分の名前が刻まれた石を見つけたためなどの説があるが、実際のところ、具体的に何がきっかけで過ちに気づいたのかは謎)。
真実に気づいたベリンガーは意気消沈しながらも、なんとか過ちを改めようと、自分の本を買い上げようとしたというような噂もあったらしいが、それに成功したかは怪しい。なんと彼の死後には、『リトグラフィエ・ヴィルセブルゲンシス』は第二版が出版されている。
ベリンガーを騙した犯人は、ずいぶん長い間、悪戯者の学生と推測されていたという。しかし1934年、ヴェルツブルク市の公文書庫で、ハインリッヒ・キルヒナーが、ある文書を発見した。それは、1726年4月に開かれた、ヴュルツブルクとアイフェルシュタット(ヴェルツブルクの近郊に位置する、ベリンガーが化石を採取した山のある市)の役人を前にした、聴聞会(行政機関が規則制定、争訟の裁決や行政処分を行う際、利害関係人や第三者の意見や弁明を聞くためにとられる手続)の記録。その記録では、3人の少年が、自分たちの無実を主張すると共に、自分らが雇われる形で関わった、真の犯人たちを名指ししていた(2人の少年などは、「もしそんな見事なレリーフを掘った石板を造れるような技術があるのなら、穴堀りの助手なんてやってるわけがないだろう」と語った)
その犯人とは、ヴュルツブルク大学ののベリンガーの同僚だった、(どうもベリンガーの才気に嫉妬していたらしい)地理と代数学の教授J・イグナッツ・ロデリック(J Ignatz Roderick)と、裁判所と大学の司書だったゲオルク・フォン・エックハルト(Georg von Eckhart)。2人が用意した贋化石は、さらに職人に製作を発注したものらしいが、ロデリックの方は、自らが贋作制作に直接携わった節もあるようだ。
それが人工物でないことは確か
(単に態度も悪かったのかもしれないが)同僚に嫉妬されるほどの才があって、 その著作もそれなりに影響力があるような学者であったベリンガーが、天体や文字まで彫られた贋化石の石板に騙されたという事実は、18世紀という時代における、化石というものへの理解の程度を実感させてくれよう。
少なくとも当時の基準(いくつかの標準的学説)において、その贋作化石は、おそらくそれほど出来の悪いものでもなかった。それは子供のちょっとした悪戯ではなく、悪意を持った大人たちが、本気で学者を騙すために用意したものだったのだ。化石が生物由来というのは、当時は(すでに有力なものになっていたとは思われるが)仮説の1つでしかなかったわけだから、何らかの原因で形成されるその形が、生物以外のものになる可能性も、当然普通に考えられそうなことだった。
ベリンガーも、一見は、まるで慎重さを欠いていたわけではなく、リトグラフィエ・ヴィルセブルゲンシスを書いた時点での、贋化石に対するベリンガーの見解も、「それらは人工物ではないだろう」くらいのものだったようだ。それを広く公表しようと考えた理由も、(驚くべき真実を明らかにするというより)その形成に関する謎を、他の者たちの知恵を借りて、解決したいという気持ちからだったらしい。
もしかしたら彼は、化石の無機物起源説の支持者で、天体や文字の化石はその強い根拠になると考えていたかもしれない、と見る向きもある。
ただし、彼が急ぎすぎていたのは間違いない。彼が持つことができた知識を考慮するとしても、それらの化石が人工物だと思わせる手がかりは確かにあったから。完璧すぎる保存状態、くっきりしすぎている形状、それに文字は、当時の基準からしてもやりすぎであったのでなかろうか。
遅すぎた説得
(そうなると、どこで気づいたのかの謎が深まるかもしれないが) 本を出版しようとした頃、一番完全に騙されていた頃のベリンガーは、ほとんど狂信者のそれであったらしい。
エックハルトとロデリックも、あまりに上手くいきすぎた悪意ある計画に罪悪感を抱いたのか(あるいは、その後の成り行きによっては自分たちも危ないだろう、と考えたのかもしれない)、報告書を出版しようというベリンガーの考えを知ったところで、どうにかインチキに気づくよう、いくらか警告もしたようだ。ロデリックなどは、同じような贋作石をベリンガーに送り、細工方法まで伝えた。
しかし結局、それが人工的に造れるということを理解してもなお、彼の確信は揺るがなかった。彼は自らの報告書に書いた。「私が作業をほぼ終えていた時点で、世間に流布する噂を聞いた。つまりこれらの石すべてが、人の手で造られたというものだ」
ベリンガーはしかし、そんなものは世紀の発見を妬む誰かの陰謀だろうとした。「そいつは、私の石が偽りであることを暴露するぞと 書いた、いわば宣戦布告でもある不遜な手紙を、彼が用意した偽物の石と一緒に寄こした。実に恥ずべき行為だ」と。
岩石の潜在的な力か、天体からの放射の影響か
自然に勝手に発生するとは考えにくい、色々な形の化石が、やはり岩石や泥から、何らかの特殊な変化によって発生するという考えが、根強く支持された理由に関しては、生物の発生に関しての謎と関連したかもしれない。
例えばウジ虫のような単純な生物群は、腐った肉などから自然発生するというような説が、ベリンガーの生きた時代には、まだ普通だったとされる。よく三界として認識されていた動物界、植物界、鉱物界の内の1つでは、明らかに自然発生という現象がありうる。とすれば、鉱物界においても、何か固有の力と、熱や特定の化学変化が相互作用することで、単純な図像を形成するというのは、奇妙な説でもなかった。
化石について、岩石内の潜在的な可塑的力が生み出したものというより、星からの特殊な放射エネルギーを岩石が受けて、生物そっくりな物質、あるいは(岩石内で成長すらする)疑似生物というようなものが生成、または複製されることがあるというような説もあったらしいが、天体の投影などは、そうした発想が根底にあったかもしれない。
レオナルド・ダ・ヴィンチの化石研究
本業を芸術家としながらも、いくつもの先駆的な研究を行った、偉大な趣味人として知られるレオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci。1452~1519)の その先駆的な研究の中には化石についてのものもあったとされる。
 「レオナルド・ダ・ヴィンチ」研究者としての発明、絵画と生涯の謎
「レオナルド・ダ・ヴィンチ」研究者としての発明、絵画と生涯の謎
レオナルドの化石研究の目的として、化石に関して、当時主流だった2つの仮説を打倒したいという思惑があったようだ。
つまり海生生物のはずの貝の化石が、なぜ陸の地層に見つかることがあるのかという疑問に対する2つの解答。「世界規模のノアの大洪水によって陸に運ばれた説」と、「そもそもそれが生物由来ではないという説」。
もちろんこれは、古代ギリシャの哲学者たちよりはずいぶん後であるものの、アグリコラとゲスナーの子宮石、山猫アカデミーの化石樹、ベリンガーの贋化石よりも以前の研究である。
二枚貝の2枚の殻
まずレオナルドは、渓谷の両岸の層を比較して、積み重なった地層が、堆積物の時間的な推移と正しく認識していたという。
また彼は、積み重なった地層ごとの化石が、堆積の時間的順序の手がかりになると考えていたとも。
山にすら見つかる化石貝に関して、レオナルドは、二枚貝の2つの殻のうちの1つが単独で地層に埋まっているならば、それは死後に水流などで運ばれた可能性が高いとした。しかし二枚貝の2つの殻が一緒に埋まっているなら、それは生きていた場所にそのまま埋められたはずと推測。
2枚の殻ははなから固着したものではなく、生体組織(蝶番靭帯)で繋がれていたものだから、死後、いくらかの時間で必然的に外れてしまう。だから死後に運ばれるなら、2枚の殻が別々になるはずと。これは見事な経験則だが、地質学者の間で一般的になったのは19世紀くらいから。
レオナルドはさらに、貝化石の年齢の判断に使える成長線にも言及しているらしいが、この手法も、かなり時代の先を行っている。
化石は生物由来という結論
化石は、ノアの大洪水の高波や水流で、山の上にまで運ばれた生物の痕跡という説に関して、レオナルドは、死後に運ばれていないと推測できる貝化石が多くあることを根拠に、否定した。
化石は古代生物の遺骸ではないという説はどうか。レオナルドは否定した。貝に年齢の痕跡が見られることや、水流に流されているような化石と、流されていないような化石が、ランダムというより場所単位で集積していると思われることなどから、化石は生物から生じたのではないという結論には説得力がないと。
(もちろん化石貝は、水中限定で起こる化学作用の影響でのみ岩石から生じ、かつ年齢の痕跡の成長を陸に現れてからは止める、というような発想もできたかもしれないが、そんなのでは(力業な理論すぎて)単に可能性として、生物由来の説よりもずっと弱かったろう)
マクロコスモスとミクロコスモス
さすがにレオナルドが、現代的な(でなくとも19世紀以降の)生物学に追いついていた立場で、「化石が生物由来」説を擁護していたとは考えにくい。実際そうではなくて、彼は、おそらく彼の思想と芸術に深く関連している(それもまた現代から見ればファンタジー的な印象の)ある世界観を守ろうとして、化石の研究を行っていたらしい。
その世界観とは、それもまたアリストテレス流の哲学から派生したとされる、「(文字通りの)全宇宙の背景で伸びた因果の糸で繋がりあった、マクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(小宇宙)の群」というようなもの。そしてこの思想には、「ミクロコスモスとして定義できるあらゆる生物、物質、あるいはマクロコスモス(地球や太陽系や宇宙全て)、全宇宙としてのマクロコスモスに対するミクロコスモスとしての地球や惑星。それら万物には、スケールを超越しているような、普遍に一致(共有)するもの(因果的統一性)がある」というような考えを含むが、それこそ化石が鉱物界の産物という説をレオナルドが否定しなければならなかった理由。
レオナルドが、 その化石研究の成果を記述したのは、 全体としては水の性質についての研究記録である(とされる)はずの『レスター手稿(Codex Leicester))』。これはおそらく、全く関係のない研究を一緒くたにまとめたとかでなく、しっかり関連するものとレオナルド自身考えていたのである(ただし単純に、海の生物の化石の話は、とにかく水について多角的に扱ったための例と推測されることもある )
水は、ミクロコスモスたる人間の体にも、マクロコスモスたる地球にも多い。レオナルドの最も有名な絵画作品である『モナ・リザ』の背景に描かれている複雑な地形も、まさしく人の体内に張り巡らされた水流管(血管)に対応する、地球の大地から天までの水の循環を描いているという捉え方もある。
重い元素の循環の謎
しかし人間の体と地球との対応関係、そのアナロジー(類推、解釈)の大きな問題点を、レオナルドは無視できなかったろう。
人間も地球も四元素が混ざりあった構成物というのは、当時はほぼ通説であったろうが、人間の体は、それらの元素を明らかに(自らを維持、つまり生命を安定させるために)循環させていた。特に水(血液)の巡りは重要と思えた。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
すると、2つのコスモスの対応が成り立つためには、マクロである地球の方も、何らかの循環により自らを維持しているのだ、と考える必要があろう。
しかし(それはまた古くからの考え方として)四元素は、重たいものほど、その構造の下に沈み込む。すなわち地球は、その中心を最も重い元素である土として、続いて水、空気、火と、4つの層をなす。だが、特に重たい土と水は沈みすぎて固まって(表面に何らかの圧力がかかり流されるとしても、普通に観測されるものは緩い)、循環の役割を任されているのは、軽い元素である空気と火のみに思える。
(むしろこの世界観だと、なぜ人間においては、重さに関係なく全元素が循環するのだろう? 例えば魂的な存在のコントロールがあると、考えられたりしたろうか)
だからレオナルドには、コスモスの対応関係を守るために、空間の中で球体状に固定されているようにも思える水と土を、上昇させ、循環させる仕組みを考える必要があった訳である。
この目的からすると、化石(というか(運ばれたのでなく水中で死んだままの)海生生物の山の痕跡)は、まさしく土か水が上昇することの根拠になりえたろう。
重い元素の循環の仕組みは、(その信仰的にも、学的にも)ほぼ間違いなくレオナルドにとって重要な興味であった。ならば確かに、水の性質と、水中で死んだはずの生物に由来する陸の化石の研究を、 同じカテゴリーの中で扱おうとしたのも、そうおかしくないだろう。
熱の圧力か、スポンジの飽和か
実際、レスター手稿において、レオナルドは、地球内部の水を上昇させる物理システムをどうにか提案しようと苦闘しているとされる。
もちろん、水は水蒸気(気体)となって上昇し、空に達して冷やされると、雨(液体)となって山にも降ってくるとは、レオナルドにも考えれたろう。だがこれは、血管のそれのような循環とは明らかに違っている。文字通り水路と定義できるものを、地球内部の水が水の循環できる仕組みが望まれた。
だがレオナルドは明らかにその点(水の循環システム)に関して、考察に失敗した。その内部の水を地球規模で循環させるどの方法にも問題点があった。
太陽熱が山の内部を走る血管(水脈)に沿って、水を吸い上げるという説明は、まず熱源である太陽に近いはずの山頂でも水が冷たかったり、凍っている場合があることが厄介だった。それに季節的な川の水位の変化と、太陽熱の強さ(体感的な暑さ)はあまり関係なさそうだった。
地球内部に集積した水を地熱が沸騰させ、 土中を上昇する水蒸気がその流れの中で行きたいに戻って最終的に地上へと噴出する(いわば地下水路の圧力によって水蒸気の変化力をそのまま、水を上昇させる圧力として利用する?)という説明もある。しかしこれだと、天井が渇いた洞窟(地球内部の空洞部)の説明などが難しかった。
山はスポンジのようになっていて、水を吸い上げるのだが、飽和状態になると、それを放出していくというような説も出されたが、そう考えるための物理自体が謎すぎだった。
宇宙の幾何学的中心の、地球の重心
レオナルドは、水の循環に関してはどうしても納得いく答を見つけられなかったが、土に関しては違っていたらしい。
土を上昇させる一般的な仕組みのほうは、重力に関する彼なりの見解と浸食に関する独自の考え方を組み合わせることで自ら納得できるかたちで解決した(私はレオナルドがそれらをミックスさせた複雑な解釈と何日も格闘した……私はその議論を理解したと確信しており、スッキリと要約したものを提供する自信がある)。
レオナルドは、「世界の中心」とか「宇宙の中心」 とか呼べるような、幾何学的中心が地球にあると信じていたそうである。
明らかに、万物は中心にひたすら落ち続けているという重力理論を基盤とした、アリストテレス的な(つまりプトレマイオス型より、むしろ旧式な)天動説の世界が前提としてあった。
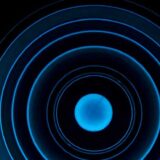 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
地球の水と土の個体部としての球体の表面は、どこであっても中心から等距離にある(宇宙の初期状態にも関係なく、最終的にそういうふうに落ち着く)はず。しかし現実には土元素自体の重さと、元素間の隙間に染み込むか、あるいは溶け混ざり合った水や空気元素の影響で固さの変わった元素群は、形成される球体表面を不規則にする。それは球体内の土の分布が不規則ということでもあるが、したがって地球は、半球の一方が、常にもう一方より重いという状態。
地球の「塊の中心(おそらく重心。つまり力のかかる点として定義できる、(重力の場合は質量の)空間的分布の中心)」は、均質な地球なら世界の中心と一致するが、半球の重さが異なっている(つまり実際の)地球の場合は、一方の重い方の半球側へとズレているはず。地球は、一個のマクロコスモス(生物)として、均衡を保つために、常に重心を幾何学的中心と合わせようと機能する。この過程のために、半球の重い方の大地は(表面的に)沈み、軽い方の半球の大地は上昇することになる。もちろんこの大地の動きのための 重さの移動が、中心をいつまでも一致させない結果にも繋がる。
(我々の経験的にはともかくとして、地球の大地を動かす作用は、おそらく急速すぎるのだろう)
レオナルドは、一方の半球を軽くし、もう一方の半球を重くする、より具体的な原理として、地表と地球内部それぞれの水による侵食作用も提案していたという。つまり、水の影響が全体としての土塊に空洞を造り、その空洞内で(もちろん万物を世界の中心に向かわせる重力による)岩石群の移動があり、 それが結果的に、球体全体の重さの不規則な分布を維持する(特に、地球中心近くでこの現象が起きたなら、半球から半球へと重い元素を直接的に移動させることにもなろう)
化石研究の先駆者たち
多くの地質学者や古生物学者たちに先んじて、レオナルド・ダ・ヴィンチは、大地が上昇下降するという事実にまで到達していたとされる。しかしそれは、大陸移動説とかプレートテクトニクス的な発想があったのでなく、陸の貝の謎にどうにか解答を与えようとして、古代ギリシャの哲学者たちもたどり着いていた仮説(大地が上昇し下降するという説)を、より具体的な世界原理として再構築する仕事の上でのことだったらしい。
それでも彼の研究成果は見事と言えるだろう。ただ「先んじていた」と言えそうなのは、彼だけではなかった。
(SF的な発想だが) 明らかに時代に合わない大天才である彼は、未来からのタイムトラベラーだった、というようなレベルではおそらくなかった。
 夏への扉、月は無慈悲な夜の女王「ハインライン長編」
夏への扉、月は無慈悲な夜の女王「ハインライン長編」
彼は世紀の天才ではあったろうが、おそらく、時代的にありえない天才ではなかった。化石の研究は、無生物から自然発生する疑似生物というような今から振り返ると妙な理論を後押しする一方、長生きしてもほんの100年程度しか生きない1人の人間が、実際的に確かめられるよりもずっと長い時間の世界の変化の手がかりを与えてくれる。
もちろん中には(ただ運がよかっただけの者もいるだろうが)正しい答のある方向を向いていた者もいたろう。レオナルドは、化石が生物由来という点に関しては、そのような正しい方向を向いた者たちの1人だったわけである。