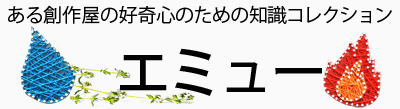古代の龍。龍はいつから龍なのか
中国、そして中国から日本に伝わってきたのだろう龍なる生物が、まったく架空の生物であるなら、その原型が蛇であることは間違いないだろう。
 「アステカ神話の神々一覧」テノチティトランの最高神、破壊神、恵みの神
「アステカ神話の神々一覧」テノチティトランの最高神、破壊神、恵みの神
だがそれはいつ想像されたものであるのか。
 「ヘビ」大嫌いとされる哀れな爬虫類の進化と生態
「ヘビ」大嫌いとされる哀れな爬虫類の進化と生態  「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
竜の原型となった龍の甲骨文字。青銅器の龍の絵
殷(紀元前17世紀頃〜紀元前1046)の『甲骨文字』には、すでに龍に相当する文字が存在しているそうである。
 「殷王朝」甲骨文字を用いた民族たち。保存された歴史の始まり
「殷王朝」甲骨文字を用いた民族たち。保存された歴史の始まり
それは、尾を巻いた、蛇の胴体に角をつけたもので、今日に伝わる、漢字の「竜」の原型となった文字とされている。
また、殷は『青銅器文化(Bronze culture)』であったが、青銅器に彫られた龍らしき絵も見つかっているという。
そして見つかっている龍の絵には、角らしきものが、やはり描かれていて、手足も付いている。
まず確実に言えることは、普通、蛇に見られない角と手足という特徴が描かれている時点で、ほぼ確実に、これは蛇でなく龍として描かれたものなはずである。
爪の数の意味。権力の象徴、皇帝の黄金龍
秦(紀元前221〜紀元前206)、漢(紀元前206〜紀元220)の頃には、龍の典型的イメージも、ほぼ完成していたようである。
 「秦王朝」始皇帝政の父母、性格、政治政策、最期。統一国家、中華の誕生
「秦王朝」始皇帝政の父母、性格、政治政策、最期。統一国家、中華の誕生
そしてこの頃から、権力の象徴としての役割も、龍に与えられることになった。
かの司馬遷は、史記において、始皇帝を祖龍と称しているという。
また、天子の怒りに触れることは、竜の逆鱗に触れることに例えられた。
 「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
「漢王朝」前漢と後漢。歴史学の始まり、司馬遷が史記を書いた頃
時が流れ、王朝が移り変わっても、龍が権力の象徴であることは変わらなかった。
特に5つの爪を持つ黄金龍が、皇帝のシンボルとされた。
民間に伝わっていた龍は、3つか4つの爪しか持たない。
5つの爪の黄金龍は、皇帝にのみ許された、特別な龍であった。
龍とはどの様な動物か。キメラか神か
形態。蜃気楼の息
秦代以降に完成した、龍の典型的イメージとはすなわち、様々な動物の長所を合わせ持った、キメラ的な怪獣と言うものである。
宋(960~1279)の時代に書かれたという『爾雅翼』という書には、龍は「角は鹿、頭は駝、眼は鬼、頸は蛇、腹は蜃、ウロコは鯉、爪は鷹、手は虎、耳は牛に似ている」と紹介されている。
 「鬼」種類、伝説、史実。伝えられる、日本の闇に潜む何者か
「鬼」種類、伝説、史実。伝えられる、日本の闇に潜む何者か
 「猛禽類」最大の鳥たちの種類、生態、人間文化との関わり
「猛禽類」最大の鳥たちの種類、生態、人間文化との関わり
駝は、ラクダの事だが、これはまた伝説上の麒麟を意味する場合もある。
蜃は、蜃気楼を発生させるという伝説の生物で、これ自体、龍の姿で描かれるか、あるいは巨大なハマグリとされる。
また、龍の吐く息が『蜃気楼(mirage)』となる、という説もある。
めでたいとされた9という数字
爾雅翼などの多くの書は、龍に9つの生物の特徴をあてている。
部分部分で例えられる動物が変わっても、基本的に龍は9種類の動物の特徴を併せ持つとされる。
このことは『九似説』と呼ばれる。
9というのは、 中国では、めでたい、神聖な数字とされていて、偉大なる皇帝の象徴動物としては、理に適った特性である。
さらに龍は、背中に81枚の鱗を持つという。
これも9×9の数である。
髭。逆鱗。博山
龍の口元には髭があり、顎下には『逆鱗』を持つと言われる。
この逆鱗に触れると、龍はひどく怒るという。
それに、龍の頭上には『博山』と呼ばれる、肉の盛り上がりがあるともされ、ここには、力の源たる水が入っているようである。
体色は変わるのか
龍の体色は、青や黄で描かれることが多いそうである。
他には、赤、白、黒、の龍の場合もけっこうあり、それら5色を合わせ持たされる場合もあるという。
体色に関しては、年齢によって変わるという説もある。
5世紀頃に、任昉という人が書いたとされる『述異記』には、「青色の龍は若いが、年を重ねると黄色になっていく」と書かれてるそうである。
基本的に変化は徐々に起こるとされ、龍の寿命は数千年と、非常に長いので、普通の人間が生きている間に、ある龍の体色が変化していく様を確認することは、ほぼ不可能と思われる。
霊獣か瑞獣か
龍は、東の青龍、南の朱雀、西の白虎、北の玄武の四神として、他の霊獣と並べられる事もあるが、やはりたいていの場合においては、別格であり、最高の存在であった。
龍は、ウロコのある全ての動物の長とされているが、麒麟や鳳凰などの、他のあらゆる霊獣も含めた、全ての生物が、龍から生じたという説もある。
 ロック鳥。ビッグバード。鳳凰。コンガマト「未確認動物としての巨鳥、怪鳥」
ロック鳥。ビッグバード。鳳凰。コンガマト「未確認動物としての巨鳥、怪鳥」
また、龍のような、ある動物群の長を、瑞獣と言う。
龍の能力。水神としての力。変幻自在の神通力
尺水は何か。なぜ龍は水から生じるのか
龍の頭部の博山は、『尺水』とも呼ばれている。
あるいは、博山に、蓄えられた水が、尺水と呼ばれる。
戦国時代(紀元前5世紀〜紀元前221)から、漢にかけてくらいに成立したとされている『管子』においては、「龍は水から生ずる」とされている。
龍は水の神、水の化身、水の霊獣、あるいは単に水棲動物。
いずれにしても、水に関連が深いと考えられているのだ。
龍は、多彩な神通力を持っているとされているが、その力も、源たる尺水あっての事なのだという。
水を失ってしまった龍は、蟻にすら勝てない、という話もある。
天候操作。天に上昇するための雲
水神なので、当然のように、龍は雨を呼ぶ力を持ち、怒り狂った時は、大洪水を起こすとされる。
中国では古くから、龍の模型を使った雨乞いもよく行われていたようである。
16世紀くらいの書である、『本草綱目』においては、龍は、角と鬣を持つ大蛇であり、蜃気楼は、雨の中で吐く息とされている。
 「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
また雲も、龍の吐いたものであり、龍は自らが吐いた雲に乗ることで、天に上昇していけるのだという。
変形、変身能力
龍は巨大な生物と思われがちだが、実のところ、変幻自在だという説もある。
管子には、龍は「小さくなろうとすれば、虫ほどの大きさになれる。大きくなろうとすれば、天地を包み込めるほどの大きさになれる。高く上れば、天上の雲を突き抜け、低く下がれば、深い泉に身を沈める」と書かれているという。
 「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
「昆虫」最強の生物。最初の陸上動物。飛行の始まり。この惑星の真の支配者たち
また、龍は、ヘビ型以外に、カメや魚のような種がいるという話もある。
それらは、単に変身した姿なのかもしれない。
違いはどれほどか。蛇との関係
昔の中国人は、蛇と龍を明確に区別していたようだが、両者が近しい関係にある事は意識していたようである。
そこで、蛇に似ているが4足を持つ蛟(みずち)や、 角を持っている蛇である虯といった、蛇と龍の中間の生物も、よく考えられてきたようである。
また、「水を帯びた蛇は、 500年で蛟となり、1000年にして龍となる」、というように、龍が蛇から進化したという説もあったようである。
龍は、化け蛇なのかもしれない。
 猫又、鎌鼬、送り狼「動物、獣の妖怪」
猫又、鎌鼬、送り狼「動物、獣の妖怪」
仏教の守護神としての龍。ナーガとの関係
法華経のような、経典には、龍の長たる龍王の記述がよくあるという。
 「天台宗、天台密教」比叡山の最澄。空海の真言宗との違いと関係
「天台宗、天台密教」比叡山の最澄。空海の真言宗との違いと関係
ただこれは、インドに古くより伝わるナーガの王、ナーガ・ラージャである。
 「インド神話の神々」女神、精霊。悪魔、羅刹。怪物、神獣の一覧
「インド神話の神々」女神、精霊。悪魔、羅刹。怪物、神獣の一覧
どうも、仏教を学んだ中国人達が、ナーガの事を訳す際に、 それを中国の龍と同一視したらしい。
しかし、ナーガもまた蛇を原型とした、架空の生物とされているが、より蛇に近い。
頭部を複数持ってたりするなど、異形の特徴もあるが、それらは龍とは共通していない。
神聖な龍に比べると、ナーガは悪とされる事も多い。
中国でも、龍と区別される蛇は、毒性が強調され、悪とされる場合が多いという。
ようするに、ナーガはあくまで蛇神(蛇)であり、龍とは違うと思われる。
中国人が、ナーガを龍と同一視した事に関しては、ナーガもまた水や雨の神であったからという説もある。
日本に伝わってきた仏教は、中国ですでに再解釈された仏教であり、日本の寺などには、守護神として、中国風の龍が描かれている事もあるが、冷静に考えれば、あれは間違った解釈なのかもしれない。
 「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
仏教の龍は、中国人がナーガ、あるいは特別ないくつかのナーガを置き換えたものとも言えるから。
諸々の特徴からするに、よく龍とされる、日本神話のヤマタノオロチ(八岐大蛇)は、龍というより、名前通りに蛇(ナーガ)なのかもしれない。
 「日本神話」神々の国造りと戦い。現代的ないくつかの解釈
「日本神話」神々の国造りと戦い。現代的ないくつかの解釈
龍の一覧
応龍。古代の皇帝に仕えた、翼を持つ龍
珍しい、翼を持つ龍。
そのために応龍は、「翼ある龍」とも称される。
鷲の体と翼を持ち、翼はコウモリの翼という説もあるが、これは西洋のドラゴンの影響があるのかもしれない。
 「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ
「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ
ただし、この龍自体は、かなり古くから伝えられている。
4本の足のそれぞれに指が3本。
毛皮を持つという説もある。
長く生きた龍が、より進化した姿と考えられる事もある。
翼を持ったためか、飛翔速度が、通常の龍よりも、遥かに速いそうである。
強力な力を持つが、神の位ではないとされ、かつて、女神である女媧に戦いを挑み、敗れた事で、仕える事になったとされる。
また、伝説上の人物ともされる黄帝にも仕えていたという。
瑞獣の中でも、古くより別格な四霊の1体とされる事もある。
他の四霊は、麒麟、鳳凰、霊亀である。
四海竜王。龍宮城の伝説
東西南北の四方それぞれの海(あるいは領土)を支配するという4体の龍。
真の姿は龍であるが、普段は巨大な龍神の姿をして、海底深くに用意された『龍宮城』を治めているとされる。
雨を司り、各地の水量を管理しているそうである。
あるいは海や、水に関する様々の守護者とされている。
東海龍王が、別格的で、最大の領土を持つという。
天の四方を司るという、天之四霊とも呼ばれる、四神(青龍、朱雀、白虎、玄武)の中では、東が青龍であるが、それは関係してるだろうか?
黄龍。大地と黄河
麒麟は珍しく、 それだからこそ会場に見せたい動物とされているが、黄龍も同様。
あるいは、より珍しく、よりめでたいという。
五行説などにおいて、黄は大地の色であるから、この龍は地の属性を持つ龍とされる事もある。
四神の中心に麒麟を置いて、五神とする説もあるが、その場合も、麒麟でなく黄龍が置かれる場合がある。
案外麒麟が長く生きると黄龍になるのかもしれない。
また、年老いた応龍と言われる事もある。
中国の皇帝が象徴としてきた黄金龍は、実はこの黄龍のことである、という説もある。
黄帝の時代や、夏王朝(紀元前20世紀〜紀元前17世紀)の、禹の時代に、黄河より現れた、という伝説がある。
 「夏王朝」開いた人物。史記の記述。実在したか。中国大陸最初の国家
「夏王朝」開いた人物。史記の記述。実在したか。中国大陸最初の国家
青龍。緑色食物の支配者か
四神の1体とされる青龍は、東方の守護神。
青は、blueでなくgreen、つまり緑の事とする説が有力である。
五行説に照らし合わせた五神説では、木を司る。
体色に関しては、普通に青(blue)で描かれる事も多い。
本来の緑(green)とは、ようするに緑色植物の緑らしいから、青龍が、年取った植物が化けたか、あるいは植物の支配者ならば、青の青龍もいて、おかしくはないのかもしれない。
 「光合成の仕組み」生態系を支える驚異の化学反応
「光合成の仕組み」生態系を支える驚異の化学反応
白龍。最も速い龍
天上界を統べる天帝に仕えていたとされる白龍は、飛行速度が、最も速い龍とされる。
他のいかなる龍も、一度逃げ去った白龍に追いつくことは、決してできないという。
五神を全て龍とする、五竜説では、中央の黄龍、東の青龍に加え、西の白虎と置き換えられる。
金を司り、南総里見八犬伝では、白龍の吐いたものが地面に入り金となる、と説明されている。
赤龍。火山から生まれし、炎を吐く龍
五竜説において、南の朱雀と置き換えられる赤龍は、太陽、あるいは火山から生まれたとされている。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
 「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
火を司り、その吐く息も、火なのだという。
ある意味、正統派の龍と対極的な存在と言える。
水に弱いのかは不明だが、もしも、その武器が火ならば、少なくとも攻撃力を弱めるのに使えると思われる。
前漢(紀元前206〜紀元8)の初代皇帝である劉邦は、この赤龍の子である、という伝説がある。
彼の母が寝ていた時に、現れた赤龍が、母の上にきて、その後に劉邦が産まれたそうである。
黒龍。邪悪の化身か、海の守護神か
五竜説で、北の玄武に置き換えられる黒龍は、神聖でありながらも、悪の存在らしい。
単に、災いをもたらす邪悪の化身とも言われる。
姿は龍だが、なぜか2本の前足のみしか持たないという話がある。
黒竜は、光を嫌い、平時は、深海に生きている。
そして新月の夜のみ、海上に姿を現すともされる。
水を司り、海の動物達の守護神でもある。
魚を乱獲する者を、深海の闇に引きずり込んでしまう。
 「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
こんなだから、当然のように、闇属性であるという説もある。
禹。偉大な王の秘密
夏王朝の初代皇帝とされる禹は、まさしく龍であったという伝説がある。
史記には、禹は「山と川の神」として崇められていた、という記述があるようで、あるいは彼はやはり、人里に下ってきた山の龍だったのだろうか。
禹は、強力な神通力に、優れた知能を有していた偉大な王であり、龍に例えられていた可能性もある。
ただし、夏王朝の時代に、龍の認識が今と同じようなものだったかは、ちょっと疑問であろう。
一方で、人里に現れた禹の存在から、龍という生物の存在が知られるようになったのかもしれない。
虹蜺。虹の正体
虹蜺、あるいは虹霓は、虹の正体である龍と考えられていた。
単体の龍でなく、鮮やかな色の雄である虹と、暗く淡い色の雌である蜺の、組み合わせとされる。
なので、虹と蜺が出会うと、初めて虹となるのかもしれない。
甲骨文の研究より、中国では、殷の時代には、「虹は龍」とする思想はあったのではないか、と考えられてもいる。
虹龍は、時に人に変身し、地上に現れることもあるという。
その場合は、単体であるそうである。
螭。魔除けとして親しまれた龍の子
螭、あるいは螭龍は、1〜3メートルくらいの、小型の龍か、あるいは龍の子供ともされる。
体色は、赤、白、青の3色で、角は持たないようだから、蛟や虯の可能性もある。
漢の時代に、武帝が、長安城にて、目撃したという話もある。
古くは、魔除けの象徴として、石などによく刻まれていたという。
斗牛。人里に迷い込んでしまった龍か
斗牛は、16世紀ぐらいに、よく地上に出没しては、人々を驚かせたという。
龍とされるが、その性質は、かなりドラゴンに近い。
金などの高価な宝物を好み、そういうもので作られた柱などによく巻きついたりしたという。
集めた金銀財宝で、自ら柱を作っていた、という説もある。
龍らしく風雨を操り、霧が現れたと思うと、そこから突然姿を見せたりしたという話もある。
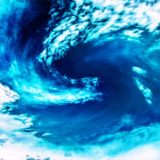 「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差
「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差
最終的には、徳の高い帝により消し去られたらしい。
龍は、本来は霊山など、普通、人が関われないような領域に暮らしているとされている。
斗牛はもしかすると、人里に迷い込んでしまった龍だったのかもしれない。
共工。暴君だった人面龍
共工は、人の頭部を持つ人面龍。
赤い髭が全身を覆っているとか、手足も人間である、という説もある。
自身に従わない者には、容赦のない乱暴を働くことから、かなり恐れられていたという。
どうも、この人面龍は、人間ぽい。
どこかの暴君魔術師の変身形態だったのかもしれない。
あるいはナーガぽい。
相柳。普通にナーガか
共工には相柳という臣下がいたとされる。
相柳は、普通に、龍でないかもしれない。
共工よりも、さらにナーガぽく、蛇の体に9つの頭部を持ち、やはり人面である。
とにかく、視界に入ったものを食い尽くそうとする習性があり、その体からは、 毒性の強い水が分泌され、大地を進むたびに、
荒れ果てさせる、という説もある。
夏王朝の頃に、禹によって討たれたという伝説がある。
竜生九子。9の偉大な子達
竜生九子は、龍が生んだ9の子とされる。
ただし、彼らはなりそこないで、龍の子にして、龍ではないのだという。
書によって、9の子の名前や特徴などは異なるらしいが、ほぼ共通しているのが、9の子のそれぞれの外見には、各自別々の動物があてられている事。
そして、文筆の才があるとか、戦闘が強いとか、それぞれに得意分野がある事。
竜生九子について、かつて龍がそういう子達を生んだ事があるのか、もしくは、龍は龍以外にそれらの種を生む事があるのかは、おそらく解釈が分かれる。
よく言われるのが以下の9種。
贔屓(ひき)
亀に似ている。文学、あるいは重いものを持つ事を好む。
螭吻(ちふん)
魚、あるいはクジラに似ている。水を好む。
 「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
蒲牢(ほろう)
龍に似ている。クジラ(巨大なものか、あるいは螭吻?)をなぜか恐れ、襲われた時は凄まじい吠え声をだす。
狴犴(へいかん)
虎に似ている。非常に好戦的。
饕餮(とうてつ)
曲がった角を持つ獣。財産と食物を貪るとされる。
蚣蝮(はか)
魚に似ている。水か、あるいは重いものを持つ事を好む。
睚眦(がいさい)
龍に似ているが、角が1本しかない。好戦的、というより、命を奪うのが好きであるという。
狻猊(さんげい)
獅子に似ている。座る事、あるいは火の煙を好む。
因牛(しゅうぎゅう)
龍に似ているが、小さい。音楽が好き。
吉弔。食用には向かない
吉弔もまた、龍の子であるが、龍ではないとされている。
その見た目は、亀の体に、竜の頭部を持っているというもの。
甲羅は、龍のウロコが何重にも重なったもの。
また、頭と尻尾が長すぎて、甲羅に入りきらないのだととも言われる。
ある伝説によると、龍は卵を産む時、必ず2個産む。
そして、卵のひとつからは龍が、もうひとつからは、この吉弔が誕生するのだという。
古くは、吉弔は、狩られる事があったともされる。
その肉は柔らかすぎて食用には向かなかったそうだが、血と肉と脂肪を練り合わせれば、腫れ物の薬になったそうである。