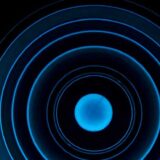懐疑論者による最初期のエセー集
人間とは何か、どのようにして生きているのかというようなことを、いろいろ考え、それを実際に文章として綴った、主に16~18世紀くらいの、フランス語圏の思想家を、モラリスト(moraliste)と呼ぶ場合がある。
哲学者ミシェル・ド・モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne。1533~1592)は、そうしたモラリストの代表的な人物の1人。そして、彼が書いた『随想録(Les Essais。エセー)』という書は、まさしく最初期のエッセイ集とされている。
モンテーニュ随想録
エッセイとは、筆者の体験や読書などから得た知識をもとに、それに対する感想・思索・思想をまとめた散文。つまりは、基本的な文章の形式などにとらわれずに書かれた素直な文章。
モンテーニュ自身は、いろいろなことをテーマに、自分なりの考えとかを語っている。歴史や伝説における、様々な各テーマに関連する事例なども紹介している。
彼は懐疑論者とされるが、いくつか、宗教とか文化とかの考察を見れば、そのことは明らかだ。
シリアスな話題も多いが、よい名前、悪い名前の考察をしていたりとか、ちょっとお遊び的な話もあったりする。そこも言ってしまえば、エッセイ的か。
タイトルが違っているだけで同じような話題も多い中、ここではいくつか、個人的に興味深かった話を紹介する。
異なる手段で同じ結果に達すること
自分に恨みを抱いている誰かが、しかもその復讐が可能という状況になった時、たいてい、なんとかとれる最も有効な防衛策は、降参して、相手の同情に訴えること。しかし、あえてそれとは違う勇壮な(つまり勇ましい姿の)態度などが、良い結果をもたらした例が紹介される。
3人の貴族の凄い豪胆さ(物事を恐れない姿勢)に驚嘆し、 憎しみを抱いていたリモージュ人たちへの怒りを和らげた、エドワード黒太子(Edward, the Black Prince。1330~1376)。
亡きものにしようとしていた兵士が、最初は許してくれとひたすら嘆願していただけだったのだが、最後には立ち向かうことを決心した勇気を見て、憐れみををかけた、アルバニア君主スカンデルベグ(Skanderbeg。1405~1468)など。
しかし、特にローマ王コンラート3世(Konrad III。1093~1152)が、バヴァリア(バイエルン)公ヴェルフを追いつめた時の話は、ややぶっとびすぎな感じもする。
包囲されていた城の中で、貴婦人たちだけは、肩で背負える荷物だけを持って脱出することが認められた。のだが、彼女たちはなんと、その肩に、夫や子供たち、自分たちの崇拝する君主様をも背負って行こうと試みた。そして、それを見たコンラートは感動のあまり、バヴァリア公を許したのだという。
悲しみについて
自分は、誰よりもこの感情を免れているとモンテーニュは言う。
世間で、この感情がどれほどに尊敬されたり、愛されたりしようが、自分はこの感情を愛しないし、重んじもしない。世間の人々は、知恵や徳や良心をこれで装っている。そんなものみっともない馬鹿げた飾りだと、彼は言うわけである。
ここでは、エジプト王プサメニトス(Psamtik III。Psammetichus。エジプト第26王朝の王)が、ペルシア王カンビュセス(Cambyses II。アケメネス朝ペルシア第2代の王)に捕らえられた時のことなどが語られている。
 「古代エジプトの歴史」王朝の一覧、文明の発展と変化、簡単な流れ
「古代エジプトの歴史」王朝の一覧、文明の発展と変化、簡単な流れ
プサメニトスは、娘が奴隷にされても、息子が死んでしまっても悲しむ様子を見せなかったが、親友の1人が捕虜として連れて行かれるのを見た時、悲しみのあまりに自らの頭を打ち叩いたという。
この話のオチとしては、王自身が、「最後の悲しみは、どうにか表現することができたが、最初の2つは、どのような方法をもってしても、表現なるものをはるかに超えてしまっていたからこそだ」という釈明がある。
われわれの行為は意図によって判断される
昔の人は死ぬ事についてどのように考えてきたのだろうか。
死は義務からの解放という考えがあると、ここでは語られる。
しかし、結果や実現を我々の能力でどうにかすることはできない。我々は我々の力や手段の及ばないところまで責任を負うこともできない。意思を除いては、何も我々の自由にはならないから。だからこそ人間の義務について、あらゆる原則が、必然的に意思の上に基礎付けられている。
死ぬことで逃げるなというような怒りも感じる。「現代の多くの人たちは、他人の物を返さないでいることを自分で意識していながら、遺言によって、自分の死後にそれを返済するつもりでいるのを知っている。すぐになすべきことを引き伸ばし、そして自分には痛くも痒くもなくなってから損害を償うなどというのは虫がよすぎる」
確かにそれはそうかもしれない。
また、それ以上に悪いこととして、隣人に対する何かの恨みを、自分の生きている間は隠しておきながら、遺言においてそれを打ち明ける人たちを、ここでは攻めてもいる。それは自分の名誉というものをあまりにも考えてなさすぎる証拠だとして。
そして、「自分はできることなら、その死の時、生前に言ったこと以外は言わないように心がけよう」と決意が示される。
占いについて
やはりオカルト的な話はより興味深いか。
モンテーニュは懐疑論者だったことでも知られているが、ここでは、神託について、「キリストよりもずっと以前に、すでにそれに対する信頼が失われ始めていたことは確かだ。なぜならキケロ(キケロ(Marcus Tullius Cicero。紀元前106~紀元前43)が、それの廃れた原因を見出そうとしているのを我々は知っているから」と、(彼の時代の視点から)昔の人たちの中にも、すでに宗教に疑いを抱く者がいた、というようなことを語っている。
それにしても、昔に比べると占いの権威が失われていることも事実、と書かれているのも面白い。
適当にたくさん占えば、当たることも当たらないこともあるが、何か当たったからといって別に感心することはない。むしろ占いがいつでも外れると言うのならば、かえってそれはあてになるだろう。
しかし、毎度のあて損ないは、みんな記録しないが、当たることは稀だから、信じられないほど驚くべきことだと人々は噂し、そればかりが有名になるとも。
 「インチキ占い師、霊媒師の手口」予言のテクニックはどういうものか
「インチキ占い師、霊媒師の手口」予言のテクニックはどういうものか
キケロは、無神論者だったディアゴラスという人の話などを伝えている。
ディアゴラスはある時、サモトラケ島に行ったのだが、そこの神殿にて、海難を逃れた人々が、たくさんの品を奉納していた。
「どうです。神々は人間などには無関心なのだとあなたは言われてるようだが、こんなに多数の人々が、神々の恵みによって救われてるではありませんか」と人々に言われたディアゴラスは、以下のように返したという。
「それはつまりこういうことだ。溺死した人の数はもっと多いのだが、溺れてしまった人たちは、ここに来て、神に感謝を述べることができない」
善悪の味は多くのばあいそれについてわれわれのもつ考えかたによって
エセーのあちこちで、霊魂に関して、それが存在していることがかなり当たり前のように語られている。おそらくそれは生命の原因としてだ。
「……身体は、多少の差こそあれ、一つの調子、一つの傾向しかもたない。霊魂はさまざまな形に変貌することができる。霊魂は何らかの仕方で、身体の感覚やその他の出来事を自己に従わせ、自己の支配のもとに置く。それゆえ、われわれはわれわれの霊魂を研究し、その能力を吟味し、霊魂のうちにその全能な活力を呼びさまさなければならない」
例えば死体を肉の塊とか考えるとして、ではなぜ肉の塊は、その時までは生きていたのか。
後に、( 少なくとも生物というシステムに関しては唯物論的な見方をしていたと考えられる)生物学者のラマルク(Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck。1744~1829)などは、彼の時代には新しい発見で、モンテーニュの時代にはほぼ神秘的な現象という理解しかされてなかったろう電気に希望を見出した。だが、確かに モンテーニュの時代に、生物の物理的原理を考える場合、霊魂説は考えやすかったろう。
 「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち
「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち  「ラマルク。進化論と動物哲学」用不用説、生物世界唯物論、そして系統樹の発見の物語
「ラマルク。進化論と動物哲学」用不用説、生物世界唯物論、そして系統樹の発見の物語
ただし、現代における電気と違って、霊魂という現象は、はっきり物体に対する影響という形で確認された(信頼できる)記録がないのは重要だろう。今でも、生物という現象に関して未知な部分を 霊魂というもので説明することは可能と思われるが、では霊魂とはどんなものか、その機能の背景を具体的に説明する(というか説明に大きな説得力を持たせる)ことは、おそらく誰にもできない。おそらく今も昔も。
モンテーニュが実際にどう考えていたのか、エセーから読み取ることは難しいが、彼が霊魂について語る時、それは単に生物の機能の原因、例えば今で言う神経系の電気ネットワークのようなものだったかもしれない。
ただ、それと(高度な?)精神との対立(つまり、性能が優秀すぎる精神が、霊魂の本来の意図に逆らえるために起こる対立)を考えてるような記述も見られる。しかし普通の物質に精神のようなものが見出せないとするならば、生物、少なくとも人間の精神もまた、非物質的な何らかの原因があると推測しやすいだろう。
ところで、単に興味深い記述として以下のようなものもある。
「……世には、身を切開されながら読書をやめようとしなかった人があるが、これは何という人間であろうか? また、いくら拷問にかけられてるあざ笑ってそれに耐えたので、彼をおさえつけていた刑吏の猛り狂う残酷さと、次々に加えられる責苦の工夫の方が、ついに根負けしたという例もある。だがそれは哲学者のばあいだ。
カエサルの或る剣闘士は自分の傷をさぐられ切開されながら、笑ってそれに耐えた。これについては何と言おうか?」とは、キケロの引用らしいが。
人間と動物の霊魂
モンテーニュは、霊魂が、この世界においてとても自由なものかもしれないと考えていたようだ。そして自然至上主義的な思想もあるように思う。人間などは我が強すぎて、自らの霊魂の自由性を減らしてしまっているというような。
結果的に、動物はより自然的で自由であるとか。しかしそれは、霊魂に従順であるとも言える。「良きものに従うのが良い」、のだろうか? モンテーニュは多分そう考えていた。
もちろん、霊魂を縛り付けるのは、自分たち自身の、つまり個人的自由の代償でもあるだろう。
「精神を首輪で繋いでいる動物は、彼らの感覚を身体の感じるままに放任しておくので、自由かつ素朴な感覚……もしわれわれが、われわれの肢体にそれぞれ所属している感覚能力を、妨害しなかったならば、われわれはもっと幸福であったかも知れない。自然はわれわれの肢体を、快楽に対しても苦痛に対しても、正しくほどよく調節してくれたことであろう……われわれはすでにそういう自然の法則から自己を解放し、われわれの空想のとりとめなき自由に身を委ねてしまった」
モンテーニュは度々、人間が、自分が本来あまり良くないと考えてることさえ、してしまう衝動が発生したりすることがある、として、その原因を精神の適当さと推測していた印象がある。例えば(現代でも馴染み深い例として)ゲーム依存とか、ギャンブル依存とか、そういう話と思う。
ただ、別に人間に限らず、一見すると奇妙な、あるいは一見どころかどう考えても奇妙な、生物の習性とかが発見されたとして、今の時代なら、モンテーニュの生きていた頃ほど驚かれることはないのでなかろうか(人間社会の、長期的に考えると無意味と理解しながらも、ハマってしまう娯楽などと同じような次元で考えるべき問題かは微妙だろうけど)。一般的に生物自体の根本的な原因が謎であるとしても、少なくとも生物種の多様性の原因は、進化というシステムと考えられているだろう。そして様々な環境によく適応した生物構造が生き残りやすいというのが、進化の基本的な考え方であるが、もちろんそれだけだと、あまりに物事を単純化した見方。ある環境、と簡単に言っても、それは背景となる物事の状態だけでなく、そこにある、あるいは入り込んでくる全ての生物種が、非常に複雑な変化ネットワークを構築する。場合によっては、どんな生物種が生き残るのか、実際それが生き残るまで、予測などほとんど不可能なこともあるだろう。そして、ある生物種とその生物種に関連する全生物種が生きている全ての長い時間の一部だけを見るとき、その一部の間、非常に奇妙な習性が現れていることは、確率的にそれほどおかしいことではないと思う。
非物質的霊魂、物質的精神。進化論、AI、現代における手がかり
しかし、電気ネットワークのような物理的なものか、非物質的、オカルト的なものか、いずれにしろ霊魂が生物の原因であるとする。では精神はどのように生じるのか。
もしも精神が、霊魂を原因とする生物現象から付属的に発生したもの(つまり精神が、霊魂なるものが生じさせた派生的現象)とするなら(モンテーニュも、実際そう考えていた節があるが、 霊魂の方は本来自由であり、物理的な肉体のために制約を受けるというような何かであるなら、精神は、その相互作用か何かで生じた機能の可能性が高そうではあろう)、 それらの関係は、人間と機械にも例えられるかもしれない。
人間は、 自身の置かれてる環境を良くしようと、機械(というより最初は道具?)を造る。 しかし、例えばデジタルネットワーク(例えば少しずつのプログラムや、それによる動作の複雑な組み合わせ)などにより複雑化した機械は、 人間だけでは実質的に不可能と思われるようなことを安定して実行できるようにさえなる。結果的に、有能な機械が、意識的な行動をとれるようになったら、 人間に逆らうことは簡単かもしれない。つまり霊魂に対して、人間の高度な精神は、有能すぎる機械のようなものかもしれない。
精神も 霊魂の非物質的な 部分がなければ 機能しないのか あるいは
霊魂が動作させる生物というシステムと、技術的に同じような物理体を用意すれば、そこに精神もやはり生ずるか。もしもそう考えられるなら、つまり精神はあくまでも物質的なものであるとするなら、モンテーニュの世界観では、人間とほとんど全く同じように考える人工知能というのも、かなり現実的な存在かもしれない。
少なくとも、現代の(AI、つまり人工知能を搭載していると言われる)知的機械の研究者、開発者、ユーザーの多くが、まさに疑似人間のような知的機械を求めていると思われる。
もし霊魂が、精神も含めた生物という存在に必須の非物質的要素であるのなら、(知的生物を再現しているという意味での)知的機械の発明の希望はかなり弱くなるだろう。だが霊魂が存在していようがいまいが、精神が物質的なものであるとするなら、事情は全然変わってくる。
しかしもし、実際に霊魂を根本的な原因として機能しているという、ただその点を除けば、性別というのはあくまでも物質的で、機械的に再現できるのだとするなら、自然界において、それが全然誕生しないように見えるのはなぜか?
複雑すぎるからだろうか? 霊魂が精神を生じさせ、そしてその精神がある程度優れたものであるならば、世界に対する複雑な変化(あるいは改造)の手を可能にする。そしてそのような変化や改造が、この世界に本来は霊魂なしでは存在しえないような、新しい複雑な高等生物(厳密には再現機械)を作り出すこともできると。
それとも単に、我々が局所的な環境しか知らない、つまり自然界の機械的生物を知らないだけだろうか。
現代の我々は、進化論というシステムに馴染んでいる。そこで最初、どこかで単純な生物が生じ、それが様々な環境に適応した変化をして、結果的に様々な生物を生み出し、そしてついには人間のような賢い生物さえ生み出した、と考えることは容易い。この場合にも、ある生物の動作には霊魂が必要というなら、それが最も単純な生物にも必要と考えない限り、どこかの生物構造に霊魂が入ったということになるだろう。そのようなイベントも、進化論的世界観に含めることはできる。つまり霊魂が宿った複雑な生物の方が、霊魂がない単純な生物より生き残りやすい環境があって、そしてある生物は霊魂を持った複雑な生物として、この世界で安定することになったとか。
もちろんダーウィン的な進化論は、最初の生物の登場という(高等生物のいきなりの誕生という場合よりははるかに些細と言えそうな )問題こそ残るものの、少なくとも複雑構造の獲得に関しては、霊魂などというものを用意しなくても説明できる感じである。そして霊魂が存在するという仮説に関して、過去の多くの証明が、「そういうのが存在しなければ説明できないことがある」ばかりのように思われるから、実質的に進化論というのは、霊魂が存在しないことの重要な状況証拠とも言えるだろう( そう考えると、進化論により否定される霊魂の存在は、 相対性理論により否定されたエーテルとか、大陸移動説によって否定された陸橋のようなものかもしれない)。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
それ(進化論)が熱心な宗教信者に嫌われやすい理論ということも納得しやすい。
ただ、複雑な構造だけで、人間の精神が作れるかどうかは、今でも非常に重要な問題である。
現代の人間の状況を見れば、普通に、高度な精神能力が、(少なくともこの地球環境においては)生物たちの物質資源を巡る戦いにおいて有利なことはほぼ確実であろう。霊魂が獲得したものが高度な精神を持てるのだとして、霊魂あるいは優れた霊魂を得られたものが、そのような高度な精神を持てるのだとしたら、やはりそれを進化論に組み込むことは可能ではあるはず。
今は、遠い未来でもなく、そう遠くない未来の世界観において、完全に人間を再現したような知的機械を夢見ている人も多いだろう。霊魂と精神に関する哲学的議論においても、それは非常に重要なものだ。
哲学するとは死ぬことを学ぶことである
ここでの話はやや長い。
最初はキケロの、「哲学するとは死に備えることに他ならない」という言葉が引用される。
生死感や、年齢を重ねることについてなどの考えが語られるが、 現代とそんなに変わらないような感じもする。
実際、死ぬことがあらゆる苦しみからの解放と等しいと考えるなら、その時に悲しいと考えることはバカげているかもしれない。誕生したということは死ぬことと同じ。
100年後に生きていないことを嘆くのは、100年前に生きていなかったことを嘆くのと何も変わらないような感じもする。だが100年前に生きていなかったことを嘆くのを奇妙に考える人もいるかもしれない。
アリストテレスが、1日しか生きれない生きられない小動物について語ったことも、ここでは例に挙げられる。
その動物は朝の8時に死ぬのは若死にで、夕方の5時に死ぬのは老衰 。この短い生涯で、不幸だの幸福だのと考えることを笑ったりする人もいるだろうが、宇宙の時間に比べれば、人間の一生だって一瞬のようなもの。そして生きていない時間は、短いも長いもないようなくらいのもの。
食人種について
具体的に当然のことながら、新大陸(アメリカ大陸)を、「われわれの時代に発見された」などと表現していたりする。
 「独立以前のアメリカの歴史」多文化な先住民。移民と植民地。本当に浅いか
「独立以前のアメリカの歴史」多文化な先住民。移民と植民地。本当に浅いか  「クリストファー・コロンブス」アメリカの発見、地球の大きさ、出身地の謎
「クリストファー・コロンブス」アメリカの発見、地球の大きさ、出身地の謎
そういう説があったのだろう。古くはプラトンが語った、ジブラルタル海峡の出口の正面にあったアフリカとアジアを二つ合わせたよりも広い国土を持っていたというアトランティス島、その伝説の島とアメリカ大陸が、実は同じものという仮説は、あまり真実味がないというように語られたりもしている。
 「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
「アトランティス大陸はイスパニア(イベリア半島)に近かったようだから、大洪水でそれがアメリカ大陸の位置にまで動かしたなんて、とても信じ難い」とされてるが、そういうふうに考える人もけっこういたのだろうか。
そういうのが荒唐無稽と考えられるようになっていたとするなら、例えば20世紀に大陸移動説に反対した人たちは、案外冷静だったのかもしれない。
 「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
ところでモンテーニュは、「アメリカ大陸の民族に関して、少なくとも自分の聞いているところでは、野蛮なものとか、未開なものと言えるようなものは何もないように思う」としている。
ただし各人が自分の習慣にはないことを野蛮と呼ぶのならば話は別。事実、我々は自分の住んでいる国の意見や習慣を実例として理想とする他には、真理と理性の照準を持ってないように思われるとも。
やはり考え方が自然崇拝主義的である。
新大陸には完全な宗教があり、完全な政治があり、すべてのことについて完成された習慣もある。彼らは確かに、自然がひとりでに通常の信仰から生み出した果実を、我々が野生と呼ぶのと同じ意味で野生だ。しかし我々が人工によって変質させ、普通の秩序から逸脱させたものをこそ、実は野蛮なものと言うべきなのではないだろうか。
新大陸の野生は、それこそ真実で有益で、自然的な徳と本性が生き生きと存在している。我々の人工は、それを明らかに劣化させている面もある、堕落してしまった好みに合うように無理やり順応させているだけかのような。
また、敵対する者を殺して、その後に復讐のような意味で、それらの肉を一族で食べたりする習慣などを聞いたこと。ポルトガル人たちが行ったという、彼らを捕らえた時に、彼らを腰のところまで土の中に埋め、その上半身に矢を放ち、その後に首を絞め殺すという、新大陸の者たちとは別の殺し方をしたことについて。
「私は恐るべき野蛮を悲しむより、我々が彼らの罪を裁いているにも関わらず、自分たちの罪にかくも盲目であることを悲しむ」
モンテーニュは、少なくとも死んだ人間を食うことよりも、生きた人間を、まだ十分に感覚が残っているうちに、拷問や責め苦によって引き裂いたり、火あぶりなどで徐々に殺したり、動物に噛み殺させたりする方が明らかに野蛮とする。
そして、「我々はそういうことを書物で読んだりするだけでなく、この目で見て、生々しい記憶すら持っている。しかもそれは昔っからの敵の間ではなく、隣人や同じ国の市民の間で行われている。さらに悪いことに、敬虔とか宗教を口実として行われているの見てきた」
これらの話は、魔女狩りとかのことだろうか。それとも宗教的な弾圧とかのことであろうか。
 「魔女狩りとは何だったのか」ヨーロッパの闇の歴史。意味はあったか
「魔女狩りとは何だったのか」ヨーロッパの闇の歴史。意味はあったか
いずれにしても、我々の理性の基準に照らして、新大陸の彼らを野蛮と呼ぶことができるかもしれないが、我々自身と比べることで、彼らを野蛮と呼ぶことだけはできない、とここでは語られている。
想像力について
特に興味深い話の一つ。
現代でも例えば、スポーツなどをする人が、イメージトレーニングが重要だと経験することがあるように、 想像力は単なる遊びとかだけでなく、実用的に役立つことがあるのは明らかだ。ただしここでは、(現代においては物理的現象として説明されるようなことだが)当時は未知だった現象などを、想像力による作用(または副作用)でないかと、推測したりしている。
単純にファンタジー小説などでよく見るような、再現された古い世界観とは違う、本当に昔の知識人(哲学者)が考えた、ある種の宇宙モデルを少し垣間見ることができるだろう。
「強い想像は出来事を生むと学者たちは言う。私も想像の絶大な力を感じる者の一人である……他人の苦痛を見ていると、私まで身体的に苦痛を感じる。私の感情はしばしは第三者の感情を頂戴した。たえず咳をする人は、私の肺と喉をむずむずさせる。私は病人を見舞うにも、私がたいして気にもかけずさほど心にもとめていない人を見舞うときよりも、私にとって義理のある人を見舞うときの方が、ずっと気が重い」
病気の人に病気がうつってしまうかもしれないと、直接的に接触しないように気をつけたりする。それはもちろん、病原菌のような、病気の原因としての微生物、あるいは小さな物理構造が、空気とか水とかを媒介として、自分の体の構造に入ってこないようにするため。現代ではたいていそういうものだろう。
しかしそのような、小さな生物が人間にもたらす影響など、想像も難しかったかもしれない時代。モンテーニュは、そのような病気がうつるのは想像力の作用でないかと推測(そのような説を支持)したわけである。
実際に、想像とは何だろうか。我々の精神とか、心とかそういうことの原因が何であれ、想像というのは、考えから生まれるのは、かなり明らかであるように思える。
つまり心の動作が作り出している特殊空間、というよりある種の(これを物理空間と言えるかはわからないが)情報空間と言っていいようにも思う。
そして我々は、機械のネットワークテクノロジーのため、そのような(情報空間という)概念がなじみ深くなっている時代に生きている。わけであるが、想像された世界の模様を、例えば絵として表現できるのはもっと昔からのことだ。つまりは、自分にしか見えていないはずの情報空間を、(例えば現実世界とか呼ばれる)共有される領域において、間接的にでも出力し、まさに共有することは、モンテーニュの時代でも可能なことではあったはず。
そのような、古くからの想像世界共有方法と、現代のデジタルネットにおける共有とで、利便性以外にどんな違いがあるのか。
何かの作品情報(例えば様々な要素を、いくつもの細かい点(数値や記号)で分けた場合の、それらの組み合わせのパターン)を、人間の感性にわかりやすく変換するのと(縦とか横とかの実際の方向とか、色のスペクトルみたいな、複数の、つまりX次元の数の各方向の数値分布で保存できるような絵を、実際にその情報通りに、グラフィックとしてモニターに打ち出した表現。つまり画像情報から画像への変換と)、どんな違いがあるのか。
たとえ(現実世界をどのように考えるかで、変わってくると思う)根本の原理的に違いがあるとしても、少なくとも機能の流れとしては、かなり近しい印象がないだろうか。
それで、想像力が感染症などの原因になる世界観、あるいは(感染症のように)他者に影響を与えられる想像力が存在するという世界観をどういうものと考えればよいか。
まるで世界のあらゆる物質の背景に存在する基盤的ネットワークを、直接的にか間接的にか伝わりうる何かがある。想像力がそれ(ネットワーク)に影響を与えられるなら(そしてそもそもそのような背景ネットワークが実在するのなら)、 実際的に想像力というのは、自分の構造の外部の環境を変化させることもあるだろう(まさに現代的な魔法理論と言ってよいだろうか)。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
そして、おそらく現代の我々は、この世界の背景ネットワークの存在に関しては、むしろモンテーニュよりも有力そうな根拠を持っている。つまり、現に我々の多くが恩恵を受けているデジタルネットワークのテクノロジー。拡張性高く、間接的にでも共有可能な巨大情報空間は、確かに存在しているらしいこと。
それとも、全ての情報空間は、もともと世界に存在するようなものではなく、それら全ても人工物なのだろうか。
レイモン・スポンの弁護
宗教、信仰心の関連みたいなのが多いが、とにかく様々な話題を多く含む、長い節。というか、おそらくエッセイの中で一番長い話。
実質的にいろいろな話題を詰め合わせてるみたいな感じだから、この節だけで興味深い記述もそれなりにある。 特に(おそらくモンテーニュ流)の、哲学の神学論的側面に関して。
「……プラトンは、どんなに頑固な無神論者でも、危険が迫ったときに神的な力を認めるようにならない者はほとんどないと言ったが、彼は真のキリスト教徒には関係がない……ブラトンは言う「彼ら無神論者たちは、彼らの判断の理由によって、地獄や来世の間などについての物語は、つくりごとだと主張する。けれども、老衰や病気のために死が近づいて、それらを経験する機会がやってくると、彼らは、来世の状態が恐ろしくなり、死の恐怖から、新たな信仰で満たされる」と……無神論は、不自然で奇怪な説であり、いかに高慢で放埒な人間精神にもなかなか植えつけがたいものだ。けれども、自分は俗人とちがって世を改革する意見をもっているという虚栄と自負から、わざと無神論を唱える者も少なくない……
われわれの神聖な真理についての無知のゆえに、プラトンというこの偉大な霊魂(ただ人間的な偉大さ)は、もう一つの誤りにもおちいった。「子供や老人は宗教を受けいれやすい」というのがそれであるが、これだとまるで、宗教は、われわれの弱さから生まれ、そこから信用を得ているようなことになる」
「われわれは、自分たちにとって奇妙だと思われること、自分たちに理解できないことを、すべて非難する。同様のことは、われわれが動物たちについて判断をくだすときにも生じる。彼らは多くの点でわれわれに似た状態をもっている。それらの状態から、われわれは比較によって多少の推測を引き出すことができる。けれども彼らに特有のことがらについては、われわれはいったい何を知っていよう?
……われわれは象がいくらかの宗教心をもっていると言うこともできる。というのも、象は何度も沐浴して身を清めたあとで、われわれが腕をあげるようにその鼻を高くさしのべ、昇る太陽にじっと眼をそそぎながら、一日のうちの或る時間に、自分自身の本性から、誰にも教えられたり命じられたりせずに、長いあいだ思索と冥想にふけるからである。けれども、他のもろもろの動物たちにはそういう姿が見られないからといって、われわれは彼らに宗教心がないと断定することはできない。われわれに隠されていることがらは、われわれには何とも解釈することができない」
「……医学が世におこなわれて以来、どのくらい経つか? 聞くところによると、パラケルススと呼ばれる新参者は、古来の規則の全体系をくつがえして、「今日まで、医学は人間を死なせることにしか役立たなかった」と主張しているそうである。 私の思うに、彼はこのことを容易に実証するであろう。けれども、私の生命を彼の新しい学説の実験に供するのは、あまり賢明なことではないだろうと思う。
ことわざにも言う。「誰の言うことも信じてはならない。 人はどんなことでも言うことができるからだ」」
 「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊
「パラケルスス」錬金術と魔術を用いた医師。賢者の石。四大精霊