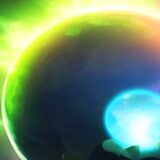生物学はいつ作られたか
生物学に興味を持ったピュシオロゴイ(哲学者)は少なかったと言われるが、例外的な人はかなり有名である。つまりアリストテレス(Aristotelēs。紀元前384~紀元前322)だが、多くの分野に影響を残した彼が、おそらく最もその生涯の時間を捧げたのが生物の研究だったとされる。彼は、自身が関心を抱いた様々な生物種の性質を記録し、時には解剖して、物理的構造としての生物を見極めようと試みさえしたとされる。
その功績から、アリストテレスこそ「生物学を作った生物学者」と称えられることも多い。ただしアリストテレス以前に、例えば生物という構造に注目した哲学者が皆無だった訳ではない。
ちなみに、ギリシャの哲学者たちの本で時々ある、魂というのは、たいてい『プネウマ(pneuma)』と呼ばれた、つまり生命力(生命という存在を成り立たせるための世界エネルギー?)というような意味合いと同義であるような印象が強い。
アリストテレス以前の生物研究
アルクマイオン。プネウマ分配システム
医学校は、紀元前5世紀頃にはあったらしい。医学というものは、哲学の登場と時期を同じくするという見方すらある。
ピタゴラス学派だったらしいアルクマイオン(Alcmaion。紀元前5世紀~紀元前6世紀)は、クロトンの医学校に属したが、彼こそまさに、実験的観察から解剖学的知識を生んだ最初の人という説がある。
彼は、感情、知識、精神、魂などの原因は脳である考えた。おそらくは感覚器官の機能を脳と関連付けて、それまでよりもずっと、生物を機械的に理解した。
心臓に血液を流す『静脈系(venous system)』と、心臓から血液を流す『動脈系(arterial system)』とを区別もしていたようだが、あまり強い根拠はなさそうだった。ただ彼の理論上、それらは睡眠に関係していた。静脈が働く時(心臓に血液が流れ込む時?)に生物は眠たくなり、動脈が働く時(心臓から流れ出る時?)に覚醒するというような。
ただ、その血管系の始まりは、心臓ではなく頭だったらしい。血管系というのはつまり、精神(プネウマ)を分配するシステムとか。
おそらく(意識も有する存在という意味での)生物の本質が頭(脳)にあると考えたアルクマイオンは、その点では時代の先を行っていた。彼以降でも多くの、生物を研究した哲学者たちが、生物の本質は心臓なのだと考えたから。
現代においては、脳の重要性はほとんど常識であろう。例えば心臓と脳をそれぞれ他人のものと取り替えてみるというような思考実験をしてみたらいい。たいていの人が、心臓を取り替えた場合よりも、脳を取り替えた場合の方が、自分が自分じゃなくなる可能性が高そうな印象でなかろうか。
そうした常識と逆のものが、古代ギリシアにはあったのかもしれない。
エンペドクレス。唯物論者に立ちはだかる生物という壁
『四大元素(four elements)』説で有名な、シケリア(シチリア)のエンペドクレス(Empedoclēs。紀元前490年~紀元前430)は、生物の発生や、視覚や呼吸についての機械的理論を提唱したりした。
例えば彼は、視覚は光を利用したものとして、目から出た光が当たった物を我々が見ていると考えた。おそらくエンペドクレス的な世界観では、外部要素が自身の生物構造のどこかの対応する要素と関わることによって、認識というものが発生する。
また彼は、光がある点から別の点に移るために時間がかかっていることも示唆していたらしい。
 「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
呼吸というのもまた、外部の、おそらく空気の要素と自身の対応する要素との相互作用であるが、人間は毛穴だらけであるから、空気物質との関わりは全身であるとか。
エンペドクレスは、元素説の提唱者とされていた。おそらくかなり唯物論的な考え方の哲学者だったと思われる。そして生物というのは、とても身近で神秘的な謎。その謎についての物質的な説明こそ、唯物論者にとって最も重要な壁だったのかもしれない。
またエンペドクレスには、カリスマ的な予言者かつ、魔術師的な医師だったという伝説もあって、死者をよみがえらせたことすらあるとも。
時代を考えると、魔術というものに、オカルトというよりテクノロジー的なイメージがあったかもしれない。すなわち優れた医療は、生物構造を利用した魔術であったとか。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
またエンペドクレスにとって、魂の有る場は、脳でなく心臓だったらしいが、彼にとっての、生物の解剖学的詳細には謎が多いという。
エンペドクレスの唯物論のモノというのには、愛(love)と言われるような感情もあったかもしれない。
彼は世界について、「愛」と「憎しみ」が創造と破壊の循環をもたらすことを語ったとされる。そのような循環の第一段階で、愛(という化学反応?)が生物組織を形作り、そのような組織から単一器官が、あるいは単一器官のみを持つ単純な生物が発生する。そして増大する愛は、物質世界の回転率を上げて、バラバラだった各器官を結びつけ、複雑な生物を作っていく。そうして発生した全体の、ある部分はオスの生物、ある部分はメスの生物になった。
このランダムな発生と複雑構造の形成過程で、おそらく生存に有利な者が生き残り、現在の生物群へと繋がっていく。
最初のランダムな混ざりあいのために発生した様々な異常なキメラは、自然の選択システムによって消えていったわけである。素直に考えるなら、ある種の進化論的発想とも言えよう。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
ギリシア哲学の後世の注釈者の1人である、キリキアのシンプリキオス(490~560)は、驚くべきことにそのような仮説(自然環境が、自動選択的に現在の生物種という枠を設定したというような説)が、実は初期の自然哲学者の間ではかなり一般的だったと書いていたという。
ヒポクラテス。心臓と血管システムの研究
生物学は実用的な医術のための研究であったろうか。
エンペドクレスとほぼ同じ時代に、コス島で医学校を始めたヒポクラテス(紀元前460~紀元前370)と、おそらくは弟子たちの様々な研究成果を集めたとされる(ただし多くの部分が、おそらくもっと後世に書かれたものらしい)『ヒポクラテス集成(Corpus Hippocraticum)』なる論文集は、病気という現象に関して、基本的には自然原理に原因を求めているという。
中には、生物発生という現象を、深く哲学的に考察したものも。例えば「生物の形成にはいかなる原因があるか、魂というものはどのようなものなのか、善とか悪とか、死ぬとはどいうことか」というような感じらしい。
ヒポクラテス、あるいはコス学派は、合理的な医学を確立したと言われもする。
彼らによると、丁寧に生命を与えるのはその絶え間ない心臓系の活動であるが、そのために発生した過剰な熱を減らすために、冷やすための空気を取り込む肺が機能しているというような。また、体に吸収された水もまた、冷却の役割を担っているとか。
(ピラミッド型ともされた)生命システムの核である心臓は、固有の生成によって栄養を得て、さらにそれら(の栄養)を体の他の各部分に巡らせる。
心臓自体についても、コス学派は、2つの結合した心室が存在し、生成される熱に変えるため、右心室は左心室よりも大きく、しかし左心室は右心室より厚いとした。体の各部に栄養を運ぶための血液は右心室にしかなく、左心室には魂の残り部分と関連する心と精神を収容していたとも。
実際、哺乳類の心臓は2心室2心房で、それは酸素を取り込んで全身に供給する血液と、そうでない血液とを区別するための見事なシステムとなっている。
どうもコス学派は、心房部分について、空気を溜め込むための容器にすぎないと考えたらしい。
プラトン。生物創造の神秘的説明
弟子のアリストテレスも含めた後世の多くの哲学者、科学者たちに、神秘主義者とバカにされがちなプラトン(Plato。紀元前427~紀元前347)だが、彼の神秘的なその説明は、世界だけでなく、生物の誕生にも及んでいて、謎を説明しよう、理解したいという考えは強そうに思える。
どういうものかはともかく、生物の構造はつまり、物質世界の中での必然的な存在。それは元素の集合体の中に存在している。しかし火とか空気とかいった周囲の元素の影響で(溶けていくというものなのか、混ざっていくというものなのか)そのための劣化を避けられないというようなシステムを、プラトンは示唆する。
本質を掴みにくい詩的な文章からは、しかし例えば神々(あるいは第一原理と考えるべきかもしれない)が、(劣化を避けられないために)死ぬことが必然的な生物(というかおそらく人間)がそれでもこの世界において長く生きていけるようにと、さらにシステムを拡張させた原初の流れ(創造?)も読み取れる。
人間の同族を、他の形態や感覚機能と混ぜて、別の生きものとして植えた。そうして、農耕によって育てることができる植物が誕生したとか(とすると、人間の食物になる植物は、人間に近しいものだから、容易に取り込みやすいというのだろうか)
まるで一部の植物を、人間に都合よくなるよう品種改良した古代人たちの話を、大げさに神話化したような印象も受ける。しかしそのような、歴史を参考にしたという認識がプラトンにあまりなかったか、あったとしても強くなかったなら、それは彼の理解として、すでに、誰が農業を始めたのかとか、そういうことがまったく謎だったということも意味していると思う。
遺伝とか、進化理論とかを考慮に入れないとしたら、最初から農業で利用される植物がそのような植物だったと考えることは、そうおかしくないかもしれない。つまりは、世界が最初に作られた時に、特定の生物のための植物も存在していたか、あるいはそういう植物が特別な何かの流れで生まれていたというような。
またプラトンは、植物を生物か、そうでなくても生物世界の一部というように扱っている印象も強い。
輪廻転生、すなわち生物の生まれ変わりという事象を前提としているような理論も見られる。
臆病だったり、不正をした男は、次の誕生時は(下等な?)女に生まれてしまうとか。
プラトンの言説は、まるであらゆる生物の基礎となっているのが人間(の男)という生物で、後はその理性レベルに応じて、神が調整することによって適当な生物が造られていった、というような世界感を思わせもする。
アリストテレスの生物学
アリストテレスは、この分野を開拓した、言うなれば最初の生物学者として語られることも多い。
アリストテレスは、おそらく紀元前335年頃に、アテナイ郊外にのリュケイオンに学園を開設。そこでアリストテレスは自然学の講座を行っていたとされるが、講義内容の大半はおそらく生物のことだった。
ところで、解剖学的な生物研究に関しても先進的だったとされるアリストテレスだが、彼の動物の本で現存しているものには、『図解(ダイヤグラム)』がない。 残念なことに、これは彼が文章のみですべてを理解しようとしたとかではなく、どうも、様々な生物の抽象的図解をまとめた『解剖学』なる本があったらしい(だが失われた)
現代の我々が、アリストテレスが理解していた生物学的知識をいくらかでも知ることができるのは、『動物誌』のような専門書がいくらか残っている幸運もある。
アリストテレスが、生物学という分野を始めたと言われるのは、つまり彼が、ピュシオロゴイたちの哲学理論と、経験主義者たちの実用知識を結びつけた功績ゆえともされる。その研究方法も、いくらか必然的と言えるのかもしれない。
アリストテレスは、彼が知ることができた多くの動物種に関して、その形態的特徴や習性などを参考に分類表を作ったもとされる。乱雑に散らばっていた生物の記録の中から、信頼できると思われるものをまとめて、後世の生物研究の基礎を築いたのである(このような方法は、先人から多くを学ぶ現代の研究者たちの科学研究の方法にも近い。大量のサンプルを集めたデータベースには質の悪い情報も多いものだが、そういうものを排除していくことから、様々な研究が始まる)。
彼はあらゆる動物の観察結果を集め、部分的特徴を参考に整理していった。そうして彼は、例えば多くの動物学者に1000年以上先んじて、クジラ類を、同じく胎生という特徴を共有する哺乳類の同族とした。
 「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識  「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
学的方法と魚
古代ギリシアでは、だいたい魚と同族と考えられていた海の生物への関心は高かったとされている。
アリストテレスも、多くの海の生物を研究した。 時代に先んじて、イルカ類を哺乳類の仲間と(正しく)提唱したことは、今となっては有名な話であろう。他にも様々な水生生物の形態や食性、生殖や移動に関する習性などを記録した。
彼が特に関心を寄せていた生物は、軟体動物門頭足綱(Mollusca Phylum Cephalopoda)のコウイカだったらしい。
ただしアリストテレス以前、魚について書かれた本で、 少なくともよく読まれていたものは、学術的な専門書というよりも、魚の利用法について書いた実用マニュアル(手引き)的な本だったようである。
美食のダイダロス(the Daedalus of tasty dishes)、すなわち「食の分野におけるたぐいまれな発明者」とも称された、シケリア(シチリア島)のアルケストラトス(Archestratos)などは、魚の捕まえ方から美味しく食べるための料理法まで本に書いたが、 生物学的な意味での関心などはおそらく大して持っていなかった。そして彼の態度がおそらく平均的なものだった。魚は人間が豊かに生きるための食料にすぎなかった
分類の開始。膨大な記録から最良のものを選ぶ仕事
アリストテレスの哲学(科学)は、常に『ファイノメナ(phainomena。現われ)』から始まっていたとも言われる。 つまりは視覚的に認識された形態とか状態。(そんなことをしようと試みるとしても、物理的に不可能だったろうが) アリストテレス自身が、彼の研究対象全てを見て回ることから始めたという訳ではない。彼ももちろん、自分自身で直接確かめることができるようなものならそうしただろうが、実際には多くの基礎的情報に関して、彼は、彼が信頼できると考えた様々な書物や証言に頼っている。
様々な研究者の記録のネットワークという頼りになる知的武器は、現代までずっと、学者にとって最も重要なものと言えよう。そういう意味で、アリストテレスはやはりとてつもなく大きく科学に貢献していると言えよう。
いろいろ学的興味からもズレた者たちの適当な記録ばかり溢れていたろう状態で、それらから自分にとって(つまり後に生物学と呼ばれる分野にとって)実用的なものばかりを選び抜き、まとめ上げたのが彼なのだ(とされている)から。
つまり彼は、集めた様々な生物のデータを整理した。 理解のための分類をすることを始めた。例えば翼を持つ動物、角を持つ動物、無血動物というように。
アリストテレスが持つことができた膨大な動物のデータは、 家庭教師として親交あったとされるマケドニアのアレクサンドロス大王が提供したものという説もある。敬愛する師の、動物という謎への飽くことなき知的欲求に関心を抱いたアレクサンドロス大王が、自らが支配する領土のあちこちから、あらゆる生物をサンプルとして集めさせたとか。
しかし、この説の出所はプリニウス(Gaius Plinius Secundus。23~79)らしいが、肝心のアリストテレス自身は、生物研究に関して、アレクサンドロス大王の助力を思わせる記述など全く残していない。
占いの本も参考にしていたか
アリストテレスは、 情報の信頼性には気をつけたかもしれないが、情報源の媒介自体はほとんど気にしなかった節がある(おそらくそんなことを気にしていたら、それだけで手がかりが大幅に減少してしまうからだろう)。
例えば彼は、神話を語った書物の中の生物の描写とかでも普通に拾っている(ただし、例えばキリスト教社会において、科学研究の根拠または参考に、聖書の記述が持ち出されたりとか言うことは、近代でもあった)。
また、哺乳類の生体構造に関して、『胆嚢(gallbladder)』を重要視していたようだが、それは彼が、内臓予言を書いた占い師の本を参考にしたからとも言われている。胆嚢は肝臓で作られた胆汁(ある種の消化液)を溜める器官。
占いの本には、敵対している動物同士とか、仲間同士で集まるとされた動物などの話もあって、動物の行動を考えるための参考にされた可能性も高い。実際アリストテレスは、ワシとハゲワシやサギやヘビ、クモとヤモリやカリバチなど、自然界の戦いの話も記録している(現代人が見る場合、荒唐無稽というより、ファンタジー的に感じる話も多いかもしれない。いくつかの鳥が他の鳥の卵を泥棒するなど)
そもそも医学関連を抜きにして考えた場合、彼以前に、生物を主題とした論文を書いた者もおそらくほぼいなかった(そのような書が現存していない)とも。
懐疑的、論理的に考える
少なくともアリストテレスは、 大量に集めた怪しげなデータを何も考えずに鵜呑みにしていたわけではないだろう。
体のバランスを保つため石を運ぶツルは、食べたものを金塊にして吐くとか。ライオンの出産は子宮を外に出すことから始まるとか。西ギリシアの、肋骨が七対しかないリグリア人の頭は、体から切り離されてもしばらく喋り続けるとか。とにかく、彼が信じることを拒否した情報も多い。おそらくは、どこかに紹介することすらなく、選別の段階で消去された話も多いだろう。
例えば、切り離された首が喋らないという理由に関して、アリストテレスは、そもそも言葉を喋る原理として肺からの息の圧力があると思われるから、体から離された首だけで言葉を語れるはずがないと。実際、人は喋りは、『声帯(vocal cords)』という膜を息で震わせているというような仕組みとされているが、アリストテレスの論理はなかなか納得しやすい。
アリストテレスは、たいていの人が常識的に考えていることでも、改めて考え直すことが、真の理解のために必要であることをよく理解していた。
海の生物に関してアリストテレスに多くの情報を提供したろう漁師たちは、例えばメスの魚は食べた精子を 地震の卵子に受精させるというような話を語っていたらしいが、アリストテレスは、それは単に求愛行動だろうとした。
旅行記が伝えていたこと
アジアやアフリカといった、遠い国での話を書いた旅行記も、アリストテレスにとって重要な情報源だった。
ペルシア宮廷で侍医をしていたクニドスのクテシアスの書いた、ペルシアとインドについての本は、アリストテレスにとって、信頼していいのか微妙なラインだったらしい。一方で、有名な歴史学者ヘロドトス(Herodotus。紀元前484~紀元前425)のことなどは、かなり信頼していたようだと言われる。
クテシアスに関しては、例えば、トラのことらしいのだが、彼が語る、上下に二列の歯を持つという胎生四足類(哺乳類)マルティコラス(martikhoras)のことを信じていいのかアリストテレスは迷う。しかしライオンと同じように毛で覆われているとか、人間に似た顔、サソリの尾のような毒針付きの尻尾とかは、実際のトラともかなり違う印象がある。
まだまだ先にまで、息の長い伝説として残るユニコーン(一角獣)についても、アリストテレスは懐疑的に考えながらも、はっきり否定はせず。
 「ユニコーン」伝説の生物である一角獣。実在するイッカク
「ユニコーン」伝説の生物である一角獣。実在するイッカク
ヘロドトスのことは、アリストテレスは確かに 彼を信頼していたのだろう。自分の目でちゃんと確かめたことだけを記録しているという彼の言葉も含めて。
しかし、ヘロドトスが出所らしい情報に、怪しげなものが少ないかといえば別にそういうわけでもないようだ。 アリストテレスも、おそらく疑わしいと思った情報に関しては、「~と言われている」というような慎重な書き方をしている。
ヘロドトスの話として、例えばカリア(アナトリア)女司祭はひげを生やすとか、ラクダがウマとケンカするとか、エジプトの動物はギリシアの同種のより大きいなどがあった。
エチオピアに空飛ぶヘビがいて、確かにその骨を見たという話などは、アリストテレスも怪しんでいた節があるとも。
いくつかの話は否定もしたが、その場合はヘロドトスの名を避けたとも。しかし名前を出している否定もないわけではない。アリストテレスはヘロドトスの「エチオピア人の精液が黒い」という話は間違いとした。
ゾウを解剖したか
ゾウに関するものなどは、アリストテレスの記述の中でも特に不可思議なものの1つとされている。間違っているのがおかしいのでも、正しいのがおかしいのでもなく、真偽が入り混じっているのが奇妙なのである。
巨大な体で、長い鼻に牙というような、表面上の特徴だけではない。胆嚢を持たないことや、肝臓の大きさ(ウシの四倍ほど)、脾臓の大きさ(ウシより小さい)など、アリストテレスは解剖学的特徴までいくらか知っていた。もちろん、当時の旅行記などにそこまでの詳細が書かれているものがあったとは考えにくい。
ではアリストテレスは、実際にゾウを解剖してみたのか、あるいは そのような場に立ち会ったのか。
一応、紀元前三三一年、ガウガメラ(イラク北部らしい)で、アレクサンドロス王がペルシア人との戦いに勝利した際、捕らえた戦闘ゾウの1頭を、アテナイに送り、それをアリストテレスが解剖してみたという伝説が残っている。
しかしアリストテレスは、ゾウの後ろ脚は、前脚に比べてかなり短いというような、見てすぐわかるような特徴を間違えてもいるのである(ただし、垂れ下がった皮膚のひだに覆われたゾウの後ろ脚は短く見えるとされる)。
他にも、アリストテレスが実際に確かめたのかどうか、微妙な知識が数多くある。
部分的には、当時の常識とか先入観が原因の間違いもあったろう
ハイエナの生殖器
哺乳類には7つの頸椎(首の骨)があるが、アリストテレスは、ライオンの首には骨が1つだけなのだとした。
しかし彼の生きた時代のマケドニア近く(つまり彼にとってはそう遠くもないはずの場所)にはインドライオンがいたという。
ダチョウは足に鉤爪を有するが、アリストテレスはそれを『蹄(hoof)』とした。
ハイエナに関しては、ヘロドロス(Herodorus。紀元前4世紀頃)という人が伝えていたという、全個体が雄雌の生殖器を持つ、つまり雌雄同体の動物という説を否定した。
アリストテレスは、ハイエナが雌雄同体でないことだけでなく、 なぜそのような勘違いがあるのか、その理由までしっかり認識していた。つまりハイエナは『肛門(anus)』の近くに窪みを形成する分泌腺(肛門腺)を持っているのだが、これが雌の生殖器に間違えられやすい。雄の生殖器(penis)はイヌのに似ているが、目立たない雌の真の生殖器(vagina)は、問題の部分(肛門腺)のさらに下にあると。
アリストテレスとテオプラストス
おそらく十代後半頃から、20年ほど、学び、時には教師として教えたと思われるアカデメイア(プラトンの学校)を去ったアリストテレスは、アッソスの君主ヘルミアスに招かれ、そのアッソスでわヘルミアスの姪であるピュティアスと結婚。
しかし間もなく、ヘルミアスがペルシア帝国に捕まると、難を逃れようとレスボス島に移住した。
アリストテレスの生涯の中で、レスボス島で暮らした2年ほどは記録に乏しい空白期間とされている。しかし一説によると、彼はこの時期この島で、生物の分類リストを作るという仕事を開始したのだという。
レスボス島にやってきたアリストテレスには、奥さんの他、おそらく哲学者仲間のテオプラストス(Theόphrastos。紀元前371~紀元前287)も同行していた。彼は年下の学友であるが、アリストテレスの親友にもなって、最終的にはアリストテレスの知的財産も受け継ぐことになる(テオプラストスとアリストテレスはアカデメイアの学友だったわけではなく、普通に2人はレスボス島で出会った説もある)
テオプラストスというのは「神のように語る」という意味のあだ名(正確な本名は不明)で、彼はまた、”動物学の祖”と呼ばれるアリストテレスに対し、”植物学の祖”と呼ばれる。 米子共同研究者だった彼らが 動物と植物という研究対象を それぞれ意識して分けていたという説もあるがその辺りの詳細は不明。 しかし現存していないものも含めて、おそらくアリストテレスは動物の本を、テオプラストスは植物の本を多く書いたというのは、かなり確かとされる。
テオプラストスの植物学の本から読み取れる彼の方法は、アリストテレスにかなり近いとされている(というかアリストテレス流の方法を、動物でなく植物に適用してみたような)
彼は各植物の部分的特長を見出して、「高木、低木、亜低木、草本」というように分類した(この分類は、そのままルネサンス時代(15世紀くらい)まで語り継がれていたらしい)。
さらには、なぜ実り、なぜ枯れるのか、植物の成長に関して環境の原因などを調査した。
ただし、アリストテレスとテオプラストスは、思想家としてはかなり異なるタイプだったという説がある(だからこそお互いがお互いに影響を与え合う、よい関係を築けたのかもしれないが)。
アリストテレスはどちらかと言うと理論家で、時には大胆な仮説を唱えたが、 それに比べると、テオプラストスは慎重な経験主義者的だったようだ。
片方が動物、片方が植物を研究対象として重要視したことは、共同研究の役割分担的なものだった可能性はある。とすると、1つ気になることはやはり、どちらがどちらを、自分の研究に誘ったのかということだろうか。
解剖して研究
アリストテレスは、解剖学的研究に関しても、かなり先進的だったとされる。
そもそも解剖というのは普通、手先の器用さはもちろん、優れた観察眼がなければ実用的にもならない高度な技術。死後間もない死体を切開した時にまず見るのは、たいてい体液の沼と、微妙に識別できるかできないかというような各部ともされる。
アリストテレスは自分の研究方法(解剖の利用法)が、生物の構造を理解するために非常に役立つという自信も持っていた節がある。
人間を解剖したことはなかったか
「まずはじめに人間(anthrépas)の各部を理解する必要があろう。我々は物の価値を、まず我々がよく知っているものによって判断するものだ。当然、人間というのは、我々にとってもっとも身近な動物だ」
そのようにも述べたアリストテレスは、おそらく師のプラトンほどには、人間という物を特別なものと考えなかった。
プラトンは、世界の生命の創造を考え、文字通りに人間が最も基本的な生物であり、他の生物は人間を基準にしたり調整したりして生み出されていったもの、というような物語まで残している。
アリストテレスはもっと冷静に、人間は典型的な動物ではないと考えたようである。人間には手があって直立歩行とか、多様な目の色とか、両まぶたのまつげとか、特異的な特徴があるから。
しかしアリストテレスが、まさに身近な動物である人間を解剖したことがあったかはよく議論された謎。
ギリシア人は仲間に素晴らしい敬意を表し、死体も丁重に扱ったという話がある一方で、古代ギリシア世界にはもちろん多くの異国人奴隷もいたとされる。
しかし、彼の残した人体内部に関する記述の曖昧さや間違い(他の多くの哺乳類と同様に、子宮が2つあるなど)こそ、まさに事実を示唆していると考える向きもある。
ようするに彼は、人間の内部構造を考えるにあたって、基本的には他の近しいと思われる動物(哺乳類)の構造を参考にしているため、人間特有の構造(例えば子宮が1つしかないこと)などをあまり知らなかった感じでなのである。
血液循環システムの観察
アリストテレスは、人間はともかく、動物はいくらか確実に解剖を行ったはずとされる。動物の殺され方による調査のしやすさの違いとか、解剖の際に特定器官の位置がズレてしまうための見落としを警告したりもしていた。
さらに、強い関心を抱いていた血管系の研究に関しては、「解剖学」や「動物誌」を利用するのがいいとしたが、つまり彼は、そうした(動物の内部の)研究を行うにあたって、彼の方法を推奨していたらしい。
アリストテレス以前から、体内を巡る血液の流れは生物について考える哲学者の関心の的であった。
血管と心臓との関連に気づかない者もいた。左右に別れた血管系に異なる役割(血液を送る器官の違い)が与えられることもあった。
アリストテレスは、この血液を巡らせるシステムの核が心臓であることを理解していたとされる。彼は心臓から血液が流れる『動脈(artery)』と、心臓へと血液が流れ込む『静脈(vein)』を区別しなかったらしい。血液各部に細かい名称も付けなかったようだが、心臓に繋がる動脈の本幹部とも言われる特に太い『大動脈(aorta)』は『アオルテ(Aorte)』、同じように動脈の本幹部と言われる大静脈を『大血管(great vessel)』と呼んでいた。
アリストテレスは、大血管から枝分かれする血管、各部で細い血管(毛細血管)として肉へ消えていく、(まだまだ血液の経路に混乱があり、間違いは多くとも)そのネットワークを認識し、記録したとされる。
酸素を身体中に供給する血液と、供給してきた後の血液を区別できるような仕組みが、哺乳類の心臓にはある。つまりは2心室2心房という4つの区画分け。
アリストテレスは、人間の心臓の区画は3つだけとした。はっきりどこがとは言えないが、どこかとどこかを一緒くたに考えてしまった結果だろうとされている。
生命の核となる器官
アリストテレスも、2つの心室を認識していた訳だが、どちらも血管を通して肺と接続していると考えて、心臓へと空気が流れ運ばれるというシステムも見いだしていた。
2心室のスケールの違いも、取り込んでいる空気の量が関係しているとも。
彼が理解したそのような心臓を中心としたネットワークは現代的な考え方にも近くなっている見事なものだが、 やはり心臓の役割に対しての過大評価は目立つ。彼は全ての血管のみならず、全ての神経の起源を心臓と考えたともされる。
つまりアリストテレスもまた、心臓こそ魂、生命の核となる重要な器官と考えた。
彼にとってのプネウマ(生命力)は、おそらく魂の一部であり、 呼吸により取り込んだ空気は、直接的にそのような生命力と関連してるわけではなく、やはり空気の役割は心臓を冷やすこと。
また、脳もまた心臓を冷却するための器官と考えたらしい。
古代ギリシアの進化論
古代ギリシア流の進化論というような説の起源が、アリストテレスでないことはかなり間違いない。
エンペドクレスは、おそらく第一原理という意味での愛の力は、世界の創造の初めの時、単純な単一器官ばかりをランダムに発生させたとした。様々な器官もまたランダムに次々結びついたが、生存に適した組み合わせの者だけが生き残って、現在の生物群になったというような説を唱えていたとも。ただし、この仮説のそういう(進化論の自然淘汰を思わせる)詳細はかなり後世の人の記録頼りらしい。
エンペドクレスの説は、生物種の自然選択は遠い過去の出来事で、いわば現在の安定した世界を作るための流れであったというもの。つまりは現在の各種はもう、ある種として固定されているというもののようである。
アリストテレスはさらに進んで、選択はこれまでだけでなく、今も続いている可能性に触れた。
現在の我々に馴染み深いダーウィン進化論は、世代から世代へと部分的特徴を伝えていく(その際、時には部分的変異が生じたりもする)遺伝システムが基礎となる。
アリストテレスは、 変化が今も続いているという点では独自的なものだが、自然選択の理論そのものはエンペドクレスのに近いとされる。つまり生物の各個体は、他個体から何かを受け継ぐというより、(ランダム性の高い)発生のメカニズムのために多様なパターンを生じさせて、その中で適した種が生き残るというような。
しかしそうした選択が今も発生しているのなら、なぜ生物の多様性はもっと無茶苦茶でないのか。見るべきスケールの問題かもしれない。つまり、大スケールだけでなく小スケールでもそれが起きている感じがあるのだ。例えば人間の女の子宮の中で子が発生する時にも、物質のランダムな混じり合いが様々な形を形成していくわけだが、結局のところ人間の子宮の中にふさわしいような形の生物、つまり人の子供ができるというような。
あるいは前成説的な、つまりは、ある生物はすでにかなり未来の子の世代まで、体の中に種をすでに持っている、というような世界観も議論されたかもしれない。しかしそういうことでもないなら、アリストテレス流の生物発生は、宇宙生成の理論的である。
後世の多くの哲学者や神秘主義者にも支持された、巨大なマクロコスモス(宇宙)と、その中で存在するミクロコスモス(生物)というような、階層構造的世界観の印象もある。
石筆ウニのトゲはなぜ長くなったか
アリストテレスは、レスボス島近くの海底に生きているという、体に比べてかなり大きくなトゲを持つウニのことを記録したことがあった。それはおそらく、石筆ウニ(Cidaris cidaris)という種なのだが、アリストテレスの時代には、排尿の痛みを和らげる薬(の素材?)として知られていたらしい。
アリストテレスの興味はもちろん長いトゲにあり、 どうも彼はそれを、機能的なものというよりも余剰的なものと考えたようである。
つまり、実のところそのような長いトゲは、そのウニには必要ないのだが、余分な質料がそうした無意味な構造を形成しているというような。
アリストテレスは唯物論を嫌っていたともされるが、形相(形)は質料(素材)なしにはありえない。とは考えていた。
アリストテレスは血液や精液、肉や骨や毛といった生物を構成する細かな部分を『等質部分(ユニフォーム・パーツ)』とした。
アリストテレスはその等質部分、さらにはそれらのさらに集合で成る生物の各器官、そして生物個体に関して、実際的には元素の集合ではあるのだが、本質的には集合体というより固有の物として扱っていたという見方がある。さらには、それら固有の部分ごとに、柔らかいとか、乾燥しやすい、というような様々な性質があるとか。そしてそれら固有の部分の性質が、例えば極端には骨のある生物、骨のない生物というような、動物種ごとの基本的性質と関連する。
アリストテレスは動物間で、明らかに等質部分が異なっていることは、生活する地域の気候とか、食事とかいった環境に関係していると考えたらしい。
ウニの長いトゲについては、まさに環境のためのもの。つまりは、食べ物を上手く消化するための暖かさが不足している水域で、上手く機能的部分として取り入れることができなかった余計な部分が、やはり寒さにより個化されて(そのために排泄物として捨てれもしなかった?)、結局硬く長いトゲになったのだという。
種の特徴の説明(それがどのようになったか)というよりも、ある特殊な個体(または群)の特異な形質の説明のようでもあるが、アリストテレスは遺伝学的な視点など持てなかったと思われるから、これは仕方がないだろう。
このウニのトゲに関する説など、アリストテレスは、目的論的な考え方以外の方法でも、生物の形質などの原因をよく考察していた。つまりそれが何のためかでなく、単になぜあるのかと。
プラトンとかに比べると、機械的に捉える視点がアリストテレスには多いようにも思われるが、そういうところかもしれない。古代ギリシアどころか、おそらくダーウィン進化論以前、生物を考える上で、目的論は常にそれ自体が議論の的だったともされる。唯物論者か、人間と動物の生物としての本質に明確な壁を設けた者以外、ほとんどの生物学者は、目的論の誘惑に逆らえなかった。アリストテレスが全体の中のほんの少しでも、定められた目的論より生理的特性のような原理で生物の多様性を説明しようと試みたことは、まさしく理性の勝利と言えるのかもしれない。
ただし唯物論者ではないアリストテレスは、プネウマとか第一原理については神秘的に考えていた感じで、その上で、集合体から形成される高次元の物質世界においては、様々な機械的法則も働く、というように考えていたようである。例えば子が父に似る原因は、プネウマのシステムが似た形相を胚に与えるのもあるが、精子という質料の加熱と冷却も関わるとしたり(例えばそれが、兄弟が全く同じような形態にならない理由とも考えたかもしれない)。