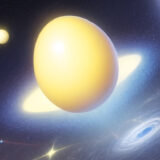人種の本質的優劣によるランク付けの謎
正確なきっかけとかは今となってはわからないだろう。本当の始まりで言うなら、それこそある人たちの集団が、別の人たちの集団と知り合い、「彼らは自分たちとは違っている」と少しでも考えるようになったのが始まりだった、と言えるかもしれない。
18世紀や19世紀は、特に科学文明が発展していたヨーロッパにおいて、 様々な迷信が取り除かれ、そしてそれまでは奇妙ともされていたいくつも科学的な仮説が説得力を増した。
例えばこの世界には、最初から人間がいたわけではないのかもしれない。人間がいたのだとしても、その始まりは普通に考えられていたよりもずっと古いかもしれない。そしてある生物種が、もしかしたら永久に消えてしまうのかもしれない絶滅という現象。
ダーウィンが『種の起源』を発表するよりも以前から、「進化理論」というのも、普通に議論の対象であった。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
そしてそうした中で、当然ヒトという生物、つまり我々の起源や、自然界における本当の立ち位置なども、多くの人の興味関心を集め、科学的な研究の対象となった。
だが、そこには初めから、それまで数多くの宗教や文化の思想などの中で常識として根を張っていた、非常に強い偏見が影響を与えていた。
つまり、この世界の全ての動物から、人間という特別な種を抜き出してみたとして、その人間たちという集団の中でも、本質的に決まっている、はっきりとした生物学的基準による性能の優劣、ランク付けがあるのだという思想である。
常識的だった自然ヒエラルキー
ある時期のヨーロッパにおいては、社会の権力者であろうが、尊敬される知識人であろうが、白人種を頂点とする自然ヒエラルキー(階級)は存在しているのが当たり前すぎて、疑いを抱くこと自体が難しいようなことであったろうと思われる。おそらく(当時の基準からしても)非人道的とされるような「奴隷制度を正当化したい」というような願望も後押ししていたろう。
人種がどのくらいの数に分類されるかということも含めて、いろいろな説があったが、かなり広く共有されていた認識として「白人(ヨーロッパ系)>黄色人(アジア系やアメリカ先住民)>黒人」という順位があったとされる。
そうした(今のところ大した根拠はないと考えられている)人種のランク付けという思想は、実は現代にまで尾を引いている。なぜか生物史の中では後の時代、つまり「最近進化して現れた種が優れている」というような考え方があって、やはり最初に生まれた黒人が劣っていて、最後に現れた黄色人種が一番優れている、というような。
 「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
奴隷制度の正当化の理由になったか
しかし最も優れている人種とはどのような存在なのか。それはようするに賢い存在(であったのだろう)と思われる。人間は賢い生物というイメージも強いから。特に優れた人間は、知能が高い人間というような。
肉体的には劣化したという考え方もあって、その場合には黒人が一番バカだが、代わりに力が強いというような発想もある。そういう考え方は、社会の中での奴隷制度とかの正当性を強めてきた。
ただし、人種に優劣があると考えている人であっても奴隷制度は悪しき習慣であると考える人もいる。例えばダーウィンも、明らかに人種間の優劣を認識していたが、一方で彼は奴隷制度には反対していたとされる。
劣等人種を救えるか否か
とにかく、人種のランクづけの妥当性は当たり前であった。それは、奴隷制度のようなものに強く反対している者たちにとってもだ。
ようするに強硬派と呼べるようなあるグループは、「黒人は劣等で、生物学的地位として奴隷が当然。彼らの劣った文明を植民地化することも慈悲深い行為」とした。一方で柔軟派と呼べるような別のグループは、「黒人は劣等だが、人々の自由に対する権利は、その人の(知能)レベルに依拠するものではない」としていた。
柔軟派グループの中でも、黒人を社会の中でどのように扱うべきか、いろいろと議論があったようである。
人によっては、知能レベルというのは、 知識を学ぶことが単に難しいというだけというような程度の認識で、例えば低い知能レベルに合わせた適切な教育を順序よく行うことで、彼ら(黒人や黄色人種)も白人レベルにまで高めることができる、というような説もあった。
伝記がよく取り上げる話について
ちょっと興味深いのが、近代における白人国家の奴隷解放の経緯の、特にピックアップされがちな部分。
奴隷解放の物語として、後世でよく、例えば映画とかで取り上げられるようなものは、政治家や宗教家の人道的な面が強調されてるような話が多いような感じがしないだろうか。
しかし個人的には、人種の違いというものをしっかり研究し、そして少なくとも知能レベルにおいて、そんな決定的な差があるような証拠はないと主張した科学者の意見とかの方が、説得力としても強いように思う。
例えば(当時は、宗教的信念が今に比べて大衆の心の中で強かったことを考慮に入れたとしても、おそらく)「神の前ですべての人種は平等であるはずだ」とかいう主張より、「2つの人種の脳を比べてみたところ、知能の違いの優劣さを想定できるような違いなど何もなかった」とはっきり言われる方が、何もかも明らかで、衝撃的でもあろう(つまりメディアが好むテーマにもなりうるだろう)。
もちろん物語としては、「奴隷の人たちがいかに残酷に扱われてきたか」というような所を強調したほうが、大衆の心に響きやすいというのも、我々は経験的によく知っているだろう。だがやはり、客観的な示唆や証明があってこそ、そういうドラマ(その悲劇性)もより理解しやすくなるのもまた事実でなかろうか。
なぜ(少なくとも本人の意識的には)客観的な研究により人種の平等を訴えた科学者たちは、 奴隷解放や反対の物語でも比較的マイナーぽいのだろうか。
(だからこそか)個人的にもあまりそうだと思いたくないが、もしかしたらそれこそ人種差別の残り香が残っているためなのかもしれない。
例えば奴隷を解放するだけでは、イコール人種の優劣を否定することにはならない。仮に世界は神が造ったのだとして、その時に白人を黒人の上に置いているとする(そしてそれが抗えない事実だとする)。すると白人は劣ってる黒人を奴隷にしたわけだが、だが劣っているとはいえ、それでも奴隷制度なんてのは、(優れていようが劣っていようが)人間である者なら誰もが持っている人道的な心にとってダメなことである。そこで奴隷を解放する。つまり能力的な違いがあろうとも、上の者が下の者を奴隷にするのはよくないと。
そういう考え方は、科学的な見解を持ち出さなければ残すことは容易だ。だがここで科学的見解を持ち出し、それによって客観的に、人種間の違いがないと示されてしまったらどうなるか。
それ以上決定的な奴隷解放の根拠はないかもしれないが、だからこそ物語は、「慈悲深き解放」から「愚かさゆえの過ちの清算」ということになりかねない。つまり、「優れているものが下のものを奴隷にしてたが、それはよくない」でなく、「そもそも人種的優劣などなかったのだが、偶然に文化を攻撃的に発展できた者たちが自分たちの方が上なのだと自惚れていた」というような。
しかし開放する側の者たちの心情としては、「無慈悲深い神の名のもとに、劣っている者たちすらも平等に社会の中の一員として扱ってあげた」の方が、心地よかったろう。
いろいろな部分で人種平等が理想とされるようになった現代でも、 人種の優劣という思想がいくらかは残っているだろう。いくらかというよりも、いっぱい残ってるのかもしれない。
ダーウィニストたちが探していた人種の連続性
人間の進化と性淘汰
ダーウィンは『種の起源』の第1版では、後の進化論争の中で問題となった、サルとヒトの関係性について全然何も語っていない。つまり彼は、その研究により「人間の起源とその歴史についても光が当てられるようになるだろう」と書いただけだった。
ダーウィンは、それからかなり後に(どちらかというとそっちがメインぽいが)性淘汰と人間の進化についての本『人間の進化と性淘汰(The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex)』も書いた。 その前書きで彼は、「私は、人間の起源、または由来についても個人的に多く書きためてきたが、出版する気はなかった。それを出版すれば、私の考え方に対する偏見をあおることになるだけだろうと思っていたから」というようにも語っている。
 種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
種の起源、ミミズと土、人間の由来「ダーウィン著作」
下等生物と高等生物との繋がり
進化という現象が、現在の生物の多様性をもたらしたか否かという論争で、ダーウィンを含む進化論派の人たちへの反論として、下等な生物と高等な生物の区別があまりにはっきりしすぎてるというものがあった。
逆に進化論派の人たちは、最も下等な(基本的にはキツネザルと考えられていたらしい)サルから、 チンパンジーやゴリラといった高等な類人猿、そして人間との連続性を主張した。
しかしどちらの派閥にも共通の常識としてあったのが、別種同士の違いの大きさや連続性でなく、そこに見られる本質的な(特定の基準においてとかいうより、この世界にそもそも設定されているようなものと言えるかもしれない)優劣。そして、その順位付けは、最も細かくした場合、人種も分けられる。
ダーウィンの『人間の進化と性淘汰』も、 そのような問題(類人猿と人間、下等な人間と高等な人間との連続性)を結構直接的に扱っているが、例えば最後に書いたミミズの本などでも彼は、下等とされている生物がどれほどに、しっかり賢さを持っているかのように振るまうか、ということに注目している。
単純に面白いとか、興味深いとか考えていたこともあろうが、やはり連続性を証明したいという気持ちもあったかもしれない。
下等猿から高等人類までの連続性
論争で活躍した進化論者として有名なハクスリー(Thomas Henry Huxley。1825~1895)が、「もっとも下等なサルと、チンパンジーやゴリラとのあいだに存在する溝は、それら(チンパンジーやゴリラ)ともっとも高等な類人猿(人間)とのあいだに存在する溝よりも大きい」という理論を展開したことはよく知られている。ただし、彼がチンパンジーやゴリラと比べるべきと考えていた人種は、おそらく人間の中でも下等な黒人種であった。
ハクスリーは(おそらく自らの説の補強として) いくらか部分的には、高等な人種と最下等の人種との溝が、最下等の人種とゴリラとの間の溝よりも大きいかもしれない、というような主張までしていた。脳の可能なサイズ、つまりは頭蓋容量に注目し、「その差は、高等な人間と下等な人間より、下等な人間と高等な類人猿と間の方が、相対的にも絶対的にも大きい。頭蓋容量という重要な点においてすら、人間と類人猿より、人間内の変異幅のほうが大きいのだ」と。
遺伝研究が明らかにしたこと
20世紀後半以降の遺伝研究が示していることは、人種間の違いは本質的にはものすごく小さいということだ。それはいかなる思想を持ってる人たちにとっても、たいていは衝撃的なくらいだったとされている。人種のランク付けや差別を正当化したい人たちにとっても、この幅は大きいほうがよかったろう。
現在の人類の遺伝的多様性の低さに関しては、7万5千年くらい前に、インドネシアのトバ火山の大噴火が原因で、一時期人類が絶滅寸前になった(おそらく人類全体で数万人程度の集団になってしまった)ためでないかという説(Toba catastrophe theory)がある。
ダーウィン進化論が示唆していた活路
おそらく進化論者(というよりダーウィニスト)たちには、白人が黒人よりも優れていると考えている人たちでも、環境などをしっかり整えることによって彼ら(劣った人たち)のレベルを引き上げることができると考える柔軟派が多かったろう。 ダーウィン進化論を適用するなら、現在の高等な人類も、昔存在した、より下等な生物から、進化によって徐々に発生してきたはずであったから。
 「断続平衡説」化石記録の不完全さへの反論。ワンダフルライフな世界
「断続平衡説」化石記録の不完全さへの反論。ワンダフルライフな世界
ダーウィン自身は(彼の基準における) 文明人と適当な未開人を比べたら、いろいろな部分でその差が結構大きいように思えるが、しかしやはり、普通に近しい者たちを隣に置いた場合、結局人類全体ではかなり連続的な模様を見せるとした。
遺伝子の解析などできなかった時代だから、当然、誰にせよ、 人種間の違いや連続性を見出すために調べられたことは、身体能力や知的レベル、根付いていると思われる文化や風習、そして解剖学的な情報。
生殖可能性の壁、雑種人類の問題
ところで生物の種同士を分類するにあたって、その種同士のオスとメスが、健康な子を産めるかどうかというのは、現在でも、生物学的に重要な壁である。
ダーウィンも、人種同士を掛け合わせた場合の不妊性には注目していた。
彼はポール・ブロカの著作の中にあった、「オーストラリアとタスマニアの原住民女性と、ヨーロッパ人男性との間には、子がめったに産まれない」という主張を否定した。その調査結果の価値は完全に失われていると。
ようするに混血児は、純粋の原住民たちに殺されていたらしい。
彼はまた、オーストラリアで11人の混血児が殺されて焼かれたという事件の報告(Anthropolog Review1868年4月号)の中で、「オーストラリア人女性が白人男性との子を産んだ後には、自分の部族の男性との間では不妊になった」というストゥルツェレッキ伯爵(Paweł Edmund Strzelecki。1797~1873)の話は間違いだとされているのを、興味深いとしている。
他にも、オーストラリア人と白人はたがいに不妊ではないことの証拠を大量に集めたというカトルファージュ(Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau。1810~1892)の研究。
何世代もムラート(主にアメリカにおける白人と黒人の混血)どうしで結婚し、普通に世代交代している家族を紹介し、「ムラート同士の間には子が産まれない」という迷信を否定するバックマン(Dr. Bachman)の報告。
さらにチャールズ・ライエル(Sir Charles Lyell, 1st Baronet。1797~1875)も、この問題に取り組み、そして同じ結論に達したことを個人的に教えてもらったと、ダーウィンは紹介している。
ダーウィンは、バックマンの「合衆国で1854年に行われた人口調査で、ムラートは40万5751人だった」という報告については、「この数字は、いろいろな状況を踏まえると少ないようにも思えるが、そのような人たちの多くが置かれている社会的状況を考慮するべきだろう」としている。ムラートの多くは、社会の中で低い地位に置かれ、(それも社会的状況のためだろうと思われるが)女性も不品行であることが多く、さらにムラートの一部は黒人に分類されてしまうことがよくあると。
ただ、ムラートに精気がないことは、信用できる書物にも書かれている、「よく知られた現象」らしい。しかしそれは(その話が完全に真実としても)彼らの繁殖力とは別問題とも。ダーウィンは、ラバが、寿命が長く元気よいことで有名だが、不妊であるという事実も持ち出している。
ダーウィンは、人種のたがいの繁殖力だけでは、 種の分類の基準としてはあまり強くないことも認識していた。妊性というのは、生活条件や、交配のスタンスなどに大きく影響を受けることがわかっていると。
人種分類に関する多すぎる見解
ダーウィンは、交雑とは無関係に、明らかに全人種には連続的変化が認められる(逆に言えば、ある人種とある人種で、明確に別種と定義する参考にできるような違いは認められない)とする文脈において、そもそもその問題(人種の分類)について、多くの研究者たちがまったく別の見解を持っていて、全体としては混乱しているとも語った。
例としてダーウィンは人種数の仮説として、1~2種(ヴィレイ(Julien-Joseph Virey。1775~1846))、3種(ジャキノー(Honoré Jacquinot(1815~1887))4種 (カント(Kant))、5種 (ブルーメンバッハ)、6種(ビュフォン)、7種(ハンター(Hunter))、8種 (アガシ)、11(ピカリング(Charles Pickering。1805~1878)) 、15(サン・ヴァンサン(Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent。1778~1846))、16(デムーラン(Desmoulins))、22(モートン) 、60(クローファード(Crawfurd))、63(バーク (Burke))などを紹介している。
ダーウィンは、このように人による判断の違いがかなりバラけているのは、それこそ人種が連続的で、どこで分けるかが単に主観的な判断にすぎない事実の証明だろうとした。
さらに続いて「私は自分の経験に基づいて述べるが、非常に変異の大きい生物を記載する不幸に見舞われてしまった博物学者なら、誰でも、人間におけるものとまったく同じような例に出会ったことがあるはずだ。そして記載者が慎重な性格の人であれば、最終的にはたがいに連続している形態のすべてをまとめ、単一種として分類するはず。なぜなら彼は、自分が定義できないものに名前をつけることはできない、と自らに言うだろうから」とも。
進化論以前の理由
生物学者たちの間で、進化論というのが主流でなかった時代。人種間に本質的(絶対的)優劣があると信じていた人たちは、その(彼らにとっての事実について)どのような理論を展開していたのだろうか。
モノジェネシス、ポリジェネシス
ヨーロッパ系の白人社会では、その(人種の優劣を定義づける)流儀として主に2通りあったようだが、どちらもヨーロッパ系社会全体で強い影響力のあったキリスト教と関連している。ようするに、聖書の記述を参考にした『人種単起源論(モノジェネシス。monogenesis)』か、それ(聖書)は不完全な記録として、都合のよい部分だけを取り上げた『人種多起源論(ポリジェネシス。polygenesis)」かである。
モノジェネシスは、つまりすべての人々は、世界最初の男女の一組アダムとイヴの子孫たちであり、少なくとも始まりの時には人種というものはなかった、という理論。
この場合、人類は最初は完璧な人類(アダム・カドモンというやつだろう。つまり神のコピー的な完全人間)であったが、長い時間をかけて世代交代を続けるうち、だんだんとその完璧さを失って(劣化して)いった。
 「カバラ神秘主義」セフィロトの樹の解説と考察。神様の世界創造魔術
「カバラ神秘主義」セフィロトの樹の解説と考察。神様の世界創造魔術
つまり、今のすべての人類は、元の完璧な存在からいくらか退化してしまった存在。だが、その退化の度合い自体は人種によって異なっている。最も本来の状態に近いのが白人で、かけ離れてしまっているのが黒人という訳である。
ポリジェネシスの方は、つまり、人種ははなからそれぞれ別個に創造された種という考え方。
しかしこちらは進化論を否定する人にとってすら結構奇妙な所があったのでなかろうか。少なくとも、雑種人の不妊性が真でないと。
とにかく、事情は何にせよ、モノジェネシスの方が研究者人気は高かったようである。
劣化を修正できるか
最初から別の種としてあるポリジェネシスに対し、モノジェネシスの場合、なぜ人々の劣化度合いが異なっているのかを説明する必要があろう。
典型的な仮説としてあったのが、人々が住み着いた各地の気候の影響。ヨーロッパの人たちは幸運と考えられていたかもしれない。
退化論者たちの間でも、劣化してしまった人間としての性質を、上手くすれば取り戻せるのかどうか議論があった。
中には、各地の気候の影響などを受けて変化したのは、初期の創造段階の時代での話で、すでに神が完全に創造を終えた現在の完成(固定化)された世界では、もはや人種の優劣はどうやっても覆らないだろう、というような説も提唱されていたという。
人類学のアメリカ学派
イギリスから独立してから、アメリカでは、科学理論研究や、哲学的思想の面でも、独立国家アメリカとしての自分たちのアイデンティティを確立しようという、理論家、専門家たちの活動も見られたという。
そうした学徒たちにとって、多起源論(ポリジェネシス)は非常に重要な科学理論の1つであったという見方がある。
というのも、実のところこの理論は、アメリカ起源ながら、ヨーロッパ中の科学者の注目を集めた最初期の理論だったからとか。
当時のヨーロッパ人には、ポリジェネシスを「人類学のアメリカ学派」として語る傾向すら見られたらしい。
厳密には、多起源論の先行研究者は、もちろんヨーロッパに多くいたが、しかし理論を支持するために引用される大量のデータは、基本的にアメリカ人が提供したものだったそうだ
聖書と奴隷制度を巡る論争
19世紀半ば、奴隷制の存続を主張し、連合国として一時の独立までしたアメリカ南部においては、ポリジェネシスはあまり人気がなかったとされる。
多起源論は、階級制度以上に、聖書の記述が基本的には真実だというスタンスの牧師たちの思想と(創成期のアダムとイブや、ノアの話と明らかに矛盾するから)対立したのだが、それはまた、奴隷制というものを正当化する根拠の問題にも関連して、見事なジレンマ(板挟み)を発生させていた。
 「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説
「旧約聖書」創造神とイスラエルの民の記録、伝説
多起源論者も基本的には無神論者ではなく、宗教に関する態度はさまざまであったようだが、
そもそも聖書の中でのいくつかの記述(ノアが、自分が酔っ払った時に気遣ってくれなかったことに怒って、息子ハムの子孫のカナンの民を奴隷とする呪いをかけたとか)は、奴隷制度が正当なものである強い根拠とされていたらしいから、多起源論が代わりの強い根拠を示してくれない限りは、聖書の記述をはっきり否定してしまうその理論は厄介なものだった。
普通には、単起源でも多起源でも、奴隷制を続けたがっていた者たちの理屈の説得力は似たようなものだったろうと思われる。(これには、聖書の記述を素直に受け止めていた聖職者たちも多く含まれていたと思われるが)単起源支持者は「今や知的能力が大きく劣ってしまっている劣化人種を、賢い自分たちが主人として導いてやらねばならない」と語り、多起源支持者は「つまり最初から、奴隷にされる者たちは、奴隷が性に合っているような低級な存在なのだ」と語った訳である。
呪いは普遍的な遺伝要素か
しかし、 理由はともかくとして、ある種のグループ単位でその劣化が引き継がれてきたという考え方には、前提として遺伝法則の存在があるようにしか思えないが、ずっと古い時代にはどうだったろうか。
「全人類の先祖となった数人のうちの1人にかかった呪いのための、その全子孫が奴隷になることを決定づけられた」とかいうような話を真に受けるとするなら、そこには、その子孫から固定的な要素として受け継がれていくような何らかの遺伝要素(現代的に言うなら普遍コードとか言っていいかもしれない)が存在する、と考えるべきだろうか。それとも、子孫と先祖とのつながりというのは神秘的な領域の話であって、あまり理屈的に考えてもはっきり理解できるようなことではなかった、と思われていたりしたのだろうか。
モートンの頭蓋骨コレクション
一般に、多起源論の「アメリカ学派」を世界的に有名にするデータ群を提供したのは、フィラデルフィアのサミュエル・ジョージ・モートン(Samuel George Morton。1799~1851)だったとされる。
1820年代から人の頭蓋骨を集め始めたモートンは、1851年に亡くなるまでに、1000個以上のコレクションを作っていたという。そして そのデータ収集の仕事は、将来の様々な研究に役立つだろうと絶賛された。
またモートンは、自らもそのコレクションを使って、人種に関する研究を行った。 彼は脳の容量の大きさから、優れた人種を客観的に見いだせるかもしれないと考えていた。
生物の根源的な型。これまでの地球の時間
モートンは多起源論者で、人種間での生殖可能性というビュフォンなどが重視した基準も否定したがった。いくらかの「異なる人種同士の子孫には生殖能力がない」という報告を取り上げ、そうした雑種の不妊性を、生物の「根源的な型」不一致のためとした。それにそもそも自然界では異なる種同士の交雑はありふれたものとも主張。
問題は、それこそ生物の分類の基準とするべきと、彼が考えていたらしい「根源的な型」というのは、何か。どうやってそれを生物種に見るか。
モートンは、これまでの時間に注目した。聖書の記述から考えると、ノアの方舟の時代からほんの数千年程度の時間しかない。そんな程度の時間では、人類(つまりノアの一族の子孫たち)が、元の形からいろいろに変化して、様々な人種に分かれた、と考えるには時間が足りなさすぎるだろうと。逆に、そんなわずかな時間で生物種が変化するのだとしても、明らかに現在、その変化速度が急激に遅くなっているのはなぜなのかと。
そういう理由でモートンは、最初の創造の時から、人種は別々の生物グループだったという考えを支持していたが、さらに頭蓋骨の比較研究によって、人種間の本質的な(知的能力の?)優劣も確かめられるかもと希望を持ったのだとされる。
しかしそうした解剖学的な研究以前から、彼はエジプトの壁画の解釈などにより、黒人の生物学的地位は、古代よりずっと奴隷や召し使いであるという自説を持っていたとも(あるいは人種間の優劣に関する自説を補強するために、そういった話も調べていたらしい)
頭蓋骨容積を計測する
彼の計測法は、頭蓋腔(脳が入る空洞部)に、(最初はカラシの種子を使ったが、精度があまりよくなかったから、鉛玉に変えられた)ものを限界まで詰めて、その後に目盛付きのシリンダー(円筒形の容器)にそれを戻し、頭蓋骨容積を目盛から読みとるというもの。
そして彼は「(言うまでもないかもしれないが)コーカソイド人種(白人種。インド・ヨーロッパ系)が、最大の脳容量を有している」ことをついに確かめる。
モートンは人間の頭蓋骨の大きさに関して、1839年の『クラニア・アメリカーナ(Crania Americana)』や1844年の『クラニア・エジプティアーカ(Crania Aegyptiaca)』など、いくらかの著作を発表したが、そして、彼のそれらの著作に載せられた、人種ごとの頭蓋骨の平均脳容量の比較表は、モートンの死後も長い間、人種ごとの知的能力の差が明らかであることの強い証拠として、多く引用されたという。
バイアスはあったか。モートンVSグールド
生物学者スティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould。1941~2002)が、モートンの研究についての研究を1977年に行い、その結果を公表して以来、モートンの研究には「白人種を優れたものとして考えたい」というバイアス(偏見)がいくらか関係していたかどうかが、何度か議論の的になってきた。
 ダーウィン以来、ワンダフルライフ、人間の測りまちがい「グールド著作」
ダーウィン以来、ワンダフルライフ、人間の測りまちがい「グールド著作」
グールドは例えば、モートンが、各頭蓋骨の性差なども関係する体のサイズ(通常、体の小さな人は、体の大きな人に対し(相対的には似たようなものでも)絶対的には小さな脳を持つとされる)もしっかりデータとして記録しながら、それと脳の大きさの相関性などについてはかなりいい加減、と指摘した。
またモートンは、アメリカ原住民のサンプルに関しては脳の小さなペルー・インカ系を多く取りあげ、一方でコーカサス系人種のサンプルに関しては比較的脳が小さいインド系のサンプルをほとんど取り除いたりしていたようであるが、とりあえずそれに関して、本人は大した問題とは考えていなかったようだ。
 「インカ文明」太陽、ミイラ信仰。生贄はあったか。見事に整備されていたか
「インカ文明」太陽、ミイラ信仰。生贄はあったか。見事に整備されていたか
グールドの、モートンの研究についての見解は、それもまた人種差別への反対感情がバイアスとして逆にかかっている、という指摘もある。
ブロカは残酷な真実を見つけていたのか
百科事典の人類学に関する項目に「顎の突き出た顔、黒い皮膚、縮毛の組み合わせは、知的および社会的に劣等なことを示す。白い皮膚、直毛、垂直な顔は高等な人類を示すもの。黒い皮膚、縮毛、顎の突き出た顔の民族が、自力で文明を興したことはただの一度もない」と書いたポール・ブロカ(Pierre Paul Broca。1824~1880)は、 しかしこれはあまりにも残酷な真実であるとして嘆いてもいたという。
明らかにブロカは(おそらく当時、人種間の優劣を説いた多くの科学者たちと同じように)、自分の研究も、その成果も、完全に客観的なものであると確信していた。
計測法の有効性からまず考える
ブロカは、平等主義の科学者は、政治的な理由を科学の世界に持ち込んで(人種に明らかな優劣があるという)真実をねじまげたのだと批判。
例えば黒人と白人の頭蓋容量には差異がないというティーデマンの主張についても、「人種は平等であるはず」というバイアスのための(やはり)サンプル選択で、黒人の数値(平均値)を高めているとした。
ブロカはそれまでの容量を測る方法を事前に研究し、結果的に最も優れた方法は、鉛玉とシリンダーを使うもの(つまりモートン流)と判断した。
彼は少なくとも、頭蓋容量を測る方法、算出される数値に関して、非常に細かく注意を払った。シリンダーの形や大きさ、頭蓋骨へ鉛玉を入れる速さ、頭蓋骨の中に鉛玉をきっちり詰めた後の空きの確認のための頭蓋骨のたたき方など。
ただし彼は、頭蓋骨の容量を測るより、直接的に脳の重さを比べるやり方の方がよいと考えていたらしい。
どんな偏見があり、それがどんな影響をもたらしていたか
しかし、方法についてどれほど慎重であろうが、彼には確かにとても重要な偏見があった。当時としてはそう珍しくもない。少なくともティーデマンが抱いていたかもしれない「人種は平等であるはず」という考えよりは一般的だったろうと思われる。そしてその偏見は、結論と観測事実を比較するブロカのやり方の結論の方を、あまりに強く定めてしまっていた。
ようするにブロカは「白人男性>白人女性>黒人」という(神が定めたのか、自然が定めたのかはともかく、普通には明らかと考えられていた)優劣関係を常識的な結論として、そしてそれと比較する 上で、そうした優劣関係自体を否定するデータは「客観的事実としては信頼できないもの」と定義したのである。
例えばブロカは1つの基準として「上腕骨に対する下腕骨の比(その比が大きいことは前腕が長いことであり、それはよりサル的な特徴であろう)」を想定してみた。しかし白人の数値が黒人より低いところまではよかったのだが、白人よりもエスキモー(ツンドラ地域の先住民)やアボリジニ(オーストラリア原住民)の方がさらにその数値が低いという結果が出てきた時、(つまり白人種が頂点であるという明らかすぎる事実が否定されるため)それは使えない基準と結論した。
実際のところ、現在ではなるべく客観的な方法で脳の大きさを測ってみたら、たいてい白人よりも黄色人種の方が大きいという結果になることが知られているが、ブロカはその事実に直面した時に、脳の大きさの差も(過去の研究記録から考えても、確実に、まったくではないだろうが)あまりあてにならない、と判断したという。
使わないから脳は退化したのか
ブロカは、ある生物種の生物学的地位が普遍的なものとは考えていなかったらしい。
例えば、一般的に女性の脳が男性に比べて退化している原因について、社会の中で頭を使う役割を与えられてこなかったからとした。それに、そもそも男性の脳も、文明が発達し社会が複雑化するにつれて(つまり必要に応じて)大きくなってきたとも。もちろん社会環境の調整によって、いつか劣化人種もかつての脳の大きさを取り戻すことができるかもしれない、と説いた。
キュヴィエと、ホッテントットのヴィーナス
1815年。解剖学者ジョルジュ・キュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier。1769~1832)は、「ホッテントットのヴィーナス」と呼ばれた、(基本的にその名では呼ばれなかったらしい)サーキ・バートマン(Saartjie Baartman。1789~1815)の遺体を解剖した。
見世物小屋のブッシュマン
19世紀(あるいは20世紀)までのヨーロッパでは、今よりもずっと異なる存在とされていた(おそらく奇形の白人も含む)非白人種(特に遠くの土地から連れてこられた野蛮人たち)が、本質的に高等な人間(白人種)に似ている動物として見世物にされることがあった(そうした見世物がビジネスになるくらいに人気を博していた)。
サーキも、生きていた頃に見世物にされていたことがあった。
ホッテントットという種族名は侮辱的な意味合いが含まれていることもあって、現在は普通使われない。その名で呼ばれていた人たちは、現在はコイサイ族と呼ばれる、背が低めな南アフリカの民族に(やはりかつてはブッシュマンと呼ばれていた人たちとともに)属していたと考えられている。
膨らみの謎
しかしキュヴィエがサーキを解剖して確かめようとしていたのは(少なくとも最大の目的は)人種の優劣とかでなく、コイ・サン人の女性の性的器官、その周辺部によく見られるという、特異的に思われた特徴の謎だったと思われる。
サーキは特にその特徴がよく目立っていて、だからこそ、特に見世物として注目を集めてしまった側面があったとも。
その特徴は一般的には『脂臀(steatopygia)』と呼ばれる。
脂臀は、遺伝的特性と思われるが、ようするに多量の脂肪組織の蓄積による大きくなっている臀(しり)のこと。コイサンの成人女性に顕著にみられることが有名だが、時には男性にも見られるらしい。
特定部に脂肪が多量に貯蔵されることは、(例えばラクダのコブのように)資源が不足しがちな環境において有用なのかもしれない。
古い文明の女人像に大きな臀部が備え付けられていることがあるが、これはふくよかな脂肪と豊穣を結びつけた、宗教的な意味合いが関係していることも多いようだ。
サーキは見世物になって、脂臀を直接に晒してはいても、自らの生殖器は上手く隠していたという。しかし、コイ・サンの女性の脂臀の構造が生殖器に対しどのようになっているのかというのは、生物学者たちの興味を集めていた。
キュヴィエもそうした生物学者の1人だった訳である。
サーキの旅立ち
サーキは、南アフリカのケープタウン近郊に住むオランダ人農家で、召使いとして働いていていたが、ある時に自由黒人の商人(雇い主の兄という説もある)から、イギリスへの巡業をすすめられる。彼は、ヨーロッパの方で成功すれば、もっと裕福になれるだろうと語ったともされる。
結局のところ彼女のヨーロッパへの移住が(彼女自身の認識はともかくとして)自らの意思によるものだったのか、連れ去られてのことだったのかは不明。ただ、ケープ植民地の総督であったカレドン(Du Pré Alexander, 2nd Earl of Caledon KP。1777~1839)は、その目的を後から知って、彼女に旅行の許可を与えてしまったことを後悔したらしい。
彼らは猿に近い
サーキの生きた時代の白人社会においては、人種優劣の順位として、ホッテントットとブッシュマンこそ、一般的に最下位と考えられていた人たちだった(オーストラリアのアボリジニと、どちらが最下位なのかの議論もわりとあったようだ)。進化論者が考えるところでは、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンなどの高等なサルのすぐ上の存在という訳だ。
ブッシュマンやホッテントットが人間よりもサルに近いと考える根拠としては、(当時の生物学者たちの見解として)単に外見が似ているということの他、人というより獣に近いその習性も重要視されていた。
「彼らは陰鬱で、無口で、獰猛と、性癖は動物に近く、サルよりも容貌は気持ち悪い」というような報告を大して疑わず鵜呑みにする学者もいたし、「彼らは自分たちの子供すら良心の呵責を感じずに殺す。子に欠陥があるとき、食物が不足しているとき、農民などから逃げねばならないときに。飢えたライオンが邪魔な時に、幼い子供を供物として投げ与えた例も知られる」というような記録を書いた宣教師もいた。
どうも、彼らと猿の見分けがとっさにはつかないハンターたちが、彼らを間違えて撃ち殺してしまう、ということもあったらしい
檻の中の彼女
1810年頃、ロンドンにきた彼女は、すぐに見世物としてお披露目される運びとなった。
1807年の奴隷貿易禁止法の制定から、ほんの数年しか経っていなかったこともあって、植民地の女奴隷の見世物は、かなりの論争を巻き起こしたとされる。
当時、彼女の「解放」を訴えた慈善団体のメンバーは、「檻の中にいて、飼育係に命令されている彼女は、まるで野生の獣のように仕立てられていた」などと記録してもいる。しかしサーキ自身はオランダの法廷で尋問された際、「自身の利益のために見世物となっているのは、自分の意思であって、別に監禁され強制されているわけではない」と主張したという。
見世物は続行され た。
サーキはフランス、パリでも、1年以上にわたって展示されたが、その時に彼女を見に来た博物学者たちの中に、キュヴィエもいた。
そして1815年12月29日、おそらく病のために死んだ彼女は、キュヴィエにより解剖されることになった。
知的さと原始的な部分。大学者の報告
キュヴィエは、サーキの解剖研究に関するモノグラフ(特定の主題に関する研究を記した報告文書)を1817年に発表した。
キュヴィエは研究者として、偏見など排除し「確実(ポジティヴ)なこと」だけを明らかにしようとしていたそうである。
しかし彼は、おそらく調べる前から確実だったことについては、ただただそれを明らかにする事実のみを求めた。つまりキュヴィエは、(曰く、農業を営む能力がないために、狩猟と盗みだけを頼りに生きる人種である)サーキがいかにサルに近い特徴を有しているかという点について、特に注目した(人間に関して言えば、民族ごとの形体の変化を大きいと考えても、どこかでサルに近い形質を持っていることが共通している。つまり世界中の誰でも、どこかの部位は、他の民族よりサルっぽい)
例えばサーキの鼻骨が平板なのが「とてもサルに似ている」とか。サーキの頭骨が(ただし彼女は身長1メー トル35センチ程度)小さいことも、その愚かさの客観的証拠とした。
ただし生前の彼女とも関わりのあったキュヴィエは、(生前の)サーキが確かに知的な女性であったことも知っていた。彼女は特に記憶力がよく、オランダ語の他、英語もそこそこ話せたし、フランス語も勉強中だったそうである。
また、肝心の脂臀については、もちろん「肥大化した生殖器である」という(その時まで結構語られていたらしい)仮説を否定する結果を示した。
キュヴィエ自身、支持していた見解として、やはり「コイ・サイ女性の脂臀は、原始的な特徴」なのだろうというものがあった。つまりそれは、人間的な上品さとは真逆の、いわば下品な性的特性なのだと広く信じられたらしい(ただ、現在の生物学においては、人間は霊長類のなかで、むしろ性的にもっとも活発ともされているのは皮肉であろうか)
ちなみに、ブロカは人種優劣の基準として考えたが、(白人種が明らかな一番にならないという)不備があったために放棄した「上腕骨に対する下腕骨の(低いほどよい)比」に関して、その率が白人で0.739、しかしサーキの骨格標本では0.703であったという。
カンパーの顔面角
「人類学(anthropology)」という分野を想定した初期の博物学者の一人とされるペトルス・カンパー(Petrus Camper。1722~1789)。しかし人類解剖学に関しての彼の仕事の大半は、生きてる間には未発表だったとも(彼の死後に、彼の息子が未発表の原稿をまとめて出版したらしい)
カンパーは、人種間で異なっている重要な形態的特徴として、『顔面角(Facial Angles)』というものを提唱(定義)していた。そしてそれはおそらく近世以降の生物学において、異なった人種の頭蓋骨を比較するための方法として広まった最初期の基準の1つ。
顔面角とは、例えば人間の頭蓋骨を、丸い頭蓋部と、前面の顔部分という2要素に分けた場合に、それらの関係性を確定する基準。
まず、耳の穴から鼻下までつなげる直線、さらに上顎のもっとも突き出ている部分から、目の上の眉毛のもっとも突き出ている部分までも直線を引く。顔面角とは、そうして想定された耳から鼻までの線と、顎から眉までの線がなす角とされる。
そしてこの基準を用いた初期の頭蓋測定学者たちは、顔面角はアフリカ黒人が最も(さらにいうなら類人猿が)小さく、ヨーロッパ白人が最も(特に偉大な文明を築いた古代ギリシャ人の像で)大きく、東洋人(アジア系)がその中間であることを見いだす。つまりこれは、人種差別を正当化するための科学の、最初期の便利な道具にもなった。
黒人の賢者についての不満
ただしカンパーが顔面角を定義したのは、人種の優劣を見定めるためではなかったらしい。
カンパーは解剖学と医学の教授であるが、画家でもあり、顔面角を定義した理由は、(当時は、そんな言葉が何を意味しているのかも曖昧だったとされているが)科学でなく、芸術に関する問題の解決を図るためであった。
カンパーは画家として、特に古い絵画に描かれる黒人の賢者に関して不満を持っていた。そうした黒人は、肌の肌が黒いことを除けば白人的で、アフリカ系という印象が弱かったのである(カンパーは時代を考慮し、原因は黒人のモデル不足であったのだろうと考えたらしい)。
カンパーは各人種の特徴をしっかり定義して、それを自分が描く絵に反映させたいと思っていた(彼は、人種の差異だけでなく、年齢ごとの差異などにもかなり注目していた)
カンパーは、(おそらく当時の常識として)人種の順位を疑うこともなかったが、しかし顔面角から彼が読み取っている(彼なりの)真理は、「白人の美しさに黒人は決して勝てないだろう」というようなことのみであった。それが後世には(実際そのような目的で利用する人も結構いたとされる)絶対的な知能の優劣の基準として使われるなんて、カンパーは考えもしてなかったかもしれない。
スティーヴン・ジェイ・グールドは自分の本でカンパーのことを語る際に「原著者の意図からかけ離れている後世の解釈ばかり広まることがあることに、私はもはやおどろきもしない」と書いたことがあったが、差別の根拠みたいな、誰かが誰かを支配する仕組みに関する事柄とかは、ほとんど常にそうなのかもしれない。
人種は同一種内の変種にすぎない
もちろんカンパーはダーウィン以前の人である。
今は、(かつて神による創造があったかどうかすら別にして)「十分長い時間があれば、種が変異して別の2種に別れることもある」というのが、常識(少なくとも有力仮説)であるが、カンパーの生きてた時代は違っていた。
種ごとの差異は、種ごとの根源的性質を表し、種内に変異があるにしても、気候とか食べ物などの外的要因によって、本来の原型から離れているというようなものというのが(つまり退化論、劣化論的なのが)、普通な考え方だった。
ヒトが1種と仮定すると、ヒトという種内の変異は、表面的かつ偶発的で、生まれもっての劣性というより、劣化の度合いであったろう。
カンパーは、自分でもその問題に関して色々考察していて、ヒトは多元でなく一元、つまりただ1種という(モノジェネシス)説にしっかり傾いてもいた。
さらに言うなら彼は「人種というものは単に同一種内の変種にすぎないが、それらは容易に変わりうる」とも考えていた。例えば最初に創造されたとされているアダムとイブに関しても、白人だったのか、黒人だったのかも定かでないと(実際問題、彼が本当に、白人の方が絶対的な美しさを有していると考えていたなら、もしかしたら彼は、「アダムとイブが黒人だったとしたら、彼らが美しく変わったのが白人種」というような可能性も考えていたろうか)
つまり彼は、モノジェネシス派の中でも、劣化(もしかすると、今の人がこの言葉から連想するほどにはネガティブな意味でなかったかもしれない「劣化」)を環境によって修正できるだろうと考える派閥の人であったのだと思われる。
ブルーメンバッハの五人種分類
リンネの仕事
分類学の父カール・フォン・リンネは、人間、つまりホモ・サピエンスに6つの変種があることを見いだしたことがあるが、人種分類の歴史において特に重要なのは四人種、つまりアメリカ系(アメリカヌス)、ヨーロッパ系(ヨーロッパウス)、アジア系(アジアティクス)、アフリカ系(アファー)。
他の二変種は、ときに森などで発見される野生児(おそらく大半、親に捨てられた発達障害児)と、旅行者が語る尻尾をもってたりする人間。
リンネの基準は、主に地理的分布、それに外見や行動様式のちがい。
リンネは、重要な四人種のそれぞれの特徴を(色、気性など)を書いたが、それらは基本的に実際の観察などからでなく、たいてい(例えば人の気分は4種の体液(血液と痰と胆汁と黒胆汁)のバランスで決まるとか)古い理論を利用することで見いだされていた。
ただリンネの分類は、あくまでも分類で(例えばヨーロッパ系が理性的で、アフリカ系が本能的と解釈できるような、ステレオタイプ的なイメージの示唆があったりするものの)その構造はあからさまに階層的なものではないとも。
しかし(リンネ流の)属性による分類(地図)から派生した、性能のための順序づけ(何らかの価値を基準とした直線的な順位制)という、根深く人種差別を正当化してきた思想の誕生に強く関わっていると思われる人物に、リンネの弟子、ヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハ(Johann Friedrich Blumenbach。1752~1840)がいる。
ただし(妙な話だろうか)彼自身は、人類の多様性を研究した同時代人の誰よりも、おそらく人種平等主義者だった。
最も美しいと定義されたコーカソイド
ブルーメンバッハが定義した五人種分類は、後世の人種の考え方に大きな影響を与えたとされている。
彼が定義した五人種は「ヨーロッパとその周辺地域のコーカソイド(白人種。コーカシア)。アジアのモンゴロイド(黄色人種。モンゴリカ)、アフリカのエチオピアン(黒人種。エチオピカ)、アメリカ大陸の先住民であるアメリカン(赤色人種。アメリカナ)、さらにオーストラリア先住民のアボリジニを含めるマレイ(茶色人種。マライカ)」であったが、より一般的になったと思われる「コーカソイド(白人種)、モンゴロイド(黄色人種)、ニグロイド(黒人種)」という分類も、元はブルーメンバッハの分類からきている(あるいは強い影響を受けている)とか。
ブルーメンバッハは別に芸術家というわけではなかったと思われるが、しかし彼もまた「美しさ」という基準を用いた。そしてその基準においてはコーカソイド人種は最高の人種とした。
しかし彼は、人種間の性能的な優劣に関しては、むしろ明確に否定していた。
偉大な人物に倣うのをやめる
ブルーメンバッハが五人種分類を提唱したのは、1795年に出版された『人類の自然変種』三版において。もともとそれは、ゲッティンゲン大学医学部に博士論文として提出されたものだったが、アメリカ、フィラデルフィアで開かれた会議で独立宣言が発せられた1776年に、一般向けに出版された研究書とされる。
そこに書かれた人種分類が大きな影響を及ぼしたのは、そうしたタイミングも関係してたろう。
ブルーメンバッハの基準は、主に地理的分布と外見。彼が提案した五人種の内、マレイ以外の四人種は、彼の師であったリンネが『自然の体系』で採用していたものと同じ。マレイは、ブルーメンバッハがアジア人種からさらに新たに分けたもの。
実際、ブルーメンバッハはリンネを非常に尊敬(崇拝)していたようだが、自分なりに人種分類の研究を進めていく過程で、最終的には「偉大な人物に倣うのをやめることにした」。
変質、遺伝はあっても、知的能力に差はない
ブルーメンバッハは、人種それぞれは個別に創造された説を否定し、「あらゆる人類が1つの種に属している可能性がきわめて高いことに、もはや疑いは残されていない」と主張した。彼は(同じ説(モノジェネシス)を語る他の多くの人たちと同じく)各人種の特徴とされるどんな形質も、人種全体で比べてみたら連続的である(どんな人種グループにも、少しだけ違っているだけのグループが存在している)ことが、はっきり分離されている人種なんてのが幻想である証拠と考えていた。
彼はさらに進んで、アフリカの黒人に他の人種より劣っていることを示す特徴があるという通説も否定。
ブルーメンバッハの人種の起源(現在のような人種観の違いが生まれた理由)に関する説は、モノジェネシス派の人のものとして、かなり典型的だったと思われる。彼は、人種の多様性をもたらしたのは、それぞれが移住した地域の環境(気候や地形など)の影響だろうと考えていた。ブルーメンバッハはそのような変化を『変質(ディジェネレーション)』と呼んだが、これも当時普通に用いられていた用語らしい。それは(現在この言葉の意味として一般的な)劣化というより、単に創造時の初期状態から変わっていることを意味した。
ブルーメンバッハは、そのような変化が世代交代を続ける中で遺伝していくとも考えていた。ただしそれはかなり自由度の高い変化であって、生活環境を調整することによっていくらでも元に戻れるとも。
何より重要なことは、人種の変異は外見的なものに限られているはずという考え。つまりブルーメンバッハは、変異で見た目は違っているとしても、その(人類という種にとって、最も肝心なものであろう)精神能力に関係するあらゆる要素には、絶対的な差などないと理解していたのである。
原型に近い存在
主にヨーロッパ、それにアジアとアフリカの一部の、白い肌の人々に、彼は「コーカソイド」という名称を与えた。
ブルーメンバッハ自身は、その名の由来として「この変種の呼称をコーカサス山脈から採った理由は、その近隣、特に南の地域が最も美しい人種を生んできたこと。それにその地域が、人類の原種が見つかる可能性が高い地域だから」と述べた。
美しさなんてもの、普通に考えるとかなり主観的であるが、なぜそんなものを基準にしたのか。
まずブルーメンバッハは、(その平等主義思想にも関わらず)、ヨーロッパ系変種、 全人種の中で中間に位置している、つまり最も原型からの変化の少ない存在として、階層の最上位と位置付けはした。
実のところ、ブルーメンバッハが第五の人種を追加した理由についても、その真ん中に位置する人種を唯一の頂点として考えやすくするため、と見る向きもある。
しかしどう考えるにせよ、順序づけの採用は明らかに問題を生じさせよう。あらゆる精神能力に関して、人種間に違いがないという彼の信念と、「最も完璧に近いコーカソイド」という考え方は、一見(というか、伝統に従って、本質的な能力的なものを基準にしたなら)噛み合わない。
というわけでコーカソイドが最も優れていると想定してよい基準として、ブルーメンバッハが見いだした(妥協した?)ものが、「美しさ」だったわけである。
そして、美しいというのは、つまり原型に近いということであるから、人類の起源の場も、最も美しい人たちが暮らしている地域の可能性が高いというわけだ。
黒人たちの素晴らしい才と、優しい心
言うまでもないことかもしれないが、ブルーメンバッハは奴隷反対主義者だった。
ブルーメンバッハの自宅の書庫には、黒人著者の書物専用の棚があった。彼は、黒人種の素晴らしい精神能力と、芸術的才能を褒め称えようとする時、その著作リストを例に挙げたという。
また彼は、奴隷のほうが奴隷商人よりも徳が高いとまで主張。曰く「奴隷船の中で、(故郷から離れた)サトウキビ農園で、どんなひどい目にあわせようと、白人農園主たちは、彼ら(黒人種たち)の生まれつきの優しい心を消すことができなかった」
 「アメリカにおける人種差別の根」虐げられた者たちの声は届いたか
「アメリカにおける人種差別の根」虐げられた者たちの声は届いたか
他の研究者、哲学者たちのいくつかの意見
ビュフォン。交雑可能性
ビュフォン(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon。1707~1788)は、少なくとも地球上で知られているあらゆる人種間の間で生殖が可能だというかなり確かな経験的事実は、そもそも人間というのがただ人間という1種だからでないかと考えた。
あまりに当たり前のことを語る理論に思えるが、それでも彼の時代には、 そんな考えを素直に受け入れるというのは、なかなか先進的なことだったかもしれない。
少なくともビュフォンにとっては、「同一種内の成員は互いに交雑可能だが、他のグループとは交雑不可能」という分類のための基準は、とても重要なことに思えていたのだと思う。
彼にも、優れた人種、劣った人種という考え方はあったようだが、適切な環境で、適切な教育を受けさせることができたなら、劣等人種のレベルも高めることができると考えていた。
そうした考え方だから当然かもしれないが、彼は奴隷制度廃止論者でもあったらしい。
ヒューム。白人はなぜ優れているか
デイヴィッド・ヒューム(David Hume。1711~1776)は、おそらくポリジェネシスの特に有力な支持者の1人だった。もちろん彼が、個別に創造された中で最も優れていると考えた人種は白人種であった。
彼が、白人種が特に優れた人種と考えた根拠は、普通に「文明化した国家は、全て白人国家だから」。
曰く「非白人は白人にくらべ、もともと劣っているんじゃないかと思う」。白人と比べた場合、他のどんな人種も、行動力、思索力、手先の器用さ、芸術センスと、あらゆる面が劣っていると。
ヒュームはまた、彼らのプライド(誇り)に関しても言及していたという。例えば、黒人の中で優れているといえる者は、些細なことで褒められて喜ぶ。彼らは、多くの言葉を知ったオウムのようだとか。
ホワイト。進化も嫌っていた
外科医チャールズ・ホワイト(Charles White FRS。1728~1813)もまた、ポリジェネシスの有力支持者。ジョン・ハンター(John Hunter。1728~1793)の影響もあったらしい、 頭蓋骨の比較など、解剖学的研究により、各人種それぞれの特長を見出そうという研究に没頭した彼は、最終的に多起源説の正しさを確信したのだという。
そして、1799年に発表された、ポリジェネシスについての自身の研究成果とも言える『人間における規則的な所級の格づけについての説明(Account of the Regular Gradation in Man, and in Different Animals and Vegetables)』を公表した。
ホワイトは「交雑が可能なら同じ生物グループのはずだ」というビュフォンの考え方を否定したことが有名である。例えばキツネ、オオカミ、ジャッカルのような慣習的区分で分けられる生物グループ間でも、交雑が成功することがある事実を指摘。
彼はまた、モノジェネシス派が考えていたような、気候の違いが人種の差異と関連しているという説も否定。そうした発想からさらに連想されるかもしれない、種間の進化という「下劣な概念」までも彼は嫌ったとか。
一方で彼は、おそらく人種間の優劣関係にいくらか懐疑的な所があった。(いろいろな基準によって優劣を決められるとしても)各人種が異なった生物グループだからといって、あるグループが別のグループを奴隷にするようなことを正当化できはしないと。
フンボルト。奴隷制なんてのは悪習
アレクサンダー・フォン・フンボルト(Friedrich Heinrich Alexander, Freiherr von Humboldt。1769~1859)は、自らの政治的意見として「奴隷制なんてものは、本来しっかり教育されれば優れた学者になれるような人たちの芽を詰んでしまう悪習」と語った。そもそも彼は、人間同士の本質的な優劣を否定していたという。
彼は、大著「コスモス(Kosmos)」の中で、人間はただ1つの種でしかないと書いた。
しかしそんな彼でも、 歴史の中で、同じような条件の中、優れた文明を発達させた民族と、そうでなかった民族がいた事実に関して、各民族の知的能力の差を認識せざるをえなかった。
つまり各民族の「知的洗練への適応力」の差が、都市文明などと接触した際に、それをうまく取り込めるかどうかを決定付けているのだろうと。
セール。奇妙な基準
解剖学者エティエンヌ・セール(Étienne Serres。1786~1868)は、モノジェネシス派で、退化論者で、そしてポリジェネシスについては「文明が遅れている人種を奴隷にすることを正当化するもの」として非難した。
どうもセールは、完全状態から下等な状態まで、様々な環境と努力によって変化しうることは、人間という種に固有の特徴であると考えていたようである。
それでも、解剖学者としての仕事の中で、セールは下位人種の劣等性の証拠を探しもした。ただしその試みは、そうした人種間の優劣を客観的に決定することが難しかったため、基本的にはほぼ挫折したらしい。
セールが(苦し紛れにと言ってよいかもしれない)語ったのが、反復説である。つまりは生物の発生過程は、その生物にとっての完成形へと向かうが、劣等種族の場合はどこかで成長が止まるというようなもの(後にヘッケルが、この理論と進化論を合わせた)
セール曰く「大人の黒人は子どもの白人に似ている。大人のモンゴル人種は青年期の白人に似ている」らしい。さらには臍とペニスの間の距離という基準を導入し、すべての人種で赤ん坊の時には共通しているその(身長にくらべた相対的な)長さが、成長と合わせて白人では長くなり、黄色人種も白人ほどではないが長くなり、しかし黒人では変わらないとした。
カートライト。感覚障害と逃走狂気
サミュエル・A・カートライト(Samuel Adolphus Cartwright。1793~1863)は、奴隷制度をどうにか守ろうとした時代のアメリカ南部において、モノジェネシス派の学徒の立場から、しかしかなり極端な自説を持って、そうした(奴隷)制度の正当性を主張した医者であった。
カートライトは、自由な黒人というのはそもそも、まるで適応しきれていないこの世界の中で病気に苦しむ運命にある。しかし奴隷となった者は、主人が上手く扱ってやることにより、苦しみから救うことも可能。むしろ場合によっては、(その知的レベルに適応している?)快適な暮らしを送ることができる。というような理論を展開していたらしい。
さらに彼は、そうした、自由状態よりも恵まれているはずの黒人奴隷たちがしばしば逃げる事実に関しても、精神病のレッテルを貼っている。
カートライトは、自由黒人を苦しめる病気を『ディセテシア・エチオピカ(dysaesthesia aethiopica。エチオピア感覚障害)』と名付けた。それはつまり、(劣等人種か失ってしまった部分なのか)頭蓋骨中の大脳物質の欠如と結びついた血液の大気化、(呼吸機能の)不完全性のための、自己管理が不可能なほどの精神能力の低さらしい。
カートライトは、ディセテシア・エチオピカの治療法も提案している。曰く「血液の脱炭酸作用を助けるために肝臓、皮膚、腎臓を刺激するのがよい。皮膚を刺激するのに温かい湯と石鹸で患者をよく洗う。さらに油を全身に塗布し、革でこする。さらに新鮮な外気と日光に晒された環境で、体力仕事を行わせて、肺をひろげさせる」というような。
奴隷が逃げたがる原因の精神病は『ドラペトマニア(Drapetomania。逃走狂気)』という名称。
カートライトの考えでは、黒人というのは、不変の生理学性質として、子どもの状態から精神的に成長できないような人種のようだが、ドラペトマニアは、主人のしつけミスが招いた、不安定な精神の乱れみたいなものらしい。
アガシ。アメリカでの出会い
アメリカのハーバードで、比較動物学の博物館を創設した博物学者のルイ・アガシ(Jean Louis Rodolphe Agassiz。1807~1873)も、アメリカにおける有力なポリジェネシス支持者だった。
彼はスイス出身の移住者であったが、彼を多起源説に傾かせたのは、アメリカで下層民の黒人と接した経験からだったとされている。というかアメリカ以前には、彼は、人間は1種と主張していたらしい。
いずれにしろ、アガシは政治と人種理論を合わせることはあまり好まなかった。ようするに彼もまた、人種間に決定的な違い(優劣)があることには完全に同意していたのだが、奴隷制のような悪習には反対していた。
彼が多起源論を支持した直接的な理由は、どうも彼の個人的な生物学理論と関連していたようだ。その理論とは、反進化論者であり、信心深い創造論者でもあった彼が、動植物の地理的分布の研究などから発想した創造理論。
それはつまりは、「それぞれの種は、それぞれに「創造の中心地」を持っている。つまりあらゆる種は、それぞれ固有の場所で創造され、(一部例外はあるかもしれないが) 現在までその中心地から遠くには離れずに生きてきた」という理論である。
(アメリカに移住する以前のアガシは、人間こそが例外的な種と考えていたようだ)。
また、アガシは母親への手紙に、「モートンの頭蓋骨コレクションは、アメリカ全土の様々な種族を揃えていて、これを見るためだけにでもアメリカに旅する価値があるくらい素晴らしい」と書いている。
それに、彼の人種分類の定義についても「見事なもの」と支持していたらしい。
ビーン。計測法の信頼性問題
解剖学者ロバート・ベネット・ビーン(Robert Bennett Bean。1874~1944)も、アメリカの白人黒人の脳の比較研究を行っているが、やはり多くの点で白人が優れているという結論に達している。
ビーンは、脳の左右両半球を結ぶ線維構造、いわゆる『脳梁』に注目した。その相対的大きさから人種の優劣を測れるかもしれないと。
彼は、高度な知的機能は脳の前頭部、知覚運動能力は後頭部にあるという頭蓋計測学的な基本見解を受け入れ、前部の脳梁膝部と後部の脳梁膨大部それぞれの長さを比較。
結果、白人は比較的大きな脳梁膝を持っていたから、知能の座である脳前頭部の容量が大きいとした。また、脳梁膝は知能の他、嗅覚作用と関わる線維を含んでいるとし、さらに黒人が白人より嗅覚が優れていること前提として、しかし相対的に小さな黒人の脳梁は、黒人の知能に関する部分の欠損の強い根拠になると。また、脳の、前頭部の後頭部に対する相対的大きさに関して、黒人のは「人間とオランウータンの中間」くらいとも結論。
ビーンの主張にはまた、どの人種でも女性は男性より脳梁膝が小さいことを根拠とした、性別による優劣も含まれていた。
ビーンはあまりの多くの要因の影響を考慮する必要があるために、脳全体の大きさの比較研究については難しいとした。
しかし、そもそも彼が利用していたのは、医学校に提供された身元不明の死体。そして一般に黒人が死体に対して敬意を払わないことは常識(?)で、彼らの中で身分が高い人でさえも、その死体は粗末に扱われると考えられていた。つまりは、ビーンのサンプルの内、白人のは売春婦とか生活困窮者といった社会底辺の人たちの死体ばかりだが、黒人のは(あくまでも黒人種基準で) 優勝した時の死体も含まれているはずであった。
彼の考えでは、社会の階級はそのまま、個々人の本質的優劣差でもあったのだろう。ビーンは、脳自体のサイズについては、仮に大した差が見出せなかったとしても、それは結局のところ、 白人の中でも下等な者たちが、黒人の中の優れた者たちと同じようなレベルということにすぎないとした。
後に、ビーンの研究に懐疑的であったフランクリン・P・モール(Franklin Paine Mall。1862~1917)は、どの脳が白人ので、どの脳が黒人かをわからないようにした上で、ビーンの計測法を試したが、人種の間の明らかな違いは見いだせなかったという。
ティーデマン。偉大な人種平等主義者
1816年から1849年まで、ハイデルベルク大学で解剖学、生理学、動物学の教授を務めたフリードリッヒ・ティーデマン(Friedrich Tiedemann。1781~1861)は、(当時の一般的な知的エリートとして)若い頃にヨーロッパのあちこちの大学で巡る中で、キュヴィエから動物学、ブルーメンバッハから人類学を学んだ。
黒人の脳とヨーロッパ人およびオランウータンの脳との比較
研究者としてティーデマンは、魚類、爬虫類、鳥類に関する教科書などを書き、1816年には棘皮動物の形態に関する研究でパリ科学アカデミーから表彰された。
そしてハイデルベルクの教授となってから、ティーデマンは、生化学者レオポルト・グメリン(Leopold Gmelin。1788~1853)と組んで、ヒトの器官に関する未解決の問題に取り組み、特に消化に関して、いくつかの重要な発見をした。
そんな彼だが(そこまでの経緯はかなり謎であるが)1836年に、イギリスの学術誌に英語で書いた論文「黒人の脳とヨーロッパ人およびオランウータンの脳との比較」 を発表。
これは、人種差別に関する近代の科学史において、もしかしたら最も重要な論文と言えるかもしれない。
それは実質的に、人種差別を正当化してきたあらゆる思想への攻撃でもあった。
アフリカ人はヨーロッパ人と同じくらい美しい
ティーデマンは、(中でも特に尊敬していたらしい)師のひとりであるブルーメンバッハに倣い、人種分類のための基準として普遍的な美しさを採用した。ただティーデマンは、(奴隷の黒人が置かれた過酷な環境の影響がない)本来のアフリカ人は、普通にコーカソイドと同じ美しさを有していると考えた(彼の説明はしかし、白い肌、直毛、薄い唇というような特徴が「より美しい」というような常識が、彼の時代のヨーロッパでどれほど常識だったかを示してもいる)
奴隷としてでなく、自由に暮らしているアフリカ人は「多くの自然学者たちが語るものと違って、肌の色の黒さは控えめで、髪もあまりチリチリでない。鼻は扁平あまりでなく、唇もそれほど厚くない。彼らは大半、頭骨は整った形状で、美しい顔立ちをして、好ましい感じだ。女性も同じくらい整った顔立ちで、肌の色を除けばヨーロッパの女性と同じくらい美しい」
多くの博物学者たちの主張は間違っている
ティーデマンの「人種間に本質的な性能の違い(知的能力の優劣)がない」という考えの根拠としては、解剖学者としての研究成果があった。
彼は、コーカソイド、アフリカ黒人、オランウータンの脳に見られるちがいを調べた。しかし人種や性が異なっても形態上、構造上のちがいは見つからなかった。
形態だけでなく、絶対的な大きさに関しても、彼はしっかり調べた。ただし、構造は無視して、ただ大きさだけを比べていく場合、少なくとも人種と全く関係ないところで、その大きさには幅があることは当然ティーデマンも認識していた。脳の大きさは、体の大きさに関係していることはかなり確実であったから、例えば(一般的に女性は男性より小柄なことが多いから) 女性と男性の名を適当に選んでいけば 南西の方が サイズが大きいから賢いのだというような 結論が出されたりするかもしれない。
しかしティーデマンは、ちゃんと体のサイズを考慮して考えると、性別による脳の大きさの違いなど大して見出せないし、むしろ女性の方が大きいかもしれないとまで彼は考えた。
「女性の脳は男性よりも絶対的に小さいとアリストテレスは指摘しているが、体の大きさで比べれば相対的に小さいとは言えない。女性のほうが男性よりも一般に体重が少ないから。むしろ体の大きさと比べた場合の女性の脳は、大半の部位が男性より大きい」
ティーデマンは、偏見をもつ研究者たちが、(白人種が優れているという)自説に合致する頭骨サンプルを選んでいる可能性に気づいていた。アフリカ人の頭骨については最初のサンプルを、コーカソイドについては最大のサンプルを選べば、あたかも、人種間の脳の大きさに差があるような研究結果を出せるだろうと。
ティーデマンは、自分の研究においては、個々のサンプルの差の影響がなるべく出ないように、とにかく、自分が集めれるだけの大量のデータを用いた。そして彼は「人種間に脳の大きさの違いは認められない」と確信したのだった。さらに、知能の原因は明らかに脳であるのだから、その構造も大きさも人種ごとの違いが全然見られないということは、少なくとも知的能力に関しては、人種による差なんてあるはずがないと論じた。
彼ははっきりと語った。「ヨーロッパの人の脳が、アフリカの黒人より大きいという、多くの博物学者たちの主張は間違っている」
ティーデマンは、 基本的に人種分類研究の時に使われる黒人種のサンプルは、奴隷としてひどい目にあわされ、生物種としての様々な側面をひどく弱められてしまった者たちの、歪められたものにすぎないとした。
「彼らは故国や家族と引き裂かれ、奴隷にされてしまった人々だ……不幸にもヨーロッパ人にその存在が知られてしまったため、彼らがもともとそなえていた優れた特徴は、奴隷状態の恐怖により破壊されてしまったのだろう」と。
発達過程、発生過程に階級を見ること
ティーデマンが1816年に発表した、ヒトの脳の発生を、様々な脊椎動物の成体の脳と比較した研究書は、彼の代表作の1冊。
ティーデマンがどうにか解き明かそうとしていた謎は、(ダーウィン進化論もまだなかったこともあって)彼の世代の生物学者が取り組むものとしては普通だった。彼は、胚発生という現象が生物種に関係なくただ1つの一般法則に従うのか、それとも生物ごとに異なる過程があるのかを研究していた。
小さくて単純な初期状態から、大きくて複雑な成体への流れは、様々な生物種で共通しているように見えるが、そうだとするなら下等生物の成体というのは、高等生物の発生段階が途中で止まったものかもしれない。ティーデマンは、ヒトの胎児の発達と、魚類からヒトまで(つまり脊椎動物の中で最も下等な動物から、最も高等な生物まで)の脳を比較した場合に描ける、その構造体の形成、発展の系列が一致していることを見いだしていた。
実のところ、そのような発生過程と成長過程の関連性は、生物種のランク付けの一般的な根拠にもなっていた。多くの者がそれを人種のレベルで採用して、「黒人の成長段階を白人は子供の時期までに終えるから、明らかに白人が上位となる」というように論じた。その根拠としてティーデマンの研究が引用されることすら珍しくなかったとされる。だがティーデマン自身は、自らの研究によって示した、そのような生物種の階級づけの根拠を人種に拡張することはなかった。