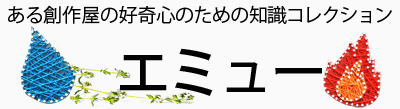ギリシア神話における人魚
今、一般的な人魚のイメージといえば、おそらくは人間の上半身に魚の下半身を持つというような生物であろう。
よく聞く、マーメイド(Mermaid)というのは、そのような人魚の内の女で、マーマン(Merman)は人魚の男を意味する。
以下の話では、人魚(あるいはマーメイド、マーマン)といえば(下半身か上半身かはともかくとして)少なくとも半人半魚の姿の存在とする。
最古のマーメイド伝説として、紀元前1000年頃のアッシリアの伝説がある。
それは例えば、不都合な妊娠を恥じた巫女のアタルガティス(Atargatis)が海に身を投げた。しかし、魚の尾を持った女神として生まれ変わったというような話。
また、2世紀ごろのギリシアの著作家ルキアノス(Lucianos)は、ヒエロポリス(トルコのローマ都市遺跡)の神殿に飾られている女神の像には、足の代わりに魚の尾がついていた、と書いているという。
ギリシャ神話の愛の女神アフロディーテ(Aphrodite)も、海の泡から生まれ、貝殻に乗って陸にたどり着いたともされているから、マーメイドではないかという説がある。
ネレーイス。海の美しい娘たち
ギリシャ神話において、陸地を囲む海流オケアノス(Oceanus)と、豊穣の海テテュス(Tethys)は、数千(たいてい3000くらい)の、深海を守る娘たちを産んだという。さらにその内のひとりであるドリス(Doris)は、海の老神ネレウス(Nereus)との間に、ネレーイス(Nereides)という娘たちを生んだ。
ネレーイスは、美しい娘たちで、イルカやシーホース(海馬、あるいは半馬半魚)といった、海洋生物に乗り、大海を自由に流れていくとされる。
ネレーイスは、その体自体に魚の要素がない場合でも、マーメイドと同類と考えられていたようである。しかし船乗りたちを誘惑して海へと誘い込む危険なマーメイドとは異なり、とても親切な彼女たちは、嵐を警告したり、よい漁場を見つけてあげたりして、船乗りたちを守ったともされる。
単眼の巨人一族であるキュクロプス(Cyclops)のポリュペモス(Polyphemus)に愛されたガラテア(Galatea)は、ネレーイスだった。
彼女は羊飼いの若者に恋をしていたので、ポリュペモスの求愛を拒否。それで怒ったポリュペモスは、若者に巨大な岩を投げつけて殺してしまう。ガラテアは悲しみながらも、恋人の血を川に変えたとされている。
ナイアス。川や泉、聖なる井戸の精霊
ネレーイスに似た種族として、ナイアス(Naiades)というのも知られている。しかし、海に生息しているネレーイスに対し、ナイアスは川や泉といった淡水の水辺に生きていたという。
 「地球の水資源」おいしい水と地下水。水の惑星の貴重な淡水
「地球の水資源」おいしい水と地下水。水の惑星の貴重な淡水
ナイアスは、ネレーイスのように親切ではなく、人を誘惑して連れ去ってしまうこともある。しかし民間信仰においては、豊穣の女神として崇拝されることも多かったようだ。
ナイアスが守護する水には、癒しの力や、予知能力を授ける効果もあったとされている。ヨーロッパにおける川や泉、聖なる井戸などに住む女の精霊に関して、ナイアスが起源(かもしれない)とされているものは多いという。例えば、ドイツのラインの乙女(Rhinemaidens)、ゲルマン系神話のニクス(Nix)、フランスのメリュジーヌ(Melusine)、スラブのルサルカ(Rusalka)、ケルトの聖なる井戸の精(Celtic Holy Wells)など。
人魚列伝
ワーグナーのオペラにおけるラインの乙女
ラインの乙女は、リヒャルト・ワーグナーのオペラ「ニーベルングの指環(Der Ring des Nibelungen)」に登場する、それぞれにフォグリンデ(Woglinde)、ウェルグンデ(Wellgunde)、フロスヒルデ(Flosshilde)という名を持つ3人の水の精。
彼女らは、ラインの黄金の守護者でもあり、 黄金得るあるいは奪うためには、愛の拒絶が必要となる。そのような設定はワーグナーの創作とされる。
乙女たちもオリジナルと思われるが、しかしその創作の過程で多くの水精(ニンフ)の伝承が参考にされたようだ。
ニクス、ニクセ。悪意ある踊り子精
ニクスは、ゲルマンの伝説に登場する水精。
ニクシー(nixie)という名前も有名な方。地域によって名前、それに姿も様々だが、ドイツにおいては、たいてい人魚であるという。また、人魚のニクスは男性で、ニクセ(Nixe)という女性版がいるとも。
普通は美しい水中の宮殿に住み、いろいろな姿(乙女や老婆だけでなく、海馬やドラゴンなど)で現れ、透明になることも可能。真の姿か、変身後にも消せない特徴なのか、人魚のニクスは、緑の歯を持ち、緑の帽子をかぶっているなんて話もある。
また、ニクスたちは非常に音楽を好み、優れたダンサーであり、予言者でもあるが、これらの特性が、普通の人間に変身している彼らを見破る手段になる場合もある。ニクスが化けた人の服は濡れているという説もある。
ニクスは悪意ある存在で、人の子を誘拐したり、人を海に誘って溺死させたりする話もある。水面でニクスが踊っているところに泳ぐ人が通りかかった時、その人は溺れるとも。また、ニクセの声はとても美しく、人間の男には気が狂うほどに魅力的とか。
さらった人間と結婚し、ハーフの子を産ませるか、産む者もいるという。助産婦をさらい、出産を手伝わせたりもするらしい。
メリュジーヌ。死の前兆をもたらす何か
ヨーロッパの民間伝承における、聖なる井戸や淡水領域(川)の女の精。特にフランスの北部、西部、ルクセンブルグ、低地の方と関係が深いとされる。
基本的に、腰から下が魚かヘビとして描かれる。また、翼か、2つの尾、またはその両方を有する。
14世紀くらいに神聖ローマ帝国、ボヘミア、ハンガリーを統治したリンブルグ・ルクセンブルグ(Limburg Luxemburg dynasty)。12世紀くらいにイングランドを統治したフランス系のアンジュー(House of Anjou)あるいはプランタジネット(Plantagenet Dynasty)。やはりフランス系で、エルサレム、キプロス、アルメニアの王を輩出し、中世のイギリス、フランスに強い影響力を持っていたリュジニャン家(House of Lusignan)など、いくつか、フランスやルクセンブルクの方と関連ある王家は、民話や中世文学上で、メリュジーヌの子孫のように語られることもあるようだ。
メリュジーヌという名前は水精だけでなく、大地(豊穣)の妖精、妖精、サキュバス、死の前兆をもたらす何かを意味する場合もあるという。
ルサルカ。不幸な女の幽霊
スラヴ民族に語り継がれたルサルカは、精霊というより幽霊で、水辺で死んだ女性、あるいは洗礼を受ける前に死んだ赤ん坊などが、ルサルカになるとも。
普通その姿は、人魚でなく裸か半裸の女として描かれるが、ヨーロッパの他の人魚伝説との関連がよく語られる。
ルサルカはただの死者というだけではなく、悪霊というような類であることが基本で、生きた人間に害をなす話もそれなりに知られる。彼女の美しい外見や声に誘惑された若い男性の足に、その長い髪を絡ませ溺死させようとする。彼女の体は滑りやすく、哀れな男は、救いを求めて彼女の体にしがみつくこともできない。残酷なルサルカは、犠牲者が溺れる様を笑いながら観察するともされる。また、ルサルカの美しさは普遍的というより、誘惑相手の好みに合わせて変身した結果という説がある。(これは邪悪、あるいは汚れし霊の一般的傾向ともされる)その緩んだ髪の毛の色は緑とされることが多いようだ。目に瞳孔がないという話もある。そしてまた、魚の骨の櫛を持っているらしいが、それは水の女精として一般的だという。
悪霊的なイメージがある一方で、ルサルカは、 キリスト教における復活祭(Easter)とも関連あるとされるスラヴの伝統的な祭り『緑の週(Green week)』の時期に、よく関連付けられてきたが、その時には豊穣をもたらす自然神としての一面を見せもする。
そもそも緑の週は、もともと『死者崇拝(cult of the dead)』や『春の農業の儀式(spring agricultural rites)』に繋がっている伝統なようだ。
緑の週の儀式で作られることがある卵や花冠の供物は、この時期に活発に活動する、あるいは陸に上がってくるルサルカをなだめると考えられた。供物に満足したルサルカは、季節中は村から離れるのだ。
ルサルカはしかし、水と肥沃度と関わりが強く、緑の週に陸に上がって走り回る彼女らは、畑(ライ麦畑や豆畑)に水分と活力をもたらしもする。だから、意図的に彼女らが呼び出されることもあるが、その場合、大人たちは、子どもたちに畑に近づかないよう警告したとも。
緑の週の間は、水泳も禁止されている場合があったが、それもルサルカを恐れてのことだったとされる。
ルサルカという名には、古くは学術的なイメージがあって、20世紀くらいまでのロシアでは、ヴォジニザ(vodyanitsa)やマブカ(mavka)といった、地方ごとの他の名前の方が、より大衆文化の中で一般的だったという説もある。
民族学者のウラジミール・プロップ(Vladimir Yakovlevich Propp (1895~1970)は、ルサルカというのは本来、(キリスト教徒ではない?)異教徒のスラブ人が使用した名称で、豊穣や多産と結びついていたが、邪悪な存在ではなかったとしている。春に水から出て、生命の水を畑にもたらしてくれた。
しかし19世紀になると、ルサルカは汚れし危険な霊となった。
民族学者としてプロップの師であるドミトリー・ゼレニン(Dmitry Konstantinovich Zelenin。1878~1954)は、ルサルカを、不幸な結婚や結婚生活、望まない妊娠のために、(特に溺死による)自殺を選んだ女性の霊を起源とする説を出した。
ルサルカの悪意は恨みのためであり、復讐を遂げたなら静かに消えさると語られる場合もある。
ケルトの聖なる井戸の精
井戸の精の伝説は世界中にあるが、普通、「ケルトの聖なる井戸」と言えば、アイルランド全土で見られるという、まさしく聖なる井戸である。
井戸には純粋な水があって、人々はそれぞれの願いを込めて、そこにヒナギクやキンポウゲといった花、あるいはロザリオやキャンドル、カードや杖や人形といった神秘的意味を有する品などを供えたりするという。そうした儀式は、カトリックの信仰と関わりがあるともされるが、起源はキリスト教伝来以前という説もある。
いずれにしろ聖なる井戸の伝説は、人魚伝説自体とはあまり関連がないようにも思える。しかし水源という出入り口で繋がる異世界領域というのは、人魚の見た目の水の精霊の世界というようなものをイメージもさせる。
井戸の綺麗な水は、癒しの力と関連付けられることもあるが、そうした治療的特性は、単に化学的な話でなく、その地域に住んでいたか、あるいは関連する聖人の奇跡に起因する見方もある。古くは(あるいは迷信深い人なら現在でも)病気になった時に、聖なる井戸の水に自らの装飾品を浸すことで、癒しを求めることもあった。
キリスト教以前のアイルランドの暮らしは、自然界との関わりが強くて、植物の栽培でも、動物の育成においても、井戸の水は重要で、神聖視するべき対象と言えた。
古い教会には、地下の泉に通じる地下室があることがあり、それは、教会の真下にある内側の聖域、内側の聖なる井戸と見なしてよい。そのような教会の「異教の聖なる井戸」の近くに建てられたものであり、初期のケルト系教会は、それら聖なる井戸を洗礼のために利用したとも。
元々ケルトには『知恵の井戸(Well of wisdom)』という伝承があって、それは異界の中心ともされる。ケルト人にとって、知恵の井戸は、水を通して祖先を称えるための神聖な場であったという話もある。
カトリック人口が多いアイルランドにおいて、古くから神聖視される多くの井戸には、聖人が関連付けられているが、なぜか多くは女性のようだ。何らかの事情(例えば禁じられてたりとか)で教会に集まることができない時、井戸を仮の集会場として、水を通して祈ることもあったとか。
井戸にコインを投げ込む伝統は、完全にキリスト教以前に起源を持つ可能性が高い習慣とされる。どうも古代ケルト人は、貴重な金属の品を水域に投げて捧げることで、異教の神々への信仰を示したようだ。金や銀で造られた剣や盾も投げられたが、その価値から考えて、むしろ実用的なものではなかったはずで、そのような品は初めから儀式で捧げるように作られたものだったと考える民族学者、考古学者もいる。
宗教的儀式における奉納品というのは、ケルト世界において、井戸(あるいは水源)が、「異世界への入り口」だったことを示唆しているとする向きもある。古代人は井戸水を介して、彼らの精神的同盟国に贈り物を与え、祝福、実り多い収穫、戦いでの勝利という見返りを望んだのだと。
現在にも、願いを込めてコインなどを井戸(他には噴水など)に投げ込む習慣はあるが、直接投げ込むわけでなく、水源の隣にコインボックスが設置されてたりする場合もけっこうある。それはもちろん、投げ込まれたコインのために、井戸の水質が低下するのを防ぐためである。宗教的精神と、科学的知識からの道徳の折り合いである。
セルキー。アザラシの皮をかぶった海底人
アイルランドやスコットランド、アイスランドなどでも語られる、美女に変身できるか、あるいは変装したアザラシだが、その姿は人魚だったという目撃例もわりとある。
多くの話の起源が、オークニー諸島、シェトランド諸島にあるとも。一部では、海のエルフと呼ばれることもあるらしい。
セルキー(Selkie)に関して、よくある典型的な話として、羽衣伝説的なのがある。
つまり、毛皮を脱いで水浴びしていたセルキーの群れに出会った漁師の男が、毛皮を盗み、陸に上がることを余儀なくされたセルキーが、そのまま男と結婚するというもの。男とセルキーの間にはやがて水かきのある子供が産まれるが、ある時、自分の毛皮を見つけたセルキーは海へと逃げてしまう。
人間の妻になったセルキーは、しかし陸で暮らしている間中、真の故郷のことが忘れられず、海を前にすると、よく悲しげな姿を見せる。海では同族の夫がすでに存在し、待っている場合もある。
人間の男が、その正体を知らないで、セルキーを妻にしてしまったという話などでは、たいてい、その正体を知ってしまうというのが物語の結末となる。
海に去ったセルキーが戻ってくることはあまりないが、子供たちの前には時に現れるという説もある。その場合、人間の姿でなくアザラシの姿で、母親とも名乗らず、ただの動物のように振る舞ったりすることもある。
男のセルキーの話もあり、基本的には孤独な漁師の妻が、海に7粒の涙をこぼすと、男のセルキーが波間から現れて、妻を誘惑するとか、そういうもの。
人とセルキー(アザラシ?)の子は、手に水かきを持つとされるが、それにはどうも再生機能があるらしい。普通の人間として生きようとする子供は、指の間の角質の膜を切り取るという行為を定期的に続けなければならないようなのだ。
先住民でもある研究者として、オークニー諸島の様々な伝説を収集したウォルター・トレイル・デニソン(Walter Traill Dennison。1825~1894)によると、そのようなハーフの子孫らしい何人かに、実際そういう遺伝的特徴が認められたこともあるとか。
セルキーという存在は、祝福されない魂を収容する器であり、7年に1度しか人間の形をとることができないという説もある。それによると彼らの正体は、罪深い悪行を犯した人間、あるいは堕天使だという。
オークニーでは、セルキーは(ハイイロアザラシ以上を基準として)大きなアザラシのことで、つまり小さなアザラシには人間に変身する能力を持たないとも。
海底には、海底人の領域(おそらく巨大な泡の中のような世界)があって、アザラシの民はそこで生きている訳だが、この場合にアザラシの衣は、陸へ続く水路を進むための保護スーツというように示唆されている場合もある。皮膚服を喪失した彼らは、海底の国に戻れないとされるが、もしも現在の文明の機器である潜水服などがそれの代用にできないのなら、非常に興味深い点であろう。
スコットランドの民俗学者デビッド・マクリッチー(David MacRitchie。1851~1925)は、スコットランドの初期入植者が、その(動物の皮で作られた)カヤック(船)や衣服のために、先住民を誤認したことが、アザラシ人間伝説の始まりではないかという説を出したらしい。
メロウ。妖精人魚
アイルランドのおとぎ話によく登場するこの人魚の起源は、ギリシャ神話において、美しい歌声で船乗りの心を誘惑するという半人半鳥の生物セイレーン(sirens)であるという説がある。
このメロウ(merrow)はまた、実はアザラシの女性であり、セルキーとの関連が示唆される場合もある。やはり人間との子を産むことも可能で、コネマラという土地に由来するコネリー氏族(Conneely clan of Connemara)には、アザラシの子孫を有するという伝説があったとも。
トマス・クロフトン・クローカー(Thomas Crofton Croker。1798~1854)という人により、1828年に最初に発表された、メロウに関する2つの物語、『ゴルラスの婦人(Lady of Gollerus)』と『魂の籠(The Soul Cage)』の内、魂の籠の方は 古くからの伝説というわけではなく、トマス・カイトリー(Thomas Keightley。1789~1872)という作家の創作らしい。
メロウという人魚を世間に浸透させた、オハンロン(John Canon O’Hanlon。1821~1905)やウェイツ(William Butler Yeats。1865~1939)といった作家は、基本的にはクローカーから引用していたとされる。
女性のメロウは典型的な人魚で、髪の毛が緑色。上半身は完全に人間というわけでもなく、手には水かきが見られるという。
けっこう人間に対して友好的で、恋に落ちたり、結婚することもあるが、 激混みが恋しくて去ってしまうことも多いようだ。しかしメロウが持つ『魔法の頭巾(cohuleen druith。コホリン・ドゥリュー)』を上手く隠すことで、彼女を陸に引き留めておけるらしい。このコホリン・ドゥリューなる被り物は、セルキーの衣と同じく、潜水服の役割を果たすとも。
例によって、人とメロウの子には、うろこの皮膚や水かきといった特徴が遺伝するという。
メロウの女性は時に、若い男に魔法をかけて、海中で共に暮らせるようにする場合もある。
興味深いことに、髪の毛だけでなくその体も緑色なメロウの男は通常、赤鼻に豚みたいな目、つまりは容姿が醜いとされ、女性のメロウが人間と恋愛したがる原因はそれだとする説もある。
セドナ。怒りにより嵐を引き起こす女神
北極園のイヌイットが信仰している海の女神だが、その姿は、アザラシの下半身と尾に、もつれた長い髭を生やした女の顔を持っている、巨大なマーメイドという説がある。
元々セドナ(Sedna)は美しい人間の娘だった。しかしある時、邪悪な鳥の精霊に騙され、結婚を強いられる事になってしまう。
彼女は助けに来てくれた父親と共に逃げたのだが、急いでカヤックを漕ぐ2人に、鳥の精霊が激しい怒りの嵐をぶつけてきた。父は恐れをなし、娘を嵐の海へと突き落としたが、娘は必死にカヤックにしがみつく。ついには、父は娘の指を切り落として突き放した。
その時に切り落とされた指が、クジラやアザラシなどの生物となり、彼女はその主人たる女神となったのだった。そしてその怒りは、今でも激しい嵐を引き起こすのだという。
イヌイットのシャーマンは、毎年セドナの機嫌をとり、豊漁を願うという。
 「イヌイット」かつてエスキモーと呼ばれた、北の地域の先住民たち
「イヌイット」かつてエスキモーと呼ばれた、北の地域の先住民たち
ヨークヨーク。緑の髪の毛
水面に海藻や、緑の藻がたくさん浮かんでいる場合、オーストラリアの先住民たちは、ンガルクンブリヤイミ(Ngalkunburriyaymi)という別名でも知られるヨークヨーク(Yawkyawk)の髪だと考えたとされている。
ヨークヨークは、聖なる池に住むとされる女の精霊で、たいていは若い娘に魚の尾がついたような、つまり人魚の姿だという。しかしワニ、トンボ、ヘビ、メカジキなどに変身することもある。
また、ヨークヨークは豊穣の精霊とされ、恵みの雨を降らし、作物の成長を促す他、彼女が住む池の側に近づいただけでも、女性は妊娠するとされる。恵みと言うか、天候を操る能力を持っていて、怒らせると嵐を起こしたりもするようだ。
人間と結婚する場合もあるが、やはりどこかで水の世界に帰り、結婚生活は終わってしまう。
この人魚は、創成の精霊ともされる虹蛇のンガルヨッド(Ngalyod)の娘、あるいは両者は同じ神の2つの側面とする説もあるが、どうやらその能力からの推測らしい。
マーミ・ワタ。神の領域の精霊
上半身が女性(まれに男性)、下半身が魚あるいは爬虫類とされる、水の精霊。
完全に人間の姿のみ見せる場合もあるようで、その場合は、単に容姿が美しいというだけでなく、流行りものの服を身につけて、綺麗な宝石もたくさん身につけているという。また髪が非常に長く、いつも金の櫛でとかしているともされる。
このマーミ・ワタ(Mami Wata)は、人間の時であっても、人魚の時であっても、時計や鏡など、高価な小物をたくさん持っている。また、ヘビを率いていることも多い。アフリカの民間伝承においては、ヘビは超能力や神性の象徴ともされているので、その関係とも。
人間に対しては気まぐれで、水泳中の人間をさらい、水中の住処に連れてくるや、自分を崇拝するよう誓わせてから解放したりする。強い引き波で海岸で泳ぐ人間を殺すこともある。しかしちゃんと自分を崇拝する者に対しては、様々な物質的な富や、精神の充実をもたらしたりもする。
ある種の伝説においては、彼女はよく川辺などで、鏡で自分を映しながら、髪をとかし、身だしなみを整えている。そこに誰か(男?)が現れると、彼女は水に逃げ込むが、その際に持ち物を残す。それは貴重なもので、持ち帰った場合、マーミ・ワタは夢の中に現れ、物の返還を要求する。拒否は不幸を招くが、彼女は忠実な者には富を与える。夢において、彼女は性的繋がりを要求することもあるとされる。
鐘、彫刻、人形、お香、精霊や犠牲の残骸とされる何か、そしてなぜかキリスト教かヒンドゥーの版画などが飾られていることもある、マーミ・ワタを信仰する神殿などでは、シンボルカラーとされる赤と白を身につけた信者たちが踊り、憑依したマーミ・ワタから、助言や祝福などを授かったりもするという。赤と白の服はマーミ・ワタの性質を表しているともされ、赤は死や破壊や熱や男性や力など、白は美しさや創造や女性や生命や精神や水や富を象徴しているようだ。
彼女はその手に鏡を持っていることもあるが、その鏡には現在と未来の動きが映る。 マーミ・ワタを信仰する者は、踊りの儀式で、(マーミ・ワタの領域である)神聖なる領域世界に現れる自分たちを実現しようとする。いい具合にその世界に馴染めれば、彼女の神聖な力を体現し、現実の発明に応用することができる訳である。
マーミ・ワタの神憑りに関連するトランス状態に入るためには、ギターやハーモニカ演奏を伴う激しい踊りが必要ともされる。食べ物や飲み物、アルコールや香りのよいものなどが贈り物として用意されることもある。現代では普通に加工食品や工業製品が捧げられる場合もある。
ジェング。秘密結社の信仰
カメルーンで信仰されている、海や川に住まうという精霊。マーミ・ワタと同種説もある。ジェング(Jengu)は単数形で、複数ではミエング(miengu)らしい。
やはり美しい容姿の人魚姿で、長い髪は縮れていて、すきっ歯を見せて笑うとも。性格は慈悲深く、また信者同士、あるいは精霊と信者の間のメッセンジャー的な役割を担ってくれることもあるようだ。信心深い者には幸運を授け、伝染病から守り、競争に勝たせるとされている。普通に病気を治す力があるとも。
ジェングの崇拝は、エカレ(ekale)なる誰かが率いる秘密結社が広めたという説がある。
ただし、そのような秘密宗教的な側面は、20世紀半ばくらいまでほぼ消滅してしまったともされる。
ジェング信仰は特に癒しと、それに薬に関係し、祈り、または呼び出しは、他の標準的な治療法が失敗した時の、最後の手段というような感じもあるようだ。
アダロ。魂の邪悪な側面
ソロモン諸島の神話において登場するという、邪悪な闇の精霊。死者の魂の邪悪な面が形になったものともされる。人間に似ているのだが、足にはヒレがあり、サメのような背鰭と、メカジキのような角を頭に持っている。
このアダロ(Adaro)は太陽に住んでいて、虹を使い地球にやってくるともされる。雨や竜巻で移動することもあるという。毒を持っていて人間を殺すこともある。
ンゴリエル(Ngorieru)という長がいて、サン・クリストバル島に棲息しているともされるが、近代の創作かもしれない。
夢の中に現れた場合は、新しい歌や踊りを教えてくれたりもするようだ。
シーモンク。海の世界のキリスト教
これはシービショップ(Sea Bishop)とか、ビショップフィッシュ(Monkfish)とも呼ばれる。
ただの巨大な魚のような感じなのだが、尾びれが長靴のように見え、胸ビレは鉤のついた指のよう。そして頭は円錐形で、司教の冠のような見かけ。
コンラッド・ゲスナー(Conrad Gesner。1516~1565)の『動物誌(Historiae animalium)』には、この生物のイラストが紹介されているという。
1531年には、ポーランド、あるいはドイツの海で、このシーモンク(Sea monk)が捕獲されたという話もある。この時、シーモンクは司教たちの前へと運ばれてきたが、鉤爪のような手で逃がしてほしいと伝えてきていたようだった。司教らはシーモンクを返してやることにしたが、そうすると彼(?)は、十字を切ってから、また海へ消えたという。
1850年代頃には、デンマークの動物学者ヤペトス・ステーンストルプ(Johannes Japetus Smith Steenstrup。1813~1897)が、シーモンクは巨大なイカだという説も唱えている。
 「クラーケン」海で最大、島ほども巨大とされた怪物の伝説の起源と変化
「クラーケン」海で最大、島ほども巨大とされた怪物の伝説の起源と変化
かつて、デュ・バルタス(Guillaume de Salluste Du Bartas。1544~1590)のような詩人が語ったように、 陸と空にあるものはすべて海にもあるという説があった。
つまり、海の世界にもキリスト教があり、司教はもちろん、その地位を与える法王まで存在している。司教たちは、しっかりと司教冠(ミトラ)も被っているという。
ただし彼らは言葉を喋れないともされる。
空にも、陸とは別の世界があったりしたのだろうか。だとすると、そこでの法王が神で、司教たちが天使たちとされたのかもしれない。
八百比丘尼。不死身となるための肉
日本や中国といった東洋世界でも多くの人魚が語られてきたが、基本的には西洋世界のような美しい乙女のイメージはあまり育たなかったとされる。
古代中国における(少なくとも現代人からすれば、かなりオカルト要素が強い)自然ガイドである『山海経』にも、半人半魚の生物がいくらか紹介されてたりはするが、基本的には(西洋世界の美しい人魚が語り伝えられるまで)怪物のイメージが崩れることはなかったようだ。
日本においては、人魚の肉を食べたものは不老長寿になるという伝説が古くからある。日本の多くの地域に伝承されてきた八百比丘尼の物語においては、人魚の肉を食べた娘が800年の時を、若い姿のままで生きている。
昔、ある男が、見知らぬ誰かに誘われ、おそらくは竜宮のような異世界領域に招待された。男は、人魚の肉が料理されているのを見たが、その後にご馳走として出てきたその肉料理を、気味悪がって食べないで、結局、土産として持ち帰る。持ち帰ったその人魚の肉を、男の娘、あるいは若い妻が食べてしまう。その女は不老となったが、自分だけがいつまでも生きて、周りの人が死んでいく悲しみに耐えられず、ついには比丘尼(仏道に出家した女性)となって、全国をめぐった。とそういう話。
オアンネス。地球外生物の仮説
古代バビロニア南部のカルデア地方の歴史家ベロスス(Berosus)が伝えるところによると、オアンネス(Oannes)、あるいはギリシアでクロノス(Kronos)にあたるというエア(Ea)という神は、ニムルードより出土する彫刻に見られる、魚頭の神なのだという。
ニムルドの他コルサバードでも、この神の粘土象はよく見つかっていて、封印や宝石などにもよく描かれていたようだ。
ベロスス曰く「かつてバビロンには様々な人間がいて、多くの人がカルデラに入植していた。そして彼らは、まるで動物のように法律というものが存在しない生活を送っていた。だがある時に、エリュトレアの海(ペルシア湾)のバビロニアと接する海岸から、オアンネスなる生物が姿を現す。オアンネスは魚なのだが、その頭の下には理性ある人間の顔があり、尾からは足が見えていた。オアンネスは食べ物は食べない、夜には海に戻り、日中を人間と過ごした。そして、人間たちと一緒に過ごしながら、文字や学問、技術などを伝授していた。そして、今の世の中に優れたものとされているものは、全てオアンネスが伝えたものだとされている」
そしてこの魚人間は、文明を与えたという伝説から、地球外生物なのではないか、という説もよく語られる。
人魚の正体
よく、古くギリシャやフェニキアに伝わっていた人魚伝説は、船乗りたちが、海中で子供を抱いて授乳する、海牛類のジュゴンやマナティの母子から着想を得たものだと推測されている。
人魚といえば、男の心を惑わす絶世の美女というのが一般的なイメージであるが、現実のジュゴンは、ブタかカバみたいな顔の海生哺乳類である。つまりは、とても(美女の)モデルになったとは思えない。
 「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
「哺乳類」分類や定義、それに簡単な考察の為の基礎知識
しかしヨーロッパにおいて、文明の発達とともに、近場の海から姿を見せなくなっていったジュゴンの話に、だんだん想像の尾ひれが付いていて、いつのまにか絶世の美女としての人魚伝説に変形してしまった可能性はある。
ギリシア神話に登場する、人の心を狂わせる素晴らしい美声の持ち主である海のニンフ、セイレーンたち(セイレネス)は、元は半人半鳥の存在だったとされているが、後には人魚のイメージも強まった。
ジュゴンから始まった人魚話に、海繋がりからセイレーン伝説が融合した可能性もあろう。
マナティの母子
人魚に関する古い記憶の中には、それらはとても夫婦仲がよい生物だというものが多いとされる。仮に一緒にいる夫婦の一方にモリなどを打ち込むと、無事な方は、尾でそれを叩いたりして、必死に相方を助けようとするのだという。
マナティーは通常、つがいを構成する期間がごく短いとされる。
しかし母と子は、3年ほども一緒に過ごすし、基本的に母親は子供を溺愛するとされる。だから、昔の人たちが仲のよい夫婦だと勘違いした人魚たちは、実は、ある程度大きく成長した子と、母だったのかもしれない。
コロンブスが目撃したセイレネス
1493年1月9日。
カリブ海に到達したコロンブスも、セイレネスを目撃したそうだが、これはおそらく人魚だったろうとされている。
 「クリストファー・コロンブス」アメリカの発見、地球の大きさ、出身地の謎
「クリストファー・コロンブス」アメリカの発見、地球の大きさ、出身地の謎
より正確には、それはおそらくアメリカマナティーだったのだろう。
コロンブスはヒスパニオラ島の入り江で3人のセイレネスと出会ったが、その顔は確かにいくらか人間に似ていたものの、とても美しいとは言えないような生物だったと記録した。
なぜセイレーンは人魚となったのか
ホメロスの書いたセイレーン
「船乗りを誘惑し、(最悪のパターンでは)死という不幸を招く人魚」というイメージは、紀元前8世紀頃のギリシャの詩人ホメロス(Homer)が書いた長編叙事詩『オデュッセウス』における、セイレーンに関する描写に由来するとは、よく言われる。
 「イリアス・オデュッセイア」ホメロスの二大叙事詩。ギリシア神話文学源流
「イリアス・オデュッセイア」ホメロスの二大叙事詩。ギリシア神話文学源流
ただしホメロスは、そのセイレーンなる、危険な海の生物に関する具体的な情報を、ほとんど書かなかった。そもそもその生物群がどのような姿をしていたのか、そして、なぜその歌声が人々の心を惑わすのかも謎のまま。だが後の創作家たちは、実に勝手気ままに、自分たちの想像を付け足していき、セイレーンを典型的な人魚へと変えていったのだった。
ピタゴラスの天球の音楽仮説
哲学者ピタゴラス(Pythagoras。紀元前582~紀元前496)は、 この宇宙そのものに優れた音楽性(芸術性)を認識していたとされる。
彼は、夜空に確認できる7つの天球、すなわち、月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星のそれぞれは、世界楽器の1つずつの弦であり、地球の周りを公転しながら奏でられるハーモニーは、あらゆる魂を躍動させるとした。セイレーンの歌声は、天球の音楽を垣間聞かせるものだという考え方もあった。セイレーンは天球の魂、あるいはその一部であり、世界を自転させている本質そのものと深く関わる。それはむしろ死を招くというよりも、その音楽性で、肉体という牢獄から魂を解放すると。
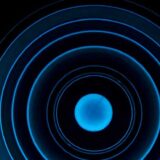 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
しかし時々、セイレーンの歌声よりもさらに美しい音楽を奏でたりすることで、その誘惑に打ち勝ち、さらには敗北によるショックを受けたセイレーンたちが、自ら海の藻屑となる(自殺する)伝承もいくらかある。
セイレーンの姿に関して、おそらく半人半鳥のイメージは人魚よりも古いが、歌で人を惑わす鳥人間というのは、その起源をかなり古くするかもしれない。
美術品に描かれていたようなギリシアの民間信仰の中では、セイレーンは翼ある精霊で、死者に付き従い、その心を音楽で慰めながら、自分たちの住処(つまり死後の世界)へと送り届ける。女の顔をした鳥(古くは男バージョンもあったようだが)というモチーフは、紀元前15~12世紀くらいのミケーネ文明や、紀元前30~15世紀くらいのクレタ文明から受け継がれてきたものと見る向きもある。 またはそれらよりもさらに古い、古代エジプトに起源を持つかもしれない。エジプトにおいては地上を去る死者の魂は人面鳥として表されていたとされる。そのような人面鳥は、ギリシアにおけるセイレーンと同族であり、音楽で人の心に影響を与える能力や、死者を誘う役割、冥界(死後の世界)との繋がりなどが共通する。
キリスト教世界で発展した、美しき悪の人魚伝説
西洋世界にキリスト教が広がり始めた時代には、 セイレーンはすでに、古い神話における雄大なイメージをほとんど失っていた。
ホメロスの注釈で、「野原で歌う鳥、あるいは魅力的で嘘つきな女の比喩。または擬人化されたお世辞。そのようなものはよく我々の心を欺き、言うなれば誇りある魂を殺すものだ」というように書かれるようにもなったこの生物は、キリスト教的な一神教世界における、人間のための何らかの意味が与えられているこの世界のあらゆる象徴的なもの1つになった。つまり、大自然の世界に共存する人間と精霊たちというような世界観は否定され、人間のために作られた特別な世界が大衆の心に浸透し始めたのである。最も重要なのは人間の救済であり、人間の行うべきことは自然の原理を知るための哲学(科学)ではなく、神があちこち配置された数々の教訓の意味を理解することみたいな。
キリスト教世界において15世紀くらいまで非常に重要なキリスト強的動物学の書であった、(3世紀くらいにギリシアのキリスト教徒に書かれたとされる)『フィシオロゴス(Physiologus。博物学)』においては、セイレーンは人魚と関連付けられているが、その姿はグロテスクだとされている。
セイレーンが娼婦という説は、(少なくとも初期の記録にはそう感じさせるような話などほとんどないにも関わらず)古代ギリシアにおいても人気を集めていたが、キリスト教の時代でもそのような設定は掘り返され、今度は人の魂を堕落させる、より邪悪な存在として語られるようになった。
その姿を美しいものとして、もはや歌声だけでなく、視覚的な魅力によっても人を惹き付けると設定も、キリスト教徒の研究者たちが広めたものという説がある。
精神的に汚れた女の誘惑が人を堕落させるというような考え方は、男性優位の見方を思わせる。
また、キリスト教にセイレーンの伝説が入ったのは、聖書のイザヤ書に関連する記述があったからともされるが、実はそれはラテン語訳の際に、「野犬」の意味であるヘブライ語tannimを誤訳した結果だったようだ。
泡の中から生まれ、死んで泡となる人魚
人魚は、泡という物理現象と関連付けされることも多い。
古代において、人魚と関連ある海の女神には、泡から生まれたというような伝説があった。そして比較的近代の、人魚を題材としたおとぎ話の中では、恋に敗れた人魚が泡となって消えてしまうというような描写が見られることがある。
海の泡から生まれるという現象を、どういうふうに解釈するべきか。
泡というのは、固体や液体の中に気体が詰まっているような状態。特に液体の場合は、気体を囲う液体が表面張力によって、膜ようなものを構成している状態として、今はよく知られる。
表面張力というのは分子間同士の結びつきを由来とするが、分子という概念自体は知らなくても、気体を覆う膜のように働く、水の性質と理解することは可能と思う。昔の人は、この現象自体にどのくらいの不思議さを感じていただろうか。
泡内部の気体領域を、表面張力によって作られた水の膜に覆われた 閉鎖系(空間)と考えた時、そこは人魚という生物の発生の場となるのだろうか。
だが、そういうことなら、滅びる時に泡となるのはなぜなのか。そちらの方は後世の創作と片付けてもよいかもしれないが……