ソクラテスの弟子。神秘主義に近かった(?)哲学者
有名な哲学者プラトン(Plato。紀元前427~紀元前347)の、現存している本は対話篇、つまりは複数人物が対話するという形式で書かれたものが多い。
そして、多くの話に登場するのがソクラテス。彼はプラトンの哲学の師だったらしいが、彼自身の著作は残っていない。
プラトンの著作のほとんどは、ソクラテスがひたすら何か語るか、あるいは誰かとの対話が描かれている。
プラトンは自分の思想とか仮説とかを、そのような対話形式の中に含ませているのか、あるいは普通にソクラテスの思想をそのまま伝えているのか、いくらか著作を読んだくらいでは判断難しいと思う。
しかし一般的には(当然といえば当然だろうが)、プラトンのどの著作でも、基本的にそこに見られるのは彼自身の考えとされる(そういう意味では、ソクラテスの本来の思想は謎が多い)
そしてプラトンといえば、(哲学はともかく)科学の歴史以上に、オカルト関係の話に興味のある人に、詳しい向きが多いかもしれない(または強い関心持たれてるかもしれない)。 それは単に、彼の書籍が宗教的、神秘的な記述にあふれているという事実だけでなく、とても人気の高いある伝説のネタ(?)を提供してくれた人なので。
端的に言えばプラトンという人は、いわゆる『アトランティス』という、古い文明世界を記録に残した訳である。
 「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。 ソクラテスの弁明、クリトン。死ぬことを考える
プラトンの師ソクラテスは、宗教的な問題のために死刑を宣告されたが、その裁判において彼が語ったとされる論。人々が想像するいくつかの世界のパターンのどれが正しいのか。どれが正しいにしても、共通して考えられる理論とは何であろうか。そういうことがよく語られている。
これはまさに、死の運命を間近にして語る言葉であるからして、死についての話題がメインであるように思う。
 「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか 死は、幸福の世界への扉か
「私の聴き慣れた(神霊の)予言的警告は、私が何か曲ったことをしようとする時には、いつも私を諫止してきた……だが今日のこの事件において、私が何をしても何を言っても、それは一度も私を諫止したことがなかった。何が理由か話そう。つまり今私の身に降りかかろうとしていることは善い事だからと思われる」
死が多くの人々が考えているほど悪いようなことではないのかもしれないとソクラテスは論じるが、 その内容は実際には「特定宗教の神、または教えなどを信じるべきか否か」という話にも関連している印象。
物理的現象としての死ぬことがどのようなものであるのか、ということより、むしろここに見られるのは、生命というものが神秘的なものなのか、あるいは物質的な現象なのかの違いをどう考えるべきか、というような話題。
「……死がある種の幸福だと考えるべき有力な理由は2つある」
つまりは、死は2つのいずれか。虚無に帰するもの、死者は何についても何らの感覚を持たない。あるいは、それとも(多くの人が語るように)ある種の世界、この世(生者の領域)からあの世(死者の領域)への魂の移転か。
夢さえ見ないほどに熟睡した夜を、他のさまざまな日の夜と比較した場合、それほどじっくり寝られるほど心地良く過ごせた日が、他にどれほどあるのか考えた場合、それはとても幸運なはず。だから、死が感覚の完全喪失、夢も見ないほど永遠に眠り続けることなら、それは良きことではないだろうかとソクラテスは語る。
しかし、よく眠れる日がどれほどいいことか、というのは、社会の中の人間ならではの疑問なのか。あるいはこの世界の中で生きていくことはずっと結構危険であって、それが常識だから、そういう発想であるのか。
一方で死ぬということが終わることでない場合、つまりは魂でも何でもいいから、何か、意識とかと関係している何かが、死んだと我々が考えるような時に、(生きている者がまさしく生きている世界とは違う?)あの世の世界へ旅立つということであるなら、その場合をどう考えるべきか。
ソクラテスは、 それこそ最大の幸福だと語る。それはそうだと。神として語られるような者、半神たち、あるいは過去に存在したとされる偉大なる者たち、そういう者たちと出会うことができるのだから。そのような幸運に巡り合うためなら、自分の命など簡単に捨てようという者もたくさんいるだろうとも。
妙な決めつけがやはり興味深いだろうか。
死ぬ時に、自身の意識に関する何もかも無くなってしまうのか、それとも何かがやはりあるのか。確かに、前者の場合は何もなくなるわけだから、死ぬこととはつまり、すっかり夢も見ない永遠の眠りにつくようなものと考えていいかもしれない。
しかし死んだ場合にまだ続く新たな世界がある場合は、そう簡単な話ではないだろ。死後の世界が、例えば死者たちがみなで会えるような、そういう世界である保証などどこにあるのか。
 「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で
「意識とは何か」科学と哲学、無意識と世界の狭間で  「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験
「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験 尊き友情をどう理解するか
『クリトン』は、『ソクラテスの弁明』の続編とされる著作だが、死がどういうことかはもうあまり関係なく、生きる場合、生きていく場合のこととか。
主に死刑執行の時が迫った時、友達らしいクリトンなる人物とソクラテスの会話であり、前作よりもやや物語的。クリトンはソクラテスをどうにか死の運命から助けてやろうとするのだが、説得されて諦めるという流れ。
これから死ぬことになっている友達を助けることができたかもしれないのに助けなかったのだと思われてしまう。本人が助かる事を拒否したのだと、本当のことを話しても大衆は信じないだろう。そしてその大衆というのは人を傷つけるのが非常に得意なんだ。
とか、クリトンの説得の言葉の中には、そういう感じのもある。
ソクラテスは「多衆が最大の禍害を加え得る者ならむしろいい。それなら彼らは最大の福利をも加え得るわけだから。それなら結構な話さ。ところが彼らはどちらも出来ない。彼らには人を賢くする力も愚かにする力もない。彼らのすることは皆偶然の結果だ」と返す。
やはりよくわからない理屈ではある(なぜ「禍害を加え得る者=福利をも加え得る者」なのか)。
しかし、クリトンの恐れていた大衆の攻撃は、通信情報コミュニティが発達している現代と比べたら、まだマシなものだったのか、(一般的な教育とか常識とか、あるいは社会のスケールとか考えるとその可能性もなくはないだろう)実はひどいものだったのか。
饗宴。神話と愛の考察
弟子のアリストテレス(Aristotelēs。紀元前384~紀元前322)などに比べると、古い神話の語る歴史などに関してプラトンは寛容だったようだが、この『饗宴』という著作などは、そのような神話の出来事の考察が多い。
『饗宴』
エロスは最古の神であるか
「……まず初めにパイドロスが語る……エロス(恋愛)は偉大な神……他の多くの点からも言われるが、とりわけその生まれにおいて」
つまり、これが最古の神であるだろうから、偉大という理屈。
このような、「古くから存在するものほどいいものだろう」という発想は、なんとなく、この世界というのがあまりうまくいっていないような感じで、長く存在するシステムは劣化していっているような。だから、新しく生まれるものは、劣化したシステムのために不備があるというような。そういう感じの世界観も思わせるだろうか。
しかし、なぜこの神(エロス)を最古だと思うのか、ということに関しては 、伝えられるどの話においても、この神の生みの親が語られていないということがあげられている(ただ同じ事情の神は、例えばカオス(混沌)など他にもいて、これは最古の神というより、最古の神々の一柱と解釈する方がおそらく正しい)
しかし「女神アプロディテは、いかなる神々よりも先に、エロスを案じ出された」という引用もある。
 「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン
「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン エロスは最古で善きもの。人にとって最も善きものの根源でもある。ようするに誰かを愛しく思うというような気持ち。そして、そのような愛しく思う対象に、素晴らしい少年(美少年?)以上のものがあろうか。というような話など、そこはよく言われるように、かなり人間中心的な世界観における価値観が見える。
八本の手足を有する第三の性別
アリストパネスという人は、そもそも人間は最初、恋愛というものを知らなかったという自説を語る。
根拠はともかく、ここでは、人間の起源にも関係する話が含まれていて、微妙なところではあるが、宗教から少し離れ、現実的な話になっている(のだろうか? この時代において、人間の誕生を神の業というだけで片付けないで、自然のシステムによるものとするのは、どういうことだったか)。
「……諸君は人間の本来の姿と、それが体験してきたもろもろの出来事を理解しなければならない」
それは、厳密には人間というよりも性別の起源である。プラトンか、あるいは彼が参考にした思想などは、例えば「なぜ性別というものが存在するのか」と、そういう考察から発想されたのだろうか。
とにかく、最初、人間の性は3つあったらしい。男性と女性に加え、それら両方の性に共通である第三の性。
ようするに男女両方合わせているというか、正確には、男性と女性に分かれていない性別があったみたいである。
自然界に見られる雌雄同体の生物のようなものと考えていたのかは、ちょっとわからない。そっちよりも特別性が高く考えられてるような印象もないではない。
そして個々の人間の形態の話。
それは最初「全体として球形。背骨と肋骨をぐるりと周りに備え、手足を4本ずつ持つ。顔も2つで、それらはまったく同じで、円筒形をなす頸の上についている。頭は、互いに反対向きに置かれている両方の顔の上に1つ。耳は4つ、陰部(性器も?)は2つ。とにかく、 色々と半分に分かれた性の者たちの倍ある」というような存在であったとか。
球体の体に8本の手足なんて言うと、現代ならゲームにでも出てきそうなクリーチャー的な姿を思い浮かべてしまうかもしれないが、それが進む時の様子というのがまた、そういうクリーチャー的。
ようするに、それは8本の手足を使って、回転しながら動くのだという。
恐るべき月の子と、神々のジレンマ
3種類の人間の起源はどうなっているか。
男性は太陽、女性は大地、そして両性に与っているものは月の子孫とか。
子孫というか、この世界の中の要素としてそれら(太陽、大地、月)があり、それらから最初の誰かが生じたとか、そういう感じなのかもしれない。
また月の子は、 能力的に恐るべきものがあり(それは動きも円形であるから、というようにも語られていて、円という形に何か特別な意味を見出していたことがわかりやすい)、神々の地位をも脅かしかねないような存在であった。それで神々の父ゼウスは、それらを2つの弱い人間1人ずつに分けることを考えた。
しかし人間たちを皆殺しにする案も出たが、神に捧げられる尊敬や犠牲がなくなるからと却下している(3種の人の1種だけ狙い撃つのが難しいのか、そもそも基本的に人間とは、その球体のやつだったのか。後の話からしておそらく後者)。
ところで、「人間の信仰が神々の糧」みたいな考え方は、いったい、いつどこが起源なんだろうか。
なんでいろいろな本で、あるいは創作物とかでも、それが当たり前のようであるのか。神なる存在の定義は「人々の信仰を糧とする存在(生命?)」とでも言うのだろうか(実はそうなのかもしれないけど)。
なぜ男女は惹かれあい、結果、子が生まれるのか
男女は牽かれあうもので、その原因が、半身のそれぞれは自分の半身をこがれ求め、またいっしょになろうとするから、などと語られる。
しかし、出会った2つの半分は、ただ絡み合うだけで、死んでいく。それはさすがに憐れに思ったゼウスは、またひと工夫する。
つまり、それらの陰部を前方に移したのだという。その時までは外側についていて、生むのも生ませるのも、お互いの中でなく、大地の中に行なっていたらしい(曰く、それはセミと同じ生殖方法)。
それで、陰部を前方に移した人は、生産をお互いの体内、男性により女性の内部で行われるようになった。絡み合いたがる彼らにふさわしい方法を神は与えた、とも言えるのかもしれない。
 人はなぜ恋をするのか?「恋愛の心理学」
人はなぜ恋をするのか?「恋愛の心理学」  「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎 人間以外の生物は機械的(不完全な無脊椎動物などは、自然発生か普通、みたいな説も古代ギリシャではわりと一般的だったとされる)で、人間だけが性愛というものを理解しているとして、その性愛のために繋がりたがり、そしてその結果、子どもが生じるということ。このようなシステムがどのように出来上がったのかを考えていた結果が、こんな世界観だったのだろうか。
この半身仮説において、どうも全体として”完全男性”、あるいは”完全女性”だった昔の者たちも、半身ずつに分けられたかのように語られていることは、ちょっと面白いもしれない。例えば完全男性や完全女性の半身とかが同性愛者になったそうである。
つまり半身説は、様々な性的指向などの説明も一応ある程度できるようになっている。
 「性の進化」有性生殖のメリット、デメリット。オスとメスの戦い
「性の進化」有性生殖のメリット、デメリット。オスとメスの戦い ところで、基本的に男は女よりも優れた存在という認識らしく、半身としても、完全男子の半身が優れている。よって、国家公共の仕事などに向いている優れた人は、通常、男色だとされている。
 「女性と科学」メスという性、神が決めた地位、大衆向け科学のよき面
「女性と科学」メスという性、神が決めた地位、大衆向け科学のよき面 良きダイモン、悪いダイモン
ソクラテスが時に、内なる霊の声が聞こえると語る時、 その霊(霊的存在)とは、つまり『ダイモン(daimōn)』のことであったとされている。
古代ギリシャにおいては一般的に、ダイモンは、それぞれの人々が持つか、あるいは人々に憑くようなもの。よきダイモン(エウ・ダイモン)がつくと幸福になり、悪しきダイモン(カコ・ダイモン)にとりつかれると不幸になると考えられていたという。
そして、エロスが偉大な神かどうか、という議論で、ディオティマという人はソクラテスに、「エロスを神ですらないと主張している人々がいるのに、その人々によって偉大な神であると認められようはずがない」と言う。
彼女曰く、そのような、エロスを神と信じない人々の中には、ソクラテス自身もふくまれる。
つまり、「あなたは神々はすべて幸福で美しいと主張しています……あなたが幸福だとおっしゃるのは、善きものや美しいものを所有している者のこと……しかし、あなたは認められた。エロスは、美なるものに欠けているがために、まさしく自分に欠けているそのものを欲している……いやしくも美なるものに与かっていないものが、どうして神でありえましょうか」
このような理屈を語られたソクラテスは、「……いったい何だというのです? エロスは死すべきものなのですか?」と問う。
ディオティマの答は、「死すべきものと不死なるものとの中間にあるもの」 。つまりそれは「偉大なダイモン」なのだという。
ディオティマは、ダイモンなるものはすべてが、神と死すべきものとの中間の存在とも説明する。そしてその説明の限りではこれは、ユダヤ教派生の世界観の天使に近いように思われる。
 「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?  「天使」神の使いたちの種類、階級、役割。七大天使。四大天使。
「天使」神の使いたちの種類、階級、役割。七大天使。四大天使。 ようするに、「人間たちから出てくるものを神々のため、また神々より与えられるものを人間たちのために、通訳したり伝達したりする」
人間の祈りや犠牲と、神々からの勅令や犠牲の意味をしっかり発生させる者というような印象もある。この宇宙(壮大な1つの結合体)における、神々と人間たちの隔たりの領域を埋める者とも。
さらには、様々な占術、秘儀、呪術、魔術などが機能する原理としても、人々と神々を仲介するこのダイモンというのは重要らしい。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎 永遠なる存在がなぜ必要なのか
しかし神とはどんな存在なのであろうか。
それは死なない存在で、そして、とても美しい存在らしい。
世界自体が無限に続いてきたようなものでないとすれば、というよりいつか終焉の時がくるようなものなのであれば、死なない存在は世界の存在に関係なく生きていられる存在ということになる。だから創造主的な役割を想定することも、普通の生物の場合よりはかなり簡単と思う。
 「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか
「人はなぜ神を信じるのか」そもそも神とは何か、何を理解してるつもりなのか もっとも現在の我々は、この世界がコンピューターシュミレーションとかの世界とするなら、別の宇宙の普通の知的生物が、この世界の創造者かもしれない。というようなこともわりと考えるが。
とにかく、もしも世界が有限であるなら「ではこの有限の世界はいかにして発生したのか」という問題において、永遠に生きる存在というのは、やはり創造(クリエイト)のイメージと結びつきやすいだろう。というよりも他に考えられる可能性がない。
今でも、無から何かが発生すると考えるよりは、永遠に存在している何かが世界の発生に関わっていると考える方が、少なくともたいていの人には妥当な理論に思えるのでなかろうか。
だが問題は、そのような永遠なる何かが存在するのかどうか。
 「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性
「宇宙プログラム説」量子コンピュータのシミュレーションの可能性 古代ギリシャの哲学者たちの間で、(実体的にしろ、架空的にしろ)神々と呼ばれる存在が語られる時、その神々というのは、創造主というより「永遠なる存在」というようなイメージが強いように思う。
ソクラテスがプラトンの思想の代弁者であるとして、彼は神々やダイモンの存在は信じていても、ダイモンが具体的にどのような存在であるのか、そしてそれを利用した魔術などの原理などに関しても、説明される立場である。
この辺り、自分でもどれくらい信じていたのかとかの関係があったりするだろうか。
幻の対話編三部作
『ティマイオス』と『クリティアス』は、おそらくプラトンの作品の中でも最も有名であり、彼の思想を研究する上でも最も重要とされる2冊。
本来は三部作で、二部の途中までしかテキストが残っていないという説が有力。つまりこれは、一般的には未完の作品。
ソクラテスが、哲学者のクリティアスやティマイオスの(祖父が語っていたりとか、エジプトから伝わってきたとかいうような)昔話とかを聞く話だが、その中に、プラトンが思い描いていたと思われる、この世界の歴史とか、自然の原理とかの説明が含まれている。
 「古代エジプトの歴史」王朝の一覧、文明の発展と変化、簡単な流れ
「古代エジプトの歴史」王朝の一覧、文明の発展と変化、簡単な流れ 過去の大災害の記録
「エジプトの三角州の中に、ちょうどナイル河の分岐する頂点のあたりになるが、サイス州と呼ばれている州がある。その州最大の都市がサイス市だが、その土地の人々がかれらの都市を開いた守護神としているのは、エジプト語ではその名をネイトと呼ぶ神だ。これはギリシア語では、かれらの説によると、アテナ(ギリシャの知恵の神)だという」
エジプトの都市の中で、ギリシャの都市国家アテナイがかなり重要視されているのはなぜか。エジプトへ渡ったソロンという人は、土着の人たちに歓迎されたが、なぜそうなのか気になって、聞いてもみた。
古い記録をよく知っている神官曰く「おお、ソロンよ、あなたたちギリシア人は子供だ。ギリシア人に老人はない……あなた方は心が若いのだ。あなた方は、古い言い伝えに基づく昔の説も知識も、心に残していないから」
しかし神官が語る話は、さらに古い時代のことを説明する神話のようでもある。
まずこれまでに、人類は何度か滅亡している。どうも大災害のためらしい。最大のものは火と水が原因だが、細かな要素に注目すれば原因は無数にあるという。
神話の形で語られている伝説の中には、そのような大災害の記録が 混じっている。例えばギリシャ神話における「かつて太陽(ヘリオス)の子パエトンが、父の車を、父の軌道で走る(馬に走らせる)ことができなかったため、地上のものを焼きつくし、さらに自身も雷に撃たれて死んだ」という話は、つまり天を運行するあの巨大な火の玉(太陽)、または他の惑星も含めた各種天体群の軌道の乱れが原因となって引き起こされた地上の大災害、 全世界規模の大火事だったとか。
当時の人類は大いなる恵み、ナイル川によって救われたらしい。
しかし、これまでに何度も人類が滅亡したというよりは、滅亡寸前にまでいった。という解釈が正しいかもしれない。太陽が原因の大火事でも、人類は厳密な意味で絶滅してはいない。
あるいはプラトンは、文明の破壊=人類の絶滅、と捉えていたのかもしれない。そしてその度に人類(新たな文明)はまた再生したというような。
大火事だけでなく、大洪水に対してもエジプトは強いらしい。ようするにこの国は大災害に強いから、何度もの文明の滅亡(あるいは滅亡危機)を乗り越えて、古い記録を残しているという道理。
ちなみに、普通は大洪水の時には、山に住む者たちだけが助かり、多くの都市は沈み、海へ押し流される。しかしエジプトにおいては、「上方から平野へ水が流れ落ちるという通常の流れでなく、水は下からあふれてくるというような自然の構造があって、大洪水でも、都市が沈むということはあまりない」というような説明もある。
また、ギリシャ神話には(多くの神話で見られるように)大洪水で一度人類が絶滅の危機に陥った、というような伝説があるが、そのような話は、 たくさんあった大洪水の最後の記録とか。
 「洪水神話」世界共通の起源はあるか。ノアの方舟はその後どうなったのか
「洪水神話」世界共通の起源はあるか。ノアの方舟はその後どうなったのか 最も偉大な人種としてのギリシア民族
「過度の寒さや暑さが妨げとならない限りのどんな場所にも、多かれ少なかれ、いつも人間の種族が存在しているのには変りはないのである」
このような理屈は、どう考えるべきか。
まだ話の中で、人間の種族、人種というようなものの存在が明確に認められていることは、かなり確かと思われる。
「およそ人類を通じて最も立派な、最もすぐれた種族が、あなた方の国土にいたのを、あなた方は知らない」
これは人種の話というよりも、ギリシア人という存在を讃えるための説明。ギリシアの土地に生きていた最も素晴らしい人種。たくさんの災害を生き残ってきたその者たちの子孫が、現在のギリシア人ということであるから、結局ギリシャ人は最も偉大な人族というような。
もちろんエジプトの古い記録を記録している都市において、ギリシャが崇拝されているのはそういう理由。
 「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種
「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種 都市国家が始まったのは紀元前8000年頃なのか
「ソロンよ、かつて、水による最大の破壊に見舞われる以前、アテナイ人の国、あの都市国家が、戦争において最強で、またあらゆる面で卓抜した法と秩序を有していた。その国家の遂行した偉業も国政も、およそこの天の下で最も立派なるものだったのだ……その都市は、女神が地母神(ゲー)とヘパイストスから、あなた方の種子を引き取られた時から……我々の地の都市制度が整えられてから八千年という年数の経ったことが、われわれの国の聖なる文書に記されている。あなたたちのその都市はさらに千年古く、つまり九千年前にすでにいた」
まず、大災害の頻度がどのくらいなのか気になるところであるが。
とにかく、年代に関して、偉大なギリシャの都市の方が、おそらく当時最も古い領域とされていたエジプトよりも、さらに古いというようにして、それを讃えている感じがする。
しかしエジプト文明(エジプトの都市国家?)が、プラトン(あるいはソクラテス)の時代から8000年前に存在したという話に関して、現在ではすでに奇妙な感じであろう(現代のエジプト史の本などでは通常、エジプト文明というものが存在していたと考えられている時は、せいぜい紀元前4000年くらいからと解説される)。
プラトンはだいたい紀元前後(紀元前4世紀くらい)の人であるから、ここでの話を素直に受け取るのならエジプト文明、つまり都市国家が始まったのは紀元前8000年ぐらいとなる。
紀元前8000年頃といえば、だいたい、多数の人(サピエンス)たちが、ユーラシア大陸で(とおそらくアメリカ大陸でも)農業を基盤とした定住生活を始めたくらいとされている時期と近い。
単なる偶然であろうか。
「まずその法律だが、われわれの都市のものを参照したらどうか。というのは、現在の我々の国家の法律の多くは、それと近い……第一に、神職の人々が1つの(社会)種族として、その他の種族から区別されている。次に、手仕事に従事する人々、牧人、狩猟に携わる者、そして農夫の種族。それぞれが独立して他の領域を侵すことなく、自己の職分を果している。
また戦士の種族は、この国では、 他のすべての種族から区別されている。かれらは、軍事以外のどんなことをも関心事としないよう、法律によって定められている……こと宇宙にかんしても、そうした神的な事柄から、人間界の諸事への応用、占卜術まで、あらゆる技術を考え出したほか、あらゆる学問知識にしても、そのすべてを獲得している……この制度・組織の全部を、あの女神は、われわれに先立ってあなた方を定住させられた時、その制度として整えられた。あなた方の生まれた場所を選ばれた理由は、その土地の気候が、優れた賢き人間を産むだろうことを見て取られたから……」
実際のエジプトが、どのくらい参考にされていたのかは、判断が難しい部分でもある。ただ、ここで語られている、かなり明確に階層分けがはっきりしているような、言ってしまえば”真社会性”の生物の社会構造のような、個別の役割分担が完全に決まっている(調整されている)社会こそ、プラトンが理想としていたものだったのだろうか。
アトランティスはどのような役割を与えられてるか
プラトンに始まる最も有名な伝説と言えば、まず間違いなく、あの失われた大陸として名高いアトランティスであろう。
そしてこの、伝説の大陸(というよりも大国家)は、まず、偉大なギリシャ国の忘れられた昔話の中で出てくる。
ようするにこの大国家は引き立て役である。最も偉大な時代のギリシア国家は、このアトランティスの侵略に対してさえ、見事防衛に成功した。というような話だ。
「……文書は、 どれほどにまで大きな勢力の侵入を、あなた方の都市がかつて阻止したかを語っている。その国は、外海アトラスの大洋(大西洋)を起点とし、全ヨーロッパとアジアを侵略しようとしていた。当時、あの大洋は渡航可能だったのだ。あの大洋には、あなたたちが「ヘラクレスの柱」と呼んでいる入口(ジブラルタル海峡)の前方に、1つの島があったのだ。それはリビュア(アフリカ)とアジアを合わせたよりもなお大きなもの……あの外海こそ真の大洋であり、またこれを余すところなく取り囲んでいる陸地こそ、真実、文字通りに大陸と呼びうるものであろう。このアトランティス島に、驚くべき巨大な、諸王侯の勢力が出現し、その島の全土はもとより、他の多くの島々と、大陸のいくつかの部分を支配下におさめ、海峡内のこちら側でも、リビュアではエジプトに境を接するところまで、またヨーロッパではテレニア(イタリア半島の都市国家)の境界に到るまでの地域を支配していた。実にこの全勢力が一団となって、あなた方の土地もわれわれの土地も含めた、海峡内全地域を、隷属させようとしたことがあったのだ。さあその時、ソロンよ、あなたの都市の力は、その勇気においても強さにおいても、全人類の眼に歴然。すなわちあなた方の都市は、その勇気と戦争の技術とであらゆる都市の先頭に立ち、ある時には他の諸都市の裏切りにもあいながら、侵入者を制圧し、勝利の記念碑を建てて、未だ隷属せられていなかった者を助け、 すでに奴隷であった者たちも自由の身にしてくれたのだ」
 「世界地図の海」各海域の名前の由来、位置関係、歴史雑学いろいろ
「世界地図の海」各海域の名前の由来、位置関係、歴史雑学いろいろ 言ってしまえばアトランティス大陸は、とてつもない力を持っていたが、最も優れた人種の、最も優れた国家ではなかった。力尽くで世界を征服しようとした彼らも、真に偉大な国家の前に敗れ去った、というわけである。
だが最終的に自然の脅威はあらゆる国家の人々を痛み分けにした。
有名な、アトランティス大陸を一夜で海底に沈めたという大災害は、当時の最も偉大なギリシャ国王も滅ぼしてしまったというわけである。
「しかし後、異常な大地震と大洪水が度重なって起こった時、苛酷な日がやって来て、その一昼夜の間に、あなた方の国の戦士はすべて、一挙にして大地に呑み込まれ、またアトランティス島も同じようにて海中に没して姿を消してしまったのであった」と。
 「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法 障壁となった泥土の謎
「(広大な大陸が沈んだから)そのためにいまもあの外洋は、渡航もできず探険もできないものになってしまっている。というのは島が陥没してできた泥土、海面のごく間近なところまで、航海の妨げになっているからだ」
泥土が、その先の海への航海を阻んでいるという仮説は、おそらくプラトンの記述が最初らしい。
これ以降には、例えばアリストテレスが「ヘラクレスの柱の辺りは、泥土のため水深が浅い」というように書いてたりするようだが、プラトンの世界観において、具体的にはそれがなぜ航海を難しくしていたのかはよくわからない部分。
直接的に物理的障壁となっていたのか。あるいは海底の大量の泥が何らかの効果を海面に起こしているのか。
もちろんこの有名な対話篇は単なるプロパガンダの(つまりギリシア賛美の)書ではない。それはプラトンの哲学の集大成ともされている。実際、彼が理解し、想像していたのだろう、この宇宙全体の世界観の話がそこに確かにある。
ティマイオス、クリティアス、そして(おそらく書かれる予定であった)ヘルモクラテスの三部作のタイトルは、それぞれがソクラテスに、彼らそれぞれの知っている世界の知識を語るという形式。
その順番にもしっかり意味があるようである。
「こうしよう。まずティマイオスが、この人はわれわれの中で一番よく天文学に通じ、万有の本性を知ることをこそ仕事とする人だから、 最初にこの人に、宇宙の生成から始め、人間(あるいは自然)のなりたちで話を終えてもらう。そしてその次にはわたし(クリティアス)が、ティマイオスの話で出生させた人間の話を……」
ティマイオス。宇宙創成の物語と、自然の原理
何かを造る時には必ずモデルが必要となる
そうしてまず、世界(宇宙)がいかにして発生したのかが語られる。
「……生成するものはすべて、何か原因となるものが必要。どんなものでも、原因となるものなしに生成することは不可能。また何を製作するにしろ、製作者が、常に同一を保つものに注目し、その種のものをモデルとし、当の製作物の形や性質を仕上げる場合、そのようにして作り上げられるものはすべて、必然的に立派なものとなるだろう。しかし製作者が新たに生成したものをモデルにした場合、製作物は立派なものにはならないはず」
古きものこそ良きものである、というようなギリシア哲学(だけでもなく、とにかく数多くの古い哲学)に普遍的に見られる信仰が、ここでも見られる。
しかしそれ以上に、ここでは”劣化”の概念がはっきりしているとも思う。
この世界がどのように生成されたにしろ、その時点で世界に存在している(普遍的な)要素が最も良きものであって、何か新しいものを造る場合、その良きものをモデルにするのがいい。
だがそうして新たに造られたものを、さらにモデルにして造る場合は、あまり良くないものになる。というのは、何かを造る場合にはモデルが必要(つまり完成させるものを製作者が理解している必要がある(?)。少なくとも、 その構造の各要素については知っていないとダメなのでなかろうか)であるが、そうして制作の連鎖を続けていくたびに、つまり最も良きものである古きモデルから制作の基盤が離れていく度に、完成するものはあまり良くないものになってしまう。
この宇宙のモデルは、永遠なるものか
「……第一に、およそどんなものについても最初に考えなくてはならないとされていることを考察する必要があるでしょう。つまり宇宙は、生成の出発点というものがなくて、常にあったものなのか、それともある出発点から始まって、生成したものなのか」
つまり無限か有限か。
 「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法
「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法 しかし有限であるということは、つまりこの宇宙自体も(するとおそらく我々が認識可能なすべては)創られた、あるいは発生した何か、ということも同じであろう。
プラトンは、まずそれら(この宇宙のすべて)は造られた生成物と考えていたようである。
わかりにくい部分でもあるが、プラトンはどうも、世界に存在する何(どの要素)を見てみても、明らかに(造られた)生成物、つまり何かをモデルにしてる何かであるのだから、なればこそ、認識可能なすべては生成物のはず。と考えていたようである。
さらには、すべて、何かモデルが必要な生成物であるのだから、より高次元の、我々が認識できない創造主(何もかも造られた生成物であるこの宇宙の万物の、造り手)が存在するはず、とも。
ただしそれは(すなわち万物の造り手、いわゆるデミウルゴス(dēmiourgos)自体がいかなる存在なのかについては)、理解しようがないような領域であるから、さすがに考察対象外としているが。
「……生成したものは、何か原因となるものによって生成したのでなければならないとわれわれは主張してきた。しかし、この万有の製作者が、実際どんな存在なのか見出すことは困難だし、仮にどうにか理解したとしても、他の者たちにまでその理解を共有できるよう説明するなんて不可能だろう」
ではわれわれが認識することのできる最も基本的な領域、つまりこの宇宙という基盤。それは根本的にどのくらいのレベルの創作物であるのか。つまりは、すでにこれが最も良いもののコピーの連鎖によって、あまり良くないものとなっているものなのか。それともかなり良きものなのか。
そういう疑問も発せられる。
「つまり宇宙の構築者は、永遠なるもの(真に良き第一原理?)に倣ったのか、それとも別の生成したものに倣ったか」
しかし答は、またあっさりと出される。
つまりは「この宇宙が立派なものなら、製作者はすぐれた善きもので、その製作者が永遠のものに注目したのは明らかだ。しかし宇宙が劣悪なものなら、製作者は悪しきもので、すでに生成したものに注目したことになる。ということは、製作者が永遠のもの(それすなわち最も良きもの)に注目したということは、誰が見てもはっきりしているわけだから、宇宙は生成物として最も立派なもの、製作者も最善の存在なのだろう」ということらしい。
妙に前向きな印象もある。
永遠ではありえないものを永遠にするにはどうするか
プラトンは、宇宙が永遠であるということが、誰でも知ってる常識みたいに考えていたようである。それも古代ギリシャの哲学者にはよくあることだ。
ただそれより注目すべきは、モデルが必ず必要という、生成物の基本原理かもしれない。
「この宇宙が何らかのものの似像であることも、これまた大いに必然的なこと」
その宇宙のモデルこそ、つまりプラトンの哲学において代名詞とも言えそうな『イデア(idea)』なのであろうか(少なくともそう解釈されるのが普通であるが)。
イデアとは、時空間を超越した非物体的、絶対的な永遠の実在する何かで、つまりは認識可能な世界の(あるいは各種個物の)原型とされる。
 「ホログラフィック原理」わかりやすく奇妙な宇宙理論
「ホログラフィック原理」わかりやすく奇妙な宇宙理論 そして創造主は、自身の存在と同じような、とても良き作品(この世界)に満足していたが、善きものであるからか、 常に今よりももっといいものを造ろうと努力しようとしたらしい。
「……もっと(最も根本的で最善のものである)モデルに似たものに仕上げようと考えていた。そもそもモデルそのものは永遠なる存在……しかし永遠なる性質を、生成物に完全に付与することはできないだろう。創造主が創ろうとしていたのは、永遠を写す何か動くもの。似像と言えるようなものだろう」
それは一瞬では静止している永遠を写す、しかし常に機能することで、擬似的に永遠を実現(その似像をつくる)。それこそ、まさに「時間」と名づけられたものとか。
 「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去 なぜ宇宙はたったひとつか
とりあえず、宇宙万有の構築者は善きものと結論される。
「……構築者はすぐれた善きもので、善きものは嫉妬心なんてものとは無縁なので、それが創るすべてのものは、また良きもの。つまり構築者自身に似たもの」
宇宙にしっかり秩序があるのは、それが良きことであるから。
さらにプラトンは、理性なきもののほうが理性あるものよりすぐれて立派なものになることはないとも(前述もそうだが、それよりさらに決めつけ感が強い)。
理性は魂を離れては何ものにも宿れないから、善きものは、理性を魂に、魂を身体に結びつけることで、それらの良きものをこの世界に具象化した。
その具象化した魂を備え、理性を備えた生きものは、 この宇宙そのものというようにも。
ところで、明らかにここで語られているような宇宙はひとつでない可能性がある。宇宙は神の創作物だとして、創作物を1つしか創らなかったとする根拠などないだろう。
だがプラトンは、宇宙は無限個でも、多なるものでもないとする。「それは1つのものとして呼んで正しかった……およそ理性の対象となる生きものすべてを包括しているものが、一つでないことなどありえないはず」と。
この宇宙が2つ以上あるなら、それらを含むさらに大きな何かが存在するということになって、この宇宙はその”部分”ということになってしまう。だが、最も善きものは最も良き宇宙を創ったのだから、つまり部分でなく完全な存在(1つのみの宇宙)であるはず、というような理屈らしい。
 「グッドマンの世界制作の方法」認識されるいくつもの宇宙。記号が意味するもの
「グッドマンの世界制作の方法」認識されるいくつもの宇宙。記号が意味するもの また、プラトンが理解している善きもの(創造主。神)が、何もかもの理解を超越しているような存在でなかったことだけはほぼ間違いない。それには明らかに感情があるような描写もされる。
「……生まれて来たもの(宇宙)が生きて動くことは、生みの父には喜びでした」
四大元素と魂
プラトンは、明らかに幾何学に強い関心があった。その点に関しては弟子のアリストテレス以上だったかもしれない。
宇宙の説明、考察には、その形に関してのものもある。
宇宙が立体的なものなら「いつも2つの要素がこれらを結び合わせる。そういうわけで、善きものは、火と土の中間に水と空気を置いた……可視的で可触的な宇宙を結び合わせ、構築した」
もちろん、”火、土、水、空気”という四大元素は、古代ギリシア哲学に由来するか、少なくとも、そのような哲学が由来の1つである概念である。
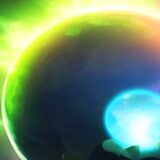 「古代ギリシアの物理学」万物の起源を探った哲学。遠い現象の原理
「古代ギリシアの物理学」万物の起源を探った哲学。遠い現象の原理  「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち ただ、四大元素論は必ずしも原子論と同じでもなく、その関係は、それを取り入れている理論によって変わる。
一般的には二つのパターンがあると思われる。
まず、それらを認識する人間も含めた理解できること全てが完全に(少なくともこの世界のものは)物質、ようするに全ては物質を構成する原子の組み合わせとする、唯物論的な発想のもとでのパターン。つまり原子自体に最初から備わっている個性、あるいはもっと根本的な原子の最初の組み合わせによって生じる最も基本的な分子としての四大元素。
もう1つのパターンは、世界を構成するいくらかの要素の1つとしての四大元素。ようするに、非生物と言える物質を構成している要素としてはあるが、生物の意識などのようなものは、別の神秘的要素(例えば魂とか)があるというような。
ちなみに生物の特殊性の原因の何か(要素)として、古代ギリシアでは、一般にプシュケー(これは霊魂と訳されることも普通)と呼ばれていたものがある。極端な原子論者などは、このプシュケーを否定することに多大な努力を払っていた向きがある。
また、場合によっては例えば愛とか、善とか悪とかいうような概念が、ある種の原子的に考えられていた節もある。
 「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの
「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの 太陽、月、惑星。大いなる天空の時計
天空の動きは時間と関連付けられている。
「そして、創造主が時間の生成時に考えた、その計算と意図から、太陽や月、他「惑星(彷徨する星)」という呼び名を持つ五つの星々が、時間の数を区分し、見張るものとして生じた」
星は生き物のようにも説明される。
造られたそれらは、循環する回転の運動のための領域に置かれた。それらは時間を数える、あるいは演出、あるいは定義する。
星々は、それぞれがそれぞれの役割を、その生物特有の絆(魂?)によって、しっかり理解しあい、それぞれの運動を開始した。
仮に、循環運動する天体の領域が宇宙の外縁部だとすると、プラトン的には、時間は永遠なるものでも、宇宙空間そのものは、それほど大きなものではなかったのだと考えられる。
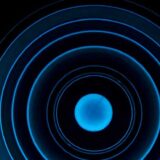 「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論
「天動説の宇宙」アナクシマンドロスの宇宙構造。プトレマイオスの理論 また、ここでは主要な運動体が8つともされているのだが、「太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星」と、地球が同類的に扱われてるのかは、ちょっと謎。
ただ、太陽はさすがにやや特別で、 天空の各運動体の進行の、わかりやすい物差しとしてあるために、地球を基準として二番目に当たる軌道で光るようである。
とにかく、「8つの循環運動の相対的な速さ(周期)が同時にその行程を完了して、大団円に到達する時、時間の完全数が完全年を満たす」という感じに、その時間を数える循環運動は、素晴らしく知的に計算されたものらしい。
 「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史  「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性 生物の大分類
「創造主は、作品の残りの部分を、モデルの本来あるがままに、その通りにつくり上げようとした。それなら、まさしく生物であるものは、どのような種類(相)が、どれだけあるか、理性が捉えられる限りの種類と数に対応するものを、この万有もまた含んでいるべきだと神は考えた」
この辺りをどのように解釈すべきか。
宇宙のモデル、(神自身かもしれない)最上のものに、 あらゆる生物が存在しているのか。あるいは、特別な理性(知性)が認識することのできる全要素のために、この世界に生物が存在するのか。
いずれにしろ、必然的に(生物の)大分類は4つらしい。
第一に、天の種族、この宇宙で天体という実体を有する神々。しかし実際的なことを考えるなら、それらも宇宙の中の部分であり、永遠なるものたちではあっても、おそらくプラトン哲学的には完全なるものではないので、擬似的な神々とか言った方がいいのかもしれない。
第二は、翼を持って、空中を飛翔する種族。
第三が、水生の種族。
第四が、陸生の種族。
創造主の神経系
普通には、特に興味深いのは、その分類よりも各種族の発生過程と思われる。
「神的種族(天体)は、輝やかしく美しくあるように、火で造られた。万有に似せて丸い。さらにこれを、至高のものの知的活動の場に置いた……この種族は全天一面に配分され、それが天のコスモス(飾り)となった……そうして神的で永遠なる生物として、同じ場所を一様に回転し、つねに自らの場に留まる恒星(惑星以外の全天体)が生まれた……神は大地(地球?)を、われわれの養い手として、万有を貫いて延びる軸のまわりを旋回し、夜と昼とを作り、見張るものとした。この大地こそ、この宇宙の内部に生じた限りの全神々(天体)の中で、最初のものであり、最年長者」
このような説明などは、興味深い部分が、わずかな間に数多くあると思う。
書かれてることを素直に解釈するなら、やはり地球も天体の1つであって、動きの総体の基準とはいえ、それ自体動いているような印象を受ける。そして、地球は最も古い星。
火の元素で造られているのは、輝く恒星ばかりでなく、おそらくこの地球含む惑星もである。
しかし何よりも注目すべきは、それらが知的な活動の場に置かれた、というような描写かもしれない。
この宇宙自体が、その創造主、つまり最も善きものをモデルにした、言わば最小のコピー数で創られた、やはりもっとも良きもの(あるいは第二の良きもの)であるとするなら、この宇宙は創造主と同じような構造の同じような存在(生物?)ということになるだろう。
永遠なるもの、そして理性が重要視されているところから考えると、知的活動の場とは、つまり生物では神経系のような、ようするに知性の原因の領域という意味かもしれない。とすると、天体群の、時を計るその動きの総体は、創造主、神の知性そのものということになるのでなかろうか。
万有引力とか重力とか呼ばれる概念を知らなかったであろうプラトンが、天空の星々の動きの理由を考えていて、最終的に行き着いた答が、こういう話だったのだろうか。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙 感覚能力は接続のためか
1つ、かなり確からしいことは、プラトンは(多分いくらかは疑いながらも)、単に天空を規則正しく循環運動する星々という神々のみならず、もっとはっきりと人格を有していて、生殖能力すら有しているような、そういう生物的な神話の神々の可能性も、ありえないようなものとは思っていなかった。
「……その他の神霊ですが、われわれには及びもつかないようなことですから、この場で深く語ることは避けましょう。ただ、以前にこのことを語った人々を信用するしかないでしょう。何しろかれらは自称、神々の子孫で、だからこそ自分たちの祖先のことを詳しく知っているらしいから」
ただ、かれら(神々の子孫を称する人たち)の話に、それらしい証明がまったくないことは、プラトンも認識しているようである。
プラトンはそもそもこの時、神々の系譜などは、あまり重要でないと考えていたかもしれない。
ただ擬似的な神々にせよ、実際の最初の神にせよ、そのような存在はおそらく実在するはず。我々に感覚のための能力(視覚や聴覚)を与えてくれたのは、そのような存在のはずだと理解していた節はある。
「仮にわれわれが星も太陽も見たことがなかったとしたら、話もされなかったろう……神がわれわれのために視覚を贈り給うたのだ。その目的は、われわれが、天にある理性の循環運動を観察し、この乱れなき循環運動を、同族ではあるが乱れた状態にあるわれわれの思考の回転運動のために役立てるように」
ここだと、まるで感覚能力は、劣化現象のために不完全な生物群(つまり我々)を修正するため、完璧なシステムとそれらを繋ぐための接続コードみたいである。
しかし自然(神の知性たる天空の知識)を学ぶことが、正しき知性に近づくための方法とするなら、ここにもやはり、良き理性こそ良きもの、というような思想が見える。
 「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか
「視覚システム」脳の機能が生成する仕組みの謎。意識はどの段階なのか 聴覚についても、「……音声を聞かせるあらゆる分野のものに、『諧調』のため与えられている。この諧調(ハルモニア)というのも、われわれの内の魂の循環運動と同族の運動を持っているもの」というように、やはり劣化物と良きものどもを繋ぐための(関連付けさせるための)能力のように説明される。
原初の状態は不毛であったか、混沌であったか
音と振動との関係はどのように考えていたろうか。
四大元素の機能原理の説明は、特に幾何学との関連が深い感じだが、振動する状態というような考え方も少し示唆されている。
「……4つの種類のものがその容器によりゆすぶられていたが、容器そのものは、ちょうど振動を与える道具のように動き、相互に最も似ていないものをお互いから最も大きく引き離し、また最もよく似ているもの同士を最大限に同じところに集まるように押しやっていた」
そのような、同族の物体群ばかりがひとかたまりに固まっているような宇宙は、原初の状態かのように語られる。
ここでの”容器”というものを、そのまま解釈するのは奇妙なようにも思う。それはむしろ、性質というように考えるべきでなかろうか。
つまりここでは4種類のもの、つまり四大元素それぞれが有する固有の振動が、別のそれぞれを遠ざけながらも、同族は近づけあう、というような。仮に、それが文字通りの容器なのであっても、考え方や結果に関してはそういう見方で正しいと思う。
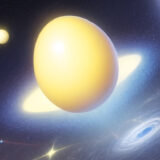 「ドゴン神話」創造神アンマ、世界の卵、ノンモと祖先たちの箱舟
「ドゴン神話」創造神アンマ、世界の卵、ノンモと祖先たちの箱舟 「それらのもの(四大元素の各種)は、それぞれ違った場所を占めていた。宇宙の生まれる前には、これらすべてのものはまだ比率も尺度もない状態にあった。あるいは万有の秩序づけが試みられた時、火、水、土、空気は、すでにそれ自身の類いの痕跡を持ってはいたろうが、しかし何ものたりとも、神不在の場合にはそんな(不毛な)状態だけだったろう」
この辺りは、神が文字通りの創造主でない可能性も思わせる。最初に混沌があって、そこから世界が発生したというような、神話の影響もいくらかあったかもしれない。
ただ、物質の素材群が存在していて、それだけというような世界で、それらの素材に秩序を与えることで創造がなされたというような物語。
最も基本的な形としての直角三角形
やはりプラトンの四大元素、むしろ物質世界に関する説明で最も重要なことは、それをあたかも、数学的な発想の上で、世界に必要な要素として定義付けたかのような、つまりは各元素の形についての話であろう。
まず、火、土、水、空気の四元素がそれら自体、すでに物体であることは明白なことが出発点となる(ようするに、物質を要素に分解して、そのまま要素をさらに要素に分解というようなことを繰り返して、最小の要素に行き着いた場合、普通に考えるなら、その手順の中に神秘的な影響とかがない場合、その最小要素も物質と定義して問題ない。というような理屈と思う)。
そして「物体であるならば奥行きを持っていて。奥行きは面を取り囲んでいるというのが絶対。さらに面のうちでも平面は、三角形を要素として成り立っていると考えれる」
ようするに、物体の外縁を線でなぞるとしたら、まずその線が0の長さであることはありえない。量がゼロである物体などありえない。というような考え方がここにあるのであろう。
さらには平面というのも、それを作ろうとする時、直線で結ぶことのできる点は最低限3つは必要となるのだから、つまり3つの点を線で結んだ三角形という形が、最も基本的な平面(平面の最小構成要素)。そういう意味で、ここでは「平面が三角形からなる」と結論しているのだと思われる。
次に、どのような三角形も、直角三角形の組み合わせとして考えられるとする。
ちなみにプラトンは、直角でない2つの角が直角を二等分したもの(つまり直角二等辺三角形)と、それ以外のものとは違う種類、要は直角三角形自体が2種類あるとしている。
物質が立体物であるという自明な事実から、よく考察した結果だったのだと思う。
つまりプラトンは、おそらく最も基本的な形とは直角三角形であり、そしてそれこそ立体である物質の、最も基本的な要素だと考えた。
ただしそれは、我々の理性(知性)が理解できる限りの領域においてのことであり、あくまで仮定。
ただしもちろん、さらに基本的な要素が直角三角形というものを存在させるのだとしても、それはもう普通には理解することができない(つまり神の)領域なのだろう、というように推測してもいる。
しかし四大元素が直角三角形というわけではなく、それらは神が直角三角形を利用して組み立てた、要はそれらの組み合わせからあらゆる物質をさらに生じさせるような、素晴らしき要素物質の形を与えられた立体(物質元素)とした。
もしプラトンが、かなり純粋な意味での原子論者だったとしたら、原子の形は”直角三角形”だったろう。それも”直角二等辺三角形”のような、特定スケールにおいて(つまり)形体パターンが唯一無二と思われる直角三角形、と書いたかもしれない。
普通に考えるなら、明確に4つに分けられるような基本構成要素としての元素に、たくさんの形のパターンがあるのは奇妙である。おそらく四大とかじゃなく、ただ原子というのがあるだけ、という場合以上に(ただ原子があるという場合は、むしろその段階ですでに無数のパターンがあるというようにも考えやすいだろう。はっきり基本要素は四つと定義されているよりは)。
プラトンが四大元素の形として(まさしく直角二等辺三角形のように)あるスケールでの形体パターンが唯一無二の、特別な形を選ぼうとしたのは、わりと納得しやすい流れと思う。
二つの直角三角形と、四つの正多面体
プラトンは、直角三角形の無数の形体パターンから、基礎的なものとして適切な形(つまり最も良い形)を選ぶのにかなり悩んだ感じである。それでも、確信をもってとはいかないかもしれないが、あくまで仮定として、 唯一無二のパターンである直角二等辺三角形と、正三角形の半分の(つまり30°、60°、90°の)直角三角形を選んでいる。
それら2種の形を選んだ理由はちゃんとあるらしい。しかし、「話が長くなる」とかで書いていないのだが、「もっとふさわしい形があることを証明する人も今後現れるかもしれないが」というように、妙に念を押していることから、実はあまり自信のあることでなかったのかもしれない。
とにかく、元素の立体の素材として、二種の三角形が選ばれた。そしてプラトンは、元素と元素が合成したり、あるいは合成物から元素が離脱したりする時、(その相互作用する各元素の種類にも関わらず)実際に起きている現象は、より基本的な要素である三角形の交換や移動だと想定した。
しかしもちろん2種あるために、場合によっては普通にそのままの交換ができない場合もある。
そして、端的に言えばプラトンは、『正多面体』、すなわち全ての面が同一の正多角形で構成され、すべての頂点において接する面の数が等しい多面体(平面で囲まれた立体)こそが、元素の形としてふさわしいものと考えた(そのため正多面体は『プラトン立体』と呼ばれることもある)。
彼が幾何学にも明るかったなら、もちろん正多面体のパターンが5つ(正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体)しかないことを自分でも証明できたろう。ただし新しい元素の説明の前に、そうした証明を行ったりはしていない。
(簡単には、同一の形だけを組み合わせた正多面体、すなわち正多面体を作れる正多角形がまず正三角、正四角、正五角形の3つのみ。そして適当な1つの頂点に集まっている面の数が、正三角形は3か4か5、正四角形と五角形は3つの場合でないと正多面体を作れない。頂点に集まる正三角形が3つの場合の正多面体が”正四面体”。正四角形3つの場合が”正六面体”。正五角形3つの場合が”正十二面体”。そして正三角形4つの場合が正八面体で、5つの場合が正二十面体)
プラトンは、答から逆に考えて、基本要素としての直角三角形2種を見いだしたのでないかと思いたくもなる。 プラトンは正十二面体の形はさらに特殊なものとして、他の4つの正多面体を、四大元素それぞれの形に当てた。すなわちそれらを構成するのに必要だった面の形は(正四面体、正八面体、正二十面体のための)正三角形と(正六面体のための)正四角形。
選ばれた2種の三角形の1つは、正三角形を半分。そしてもう1つの直角二等辺三角形は正方形(正四角形)の半分である。つまりそれらは、必要な正多面体を作るための要素となりうる直角三角形。
ちなみにプラトンは元素の正二十面体の要素を120としている。
そもそも正三角形の半分の直角三角形は、スケールが小さいだけで同じ形の(すなわち”相似”の)三角形3つに分解できるという特殊な性質を有する(一般的にどの三角形も、相似の三角形4つには分解できるとされる)。すなわち正三角形は、半分の直角三角形と相似な直角三角形6つに分割可能。その6等分されたスケールの直角三角形が、多面体の面となる正三角形を構成する直角三角形とプラトンは考えた。
つまり、直角三角形6×20で”120″の構成要素というわけである。
もちろん、この作り方から、元素の正四面体は”24″(6×4)、正八面体は”48″(6×8)の構成要素からなると思われる。
また正六面体を作る正方形に関してだが、この場合、最低限必要な直角二等辺三角形はやはり2つであるのに、プラトンは4つを想定している(すなわち、元素の正六面体の要素数は4×6で”24″)
なぜ、必要最低限の数にしなかったのだろう?
各元素の形。動きやすいかどうか
とにかくプラトンは、 最も基本的な形、2種の直角三角形、すなわち角が45・45・90°の三角形(以降type1三角形)、または30・60・90°の三角形(以降type2三角形)を組み合わせた4種の正多面体が、4種の物質元素の形と定義した。
では具体的に、火、水、土、空気の 4種の元素それぞれは、どの正多面体であるのか。
まず、唯一type1を構成要素とした立方体(正六面体)は、その形状から最も安定しているとして、動かしにくく可塑性に富んでいるという土元素に与えている。
そもそも構成要素のtype1三角形からして、3つの辺の数が全て異なっているtype2より 秩序正しくつまり安定しているらしい。
物質の動かしやすさという基準は、プラトンにとって、そのような形状分類を決定する大きなヒントになっていたようだ。
なぜそうなのかということはともかく、彼はtype2三角形を組み合わせた正多面体のでは、水が最も動かしにくく、火が最も動かしやすい元素と考え、つまり水は一番動かしにくい形、火が一番動かしやすい形と推測した。そして必然的に残る、動かしやすさが中間にあたる形が、空気の形。
動かしやすさは単体の重さにも関係しているのか「大きい形が水で、小さい形が火と言ってもよい」とも。
つまり、水は面の数が最も多い正二十面体。火は面の数が最も少ない正四面体。空気はその中間である正八面体。
すなわち四種の物質元素の形は、2種の直角三角形を構成要素とした4種の正多面体。土=正六面体、火=正四面体、空気=正八面体、水=正二十面体。
プラトンの世界観においては、4種の元素の形が、単に異なっているというだけでなく、角の鋭さの違いも重要視されている。
最も安定的な立方体は平らな平面。一方で角が一番鋭い正四面体、つまり火は、他の元素とぶつかる時に強烈な影響を与えやすい。
そこで、例えば火とぶつかった他の元素が分解され、その基本要素、つまり直角三角形がまた混ざり合ったりする。それが複数の元素が入り混じる中でのことなら、マクロな視点では、集合体の要素の分布図の変化、つまり実質的に物質の変化の現象として見出せたりする。
特に基本的な要素として、type2三角形が共通している火と水と空気は、組み合わせの変化のために、元素自体が変化することもありえる。一方でtype1三角形は火と水と空気の基本素材とはならないことから予想できるとおり、土以外の元素には決してならないという。
「次のようことがありそうです。火の鋭さなどのため土が分解されたとして……土の部分(直角三角形の素材)は、再び互いに、元素の構造に必要な数一緒になる(つまり土元素を再構築する)まで、移動を続ける……水や空気が、火によって分解されたとしたら、例えば水だった(120の)直角三角形(type2三角形)の内、(24の)ある部分が結合して火元素(正四面体)1個を、(48×2の)残り部分が別々に結合し空気元素2個を生じさせたりもできるでしょう」
ようするに”24+48+48 = 120″である。
この基本要素の直角三角形は、現代的な概念としては、むしろ質量(エネルギー)に近いのかもしれない。そう解釈すれば、ここに現代的な”質量保存法則(エネルギー保存法則)”に近い考え方を見出すこともできると思う。
もちろんプラトンは、さらなる基本構成要素があるかもしれない、と書いてる訳だが、少なくとも理解できる最小要素は、この直角三角形としている。
それはつまりデジタル的な要素(という点も現代の考え方に近い)。さらに注目すべきは、物質の四元素の内の1つしか構成できないtype1と、その1つ以外を構成できるtype2の二種類があることだろうか。
もし、この世界観において、基本要素の直角三角形を質量のようなものとして解釈するなら、(まるで現在のSFでありそうなアイデアだ)質量に2つのタイプがあることになる。そういうアイデアとして、最も古いものともいえるかもしれない。
“超ヒモ理論”の考察などに持ち出されることがある、異なる2種の”長さ”の概念などを思い出す向きもあるだろうか(もちろん、プラトンが超ヒモ理論なんてものを知ってたはずがない。そういうことではなく、ただ彼の世界観もまた、そのような普通には考えにくいような種類を想定する必要があり、そしてそうした奇妙な種類を必要とする最初の世界観が、彼のものだったのかもしれない。という話)
 エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」 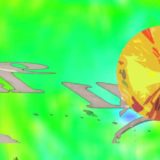 「超ひも理論、超弦理論」11次元宇宙の謎。実証実験はなぜ難しいか。
「超ひも理論、超弦理論」11次元宇宙の謎。実証実験はなぜ難しいか。 ちなみに、四元素の要素変換式は以下のようになる(火=F、空気=A、水=W、土=Eとする。また()内の計算の数は面の数だが、直角三角形の数を使っても、数字が大きくなるだけで結果は同じ。[]内の数字はtype1三角形で構成される面の数)
・大きい粒子を解体し、小さい粒子に変換
1W→1F+2A (20=4+2×8)
1A→2F(8=2×4)
・小さい粒子を結合し、大きい粒子に変換
2F→1A(2×4=8)
2A+1/2A→1W(2×8+1/2×8=20)
・土も交えて変換
1W+E→1F+2A+E (20+[6]=4+2×8+[6])
この保存法則と、宇宙を創造した神はいても宇宙を造るのに必要だった素材はそれ以前からすでにあったことを思わせるいくらかの記述などから考えると、完全なゼロ(無)から何かが生まれることはないはず、という思想が、やはりプラトンにはあったのだろう。
 「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見
「ゼロとは何か」位取りの記号、インド人の発見 また、物質の様々な変化、例えば水が凍ったり、気化したり、濁ったりみたいな変化。そうしたものは、三角形要素の不足や過剰、不均等のために生じるとか。
 「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か コスモスか、描くものか、元素か。最後の正多面体の謎
元素の形として 使われなかった もうひとつの正多面体、すなわち正五角形で構成されている正十二面体は、普通はコスモス、つまりこの宇宙自体の形として理解される。だがそうだとして、いくつか奇妙な部分がある。
四大元素の形を説明している途中の部分。
「……第五の構成体については、神はこれを、万有のため、そこにいろいろの絵を描くのに用いた」
これは、プラトン哲学の研究所の間でも、長きにわたって謎とされてきた表現らしい。描くのに、というのはつまり何を意味しているのか。
「ところで宇宙は無限のものか、それとも有限のものかを問題にするのに、これまでのことすべてを勘定に入れるとしたら……しかし、いったい、宇宙は本当に、もともと1つのものと言われるのがふさわしいか、それとも5つのものと言われるのがふさわしいのか、この点に立ち止まって問題を提起するほうが、むしろ当を得ているのでないか」
突然の、無限か有限かという話で、1か5の宇宙か、と唐突に出されたこの疑問は、 これが元素の形としてありえるのが正多面体であって、その正多面体は5つある、ということを解説した前の(あるいは正多面体の数と、具体的に5つの形の内の4つの形がどの元素であるか、という説明の間の)文であるということを考慮してもなかなかに唐突感がある。
一応ローマ時代くらいから、この辺りの記述は、宇宙の第五元素 “エーテル”、すなわち天空の元素の事を語っているのだという説があるらしいが、普通に何の根拠もない。
生物である植物。人間が食べることのできる植物
ティマイオスの話は、予定通り、人間を含めたあらゆる生物の誕生の経緯(創造の過程の詳細?)をクライマックスとする。
「死すべき定めの生物(人間)の部分となり肢体となるもののすべてが、結び合わさって一体化されると、その生物にとっては、生命を火と空気の中で保っていくのが必然となった。しかしそうなると、それは火や空気のために溶かされ、衰弱していったから、神々は、その生物を救うための策を講じた。すなわち神々は、人間の性と同族の性のものを、別の形態、他の感覚機能と混ぜて、別の生きものになるようにし、これを植えつけた。この生物が実は、現在のわれわれに馴染み深い、農耕により、栽培された木とか、いろいろの植物とか種子とかである」
人間の糧にならない野生の植物については、もっと古くから存在しているものとも。
古い野生の植物に対し、人間から造った”栽培植物”というような区別を想定するまでの流れも想像しやすいだろう。例えば、人間がそれを食して自らの栄養とすることができるのは、それが人間と近しい素材でできているから、つまり人間が自身の破損の修復に利用可能な素材で造られているから、というような発想があったのかもしれない。
ところで、 植物を「生物」扱いすることについて、「じっさい、およそ生命に与っているものならどんなものでも、生物と呼ばれる資格があるはずだから」としている。
植物は生物か否か、というような議論が、この頃にも普通にあったのだろう(植物が当然、生物として認識されるのが常識となったのは、人の歴史全体を見た時、そんなに昔の話ではない)
プラトンは、おそらく生物であるのだからという理由で、植物の有する魂(あるいは生命力)についても少し説明を入れている。
栽培植物の備える魂は、中でも第三の種類のもので「つまり横隔膜と臍の間の座を占めると言われる、あの種類のものなのだ。この種の魂は、推理や理性などとは関わりなく、ただ快楽や苦の感覚と欲望だけ与っている」とのこと。
輪廻転生を思わせる生物発生
人間も含めた動物の誕生に関しては、さらに神秘的な感じがある。プラトンはそれを本気の話として語っていたのか、それとも何かの比喩であるのかが長く議論されてきたほどだ。
考え方に変化があったのか、 同じく神秘的とされがちな、『饗宴』で書かれていた人間の誕生の話とも違っている。
「男に生まれた者の中でも、臆病な者、生涯を不正に送った者たちは、ある言論に従えば、第二の誕生で「女」に生まれ変ったことになる。神々が繋がりあうこと、あの性的な欲望を考案したのは、ちょうどこの時になってのことだろう。つまり神々はその時に、魂を備えた生きものの1つを男の中に、他の1つを女の中に組み立てた」
どうも、男が先にいて(それが原型だった?)、後から女が生じたような感じだが、同じように、動物たちもおそらく人間の男から生じているとされる。
鳥類は、罪はないものの、あまり深くは考えられないような、言わば根が単純な男たち、目で見られるものしか信じない程度の人々
が、毛髪の代りに羽を生やすように変えられた存在。
陸上の獣類は、もはや自らの頭の軌道(理性)を用いなくなってしまって、胸の辺りの(第三の?)魂由来の本能のままに生きているだけの男たちから生まれた。
わりと興味深いのは「彼らの頭頂部は、その各々の回転運動がろくに機能していないために、圧を受けるだけで、そのひしがれ方に従い、様々な形になった」というような説だろうか。
また、足の数などは、その生物(元となった人?)の愚かさの程度に関係しているとか。そしてもちろん、足の数が少ないものが偉いようである。一応愚かなものほど、それに比例して偉大なる天空から離れるように、つまり大地に縛り付けられてしまうから、足の数が多いのがダメというような説明もある。ちなみに(陸の動物で)最も愚かなものは、もはや足の必要がなくなった、無足の、地面を這うもの(ヘビだろう)らしい。
これ以前にはともかくとして、これ以降にはあまりにも長く一般的であり続いた生物の序列であるから、簡単に予想つく向きもあるかもしれないが、やはり水棲の生物が最も劣った動物とされる。
つまりそれらは、知性や学とこの上なく無縁な人々から生じた。
「変形させ、造り変える技術者のような神々は、無知な者たちの、不純な状態の魂から、かれらはもはや純粋な呼吸に価しないと考え、濁った水の深みへと突き落とした」
(陸の領域で)呼吸する、ということに何か特別な価値があるかのような発想も、かなり後世の生物学でも結構見られるものだ。ただしなぜ呼吸するものが偉くあるのかは、普通には謎なことが多い。
ラマルク(Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck。1744~1829)などは、それ(呼吸)は複雑なシステムを必要とすることだから、つまりより複雑な生物(生物として優れている存在)の1つの指標になる、というような考え方を出したりしている。
しかし「すべての生物が、あの時も、現在も、理性と無知を失うか得るかにより、その場所を変え、互いに変化し合っている」とも。
単純に輪廻転生の考え方から出てくる表現なのであろうか。おそらくそうとは思われるが。
クリティアス。未完と幻の続編
この宇宙がいかにして発生したのか。万物がいかにして機能しているのか。生物がどのように生まれたのか。そのような、時間的にも空間的にもこの上なく壮大と言えるような話を、まずティマイオスが終えてから。
「……天界や神々に縁のある話などは、ほんの少しのそれらでも聞かされれば、それでもう我々は満足してしまう。だが死すべきものでも、人間たちの話は別で、詳しく吟味したくもなる……しかしソクラテス、わかってほしい、これからの話については、どうか寛大な心を持って聞いてもらいたい……」などと前置きするクリティアスに、ソクラテスは以下のように返す。
「もちろんだ、クリティアス。しかし何をためらうことがあろう? 大きな気持ちでお話をうかがうということについては同じだ。それにまた、わたしどもは第三の語り手ヘルモクラテスの話も、同じように寛大な気持で聞く必要があるだろう。遠からずかれに話の番がまわってきた時、彼もあなたと同じ申し出をするだろうよ」
しかし現代の我々は、 その第三の語り手ヘルモクラテスが語った、あるいは語るはずだった物語については適当に推測するしかない。 クリティアスの話に関しても途中まで、むしろ序盤のテキストしか残っていないと思われる。
ただ、クリティアスの話は、人間の話と言うか、人間の築いた文明の歴史の話というような感じであるので、ヘルモクラテスの話は、現代の人間の話とかだったのかもしれない。
アトランティスの歴史の話の途中
しかし神話と関連しているような記述が一切なくなるわけではもちろんない。
例えば国土を分配したのは神々で、例のアトランティス島は、ポセイドンが受け取りたまった土地だという。そして彼(つまりアトランティスの神)は、人間の女に生ませた子どもたちを、この島の、実り豊かな平野に住まわせたとか。
しかし、最終的に世界を征服しようとして、ギリシアに負けるまで、しっかり詳細に語られるはずだったのかもしれないが、残念ながら現存するテキストは、そのアトランティス島の国家の歴史の話の途中で終わっている。
その始まりは、神と人間の様々な都合によって、大地の形とか、特別の島とかができたり、あるいはその後に、どのような者たちが王族であったかとか、そして王位継承の話など、歴史の本によく書かれているような、まさしく典型的な内容に続いていた。
ただ、それだけである。



