ガゴゼ。妖怪の始まり伝説
古くは、妖怪のことをガゴゼと呼ぶことがあった。
その昔、敏達天皇の頃(6世紀くらい)。
 「歴代天皇」実在する神から、偉大なる人へ
「歴代天皇」実在する神から、偉大なる人へ
一人の農夫が木の下で雨宿りをしていた。
すると突然、雷が落ちてきて、小童となった。
農夫は、妖魔の類に違いないと考えたのか、その小童を殺そうとした。
すると小童は、「許してくれれば、あなたの望みを叶えよう」と言った。
その農夫には子がなかったので、子供を願った。
それから、農夫の妻は男の子を産んだ。
生まれた男の子は、大層な力を持っていて、ある日、評判を聞きつけた朝廷に招かれ、次には、蘇我馬子が明日香に建てたという、元興寺の童子となった。
元興寺の鐘つき堂には、鐘を鳴らしにきた童子を殺す、霊鬼という化物が潜んでいたが、怪力の童子は、これを追い払ったという。
童子はその後は、僧として修行を積み、やがては、道場法師と称されるようになった。
妖怪の事を、ガゴゼと言うが、このガゴゼは、元興寺からきている言葉という説がある。
霊鬼は、逃げたというのが、また面白い。
もしこれが最初のガゴゼ(妖怪)なら、後の妖怪達は……。
雷獣。雷そのものなのか、雷を操るのか
ガゴゼの話で、雷と共に現れた小童の正体は、この雷獣という説もある。
北米のサンダーバードのように、雷となんらかの獣が関連付けられている伝説は多い。
 ロック鳥。ビッグバード。鳳凰。コンガマト「未確認動物としての巨鳥、怪鳥」
ロック鳥。ビッグバード。鳳凰。コンガマト「未確認動物としての巨鳥、怪鳥」
雷が電気であると気づかれるまでは、 それがとてつもなく不思議な現象であったのは間違いないだろう。
 「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち
「電気の発見の歴史」電磁気学を築いた人たち
しかし、雷獣は雷そのものなのか、それとも雷を操るのか。
どっちのつもりだったのであろうか。
土蜘蛛。もっとも恐ろしきイメージ
その名前の通り、土蜘蛛はクモの妖怪だが、かなり巨大で、恐ろしい存在だとされる。
 「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
「クモ」糸を出す仕組みと理由、8本足の捕食者の生物学
無限かと思えるようなほど大量の糸を吐き出し、本体もかなりの怪力を持つ。
さらに厄介な事に、その姿を自由自在に変えられる、という話まである。
古くは、朝廷に従わない敵対勢力の事を、土蜘蛛と呼んでいたようである。
もしかしたら、鬼との一種というイメージもあるかもしれない。
一本ダタラ。落ちぶれた、鍛冶の隻眼神か
一本足で一つ目という、異形の姿の妖怪。
古くは、人に似た獣のように考えられていたそうである。
一本足で一つ目の鬼とも、電柱のような体に、目と鼻をつけたような姿だともされる。
地域によっては、一本足の足跡のみを残す姿を見せない妖怪である。
人を襲うという話も多いが、なぜか郵便屋だけは襲わないという説がある。
ダタラとというのは、タタラ師(鍛冶師)からきている可能性が高いようである。
かつて鍛冶師は、仕事中に一生ものの傷を負う事も多かった。
一本だたらの出没場所には、鉱山跡が多いと指摘する人もある。
また、鍛冶の隻眼神、天目一箇神)、あるいはその堕落した姿という説もある。
ガラッパ。カッパの仲間か
見た目はカッパによく似た妖怪で、頭には皿があり、その手足はかなり細長いという。
 「河童」UMAとしてのカッパは実在の生物か、妖怪としての伝承。その正体
「河童」UMAとしてのカッパは実在の生物か、妖怪としての伝承。その正体
口からは、常によだれを垂らしていて生臭いともされる。
姿形だけでなく、名前までカッパに似ているので、単にカッパの地方訛りだという説もある。
ただしガラッパは、春は川に住むが、秋には山に住むと言われている。
山に住むガラッパは、訪れた人を迷わせたり、ゴミを放ったりと、いろいろな悪戯をするらしい。
また、山の中で自分の悪口を言った者に仕返しするとも言われる。
しかし、このガラッパと友達になれば、神通力で、魚がよく釣れるようにしてくれる、という話である
海坊主。船をひっくり返す
海に出現するという巨大な妖怪。
真っ黒けで、その巨大な目は光り、くちばしがある場合もある。
ただし目も口も鼻もなかったという話もある。
これは案外、後ろから見た姿、というだけではないだろうか。
海坊主が出現した場合、黙って、それを見ないようにすることがよいとされる。
もしもそれを見て、反応してしまうと、海坊主はたちまち船をひっくり返すのだという。
大きいばかりでもなく、昔は、海坊主は、名前通りの丸坊主の人型だったともされる。
その正体は、化けた魚とも考えられていた。
 「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
「魚類」進化合戦を勝ち抜いた脊椎動物の始祖様
あやかし。シーサーペントのような妖怪
いくち、とも呼ばれる巨大うなぎの怪物。
地方によっては、あやかしとはコバンザメの事のようだが、サメとは似ても似つかない。
とにかくその体は長く、何千メートルもあるという話もある。
一方で、長さのわりには、太さは控えめだとされる。
あやかしは、船を襲うという話もあるが、船を、その長い体で、長い時間かけて乗り越える事もあり、そうした場合、船はあやかしの体からたれてきた油で一杯になってしまう。
つまりシーサーペントのような怪物だが、その正体は、海で死んだ人の魂が、仲間を恨んで現れたものとも言われる。
 『シーサーペント』目撃談。正体。大海蛇神話はいかに形成されたか
『シーサーペント』目撃談。正体。大海蛇神話はいかに形成されたか
塩や真水、灰をまく事で退散させられるという話もある。
おとろし。古い神様を守る妖怪
古びた屋敷や神社などに住みつくとされる、異形の妖怪。
神様を守る妖怪ともされ、人が忘れたような古くさい建物の中などに潜み、そこをのぞいてきたりする人があると、脅かしたりするのだという。
全体的な姿は、巨大な顔の鬼をイメージさせるような姿らしく、顔も体も赤いという話がある。
 「鬼」種類、伝説、史実。伝えられる、日本の闇に潜む何者か
「鬼」種類、伝説、史実。伝えられる、日本の闇に潜む何者か
悪戯する者などがいたら襲いかかって殺してしまう事もあるようである。
神聖な存在は、時に恐ろしい存在なのである。
神社にいる場合、鳥居の上に居着いていて、不信心な者が通った時に、どさりと落ちてくる、という話もある。
わいら。山奥に潜む謎の怪物
この、わいらは、詳細のはっきりしない妖怪だが、どうも牛のような姿であり、その前足には一本ずつの鋭い鉤爪があるのだという。
サイに似ているという話もある。
あるいは化けたガマガエルであるという説もある。
オスとメスがおり、オスは土色、メスは赤色。
山に生息し、山から出てこないともされる。
また、わいらが、モグラを食べていたのを見た、というような目撃談があるという。
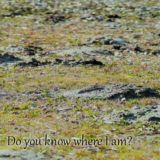 「モグラ」目を退化させて手に入れた謎だらけの生態
「モグラ」目を退化させて手に入れた謎だらけの生態
大入道。伊達政宗と戦った怪物
大岩が変身した巨大な妖怪とされている。
かつて仙台に現れたこの怪物の評判は、藩主であった伊達政宗の耳にも入ってきたという。
 「伊達政宗」独眼竜と呼ばれた戦国武将
「伊達政宗」独眼竜と呼ばれた戦国武将
政宗は、家来に現地を調査させる。
翌朝、家来達は、大入道の出現は真実であり、我々には手に負えないと弱音を吐いた。
政宗は自ら出向いて、この化物を見てやろうと、日没後に現場にやってきた。
すると、大入道は本当に現れ、政宗を睨みつけたが、政宗はひるまずに、白羽の矢を放ち、大入道の足元を射た。
そしたら大入道はたちまちに元の大岩となった。
大入道の足に刺さった白羽の矢は、行方不明となったと思われたが、岩の近くで発見された、大きなカワウソの脛に刺さっていた。
つまりこれが大入道の正体だったのである。
キジムナー。毛むくじゃらの、木の精
古びた木の精霊とも言われるキジムナーは、赤ん坊程度の大きさで、全身が毛に覆われている。
夜道を行く人から提灯を盗んだり、家畜を飛び跳ねさせるなどの悪戯を好み、魚やカニをよく食べるが、飽きっぽく、魚などは片目だけをくりぬいて食べて、後は放置するという。
しかし、うまくおだててやれば、その残りをもらえるともされる。
キジムナーは、火を出せるらしく、よく原因不明の火は、キジムナーの火とされていたようである。
ノウマ。ひとつ目の人食い
夜に一人で歩いている人を見つけては、姿を見せて、その人を食ってしまうのだという妖怪。
ひとつ目の妖怪であり、おそらく数多い、その類の妖怪の中で、最も恐ろしいと言えるような存在。
具体的な姿がよく伝わってないのは案外、実際にそれを見た人がいたからなのかもしれない。
それで、ひとつ目という特徴がしっかり伝わっているということは、 それに襲われて生き延びた人がいたということなのだろう。
大かむろ。巨大な顔
何か音がするなあ、と思って障子を開けてみたら、そこに現れている、巨大な顔の化け物。
大かむろは、タヌキが化けたものもとされているが、この巨大な顔が、文字通りの顔の部分だけというのならば、大かむろはタヌキが化けた妖かしの中でも、特に巨大な怪物と考えられる。
ただしこれは文字通り顔とされ、そしてタヌキの見せる幻覚とされている。
普通は害はなく、ただ人を驚かすだけなのも、いかにも、(タヌキでないにしても)悪戯ぽい。
空に現れるという、巨大な女の顔の妖怪、大首と同じ類のもののようである。
ただし、巨大で、これほどインパクトある妖怪にしては、伝承上の記録が少なく、いずれも創作されたものとする説が有力。
がしゃどくろ。超巨大髑髏
野垂れ死に、ちゃんと埋葬されなかった人々の恨みが集まることで、この巨大な妖怪は生まれるのだという。
基本的には、夜に出現し、どこからともなく、ガチガチ音をさせながら歩いてきて、見つけた人に襲いかかるのだとされる。
人を握りつぶすとか、食べてしまうとも言われる。
基本的には、第二次世界対戦以降に創作された妖怪だとされているが、確かに、いかにも戦争が生んだ妖怪という感じである。




