ビュフォンとは何者か
天才とは忍耐力。ルクレール一族の人生哲学
後にビュフォン伯爵として知られるようになる、ジョルジュ・ルイ・ルクレール(Georges Louis Leclerc, comtede Buffon)は、バンジャマン=フランソワ・ルクレールとアンヌ=クリスティーヌ・マルランの第一子として、一七〇七年九月七日、フランスはブルゴーニュ地方モンパールで生まれた。
ルクレール一族が、親戚のナドー家やドーパントン家とともに、モンバールに居住してきたのは、ジュルジュよりもいくらか前の世代の時らしい。
彼らは三家の間でばかり婚姻をおこない、助け合いながらも、時には遺産のために争いもした。彼らは長生きな傾向があり、また倹約家であったからか、けっこう財をなしたとされる。
ビュフォンは語った「天才とは、より大きな忍耐力にほかならない」。彼の人生哲学は、おそらく家族から受け継いだ、伝統的なもの。
ビュフォンの父は、ブルゴーニュ高等法院の弁護士。塩税局の国王代訴人(法律関係の専門職)として、評判の悪かった塩税の徴収をおこなった。
父との関係は、ビュフォンにとってあまり好ましいものではなかったらしい。
一方で母親は、ビュフォンの最初の家庭教師役を果たしたと言われている。後にビュフォンは、自分に知的、精神的な長所を与えてくれたのは母親である、とまで語ったという。
ビュフォンは、イエズス会士の運営するゴドラン・コレージュで学んだが、あまり優秀な生徒ではなかったそうである。「知的な作業よりも運動を好んでいた」というのが、記録に残っている級友たちの印象。
しかし彼が、強い知的好奇心を持っていたことは間違いないだろう。彼は数学に熱中し、授業と関係ないところでも、微積分法の研究書などを読んだりしていたらしいから。
微積分法は、彼の時代にはまだ、かなり最新の数学だった。
ビュフォンは、少なくとも知識人としてはとても立派に育ってくれたろうが、イエズス会士の学校の生徒としては、かなり微妙な側面があった。つまり彼は、宗教にはあまり関心が持てないようだった。
ビュフォンはキリスト教を否定はしなかったが、明らかにその教義をたいして信じていなかった。ただ彼は、(時代を考えると、当然であり、また賢い選択であろう)一応は社会の中で、キリスト教に気を使ってはいたようである。
異端の科学者として
ビュフォンは、(つまり同僚、科学者ではない)一般読者にも、教養ある者は結構いるはず、と考えるタイプだった。
ビュフォンは、ただ自らの思想を広めたいというだけでなく、多くの読者を、楽しませるより、むしろ考えさせたがっていた節があるという。大衆のくだらない好みや軽薄さを知っていようとも、それでもそんな彼らに迎合するでなく、彼らにも推論する能力がちゃんとあるはずと。
もちろん一般読者にこそ、科学アカデミーの権威ある学者たちが与えてくれないような栄光を期待していた部分もあったかもしれない。時にパラダイムシフト的な(つまりそれまでの常識を覆すような)考え方は、専門家よりも、一般の人に先に受けいれられることは珍しくない。
実際、ビュフォンの提唱した自然の世界観と、それに関連した哲学思想は、おそらく当時の時代にあっては、かなり先鋭的なものだったと思われる。
そして彼は、自然科学、生物学史において、非常に重要な資料の1つであろう、長い『博物誌(L’Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi。王室博物館の解説による博物誌、総論および各論)』を書いた。今に伝わる彼の世界観、哲学などは、ほとんど全てこの書物から読み取れる。
分類をどう考えるべきか
創造主の手は誰のためか
「……存在しうるものはすべて存在しているように思われる。創造主の手は、ある限られた数の種に存在を与えるためだけに開かれていたなんて思えないが……」というのも、ビュフォンが持ち出した1つの疑問。
ビュフォンは、神の存在をはっきり否定することに関してはかなり慎重なようだった。しかし結局のところ、ほとんど確実に、例えば神が存在しなくてもいい自然世界の可能性を普通に考えもした。
ビュフォンが理解していた、自然世界の驚くべき多様性と、それら全てを含んでいる場合の世界の複雑構造。つまり「存在しうるものはすべて存在している」世界観。それは、人間の幸福や、善意を願う偉大な創造主が作ったものとしては、あまりにも混乱していてバカげているように感じていたのかもしれない。
科学の方法、自然世界の現実
またビュフォンは、リンネの分類法を強く批判した。
どうも、実際に自然を観察してみた時、「どこかにある種とある種の明確な境界線があるわけではない」というのが、ビュフォンの哲学の基礎的な思想の1つだったようである。
ビュフォンは、リンネの分類には、「奇妙で根拠のない寄せ集めにすぎない」ものがいくつもあり、そもそも分類などできないものを無理やり分類しようとしているための結果、というようにそれを嫌ったとされる。
いろいろな特徴を共有する様々な分類を定義したいというのは、そもそも人間精神らしい要求であるが、別に自然が、その要求に応えるような構造をしているわけではないと。
特にビュフォンの思想に関して、現代的な観点から興味深いと思われることの1つは、彼の方法論の否定であろう。
「(分類法のような)こうした研究方法は学問とは言えず、せいぜいのところ約束事、恣意的な表現方法、相互理解の手段にすぎない……それらの方法は、意思の疎通をはかるために取り決めた記号としてのみ用いるべきだ」ただし「記号は事物の性質についてわれわれに何も教えてくれない」
「諸科学がきちんと研究されているように思われる今世紀においてさえ、哲学が、おそらくほかのどの時代よりもないがしろにされているのを認めるのは容易だ。俗に科学技術と呼ばれるものが高い地位を得て、算術と幾何学の方法、植物学と博物学の方法、公式とか辞書ばかりが人々の関心事となった……しかし、それらは技術にすぎかい。学問を理解するための足場にすぎない。それらは学問そのものではないことを理解すべきだ」と。
ビュフォンが、おそらく数学的方法にも精通していたことは、注目すべきことかもしれない。例えば、彼はほぼ間違いなく、自然世界を研究する道具としての微積分法の威力を知っていたろう。
しかし彼は、真の学問の最高の対象である自然世界を、あらゆる要素を記号に置き換えた人工的体系で、しっかり理解できるか怪しいと考えたようだった
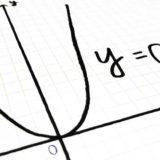 「微積分とはどのような方法か?」瞬間を切り取る
「微積分とはどのような方法か?」瞬間を切り取る
博物誌の第一巻第一説の最後、ビュフォンは、数学的真理と自然学的真理の区別を試みたとされる。
「われわれはいくつか仮定し、それらを様々な方法で組み合わせる。この組み合わせの集合が数学である。したがって数学には、われわれがそこに投じたものしかない」
仮に神が存在するとして、それは偉大な幾何学者というわけではない。幾何学者は人間であって、自然の動作を理解するために数学を使っているかのようだ。
そしてビュフォンは、「つまりは、数学的真理はつねに正確で論証的であるという利点があるが、しかしながら抽象的かつ知的で恣意的なもの以上にはなりえない」とした。
これは、ビュフォンの同時代人の多くの科学者が持った(あるいは持とうとした)、数学こそ神の英知とするような、つまり最も優れた幾何学者の神の(実際、現代まで、科学と神を普通に共存させるためのパターンとしては最も一般的であろう)世界観とは相入れない。
自然の世界で最初に目覚めた人が見るもの、知るもの
ビュフォンは、アリストテレスを絶賛した。彼の著作には「作品の構想や、その配列、例示の選択、比較の適切さ、ある種の思想の表現の仕方、つまり私が進んで哲学的性質と呼ぶもの」があると。
おそらくは、キリスト教文化に広まっていた哲学者アリストテレスでなく、博物学者としてのアリストテレスの崇拝。
アリストテレスは、「ヒトがもっとも完璧なものであるというよりも、むしろ、もっともよく知られた動物であるから」という理由で、比較研究の出発点に人間を選んだが、ビュフォンもそれに習った。
しかし、自然世界の中心の存在としての人間を、ビュフォンは、アリストテレスよりも重視したと言われる。博物学は、人間の主観的なものだから。
「実際にすべてを忘れた一人の人物、あるいはまわりを取り巻く事物に対し、今はじめて目覚めた人がいるとする。この人が、動物、すなわち鳥類や魚類、植物、石類などが次々とあらわれる田舎にいるならどうか。最初、この人は何も見分けられないだろう、すべてを混同するにちがいない。しかし同じ事物を何度も知覚することにより、徐々に彼の観念は固まってゆくはずだ。やがてこの人は生命のある物質について一般的な観念をもつようになり、それを生命のない物質と容易に区別するようにもなるだろう。そしてついには、動物、植物、鉱物という、最初の大区分に到達するだろう」
この、自然世界に目覚めた最初の人が学んでいくイメージは、特に引用されることが多い。
動物、植物、鉱物は、基本的な自然の三界として定義されていたもの。
三界は「自然そのもの」からくる。よって創造された全てのものにあるらしい「存在の連鎖」、「自然物の階段」、つまりはシームレスな(つまり切れ目のない)系列を想定する必要はないはず。
しかしビュフォンは、人間を「創造された全存在の頂点(人間の領域)に身を置いたなら、もっとも完全な生物からもっとも形の定まらない物質へ、もっとも体制の整った動物からもっとも粗雑な鉱物へと、ほとんど知覚しえない段階をたどって下降してゆくことができるのを、見ることになるだろう」とも言う。しかし彼の別の理論と合わせて考えるとすると、それは実用的な方法ではあるが、おそらく真理ではないということになる。
実際のところ、ビュフォンが分類というものを恣意的なものとして軽んじていたことは確かと思われる。ある生物種と生物種に優劣が定義できるとしても、それが絶対的なものであると考えていたかも微妙。
地球の理論。自然の諸時期の理論
ビュフォンの記念碑的著作『博物誌』は三六巻もある(ビフォンが単独で書き上げたものではないようだが、基本的には彼が細かく指揮をとったという)大作であり、ビュフォンは、結局その全てが出版されるのを見ずに死んでしまった。
ビュフォンは1778年、つまり71歳の時、『博物誌』の補遺第5巻を出版した。それが、「自然の諸時期」とか、「地球の時代」と呼ばれているもの。
それは出版当時から、大反響と論争を巻き起こしたとされる。徹底的に史的自然観への移行をうながしたものとして、まさしく歴史上における重要な科学書とも。
『自然の諸時期 (叢書・ウニベルシタス 456)』
通常、ビュフォンの「地球史理論」は、彼の時代に学者たちの間で加熱していた地球の年代や、その表面世界を造る自然システムに関する議論への、1つの答。
海生貝類の化石が山などでも見つかることから、「現在、陸地であるところと海であるところが、時代によって変化していた」という説は、少なくても古代ギリシャの時代からある。
 「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの
「古代ギリシアの生物科学」自然哲学のいくつかの特徴。アリストテレスが変えたもの
しかし、西洋世界でキリスト教の影響が強まると、それほど遠くない昔に起こった大洪水伝説も一緒に有名になったから、陸地で見つかる海の生物の化石は、かつてほど奇妙なものとは考えられなくなったようだった。
 「洪水神話」世界共通の起源はあるか。ノアの方舟はその後どうなったのか
「洪水神話」世界共通の起源はあるか。ノアの方舟はその後どうなったのか
中世でも、少なくともルネサンス期に入ると、「単なる大洪水の結果」から離れる研究者もいた。
一四世紀のニコル・オレーム(Nicole Oresme。1323~1382)は、地球の全般的均衡に関して、地塊と海水塊は浸食作用と堆積作用によって変化しうるという考察をしたという。
またレオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci。1452~1519)も、山で見つかる貝類化石の原因が大洪水であるという説を否定した。
 「化石の謎」大地の動きの理論、無生物起源説。いくつかの論争
「化石の謎」大地の動きの理論、無生物起源説。いくつかの論争
しかしながら、彼らの説はマイナーな説だったと思われる。
一般に、コペルニクス(Nicolaus Copernicus。1473~1543)や、ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei。1564~1642)などが始めたとされる天文学の革命は、地球に関して、”宇宙の中心”という設定を外し、それをただの1個の、広大な宇宙の中の点へと変えたとされる。
しかし、それがおそらく、この地球という世界自体への強い興味を、再び学者たちに与えることにもなった。
ビュフォンも、その新しい天文学の世界観に影響を受けている節がかなりある。
では具体的に、「自然の諸時期」にはいったい何が書かれているのか。
観察と実験が明らかにしてきた重要な事実
「……時間の闇の中に分け入り、現在の事物を観察することにより、消滅した事物の往時(過ぎ去った昔)の状態を知ること、残存する事実だけを用いて埋もれた事実の歴史的真実にさかのぼることが重要だ……次の三つを主要な手がかりとすることにする。第一に、自然の起源にわれわれを近づけてくれる事実。第二に原初の自然の証人と見なされるべき遺物。第三にその後に続く時代の概観を与えてくれる伝承……」
そしてビュフォンは、第一の手がかりである事実として、以下のような五つを挙げる。
第一事実=「重力と遠心力の法則が要求する割合に応じ、地球は赤道で高く極で低い」
第二事実=「太陽光線が地球に伝達する熱とは別に、地球はそれに固有の内部熱をもつ」
第三事実=「太陽が地球に送りだす熱は、地球の固有の熱と比べればかなり小さい。明らかに太陽からの熱だけで生きた自然を維持することは困難」
第四事実=「地球を構成する物質は一般にガラスの性質を有し、すべてガラスに還元しうる」
第五事実=「地球の表面、また高さ一五〇〇、二〇〇〇トワーズの山の上にさえも、貝殻を始めとする海産物の遺骸が大量に見られる」
これらのことに関して、彼はどれくらい確信を持っていたろうか。
まず第一の事実は「重力の理論と振子の実験により、数学的に証明され、自然学的に立証されている」としている。ビュフォンの持ちえた知識的にも、この結論はおそらく最も納得しやすいものだ。
興味深いことは、完全でない球という形が、素早く自転する液状物体が落ち着く形として考えやすいという指摘。ビュフォンは、現在の地球の形こそ、まさにその形が定まった時にこの巨大な物体が液体状の何かだったことの強力な根拠とする。もしも地球が自転を開始した時に、現在と同じような硬い塊であったとするならば、遠心力の影響はほとんど受けず、最終的に現れた形は完全な球体だったはずと。
さらに、これまでの様々な観察事実からして明らかに「熱がなければ物質は固体にしかならない」。
ビュフォンは一応、初期の液体状態が、「全てが水に溶けていたため」という可能性も考えてはいる。しかし実際に地球上で観察されている多くの個体物質が、水に溶けにくい事実から、それは低い可能性としている。
こうして彼は、初期の地球はとてつもなく高い熱が原因で液体状態だったと結論する。
ビュフォンは、地球の初期状態が熱い液体だった説が、さらに第二第三の事実により補強されるとする。
つまりは「太陽からやってくる熱よりも、現在もなお残存する地球内部の熱が大きいことは、つまり地球の表面が地球の内部より冷却されていることを証明している」と。
ビュフォンは、人間たちがそれまで地球表面に開けることのできた穴のスケールがずいぶん小さい事実を残念がりながら、多くの観察事実が、その表面にかなり近いところの(つまり浅い)地下ですら、地表よりも熱い結果を示すと言う。そして、それは地球内部にいくほど熱が高まっていくことを示唆していると考えた。
全てはガラス物質であるのか
第四の事実は、今の人から見て、おそらくもっとも奇妙な結論。
ビュフォン曰く「……地球を構成する物質がガラスの性質をもつことに疑問の余地はない。鉱物、植物、動物の本質はガラス質物質でしかない。なぜなら、それらのすべての遺骸、それらのすべての砕片はガラスに還元されるからである。化学者が「耐性がある」としてきた物質、炉の火に抵抗しガラスに還元されないゆえに彼らが融解しないと見なしている物質も、さらに激しい火の作用にさらせばガラスに還元される。したがって地球を構成するすべての物質、少なくともわれわれに知られているすべての物は、ガラスをその実体の基礎とし、それらに激しい火の作用を加えれば、いまからでもすべてを原初の状態に戻すことができるのである」
現代においては、ガラスという物質を、例えば金属やセラミックス(非金属)と区別する一般的な基準は、その分子構造である。
ビュフォンは、(彼がそれに関するどのくらいのデータ量を持っていたのかはわからないが)どうやら様々な物質の性質を研究して、全てのものは実質的にガラスの性質を帯びることがあると考えたらしい。
さらには、そもそも地球の物質全てがガラスの性質を有しているという事実もまた、初期の地球が高い熱を持った液体であったことの根拠の1つとする。
しかしまた興味深いのが、ガラス質物質とは別の、「石灰質物質」が存在するというもの。少なくとも地球上の物質は全てガラスに還元できるとは結論しているものの、今の地球には(あらゆる物質がガラスに変わるほど高い温度より)はるかに低い温度で石灰に還元される性質を有する石灰質物質があると。
第五の事実と合わせ、そのような(実質的に、超高温にさらされない限りはそれで安定しているのであろう)非ガラス物質は、初期の高熱世界とは別の時代に、別の作用によって形成されたものとビュフォンは推測する。さらには、「原初の火の作用から直接生みだされたのではない全物質は、貝殻などの海産物の遺骸で構成されているようだ。従って、それらは明らかに水を介して形成された」とも。
ビュフォンは、活岩、石英、砂、砂岩、花崗岩、粘板岩、片岩、粘土、金属、金属鉱物をガラス質物質に分類した。
それ以外の物質、石灰質の砂や砂利、白亜、石村、切り石、大理石、アラバスター、方解石などが、石灰質物質。
前者が、初期の高熱により形成された物質群。後者も、元はそうと言えるのだが、しかし様々な段階を経て変質させられて、現在の地球の気温の中では別の性質の物質として安定している群。
より具体的には、後者は「水の中で形成され、いずれも石サンゴや貝殻などの水生動物の遺骸や、その砕片によって全体が構成されている」物質群。
もちろん石灰質物質は第五事実のそれ(海産の遺骸)でもある。
全ての物質が、最も根本的なレベルではガラスとしながらも、特定の(現在の地球のような)環境や、そこに至るまでの過程の中で変質が生じて、実質的にガラスと区別できる物質も誕生するという考え方が明らかにある。
地球の気候変化と、生物の生息場所の変化とのリンク
地球の歴史研究のための主要な手がかりの第二、遺物もまた、ビュフォンはいくつかに分ける(彼が、研究のための分類を便利と感じていたことは、ほぼ100%間違いない)
第一の遺物=「地球の表面や内部で発見される貝殻などの海産物。石灰質と呼ばれる物質はそれらの遺骸によって構成されている」
第二の遺物=「ヨーロッパ諸国の地中から掘りだされる貝殻や他の海産物を調査してみると、これらの遺骸の主であった動物種の大部分は近隣の海では発見されず、その種はもはや生存していないか、南の海にしか生存していないことが明らかになる。同様に、非常に深いところにある粘板岩などの物質の中に、われわれの気候帯にはまったく所属していない種類の魚や植物の刻印が発見されるが、それらもまた生存していないか、南の気候帯にしか生存が見られないもの」
第三の遺物=「シベリアを始めとするヨーロッパとアジアの北の地方で、ゾウ、カバ、サイの骨格や牙や骨片が大量に発見される。こんにちでは南の土地でしか繁殖できないこれらの動物種が、かつては北の土地に生存し、そこで繁殖していたことの証拠。また、ゾウなどの陸生動物の遺骸がかなり浅いところで出現するのに対し、海産物の遺骸は、それより地中深く埋められていることが観察されている」
第四の遺物=「ゾウの牙および骨とカバの歯は、われわれの大陸の北の土地だけでなく、アメリカ大陸の北の土地でも発見されている。新世界の陸地には、ゾウの種もカバの種も現在まったく生存していないにもかかわらず」
第五の遺物=「大陸中央部、海から最も離れた場所で、無数の貝殻が発見されている。その大部分は南の海に現在生存している種類の動物が残したものだが、他のいくつかには類似の生物がまったく見られないため、それらの種はいまだ知られざる原因によって絶滅させられたものと思われる」
ビュフォンは、それらの遺物群と、現在の地球生物の生息分布の比較した場合に見られる違いが、長い時間の中での地球各地の温度の低下(つまり原初の熱の影響の弱まり)が、生物の生息場所を変化させてきたためと考えた。
まず最初に、地球を構成することになる全部質は、火によって融かされた(第一の時期)。
その後、地球の物質は硬くなり、ガラス質物質の巨大な塊を形成(第二の時期)
次に、海が現在生物の居住している大地を覆い、有殻動物を育て、その遺骸が石灰質物質を形成(第三の時期)
さらに、大地を覆っていた海が後退した(第四の時期)
そして、第五の時期では、いよいよ陸の動物がこの地球に現れる。最初、ゾウやカバのような温暖な気候を好む動物は、北の大地に住んでいた。つまりそれらの、現在においては寒帯とされている地域も、昔は熱かった。
プレートテクトニクスどころか、大陸移動説も、普通は20世紀の理論とされているので、当たり前だが、ビュフォンはその、かつて北が熱かったという自説について「驚くべきことであり、信じがたいこと(しかし、寒い地域で象牙が見つかることから、間違いない事実)」と述べている。
興味深いことにビュフォンは、動物の体(体質)が「自然の中で最も固定的なもの」としている。「動物の体の基本的形態、例えば昔のある時代のゾウに、トナカイの体質が備わっていたはずがない」と。
ビュフォンは、ラマルクの進化論に影響を与え、ラマルクはダーウィンの進化論に影響を与えたとされている。しかしまだ、進化論までは大きな距離があったのだろうか。
とにかくビュフォンは、動物の体質が環境そのものよりも固定的であるはずだから、温暖な気候を好む生物が、昔は寒い地域に住んでいたということは、つまり寒い地域が昔はもっと暖かい気候だったと考えた。
なぜ惑星は冷えていくのか
しかし、初期状態の高熱の液体物質が、だんだんと冷えていったというシナリオにおいて、問題になることの1つは、そのようなダイナミックな温度変化がなぜ起こるのかということ。
宇宙の物は、自然に冷えていくのが摂理なのだとしても、なぜ高温の状態が最初にあったのか。または物が必ず冷えていくというものでないのなら、いったい高熱の液体だった地球がなぜ、温暖な気候を好む動物が生きるのが難しいほどに寒い地域ができるほどに冷えてしまったのか。
ビュフォンは、長い時間をかけて少しずつズレていく地軸のズレが、地球の各地帯の温度変化と関係しているという説に触れて、しかししっかりと検討すれば、それはおそらく間違いとしている。
明らかに、地軸のズレの原因は他の惑星群の引力とし(現在では地表の質量配分説の方がよく聞くが)、「しかしそれは、連続的かつ恒常的な減少または増加ではない。それは制限された変動でしかない」、従って、計算上はそうと考える何の根拠もないような、全ての惑星の軌道変化でもないなら、地球の温暖地域をそこまで大きくずらすような地軸変化は望めないはずだと。
地球はなぜ冷えていくのか。しかし広大な宇宙空間という熱を捨てる場がすぐそこにあるのだから、宇宙の中の点である地球世界の温度が、普通は冷えていくというのは、ビュフォンの時代でも想像するのは難しくなかったろう(実際、彼がそのように考えていた節がかなりある)。
もちろん「地球は現在の状態にまで突然冷えたのではなかった」。それは少しずつの変化で、長い時間がかかった。そしてまさに少しずつの変化であったのだから、今とても寒い地域でも、そこまで寒くなく、そこそこ暖かかった時期があったということになる。まさにそれが、雪国で象牙が見つかる理由とビュフォンは考えた。
地球の各地で温度の変化の各時期にズレがある理由も、ビュフォンは、地球が完全な球体でないことから説明した。つまり、球体の中の厚みのある部分は、たくさんの内部熱が保存されているために、冷却が遅れたと。
そしてさらに第六の時期。その時には二大陸の分離があったとビュフォンは推測した。どうやらそれも、古代種(化石種)と現生種の分布から着想したことらしい。また、プラトンが記述したアトランティスは、その大陸間を繋ぐものだったかもしれないとも。
 「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
古代の巨大生物の理由
生物の構造は、自然世界の中で最も固定的という説に関して、何か根拠はあったろうか。
彼は、まさに今の時代の反進化論者が語る話を提示している。つまり、化石種と現生種に違いがほとんど見られないこと、変化するにしても、その途中の種が明らかに見つからないこと。
もちろんそのような説明は、(実際、ある種と種の中間的と思われるような種の化石も結構見つかっている)今の時代よりもずっと説得力があったものと思われる。世界中の誰も、恐竜の存在すら知らなかった時代である。
 「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。
「恐竜」中生代の大爬虫類の種類、定義の説明。陸上最強、最大の生物。  「ギデオン・マンテル」恐竜の発見者。イグアノドンの背に乗って
「ギデオン・マンテル」恐竜の発見者。イグアノドンの背に乗って
「このような生きた自然の太古の遺物と現在の自然の作品を比べてみると、各動物の基本的形態は、その主要部分において変化はなく、同一のままで保存されてきたことが明らかになる。それぞれの種の類型はまったく変わらず、内的鋳型はその形態を保ち、なんの変化も引き起こしていない。時間の連続をどれほど長くとろうとも、世代の数をどれほど多く仮定しようと、こんにち各種族の個体は最初の時代の個体と同じ形態を示しているのだ。特に刻印がより揺るぎないものであり、本性がより固定的なものである大型の種においてそのことは明らかだ」
しかし彼は「下等な種は退化をもたらす種々の原因の影響を顕著にこうむってきた」ともし、さらには「大型種の遺物(化石種)は、現代の同種よりも明らかに大きい傾向がある」という事実も、重要とした。
昔の生物が大きかったが、今の生物が基本的に小型化の傾向があることに関しても、自説の根拠として扱っている。ようするに昔の自然は、あるいは具体的に地球の内部熱は高く、つまり活力に満ちていたろうから、それを自由に使えた生物群に巨大化の傾向があったのは当然であろうと。
一般に、生物学の世界に”生物種の絶滅”という概念が定着するのは、もう少し後の(例えばキュヴィエの)時代とされているから、以下のような、消滅してしまった生物種に関する話も興味深いか。
「もし(いくつかの遺物から明らかなように)失われた種、すなわちかつては生存していたが現在はもはや生存していな動物があったなら、それはその本性が、現在の熱帯の熱より大きな熱を必要としていた動物であったとしか考えられない。摩耗した大きな突起のある、ほぼ四角の巨大な臼歯を有する動物、石化した巨大な巻貝、現在ではどこにも類似の生物を見ることのできない化石の魚類や貝類、これらは原初の時代にしか存在しなかったのだろう。その頃には、今のどこにも見れないほど熱かった陸と海が、それらの、大きな熱を必要とする動物を育てあげていたに違いない」
神、信仰への言い訳
ビュフォンは明らかに、素直に解釈できるような聖書の世界観は拒否していたものの、気をつかってはいた。
しかし、彼はそれを「不当な非難とも称し得る」としている。例えば、盲目的に聖書を信じ、何らかの科学的な説を否定する態度とかを、かなり嫌っていたのかもしれない。
しかしそれに、自分なりに答える必要性を感じていたのはかなり間違いないだろう。
「……人は言うかもしれぬ。あなたは、あなたが物質に与えているとてつもない古さと、世界に六〇〇〇年か八〇〇〇年程度の長さしか許さない聖なる伝承とを、どのようにして一致させるか。証拠がいかに強力でも、事実がいかに明白でも、聖書に記されている事実はよりいっそう確実なのではないかと……
しかし、偉大なる神の御名、神聖なる神の御名が濫用されるたび、わたしは悲嘆にくれる……わたしは自然の懐の中に入り込めば入り込むほど、ますますその創造者に感嘆し、深い尊敬の念を捧げてきた。しかし盲目的な尊敬は服従に他ならないであろう。反対に、真の宗教は理性に支えられた尊敬を前提とする。それゆえ、天地創造に関して神の代弁者がわれわれに伝えた最初の事実を、正しく理解するよう努めようではないか……」
そして彼は、聖書の、それほど文字通りでない解釈について語る。
例えば、第一日に「神が天と地の物質を創造された」ばかりの頃、(太陽や月が使えるのは第四日だから)まだ天と地の物質は明確な形態をもたずに存在していたはず、その古い時代は、長期間続いていたように思われる。とする。
ようするにビュフォンは、典型的な、”はっきりとは書かれていないが、実は創造の7日間とか言われている時代などは、今で言う7日間じゃなくて、とても長い時間だった”というような説を持ち出している。
しかし、本当にそう思っていたのか、ただのその場しのぎの言葉かはともかくとして、なかなか上手く言う。
「そもそも神が与えられるあらゆる霊感も、人間の器官を介した間接的なものということをちゃんと理解しておくべきだ。神の言葉は、抽象的観念を盛るには正確な表現を欠いた、貧弱な言語によってわれわれに伝えられたので、神の言葉の代弁者は、状況によってしか語義が決定されない言葉をしばしば用いなければならなかったのだろう……
……実際のところ、神の代弁者は民衆に話しかけねばならなかったのであり、もしも彼の言葉がこんにち発せられるようなものであったなら、それは全く理解されないままに終ったろう。こんにちでさえ、天文学と自然学の真実を確実に知り、その言語を理解できるほどの人間は、ほんのわずかしか存在しないのに」
ただビュフォンは、「「自然の諸時期」に書かれたわたしの体系は、純然たる仮説であり、啓示された真実を害することはできないのだと知っておいてほしい」などと書いてもいる訳で、やはり自分の理論と神の言葉がすっかり調和することは、おそらくないと考えていた。
火の元素と、太陽系を始めた最初の衝撃
しかし原初の地球に熱を与えたのはいったい何だったのか。
ビュフォンは最新の天文学を参考にした。
「融解した地球が自転しながら形をなし、赤道で高く極で低くなった第一の時代、他の惑星も同じ融解の状態にあった。そのことは、自転していたそれらの惑星のとった形が、地球と類似していることから明らかである……
さらにすべての惑星は太陽のまわりを同一方向にほとんど同一平面上を公転しているので、それらは共通の衝撃によって同時に始動させられたと考えられる。この公転運動と自転運動は、火による融解や溶解の状態とともに同じ時代に開始されたのであるから、その運動を生みだした衝撃がそれ以前に存在しなければならないだろう」
問題は、最初に、この太陽系というシステムに影響を与えた衝撃とは何だったのか、ということ。
まずビュフォンは、太陽系の生成過程に関して述べる。
惑星の周囲をめぐる衛星、というのは、おそらくまだそれらが液体状であった頃、極めて早い自転のために、ある時、遠心力の効果が重力の効果を上回ったため、惑星のかけらが飛び出したもの。「もちろん球体表面が冷却により粘りけと硬さを持ち始めると、物質は同じ強さの遠心力で駆り立てられても、凝集力によって引きとめられているため、自転運動によって惑星の外に分離され放出されることはもはやなくなる」
そして同じように、太陽の周囲を公転している惑星群は、太陽のかけらが糧になっていると考えられる。太陽が高温の火の塊であることも重要。「われわれは太陽の火以外に、地球と惑星の物質を融かし融解状態に保つ、いかなる火も熱の原因も自然の中に見つけることはできないので……」
火の元素(フロギストン)という幻想を破壊したプリーストリ(Joseph Priestley。1733~1804)やラヴォアジエ(Antoine-Laurentde Lavoisier。1743~1794)は、ビュフォン(1707~1788)よりも少し後の人物。まして「火の元素が存在しない説」もまた、すぐさまあらゆる科学者に受け入れられたものではない。
 「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち
「原子の発見の歴史」見えないものを研究した人たち  「ヘンリー・キャベンディッシュ」最も風変わりな化学者の生涯と謎。
「ヘンリー・キャベンディッシュ」最も風変わりな化学者の生涯と謎。
少なくとも、ビュフォンの太陽系形成の物語の中に出てくる、太陽を構成し、各惑星を融解した火というものは、まだかなり物質的なイメージを抱かせる。
またビュフォンは、それまでの様々な実験が「火が物体を融解温度まで熱するには、それを冷却するのに必要な時間の少なくとも一五分の一は必要」と示しているとする。「各惑星の体積が膨大であることを考慮するなら、融解に必要な温度を獲得するためには、それらは太陽の近くに数千年間静止していたと考えざるをえない」と。
しかし「なんらかの物体、なんらかの惑星や彗星が、一瞬なりとも太陽の近くに静止していたという例は宇宙に存在しない。それどころか、彗星は太陽に近づけば近づくほど運動を速める。彗星が近日点にある時間は極端に短いため、太陽の火には、太陽に最も接近した彗星の表面を焼くことはできても、その塊の中に侵入する時間もあるはずがない」
「宇宙に」という表現は大層な言い方に思える。ビュフォンは何を知れたのか。宇宙に輝く星々が太陽のような恒星であることが認識できていたとしても、それぞれが太陽系のような、つまり惑星や衛星が恒星周囲をめぐっている世界観とははっきり知らなかったはずだ。
しかし宇宙の星(だけでなくあらゆる物質だろうが)の動作モデル、つまりは恒星の近くで、惑星が長い時間静止しているなんてことがほとんどありえないような世界観に関しては、おそらく自信があったろう。新しかったニュートン(Isaac Newton。1642~1727)の重力法則を用いて計算すれば、そうだと結論するのは、数学が得意な彼には、それほど困難なことではなかったはず。宇宙のどこでも、ある科学法則は平等に働いているはずという考え方(あるいは理想)が想定するまでもなく、そこに明らかにある。
ビュフォンは、太陽系というシステムを構成している各惑星の動作のある程度の均一性(例えば各惑星は同一方向にほとんど同一平面上を公転している)から、それらの初期状態のために与えられた衝撃はただ一つと推測。
一方で、「太陽のまわりを回転してはいても、様々な平面上で方向も様々である彗星群は、個別の衝撃で始動させられたのだろう」としている。
特に重要なことは、各惑星の動作を決めた(さらには初期状態の高い熱を与えた)のは、ただ一つの衝撃だったということ。
ビュフォンは、それがあくまで自分の想像でしかないことを認めながらも、非常に興味深い1つの物語を想定する。
「すなわち、わが太陽系の彗星は、われわれの太陽に近接した一つの恒星、つまりもう一つの太陽の爆発により形成された。そこからまき散らされたすべての破片は、もはや共通の中心や焦点をもたないため、われわれの太陽の引力に従わざるをえず、それ以後は太陽がそれらすべての彗星の中心および焦点の役割を担うことになった。
しかしわれわれとわれわれの子孫は、将来の観察により、彗星の衝撃運動の中になんらかの共通の関係が見出されるまでは、これ以上のことは述べられないであろう。われわれは比較によらなければ何ごとも知りえないのであるから……」
やはり、もう1つの太陽というのは、注目すべき記述かもしれない。
ビュフォンの太陽系に関する記述には、同じような星系が他に存在してもおかしくないと思わせるものも多い。
これはすでに、地動説を唱えたため火あぶりに処されたとされるジョルダーノ・ブルーノ(GiordanoBruno。1548~1600)も唱えていたようだから、別に新しい考え方でもない。
それでも、宇宙要素のダイナミックな変換というアイデアはやはり興味深い
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性  「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
「地動説の証明」なぜコペルニクスか、天動説だったか。科学最大の勝利の歴史
ビュフォンは、彗星の運動の原因こそわからないものの、恒星から素材を引き剥がして、惑星を形成するような動作は、それにぶつかった彗星が原因じゃないか、という説もすでに語っていた。それ以外に、それほど大きなスケールでの星の分裂を引き起こすような衝撃が知られていないから、と。
さらに太陽(というより恒星?)は、周囲を回る物体群の重量と浸透力の作用を受けとり、同時に塊のあらゆる部分で起こる内部摩擦の作用に耐えているのだろうとし、それなら「太陽を構成する物質は最も激しい分裂の状態にあるに違いない」とも。そして太陽黒点の不規則な運動などの観察記録から、恒星はつまり液状天体と推測している。
そして、そもそもそのような状態(太陽の熱)の原因もまた、惑星よりもさらに昔から周囲を巡っていると思われる彗星の圧力しかないと。
ビュフォンはどのくらいに神を疑ってたろうか(そもそも本当に疑っていたのだろうか)?。
彼の考えていた宇宙は、明らかに、それ以前の状態からの変換後の姿であると思われる。本当の初期状態が、いったいいつ、どういうふうに存在していたと考えていたのか。
四大元素と、時間の量
ビュフォンは、地球や、他の惑星の多くの起伏、凹凸、窪み、高地、空洞は、灼熱の液体からの冷却過程における「諸元素の生成とそれらの争い」が原因とした。
元の素材は太陽の欠片なわけであるから、初期の高熱の液体状態の各惑星はどれも”小さな太陽”と言えるものだった。そして冷却の原因は「光と熱の外部への発散」としているから、もちろん単純に、体積が小さな惑星ほど早く冷える。ビュフォンは「惑星が中心まで固められない白熱の時代は、地球ではおよそ二九三六年、月では六四四年、水星では二一二七年、火星では一一三〇年、金星では三五九六年、土星では五一四〇年、木星では九四三三年」と算出している。
もちろん彼は、ずっと後に地球の年代を、熱の発散速度を参考に計算して間違ったケルヴィン卿と同様、原子力のことなど知らなかったし、それどころかケルヴィン卿の大きな力であった熱力学さえも彼の時代には成立してなかった。謎の計算結果も仕方がない話であろう。
 エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
また、それも時期を考えれば当然なのだろうが、ビュフォンは、火の元素だけでなく、明らかに四大元素を基盤とした物質世界論を利用した。
最初の熱が少しはましになった時代(第一の時代)。高熱のための混沌(カオス)状態から自由になった「火の元素は、いわば他の三つの元素を奪い取っていた。それらは単独には存在できなかった。火に貪られ、混ぜ合わされた土と空気と水は、明確な形態を保てず、燃えさかる蒸気に囲まれた焼けた塊でしかなかった」
ビュフォンは明らかに、自分の考える地球の年齢が、多くの人にとっては、あまりにも長すぎるものであろうことを危惧している。
それでも結局のところ、彼が算出した地球の年齢は7万5000年程度。現代の我々の知見(一般的には、地球の年齢は45億年)と比較した場合は、驚くべき短さである。
そして興味深いことに、ビュフォン自身もそのことをいくらか自覚していた。「……しかし人々は、わたしが時間の幅を必要以上に拡大したのではなく、短縮しすぎたのかもしれないということに気づくであろう。人間の精神は、大きさ、重さ、数の考察や空間の広がりにおいてよりも、時間の広がりにおいてなぜ困惑するように思えるのか」
彼は言う。「この長い時間を理解する唯一の方法は、それをいくつかの部分に分け、それぞれの部分が存続する時間と、そこに生起する重要な現象とを、とりわけ自然の構築物とを、精神の目によって比較することだろう。大量の有殻動物を作りだすのに必要だった世紀の数、次にこの貝殻とその砕片を運搬し堆積させるために流れたさらに大きな世紀の数、最後にそれら物質を石化し乾燥させるために必要だったその後の世紀の数……七万五〇〇〇年という長大な時間も、自然の偉大な作品にとってはさして大きなものでなかったこともわかるはず」
膨大な時間をいくらかの時期に分ける、というやり方は現代の地質学、古生物学などの方法と同じである。ビュフォンは、生物の恣意的な分類を明らかに嫌っていたわけだが、それでもこの、部分で分けて考えるという方法の強力さも、やはりよくわかっていたのだろう。
水が全てを覆っていた時代
「惑星の形成から三万年ないし三万五〇〇〇年が経過した頃、地球は水を蒸気として追い払わずに受け入れられるほど冷却した。大気の混乱は収まりつつあった。水ばかりでなく、あまりにも強い熱のため遠ざけられ、空中に留め置かれていたすべての揮発性物質も次々に落下してきた……
……かつて海がヨーロッパ大陸を覆っていたという明白な証拠がある。それこそアルブスやピレネーの山で、貝殻などの海産物が発見されているから。同様の証拠はアジアやアフリカの大陸にも存在している」
もちろんビュフォンは、現代の人のように、大陸が移動するとは考えなかった。地球の海の水位がかつて上昇していたことがある(あるいはかつてよりも今が減少している)というのは、もっと古くからある説である。しかし彼の場合は、それは未知の原因による謎現象とかではなく、地球の形成過程から現代に至るまでの変化の歴史を考えると、むしろ当然の出来事と言えるようなものだったと思われる。
 「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
「プレートテクトニクス」大陸移動説からの変化。地質学者たちの理解の方法
そして、火に続く、水の影響がまた、地球を現代のものに近づけてもいく。
「空洞は火の作品であった。水はそれを、今までずっと破壊し続けている。したがってわれわれは水面の低下を、事実によって証明された唯一の原因である空洞の陥没に帰さねばならない。それは水の密度、重さ、量によって引き起こされた最初の結果。しかし水はその質によっても別の結果をもたらした。水は薄めたり溶かしたりできるすべての物質をとらえた。水は空気、土、火と結合し、酸や塩なども形成した。水は原初のガラスの屑や粉末を粘土に変え、さらにはその運動により、それら砕かれた全物質をさまざまな場所へ運搬した」
つまりは、第二の時代とは、地球上の全陸地を覆っていた大量の水、つまり全てを含んでいた海が、あちこちの空洞の陥没による窪みを満たすため、次第に水面を低下させたた時代。また、 様々な物質にそれが溶け込んだために、現在の地球で見られる新たな物質のいくつかを生成した。
偶然の世界か、人類のための世界か
ビュフォンは、(傾斜しているのだから)「傾斜地の上に流水によって運ばれてきたと思われる。多少とも瀝青の混じった植物で全体が構成されている炭層」というのについて語っているが、これはおそらく石炭紀(3億5920万年前~2億9900万年前)の(名前通りに石炭が多い)地層のことと思われる。
それを手がかりに、彼は大量に植物が生み出された時代のことも考える。「水面より上にでていた地球のすべての部分は、当初から、あらゆる種類の草木と樹木を数限りなく生みだした。それらはやがて老いて倒れ、水によって運ばれ、あちこちで植物性物質の堆積を形成したのだろう」
例えば瀝青というのは、炭化水素からなる化合物ともされる(ビュフォン自身の説明では「動物性物質と植物性物質に由来し、酸はガラス質の砂が火と空気と水によって分解されて生じる。また植物油と酸によって瀝青を作ることができるのであるから、酸は瀝青の構成に関与している。したがって水は瀝青と混ざり合い、瀝青を完全に溶かし込んだのだと思われる」)。他のところでも塩化物体とか、いろいろな種類の物質に触れながら、根本的なものは四大元素というように考える。
かなり一般に錬金術的な物質理論があるように思われる。つまりあるスケールにおいて基礎的な元素物質と考えられるようなものは、四大元素以外にもあるが、結局それらも四大元素のいずれかが、どういう形だかで混ざった結果、というような。
ニュートンも、錬金術に強い興味があったとされているが、まだまだそういう時代であり、少し後に再考された原子論は本当に革命的だったのかもしれない。
 「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
それほど膨大な数の植物の地層を形成できた理由の1つは、人間が存在していなかったことだと推測している。つまり、人間による火の破壊が存在しなかったことが重要と。
「したがって植物性物質は炭層の第一源泉だ。それは多くの人間にとっていずれ必要となるものを、自然が前もって蓄積しておいた宝なのだろう。人間が増加すればするほど森林は減少する。木がもはや人間の消費に追いつけなくなるため、人間は可燃物質のこの巨大な堆積に頼ろうとするであろうし、地球がますます冷却するだけになおさらそれは必要になるだろう。それでも人間はそれを使い果たすことはないはずだ。たった一つの炭層だけでも、広い地域の森林全体より多くの可燃物質を含んでいると思われるから」
そのような可燃物質(化石燃料)が枯渇した未来すら、よく想像されている現代の人からすると、興味深いほどの楽観ぶりかもしれない。ビュフォンも、熱によるダイナミックな変質という過程を想像しながら、実際に膨大な熱を使うテクノロジーなどは少しでも考えなかったのだろうか。
また、神ではなく、「自然が人間のためにそのようなものを残しておいた」というような記述からは、まるで人間世界(知的生物の世界?)が生成される場合の、システム的な縛りを思わせるかもしれない。ビュフォンは、生物の型は固定的というように考えていたようであるから、知的生物としての人間も、絶対的な種としての人間だったはず。しかし、もしも人間のような知的生物が賢く生きていくための道具(というかそれを作るための素材)がない場合、実際に、知的生物は長く生きていけるだろうか? もしも炭層がなければ、おそらくビュフォンの世界観では、地球の冷却になすすべなく、人類ももっとあっさり滅んでしまう。だが人類の誕生よりも以前に炭層が生じる過程があるからこそ、人類の歴史は、それがない場合より長く続く。
ビフォンの考え方は、幸運よりも必然を確信しているかのように思われるが。
火山と電気の理論
「海は水の上の大地から引き剥がされたすべてのものを収容する、全世界的な器も同じ。原初のガラスの砕屑や植物性物質が、大地の突起から海の深みへと連れてこられた。海底では、それらがガラス質の砂、粘土、片岩、粘板岩の最初の層や、石炭、塩、瀝青の集積を形成し、後者は海全体に溶け込んだ……
塩や粒状の鉄や硫化物質などの物質の集積に関しては、酸がその構成に関与するため、水の落下が形成過程で重要になる。それらの物質は、低地や地球の岩石の割れ目の中に運搬され、堆積し、地球の高熱により、すでに昇華されていた鉱物物質と出会ったのだろう。そして、将来の火山の糧の最初の基盤を形成することになる」
 「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
「火山とは何か」噴火の仕組み。恐ろしき水蒸気爆発
火山も、古くから知られている自然世界の脅威であるが、しかし長く続く謎でもあった。もちろんビュフォンは地球が現在のようなものになった過程を考える時、それの説明を避けなかった。
彼は、水に運ばれた素材が火山の基盤を作ったと考え、水面が低下して、それが陸に姿を見せ、活動を開始したとした。
ビュフォンは、海底火山は周囲の水のせいで、それほど派手には爆発できないとしながら、地上の火山も多くが死火山である理由は、おそらく火山活動には水もいくらか必要だからなのだろうと考えたようである。つまり火山の力は「火と衝突した大量の水の力」なのだと。
「種々の観察によって確かめられているが、現在活動しているすべての火山は海の近くに位置しているし、活火山よりはるかに数の多い死火山は、すべてが陸地の中央か、少なくとも海から幾分離れた場所に置かれている」
ここでもダイナミックな流れがある。地球は全て水に覆われていたが、最初の頃に水が引き始めた時、最初にあらゆる陸地は、今現在、海から離れた土地であった。つまり地球の凸凹では「起伏の高いところ」。そして火山の力は、「水と火のぶつかり合い」が原因であるので、陸として現れたりばかりの火山は最初は活発だった。しかし水が引くにつれて、海から離れた位置になる火山は活動を止めていく。そしてまた、海に近い火山が活発に活動する。そういう流れ。
この火山の力の原因に関する考察は、さらに興味深く続く。
「たしかに結果について述べられるほどに、われわれはこの恐るべき火砲の内的構造を充分観察してはいないだろう。それでもわれわれは、火山と火山をつなぐ地下の連絡がしばしば存在することをはっきり知っているのだ。またわれわれは、火山を燃やす炉心は頂上からさほど遠くないところにあるにもかかわらず、それよりはるか下にまで延びる空洞があり、深さも広さもわれわれには未知であるその空桐は、全体として、あるいは部分的に、現在燃えている物質と同じ物質によって満たされているらしいことも知っている。
他方では、地震や火山の噴火において、電気がきわめて重要な役割を演じているとわたしは推測さている」
ビュフォンは、水と火のぶつかり合いが魔法を生むのでなく、はっきりと、それは地下の空洞での衝撃なのだというように推測する。
そしてまだまだ未知の力であったろう、電気。
「……電気に関する諸実験の比較から、電気物質の本質は地球に固有の熱だと、わたしは確信している。その熱の連続的発散は、感知はされるが見ることはできず、自由で直接的運動をしている限り暗熱の形態のままに留まる。しかしその発散が方向をそらされたり、物体の摩擦によって蓄積されたりすると、たちまち激しい火と強烈な爆発を引き起こすのである。地球内部の空洞は火と空気と水を含んでいるため、火という第一元素の作用は、猛烈な嵐と雷鳴を伴った、地上の雷によく似た地下の雷を生みださずにはおかない。そのような現象は、堅牢な大地が至るところで地下の雷の電気力に頑強に抵抗するので、より激しく、また持続的なものとならざるをえない。電気により燃やされ、濃密になった蒸気が混じった空気の反発力、火によって弾性に富む蒸気に変えられた水の応力など、電気の力が生みだすありとあらゆる推力は、地表を持ち上げ、押し開き、少なくとも震動により揺り動かすのだろう」
つまりその自然界の電気の作用により、ここでは地震の理由も説明されている。ここでは、電気というのが、そもそも熱の一形態というような印象を受ける。そして、熱というのは、第一元素の火と、様々な物質が関わることによって生じる物理現象というような。
長く生きるクジラの伝説
ビュフォンは、昔、存在していた大型動物が、高い熱の影響で自然の活力が高かったから存在できた、と考えたが、クジラに関しては、別の興味深い仮説を提示している。そうせざるをえなかった理由は、大型のクジラが基本的に寒い北の海の生物種であり、温暖な海の近い系統の手話基本的に、北の海のクジラよりも小型のものが多いという観察記録。つまりそれは、ビュフォンの自然世界観においては、矛盾している出来事のように思われた訳である(寒い地域に大型の種が存在している。また、大型のクジラの中でも放浪好きの種であるとして、マッコウクジラは例外扱い)。
ビュフォンは、人間たちの捕鯨文化に注目した。
つまりは、巨大な生物は基本的に非常に長命であって、クジラも本来は、例えば1000年とか生きれるのかもしれない。しかし、今の我々は、捕鯨の影響によって、数百歳とかの段階の、若いクジラしか知らないとか(この場合、高い熱、あるいは生命力が必要となる、もっと大型になったなら、クジラも温かい海にやってくる、という流れも考えられたろうか)。
また水生動物にとって、温度の変化は、陸の動物の場合ほど問題ではないはず。海の中では大気の影響が弱いため。さらには大型のクジラの体を覆う大量の脂肪と油は、それらの種から鋭敏な感覚を奪うのでないかとも。
生命のための有機分子は、魂の代わりか
ビュフォンの世界観では、基本的に、地球のある部分(北の地域)が生物に住めるくらいの温度にまで下がった時、そこでまず、高熱を好む様々な生物が誕生した。しかしその後、南の方がまた暖かくなる一方で、北はさらに寒くなってしまい、暖かい気候を好む大型動物たちは南へと渡ってきて、現在の分布になっていった。
つまりは、南側の生物は北側からやってきた生物たちであって、そこで誕生した生物ではない。あるいは仮に、南で生物が誕生したのだとしても、それらは「大きさと力の点で、北から訪れた種よりきわめて劣った種でしかないだろう」というのが、ビュフォンの見解だった。
いったいなぜなのか。
その理由の説明もまた注目すべきものと思われる。そこで述べられているのは、実際的な生物発生の過程の推測そのもの。
「生成と生殖、成長と発育には、必ず大量の生きた有機分子の協力と結合が必要なはず」
明らかにそうだからこそ、生物は、非生物物質と区別できる。これは、神や魂の存在を少しでも疑っているのなら、それで、生物をただの物質として考えたくないのなら当然の推測だろう(現在でもそうだろう)。
しかし、生命のための有機分子。
「すべての有機体に生命を付与するこの分子は、あらゆる生物の栄養摂取や生殖に次々と用いられる。生物の大部分が突然消滅させられたとしても、破壊されることなく常に活動するこの有機分子は、別の有機体を構成すべく結合するので、新しい種が出現すると思われる」と、これはほとんど、輪廻転生なども説明できる、神話的世界観の魂の代わりと言えるようなものかもしれない。
ここから特に興味深いのだが、ビュフォンは、南の地で、先に北で起こったような生物発生がおそらくなかった理由に関して、容量制限という説を唱えている。
「もしその分子が、既存の生物の内的鋳型によって完全に使い果たされていれば、少なくとも大型動物のような自然の第一の種類において、新しい種が形成されることはないだろう。大型動物は北から南の土地へやってきた。それらは南の土地で栄養を摂取し、生殖し、繁殖し、おそらくは生きた分子を使い果たしてしまった。だからこそそこに、新しい種を形成できるほど余分な分子は残らなかった」
南アメリカなどの一部の地域では、後からでも大型生物が生成されたとしているが、その理由も「生きた有機分子が既存の動物の内的鋳型によって使い果たされてはいなかった」ためとしている。しかし(十分な量ではないためか)力や大きさの点で、北から南へやってきた動物種よりも劣った種しか形成できなかった。
そして人間について。自然の王は必然の存在であるか
「われわれは、身体的特質という点では人間という種が他の種と本質的に異なるところはなく、その点では人間という種の運命は他の種の運命とほとんど同じであったことを認める。しかし……人間においては、物質は精神によって導かれていることをわれわれは知っている。人間は自然の結果を変更することができ、気候の厳しさに抵抗するすべを見出してきた……知性にのみ由来する火の元素の発見と使用は、人間をいかなる動物よりも強く頑健にし、冷却がもたらす悲惨な結末にも立ち向かえるようにした……人間という種だけが、地球の表面の寒い部分にも暑い部分にも、等しく存在することは別段驚くべきことではない」
世界中のどこにでも人間はいると説明するここで、ビュフォンは平等主義的な思想も見せる。
「……人が居住する土地からきわめて遠い海の小島にいる人間さえ、われわれと種の異なる人間だとは言えないだろう。その者たちはわれわれと交わって子を作ることができるのだから。われわれと彼らの本性の違いは、気候と食物の影響によるわずかな変異でしかない」
しかし重要な問題は、「寒さに対しては容易に備えることのできる人間も、激しすぎる暑さに対してはかなり無力」であることとビュフォンは指摘する。
結果、人間の創造は、必然的に熱を好む大型動物よりもあとのはずであると。
「したがってわれわれは、聖書の権威を離れても、われわれが最後に創造され、地球が支配するに値するものとなったとき初めて王笏を得るために出現した種であると確信できる」
ここにもまた興味深い流れが見られるだろうか。
人間は実質、自然世界の中で支配者としての役割を与えられているような存在、のようである。しかし一方でビュフォンは、最初の頃の人間は絶え間ない(人間から見た場合の)天変地異のような出来事や、初期の巨大な野獣たちによって、ほとんど常に恐怖にさらされていたとも推測している(しかしもちろん、最初は、その恐怖こそが、技術の急速な発展のための原動力になった。また、初期の天変地異の記憶が、様々な迷信の原因の可能性になったという指摘もある)
ある生物種としての人間は自然の王。しかし、まずはっきりとそのような座についていると考えられるような状況になるまでに、多くの犠牲もあったに違いない。
種と個別の存在の関連性をどのように考えればいいのか。
人間社会の中でも、格差や権威などというものが設定されることは珍しくない。しかし現実の人間の王国の王は(長い歴史の中のわずかな出来事として見た場合に)あっさりと引きずり降ろされてしまうこともあるだろう。
自然世界ではどうか。「王笏を得る種」とは単なる比喩みたいなものだろうか。
ビュフォンは、生物種の内的鋳型は変化が生じにくいととしているが、宇宙には様々な変化が生じてきて、そして生物の変化も、生物に必要な有機物質と、普通の物質群との反応による変化の結果。
「聖書の権威を離れても」と彼は言うが、人間が支配する自然世界というのは、彼の世界観だと”ある変化パターンの上に生じた一時的な物質世界”というような印象である。人間は明らかに、神が創った絶対的世界における、絶対的な支配種ではない。
それでもビュフォンは、宇宙の中で生物が登場するパターンというのは、かなり限られているものとか考えていたろうか。
いずれにしろ、限られた時間の話であることはほとんど間違いない。明らかにビュフォンは、魂より、特殊な物質を想定している。それはオカルトより、物理的システムそれだけの機能であることを思わせる。
ビュフォンが内的鋳型は変化しないか、しにくいと考えたのは、真に適当でデタラメなと言えるような自然世界を否定したかったからともされる。
おそらくは、その「内なる鋳型」という概念は、アリストテレスの哲学における、性質などの「形相」と、個々を構築する素材である「資料」の区別に影響を受けたもの。
形相は永続的で外因的な、つまり外部からの影響による変化でなく、資料を内側から形成するようなシステム要素。内なる鋳型は、その形相に近く、それが質料(つまり構成素材)と同じくらいに柔軟(可変的)だと、全体のシステム的にはおかしくなるだろう。
ようするに、自然世界がどういうものであるにせよ、何かちゃんとした規則的なものはほしかった。そしてその鍵こそが、変化の乏しい各種の生物の本質と関わる内的鋳型だった。しかしそれでも環境の変化の影響で素材部分はいろいろ変化する。考えてみると、ビュフォンの想定した生物種の鋳型というのは、遺伝子とか、遺伝コードというものに近いのかもしれない。
驚くべき天文学を発明した古代文明
「アフリカでも、アジアの最も南に突きでた土地でもなかった。それらの地域はまだ焼けるように熱く無人であったはず。アメリカでもなかった。アメリカの山脈以外は新しい土地に他ならない。最初、文明人が定着したのはヨーロッパでもない、そこははるかのちに東方の知恵を受けとった場所にすぎない。ローマが建国される以前、ヨーロッパで最も恵まれた地域イタリア、フランス、ドイツには、半未開とも言えないような人間たちしかいなかったのだ。ゲルマン人の習俗に関するタキトゥスの記述をひもといてみれば……
したがって人間の知識の幹はアジアの北の地域において成長したはずだ。この知恵の木の幹の上に、人間の能力の玉座が置かれた」
この説は、人間が”それ(知性)を利用する機会が多ければ多いほど、知識を増大させていくだろう”という推測に基づいているようである。つまり「空を観測するためには澄んだ空が必要であり、地を耕すためには豊かな大地が存在する恵まれた気候帯が……」。そしてビュフォンが、条件に当てはまる地域として考えたのが「緯度四〇度から五五度までのアジア大陸の中央部」だった。そして彼は、インド世界の司祭であるバラモンが、古代人から受け継がれてきたと思われる、天文学のいくらかの記録(?)を参考に、そこに興味深い高度な古代文明を想定した。
「バラモンが食を計算するときに用いていた公式は、現代の天体位置換算表を作成するときに必要な学問と同程度の学問がなければ発明できなかったろう。しかしバラモンは、宇宙の構造に関してはなんの考えも抱いていなかったようだ。彼らは食の理論を知らずに食を計算していた。自分たちには理解できない複雑な公式に、機械のように導かれていただけだ」
だがバラモンが確かに何かを受け継いだというなら、その何かを開発した者たちが、さらに昔の時代にいるはず。
しかし中国人、カルデア人、ペルシア人、エジプト人、ギリシア人も、その賢明な最初の民族から、特に重要なことは何も受け継がなかったようだと、ビュフォンは推測した。いずれも、完全な形でその知識を受け継いでいたのならば、例えば考えにくいような迷信にとらわれたりしているから。それに、結局のところ、独自に色々な学問を発明したりしていても、それらはまだ不完全なものでしかなかったとか。
ビュフォンの考えでは、つまり偉大なる最初の文明、彼らが開発した最初の学問は、「蛮族の斧によって人間にもたらされた不幸な混乱の結果」として、破壊されわずかな痕跡だけを残して消滅してしまった。
しかし「博識であると同時に強大でもあったこの最初の民族は、長い間栄華を誇っていた……学問研究に必要なすべての技術において偉大な進歩を遂げていた」
ただし、本当の意味で何もかも破壊されたわけではない。精神の偉大な発見とその記憶は、人間という種が存在している限り、つまりその精神性が完全に途切れない限りは、すっかり消滅してしまうことはない。だからこそわずかな痕跡からとはいえ、現代の人でもそのような古代文明の存在を知ることも可能。そのような推測は、現在の超古代文明論者が好むような、”最も偉大な最初の文明の知恵が、世界中の様々な知的文明の種となった”という仮説も思わせる。むしろそのままである。しかし当然のことながら、そのような仮説も、現代におけるものよりずっと説得力が高かったろう。




