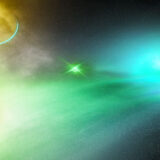「高度な科学力は魔法と見分けがつかない」が有名な人
SF作家としてのアーサー・C・クラーク(Arthur Charles Clarke。1917~2008)は、ヴェルヌ(Jules Gabriel Verne。1828~1905)やウェルズ(Herbert George Wells, 1866~1946)といった、一般的なSFパイオニアの他、ファンタジー系の影響もかなり強いように思う。彼の小説において、度々出てくる「高度に発達した科学は魔法と見分けがつかない」という有名な警句(?)は、まさに彼が、高度な科学力を持った地球外生物や、未来人のテクノロジーの描写時に意識していたものとも思う。とにかく、謎のテクノロジーというよりも魔法かのような。
 海底二万里、月世界へ行く、地底旅行、悪魔の発明「ジュール・ヴェルヌ」
海底二万里、月世界へ行く、地底旅行、悪魔の発明「ジュール・ヴェルヌ」  タイムマシン、宇宙戦争、透明人間、モロー博士の島「H・G・ウェルズ」
タイムマシン、宇宙戦争、透明人間、モロー博士の島「H・G・ウェルズ」
いわゆるオカルト現象への強い関心もかなり明らかで、キリスト教や仏教といった、宗教やその特定思想への傾倒を感じれるような作も多い。例えば、高度知性というか、物質や精神といったものを超越しているような、あるいは通常の1つの宇宙の外側の存在というような、つまり別次元的存在が重要な世界観設定もけっこうあるが、ほとんど必ずと言っていいほど人間が理解している”神”の概念との関連が示唆されているように思う(説明などにおいて、便宜上そういう概念を使うというより、実際的にそういうものが、そのような概念の発生と直接的に関連しているかも、というような)
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束  「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
「仏教の教え」宗派の違い。各国ごとの特色。釈迦は何を悟ったのか
幼年期の終わり
クラークの作品の中でもかなり有名なものと思われるが、典型的なSFというよりかは、彼のオカルト趣味がかなり色濃く出ているように思う。
『幼年期の終わり』
出版年は1952年。案外、現実のUFO神話とかにも大きな影響を与えているかもしれない
 「エイリアン・アブダクション」宇宙と進化の真相か、偽物の記憶か
「エイリアン・アブダクション」宇宙と進化の真相か、偽物の記憶か
物語としては、ある時に地球にやってきた、オーバーロードと呼ばれることになる宇宙生物が、地球生物を管理しているような状態となり、結局目的は何なのか、というようなもの。
宇宙に発生する生物の、進化の到達点。いくつもある1つというより、おそらく数少ない、真の意味での到達点の可能性が語られるのは、『宇宙の旅シリーズ』と同じだが、こちらの場合は、人類という生物種自体が、その流れの一つにのってしまうというか、のせられる、というような話にもなっている感じ。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか 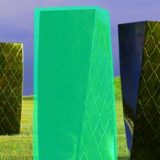 「宇宙の旅」モノリス。人工知能HAL。エネルギー生命。ミレニアムのIF
「宇宙の旅」モノリス。人工知能HAL。エネルギー生命。ミレニアムのIF
幼年期というのは、オーバーロードが地球にやってくるまでの、またはそのオーバーロードが、管理を必要としなくなるまでの人類の状態のことと思われる。そういう意味で、まさにこの作は、タイトル通りに、人類の幼年期の終わりの物語。
しかし、方向性とまでは言わなくても、進化に何らかの到達点があるというような世界観の場合、普通その到達点にたどり着く道を自ら閉ざすような生物は愚か、というように考えられるものだ。
でも本当に、自らの開発したテクノロジーや、文化や社会の誤作動などで、自滅してしまうような生物。そんなことにならなければ、宇宙に飛び出し、生きる場を無限の宇宙に広めることができるのに、1つの惑星の中で、短い時間だけの栄光で満足する(というよりそのひとときのために、無限の未来を犠牲にするような)者たち。そういう生物は、そもそもダメな生物なのだろうか。
例えば、人形遊びがとても幸せな誰かに、ハイテクロボットを押し付けて不幸にしてしまうような。そんな考え方もできてしまわないだろうか。
SFでどうとでも描けるように、結局、宇宙についての我々の知識はわずかすぎるとしたら。
 「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
「進歩史観的な進化論」複雑性、巨大さ、賢さへの道は誤解か
管理するもの、オーバーロード
ところで、この作品で描かれているのは、驚異的なテクノロジーの出会いというよりも、人類を縛り付けている宗教からの脱却、というような感じもある。
それは、賢くなってバカな迷信の誘惑に打ち勝てるようになるとか、そういうものでもない。理解できなかった全ての現象を、理解することにより、神秘的現象から、この宇宙全体における普通の現象へと変換してしまう、というような。
オカルト現象が実在するもので、その原因が、やがて人類が理解できるようになる領域にある。だが、それをまだはっきりとつかめず、オカルト現象を、つまり謎の何かとしてしか理解できない。それも、この作的には、幼年期にありうるパターンと言えるだろう。明らかにその原因は、幼年期においては、物質の領域が、認識される多くの部分としてあるから。
そういう状態が不安定なのか。そもそも中途半端な物質文明は基本的に脆いものなのか。オーバーロードの管理は、人類のような生物の、幼年期における”唯物論的宇宙からの離脱”までの、安全を確保するためのものみたいでもある。その管理は、物質的力によって行われる。オーバーロードは完全なる物質的存在であるから、それは当然。そして、その場合、人類が問題としていた部族間とか国家同士の対立とか、とにかく様々な争い事、そういうものみんな無知な子供の失敗みたいである。
ようするにオーバーロードは、その圧倒的科学力を、無言の抑止力的に置いて、人類世界を1つの国家(世界連邦)みたいにしてしまう。
人間社会、世界内における全体としては無益な争いへの、クラークの批判精神もけっこう見えるか。
誰にとって受け入れがたい真実か
しかし、少なくともそれまで人類が、「平和」と言っていたような平和を実現したオーバーロードが、代わりに何かを奪ったか、という議論。
それは宗教の問題にも繋がる。
つまり「みずからの生活を律する自由を失いました。神のお導きによってみずからの生活を律する自由を」とか。
さらにオーバーロードのカレルレンの見解は興味深い。
「そういうやつは、世界のどんな宗教にも、必ず一人や二人はいるものです。彼らはわれわれが理性と科学とを代表していることを知っている……われわれが彼らの神をその台座から引きおろすのではないかと恐れている……科学が宗教を破壊するには、ただそれを無視するだけでいい。それだけで、その教義を論破するのに劣らぬ効果があるものです。わたしの知るかぎり、ゼウスやトールの非実在を実証した者はない。だがこんにちでは、これらの神々を信奉する者はほとんどいなくなった」
こういうのも、ある種の魔法のようだ。驚くべきほど人間という種への理解が深くて、しかもその理解は生物学的とか物理学的とか、そういうものでなく、文化や思想というような、社会内現象(?)についてとか。
そして「地球人の信仰を破壊してみたところで、何も楽しくはないのですよ。だが、世界中の宗教全部が正しいということはありえない」
こんな指摘は、別に宇宙生物が存在しようがしまいが、すでに大昔から、多くの人間たちにも言われてきたものだが、それを地球生物よりもはるかに物事をよく知っているだろう宇宙生物に言わせるあたり、このような考え方に関してのクラークの自信も見えるか。
しかし、そういう考え、本当に多くありうるのだろうか。
この宇宙が実際どういうものにせよ、完全に間違っている認識を我々が持ってしまっているとして、それが(宗教的なものかどうかも関係なく)、より優れた生物に真実を告げられたために崩れた場合、我々は、ただ世界観を突然に変えられたくらいで、強い怒りや悲しみをどうしようもなく抱いてしまうくらい、例えば知的好奇心とかがないものだろうか。
宇宙の真実を知って、それが自分の信じてきたもの、その可能性が高いと考えていたもの、理解できていると考えていたものと違っているものだったとして、それは本当のことを理解できた喜びや楽しさを帳消しにするくらいに悲惨なことみたいに感じる人、多いだろうか。
クラークは多いと考えていたのだろうと思う。おそらく、自分は、たいてい昔の人より物事を知っているであろう現代人、と自負している多くの人と同じように。
慈悲深さか、計算高さか
オーバーロードはなかなか姿を現さないが、それは人類の受け入れの準備を、つまり人類の変化を待っているというような。
しかし物質的操作ではなく、時間をかけて待つという行為は、精神構造の特別性の示唆も同然かもしれない。例えば、人類のそれよりもはるかに高度と言えるような、すごいテクノロジーを持っているのなら、数十年、数百年先とかの未来の予測できる段階(あるいは、結果的にそうなってほしい段階)までさっさと物質を操作して、変化させることができないだろうか。
だがオーバーロードは、それはしない。もしそれがある種の慈悲深き行為というよりも、できないというのなら、それをどう考えるべきか。
オーバーロードは、人類を「長期的な記憶を持つ種族」と表現もするが、さらに自分たちも人類のように「失敗したことがある」。そして失敗してしまった時は「待つ」とも。
オーバーロードの視覚的な姿に関してのちょっとしたトリックは、SF的で面白いと思う。
物質領域の限界生物
オーバーロードは少なくとも、昔ながらの唯物論的宇宙における、最高の状態に立っているというような、そういう生物の印象。ただ少なくとも、この作の描写的には、それは普通に、1つの方向の到達点というよりも、1つの階層の到達点というような印象が強い。
そういう設定は、よくある還元主義的精神の影響もあるだろうか。つまり、物質はこの宇宙全体の中での根本的な原理の階層とは考えにくい。だから全体において、その幅広い部分に対して(おそらくもっとはっきり、「重要になるのは」とか言ってもいいだろうが)影響力を持つのは、(少なくともオカルト現象の原因である領域の)非物質。
それは決して、唯物論的生物には到達できないものも有している。というような考え方は、オカルト現象が実際に存在するとしたならば、その通りだろうと考える向きも多いと思う。クラークも多分そう。
もっとシンプルに考えるなら、つまり、この宇宙において真に重要なのは、コントロールされる物質の集合ではなく、(そういうものが存在するとしたなら)コントロールする高次元意識、とか。
そして、唯物論の領域における、いわば極限の知的生物は言う訳である。
「人間のような生物が羨ましい」と。
四次元時空を含む場合
すでに述べたように、オーバーロードは普通の物質世界における進化の到達点と言えるような、そういう生物であり、つまり物質テクノロジーで実現可能な全てを実現しているような存在だ。だがその到達点、限界というのをどう考えるべきか。
その姿と、人間の種族的記憶と思われる、ある特定の存在への恐怖の関係などは、素直に読むなら、人間の非物質的部分の影響があると思う。ようするにそれは、時間次元における因果関係をいくらか無効化してしまうようなものだが、作中でも説明されているアインシュタインの相対性理論は、基本的には物質の存在する時空の理論であって、物理ネットワーク(でなくとも、物理的システムとしての)の知性にちゃんと認識可能なものと考えられる。
 「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙
オーバーロードは、歴史の中の伝説に関しての真相を知りたいという人類のために、過去を覗き見るためのテレビを用意してくれるが、それこそ、この世界観における時空間というものをどう考えるべきかに関する最大のヒントであろう。
 「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去
「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去  「テレビ」映像の原理、電波に乗せる仕組み。最も身近なブラックボックス
「テレビ」映像の原理、電波に乗せる仕組み。最も身近なブラックボックス
そのテレビ受像機には、「時空の四次元連続体における座標を決定するための一連の精巧な装置が組み込まれている」のだが、それだけではなく、おそらく安定した、その四次元利用のためのものだろう、例によって人間には理解できないような、複雑機械とも繋がっているとか。
宇宙の深淵への旅
終盤にはこの宇宙のイメージもいくらか語られる。
基本的にそれは、物質生物であるオーバーロードが、人間という種が踏み込もうとしている非物質的領域からの影響を介して得られた情報。それは確かに宇宙の構造というか、ありうる部分というか、そういうものと思われるのだが。ようするに、存在可能と思われる全ての世界のパターンというような。
「……その光景は、一瞬の雷光の中に替見したもののように、しんと凍りついている。そして、遠い遠い地平線の上に、地球のものではない何ものかが見える。白いもやに似た円柱の列だ。それぞれわずかに先細りになりながら、海から垂直に立ちあがり、その先端は雲の中に隠れている。それがこの惑星のふちにそって、整然と、等間隔を保って配置されているのだ。生物の手になったものとして見るにはあまりに巨大すぎるが、かといって天然のものにしてはあまりに規則的すぎる」
それは「シデニュウス第四惑星と〈あかつきの柱〉」、「〈宇宙〉の中心部」とオーバーロードは認識する。
しかし旅はそれでも始まったばかり。
「……その惑星は完全な平面だった。遠い昔、その凄まじい重力が、燃える青春の山々。もっとも強大な峰でさえついに数メートル以上には達しなかった山々を、均一の高さにまで押し潰してしまった。しかし、ここにもなお生命は存在した。見れば惑星の表面は無数の幾何学模様で覆われていて、その一つ一つが這いずり、蠢き、そして色を変えている。ここは二次元の世界なのだ。そしてここに住む生物は、どれも一センチの何分の一以上の厚さにはなりえない」
それは「へクキネラックス第二惑星」で、オーバーロードに知られている宇宙の中でも唯一と言えるぐらいに珍しい世界。
さらには、「六つの多彩な太陽が空を分けあっているために、光が変化することはあっても、決して暗くなることはない」世界。「それぞれの重力場の衝突と吸引との中で、惑星は輪を、曲線を描き、とうてい想像もできないほどの複雑な軌道上を運行する。そして、二度とおなじ道を通ることはない」もちろん、そこにも、「やはり生命は存在する……巨大な多面性の水晶は、複雑な幾何学模様を描いて群生している。そして、寒冷期にはたがいに身を寄せあって凝然と立ち尽くしているが、やがて世界がふたたび暖かくなりはじめると、その鉱物性の血管にそって徐々に成長していく」
そのカオス(?)な世界はオーバーロードに知られていなくて、だから銀河系外かもしれないとされるから、シデニュウス星系は、つまり銀河系の中心なのかもしれない。実際そうと思う。銀河系を「島宇宙」とする表現は作中にもあるし、この小説が書かれた年代も、銀河系が小世界と認識されるようになってから、四半世紀くらいしか経ってない。
 「宇宙構造」銀河集団、観測可能な宇宙。フィラメント、グレートウォール
「宇宙構造」銀河集団、観測可能な宇宙。フィラメント、グレートウォール
その宇宙の精神の旅のイメージで捉えられるような惑星世界が、あくまでも惑星であることと、さらに「こんなところにすら生命は誕生する」といったオーバーロードの理解を合わせて考えるなら、むしろ生物の発生には物理的条件が必要で、しかも非物質的存在に近づくパターンは進化の分岐の結果かもしれない。とすると、非物質的存在は物質的存在よりも後に生じたことは間違いなくなると思う。そうなるとこの宇宙は(無限の実在ではないとして)最初は唯物論的というだけの世界だったが、後から特殊な生物によってそうでなくなった、というように考えるべきなのだろうか。それとも、非物質的な領域があって、生物というシステムがそこに触れられるようになるまでに時間があった、というだけのことなのか。
 「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要
「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要
幼年期を終わらせる変化が置き去りにするもの
非知的生物、あるいは科学文明を作ることができない程度の知的生物のことを考慮に入れると、話はさらにわけわからなくなってくる。
まず、地球の管理の初期。人間の動物への、不必要というか、快楽目的とかの攻撃に対する、オーバーロードの怒りはなかなか興味深い。
「人類は、望みとあれば好きなだけ殺し合うがいい……それは人類と人類自身の法律とのあいだの問題だ。しかしもし人間が、食用かあるいは自衛以外の目的で、人間と世界を分かち合っている動物を殺した場合は、そのときは人間はわたしに対して責任を負うのだ」
そして、闘牛を楽しむ者たちにかけた、たった1つの脅しが、人間たちの身勝手な残虐さから、多くの動物たちを救う流れになる。
精神の進化(?)を行うためには、ある程度の物理的進化の段階も必要としか思えないような描写は多くある。結果的には、精神的構造の進化、つまりそれを高度にするということが、科学文明を作るような賢さを派生させる、というだけかもしれないが。
だが、この場合、地球生物の中で、人間とはどういう存在であるのだろうか。
少なくとも物理的進化の段階では、過去のものを完全に消したことはないみたいだ。だが地球生物の精神構造の段階を基準とした連続(グラデーション)を見てみる時、もっとも非物質的存在に近くなるのだろう人間とは真逆の端に存在してるような生物は、何か。つまりそれは、オーバーロードと同じような物質生物なのか。それとも、すでに非物質生物の可能性を秘めた物質生物なのか。あるいは、まだ物質生物とも非物質生物とも確定していない段階が存在するのか(進化段階のあるところで、物質か非物質かの分岐(ルート)が確定するかのような、オーバーロードの認識からすると、この可能性が案外高いかもしれない)。そしてどれにしたって、幼年期を終えようとしている人類のために変化する地球の描写は、なかなか妙と思う。
「……カメラはつぎつぎと子供たちの姿を写し出していた。すでに彼らの顔は、一つの共通したパターンを持っていた……彼らは、眠っているか、あるいは忘我状態にあるようだった……ところがつぎの瞬間、文字どおりあっという間もなく、あらゆる草木、あらゆる生物が、そこから姿を消してしまったのだ。あとに残ったのは、波一つない湖と、蛇行する河と、緑色の絨毯をはぎとられた褐色の山。そして、この破壊作業のすべてをやってのけたあの無言の、冷やかな影たちだけ」
オーバーロードは推測する。「おそらくその霊の存在が邪魔になった……植物とか動物とかの、ごく未発達な霊でさえも。いずれは彼らは、物質世界の存在もやはり自分たちの妨げになることを知るだろう」
宇宙への序曲
これは少なくとも、世間に出ている中では、クラークの最初の長編らしい。
サイエンスフィクションというよりもサイエンス小説という方がしっくりくるような内容の(当時における)近未来小説。
基本的には、後の彼の作品の多くは、ウェルズ的な大胆さがあるように思うが、これはなかなか保守的な印象があって、言うなればヴェルヌ的なのだと思う。
特にコレクター的ファンでもない、ただクラークの有名な作品いくつかが好きというような人にオススメできるかと言うと、結構微妙。
『宇宙への序曲』
むしろ、1951年という、宇宙旅行の夢が本格的に実用的に検討されるようになり始めた時代に、若きSF作家が考えた、宇宙開拓計画のシミュレーションというような意味で、資料的価値が大きいかもしれない。もちろん、あくまでもIFであるが。
しかし、この話でもしっかり説明される、太陽系の開拓の初期段階として重力低い月を拠点基地とする、というような発想は、いったい最初、いつ誰が考えたものか気になる。
宇宙計画はいかにして実現されうるか
いかに計画のための資金が集まったか、というような話もしっかりあり、さらには宇宙開拓計画の中で変わってきた人々の意識の変化など、もうシュミレーションというか、作者の夢の未来の妄想というような印象もある。ようするに「こうなったらいいのにな」感もかなりある。
「一九六二年には宇宙飛行の問題に関する研究に専念するためにインタープラネタリーが設立……この分野での最高の科学者を徐々に惹きつけるようになったのです。彼らは原爆を運ぶミサイルを建造するよりは、俸給は少なくても建設的な計画に従事するほうを選んだのです」
「一部の者たちは過去に固くしがみつき、祖先たちの政治的観念が他の天体に到達した後も通用するものと信じている。宇宙空間を越えるためには、全世界のあらゆる国の科学者たちの一致した努力が必要だったことを忘れている……成層圏の外側に国籍はない。われわれの到達するいかなる天体も、全人類の共通の財産である。ただし、他の生物がすでにそこを領有していないかぎりだ……しかしここに未来永劫にわたって厳かに宣言する。われわれは宇宙に国境を持ちこまない」
個人的には、宇宙船の話とか以上に、例えば「彼の教養をもってしても、ヴィクトリア時代の大発見このかた一般化している科学への恐怖から、完全に抜けだすことは不可能だった」とかいったサイエンスという概念自体の評価に関係する描写が、興味深いとも思う。
しかし、現実のアポロ計画での月面着陸が1969年ということを考えると、1970年にアメリカのロケットが地球をまわる最初の軌道飛行に成功した、というのは、やはり保守的だったのだろうか。
若き日のクラークの、太陽系の生物世界可能性
地球で十分だと考えている人がいるように、未来の太陽系時代の人たちは、「太陽系で十分なのに他の星系なんて開拓する必要があるだろうか」というような議論をしているかもしれない。というような、もっとずっと先の未来のこともいくらか語りながら、やはりこれは”序曲”なので、まず見るべきは太陽系。
哲学的な話として、その太陽系の生物世界の可能性も示唆されている(古いSFや科学史が好きな人には、結構馴染み深い世界観の典型のようで、この辺りも今となっては、むしろ資料的価値が高いと思う)
それは例えば「生命、その起源、および運命について……生命の未知のドラマが繰り広げられるべき宇宙時代について」ある男が語ったもの。
「……巨大な太陽に焼かれる小さな水星は、融けた金属の静かな大海に洗われる、焼けただれた岩の世界……地球の姉妹惑星である金星は、人間が見つめてきた数世紀のあいだに一度も切れめをみせたことのない波打つ雲の層によって、永遠にわれわれから隠されている。あの覆いの下には、大洋や森や未知の生命の活動があるかもしれない。あるいは、焼けつくような風に吹きさらされた不毛の荒地にすぎないのかも……」
さらに火星。「ここにも生命があるのだ。われわれは色彩の変化を見ることができ、それは、われわれ自身の世界では、移り変わる季節を意味するものだ。火星には水がほとんどなく、大気は成層圏のように希薄だとはいえ、植物が、そして、ことによれば動物も存在しうるのである。知能を持つ生命については、決定的な証拠は少しもない」という自信(あるいは期待)は、このくらいの時代のアシモフ(Isaac Asimov。1920~1992)とも共通している印象。
さらに木星と土星。「厚さ何千マイルもの大気に押しつぶされ、そのメタンとアンモニアの大気は、五億マイルまたはそれ以上の宇宙空間を隔てても観測できる暴風によって切り裂かれている。この未知の外惑星、あるいはその先のさらに極寒の惑星に生命があるとしたら、われわれの想像を絶するような不可思議なものだろう。ただ太陽系の温帯にだけ、金星、地球、火星の浮かぶ狭い帯状の区域にだけ、われわれの知る生命が存在しうる」
そして、そういう訳だが、結局我々がいったいこの宇宙のあらゆる生命のパターンのどのくらいを知っているのか、我々が語る普通の生物とは、いったいどのくらい狭いパターンなのか。というような話が続く。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「宇宙は、生命に対する敵意などは持たず、ただ無関心なだけだろう。その不思議さは、新たな機会でもあり、試練でもある。知性は、その試練に立ち向かうだろう」とか、普通に前向きとも思う、このような見方は、後のクラークの作品でもかなり感じられる。
渇きの海
個人的にはクラーク作品の中でも特に好きな1作。
管理しきれていない世界を利用した遊び、ビジネスにつきまとうリスクを描いた、パニックSFの王道と思う。
『渇きの海』
影響あるかわからないが、例えばクライトン(Michael Crichton。1942~2008)やチャイルド(Lincoln Child)のような作家が好きな(まさに自分みたいな)人には、まず間違いなくこれはオススメできる。例えば『ジュラシックパーク』や『ユートピア』などは、いくらか(脆い管理を逃れた、扱いきれないリスクから始まる、小世界全体の暴走とでも言えるような)テーマ(?)的にも近いと思う。
 レリック、ユートピア、マウント・ドラゴン「リンカーン・チャイルド」
レリック、ユートピア、マウント・ドラゴン「リンカーン・チャイルド」
〈渇きの海〉とは、月の表面をいくらか、あるいは大部分覆っているという説があったらしい”塵の海”のこと。この小説は実際にそれがあって、その海を渡る観光ツアーが行われているという未来が舞台。だが、地球には存在しないその特殊な海で、遊覧船セレーネ号が見舞われる災難が描かれている。
月面の塵の海説
現実には、渇きの海は現在まで月に確認されていないし、もう普通に幻の説だったことは間違いない。しかし、むしろだからこそ、この小説における空の描写は、これが書かれた当時以上に興味深いかもしれない
「……灰色の粉末状の表面が、星々に連なるところまで、果てもなくひろがっている……この〈海〉が液体なのか固体なのかは、だれにもわからない。平坦でなんの変化もなく、この不毛の世界ではいたるところに見られる無数の割れ目や裂け目も、ここにはまったくない。ただひとつの丘も岩も小石も。とにかく、この単調な均一性を破るものはひとつとしてない……水をたたえた海ではなく、塵をたたえた海」
だからこそ、「人類の持ついかなる経験とも相容れないもの」。未知の領域。
塵の一部は星の残骸とされる。つまり過去に月の表面に落下した隕石の破片。月の昼夜の極端な温度差が引き起こす、岩の膨張収縮により表面から剥げ落ちたものも。
機械視点の通信ネットワーク
通信を中継するコンピューターの描写で、超高速の電子スケール世界における長い5秒。
つまり、ネットワークの乱れがあり、それを確定する動作(特定回路を閉じる)までの待機時間。長い5秒が「無限のような」とも表現されている。
 「ネットワークの仕組みの基礎知識」OSI参照モデル、IPアドレスとは何か
「ネットワークの仕組みの基礎知識」OSI参照モデル、IPアドレスとは何か  「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか
「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか
クラークは通信技術者として働いていたこともあり、その経験のためなのか、通信関係の描写に関しては結構拘りを感じる。
この作品においては、通信機械は、ネットワークとしての舞台、乾きの海で危機に陥る船を含む不完全な管理システムの一部、連結部。
機械が感知した異常事態が、人間たちに伝わるまでの描写は、物語そのものには必要ないかもしれない。しかしそういうのがあるおかげで、人間が機能している宇宙システムの一部と、全体の違いも実感しやすい。
地球でない環境で、まだ多くのことが理解できてない状態で、それでも人はさっさとそれを利用しようとする。少なくともこれまでは科学テクノロジーの発達にも重要だったと考えられる”人間社会”という領域の中では、その中での自身の地位、立場をよきものにしようという野心に溢れた者たち(ようするに金が欲しい者たち)が、どうしたって競争したがるから。
こういうのも、SFの醍醐味だろう。宇宙、人間、人間社会。テクノロジーが結ぶあらゆる要素のネットワークと、そうした繋がりのために、全体から見るとほんのわずかな部分の身勝手が、広い領域に影響し、社会の領域の他の成員たちに危険をもたらしてしまうモデル。
もちろん現実でもそういうことはあるだろうが、そもそも構成ネットワークが複雑であれば複雑であるほど、全体像はつかみにくくなってしまうと思う。それが実際どのくらいのスケールの危機なのかも実感しにくい。それを描けることが、創作というもの自体の興味深いところかもれない。
文明から切り離された閉鎖空間サバイバル
この話は月の塵の海で船が遭難するという話だが、船が過酷な環境を切り抜けていくというようなものではない。救助が難しいところで動けなくなった船という、いわば閉鎖空間でのサバイバルが中盤以降はずっと続く。
文明から切り離された空間。宇宙時代に、様々な娯楽機械が、まるで意味なくなってしまう。生きているのに、おそらく助かることなく、死を待つだけかもしれない状況。
そうした中で、この話はクラークの作の中でも一般人的なキャラクターが多いので、突然に崩れた安全がなかなか恐ろしく感じやすいとも思う。
民族問題。UFO現象。乗客たちの様々な話
過酷なサバイバルの中で、色々な乗客たちの色々な話もあるが、いくつかの危機を予想もした物理学者の、民族と国家に関する話などは、クラーク自身の考えもかなり含まれてると思う(他の作品で出てくる、似たような話とかなり共通してもいる)
「……わたしは、オーストラリア人であって、原住民族であることは二義的なものです。ただ、わが白人の同胞が、しばしばかなり愚かであったことは認めればなりますまい。なにしろわれわれを愚かだと考えるくらいですから。前世紀ごろには、われわれを石器時代の未開人だと考えてるやからがたくさんいました……わたしの祖父は、紀元二〇〇〇年という年を迎えるまで長生きしました。けれども最後までついに十以上の数を教えることは覚えませんでしたし、皆既月食について言ったことは、『イエス様の石油ランプが、はあ、みんな食べられちまっただ』というものでした。現在わたしは、月の公転運動に関する微分方程式を書くことができますが、自分が祖父より偉いなどと思ったことは一度もありません。もし時代をとりかえっこしたら、祖父はわたしなどよりはるかに優秀な科学者になっていたでしょう……祖父には数を数えることを学ぶ機会がなかった。いっぽうわたしは、砂漠で家族を養ってゆく必要がなかった。これはすこぶる熟練を要する、とても片手間なんかではできない仕事です」
アーサー・C・クラークは、1950年代から長編を書き始めたSF作家。一般的に行ってかなり知識人であることは間違いない。つまり知識人のイギリス人。もちろん第二次世界大戦も経験している。
いったいいつまでが、(大多数にとっての)賢き西洋人と、植民地の野蛮人たちの時代だったのだろうか?
また、個人的にもう1つ興味深い話題として、例によってオカルト現象と関係したものがある。
そもそも、船が災難にあっているのは、「自分のせいなのだ」と語り出す男。つまり、人類が太陽系の開拓を始めるよりもさらに以前の時代から、すでに地球を監視しているような星系外からの存在という妄想。
「空飛ぶ円盤のことはお聞きになっておられるでしょう?」基本的には、それは宇宙旅行に関する古い書物で紹介されてたりするバカバカしい迷信で、若い世代には知らない人も多いというような感じ。
この小説は1963年の作品らしいが、その頃にはすでに、宇宙人の侵略とかUFOの登場する映画などもある。しかし21世紀まで、ある意味、SFの絶対的1ジャンルとして残ってるだなんて、クラークも想像してなかったかもしれない。事実関係はともかくとして、少なくともそれ(UFO神話関連のいろいろ)は、当時の多くの知識人が思っていたほど簡単に解ける謎でなかったことだけは確かと思う。
 「ケネス・アーノルド事件」空飛ぶ円盤、UFO神話の始まりとされる目撃譚
「ケネス・アーノルド事件」空飛ぶ円盤、UFO神話の始まりとされる目撃譚
ただ、ここで語られるのは非常にぶっ飛んだ話で、いわゆるトンデモ本に書かれてそうなものだ。いくらかクラークのオリジナルもあったかもしれないが、多分、多くの部分は、単にオカルトマニアとしての彼自身が、様々な本などで出会ってきたものだろう。
「……〈宇宙〉では、善悪の両勢力が二手に分かれて戦っているのです。ちょうど地球上でとおなじように。円盤人の一派は、われわれを助けようとする。もういっぽうは、われわれを食いものにしようとする。このふたつの勢力は、何千、何万年にもわたって死闘をくりかえしてきた。ときには、その衝突が地球を巻き添えにすることもある。アトランティスが消滅したのも、じつはこのためなのです」
そうした話をバカげたものとして知っているハンスティーンという人は、そういうのが、結構オカルト話としては典型的みたいな反応。「アトランティスは、遅かれ早かれ、いずれは舞台に登場するのだ。アトランティスでなければ、レムリアかムーが。これらはいずれも、このての精神的平衡を失った、神秘大好きの手合いには、ひどくアピールするものがあるらしい」と。
 「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。
「アトランティス」大西洋の幻の大陸の実在性。考古学者と神秘主義者の記述。  「ムー大陸」沈んだ理由、太陽神信仰の起源、忘れられた世界地図、機械仕掛けの創造宇宙
「ムー大陸」沈んだ理由、太陽神信仰の起源、忘れられた世界地図、機械仕掛けの創造宇宙
クラークも、やはりオカルト好きなのだろうと納得するべきか。この現象に関しての一般的見解の(IF未来の)流れも、ハンスティーンが思い出してたりする。
「この問題が、ある心理学者グループによって徹底的に究明されたのは、ハンスティーンの記憶に誤りがなければ、一九七〇年代のこと。結果、彼らは結論した。ほぼ二十世紀のなかごろ、全人類のかなりの割合を占めるひとびとが、地球はもう絶滅しかけていると信じるようになった。地球を救う道は、宇宙からの調停にしかない、と彼らは考えた。自らに信頼を失った人間は、救いを大空にもとめた」
だが空飛ぶ円盤神話は、あっさり終わった。
「……心理学者グループは断定する。ひとつはたんに飽きられたということ。もうひとつは、人類自身が宇宙へ進出する先駆けとなった、例のIGY、すなわち国際地球観測年」
つまりそのIGYなる、大空の徹底的な観測が、そんなものが存在するなら必ず見つかるはずのUFOを見つけられなかったことが、重要な転換点となったと。
楽園の泉
互いに大して関連もないような色々な話が、作られた世界観を照らしていくような話だが、全体の構成的には『宇宙への序曲』のような、人類のテクノロジー開発の流れを描いた作品と思う。
つまり、いわゆる”軌道エレベーター”の開発物語。そういう意味でちょっとIF未来のドキュメント的な感じもある。
また、クラークの仏教趣味が特に色濃い印象。
ある意味、それまでのクラークの集大成的な作品なのかもしれない。
『楽園の泉』
『渇きの海』は、ほぼ全編を通して危機が連続するパニックSFだったが、これはそうでない。いわゆるカオスというかバタフライエフェクト的な、つまり複雑ネットワークとして考えられるような領域内での、ある出来事が全く予想(想定)されてなかった別の出来事の原因に結果的になるというようなパターン例として、ポジティブなものも。
「……例の南極パイプライン極地の広大な鉱床から液化した石炭を世界の発電所や工場へ送るために建設された二一世紀の奇蹟に関するもの……生態学的な陶酔状態にあった地球建設公社は、パイプラインの残存する部分を撤去し、陸地をペンギンに返還することを提案したが、たちまち抗議の声をあげたのは、そのような文化破壊行為に憤激した考古学者たちと、ペンギンは遺棄されたパイプラインが大好きなのだと指摘する動物学者たち。パイプラインはペンギンたちにかつてなかったほどの水準の快適な住居を提供し、このためシャチたちももてあますほどの爆発的繁殖率をひきおこしたのだった」
もちろん、地球生態系というネットワークにおいて、ある生物種の明らかな人工的原因のための大繁殖を、ただ盲目的に「いいこと」とか考えるのは、それこそ複雑系の中の、危機に役立てないバカ部品のそれなのかもしれないが。
 「ペンギン」鳥なのになぜ飛べないのか、なぜ泳ぐのか
「ペンギン」鳥なのになぜ飛べないのか、なぜ泳ぐのか
しかし構成的に、問題意識を促すような描写も控えめぽいから、とりあえず純粋なエンターテイメント的に、SFドラマを楽しみやすいと思う。
神を目指した王。芸術家としての王
作中で扱われてる中でも、特に、タプロバニーという島国(クラークが創作した、南アジアンなイメージの国)の古代文明、現代パートでは古代の伝説的な、猿のハヌマンとカーリダーサという王子の物語について。
その実在をかなり有力にしたという、2015年の、考古学者の一隊の調査。宮殿内で、破壊されたらしい小さな聖堂の発見にニュートリノ探知器が使われている。
さらに深いところで第二の舎利室があることの発見。
また昔話にて。広大な土地に巨大な建築物に、また、自身が独占した美しい女たち。偉大なカーリダーサ王は、それは「夢がかなった」とも表現する。「嫉妬深い坊主どもがいかに逆宣伝しようと、自分はついに神になった」と。
舎利とはもちろん、仏(普通はシッダールタ。つまり釈迦その人)の遺骨。ようするにタプロバニーの古代王国は仏教と関連強いのはほぼ間違いない。一方で、生きながら神を目指した王が行うことは、人を含むあらゆる資源の独占。
それはずいぶん俗的な神な印象で、クラークの他の小説でたびたび言及されている、ユダヤ系な唯一神とは別次元的とすら言えるかもしれない。
 「釈迦の生涯」実在したブッダ、仏教の教えの歴史の始まり
「釈迦の生涯」実在したブッダ、仏教の教えの歴史の始まり
カーリダーサはペルシャ人の芸術家イスファハンの働きに感謝していたが、「役目を終えた後に盲目にされるだろう」という噂のために死んだ彼が、そのような噂を真に受けたことを悲しんだりもする。
「……芸術家同士のあいだで視力の恵みを奪おうとするようなまねをするはずがないことぐらい、わかってくれてもよさそうなものだったのに」と。
こういうのは神の人間的な部分というより、やはり神を掴みきれずに俗的な定義をしてしまった人の、他の一面みたいな印象もあるか。
俗的でも何でも、まさに偉い王とか神と呼ばれるような存在。人々から尊敬されるというより、人々を含む多くのものを自分のものにしてしまっている何者か。そういうものに対して、嫉妬してしまうような、そういう精神がある。仏教における仏とはそのような世界観から離れたものみたいなイメージもあると思う。クラークはどう考えていたのだろうか。
小さな素材の重要性
いくらかのSF的アイデアも、やはり近未来を意識したものが多い印象。
例えば、それを用いれば、木を切り倒すことも簡単な、太さが数ミクロン(マイクロ?)しかないワイヤー。
「……二百年間にわたる固体物理学の成果……連続擬一次元のダイアモンドの結晶……実際には純粋炭素ではない……正確に調整された量の微量元素がいくらか入っている。結晶の生長速度に重力が影響しない人工衛星工場でしか、大量生産はできない」というようなもの。
例えば現実のカーボンナノチューブ(ナノメートルサイズの円筒(チューブ)状物質)みたいな、いわゆるナノマテリアルは、マイクロよりさらに小さなスケールの素材(1マイクロ=1000ナノ)。ナノというか、ミクロな(つまりとても小さな)素材の実用化こそ、(多分軌道エレベーターに限らず)宇宙時代の建造物のための重要な第一歩、鍵というように、クラークは理解していたのだと思う。
作中では、「そのような科学の驚異が、(言わば新時代の建造計画と)何の関係があるのか」という問いに、工学者が「この材料には多くの応用の道がある……この繊維によって、タプロバニーは、すべての惑星への踏み石となるでしょう。もしかしたらいつの日にか、星への踏み石にまで」と答える場面もある。
一応この小説の世界観では、すでに人類は、火星、水星、月に自立した植民地を築いている。軌道エレベーターは、ロケットよりもずっと安全で効率的な移動方法としての意味もある。
信仰の物理的原理。ミスカトニック大学のある世界観
軌道エレベーターの建造計画を描いたドキュメント的な物語という本作において、いくつかある(あってもなくても別によさそうな)サブ的な話の中でも、特に本編と独立しているイベントとしてあるようなのが、”地球外の知性との人類の接触”。
しかし、物語に必要かどうかはともかくとして、それ単独で抜き出してみると、やはりなかなか興味深いものではある。
その話が出てくる前のある書物からの引用文からして、まず注目してしまう。そこには、意識とか知性も物質原理として捉える、サイバーパンク的視点が現れてるように思う。クラークは、同じ小説の中で、俗的な神の概念と、そういった世界観から切り離された存在の可能性も描く。もしかしたら、宇宙全体の中で知性とか知的生物というのがどういうものにせよ、精神構造が生んだ様々な神の概念、そういうもの全てを超越しているような精神性を考えたかったのかもしれない。例えば、そういうもの(超越的存在)が間違いなく実際に存在する宇宙を舞台にした『幼年期の終わり』とはまた違う方向性の、神(?)へのアプローチとも言えるだろうか
また、例えばニュートリノ探知機を使う考古学者チームはハーバード大学のチームだ。もちろんハーバード大学というのは現実にも存在している大学。だがこの、宇宙の知性との接触の話の前に引用されている書物を出版している大学は、(少なくともこの小説が書かれた当時においては)架空のはずの大学である。「ミスカトニック大学」。明らかにクトゥルフ神話で出てくるものだ。別にこの話を、例えばラヴクラフトの世界観と繋げて考える必要もないだろうが、その名の大学が存在する意味を考えるのは、なかなか面白いかもしれない。
 「クトゥルフ神話」異形の神、生物の伝記。宇宙的恐怖のための創作神話
「クトゥルフ神話」異形の神、生物の伝記。宇宙的恐怖のための創作神話
「……われわれは、次の設問への答を、少なからぬ不安をもって待たねばなりません。
(a)両親がゼロ、一、二、またはそれ以上の生物が、もし宗教的概念を持つとすると、それはどんなものか?
(b)宗教的信条は、発育期に直接の親たちと密接な接触を保つ生物のあいだにのみ見いだしうるものなのであるか?
宗教が、もっぱら猿、イルカ、象、犬などに類似する知的生物のあいだにのみおこり、地球外コンピューター、白蟻、魚、亀、社会的アメーバの中にはおこらないことが明らかになるとしますと、われわれはある種の不快な結論をひきださればならないでしょう。ことによると、愛も宗教も哺乳類の中にだけ、しかもほぼ類似の理由によって生じるものなのかもしれません……
(比較宗教学教授エル・ハジ・モハメッド・ベン・セリムのブリガムヤング大学における就任演説、一九九八年)」
「……いわゆる意識拡大性薬剤への探究が、脳に自然に成長する”催信仰性”物質の発見に到達することによって、それらの薬剤がまさに反対の作用をもつことを証明したのは、まったく運命の皮肉の一例である。いかなる信仰のきわめて熱烈な信者であろうとも、二-四-七-オルソパラテオザミンの慎重な投与によって、ほかのいかなる信仰にも改宗させられるという発見は、おそらく宗教がこれまでに経験したもっとも破壊的な打撃だったろう。いうまでもなく、スターグライダーの到来を迎えるまでは。(R・ゲイバー『宗教の薬理学的基礎』ミスカトニック大学出版局、二〇六九年)」
宇宙生物の機械との対話
スターグライダーというのが、つまり太陽系外からやってきた機械と思われる宇宙船。
「太陽系を走査し、人類のあらゆるラジオ、テレビ、データ伝送を傍受して得た」様々な情報をもとに英語と中国語を覚えたらしいそれは、テレビを利用して、人類との対話を試みてくる。
スターグライダーは、「六万年前にプログラミングされた一般的命令に従って作動しながら、完全な自律性を持っている」恒星間宇宙探測機と、後には理解される。それは使節と探検者との両方の機能を兼ねそなえ、恒星系に入った時に、科学文明を発見すると、情報交換を始めるというような。
「……何世紀もの間、いや、おそらくスターグライダーが次の目標に到達するまで哲学者たちは、相手が人間のあり方や課題をどこまで理解したかについて、論じつづけることだろう。だが、ひとつの点では、重大な意見の違いはなかった。スターグライダーが太陽系を通過した百日間は、宇宙、その起原、またその中での自分たちの位置づけについての人類の見方を、根本的に変えてしまった。スターグライダーが去ったあと、人類の文明は絶対にもとには戻らないだろう」
人間が、この宇宙で孤独な知的生物でないことを理解し、「そうして世界が変わった」というような、クラーク自身がかなり好んで多用していたぽい(そして後世にもかなり影響与えていると思われる)このような表現が、しかしエレベーターの建造の物語の中に入れられているというのは、なんとも奇妙、だろうか、やはり。
スターグライダーの語る世界観は、かなり『宇宙のランデブー』シリーズで明かされていく宇宙の秘密に近い印象もある。
あれは1作目だけなら、(疑問に答えてもくれないという意味でも)こちら以上に謎の存在だが、後のシリーズはむしろ、ここでのスターグライダーの話を、長編としてリブートしてるみたいな。
銀河帝国の崩壊
クラークの小説の中でも、特にかなりの未来を舞台にしていて、例の警句(高度に発達した科学は魔法と~)の考え方のためもあるのか、ファンタジー的な雰囲気も結構ある。
『銀河帝国の崩壊』
宇宙スケールというか、宇宙の構造やシステムみたいなものが、物語や設定の中で重要と思われる作の中でも、実は結構異色作なのかもしれない。クラークのスケール大きめな作は、人類が宇宙に誕生するはるか以前からすでに存在していた多くの生物たちが、すでに宇宙の謎の多くを解き明かしていて、それを人類が知るというようなパターンが多いような気がする。しかしこれに関しては、遠い未来、すでに人類もかなり科学文明を発展させて、しかし、そんな栄光ももう昔話というような感じ。
遠い未来で語られる、それまでの未来の物語
構成的にはわりとミステリー風なところがある。つまりは、かつて銀河国家まで作った人類を、最初の小さな惑星まで追い詰めた謎の敵(宇宙のさいはての暗黒のなかからの〈侵略者〉)とは何者であるのか、とか。それからどれくらいが経っていて、人類はなぜ再び、自分の生きる場を広めようとしないのかなど。
歴史の内容も、話の進みとともに結構二転三転したりするところもある。
「かつて、地球の上空は、異様な形のもので満たされたことがあったのを、アルビンは知っていた。空中から、大きな船が、見たことも聞いたこともない宝物を積んで、ダイアスバーの港へはいってきて停泊した。しかしそれは五億年も昔のことで、歴史がはじまる前に、港はすでに吹きよせる砂で埋まってしまっていた……」
「……あなたは一生ずっとダイアスパーで暮らしてきたので、人間は町に住むものと考えるようになったのです。でも、アルビン、それは真実ではない。機械が、わたしたちに自由を与えてからこのかた、二つの文明の型のあいだでは、しょっちゅう対立があったのです……」
「……《侵略者》は立ち去ってしまったが、世界はまだ、その傷口を癒しつつあった《過渡時代》の混沌……後に《大人》と呼ばれるようになったひとりの人物が現われた。その人は三つのふしぎな機械を伴っていた。《大人》の召使いで限定された知能を持つ……はるかに遠い星のなかには、戦争の大波にのみこまれないで、残っている人類の孤島が、いまだにあるのかもしれない」
「……恐れているからです。歴史のはじまりに起こったことが、また起こるのを恐れているからです」
銀河帝国と狂った精神。ファンタジー的未来世界
終盤に語れる銀河帝国の真相というか、忘れられていた物語は、『幼年期の終わり』で描かれていたような、唯物論的世界からの巣立ちみたいなものでなく、あくまでも、物質生物として、非物質的現象もあるかもしれないこの宇宙の冒険可能性というような印象。
ただしその始まりは例によっていつものパターンであるすでに人類以前の宇宙の長い時間が人類よりもはるかに優れた化学文明を築いた多くの生物たちをこの宇宙に生み出していたそしてその接触によって人類は自分たちがこの宇宙でどれほどちっぽけな存在であるかを知る。
「人間は、いつかは、空間の深みを征服できると信じて疑わなかった。また、宇宙に同類がいるとしても、人間の知能にはおよびもつかないと信じていた。それが今、その双方ともまちがっていて、遠い星のなかには、人間よりもはるかに偉大な精神があったことを知ったのである」
しかしこれはそれで終わりの話ではなくその先まである人類は最初は他の所属に助けられながらも自分たちも同じレベルに上がろうとよく努力した。やがて遺伝学と精神の研究に傾倒したが、それは進化の極限を目指す研究(他の話にも見られる、生物系の典型的物語とほぼ同じパターン)
そして「人間は永遠に生きることができ、精神感応力を養うことにより不思議な諸力を使えるようになった」
やがて人類を含む多くの種族たちの巨大な共同体。銀河の帝国の時代。人類はいつからかあらゆる種族の世界観がその感覚器官に依存していることを完全に理解する。(それは、特に哲学的には古くからある説だろうが、クラークもこの見方を支持していたのだと思う)。そうして宇宙の理想とすべき真の姿を実現するための、肉体的制限から解放された精神、純粋な知性のみの存在を造る計画が始まった。そして、その結果から始まった銀河帝国の崩壊の物語は、やはりファンタジー小説の序盤で語れる古い伝説みたいな感じで、クラークの好みがもろに出ている印象。
「夢と現実のあいだには、およそ五億年……いくたの文化の興亡があり……結末は、ほとんど銀河系を壊滅させるほど、惨澹たるものだった……銀河の上には恐怖の屍衣が垂れさがり、その恐怖は〈狂った精神〉という名前と結びついている……純粋知性は創造されたが、それは精神異常だったか、あるいは別の資料から判断して、いっそう当たっていると思われるのは、徹頭徹尾、その企てにたいして敵意を持っていた。何世紀にもわたって、その純粋知性は宇宙を荒らしまわったが、最後に、今のわれわれには想像のつかない、なにかの力によって屈服させられた……しかし《狂った精神》は不死……銀河系のさいはてに追い払い、われわれには、とうてい理解できない方法で幽閉された。その牢獄こそ、《黒大腸》として知られている、ふしぎな人工の星……」
イルカの島
イルカの知的能力を重要なガジェットとした小説で内容的には少年の一時の冒険を描いた、多分ジュブナイル系の(つまり少年少女向けの)小説。
仏教の精神鍛錬とか物質を超越した神の概念とかに強い関心を持ってそうなクラークはそういう興味が原因かは分からないが結構その作風が真面目とか上品とも言われている。そういう意味では、子供向けの物語は相性いいのかもしれない。
『イルカの島』
人間と交流する、作中のイルカのキャラクターは、脳を改造されたとかではなく、普通のイルカ。
イルカ族はとても賢く、しかし人間のレベルではない。あるいは、人間と比べると、まだ科学文明を作るための発想をどこかで得られていない。というような感じ。
問題となるのは、コミュニケーション手段。実際にもイルカと人間は、コミュニケーション手段の問題さえ解消できれば、知的生物同士らしい意思疎通ができるのではないか、と考える人は結構多いが、この小説では、まさにそういうことが全然ありうる、というような設定。
作中では、お互いの言語を覚えるという、かなり直接的な方法も描かれている。
 「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
「クジラとイルカ」海を支配した哺乳類。史上最大級の動物
また、イルカは多くの未開地域の原住民と同じように神話すら持っている。そしてその神話の中で出てくる、1万年以上前に地球にやってきたと思われる宇宙生物らしき何か、というような描写は、いかにもクラーク的か。
イルカはどのくらい人間に近いか
イルカ族は、人間とは別の知的生物であっても、宇宙生物に比べると、もちろん人間にも近しい。それで、ここでのイルカの立場は、まるで高度な文明と接触した未開地域の原住民のようである。
作中でも指摘されているが、イルカとシャチの問題、それはまるで、「穏やかな村の者たちが、人食い人種を恐れている」のだが、それを助けるべきかどうか、というような。そんな話と関連付けられたりしている。
シャチとイルカ。人間はどちらの味方になるべきか、あるいはあくまで中立であるべきか。というような議論の中で、主に重要な争点となっているのは、知的レベルと、(これは確実に人間(それも典型的な現代人の)基準と言っていい)道徳のこと。