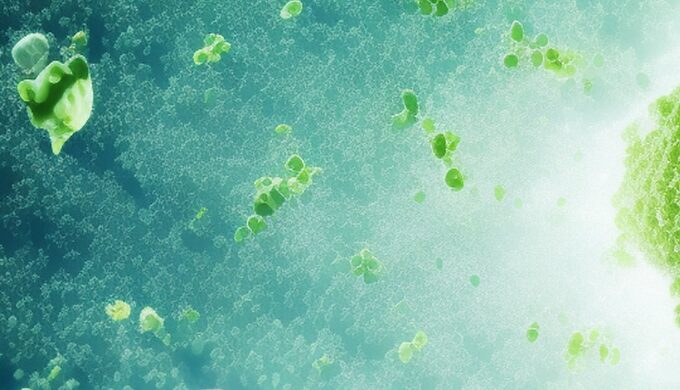五大人種を定義した生物学者
コーカサス人(Caucasiae)、モンゴル人(Mongolicae)、エチオピア人(Aethiopicae)、アメリカ人(Americanae)、マレー人(Malaicae)。基本的には肌の色を重要視した古い人種分類の中でも、特に有名な、この5分類を考案したのは、一般的には、ドイツ生まれのナチュラリスト(自然哲学者、生物学者)、ヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハ(Johann Friedrich Blumenbach。1752~1840)とされる。
生物学的な興味を横においても、人類の歴史の中で、近代の科学的人種差別に重要な影響を与えたということで、彼の定義した人種区分はなかなか重要と言えよう。ただし彼自身は、自身の人種研究における結論として、人種区別はあくまでも表面的な容姿が基準で、知的能力などに関して明確な差はないとした。
実際、彼はプライベートでは、(時代を考慮すると)かなりの人種平等主義者でもあったとか。
 「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種
「近代生物学の人種研究」差別問題、比較解剖学、創造された世界の種
その生涯の中の長い時間を、ゲッティンゲン大学の教授として過ごしたブルーメンバッハは、1775年に書いた博士論文『人種の起源種(Degeneris humani varietate nativa)』の三度目の公式出版のもの(つまり1795年の第三版)で、例の五大人種分類を定義した。
元々の論文では、崇拝していたリンネ(Carl von Linné。1707~1778)に習った、四大人種分類を書いていたらしい(具体的には、論文の最初の版では、後にマレー人として分類された者たちがモンゴル人と一緒くただったという)。しかし後の版で、新たに五代分類として再定義した。
三版の前書きでは、「リンネの仕事はもちろん素晴らしいが、彼の研究は今となっては古く、ただただ盲目的に従うことはもはやできなかった」というようにも書かれてたりする。また同じ前書きには、様々な人種の頭蓋骨コレクションにアクセス(利用)できるよう尽力してくれたらしい友人への感謝が書かれているが、やはり最初の論文から20年の間に学んだことが多かったようである(それで、彼はあらためて人種分類を定義した)。
退化の進化論。ビュフォンとの世界観の違い
生物学史においてブルーメンバッハの名は、環境の影響による生物の退化論や、前成説の否定についてとかでも、よく知られている。その辺りの関連は、いくつかの言語に翻訳され、版も重ねた『自然史ハンドブック(Handbuch der Naturgeschichte)』などでも重要視されている。
退化論。すなわちあらゆる生物種には、ある「完成した形態(完全体)」というようなものがあり、しかしその構造の各部分が、様々な環境の影響を受けることによって劣化してしまうことがある。それで結果的には、原型からいくらか劣化している、様々な変種がこの世界に発生することになる。それが生物の多様性の理由だとするのが、昔の退化論者の通常の見解。
そのような現象(生物種の退化のための変異)を語った者としては、ビュフォン(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon。1707~1788)が特に有名だが、近い時代のブルーメンバッハのそれ(退化論)も、よくビュフォンのと比べられたり、並べられたりしている。
 「ニュートン」万有引力の発見。秘密主義の世紀の天才
「ニュートン」万有引力の発見。秘密主義の世紀の天才
2人の理論で、かなりはっきり共通しているのは、どの生物種にも、基本的には環境の影響を受けない(あるいは少なくとも非常に劣化しにくい)、本質的な、いわば「内的鋳型」があるというもの。これはつまり、ある生物種を、別の生物種とはっきり分ける印となる、共有特徴のようなもの。結果的に、この世界のどんな生物も、同種内では、最初の共通祖先、つまり完全体のそれ(内的鋳型)を引き継いではいる。
ブルーメンバッハ自身も、彼の本の翻訳者たちも、種の退化というのは、ある種の”進化(evolutionis)”というように考えていたようである。実際に、想定される内的鋳型というもののスケールによっては(例えば、それをそもそも生物というものを定義する基準となる何かに限定すれば)そこからラマルク(Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck。1744~1829)やダーウィン(Charles Robert Darwin。1809~1882)以降の、枝分かれする系統樹の進化論を連想するのも容易いと思う(ただ変化の流れとしては、ある種の形成から退化のための変化なので、全く逆になるだろうが)。いずれにしろ、ビュフォンもブルーメンバッハも、各生物種の内的鋳型は、すでにそこそこのサイズの構造で、共通祖先の数をあまり少なくは考えていなかったようだが。
 「ラマルク。進化論と動物哲学」用不用説、生物世界唯物論、そして系統樹の発見の物語
「ラマルク。進化論と動物哲学」用不用説、生物世界唯物論、そして系統樹の発見の物語  「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
またビュフォンは、生物系の変化の始まりを自然発生的に考えていた節があって、その世界観はやや唯物論的な印象が強い。
一方でブルーメンバッハは、少なくともその著書においては、ある時に(神による?)創造の瞬間があったのだと普通に想定している感じである。結果、彼の理論はより古いとされる進化論により近いと思う。つまり、ある初期種が枝分かれし、様々な変異を遂げて大量の種を生み出す(この場合の初期種をごくわずかな、自然発生するほどの単純な種として想定すれば、ラマルクの説)というよりも、最初に完全体として創造された各生物種のそれぞれの変異が、それぞれの種の多様性を生み出したというようなもの。つまり、ある生物系の中に1本の枝分かれする巨大な系統樹があるのではなく、根本からすでに離れているいくつもの木が存在するというもの(言うまでもないが、これは全ての生物を神が創造したというような世界観との親和性が高いタイプの進化論でもある)。
創造をどう考えるべきか。ニュートンの影
ブルーメンバッハはまた、生物の変化については”変性(degenerationis)”という単語で表現していた。この意味は普通、退化というより、ある状態(つまり創造された時点での完全な状態)からの逸脱というような意味合いだったと考えられている。そして、そのような物理的変化の、方向性に関しての制限などは(そんなものを想定する理由もなかったろうから)実際的になく、つまりブルーメンバッハは、創造時の生物の環境に身を置くことさえできたなら、再び生物は完全に近づくことも可能、つまり逸脱した部分は修正できるというように考えていたらしい(この点についてもビュフォンと同じである)。
しかし、生物が変化することを認め、しかもそれが多様な種の原因であることも認めて、それでなぜ、最初が完全な生物なのだろうか? それはもちろん、創造論の世界観を前提にしているせいと考えるのは容易い。しかし仮に、その始まりの原因が全く不明とするなら(つまり、何かが創造したのか、自然に発生したのかなど全くわからないとするなら)、「最初の種がごく単純なものであって、それが変化によっていろいろ複雑なものに変化していった」というような考え方は、むしろ最初に出てきそうなものと、今では思えないだろうか。
だがラマルクがそれ(単純な初期種が様々な種に分岐する説)をはっきり提唱した時、それは確かに奇妙な学説だったのかもしれない。ダーウィン以降、世界が変わったとよく言われるのも、そのような世界観(進化の複雑な系統樹)が、それ以前には、「何か普通でなかった」ということを示唆しているのでなかろうか。
重要なことは、自然の原理に頼らなくても、あるいは自然とはまた別の何かの原理で、望み通りの生物を造ることができるような存在(つまり神、クリエイター)を当然のものとするなら、最初に発生する生物が、つまりこの世界に最も適応している(あるいはふさわしいと想定している)完全な生物であるという考え方は、そんなに奇妙でなくなるだろうこと。ごく単純な生物がかなり複雑な生物になるということを、普通には想像しにくいのも確かだ。だから、始まりが完全体群という世界観は、(例えば、最初に誰かが単純な生物を誰かが造り、それが様々な環境の変化で偶然、様々な環境に適応した各種に変化した、などと考えるより)むしろ合理的とすら考えられたのだろう(自然淘汰という現象を知らなければ、今でさえそうだったかもしれない)。
創造された生物が、本質以外の、つまり生物の構造的にわりとどうでもいい部分を、環境によって変化(初期形態を本来のものと考えるならば、本来のものからの逸脱、部分的劣化)させてきた。
では創造とは何だったのだろう。昔の人は迷信深かったからと納得するのは簡単だが、それを簡単に信じることができるというのが、イコールそれを信じる理由にはならないだろう(例えば、現代において「神を信じない」という人は多いと思うけど、この世界にはまだ謎が多すぎるために、神を信じることは今でもごく簡単)。なぜ自然の驚くべき力(ある生物種に驚くべき多様性を与えるような変化の原因)をよく知っていたナチュラリストたちが、当たり前のように創造などというオカルト(?)を信じたのか。
少なくともブルーメンバッハに限っては、その思想に関して1つの納得できる原点がある。
彼は分類学の父リンネとともに、偉大な物理数学者アイザック・ニュートン(Sir Isaac Newton。1642~1727)を崇拝していた節がある。そのニュートンは、例えば有名な『光学』という本で、「動物群の見事な構造こそ、それをデザインした創造主が実在することの強力な根拠の1つ」というように書いてたりする。生物の原因という哲学的問題において偉大なニュートンのそのような試行錯誤の末の結論が大きな影響を与えていた可能性はあるだろう。
 「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術
ところで、後にダーウィンが提唱した”自然淘汰(Natural selection)”というのは、ある環境にて複数の種が様々に変化(その変化に何らかの意図的な方向性などなくて、完全な偶然で問題ない)するなら、いつでも、最もその環境で有利な変異体が生き残る確率が高いだろう、という説。このシンプルな(実際あまりにも単純な話なので、後世の多くの生物学者が、なぜそれをそれまで思いつかなかったか、真剣に議論してきた)原理が正しいなら、十分に長い時間があれば、あちこちの環境で、それぞれの環境に適応した複雑構造の生物だって生まれておかしくない。
いったい、それ以前の多くの謎を簡単に解決する単純なシステムを発想することを阻む障壁とは何だったのか。それとも、単にコロンブスの卵的な話(案外、単純なことでも最初に思いつくのはとても難しい、というだけ)か
人種の起源種。もしも世界が神の芸術であるならば
『人種の起源種』という本(論文)の目標は、タイトル通りに、人類の種類を分類し、その起源種の存在を明らかにすることだったろう。ブルーメンバッハ自身は、例によってそれは、生物学史の中の小さな仕事というように序文(第三版)に書いてもいる。
ブルーメンバッハは、自然世界の見事な連続性(グラデーション)を認め、自然に3つあると思われる大区分(すなわち動物、植物、鉱物という三界分類)のそれぞれに、創造の連鎖(あるいは梯子)があると考えた。よくある哲学だ。
 「アーサー・O・ラヴジョイ」存在の大いなる連鎖の哲学、その歴史について
「アーサー・O・ラヴジョイ」存在の大いなる連鎖の哲学、その歴史について
しかし、「王国の自然物は、その外形に関して互いに受け入れ合う」というように、ブルーメンバッハは、特にその見た目を重要視していた印象がやはり強い。
自然の中で人間はどれくらい特異的な生物か
その一般的な身体的習慣を基準に、人類の多様性についてしっかり考察するなら、まずは人間そのものを知る必要があるだろうと、ブルーメンバッハは書く。これは当然であろう。
例えばある人種にあるが、別の人種にはない何かを考えるとする。その一方にあって一方にない何かが、ほとんどの生物に一般的なものである場合と、他の生物にはあまり見られないけれど人間という種では一般的である場合なら、いくらか見方も変わってくるのでなかろうか。
そこで、『人種の起源種』の最初の章は、人間という生物自体の考察である。それははたして、ある種の動物であるのか。それとも、動物とは明確に異なる人間というカテゴリーで考えれるような特別な生物であるのか。
過去の生物分類の研究で、(ブルーメンバッハ曰く、その仕事のために生まれたような不滅の人である)リンネさえ、人間の特異性を見いだすことには苦労した。ブルーメンバッハは、リンネが、人間と猿において内面化されるいかなる特殊な性格も発見できなかったと認めていたとする。さらにそこから、神は人間に特別なクラスというより、猿(腕の長い類人猿)の同族という地位を与えたのだという推測も書く。
おそらく重要だったのは、人間が猿に近い生物といったことよりも、自然の連鎖する梯子、あるいはグラデーションの中に、人間もしっかり含まれているのだということ。
そうしてブルーメンバッハは、他の多くのナチュラリストがそうしてきたのと同じように、人間を、この宇宙で非常に特別な天使とかモンスター的な存在ではなく、(とても賢き存在でありながら)あくまでも大自然の一部である、という魅力的なキャラクター性を与える。
直立姿勢と野生児の異常さ
ブルーメンバッハが見出した、どうも人間という生物の特徴と言ってるいいらしい外部構造は4つ。
1、直立姿勢(statura erecta)
2、広く、凹んでいる骨盤(pelvis lata,depressa)
3、手と呼べる前足(manus duae)
4、隣接して等しい一連の歯(dentes aequali serie approximati)
普通の状態で育てられる世界中の(興味深いことに「確認されている限り」とブルーメンバッハは言う。実際、確かに”確認されている限り”だろう)人間が直立姿勢であるというのは、それが人間の自然的な状態であることを示唆している。
またブルーメンバッハは、そのような人間らしい直立歩行をあまりしないらしい野生児(例えば「ハーメルのピーター(PetriHamelensis)」というのが有名らしい)の報告にも触れる。それは異常な状態であり、そのような子供たちが、直立歩行をあまり得意でないとしても、それを人間の自然状態の基準にはできないだろうと。
広くて凹んだ骨盤と、女性器、処女膜の奇妙なこと
(その形状が他の哺乳類と違う感じが強い)骨盤、すなわち骨格全体の中で、上半身と下半身の接続部と言えるような部分に関しては、これは類人猿と比べてもかなりはっきり違いが見られる特徴として、重要視されている。
〔これまで述べた考察において、人間の骨盤に見られる特殊構造は、最大の力を持つといえる。それは人間が、類人猿やその他のすべての哺乳類と大きく異なることを明確に示す診断的特徴を提供しているから〕
そして現在において、おそらく注目すべきものがここで現れる。骨盤の形状が比較的人間と似ている生物として、サル(simiae)とゾウ(elephantis)の他に、なんとサテュロス(satyri)なる生物が挙げられているのだ。
サテュロスというのは、ギリシア神話の半獣人の名称であるが、普通に考えるなら、これは多分、当時そのような名称で呼ばれていた、何らかの生物(おそらくは猿の一種)のことであろう。
 「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン
「ギリシア神話の世界観」人々、海と大陸と天空、創造、ゼウスとタイタン
またブルーメンバッハは、骨盤形状の「Physicotheologicum finem(物理神学的な目的)」として、シュピゲル(Spigel)という人の報告を引用している。〔すべての動物の中で、人間だけが快適に座るための、肉厚で大きな尻を有する〕と。
物理神学というのは、英語では「physicotheology」と思う。これは物理世界の構造から神の目的を探ることを目指した、ある種の古い学問。しかし、そんなものを普通に出してる辺り、何か実用的だからというだけでなく、具体的に、「偉大なる1つの意思が創った、この特別な宇宙」というような世界観が見えてくる。
もう1つ、ブルーメンバッハは、女性の内部生殖器(膣)に注目した。骨盤を構成する仙骨と尾骨の湾曲は、人間の女性器の方向を決定づけている。結果的に人間の女性の膣軸は、他の哺乳類のメスに比べ、かなり前方に傾斜し、これは出産に関して不便もあるとか。
現代においても、人間は直立姿勢のせいで子供の出産を難しくしてしまった、というのは結構普通の見方だ。それは直立姿勢の代償だったのだろうと。
もちろん直立姿勢にもメリットはある。ブルーメンバッハもしっかり指摘しているように、”妊娠中の女性であったとしても”直立二足歩行は、様々な外からの危険を回避するのに役立つだろう(例えば直立姿勢は背伸びすることで広い範囲を確認しやすく、それに広い範囲を動く場合にエネルギー効率がよいとされる)。
また、人間は、自分たちで考えて、(それが正しいかどうかはともかくとして)いろいろな世界観を考えてきた。ある生物がどういうものかを考えたりする学問というのも、その世界観の中にある。だから、当然のように人間を賢い生物と考えるのは奇妙ではない。
〔その構造のおかげで、女性も問題なく座ることができ、「神聖な事柄に心を向ける」ことができるだろう〕
こういうのをどういう解釈すればいいか。
そして性的な接触に関しては、特にそれに対する欲望は理性を狂わせる(つまりそれは、人間を悪いものにする癌)というような説に続き、「処女膜というものが人間の女性にしかない」という(現在では普通否定される)説もだされる。それで、人間の性についてはやや神秘的な印象を出そうとしてる感もある。
いくつかの強い興味も見える。つまり、人間に特有の人間的な形状は、強い性的関心と関連しているか。少なくとも人間は、その賢さのためか罪のためか、普通、性的行為に対して大きな喜びを見いだすような生物。さらに唯物論者として有名なルクレティウス(TitusLucretiusCarus。紀元前99年~紀元前55年)の時代、あるいは少なくとも、古代ローマの頃からだろう(古代ギリシャではないのだろうか?)、議論されてきたという、性交中の男性にとって最も適している体勢という論争にも触れ、それは、物理的構造の研究によって解決できるかもしれないとも。
また、”処女膜(hymene)”の他、”ニンフ(nymphis。おそらく小陰唇のこと)”と”クリトリス(clitoride)”という、女性器の部分に、ブルーメンバッハは注目した。
処女膜については、それは女性の性の猥褻さ(obscena)を取り除くためのものとか、道徳的な目的(つまり純潔の印)のためというような考えも示唆される。
 「女性と科学」メスという性、神が決めた地位、大衆向け科学のよき面
「女性と科学」メスという性、神が決めた地位、大衆向け科学のよき面
〔……人類特有の女性の性に関するその猥褻さを除くためには、処女膜について言及しなければならない……
……数年前ドイツで連れてこられたある女性の性器に関して、報告を受けたので、より注意深く検査した……それは純粋に物理的な用途を持たなかったと推測できた……
生理学者たちが処女膜の目的について述べることには、納得しなくい。特にハレルス(Hallerus)が付け加えた次のような意見「それが人間にのみ見られることから、それは道徳的な目的、すなわち貞節の印として存在するものだ。
リンネは、ニンフとクリトリスについて、人間の女性以外の、動物のメスにも存在するのかどうかを疑っていたようだが、実際にはどちらの部分も人間に特有のものではないことが今ではわかっている。クリトリスについては、多くの適切な観察者と共に、様々な異なる哺乳類において明確に観察結果がある。最近、1791年12月には、オランダのサンドフォート近くで打ち上げられた52フィートのクジラに、握りこぶしくらいの大きさのものが観察された。また、数年間飼われたキツネザルに、人間に非常に似たニンフが発見されている〕
様々な構造には必ず何らかの意味があるはずだという信念(目的論)がここに関連しているかもしれない。何らかの物理的メリットがないなら、つまりそれは何か神秘的な、あるいは道徳的な目的があるはず、というような。だからこそ、物理的にそれほど意味がなさそうな人間の女性器にだけ存在する何かがあるのか、は注目すべきことだったのだろう。
手と呼べる前足
〔人間の直立姿勢に関してこれまで述べられたことから、彼らの外部構造の最高の特権、すなわち使いやすい2つの完璧な手が自由になる。
ヘルヴェティウス(Helvetio)により、我々の時代に再解釈されたアナクサゴラス(Anaxagorae)の詭弁として、次のことがが知られている「人間は手を持っているため、最も賢明であるようだ」。これは非常に逆説的である。
また自然の真実からさらに遠ざかっているように思われるのはアリストテレスの主張「真の手を持っているのは人間だけである」。類人猿でさえ、手の主要部分、すなわち親指は比例して短く、ほとんど使えず、エウスタキウス(Eustachii)の言葉を借りれば、完全に滑稽だ。したがって、他のどの手も、人間の手と違い「手と呼べるような器官」と言えないと〕
実際のところ、類人猿や一般に人に似ているとされる他の動物(バブーン、サル、キツネザルなど)は、二足歩行でも四足歩行でもなく、四つ手(quadrumana)なのだとブルーメンバッハは考えていた。それは指の(曰く、真の親指がある)構造を観察してのこと。基本的には握るという行為に適したものが手と定義したようである。
また目的論的には、自然の中で、サルが木の上に住むことを想定しての構造と推測している。ものつかみやすい尾も同じ理由(類人猿には尻尾がないが)
ちょっと面白いのが、人間とサルがどれくらい似ているかの論争の話の時。サルが直立して歩いたという目撃報告に関して、それが自然的なことではないと指摘するにあたり、ブルーメンバッハがあげた根拠。それは、例えば学芸員が描いた(おそらく直立姿勢状態の)生きているサテュロス猿(simiae satyri)の絵からさえ感じられるという、その不快感。
やはりブルーメンバッハは、どのくらいか本気で、芸術的におかしな部分(明らかに不細工な部分)は、自然的でない可能性が高いと考えていたのだろう。
これは目的論というよりも、世界芸術論とでも言った方がいいのかもしれない。誰かが何かの目的のために世界を造ったのだとして、その何かは、芸術家の精神も持ち合わせていた、というような。
ブルーメンバッハが、人種分類の仕事にあたり、芸術的感性を基準としたのは奇妙。そんな考えは、各人種の知的能力に差がないと考える平等主義者の信念と、全てのことには序列があるという自然の梯子理論の板挟みのため、というような見方も今ではある。しかし案外、もっと普通に世界は芸術だという考えがあったのかもしれない。
または逆だったのかもしれない。つまり、人種を分類しようとする時、芸術的感性の下での序列がまず見いだせたから、最初から「知的能力が違っているはず」というような先入観を持たずにすんだとか(普通、本当に何の偏見もなく各人種のことを調べたら、知的能力にはっきり差があるというような理論を打ち出すのは、おそらく難しい。地球の生物史の中で、人類、というかホモ・サピエンスが別々の地域で隔絶されて暮らしていた時間はあまりに短い)。
綺麗に並んだ歯
〔人間の歯は、他の哺乳類の歯よりも多く、同じ系列で近似されている〕というのが、ブルーメンバッハが語った人間の特に注目すべき特徴の最後の4つの最後の1つ。
また、人間の顎には3つの特徴があるという。簡潔さ、突出した顎、そして顆頭(下顎の、側面から見た顔の中心に近い部分)の特異な形状。顆頭と側頭骨との接合部の構造は、様々な食べ物を食べる人間ならではのものと。それと、やはり色々な食べ物が、人間のためにあるということの1つの根拠であるとか。
柔らかい細胞は、人間の特権的な能力のためか
先の4つの外見的特徴(直立姿勢、平たい骨盤、2本の手、歯の並び)などは、人間という物理構造のかなり大きな部分である(すでに複数のパーツの集合部分と言ってもいいだろう)。
ブルーメンバッハは、もっと細かい人間の部分、例えば細胞(cellulosam)と呼ばれる粘膜組織についても言及する。
細胞は、現代においては、生物の基本的な構成要素(ウイルスを除けば、地球生物全体に共有されている基本的特徴。ウイルスは、それが生物だとしたら、おそらく細胞に寄生して機能するというような生物)としてよく知られている。それは17世紀頃、科学研究に顕微鏡が使われるようになって、ようやく発見された構造だが、ブルーメンバッハの時代(18世紀後半~19世紀前半)には、すでに様々な動物のそれに関して観察報告があった。
例えば彼は〔では、一般に細胞と呼ばれる粘膜組織の人間のものの特殊性、その優しさ(teneritudo)と従順な柔らかさ(obsequiosamollities)に特に注目しよう。というのは、さまざまな動物種が、それぞれに有するこの粘膜組織の内容に、それぞれ個性が見られることはよく知られているから。例えばウナギ(anguillae)のそれは粘りが強く、比べるとオヒョウ(farioni)は柔らかいことが、素晴らしい解剖学者であるツィンニウス(Zinnio。※多分、解剖学者のJohann Gottfried Zinn)によって観察されている〕というように書いている。
ブルーメンバッハは、その、見事な柔らかさこそが人間の細胞質の特徴と考えていた。ただ、その柔らかさは、生物全体の中でというより、自然の中で近い地位にある、哺乳類の中での相対的なもの。
そして、〔もし私が重大な誤解をしていなければ〕と前置きしてから、ブルーメンバッハは、柔らかい細胞は自然世界の中での、人間の特権と関連があると推測する。ようするに、その組織の柔軟性のおかげで、人間は特に様々な気候に対応できるのだろうと。
細胞の柔軟性はともかく、気候への適応力に関しては、今は別のイメージが普通と思う。つまり、人間は基本的には服や建物のような道具に頼る生物であるから、似たような他の動物(哺乳類)に比べれば、単純に構造への、気孔変動の直接的な影響にはむしろ弱いと。
ただし、どのような生物であっても、外からの変化の影響にはある程度適応する。そして、そのための方法は異なっているだけではない。この複雑な世界の中で、そのような適応のための方法には、例えばエネルギー効率の違いとかもあるだろう。
また環境の変化によって、例えばその領域内でのエネルギー量自体が著しく減っている場合はどうか。多くのエネルギーを使う代わりにものすごく適応力が強い生物などは、そもそもその方法を(エネルギーが足りないために)使うことが難しくなって、役に立たないかもしれない。
そういうことを考えてみると、やはり、実際には、「ある生物がある生物より優れている」というように考えるのはとても難しいと思われる。
長い幼少期と寿命、性的機能と余計な種子
細胞以外の、人間の(自然世界での)特権に関する特殊なこととして、他に、幼少時代の長さとか、長い寿命(寿命と関連する表の比較により、ブルーメンバッハは、84歳まで生きるヨーロッパ人の割合は多いが、それ以上生きる者は少数と結論している)、時期の限定されない自由な行為(セックス)を許す性的機能とかが注目されている。
性的な行為の可能な時期(言ってしまえば人間は、基本的にずっと発情期)などは、女性器に関する考察とも関連があるが、どちらかというと、そこでは男性の方の性的機能に注目しているように思う。
〔特に男性には、夜の汚染(pollutionumnocturnarum)の特権が与えられている。これは健康な男性の自然な排泄物を指す。もし気質や体質的な理由で、適切と判断されるなら、余計な種子(semine)を放出し、不快で過剰な刺激から自らを解放できる〕
一方で女性(の余計な種子排泄?)に関しては、選択的でなく、より普遍的というような見方。例えば月経(生理。用意されたが受精することのなかった卵子排出の結果としての出血)がそうだと示唆するいくつかの古い記述などに触れている。
素直に解釈するなら以下のような世界観だろうと思う。
子供のための種子が男女の体内にある。性欲のための男女の営みが、その種子を機能させるきっかけとなる。しかし男女の関わりがない場合でも、性欲自体はあり、そのための自らの手による疑似的な営みの刺激によって、種子が排出されることがある。それはおそらく、(過剰に生成とかしてしまっているためか)他の日常に悪影響を与えるような過剰な種子を破棄するも同じ。
しかし、もし本当に神が世界を造ったなら、余分な種子(明らかな無駄?)が発生するようなシステムにしたのはなぜか。これも本来的じゃないのだろうか? 実のところ、世界が芸術作品ならば、そのような疑問も弱まるかもしれない。
芸術家が、とても美しい傑作を作ろうと考えたとする。彼は、一部の特に素晴らしい部分を目立たせるために、ある部分を犠牲にしないといけなかったのかもしれない。それで、作品(つまりこの世界)のある部分では、ある種の無駄(犠牲にされたもの)が発生してしまう。しかし作品にとって、その無駄(いわば作品の汚れ)マイナス以上に、美しくなっている部分がプラスであれば、全体としての作品はよくなるだろう。
芸術論的な見方は、「なぜ神は悪を存在させたのか」とか、そういう疑問の1つの回答にもなりうるだろうか。
もっとも、現代のほとんどの人にとっては、そのような、世界のあちこちに奇妙な無駄らしきものが確認できるという事実は、全く別の世界観の重要な根拠になっているだろう。
つまり、ダーウィン的な進化論を前提としているような世界観。ようは、色々な偶然による変化が世界にあって、運よくその場その場の環境によく馴染んでいたものが残ってきただけというような(いわゆる盲目の時計職人の世界観)。
世界に誰かの目的なんてないのなら、誰かにとって奇妙な部分があるのは、不思議でもなんでもない。ただの偶然で話は終わる。
しかし、明らかにブルーメンバッハは(そしておそらく同時代の多くの生物学者たちも)目的論というものにかなり縛られてしまっていた。そして明らかに、世界を神の芸術作品的なものとして捉えていた節があるが……
魂の能力こそが、人間を自然の王にしたか
ところで、古くから、人間の最も重要な特性とは、その知性、意識、理性であると考えられてきた。これは、人間が、人間のそのような世界観を、知的な考察から発生させてきたのだから、当然だろう。
そして、昔の多くの哲学者たちは、その人間の理性というものの原因を、”魂”と呼んできた。
具体的に、これ(魂)をどう解釈すればいいかはともかくとして、理性というのが魂の能力であるというのは、現代でもそれほど奇妙な説でないと思う。なぜなら、脳(神経系)のような物理的構造だけで、人間の意識のようなものが発生したのが確認されたという、信頼できる研究報告など、今日に至るまでないから(そういうものが確認されない限り、魂説は語られ続けると思う)。
ブルーメンバッハはどう考えていたか。彼もまた当然のように、〔人間の最高にして最大の特権である〕理性というのが(曰く、誰もがそうだと理解しているように)「魂の能力(animaefacultatum)」と書いている。
〔そんな言葉(理性? 魂の能力?)が自分にとって何を意味するのかをより注意深く探究する人は、最も合理的な哲学者の議論が理性の概念からどれほど離れているかに驚くに違いない。
それは人間だけに特有の特別な精神能力か。または、少なくとも最上級で非常に優れた程度の能力が人間にはあり、その痕跡は野獣の魂の中にはかすかにしか広がっていないのか。あるいは、人間とは心のすべてと、個々のより高度な能力の複合体か。人間の心と機能は特異な方向を向いたものか。
しかし哲学者たちの論争を解決するのは私たちの役割ではないだろう。
私としては、人間を他の全ての生物の支配者にして主人とする特権を人間に与えてよいならば、この問題はより簡潔かつ安全に解決されると信じている。
そしてその支配が存在すること、それにその支配の原因が人間の肉体的な力にあるのではないということも明らかだ。したがって、これは魂の特質およびその卓越性にのみ帰するべきと言える。これらの特質によって、人間は他の動物をはるかに凌駕するのだ。
セネカ(Seneca)は述べた「誰であれ、人間の運命を不公平に評価する者よ、我々の父がどれほど多くのものを我々に与えたかを考えよ。どれほど強力な動物を我々が服従させたか、どれほど速いものに追いついたか、どれほどすべての死すべきものたちが我々の支配下にあるかを」〕
こういう考えが間違っているなら、驚くべき自惚れと言えよう。
ただブルーメンバッハには、一応それなりの根拠があった(少なくとも持ってるつもりだったろう)。先の考察でわかってきた人間の特性の数々がそれだ。彼はしっかりそれらを提示している。
例えばそれは「多様な環境に適応できる細胞質」や「様々なものを食べるのに適した歯(や喉とか)の構造」。つまり人間は、色々な環境で生きる生物なのだが、ここでまた目的論が出てくる。〔したがって、創造者は彼に、これらの状況に適応できる推論と発見の能力を与えたはず〕と。
世界の変化、生物の退化、家畜の領域
人間が他の動物といかに異なるか(そしていかに自然の中で特別であるのか)についてを書いてから、ブルーメンバッハは種という概念を少し考察した後、いよいよ、人間の種類、人種に関しての話に移る。
ブルーメンバッハは退化論を支持していたが、そのような原因自体の他、それによってもたらされる多様性が今どのくらい大きいのかに注目した。
まず種というものをどう考えるかに関して、特定の動物群が同じ種であると考える場合の1つの基準として、ビュフォンや、それ以前の人らしいライウス(Raius)なる人物の考えを紹介する。つまりは、互いに交尾して生殖能力のある子孫を生み出す動物群が、同じ種だと。
しかし人間によって、生き物としての暮らしがかなり強制的に制限されている家畜の種に関しては、この理論が当てはまるのかあやしいとも。
フリッシュ(Frisch。誰か不明だが、文脈的にはリンネの印象がちょっとある)という人は、生殖能力の有無という基準は野生者に限られるものだと指摘したらしく、ブルーメンバッハはそれに賛同していたようだ。
いずれにしろ、生殖能力という基準だけでの種の分類は、不完全なものであると、ブルーメンバッハははっきり認めていた感じである。だからいくつか他の基準も参考にする必要があるとも書いている。実際、本当の意味での種の分類などというものは不可能かもしれないと、諦め気味に書いてたりもする。
ところで人間は野生種と言えるのだろうか。ブルーメンバッハは、ニュートンの哲学の2つの黄金律らしい、「別々に起きているが同じものに属する自然の影響には、普通は同じ原因が考えられる」と「自然現象の説明に十分な原因以外に、自然現象の原因は認められるべきではない」を持ち出し、自分なりの結論を出している。
〔各国の人類の身体的多様性について、世界中に広く分散している他の家畜群の同様の身体的多様性と、同じ原因を帰属させる必要があるだろう〕と。
しかし生物は退化するのだとして、退化の原因はどのようなものか。
変性の原因として、ブルーメンバッハは、動物の2つの生命機能を考える。
1つは、初期条件、あるいは原理としての生命力と、依存している特定機能。
もう1つは、身体への外部刺激の受容と、結果としての反応。
外部刺激としては、特に気候の影響は、生物の肌の色とかにも影響を与えるとしているが、人種のわかりやすい見分け方に色があるとするなら、このことは重要だったかもしれない。
そもそも生物を構成している様々な元素集合構造(有機体)は、それぞれが受ける圧力や、それに対する抵抗などに応じて、いろいろ変性することは、世界そのものの変化現象から、ほとんど明らか。
そして人間の変化過程について、以下のように語られる。
〔一連の長い世代を通じて、汚染されずに保存されるか、または短期間でより変化しやすい性質に再び服従するかのどちらか……退化の原因がより多く重なって、それらが同じ種の動物に長く作用するほど、それらは元の構造からより大きく逸脱する可能性が高い。しかしこの点において、人間と比較できる動物はないであろう。人間は雑食性であり、あらゆる天の下に住み、すべての生き物の中で群を抜いて最も重要である。つまり、その種の始まりから家畜化されていると言える。したがって、彼らには、気候、食生活、そして生命の種が組み合わさった力が、非常に長い間作用したに違いない〕
ブルーメンバッハは人間という生物を、種の始まりの時から家畜化されているような、と推測している。ここで「家畜である」というのは、自然の世界から外れているというような意味だろう。つまりそれは、自然状態に比べての退化の速度の違いではなく、それに対するコントロールが可能な状態、というようなものと思う。
例えば、家畜には強い圧力がかかることもあれば、むしろ本来の自然環境の影響から守られることもあるだろう。そして人間はこっち側だとブルーメンバッハは考えていた節がある。だからこそ、世界中に広がり、世界中の環境に適応する中でも、全人種は種としてそれほど離れなかった、という最後の結論につながる。
人種分類の結論。原型を含むグラデーション
人種の主なものとして、コーカサス人、モンゴル人、エチオピア人、アメリカ人、マレー人の五分類を考えたブルーメンバッハは、その中でもコーカサス人(普通には白人)たちを、オリジナルの人種に最も近い人たちだと考えた。しかし彼は、その考えを出してすぐ、実際にはもっと細かく分けられるとか、これはあくまで便宜的な分類とか、書いてもいる。
5つの人種のそれぞれの特徴としては以下のような感じ。
コーカサス人〔白い肌、赤い頬、髪は茶色かナッツの色……全体として、私たちの国民の対称性の判断から、最も魅力的で美しいと考えられる顔の外観〕
モンゴル人〔黄色い肌、硬い黒い髪……眉間が平らで幅が広く、鼻は小さい。まぶたの開口部が狭く、直線的で、顎が突き出ている〕
エチオピア人〔茶色い肌、黒髪で巻き毛、頭が狭く側面が圧縮気味……厚い鼻と、細長い下顎……上の最初の歯が斜めに突き出ている〕
アメリカ人〔銅色の肌。硬い黒い髪、額が短い。目がより深い位置にある。非常に低いが目立つ鼻……額と頭頂部の形状は最も巧みな作り〕
マレー人〔アーモンド色の肌。柔らかく、クセの強い黒い髪……大きな口を備えている。上顎がやや突出している〕
本の最後の章では、様々な地域の人種の観察報告を紹介し、それぞれの地域の環境が、そこに行ける人たちにどのような影響を与えたか考察している。
重要なのは、ブルーメンバッハが、神が創造した人間という生物群が、まさに原型(起源種)であるコーカサス人だけと想定していたこと(神が芸術家で、この世界を美しいパターンとして描いたなら、最初に創った人種が、最も美しい原型だけというのは当然の話だろう)。つまり、その他の四人種は全て、世界の退化システムにより、新たに生まれた人たち。
さらに彼は、人間は世界中で同時に創られたのではなく、最初に創られてから広がっていったと考えたらしい。つまり、始まりの地(コーカサス)から、地球のあちこちに順次移動したと。
しかし彼は、単純にコーカサスから離れている人たちほど原型から離れてしまった人たちとは考えなかった。冷静に、様々な地域の人たちの身体的特徴などを比較し、例えばある地域は始まりの地と比較的近い環境にあるため、ある程度原型にまた戻っているのだろう、というような推測もしている。
ブルーメンバッハは、自然界に連続的なもの(変化のグラデーション)を見ていた。そしてどうやら人種の中だけでも、それを見ていた。
そしてそれは、少しの環境の影響で変わるようなもの。
つまり、原型も、その簡単に移り変わるグラデーション内に含まれているものだから、誰もが、戻ることがそれほど難しくないとした。
もちろん、生まれた時の環境におかれても、もうなかなか戻れないほどに原型から離れてしまった生物も、この世界にはたくさんいるだろう(だからこそ、全種の分類は難しい。完璧にするだなんて不可能かもしれないと、ブルーメンバッハ自身嘆いたわけである)。それで、彼は結論を下す。
人類というのは確かに、ある程度の基準において異なる人種として分類できる。しかしそれぞれの人種は、その人間ならではの能力(例えば魂の能力)に関して、はっきり差が出るほどの違いは生じていないのだろうと。
〔他のさまざまな種が連続するように、ここでも同様に感覚的にはわからないような移行がある。本書のこれまでに書いている退化の原因や方法、および他の家畜動物における類似の退化現象について議論したものとも比較できよう。このことは、最終的には、動物学的批判の助けを借り、生理学的原則を人類の自然史に適用することで、自発的に導かれる結論へと導く。つまり、これまでに知られているすべての人種の変種が、1つの同じ種に非常に高い確率で帰属すると考えられるという結論。もはやそれに疑いの余地もない〕
形成衝動について。生命のための力の謎
先の、人種分類の本でも、生物の性と、子の種子を機能させる性的行為(とその結果としての受精)に関する強い興味が見られるが、ブルーメンバッハは、種子がその生物の完全な姿に変化するまでの形成過程にもかなり注目していた。
そして彼は、全ての生物に備わっていると思われる、その初期状態(目覚めたばかりの種子、あるいは最初の1個の細胞)から、それぞれの生物の形を形成する潜在的な力を考えた。
彼はその力を”形成衝動(Bildungstrieb)”と呼んでいた。そしてそのまま、それ(形成衝動)についての本(論文)を書いてもいる。
生殖に関する疑問。最初のカップルは子作りの方法を学んだか
〔ある生物が、すべての衝動の中で最も甘い衝動に身を委ねる。今、別の衝動により受精する。そしてさらに第三の存在に命を与えるとき、その生き物の中で何が起こっているのだろうか?〕
それがブルーメンバッハにとって、非常に重要な疑問だったことは間違いない。彼が書いた多くの文章で、この問題についての彼の強い興味が垣間見れる。
ブルーメンバッハは、どこかで生物が創造されたことを信じていたようで、最初のカップルの衝動に関しても注目する。例えば、最初のカップルは、自分たちの行いが、次世代の子供を生み出す行為であることを自覚できていただろうかと。
これに関しては、おそらく創造論的世界観を前提としている場合の方が興味深いと思う。多様な生物種の存在する生態系の始まりも、基本的にはごく単純な単細胞の生物群からと考える進化論的世界観においては、抑えがたい衝動や誘惑というものをはっきりと理解できるような知的生物が誕生する頃には、もうとんでもない数の世代が繰り返された後というのが、普通の考え方でなかろうか。つまり、誰もその行為の後に子供が生まれるという現象を確認していない状態での、知的生物のカップルというのは、なかなか考えにくい。
仮にある閉鎖環境に置かれた子供たちが、性的な行為の全てに関して無知であって、彼らがそのまま、誰も子供を産むことなく死んでしまう、というようなことがあるとしても、人類という種族全体で、そのようなことが起きるとは考えにくい。
後成説と古い進化論。二つの主要な道
ブルーメンバッハは、中世(mittlern zeitalters)という時代(おそらく5世紀~15世紀くらい)を〔他のすべての知的探求精神(Forschungsgeist)が、野蛮な修道士たち(Mönchsbarbarey)の愚かな行為のため、深い眠りに埋もれていた暗い世紀〕と認識していたらしい。しかし、そんな時代でさえも、性的なこと、その謎についての深い関心が確かにあった。その時代に残されている肉欲的な多くの書籍が、そのことを証明していると彼は言う。
そのことについての、歴史上の様々な人たちの絶え間ない研究の連鎖が、たくさんの奇妙な説も生み出してきた。
曰く、〔ブールハーフェ(Boerhaave)の師ドレランクール(Drelincourt)は、先人たちの著作から262もの、ろくに根拠のない生殖に関する仮説を集め、彼自身の体系は263番目の仮説を構成する〕とか
しかしながら、〔この最大の生理学的パズルの解決策に到達するため、人が切り開いてきたらしい、それら無数の道は、最終的にはすべて2つの主要な道につながると思われる〕とブルーメンバッハは考えた。
その2つの道の、一般的に知られた名前は”進化(Evolution)”と”後成説(Epigenese)”。
それらの名称を聞くと、今だとどんなシステムを想像するだろうか。ブルーメンバッハ自身の、それらに関する説明は以下の通り。
〔それらの説のどちらも、親の成熟した、しかし未形成の生命でもある生殖材料が、適切なタイミングで必要な状況下で目的地に到着すると、徐々に新しい生き物に成長すると仮定している。
それが、エピジェネシス(後成説)が教えることだ。
あるいは、すべての世界の生殖に否定的で、すべての人間、動物、植物に関して、最初の創造の時にすでにすべての芽(Keime)が創造され、時には改良されながら、ある世代が次世代へと単に展開されていくだけだという考え方。それは進化の教え(Lehre der Evolution.)と呼ばれるが、理由は明らかだろう〕
今、一般的に、進化論を、生物世界を説明する有力な仮説として捉えている多くの人にとって、ここでブルーメンバッハがはっきり言っているほど、(彼のいう考え方が進化論と呼ばれる)理由が明らかでないことはほぼ間違いないと思う。
言うまでもなく、ブルーメンバッハの生きている間(1752~1840)に、ダーウィンの進化論が世に公表(1859)されることはなかった。一方でラマルクが、かの大著『動物哲学』(1809)で、自身の進化論と、その進化論を前提とした生物世界を存分に語った頃には、まだ彼は生きていたが、『形成衝動について』という本が書かれた時期はそれ以前(1789)のことだ。
ここで彼が、進化論として理解している仮説は、明らかに、今の我々に馴染み深い、典型的な進化論ではない。それが、古い時代に主流であった、今となってはかなり時代遅れのタイプの進化論であったというのは、かなり確かだ。
それは明らかに、ある生物世界の全体を、複雑な系統樹というもので表現できるような進化論ではない。
素直に考えるなら、各生物種のそれぞれは、創造の時点からすでに、本質的には固定的なもの。しかし、ある種の中で、その本質を変えない程度の変化が生じることはある世界観。それによって、あらゆる種の、それぞれの種内での多様性を説明するというようなものであろう。
しかし、そのような古いタイプの説において、「進化」という言葉が適切と判断されたらしい辺り、この言葉が、当時、一般的にどのような意味で理解されていたのか。むしろそれこそ、なかなか興味深いかもしれない。
パンスペルミアとマトリョーシカ
また進化(影響力の大きさ、スケールはともかく、生物の多様性の原因である変化)という現象の原因について、代表的な(だったらしい)2つの説(生物世界のシステム)が紹介されている。
 「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
「地球外生物の探査研究」環境依存か、奇跡の技か。生命体の最大の謎
その1つは、地球上に散らばった大量の生命の芽が、発達した同種の同胞の生殖部分に遭遇すると、それらに根を張り、自身の成長を抑止する覆いを破壊するというもの。これはまた、”パンスペルミア(Panspermie)”のようなものらしい。
このパンスペルミアという用語は、現代、一般的には、「生命の種子が宇宙からやってきた説」というような意味で理解されるのが普通である。ブルーメンバッハの時代(あるいはもっとずっと前の時代)でも、少なくとも、生命世界の外部からその種子が入ってきた、というようなニュアンスはあったようだ。ここから、性的な男女の接触が、世界中に大気の粒子のように散らばる生命の素材を刺激する行為、であるような世界観も想定できよう。
しかしいずれにしろ、ブルーメンバッハは、それについては、あまり説得力のない古い説として扱っている。
もう1つの説はより有力と考えられていたようだ。
つまり、生命の芽は、世界中に散らばっているというよりも、全ての世代がある種の最初の芽に、すでに入れ子(マトリョーシカ)構造として入っているというもの。
この説を信じる者たちの間では、最初に作成された時点から全ての子孫を含んでいる生命の芽が、男性が抱えているものなのか、女性が抱えているものなのか、という論争があったらしい。
顕微鏡により発見された、精子の海の虫
ブルーメンバッハは、顕微鏡の発明のおかげで発見された興味深い事実として、男性の精液の中に、大量の微小な生物の種らしきもの(精子群)が確認されたことに、注目してもいる。
曰く1677年に、ライデンで医学を学んでいたフォン・ハーメン(Von Hammen)という若者が、オスのニワトリの精子を顕微鏡で見て、まるで小さな虫(Saamenthierchen。精子生物)たちの海のようなものを発見した。それ以来「その精子の海の虫こそが、まさしく生命の種子である」という説が、よく語られるようになったとか。
精子虫が、生物は無関係と考える自然学者がたくさんいたことが驚きだとブルーメンバッハは言う。しかし一方で彼は、それが高等な動物に変異するような生物の種であるという考えは、より奇妙とも。
精子虫が、あらゆる生物の種子であるという説に疑問を感じる理由として、ブルーメンバッハ自身は、(ただし、基本的にそれらが過去の報告を参照していると前置きしつつ)系統的に近いと思われる動物種の精子虫が全く似通っていないことに触れている(例えばカエルとサンショウオのそれが似ていないとか、または逆に、かなり違う生物と思われる人間とロバの精子がとても似ているとか)。
ヒドラの再生実験と、ある生命力
田舎で休暇を過ごしていた時、ブルーメンバッハは、緑色のポリプ(ヒドラ)を見つけ、その再生能力を観察したらしい。
それが、彼の考え方に大きな影響を与えた。
ちなみにヒドラというのは、刺胞動物門に属する生物で、同じ門に属するクラゲが浮遊性、すなわち漂う生物として知られてる一方、固着性の生物として知られている。重要なことは、ブルーメンバッハが注目したような、驚異的な再生能力(例えば半分にちぎっても、2つのヒドラとして再生されることが知られている)。
〔……私は、そのヒドラの驚くべき特性を、仲間たちと一緒に観察して楽しむことにした。暖かく乾燥した夏の天気と、ヒドラの有する耐久性のおかげで、再生の試みは順調に進む。切断された部分が急速に再生されるのを確認できた。
2日目、3日目には、切り取られた腕や尾が再び成長したが、常に非常にはっきりと観察されたのは、新しく成長したヒドラがたくさんの餌を与えたにもかかわらず、以前よりもかなり小さくなっていたこと。切り取られた体の幹も、新しい部分を成長させると同時に、縮んで細くなっていくのが目に見えて明らかだった〕
このヒドラの再生の観察結果と、普通に人間が怪我をして治った後の状態を、ブルーメンバッハは比べた。怪我をした時点では失われていると思われる肉の部分も、最終的にはしっかり復元される。
それらのような再生現象から、生物の生命力というものについて、何かがわかるだろうか
〔私は、最終的に次の結論に達した。すなわち、あらかじめ形成された胚が存在するわけではなく、むしろ組織化された体が成熟し、適切な場所に到達すると、特別な衝動が生じて、最初の特定の形を取る。その後生涯にわたってそれを維持し、もし切断された場合には可能な限り再生しようとする〕
その特別な衝動は、主に、生成、栄養吸収、再生能力に関する。それは生命力(Lebenskräften)と呼べるものの1つだが、他の一般的な生命力(収縮性、刺激性、感受性など)とは異なる。また、一般的な物理力(重力など)とも異なるらしい。そして、それこそまさに「形成衝動」と呼ばれるべきものなのだと、ブルーメンバッハは考えた。
 「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
「胚発生とは何か」過程と調節、生物はどんなふうに形成されるのかの謎
面白いことに、ブルーメンバッハは、わざわざそれ(形成衝動)を普通の物理的力と異なっているものと定義しながら、ある側面的には、それが物理的力(重力など)と同じようなものとした。つまり、経験的に存在していることがわかるが、その原因(質)に関しては全く未知のもの、というように理解した(そしてこれは、それなりに正統派の考え方だったようだ。「これに関しては、いくらかの読者には説明するまでもないだろう」というようにも書いている。また、その考え方自体は、すでにいくつかの古代ギリシャの書物から読み取れるそうである)。
遺伝子コードのオカルト的側面
形成衝動が実在するものとして、それが働きかける生命の種子は、具体的にどのような物理的実体と言えるか。
生命の形成の研究について、ブルーメンバッハはいくつか引用した。
例えば、アマトゥウス・ルジタヌス(Amatus Lusitanus。1511~1568)の『薬物療法(Curationum Medicinalium)』。この本は、それが書かれた当時としては、医療を発展させた偉大な書物として有名だったらしいが、ここで引用されている記述は、現代の人からすると、医療というよりも魔術めいたものという印象を受けるかもしれない。〔我々は確かに、化学的な手法で造られた赤子が、全ての部位を完璧に形成し、動きも持っていたことを知っている。しかしそれは、容器から取り出されると、動きが止まってしまったのだ。このことをより詳しく知っていたのは、ジュリアス・カミラス(JuliusCamillus)という人物であり、彼は私たちの時代における学問と秘密の事柄、そして様々なことを探求する偉大な研究者であり、また彼は非常に丁寧で正確なヒッタイト語(Hetrusca sua lingua。エトルリア語)の文筆家でもあった〕
また、形成衝動というのは、世界のシステムの要素の一つと言えるが、先にも書いたように、それはある種の物理的力かもしれないと、ブルーメンバッハは考えていた節がある(それは当然と言えるだろう。ここは明らかに物理世界で、生物というのも、少なくてもだいたいにおいては物理現象と思われるから)。
ニュートンの、『光学』からの引用〔この引力という言葉を、一般的に物体が互いに引き寄せ合う力を意味するものとして理解してもらいたい。それがどのような原因によるものであれ〕は、その生命体を形成する現象と原因について、ブルーメンバッハがどう考えていたかの重要なヒントになるだろうか。
また、アリストテレス主義者として有名だったらしい学者F.ボナミコ(F. Bonamico)の『胎児の形成について(De formatione foetus)』からの引用〔霊(Spiritus)は、空気中の精子物質(seminis substantia)の中に包まれ、天(caelesti)からくる熱と、父親に由来する力、さらに天から分け与えられたものをふりかけられ、女性の子宮に、女性から注がれた物質を消化し、それらにさまざまな影響を与えて生物の器官(instrumenta)を作る。それを作る力は、διαπλαστικηまたはκρετείαικηと呼ばれる。しかし、器官が構築されると、その場において、以前は形成力(vis formatrix)であったものが、魂(animam)へと退化(degenerat)する〕
ギリシャ語のδιαπλαστικηとκρετείαικηは、おそらくどちらも「形成力」というような意味に訳せる。
これらの後の、未受精卵、またはニワトリの卵黄の議論などからも、同じような印象を受ける。例えば〔……新しく生成された皮膚と血管が、隣接する内臓から成長するように広がるとして、孵化されたニワトリの卵でそれが起きたなら、その血管と皮膚は黄身から外に押し出されることになる。
ただし、鋭い観察力を持つ自然科学者ポール(Paul)氏の、ハラー氏(Haller。おそらくAlbrecht von Haller)の証明への反論のように、別の可能性もある。仮に黄身の膜とその見えない血管がすでにニワトリの卵巣内に存在していたとしても、孵化中に初めてひよこが生成され、その血管がその膜の血管に移植され、両者が結びつくことができるというものだ。
ただしハラー氏はその異議ははっきり否定した。孵化中の微小なひよこの極細の血管が、巨大な黄身の血管に移植されることは絶対に不可能だと。
しかしながら、ハラー氏は、極めて功績のある人物だが、ひよこの血管の移植を不可能とする一方で、同じ著作で人間の受精に関する部分では、血管の移植を全く問題なく受け入れている。彼は、人間の極めて小さな胚は、卵巣から子宮に到達すると、胎盤を介して固定されると考えた。その固定の方法として、微小な臍帯(※へその緒)の血管が巨大な子宮の血管に移植されると〕
どの部分を切り取っても、素直に解釈するなら、(おそらく、どのタイプのものであってもそこは一緒だが)進化理論のために必要な、親から子に受け継がれる遺伝要素に、かなりはっきりとした物質構造を想定しているように思える。
つまり、現在かなり一般的になっているような、ある種の分子構造(一般にDNAと呼ばれるもの)の暗号文(少なくとも暗号文として実用的に理解できる暗号コード)に含められた、成熟した構造への変異過程の情報群というような遺伝子は、全くと言っていいほど想定されていなかったらしい。
不思議な話ではない。我々は情報テクノロジーというものの恩恵を子供の頃から存分に受ける時代に生まれ育った人たちだ。だがそういうものが一般的でなかった時代に生きていたら、「物理構造は受け継がれなくても、(その物理構造に関する)ある種の暗号文だけが受け継がれることで、生命の遺伝システムは普通に実用的に機能できる。どういうわけだか、どの生物も、それぞれの暗号文に従って、自身の体を成熟した存在へと変異させていく、謎のシステム下にあるから」というような話を、いったいどれくらい真面目に受け取ることができたろうか。
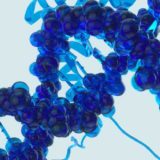 「DNAの発見」歴史に消えた多くの功績、歴史に残ったいくつかの功績
「DNAの発見」歴史に消えた多くの功績、歴史に残ったいくつかの功績  ツールキット。ホメオボックス。発生を制御する遺伝子「エボデボの発見」
ツールキット。ホメオボックス。発生を制御する遺伝子「エボデボの発見」
入れ子理論。制約の多い進化論が支持された理由
おそらく、我々が他の動物に比べて特別だと考える、この賢さを生み出す神経系さえも、その原型的な小さな物理構造が、最初の受精卵の時点で存在しているわけではない。それらは、それぞれの暗号文に従って、新しく作られていく。
だから今は、入れ子理論は完全に時代遅れとなっている。我々(の具体的な構造)は明らかに、両親の生殖細胞がくっついて、暗号文に従った生成動作を開始するまで、この世界に存在していなかった。その最終的な構造の設計図と言えるような遺伝情報でさえ、両親の生殖細胞に含まれている、それぞれの遺伝情報の混ぜ合わせであると考えられているから、その通りならば、その時(両親の性的接触により、生殖細胞が混ぜ合わされる時)までは存在していない。
そういうふうに考えると、入れ子理論における成長というのは、実質的には(その生物の、極小のミニチュア状態から始まる)巨大化かもしれない。しかしたいていの人の、子供の頃と大人になってからを見比べると、単なるそのままの巨大化という印象は受けないと思う。それに、ブルーメンバッハ自身そのように考えていた節があるように、生物には、死なない程度の部分的な体の破壊に関しての修復機能がおそらくある。つまり巨大化するのは本質的な部分だけ(ただしその本質的な部分が「造られる」のではなく、「はなから存在している」というのが非常に重要だったと思われる)。例えば入れ子理論が正しいとしても、入れ子になっているのは、最終的な全構造のミニチュアではなく、本質的構造のミニチュアと思われる。
仮に、親から子へと受け継がれていくものが、暗号でなく、ある種の構造そのものであるとするなら、以下のような考えに至るかもしれない。
まず、その構造が小さな時だけ、変化自由性(拡張性)が高いと考える根拠はあまりないと思う。それならば、その受け継がれる物理要素こそ、その生物の種を決めるような本質的な基本構造であって、例えばそれが崩れてしまったら、成熟した生物を殺せるように、その小さな段階での存在もおそらく殺せる。ただし生物としての本質は、別にそれだけで生物構造の全てでなく、おそらく生命力と呼べるような何らかの力か原理によって、その本質自体を壊さない程度に周囲の構造を変化させられる。それが各種の生物の外見とか性格とかの多様性に関わっている。しかし本質は変化できない。
そういう訳で、もっと自由なものではなく、ある種の中の多様性を広める程度の進化論が支持されたのだろうか(もちろん奇妙な宗教信仰の影響もあったと思われるが。物事はそう単純ではない)。
本当に、情報が最も重要か
しかし入れ子理論は、本当に完全に間違ってたろうか?
遺伝子と呼ばれるものは、生命の設計図の暗号文と、その暗号文を示すための分子構造。しかしその分子構造自体は、少なくとも単体では完成形のミニチュアとはとても言えないようなもの、というのはほとんど確かな話。
しかし、世界のどこに遺伝情報があっても、それがうまく機能するわけではない。それは特定の生物の卵と呼ばれる構造の中でしか機能しない。機械のプログラムコードが、機械がなければ(いわば機械の背景情報として設定されていなければ)機能しないように。
卵という構造は何だろう。我々の現代の知見が、本当にかなり生物世界のシステムをうまくとらえているものなら、そのような物理構造を人工的に作ることができれば、あとはそこに遺伝情報を注入して、古い錬金術の伝説におけるホムンクルス(人造人間)を作ることも、理論的には可能なはず。
だが、そんなことが本当に正しいなら、その行いは、生物を造るのに必要なものが特定の物理構造だけ、ということの、まさに実質的な証明でなかろうか。
とすると、まさにブルーメンバッハが生きていた時代には、今よりずっとそう考えるのが一般的だったと思われるようなこと、この人間の理性と呼ばれるものが魂と呼べるものを原因としている、という推測はどうなるか。
その魂というのは、ある種の物理構造が生み出すものと考えていいのだろうか。それとも、上記のような生命、遺伝、進化システムは、魂とは関係ない領域の話なのだろうか。例えば、魂自体は世界のあちこちに充満しているようなもので、人間のような理性を持つ生物の構造が発生した時、その構造と重なっている部分が、我々の言う魂として機能する、というような。そういうものとでも言うのだろうか。
生物と無生物の巨大な隔たり
生命力というものが、この世界のどこにでも存在する、というようなものではないとする。それなら生命力の存在している場そのものが、生物であって、そしてそれは、生物と無生物をはっきりとこの世界の中で分ける基準にもなりうるだろう。
ブルーメンバッハは、形成衝動という生命力に、そのようなはっきりとした基準になりうる、独自の特殊性を見出していたようだ。
〔私ほど、自然が、生物と無生物の間に、あるいは組織された生物と無機生物の間に設けた、巨大な隔たりに関して、深く確信している人はいないだろう。私は、全自然の段階的順序や連続性を支持する人々が、その梯子を想定するために行ってきた知的な創意工夫には心から敬意を表する。しかし彼らも、組織化された領域から、無生物の領域への移行を考える場合、とても大胆すぎる飛躍を避けられるとは思えない。
しかし、その事実自体は、それら、創造物の2つの主要な部分の一方の現象を参照することで、もう一方の現象を説明するというような方法を否定するものでないと思う。
だからこそ私は、ここでの議論が、組織化された領域における独自的な形成衝動をすっかり証明できるようなものと、考えてはいない。実際に、他の領域(無生物の領域)でも、同じような、形成する力の痕跡は、かなり一般的に見つけられる。
私が見出した形成衝動というのは、単に普遍的な形成する力というよりも、まさにある種の生命力と言えるものだ。したがってそれは決して、無生物の創造物に発見できるようなものではない〕
本質的にどういう原理であれ、何らかの生物に特有の要素(生命力)が存在しているとする。そして、それが決して無生物の変化の中で生じることがないようなものだとする。つまりそれ(生命力)が、生物世界に完全に孤立している要素であるならば、それは明らかに、「無生物から生物が生まれることはない」というシステムを示唆しているだろう。
つまりは、この世界が生じた時から、生物が存在していたという世界観。誰かが創造したかどうかはともかくとして、最初の時点で生物が生物であった宇宙。
この辺りの(ようするに、無生物から生物が発生することは決してないという)話に関しても、今の我々には、非常に重要な否定の根拠がある。我々は、「我々の生きているこの地球という惑星が存在する前から、宇宙が存在していた」というような仮説にも、とても馴染んでいる。
自然世界に普遍的な形成力。生物の形成力
しかしブルーメンバッハは、無生物の領域にも、そのような(生物の形成衝動とは異なるようだが)形成する力があることはしっかり認めている。それをどのように考えていたろうか。
〔無生物の自然領域においては、そのような(形成する)力の最も明確な証拠は、特定の非常に規則的な地層に確認されている。それは、それが形成される前の段階から、形成される過程で生じた痕跡。
ほんの数例を挙げるが、例えば特定の金属結晶は、おそらくそれ以上のものが存在しないというほどにエレガントなものだ。その外形は特定の有機体によく似ており、形成のアイデアに非常に役立つ模様を提供してくれる〕
そして自然界に存在する様々な鉱石が示唆する、明らかに存在しているある種の形成の力について簡単に書いてから、ブルーメンバッハは、あらためて、生物の独自の形成力、形成衝動について説明を試みる。だが、それがどれほど困難なことであるかも、彼はしっかり理解していたようだ。
〔公平な目で見れば、この衝動の存在と有効性を視覚化する実用的な方法は、そのような組織化された体の生成と再生を偏見なくひたすら観察すること以外にないだろう〕
先に書いた、ヒドラの観察なども、その研究の方法を実践した一例と言えよう。
ブルーメンバッハは、再生したヒドラが以前よりも小さくなってしまったことに関しては、それは明らかに再生を急ぎすぎたためと理解した。もちろんヒドラが意識的に再生を急いでいたとかいう訳でなく、形成衝動が、自然の中でかなり強引に機能した、というような。
それは、確かに、生物の形成力と、もっと自然界に普遍的な形成力が異なるものであって、そのために生じる歪みの現象というような印象を与える。
また(彼の時代において代表的だったらしい)進化論的な遺伝原理、つまりは、世界中に散らばる覚醒を待っている生命の種子群、あるいは入れ子の卵の、どちらであっても、切り離された組織が繋がる形での再生は奇妙だとも、彼は言う。
つまり、やはり重要なのは、遺伝されていく小さな完成形(ミニチュア)とかでなく、生物の領域特有の形成衝動でないかと。
それでも、遺伝子コードを連想させるような推測とかは、ブルーメンバッハの本からは読み取れない。それにたどり着いていてもおかしくなかったと思われるのに。それが当時の基準で、どれほど異常な考えであるのかが窺える
自然の手引き書。この世界の全ての分類
ブルーメンバッハは、人種分類についての博士論文(1775)から、わりとすぐ後に、自然世界のより広範な領域(というか、おそらく、彼が認識していたほとんど全て)の諸々の分類を試みる、『自然の手引き書(Handbuch der Naturgeschichte)』も書いている。
これは、最終的に12版を重ね、その内容からして、ブルーメンバッハの理解していた自然世界のことを浮き彫りにするための参考書として、先の2冊よりも、より有用かと思われる。
第6版の序文では、まず、それが第5版からあまり内容を加えてはいないものの、過去のどの版より多くの情報を扱っていると書いている。しかし、扱っている情報が多くなっているために、本の長さの調整的な問題で、いくつかの部分の記述は短くせざるをえなかったことも。
ただし、決して他の理由で制限をかけるべきでなかった(つまり、記述の長さなど気にせず、しっかりと説明するべきな)ことが、2つあると彼は書いた。
それらについては重要というよりも、しっかり説明しないと、意味を歪曲して受け取られてしまいかねないから、らしい。ただ、そういうふうに書いてはいるが、それらは他の本でも、彼がとても重要に感じていると思われることだ。
つまり、”自然界の存在の連鎖(catena entium in natura)”と”組織化された体の生成(generatio ordinata corpora)”。
もちろん前者は生物分類の上では重要な思想。実際この思想のためにブルーメンバッハは、人種分類の時に、知的能力などの差が見出せないにも関わらず、人種に序列を想定した。
後者は、生物世界の背景システムを考える場合に、非常に注目すべきと思われる現象。例えば、次世代の子供に、前の世代から何かが受け継がれているとして、それがどのような物理構造か、最低限何が必要なのかが、その生成の原理によって変わってくるだろう。そして生物世界に必ずあるはずのこの現象こそ、生物と無生物の違いが何かを、明確に定義するための重要な手掛かりかもしれない。少なくともブルーメンバッハをそう考えていた節があるわけだが、その認識は、現代でも全然奇妙なものでないと思う。
自然物と人工物。芸術と芸術的な自然
世界の物事を分類していくなら、最も基本的なものとして、自然物(corpora naturalia)と人工物(corpora artificialia)がいいだろう、とブルーメンバッハは書いた。
〔私たちが、地球上で目にするすべての物体(その形態や構造)は、私たちの目には、創造主(Creator)から与えられたものか、あるいは自由法則や自発的な自然の作用を通じて獲得されたものだ。あるいは、人間や動物によるそれらの使用、または単純な偶然の影響から、それらが受けた変化によってもたらされる。
私たちは、最も根本的な部分の分類のために、これを基準にした。つまり最初に、すべての物体を自然物体と人工物体に分類した。
私たちは、人間がまだ本質的な変化を与えていないすべての物事を第一の区分、そして人間が意図的に新しい形を与えた物事を第二の区分とした〕
それは、(人間が分類してるからか、この世界で人間が非常に特別なのかはともかくとして)、実用的にも理にかなっていると思われる。
ただし、この基本的な分類が、非常に曖昧なものであることも、彼はしっかり認識している。例えば、人間が自然のものと思われるものを、単に確認したり、コレクションしたりする過程でも、結局のところは、人工的影響が発生していて、実質的には人工物になっているかもしれない。というような。
また、ブルーメンバッハは、全ての芸術と呼ばれるものは、人工的なものとしたが、一方で〔自然の産物の多くが芸術作品に似ている〕ため、そういう点でも区別が非常に困難だとした。
芸術作品のような自然物に関する、興味深い1つの例として、ブルーメンバッハは、(おそらく)バイアエのピシーナ・ミラビリス(Piscina Mirabilis)という貯水槽に関しての議論を紹介している。
曰く、その(古代ローマにおいて最大のものだったらしい)貯水槽を覆う塗装の性質について、それが人間の芸術か、自然の産物かで、研究者の意見が対立したとか
特に芸術に関する考古学の研究家であったヴィンケルマン(Johann Joachim Winckelmann。1717~1768)と美術への関心が強い哲学者として有名なディドロ(DenisDiderot。1713~1784)は、それを人工物(人間の必要性を贅沢のために意図的に作られたもの)と考えた。一方で、考古学者アンドレア(Andrea De Jorio。1769~1851)や、マルクアール(Marquard)なる人はそれは、「水の影響による石灰岩の堆積物」と推測したのだという。
ちなみに、ブルーメンバッハ自身が、どちらが正しいと考えていたかは不明。
自然の三界は、どのように機能しているか
芸術的な構造が自然の中によく見いだせる、というのは、ブルーメンバッハにとっては、それほど驚くべきことではなかったかもしれない。人種分類の本でも、そのような考え方がよく読み取れるが、彼はこの世界自体をある種の神の芸術作品的なものと考えていた節がある。
しかし、やはりより重要であったのは、最初に創造された何かから続く、(この世界そのものの構造とも言えるだろう)複雑な連続的連鎖。
だが連続性を見いだす、具体的な手掛かりはあるだろうか。あると考えてたろう。彼も。
そしてそこに見出せたものに、自然と人工物、はっきりと区別する何かもあるだろうか。
〔第一に、自然界のある個体は常に、それと同じ種、同じ形状の他の自然体により生成される。そのため、それらの存在には、最初の創造に遡れる、類似個体の継続的な連鎖を想定できよう。
第二に、それら同じ個体は自分自身を養う。さまざまな異物を取り込み、自身の体の要素と同化させる。この作用により、腸に吸収(intussusception)されて成長する。また、私は以前の自然史で、現在の創造においてさえ、新しい種の組織体が事後に創造されたかのように生成される、という事実を提示した。
第三に、前の二つの特性は、自然体区分において特定の構造を前提としている。私が述べた方法で栄養を獲得し、さらに同種の他の存在を再生産するためには、それらを可能とするための組織が必要になるだろう〕
ここでは自然物ならではの性質について書いているわけだが、さらに第三のところの続きでは、生命と非生命との区別に関わる考え方も見られる。
つまりブルーメンバッハは、〔血管、静脈とかいった、生命体のあらゆる目的のために機能する、生命力によって活気づけられた器官〕は、生物独自のものとした。他のもの、つまり無生物のものに関しては、そのような生命力を背景とした器官は持たないとも。
だからこそ、無生物の物質は成長をしない。ただ、化学的、機械的な法則に従って、動作したり、変化するだけと。発生の本でも書いていたように、ブルーメンバッハは明らかに、生命力という、生物以外には影響を与えないような(物理的なものか非物質的なものかはともかくとして)特殊な力を想定していた訳である。
そして生命力の影響を受ける組織体には、必要な栄養分を(基本的に)受動的に吸収するものと、能動的に接種する(自らに取り込もうとする)ものの2タイプがあるという。もちろん前者が植物で、後者が動物なのだと、ブルーメンバッハは語った。
こうして古くから自然の三界とされる、「動物、植物、鉱物」、あるいはそれらをそれぞれに含む、自然物の3つの区分が明確となる。
区分の否定。連続性の問題
自然の三界説に対しては、主に2つの反対意見があるとブルーメンバッハは言う。そして彼はどちらにも反論する。
まず、1つめの反対意見は、「動物と植物を別の区分にする必要がない」というもの。
ブルーメンバッハは、まず、自然の様々な異なる対象物を比べた時、基本的には、それらを同じものと認識するよりは、区別する基準となる違いを発見する方が容易いと考えた。それは明らかだと。だからこそ、かなり異なっていると思われる様々な別種の動物たちの間にも、結局のところ、多くの共通点を見出せる。
彼は、(巣の中にいるミツバチのように)冷血動物とされている生物も、かなり暖かい熱を維持する場合があるという例を出している。これは、そもそも温度調整できる生物種、調整できない生物種というような区分が疑問視されている、現代的な観点から見て、なかなか興味深いものかもしれない。
ともかく、少なくとも動物と呼ばれている各種は、かなり離れている系の場合でも、ある程度の動物的特徴を共有しているらしい。しかし、動物と植物を比べた場合は、そのような共有される動物的特徴など全く見当たらないとか。
そして、2つ目の反対意見は、より単純に、そもそも「そのような自然界の区分など存在しない」というもの。文字通り全ての世界の物事は、生物だろうが無生物だろうが、全てが連続的に連鎖しているものだと。
それは、「自然界には飛躍などない」という主張でもあるそうだ。あるいは、「創造の完全な秩序を追求する」試み。
しかしブルーメンバッハは、そんなもの、かなり無茶な考え方と理解していたらしい。
どうも、この世界の自然物の存在量のアンバランスさ、というようなものに彼は注目していた。自然界を観察すれば、ある生物種と近い生物種はものすごく大量にいる一方で、全く孤立したわずかな生物種もいる。完全に計画的に連鎖的な世界であるなら、そのような存在比率の違いは確かに奇妙かもしれない。
再び、入れ子式の進化論
自然の連続性、三界分類、創造の連鎖(または梯子)。この3つの考え方が、ブルーメンバッハの世界を理解するための哲学において、常に重要だったことはほぼ間違いない。しかし彼は、完全な秩序を前提とはしていなかった。
普通に考えると、この世界に完全な秩序が存在していると考える(そのような第一原因からの存在の連鎖があると考えるような)人であっても、この世界の部分における変化という現象を否定することは難しいと思う。
例えば、そのような部分的変化がないというのなら、そもそも我々は、どうやってそういうものがないとかいった仮説を考案できるのか。
仮に、この知能とか言うものが、ある種の物理的動作であったとしたら、それが全く変化のない世界でも機能するだなんて、奇妙な世界観だ。
一方で、この知能とかの原因が、魂的な非物質的なものであるとする。それならそれで、まさに我々のこの意識的な思考とか、それに影響を受けた動きとかが明らかにある(物理世界に、非物質的な原因の変化があるはず)。そしてブルーメンバッハの世界観は、どちらかというとこちらに近かったのだと思う。彼は、(完全に非物質的と言えるかはよくわからないが)少なくとも特定の物理構造、あるいは基礎的物質のみに影響を与える、生命力という特殊要素を想定していた。
どうも彼は、全ての物質に影響を与える物理法則と、それとは別の、生物の組織構造の生成や成長の原因(生命力)が、この世界にあると考えた。そうすると、自然界の様々な観察結果の説明がつくと。
例えば自然界のアンバランスさについても、2つの異なる影響範囲の力が、複雑に干渉しあった結果というように考えることもできると思う。
生物の形成に、生命力が具体的にどのように作用するのか。
ここでもブルーメンバッハは、有望そうな理由として、入れ子式の生命の芽の進化論を考察している。
〔進化論の最も有名で熱心な信奉者は皆、あらかじめ形成された生物の芽が母親の卵巣に含まれており、受精の際に父親からの精液によって目覚めて発達する、ということに同意している。したがって、私たちが受胎と呼ぶものは、深く眠っている胚芽が、精液の与える刺激によって目覚める現象にほかならない」
一方で、ある組織体の特定の種が数世代にわたって種を生むと、最終的にはある種が別の種に完全に変化する可能性にも、ブルーメンバッハは触れている。そういうこともありうると考えた根底には、生命力がもたらす世界の複雑さの可能性もあるだろうか。