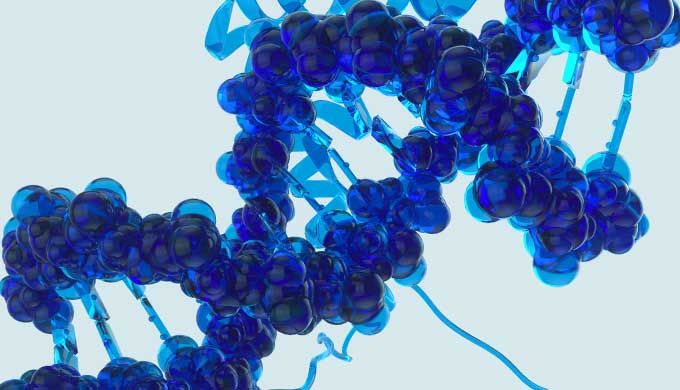胎内感応という古くからの説
進化論も遺伝子も認めていない者が多かった19世紀でも、 子が親に似ているということは常識であった。
髪や瞳や肌の色、身長みたいな見かけはもちろん、特定の病気への耐性や、精神障害の度合いまで、子供に受け継がれる場合があるとは、多くの者にすでに理解されていた。
ただそのような遺伝が、どのように原理で起きているのかはかなり謎だった。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
まずどう調べればよいかもわからず、様々な迷信ぽい俗説が生まれたという。
例えば、特に古くから広くささやかれていた俗説が『胎内感応(maternal impression)』である。
妊娠中の女性は、胎児と「臍帯」、いわゆる「へその緒」という管で繋がっている。
そこで母体と胎児の間には強い繋がりがあり、物理的なこと以外に、母親の精神状態なども胎児に強く影響するというのが、胎内感応という説である。
特に中国を中心とする東洋世界では、母親の環境を整え、その精神状態を良好な状態に置くことで、優れた子供を産んでもらおうという思想は、『胎教(prenatal care)』と呼ばれたという。
子供が両親(あるいは近しい親戚)に似るのは、母親の周囲で影響を与えている人たちが、たいていそういう人たちだから、と 胎内感応を信じる人たちは考えていたのかもしれない。
シナプスはへその緒を介するか
臍帯の役割は胎児への栄養供給である。
現在では、臍帯には神経がないために、少なくとも昔の人が考えていたような形では、母親の精神(今ふうに言うならシナプスの発火)が子に影響を及ぼすことはないとされている。
ただ原因はともかく、妊娠中の女性は精神状態が不安定になりやすいのは、かなり確かであり、強いストレスが結局母親の健康状態にも影響を与え、それが胎児への栄養供給過程に問題を発生させる場合などは普通にあると考えられる。
 「ストレス」動物のネガティブシステム要素。緊張状態。頭痛。吐き気
「ストレス」動物のネガティブシステム要素。緊張状態。頭痛。吐き気
実際にどういうのが恐れられていたか
古くは、胎内感応に関する、まるでホラー映画のような話も結構あったという。
例えば妊娠中にイチゴを食べたいという欲求を満足させることができなかった女性が、赤いシミだらけの子を産んだとか。
石炭の袋に頭をぶつけた女性が、頭の半分だけに黒い髪が生えている子を産んだとか。
海の怪獣への恐怖を抱いていた女性が、鱗に覆われた子を産んだとか。
 『シーサーペント』目撃談。正体。大海蛇神話はいかに形成されたか
『シーサーペント』目撃談。正体。大海蛇神話はいかに形成されたか
夫が演劇で悪魔の役を演じていた女王が、角を生やした子を産んだとか。
 「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
こういう記録が堂々と真実っぽく残っている場合は、(単に敵対する人が流しているプロパガンダかもしれないが)普通それは奇形児の話だと解釈される。
しかしそうなると、その子供の原因となった母親の体験というのは後付なんだろうか?
核酸の発見
フリードリッヒ・ミーシェル(Johannes Friedrich Miescher。1844~1895)は、グレゴール・メンデル(Gregor Johann Mendel。1822~1884)とほぼ同時代人である。
エンドウを使った有名な実験により、『遺伝子(Gene)』というものがいかに次世代に伝わっていくのかを示しながらも、生前にはろくに評価されなかったメンデルであるが、ミーシェルも同じようなものだったらしい。
ただ彼は、メンデルとは違って、少なくとも普通に、科学者、研究者としては、多くの人から認識されていたようである。
 「メンデルの法則」分離、独立、優性、3つの法則とその例外。遺伝子地図
「メンデルの法則」分離、独立、優性、3つの法則とその例外。遺伝子地図
少年期からの難聴により、聴診器を上手く使えないことから、元々志していた医学の道をあきらめた時、研究者の道を進めたのは、婦人科医だった父だったという。
そして1868年頃にミーシェルは、テュービンゲン大学のフェリクス・ホッペ=ザイラー(Ernst Felix Immanuel Hoppe-Seyler。1825~1895)の助手となった。
悪魔に取り憑かれたような研究熱
ホッペ=ザイラーは、血液細胞に含まれる化学物質のリストを作りたいと考えていたようだが、「白血球(Leukocyte)」の研究をミーシェルに任せた。
彼にとって幸運だったことは、白血球は「核構造」を持っていたこと。
『細胞核(cell nucleus)』は細胞内の、遺伝物質を貯蔵する「小器官(organelle)」であることが現在はわかっている。
しかしミーシェルの時代は、いったいそれが何のために存在する部分なのかまったく不明で、その(細胞全体の)空間を占めるわずかなサイズから、あまり注目されてもいなかった。
しかし当然のことながらまったく何もわかっていなかったのだから、それを研究すれば何か新しい知見が得られる可能性は十分にあった。
ミーシェルはそうした新しい発見を求め、地元の病院から提供してもらった包帯から採取した白血球を使いまくって、その核を、非常に集中して研究した。
本当に一心不乱だったらしい。
ある時など、研究の集中が続きすぎて、自分の結婚式を忘れてしまい、友人が大慌てで研究室から彼を連れて行ったという話もある。
それほど彼が研究に熱心だったのは、自分に自信がなくて、才能を努力で補うしかないと考えていたためらしい。
しかし当時の何人かの知人は、彼が悪魔に取り憑かれているから、などと噂していたようである。
膿の中の白血球
外部からの異物や、他の部分に害なほどに異常な変化をしてしまった細胞(癌)などを、生体から排除したりする自己防衛システムを「免疫系(immune system)」という。
白血球はそのような免疫システムを実行する、免疫細胞である。
生体が、打撃とか急激な温度変化とかで傷ついた場合、免疫系は、もう邪魔なだけの損傷した組織を溶解したりして、マクロ視点的(意識的)には、煩わしい痛みとかが発生したりする
このような現象を「炎症(Inflammation)」というが、特に死滅した組織の残骸が液化したのが溢れたりする炎症は「化膿(Purulence)」と呼ばれる。
化膿の際には、傷口から「膿」とか膿汁とか呼ばれる、黄白色でアルカリ性の液体が発生する。
これは微生物や損傷組織、それらを殺した白血球などの残骸の塊とされるが、ミーシェルにとって重要なのは、それには大量の白血球が含まれていることであった。
彼の最も有名な功績は、その膿から得られたものだった。
ヌクレイン
病院で使用された後の包帯についていた膿を、ミーシェルは、まずは温かいアルコールで、次に豚の胃袋から抽出した「酸(Acid)」で洗った。
そして海から抽出された、潰されたような、ようはペースト状の物質を、彼は『タンパク質(Proteins)』だと推測した。
 「タンパク質」アミノ酸との関係、配列との違い。なぜ加熱はよいか
「タンパク質」アミノ酸との関係、配列との違い。なぜ加熱はよいか
しかしそれは、タンパク質としてすでに知られていた他の物質に比べると、「塩水(Brine)」や沸騰させた「酢(Vinegar)」、「希塩酸(Thin hydrochloric acid)」などにあまり溶けなかった。
ミーシェルはさらにそれを「炭化(Carbonization)」させて、炭素水素、酸素、窒素を得た。
さらにタンパク質にはないと考えられていたリンもわずかながら取り出せたことから、これは何か特殊なものを発見したのだと、彼はいよいよ確信したとされる。
彼はそうして、膿を処理して得られた特異な物質を、『ヌクレイン(nuclein)』と名付けた。
これはつまり『核酸(nucleic acid)』、すなわち現在、『DNA(デオキシリボ核酸)』とか『RNA(リボ核酸)』とか呼ばれている物質の発見であった。
ミーシェルは1871年にその功績をしっかり認められもしたようだが、彼が発見したDNAの、遺伝における重要性など、その時は誰も知らなかった。
ミーシェルも当初、わずかなリンが発見されたことを根拠に、核酸はその貯蔵庫だと考えていたようである。
細胞核はDNAの入れ物か
ミーシェルの発見からそんなに経たない間に、核酸にはさらに小さな構成分子がいくつか含まれていることが明らかになってきた。
リンと「糖(sugar。デオキシリボース)」。
それに「塩基(base)」と呼ばれる四つの化学物質、すなわち「アデニン(A)」、「シトシン(C)」、「グアニン(G)」、「チミン(T)」。
だがそれらの小物質がいったいどのように核酸を構成しているのかは、今の我々にはお馴染みの二重螺旋構造の確定まで、謎であった。
DNAが遺伝物質として広く理解されるようになったのは20世紀だが、19世紀の時点で、すでにいくつか重要なヒントがあったらしい。
例えば細胞分裂の際に、必ず同じように分裂する染色体は、おそらくは生殖細胞を介して親から子に伝わること。
さらにその染色体のほとんどの部分はDNAで構成されていることなどは、19世紀後半には明らかにされていたとされる。
ミーシェルは白血球からオスの生殖細胞である「精子(sperm)」へと対象を変えて、さらに研究を続け、すべての細胞核にはDNAが含まれていると結論した。
彼は細胞核というのは、DNAの入れ物として再定義すること。
さらには、DNAと遺伝物質かもしれないとすら主張したが、そのことを他の者に認めさせるには証拠が少なすぎた。
ただ今となっては、ミーシェルはかなり正解に近かったことはわかる。
たった4文字で、それほど多様性を生み出せるのか
染色体にはDNAだけでなく、タンパク質の塊も結構含まれている。
そしてDNAが情報コードとして使っている可能性のある四つの塩基、すなわちA、T、G、Cだけでは、生物の多様性を表現するのに 少々物足りないような印象があった。
一方でタンパク質は、20ものアミノ酸を組み合わせて構成されるのだから、遺伝情報を記録する文字としては、そっちの方が説得力あるものに思われた。
しかし、たった4文字とは少ない
一次ソースだけで考えると、そういうふうに思えるが、(後に明らかになったように)表現形質として現れるまでの過程を考えると、最初の文字がわずか4文字であることは、多様性を説明する上でそんなに不利なことではない。
今は、遺伝子コード配列の中で、三つの塩基文字が組み合わさった「コドン(codon)」と呼ばれる単語(配列)が、ひとつのアミノ酸を意味することがわかっている。
その情報と、我々という存在(ヒトと呼ばれる形質)の繋がりについて考えてみる。
つまり、遺伝子が指定したコード、コドンはあるアミノ酸を作る。
アミノ酸は20種類だが、文字の数によって当然それで構成されるタンパク質の数や組み合わせは変わってくる。
遺伝子がある程度十分な長さの文章を表現できるなら、もうその時点で結構な数のタンパク質の組み合わせを作れることになる。
我々のような多細胞生物の場合、全細胞が一個体を構成するために作るタンパク質の数とその組み合わされるパターンは、宇宙に存在する全原子の数よりも多いかもしれない(本当にそうなら、星の数でも途方もない数として表現されるのに、さらにひとつの星に途方もない数ある原子の全部というわけだから、文字通り超途方もない数になるだろう)
ダーウィンvsメンデルの時代
20世紀になったばかりの頃。
ダーウィンの進化論は信者を増やし、メンデルの遺伝子仮説も復活した。
これら二つの学説は互いに相容れないようなイメージがこの時にはあって、二つの学説のどちらが正しいのか、ダーウィン派とメンデル派の間には、わりと泥沼な論争が起きていたようである。
 「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い
「ダーウィン」進化論以前と以後。ガラパゴスと変化する思想。否定との戦い
適者生存の進化論
ダーウィンが唱えた「適者生存(survival of fittest)」、つまりその時の環境に最も適応した変化をした者が生き残り、次世代の種をまくという進化のメカニズムには、ひとつ重要な問題があるように思われた。
つまり、その時々の環境に有利な形質の変化というのが、いったいどこから起こりうるのかということ。
適者生存は、適者が生き残ることは説明しても、それがどのように出現するのかを説明していないという意見もあった。
ダーウィンは、そのような「自然淘汰(Natural elimination)」のメカニズムは、個体ごとのごくわずかずつの変化の積み重ねにより、我々ごときのタイムスケールでは気づきにくいほど、ゆっくり長期的に作用するのだと主張したとされる。
ダーウィンが言うような長期的なメカニズムは、進化論者の間でさえ受け入れ難いものであったようだ。
ダーウィンに味方していた多くの進化論者も、たいていは、時に生物は急激な飛躍をすることがあるというふうに考える向きがあったとされる。
ダーウィン自身はこの点に関してはかなり頑固だったらしい。
ゆっくりとした作用で進化論を説明することが難しいと考えられたのは、(環境によく適応しているという意味で)優れた子が誕生したからといって、即座にそれに負けている者たちが全滅するわけではなさそうだからである。
仮に優れたものが発生したとしても、そいつらは他の劣っている者たちとやはり混じりあい、結果的には平均的な子供を産むだろう。
このようなプロセスは簡単に想像することができよう。
生物の集団というのは、そうしてだんだんと平均的な状態に近づいていくと考えられるから進化といえるような現象には繋がらないのではないか、と考えられたわけである。
そもそもダーウィンがゆっくりした作用にこだわっていたのも、上記の理由である(つまり優れた個体が生まれても、次世代では他の個体に、その特性が薄められてしまうに違いないから)。
メンデルの法則と、その再発見
メンデルの遺伝説はどうだったのだろう。
メンデルのエンドウの研究は、遺伝の兆候だけでなく、急な変化の可能性を示していた。
メンデルは、エンドウの豆の色や、茎の長さなど、かなりはっきりしている形質を基準にした。
そして、子は両親から両方の遺伝子を受け継ぐこと。
そうして受け継いだ、ある部分の形質に関するふたつの遺伝子が異なっていた場合、優性的な遺伝子が形質として現れること。
形質としては現れない劣性の遺伝子も、消えるわけではないので、それがさらなる次世代に引き継がれることもあることなどを、示した。
メンデルの法則が、1900年になって再発見された時。
細胞内の染色体は似たようなもの2つが対になっていること。
あらゆる生き物は母親と父親から等しい数の染色体を受け継ぐことなどは確認されていたから、そこで生物の多様性を生んだ物語がはっきりと浮かび上がった。
メンデルが考えたように、遺伝子、すなわち染色体は次世代へと受け継がれていく。
そして時々、遺伝子は突然に変化、つまり『突然変異(Mutation)』する。
そして突然変異で生まれた新しい遺伝子も次世代に受け継がれていく。
世代を繰り返すことで、その遺伝子が広がっていくと、それが優性にしろ劣性にしろ、多くの種の形質に表れてくる。
というようなことがいくつも起こって、現在の生物の多様性に繋がった。
 DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
DNAと細胞分裂時のミスコピー「突然変異とは何か?」
それは愚かな内戦だったのか
現代的な視点で見てみれば、進化論学者と遺伝学者が、互いの正しさを信じて争いあっていたというのは、わりとまぬけに思える。
実際当時の知見だけでも、遺伝学と進化論は、それほどまでに相容れなさそうなものであろうか。
単純に、突然変異の遺伝によって運よく発生した環境的な優位者が、適者生存によって次世代の勝利者となる、と考えてはいけなかったのだろうか。
敵対しているがゆえのプライドか何かの問題なのか、なぜか仮説を統合しようと考える者は少数派だったようである。
メンデルの信者の中にも、染色体説、突然変異説、遺伝説など、少し頑張ればひとつにまとめれそうな、バラバラの仮説を支持する者たちの間での、争いすらあったという。
結果的には、生物学内の愚かな内戦と言えるような、その状況を終わらせる立役者となったトーマス・ハント・モーガン(Thomas Hunt Morgan。1866~1945)は、それこそ ダーウィンなんて目じゃないくらいに頑固な面を持つ実験至上主義者だったらしい。
ハエ部屋での発見
ハエとゴキブリとネズミ
モーガンは、ダーウィンの仮説もメンデルの仮説も推論ばかりで、ろくに根拠がない仮説であり、特に信じる理由もないと、最初は考えていたという。
ところで、種は時に劇的な変化をすることもあるという突然変異説を唱えたのは、メンデルの法則の再発見者の一人とされるユーゴー・ド・フリース(Hugo Marie de Vries。1848~1935)である。
モーガンは彼に影響を受けていて、アメリカはニューヨークの、コロンビア大学に籍を得てからは、動物の突然変異期の研究をすることに決めた。
最初はマウスやハトなどを実験動物として使おうとしたようだが、繁殖に時間がかかりすぎるため、結局ショウジョウバエに白羽の矢を立てた。
 「ネズミ」日本の種類。感染病いくつか。最も繁栄に成功した哺乳類
「ネズミ」日本の種類。感染病いくつか。最も繁栄に成功した哺乳類
ショウジョウバエはモーガンの研究においてかなり理想的な生物であった。
12日に一世代という短期間の繁殖と世代交代。
安い餌で飼いやすく、牛乳瓶に1000匹を共存させられる。
そうして、コロンビア大学のモーガンの実験施設は「ハエ部屋」となり、モーガンとその助手たちはハエチームとなった。
ハエ部屋は控えめに言って不潔で、ゴキブリやネズミなどもうようよしていたとされる。
 「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
突然変異と遺伝子の地図
奇妙な模様を持った個体、体の色や目の色が明らかに他者と異なっている個体など、モーガンらは、ハエの突然変異を、確かに確認できた。
そしてモーガンらは、メンデルとほとんど同じような方法(つまり交配実験)で、ハエの突然変異の形質がどういうふうに遺伝するかを確かめてみた。
すると遺伝法則が正しいこと以外に、もうひとつ重要な事実が浮き彫りとなった。
どうも、調べていた突然変異遺伝子は、性別を決定する遺伝子と繋がっているようだったのである。
ようするに、それまでは基本的に(なぜか?)1つの染色体につき1つの遺伝子と考えられていたのだが、モーガンは、1つの染色体に複数の遺伝子が乗っかっている可能性にたどり着いたわけである。
モーガンたちはさらに、同じ染色体に乗っていると思われる遺伝子の連鎖が、時には起こらないことから、 染色体が分裂の際に、相同な互い同士で、遺伝子を交換し合うことがあるとした。
また、連鎖が起こる比率の原因を、染色体上における、遺伝子の位置関係の問題だと考え、遺伝子の地図さえ作成した。
そして、モーガンらが提案した新しい(とはいってもオリジナルのアイデアなどはあまり使われていないので、実際には新しいかは微妙な)遺伝子モデルは、以下のようなものだった。
全ての形質は遺伝子に制御されていて、遺伝子は染色体の上で繋がりあっている。
生物が両親から染色体のコピーを1本ずつ受け継ぐ時、親の遺伝形質は当然子へと伝わるが、その時に遺伝子の乗り換えも起こり、新たな個体には新たな個性がつく。
ただ、その変化はあまり大きくないので、基本的には子は親に似る。
モーガンらの示した遺伝子の地図は線であり、遺伝子は染色体であるという仮説を大きく強めた
悪魔が明らかにしたこと
優秀な助手の理論
モーガンは優秀な3人の助手に恵まれていたとされるが、ハーマン・マラー(Hermann Joseph Muller。1890~1967)はその内の一人だった。
ある意味モーガンとは正反対の理論家である彼は、自分たちの研究結果は明らかに、ダーウィンとメンデルの学説を補強しあっていることを示していると考えて、それをモーガンにも納得させたとされる。
マラーが明らかだとしたのは、 ある一つの建設はメンデルが主張していたように一つの遺伝子によって決まるのではなく複数の遺伝子の 総合的な制限によって成り立つ場合が多い するとか答えがどのような遺伝子セットを受け継ぐかによって、個性のグラデーション(連続的な変化)が生じる。
この変化の連続性に加え、時折起こる突然変異の内、幸運的なものは、おそらくは進化を後押しする。
形質に複数の遺伝子が関わっているとしても、遺伝子それぞれは単体の粒子群として定義できるので、生存に有利な突然変異が世代ごとの交配で薄められはしない。
その有利な遺伝子がある程度の数、受け継がれたら、後はもう、時とともに種の全体に広がっていくだろう。
もちろん有利な遺伝子を持っている者は、自然環境の中において適者生存の恩恵を受ける。
ダーウィンとメンデルはここにきてようやく出会えたわけである。
マラーの功績。放射能と精子バンク
マラーは後にはモーガンとかなり仲違いしたようで、 1933年にモーガンがノーベル賞を取った時、彼はその賞金をふたりの助手と分けあったが、マラーは無視した。
マラー自身は、1915年までにコロンビア大学を離れ、 1920年にテキサス大学オースティン校に落ち着いている。
政治に関心を持つようになり、精神を病んで、1932年には自殺未遂の騒ぎがあった。
マラーは1927年に、ハエに「放射線(radiation)」を当てることで、突然変異をする確率がかなり上がることを発見。
放射線による健康への危険性以上に、研究者たちにとって重要だったことは、それにより実験のために意図的に突然変異を作れること。
マラーはこの発見で 科学者としての名声ばっかりか、単独でのノーベル賞も取ることになった。
また、優秀な、あるいは希望する者の精子を保管、貯蔵する「精子バンク(Sperm bank)」の概念を提唱したのも彼だとされる。
原子爆弾
マラーが1946年にノーベル賞を取れたのは、「原子爆弾(atomic bomb)」という次世代の兵器の影響で、科学界全体での、放射能とそれによる生物への影響に関する関心が、高まったから、などと言われる場合が時々ある。
そもそも放射線は、 サイズのわりには多量のエネルギーを有しているとされる原子の核が崩壊したり変化する時に放出される高エネルギーである。
原子の中には不安定で、ほっといても勝手に放射性崩壊を起こすものもあるが、そのような核反応を意図的に引き起こすことで、放射線(高エネルギー)を撒き散らす兵器が、「核兵器」と呼ばれるもの。
原子爆弾は、ウランやプルトニウムの原子核の分裂反応を利用した核兵器のことである。
 「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ
「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ  「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
このような核兵器が市街地に使用されたのは、これまでに2回だけ。
1945年8月。
日本の広島と長崎である。
たくさんの人が死んだ。
生き延びた人も、体の一部を失ったり、病弱になったり、奇形的になったりした。
拳を握りしめた時に爪が全て剥がれ落ちた人もいた。
黒焦げの赤ん坊を逆さまに抱き締め、もう存在しない足で歩こうとしていた男もいたという。
生き延びた者たちが証言した地獄絵図の光景の影響は大きく、アメリカは本当に原子爆弾を使う必要があったのかどうか、現在まで議論は絶えない。
これは人間という悪魔の実験だったという人もいれば、普通に戦えばそれこそ一人残らず皆殺しになるまで戦っただろう負けず嫌いな日本人たちを救うために必要だったなどという説まである。
強烈な放射線は、DNAとその周辺の水分子に選択的とされる打撃を与える。
化学結合に割り込むようにそれを切り裂き、その崩壊は連鎖して、結果的に大きな損傷となる。
 「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用  「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
原子爆弾が落とされた時期までに、遺伝子はやはりDNAらしいこと。
DNA遺伝子は、それぞれがひとつのタンパク質の製法情報を持っているぽいことなど。
それらのシステムに関する理解もかなり高まってきていた。
広島と長崎の被爆者たちへの放射線の影響は、当時の微妙な知見的にも、予想できないことではなかったともされる。
放射線がDNAを破壊すると、それでDNA内の遺伝子も壊れ、タンパク質の生成が停止し、タンパク質で主に構成される細胞も死ぬ。
すべての遺伝子が崩壊すると、もうその生物は死ぬしかないだろうが、中途半端に残っている場合は、中途半端な形質の存在となりうる。
これが放射線による人体への典型的な被害、おかしくなる体の理由であった。
遺伝情報が大きく壊れるなどの異常を関知した細胞は、自ら「アポトーシス(細胞の自殺)」を行うのが基本だが、この方法は時に諸刃の剣となる。
アポトーシスが大量に起こった場合は、もう取り返しがつかないほどに、特定の器官が潰れてしまうことも意味するからである。
二重螺旋構造の決定
DNAが確実に遺伝子であると考える者が増えるにつれて、それを研究対象とする遺伝学者も増えていった。
そして1953年の4月。
ジェームズ・ワトソン(James Dewey Watson)とフランシス・クリック(Francis Harry Compton Crick。1916~2004)のふたりが、『二重螺旋(double helix)』という言葉を大きく広めた。
それはふたつの長いDNAの鎖が、互いに巻きつき合い、螺旋階段のような構造を作っているというもの。
塩基の階段は、必ず決まった塩基のペアを作っている。
つまりAとTか、CとGである。
忘れ去られた多くの人たちの功績
この決まったペアというのは実は結構重要だった。
DNAは長く絡み合っているということは、わりと理解されていたようなのだが、問題は、塩基の組み合わせがランダムだとすると、 どうしてもいびつな形や、不安定な格好が浮かんできてしまったのである。
ワトソンとクリックは、あえて自分たちで実験を行わず、他の研究者の有望そうな理論を統合するというやり方をとったことで、二重螺旋構造にたどり着いたとされる。
そもそも二重螺旋構造を解析して、決定的なX線写真で示したロザリンド・エルシー・フランクリン(Rosalind Elsie Franklin。1920~1958)と彼らとの確執はあまりに有名であろう。
彼女のDNA研究のライバルであったらしいモーリス・ウィルキンス(Maurice Hugh Frederick Wilkins。1916~2004)が、 彼女の 写真を勝手にワトソンとクリックに見せなければ、これに関する歴史は変わっていたろうとまで言われることもある。
他にはエルヴィン・シャルガフ(Erwin Chargaff。1905~2002)が、DNA中の、AとTの量、CとGの量は同じと示したことも、かなり大きなヒントとなったとされる。
DNAからタンパク質へのプロセス
二重螺旋構造自体は、別にDNAがどのようにしてタンパク質を作っているのかを、何も説明していない。
後には、以下のようなプロセスが明らかとなった。
化学的に似たような存在である『RNA』が、まず必要な情報をDNAから自身に転写(コピー)して、 それから細胞殻に閉じこもったままのDNAに代わって、RNAはその情報をリボソームという、タンパク質を作る小器官へと運び、そこで情報通りのタンパク質が作られる。
RNAは、その役割などによって分類される傾向が強く、遺伝子情報を運ぶ役割を持っているものは『メッセンジャーRNA(mRNA)』と呼ばれる。