ケルトの社会階層と権力者の基礎知識
死後の生、あるいは生まれ変わりを信じていたケルト人たちは、死者を埋葬する時に、その人が生前に所有していた様々なものを一緒に墓穴に埋めた。
特に身分の高いケルト人に関しては、食べ物や家畜、時には奴隷なども一緒に埋められたりしたという。
 「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
当然といえば当然の話だが、社会的身分の高い者のほうが副葬品は豪華だった。
ケルト社会ではたいていどこでも、ドルイド(賢者)、戦士、自由平民の3つ、あるいはそれらと似かよった階級があったとされている。
ユリウス・カエサル(紀元前100~紀元前44)の時代には廃れていたようだが、古くは強い権力を持つ王がいたらしい。
ケルト系の各部族の指導者であった王は、大陸では「リークス(rigs)」、アイルランドでは「リー(ri)」と呼ばれ、絶大な権力をいいことに、かなり豪勢な暮らしをした者も多かったようだ。
特に有力部族の王の身の回りのものは、日用品であれ武器であれ、すべて金か銀製でいつも光り輝いていたともされる。
しかし時代が新しくなると、王の威厳は崩れていき、貴族階級の力が強くなっていく。
社会構造自体が大きくなって、集中していた権力が分散したのかもしれない。
アイルランドでは、複数部族の連合、実質的な国をまとめる上王が存在したが、名前と立場のわりにはそれほど大きな権力を持っていなかったとされる。
王が死んだ場合、次の王が先代の親族になるとは限らなかった。
ある程度は民主主義の風潮があって、多くの者に選ばれ認められた者が新しい王となっていたようである。
 「古代アイルランド」先住民族の古代遺跡、ケルトの侵略、キリストの布教
「古代アイルランド」先住民族の古代遺跡、ケルトの侵略、キリストの布教
たいていのケルト社会においては、ドルイドとは王に次ぐ権力者の座だったようだ。
基本的には戦争や外交の最高責任者であった王に対し、ドルイドたちは宗教的な教義や、様々な科学や哲学、法律関係などで指導的立場をとっていた。
戦時においては、戦士たちを従える立場にもあったとされる。
予言者と吟遊詩人
ドルイド以外にも、ウァテス(予言者)、バルド(吟遊詩人)という 特別階級があったが、基本的にはドルイドの方が上の地位であった。
基本的に、特別階級のドルイド以外は、戦士の方がそうでない者たちよりも社会的立場が上で、階層的にはその下に各自の土地や資産を所有する自由平民という感じだったらしい。
特に大陸側におけるケルト社会の階層は、主に発見されている墓などに広さや、副葬品の数によって推測されてきたものである。
しかしある程度以下の平民たちの場合は、埋葬自体されないことも普通だったようなので、平民たちの間でも、例えば職業などによる格差があったかどうかは謎である。
男女平等だったか
古代ケルト社会は比較的男女平等だった説もある。
ケルト時代(キリスト伝来以前)のイギリスにおいては、女王や女の軍隊長、女ドルイド、ようするに女の権力者も多くいたとされている。
神話などからすると、恋愛面では女性の立場が弱い印象もやや受けるが、神話はだいたいそうであろう。
 「ケルト神話」英雄と妖精、怪物と魔女。主にアイルランドの伝説
「ケルト神話」英雄と妖精、怪物と魔女。主にアイルランドの伝説
案外こういうことかもしれない。
男であれ女であれ権力者になったら、好きなだけ下の立場の者をハーレムに囲えるが、女の場合はそういうのに興味がない者が多かったとか(後は多くの異性と関係を持ったとしても、男の場合より子が少なくなるだろうから、記録に残りにくいとか)。
どこまでが創られたドルイドか
理想の古代賢者像
ローブを纏ったあごひげの賢者。
「ヤドリギ(Viscum album)」の枝と書物を持っていて、「ストーンヘンジ(Stonehenge)」のような儀式場で、魔術を試みる。
 「ストーンヘンジ」謎解きの歴史。真実のマーリン。最重要のメガリス
「ストーンヘンジ」謎解きの歴史。真実のマーリン。最重要のメガリス
このようなよくあるドルイドのイメージは、比較的近代に作られたドルイド像なのはほぼ間違いない。
ヨーロッパでロマン主義の風潮が起こり、古代の賢者ドルイドへの関心が大きく蘇った18世紀。
ドルイドの教義の復興運動が広がり、その過程で作られた、その当時の基準での理想的古代賢者のイメージがそのまま真実として広まってしまったのが、今我々が持っている典型的なドルイドのイメージであるとされる。
志望者は多かったが狭き門だった
本来のドルイドがどういう者達だったかについては、残っている記録が少なすぎて、その実態はほとんどわかっていない。
しかし、本当にまったく何もかもわかっていない、というわけではない。
記録が特に乏しい大陸側のケルト(ガリア)に関しても、ギリシアやローマ人が書いた記録が残ってはいる。
カエサルなど、その教義に強い興味を抱いていたらしい向きもある。
ドルイドは、天文学、医学、歴史、法律などあらゆる知識に関するエキスパートであり、他の者には使えない魔術的な技まで習得していたという。
そういうわけだから、ドルイドになるための修行はとてつもなく厳しく、たいてい20年ほどはかかったとされる。
しかし大きな権力のことは置いておいても、兵役や税金の免除などの特典に惹かれてドルイドを目指す若者が多かった。
ウァテス、バルドの立場
ドルイドほどではないが、それなりに特権を有する知識階級であるウァテス。
そのさらに下であるバルドなどでも、数年は修行しなければ資格を得られなかったらしい。
ウァテスは予言を本職とし、時にはドルイドの儀式などを手伝った。
バルドは、詩や音楽などを使って、知識を民衆に伝える役割を担っていたようだ。
ある意味彼らは、研究所のような組織で、ドルイドが科学者、ウァテスが助手、バルドが広報係みたいなものだったのかもしれない。
また、少なくとも大陸側のケルトには、 ドルイドの本場、あるいは発祥の地はブリテン(イギリス)だというイメージがあったようで、本気で修行したい者はあちらに留学をしたらしい。
 「イギリスの歴史」王がまとめ、議会が強くしてきた帝国の物語
「イギリスの歴史」王がまとめ、議会が強くしてきた帝国の物語  「イギリス」グレートブリテン及び北アイルランド連合王国について
「イギリス」グレートブリテン及び北アイルランド連合王国について
霊魂の不滅性、生まれ変わり
ドルイドの思想として、霊魂の不滅生があったのはほぼ確実である。
彼らは、たとえ死んだとしても、それは魂が体から離れるだけで、やがてその魂はまた別の体に移る、というサイクルを永遠に繰り返すと説いていたとされる。
来世があると信じきっているから、戦士たちは死を恐れずに戦うことができた。
死んで生き返るまでの期間、魂はさまようのでなく、一時的に(おそらく地下の)異世界に暮らしていたともされる。
死者への手紙を燃やすことで、(その異世界に(?))贈ることができたという話もある。
借金なども基本的には来世に引き継がれるとされてたみたいだが、実際に前世の借金を要求された者とかもいたのだろうか。
罪を犯した者は人間よりも下等な生物に転生してしまう、因果応報的な 考えがあった説もある。
ウィッカーマン。神々との対話と生け贄
ドルイドは神々に通じていたらしい。
つまり彼らは神々と対話し、その教えを直接に聞くことができた。
その見返りなのか、神々が血を好むのか、動物や、時には人間を生け贄とした儀式も古くはあったようだ。
生贄の儀式の中でも特に独特なものとして、「ウィッカーマン(wicker man)」、つまり巨大な人型の編み細工檻に閉じ込めた人たちをまとめて火で焼くという方法があったらしい。
また、生け贄から流れた血や、その内臓を使う占いもあった。
さらに内臓からは個人に関する様々な情報も読み取ることができたという。
捕虜を捕らえたらその情報を聞き出すのに、尋問するより腹を切る方が早かったともされる。
森の奥深くに暮らしながら金属加工
森の奥深くに暮らす賢者というイメージもドルイド的であろう。
これも作られたものだろうか。
そうかもしれないが、ドルイドが自然崇拝を基礎としていたことはかなり確かな事実である。
数で勝るローマの軍勢に対し、ケルト人たちが森を使ったゲリラ戦をしていたことが、森と結びつけられた原因とする説もある。
またケルト人は、ヨーロッパにおいてかなり早い段階から、鉄の道具を主流にし始めた人たちともされる。
そこでドルイドは、金や銀、鉄細工のエキスパートという伝承も多い。
ケルト歴と季節の祭り
1897年。
フランスのコリニーで発見された、青銅プレートに刻まれていたコリニーカレンダーは、ローマ時代(おそらく2世紀くらい)にガリアのドルイドが密かに作った(当時禁止されていた)ケルトの歴を記録したものとされている。
これが今は、ケルト暦に関する最重要の資料らしい。
ケルト歴は今となっては歴史的価値はほとんどないと言えるだろう。
何かの出来事が起こった特定の年代を示す場合であっても、今の我々からしてみれば、西暦を使った方がはるかにわかりやすい。
しかしドルイドは特定の日に(おそらく魔力が高まるとかそういう理由で)特定の儀式などが意味を持つようになると考えていたらしいから、現在でも、その魔術的な技を学ぼうとする者にとっては、この歴は重要であるはず。
通常、ケルト歴は「太陰太陽歴(luni-solar calendar)」、つまり月の満ち欠けを基準にしながら、太陽の動きも考慮に入れた歴だったとされている。
基本、太陰歴も太陽暦も1年を12か月としているのは変わらない。
だが月の満ち欠けの1サイクルを1ヶ月とした太陰歴は、太陽歴より10日ずつくらい、1年ごとにずれていく。
それでは季節もずれていってしまうので、数年ごとに閏月という13番目の月を導入し季節を調整しているのが太陰太陽暦である。
しかしケルト歴は失われているものの、特別な祭りのいくつかは、現代にまで様々な形で伝承されている。
季節ごとの祭り(あるいはほぼ全ての祭り)は収穫祭。
そして全ての祭りは、地球という巨大な生命体の眠りと覚醒のサイクルの節目であったともされる。
 「ガイア理論」地球は生き物か。人間、生命体、生態系の謎
「ガイア理論」地球は生き物か。人間、生命体、生態系の謎
ハロウィーンの起源とされるサウィン祭
ケルト人にとって1年で最も重要な日は11月1日だったとされる。
この日はケルトの新年にあたり、夏という光の終わりであり、冬という闇の始まりであった。
自然の成長のサイクルの終わりであり、収穫の時期の始まりでもあった。
そして、この日には「サウィン祭(Samhain。夏の終わり)」という祭りが催されたらしい。
そのサウィン祭が、 現在ハロウィーンと呼ばれる行事の元だと考えられている。
泉の乙女ブリートの日、インボルク
2月1日(あるいは2日)には「インボルク(Imbolg)」という祭りがあった。
インボルクという言葉の意味は不明なようだが、「腹の中」という説が有力である。
この日の祭りはまた「オイモルグ(Oimealg)」とも呼ばれるが、こちらは「羊の乳」の意味だという。
本来はブリート、あるいはブリジットという女神の祭りらしい。
また、冬と春の境目を祝う祭りともされる。
冬が終わって暖かくなりだした大地で、太陽と泉の乙女ブリートは目覚めるのだという。
彼女は生命の女神でもあり、動物、植物、あらゆる生物の命の祝福がこの日にあったようだ。
また、ブリートは今は、アイルランド最初の聖人ともされる。
 「守護聖人とは何者か」キリスト世界の殉教者たちの基礎知識
「守護聖人とは何者か」キリスト世界の殉教者たちの基礎知識
火をつけなおす日、ベルタイヌ
5月1日は「ベルタイヌ(Beltaine)」の日。
現在は労働者の祭典とされる「メーデー(May Day)」の起源ともされるが、本来は夏の始まりを祝う日という意味合いが強く、労働者とは特に関係なかった。
ベルタイヌは「明るい火」という意味だと、かなり古くから記録にあるようだ。
どういうわけだかこの日は、不妊と死という不気味な影の日でもあった。
しかし時代が進むと負のイメージは薄れ、一族で出かけて、花で身を飾りながら、歌や踊りを楽しむ日となっていったという。
来るべき夏の妖精たちを歓迎するために、巨大な焚き火を炊いたという話もある。
さらに家庭の火を全て消して、巨大な焚き火から持ってきた火で、再びそれらを灯すというような行事もあったらしい。
大騒ぎとグリーンマンのルナサド
8月1日は「ルナサド(Lugnasad)」。
太陽が冬の暗闇に近づき始めた日とされる。
その名称自体はほぼ確実に、アイルランド神話における光の(あるいは太陽の)神ルグからきているようだ。
典型的な楽しい祭りだったという説がある。
大勢で集まって、一緒に美味しいものを食べたり、物々交換をしたり、ゲームやスポーツで競い合ったりしたという。
この祭り自体は神々が始めたものらしく、めでたい日だったから、争っていた部族の王たちもこの日だけは休戦した。
また、男女のお見合いも行われていた。
お試しの結婚もあったらしいし、互いの姿を見えなくした状態で手だけ繋いで恋愛に関する話をしたりするという妙な試みもあったとされる。
神々の収穫祭でもあったのか、生け贄が捧げられた日でもあったようだ。
収穫の神は「グリーンマン(green man)」と呼ばれたが、このグリーンマンは、現代にまで残っている伝統的には、葉っぱで顔以外を隠しているというような風貌の、ちょっと怪しい奴である。
生け贄はグリーンマンに捧げられたとも、生贄となった者がグリーンマンになったのだとも言われるが、詳細は謎。
冬至の丸太、夏至の植物の魔力
特に地球の北半球の地において、昼、つまり日の出から日の入りまでの時間が1年で最も短い日を「冬至(winter solstice)」と言うが、ケルト歴では12月21日がそれである。
また、逆に昼が一番長い「夏至(summer solstice)」は6月21日であった。
12月21日には「メアン・ゲムフリッド祭(Méan Geimhridh。真冬祭)」。
6月21日には「メアン・サムフレッド祭(Méan Samhraidh。真夏祭)」があったとされる。
メアン・ゲムフリッド祭は「ユールの丸太の祭典(celebration of the Yule log)」ともされ、十数日(おそらく12日)前から丸太を燃やしていたとされる。
現在はユールの丸太(ユールログ)と言えば、 クリスマスイブに暖炉で燃やす木のこと。
ユールというのはもともと「祭り」の意味である北欧の言葉らしい。
メアン・サムフレッド祭は、太陽と水の祝福の祭りとされていたようだ。
太陽から多くのエネルギーを受けているのか、植物に宿る魔力が高まるともされ、薬草を採取するには絶好の日とされていた。
また採取したそれらの薬草を燃やした火の儀式で、恵みの雨を呼んだという話もある。
ペースエッグはイースターエッグか
1年には通常2回、昼の時間と夜が同じくらいになる日とされる。
ケルト歴では3月21日の「春分(Spring Equinox)」。
9月21日の「秋分(Fall Equinox)」がそうである。
それらは「メアン・イアレイ祭(Méan Earraigh。春祭り)」、「メアン・フォムヘア祭(Méan Fomhair。秋祭り)」の時でもあった。
春分は、鳥が巣作りを開始する日。
そして再生、繁殖、不死の象徴であるその卵を、妖精に奉納したり、みんなで分け合い、食べたりする祭日でもあるとされる。
(このあたりの話は中世以降という説もあるが)「ペースエッグ(pace-egg)」という、特別に着色したり、飾り付けたりした卵を用意したりもした。
そのペースエッグと引換に、男女で服を入れ替えたりした「ペースエッガー(pace-eggers)」なる曲芸師が、ちょっとしたパフォーマンスを見せたりもしたようだ。
また、部族によっては、穀物の貯蔵庫に普段から、この日のための卵を隠していたりもしたという。
春分の卵の習慣は、「イースター・エッグ(Easter egg)」、いわゆる「復活祭の卵」の起源とする説がある。
イースターエッグとは、 キリスト教が処刑されたから3日後に復活したとすることを祝う復活祭にて、特別に飾りつけられる卵のことである。
また古代の春祭りは、現在のアイルランドの主語聖人パトリックを祝う日(3月17日)にも影響を与えているかもしれない。
秋分に関してはよくわかっていないことが多いが、最大規模の収穫祭の日という説がある。
そして部族中の収穫品が集められ、その豊かな恵みに感謝を抱くのである。
ドルイドと植物
ヤドリギ。最も重要視された植物
ヤドリギとは一般的には被子植物門、ビャクダン目のヤドリギ類の一種である「セイヨウヤドリギ(European mistletoe)」のことを指す。
これは「標準ヤドリギ(common mistletoe)」とも呼ばれ、亜種も含めれば、アジアやヨーロッパのかなりの広範囲に、普通に見られる植物である。
ヤドリギは、その名称が物語る通り、基本的に他の植物に寄生して、宿主の幹(胴体部)や枝から生えてくる。
よく半寄生性と呼ばれるが、これはこの種が、地面からの栄養接種を宿主に頼る一方で、ちゃんと緑の葉を持ち、光合成は自分で行うからである。
 「光合成の仕組み」生態系を支える驚異の化学反応
「光合成の仕組み」生態系を支える驚異の化学反応
そして他の植物から生えてくるという特異性からか、ヤドリギは再生の力を有する聖なる植物として、ケルト社会では特に重要視されてきた。
ドルイドたちは特別に霊力が高まる日などに木に登って、カマでヤドリギを切り落とす。
一説によると、地面に落ちたヤドリギはその神聖さを失ってしまうようで、下にいる者が広げた布などで受け止めたという。
クリスマスの飾りなどに使われたりするようにキリスト教にも、ヤドリギ信仰は受け継がれているともされる。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
ヤドリギ信仰はゲルマン人などにもあったようで、さらに古い起源がケルトと共通の可能性もある。
 「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
オークの木。カシかナラか、パナケアに関する重要なこと
もうひとつ重要なのは「オーク(oak)」の木だったとされるが、それはガリアの方だけという説もある。
オークは通常「楢」のことらしいが、(特にドルイド関連の文面では)「樫」とされることもある。
どうも日本に比べると、昔の西洋はカシとナラとの違いが曖昧だったようだ。
どちらもブナ科(Fagaceae)であるから、区別が微妙なのは当然である。
とりあえずガリアでは、オークの木に生えたヤドリギが重要らしかった。
オークが神の生命の木で、ヤドリギはその生命力を宿してると信じられていたわけだ。
そもそもドルイドという名称自体も、dru(オークの木)とvid(知恵)の組み合わせからという説もある。
ドルイドはまた、オークの木からとれたヤドリギから「パナケア(panacea。万能薬)」を作る方法を知っていたともされるが、これは錬金術における賢者の石と同じものでないか、という説がある。
 「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
「錬金術」化学の裏側の魔術。ヘルメス思想と賢者の石
様々なハーブの効能
ヤドリギやオークだけでなく、ドルイドはあらゆる植物の知識を持ち、さらに医者でもあった。
つまり彼らは「ハーブ(Herbs。薬草)」のエキスパートであった。
彼らはこの点に関しては科学者、あるいは現代魔術師的で、よく使用していた薬草の多くは、実際に試して、しっかり効果が確認されたものが多かったとされる。
適切な収穫方法や調合手順を介さないと効果がなくなるとされていたようだが、それも有効な成分をなるべく失わせないようにするガイドラインのようなものだったのもしれない。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
レンプクソウ科の「セイヨウニワトコ(Elder)」は、ドルイドにとって最も重要なハーブ、あるいはそのひとつであった。
一般的な風邪や、感染症に対しても有効とされていた。
今となっても、ウイルスに有効という説も一応はあるみたいである。
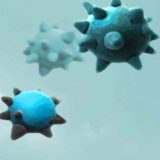 「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
「ウイルスとは何か」どこから生まれるのか、生物との違い、自然での役割
キク科の「タンポポ(Dandelion)」は古くから様々な文化でハーブとして知られていたが、ドルイドたちもよく使ったとされる。
ビタミンを豊富に含んでいるから、はっきり効果がよく出たのかもしれない
 「五大栄養素」代表的な生命を維持する要素
「五大栄養素」代表的な生命を維持する要素
ドルイドはよくタンポポを使って、心を落ち着かせるワインを作ったともされる。
日本では普通に食用の野菜としてよく知られる、タンポポ同様にキク科の「ゴボウ(Burdock)」は西洋では(またケルトにおいても)伝統的なハーブである。
血液を浄化させたり、尿を促したりする。
やはりキク科の「フキタンポポ(Coltsfoot)」もよく使われたハーブだった。
高い抗菌性の咳止め薬として知られていたが、効果が強いがゆえに、量を誤ると危険な毒になりやすかった。
「ブルックライム(brooklime)」の名もよく知られているオオバコ科の「マルバカワヂシャ(Veronica beccabunga)」は、サラダ、あるいはジュースにして飲まれたとされる。
このハーブは、ビタミンC不足により出血したりする「壊血病(scurvy)」に利くとされていた。
サクラソウ科の「キバナノクリンザクラ(cowslip)」は咳止めの他、神経系の病気に効いたし、鎮静剤、あるいは睡眠薬としても知られていた。
また、花は塗り薬として使うと皮膚病に有効だったようだ。
ムラサキ科の「ヒレハリソウ(Comfrey)」は骨に利くハーブとされていた。
関節痛にも利くし、また下痢止めにも使えたようだ。
ゴマノハグサ科の「セイヨウゴマノハグサ(woodland figwort)」は喉の病気によく効くとされていた。
同じゴマノハグサ科の「セラゴ(Selago)」は、出血を伴う怪我の治療に使えたようだ。
アカネ科の「シラホシムグラ(Clivers)」は皮膚病の薬などに使われた。
同じくアカネ科の「クルマバソウ(Woodruff)」は胃腸薬として使えたとされる。
バラ科の「サンザシ(hawthorn)」は心臓(血液循環機構?)の病気に効く薬とされていたようだ。
同じバラ科の「セイヨウナツユキソウ(Meadowsweet)」は熱冷ましに、精神安定剤に、害虫の駆除剤と、かなり幅広い用途で使えたらしい。
シソ科の「ミント(Mint)」は消化をよくした。
同じシソ科の「ウツボグサ(Self-Heal)」は予防的な意味合いでうがい薬などに使えた。
クマツヅラ科の「クマツヅラ(Vervain)」は消化をよくしたりするハーブとしての役割の他、魔除けや、清めの儀式、占いなどにも使えたとされる。
ヤナギ科の「ヤナギ(Willow)」もまた、 鎮痛剤や熱冷ましに使われる一方で、触れる者などを守護する聖なる守りの魔力を有しているとされていた。
ナス科の「マンドレイク(Mandrake)」は有名であろう。
ドルイドもこれはハーブとしていた。
基本的には鎮痛剤か睡眠薬として使われたようだ。
少し創作ぽいが、一説によるとドルイドたちは、このマンドレイクと他にいくつかの薬草を混ぜ合わせて、人を催眠状態にして操る合成ハーブを作ることができたらしい。
オガム文字。木の名前がふられたアルファベット
ケルト人は文字を持たなかった民族とされている。
確かに公式記録などには頑なに使わなかったようだが、賢者たるドルイドは、時々は文字を使っていた。
古くは近場の民族のアルファベットを借用していたようだが、4世紀頃に、アイルランドにてケルトの専用アルファベットとも言うべき「オガム文字(Ogham)」が考案された。
文字一つ一つには木の名前が付けられていて、ケルトの樹木信仰の強さが見える。
これらの文字は主に、呪文や歌の力を強めたり、長引かせたりするために使われたもとされているが、実際には単に、人の名前とか土地の名前が刻まれているだけというパターンが多いらしい。
だから、土地などの所有権を主張するために使われたという説も有力。
オガム文字は、はっきり古代ケルトと言えるような時代の産物ではない。
もしかしたら、すでに大陸側ではかなり受け入れられていたであろうキリスト教の影響などもあったかもしれない。



