吸血鬼、ヴァンパイアとは何か?生者か?死者か?
吸血鬼、ヴァンパイアというのは死した存在であるという。だが普通、死者は動かないだろう。
 「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験
「科学的ゾンビ研究」死んだらどうなるか。人体蘇生実験と臨死体験  「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
「死とは何かの哲学」生物はなぜ死ぬのか。人はなぜ死を恐れるのか
(フィクションな存在だからというのは抜きにして)死者である彼らが動く仕組みとしては以下のいくつか説明が代表的。
(1)幽霊的、妖怪的な存在。たいていは実態を伴い、場合によってはゾンビとややこしい
 「ブードゥーの魔術」ゾンビの黒、恋愛の赤。秘密結社の呪いの教義
「ブードゥーの魔術」ゾンビの黒、恋愛の赤。秘密結社の呪いの教義  雪女、山男、ろくろ首「男と女の妖怪」
雪女、山男、ろくろ首「男と女の妖怪」
(2)幽霊的な存在に取りつかれた存在。死体でなくてもいいかもしれないが、生者だと抵抗があるのかもしれない。
また、ヴァンパイアは死んではいない、れっきとした生きた何かと考える向きもある。その場合には以下のような説がよく語られる。
(1)単に未知の生物。これはむしろ一番ありえそうな考え方だろう。進化の過程で、我々サピエンスと分岐した、ホモ・ヴァンパイアなのかもしれないし。
 「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
「ダーウィン進化論」自然淘汰と生物多様性の謎。創造論との矛盾はあるか
(2)ウイルス感染。例えば狂犬病のようなウイルスで、自我が崩壊した者。
(3)黒魔術の副作用。あるいは、代償とか。
 「黒魔術と魔女」悪魔と交わる人達の魔法。なぜほうきで空を飛べるのか
「黒魔術と魔女」悪魔と交わる人達の魔法。なぜほうきで空を飛べるのか
(4)人工的な生物。強化人間や生物の一種だったりのするかもしれない。
吸血鬼の特徴、能力
創作由来のものも多いが、例えばヴァンパイアが人に作られたバイオテクノロジー的な産物なら、現実に創作由来の能力を持っててもおかしくはない。
吸血。なぜ血を吸うのか
吸血鬼が普通に食事ができるかどうか、必要なのかについては諸説ある。ただ少なくとも、生きるのに血が必要だとはよく言われる。
しかし単なる好物ならわかるが、血を吸わないと生きていけないというのはどういう事であろうか? 考えられるのは、血以外にはあまり含まれてない何らかの成分が必要とか。
もしヴァンパイアが精神的だったり、あるいは魔術的な原因での変貌なら、暗示的に必要だったりするのかもしれない。
 「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
「現代魔術入門」科学時代の魔法の基礎
血は古来より生命力の源であるという民間伝承があるので、生きるための血というのは、単なるイメージかもしれない。
血に限らず、体液が必要だという説もある。
やはり人、あるいは動物の機構内でのみ発生する何らかの成分が必要なのだろうか? また、血を吸うためなのか、犬歯が鋭く発達してるとか、舌にトゲがあるとかいう伝承もある。
高い身体能力。凄い怪力
吸血鬼は、運動能力が高かったり、怪力だったりする。
これには典型的なパターンが二つある。
まず、単に常人よりは凄いが、そこまで常識外れではないパターン。
例えば身軽さは猿くらいだったり、速力は犬や猫くらいだったり、動物の能力程度という場合。それでなくとも、物理的、力学的にまだありえそうなレベル。
一方で、かなり型破りなパターンもある。
例えば羽ばたきや加速などもなしに、空を飛んだりする。
この世ならざる存在だから、この世の物理法則に縛られないのだという説もある。
変身能力。オオカミやコウモリになる
主にコウモリやオオカミに変身するとされている。
 「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ
「コウモリ」唯一空を飛んだ哺乳類。鳥も飛べない夜空を飛ぶ  「日本狼とオオカミ」犬に進化しなかった獣、あるいは神
「日本狼とオオカミ」犬に進化しなかった獣、あるいは神
あらゆる生物に変身できるのかもしれないが、夜に関連する生物にしか変身出来ないという説もある。
とすると、例えばフクロウやタヌキにも変身できるのかもしれない。
特定の生物にしか変身できないというのは、実は逆かもしれない。
つまり吸血鬼が、何か他の生物になっているのでなく、他の生物が吸血鬼になっているのかもしれない。とすると人の姿というのは吸血鬼の特徴なのだろう。
ユダヤ教などの宗教では、人間というのは、神に似た姿の、特別な生物である。
 「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
「ユダヤ教」旧約聖書とは何か?神とは何か?
もしかすると吸血鬼というのは、人間に憧れたコウモリやオオカミが魔術により変身した存在なのかもしれない。
また、無定形のものに変身出来るというパターンもあるという。例えば霧や煙など。
風が吹いてもその場に留まっている煙や、十分寒くても液体化しない気体は、吸血鬼の可能性が高いのだという。
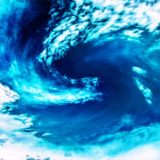 「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差
「風が吹く仕組み」台風はなぜ発生するのか?コリオリ力と気圧差  「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か
再生能力。不死身なのか
どんな傷も瞬時に、あるいは素早く治癒するという。そもそも不老不死であるという話もある。
不死身なのだとすると、吸血鬼としての特性は、代償である可能性も高いか。
単に寿命が凄く長いとか、寿命では死なないだけという説もある。
鏡に映らない。視覚的なわかりやすさを狙ったか
これは吸血鬼ものの小説や映画で、視覚的にわかりやすい表現として創作されたものだという説がある。
ただし、鏡は魂を映しているという民間伝承もあるようだから、そこからきている可能性も高い。吸血鬼はこの世ならざる存在だから、当然魂も持たないというわけである。
もしかすると魂を失ったり、抜かれたりすると吸血鬼になるのかもしれない。
動物との対話。吸血鬼ウイルスは動物由来か
特定の動物が対象なのか、動物なら何でも喋れるのかは不明。
しかしおそらくは前者。
動物をそそのかし、使いにしたりする事もあるという。
敵の敵は味方。動物には、人間に恨みを持つ者もいるかもしれないから、そういう迫害された動物たちが、吸血鬼の味方になったりするのかもしれない。
 「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か
「人間と動物の哲学、倫理学」種族差別の思想。違いは何か、賢いとは何か
吸血鬼ウイルスが動物由来という説もある。
吸血鬼の弱点
強力なイメージである吸血鬼だが、かなり弱点が多い事でも有名である。
案外脆い存在なのか。恐れられ、かなりよく研究されてきた故か。
光を浴びると灰になってしまうのか
特に日光に弱いという。太陽の光を浴びるだけで、燃えて灰になってしまうという説もある。
 「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性
しかしいくらなんでもそれではショボすぎなので、フィクションなどでは、この弱点は迷信か、少々大袈裟だという設定も多い。
そもそも、この設定自体が民間伝承ではほとんど見られないとも。ただし吸血鬼が夜の存在であることは、古くからの典型的イメージのようである。
月の光が、吸血鬼を元気にさせるいう説もある。例え日光で灰になったとしても、月光で復活できるとも。
光に弱いというが、波長は関係あるだろうか? 例えば吸血鬼は、電磁波や赤外線にも弱いのだろうか?
 「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係
もし吸血鬼が、未知の粒子とかで構成されてるなら、それがある波長に影響を受けやすいというのはありうるかもしれない。
 「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ
なぜニンニクを嫌がるか
とりあえず、死者でも生者でも、口の中にニンニク詰めとけば、吸血鬼化を防げるという。ニンニクを食わせなくても、身につけたり、自分が食ったりしたら、それで吸血鬼よけになるという説もある。
ニンニクは古くは古代エジプトの時代から、悪霊から人間を守る(普通に食べる薬としても知られていた。)薬用植物として人気だったようだ。その強烈な臭気により、魔よけの他、虫よけ、鳥よけにもなると考えられていたらしい。
そもそも、吸血鬼が強烈な臭いをとても嫌がるというのは、多くの伝承で語られていることとされる。 だからこそ身につけるだけでも吸血鬼よけになる訳である
いろいろな臭いもの
臭いが嫌だと言うなら、ニンニクでなくとも、臭いものなら何でもよさそうだが、実際、未熟あるいは腐った果実、家畜の糞や人糞なども、結構有効という説がある。
そういうものをすりつぶして、死者自身や、その棺。あるいは魔よけとして家の扉などにこすりつければよいのだという。
これは元々、悪臭を放つ蘇った死体に対して、「毒には毒」という発想からだったと推測する向きもある。しかし吸血鬼は死体であっても腐敗していないことがその証明という伝承もよく知られているのだから、死体であってもけっこう清潔なのかもしれない。
塩。腐敗を防ぐからか
ニンニクと同じく、大量に摂取する事で、吸血鬼化を防げたりするという。また、やはりニンニクと同じく、吸血鬼に直接食べさせなくても、塩そのものをけっこう恐れてくれるという。
塩は遺体などの腐敗を防ぐ効果があるが、(前述と矛盾するが)腐ったような怪物に効果的なのだろうという考え方もある。
香。木材のよい匂い
普通に香と言えば、いい匂いのする木材の香りだが、吸血鬼はそういう香りも駄目らしい。
香は、祈りが天に届く象徴であり、神や天使の加護を得られる場合がある。
あるいは心地よい匂いなのだから、あれは天界の匂いなのかもしれない。だから悪なる者が苦手なのだとも考えられる。
果実の種。数えるのに夢中になりすぎる
地域によっては、吸血鬼、あるいは危険な生ける死者を遠ざけるために、果実の種などがまかれる。
特に、ギリシャ神話において、ペルセポネが冥界の神ハデスの妻となる時に食べたザクロの実は、そうした物語から死者の象徴と考えられることがあり、その死者の果実の種子をまくと効果的とも。
特定の植物の種子を、家の入り口などにまくだけでも、死者や悪霊が寄り付かなくなるという説もあるが、多くの伝承において重要なことは、(なぜかはたいてい不明だが)霊的存在というのが、まかれている粒を拾って数えないではいられない習性を有していること。夜に墓から出てきた吸血鬼も、その周囲に種がまかれていたなら、何をするよりもまずそれらを数えてしまうらしい。それもかなり時間をかけるのだという。
これと関連しているのか、家の出入り口に網を張っておけば、やってきた吸血鬼が、その網の目を数えるのに夢中になってしまうという話もある。
銀。なぜ聖なる金属か
なぜ金でも銅でもなく、銀なのかというと、どうもその白に近しい色と輝きが、善なるモノっぽいかららしい。
銀に触れるだけでも吸血鬼は火傷したりするから、例えば銀の盾は防御だけでなく、攻撃にも使えたりするという。銀製の剣や弾丸など、吸血鬼にとっては恐ろしすぎる武器である。
もちろん純銀がよいのは言うまでもない。
フィクションではよく、吸血鬼は銀でなければダメージを与えられないが、普通の民間伝承においては、銀は効果が高いというだけで、例えば普通の銃弾とかでも吸血鬼を殺すことは可能とされる。
十字架。なぜ教会を避けるのか
吸血鬼は悪なる存在だから、キリスト教的には、神の加護や信仰心に弱い。
 「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
「キリスト教」聖書に加えられた新たな福音、新たな約束
吸血鬼は、十字架を恐れるし、教会とも関わりたがらない。しかし恐れるだけで、それで倒したりは出来ないらしい。
 「魔女狩りとは何だったのか」ヨーロッパの闇の歴史。意味はあったか
「魔女狩りとは何だったのか」ヨーロッパの闇の歴史。意味はあったか
もし吸血鬼の十字架に対する恐れが、人間が台所の黒い虫を恐がる程度のものならば、十字架は強力な防衛手段にはならないだろう。
 「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
「ゴキブリ」人類の敵。台所の黒い絶望の正体
聖水。案外脆いか
聖水というか、清らかな水に弱いという。しかしこれはちょっと曖昧な認識であろう。
果たして清らかな水とは、何なのか? 純度の高い水か?
 「地球の水資源」おいしい水と地下水。水の惑星の貴重な淡水
「地球の水資源」おいしい水と地下水。水の惑星の貴重な淡水
普通に川や海を恐れるという説もある。
では雨はどうだろうか? 仮に命に関わるほどに雨に弱いなら、やはり吸血鬼は脆すぎる。
 「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
「雲と雨の仕組み」それはどこから来てるのか?
水を怖がるというのは狂犬病の症状として有名なので、それが由来だったりするのかもしれない。
蹄鉄。魔除けの伝承
馬の蹄などの保護具である蹄鉄には古来より魔除けの伝承があり、もちろん吸血鬼にも効果ありだという。
しかしなぜ蹄鉄が魔除けになるのだろう?
一説によると、かつて悪戯をする悪魔などに、お仕置きとして蹄鉄が使われていたのだという。ただの蹄鉄ではない、神や天使の加護がかかった、悪にとっては呪いの蹄鉄である。
 「天使」神の使いたちの種類、階級、役割。七大天使。四大天使。
「天使」神の使いたちの種類、階級、役割。七大天使。四大天使。
悪魔たちは、許しをもらうまで、その蹄鉄をつけ続けなければならず、非常に恐ろしいものであった。
 「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
「悪魔学」邪悪な霊の考察と一覧。サタン、使い魔、ゲニウス
それで、悪なる存在の間には、蹄鉄への恐怖が広まっているのだという。
死者の血。生者の血は栄養。死者の血は毒
生者の血は生きるのに必要な栄養なのに、死者の血は毒だという話がある。なぜかは謎だが、死んでしまった後の、何らかの機能停止が関係してるのではないだろうか。
 「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
「生化学の基礎」高分子化合物の化学結合。結合エネルギーの賢い利用
亡くなって間もない者の血が、効果抜群とも言われる。なので亡くなる前後に伴う要因かもしれはい。
ろうそく。霊的ゆえか
吸血鬼に限らず、霊的な存在は、ろうそくの光で照らされるのに弱いという。
ろうそくでなく火か光に、あるいは蝋に弱いのかもしれないが。
ろうそくの光に照らされると、昇天してこの世を去るのだという話もある。
油と火。破壊的な力
直接かけられたりするのももちろん、油のかけられた物にも弱いという説がある。可燃性が高い事に関係してるのかもしれない。吸血鬼は火に弱いともされる。
 エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」
もしくは、疎水性の油は、実は疎霊性でもあるのかもしれない。
地域によっては、吸血鬼含め悪霊を追い払うのに、浄火の火を焚く風習などが知られている。
普通、火祭りというのは、人間と家畜のため、あるいは農作物の豊かな実りをもたらす太陽の恵みを求めたものだったと考えられている。しかし、火には破壊的なイメージがあり、災厄すらも焼き払うことができるという思想は広くあったらしい。
火の煙も、よく悪の存在には強い毒なのだと語られる。
うつ伏せ。ケルト人の教え
吸血鬼はうつ伏せから起きあがれないという説がある。
そういうわけで、うつ伏せという体勢は吸血鬼の防止法にもなる。
しかしこの弱点は、致命的なようで、そうでないかもしれない。
よくよく考えてみれば、うつ伏せに一切ならなくても、普通に生活する分には苦労しない。
また、起きあがれないだけなので、起こしてもらう事は多分出来るだろう。
これはケルト人の習慣が起源とも推測される。
 「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
「ケルト人」文化、民族の特徴。石の要塞都市。歴史からどのくらい消えたか
薔薇。貴族だというのに
近代創作などで広まった貴族的なイメージからすると違和感があるかもしれないが、吸血鬼は薔薇にも弱いとも。
正確には薔薇の花や、その香りとも言われる。その花は悪の肌を焼き、香りは悪を遠ざけるらしい。
また、はやり吸血鬼化防止にも使えるようである。
とにかく何か尖ったもの
吸血鬼は、自らの血を流すことを恐れない場合でも、鋭いトゲで傷つけられることだけは、かなり嫌がるという。
釘や針、トゲのある植物を墓や死者の口に入ておくのもいい。あるいは頭に巻きつけるようにしても、死者の吸血鬼化を防ぐことができた。
目覚めて、襲いかかってくる吸血鬼に対しても、銃よりも刃物の方が有効だという説がある。
吸血鬼ハンターの正体
ダムピール(Dhampir)
吸血鬼と人間のハーフ。男の子の場合は『ヴァムピール』、女の子の場合は『ヴァムピーラ』とも言うらしい。
人間的な側面を持ち、かつ吸血鬼と同等か近い能力を有している。
あるいは吸血鬼の能力を封じる事ができる(吸血鬼の変身を見破ったりできる)ため、吸血鬼ハンターとして人間の味方になる事もある。
というか、吸血鬼はあまり子育てに興味ないようで、人間に育てられる場合がたいていなので、人間側につく事の方が多い。
クルースニック(Kresnik)
一説によると、吸血鬼は赤い膜に包まれて生まれてくるという。対して白い膜に包まれて生まれてくるのがクルースニックである。
吸血鬼が生まれつき吸血鬼なように、クルースニックも宿命付けられた、生まれつきの吸血鬼ハンターらしい。
これも一説によると、吸血鬼の赤い膜は悪の力の成分、クルースニックの白い膜が聖なる力の成分で出来てるらしい。
という事は、普通の者でもそれらを取り込む事で、同じような力を得られるのかもしれない。
ヴィエドゴニャ(Vjedogonia)
結局、悪か善かは、生まれもった力より、その性格によるのかもしれない。
赤い膜に生まれた者でも、吸血鬼を狩る側になる事もあるらしい。それはいわば改心した吸血鬼で、ヴィエドゴニャと呼ばれるという。
ズドゥハチ(Zduhac)
やはり白い膜に包まれて生まれてくる子らしいが、能力的にはヴィエドゴニャに近いという。
もしかすると、聖なる力を帯びた吸血鬼という存在なのかもしれない。
霊体離脱が得意で、霊的な存在自体に強いとも言われる。
守護霊的な概念が吸血鬼ハンターに結び付いて、考え出されたという説もある。
聖なる力を帯びた動物
もともと白いのもいるが、本来は白くない動物にも、真っ白な個体が誕生する事がある。いわゆるアルビノというやつだが、その白い個体は、聖なる力を帯びた獣という伝承がある。
そういう獣は吸血鬼などの悪を滅ぼす事ができる。
滅ぼすまではいかずとも、能力を封じたりできるという説もある。
また、白い獣自体、すでに吸血鬼ハンターみたいなものだが、普通に人型吸血鬼ハンターの相棒にもなりうると思われる。
吸血鬼退治の方法
死者がなったとされる場合、吸血鬼は日の光が地を照らす時間には墓で眠っている。
眠っている吸血鬼なら、ニンニクを口に詰めたり、銀の釘で突き刺したり、うつ伏せにしたりするだけで、退治、あるいは動きを封じられる。
そこで、吸血鬼の墓を探すのは、すでに退治するための有効な手段となる。動物が近寄らない墓などが、怪しいようである。
また、驚異的な再生能力を持つ吸血鬼も、頭と胴を切り裂かれてしまうと、もう復活できないという。
心臓も復活させられないらしい。
心臓に関しては、通常のとは違う第二の心臓があり、それは魔力の源なので、破壊されたら吸血鬼は力を失うとする説もある。第二の心臓は普通に体内のどこかにある場合もあるが、体外に出せる事ができるとも。
それに、教会の祝福などを受け、聖なる力を帯びた武器も、吸血鬼の再生能力を無効化できるとされる。
蘇りを防ぐための策
普通に蘇りたいと願う者、吸血鬼になりたい者が、必ず吸血鬼になるわけではないとされている。吸血鬼か、それでなくても死体の復活という現象は、つまりは埋葬の失敗とも言えよう。
死者には安らかな眠りがもたらされなければならない。いつまでも死の領域に踏み込めない者は、結局この世にまた目覚めようとして、そして目覚めてしまったなら恐ろしい吸血鬼となってしまう。
どこを塞げばいいのか
とりあえず、埋葬される死者の眼は必ず閉じられなければならないとれる。死者の眼は、生者をあの世へと誘う魔力をもっている。
特にルーマニアでは、吸血鬼の遺体は、両眼、あるいはその左眼が必ず開いたままなのだと伝えられてきた。
一度体から出ていった魂が、再び戻ろうとする時、死体の口を糸で縫って閉ざしておけば、戻れなくなるとも言われる。
口もそうなのだが、鼻や耳などの穴にも、ニンニクやトゲを詰めるという対策もある。
死者の持ち物
ヨーロッパ各地で、死者の口に硬貨をくわえさせるという習慣も知られているが、これの起源はギリシャ神話かもしれないとも。また、死者が死者の国へ行くためには、硬貨が必要だという伝承は、古代エジプトや、ケルト文化、アジアの仏教の世界観などにも見られるという。死者が悪魔に捕まっても、お金を持っていたなら、それで自由を買える場合もある。
硬貨以外に、天国への真っ暗な道を照らすためのロウソクやランタンなども、死者のために用意する持ち物として推奨されてきた。
祝福されない者たち
自殺はキリスト教において罪とされ、自殺者は、死後も祝福されない。自殺者は、祝福された大地に受け入れられないという点において、教会から破門された者と立場的に近い。
いずれにしても、そういう者たちは、ちゃんとした墓にも埋葬されず、その魂が安らかな眠りにつくことも難しい。
時に、人里のとこにでも、埋めるのが危険である遺体は、川に流したり、重りをつけて湖に沈められたりしたという。
キリスト教的世界観でなくても、処刑された犯罪者などは、手足を切断したうえで首に鎖を巻いたりして、吸血鬼として甦るのを防ごうとしたとも。
もちろん、遺体は必ずうつ伏せにするのが一般的だった。
早すぎた埋葬
蘇る死者伝説の真相可能性として、まだ生きているのに死んだと勘違いし、埋葬してしまうという、いわゆる「早すぎた埋葬」という現象はよく語られる。
早過ぎた埋葬の大きな原因として、カタレプシー(強硬症)というのが、よく挙げられる。カタレプシーとはある種の全身硬直を指す言葉、原理にはまだ謎な部分もあるが、とにかくある姿勢から体を動かせなくなる、あるいは動かそうとする気が全くなくなってしまうというような症状とされる。
また当然、早すぎた埋葬があったとしても問題のない埋葬の方法というものがあろう。
例えば火葬は、仮にに死んでいると勘違いされた生きている人がいたとしても、体を燃やされて灰にされた時点で確実に死んでいる。
実は生きていた人が、実は生きていたということが確認されるのは、普通は土葬されている場合である。
東欧とかでは、かつて再埋葬の風習があった。つまり、死者を埋葬してから数年後に棺を掘り返して、死者のその肉体が朽ちていることを確認してから、また埋葬し直すというもの。
蘇る死者の話を意識していたから、このような習慣ができたのか。それとも、このような習慣があったからこそ、実は生きていた人の、棺の中でもがいた形跡とかをよく発見できたのか。
なぜ火葬はあまり行われなかったのか
死者をどのように葬るのか、その風習は地方によって 様々であるが、しっかりと宗教的な信念に基づいて遺体を処理しようとする試みで、火葬というのは実は珍しいとされる。有名なものでは仏教くらいらしい。
多くの宗教では、遺体を燃やすどころか、傷つけることも、その魂が安らかに眠る、あるいは死者の国に行くための妨げになると考えられてきた。
やがて蘇りの時が来るから、遺体はなるべく死んだ時そのままに状態に保っておくのがよいという考え方すらあった。
一方、輪廻転生(生まれ変わりの連鎖)という思想を基盤とする仏教においては、死後しばらく経って、魂が新たな肉体を求めて古い肉体を離れた後は、そこに残るのはもうただの塊である。つまり切り刻もうが燃やそうが、大した問題はない。
むしろ、苦しみの罰である現世で汚れきったその体を、火で浄化することで魂を清める、というような発想さえあったという。
ドラキュラ伯爵のモデル、ヴラド・ツェペシュ
吸血鬼という怪物の存在の様々なイメージを、広く世間に浸透させた記念碑的な作品として、ブラム・ストーカーの書いた怪奇小説『吸血鬼ドラキュラ』はあまりにも有名であろう。
そしてまた、この小説に登場する吸血鬼ドラキュラ伯爵には、かつて、ヴラド・ツェペシュ(Vlad Țepeș。Vlad the Impaler。串刺し公)と呼ばれたモデルがいたこともまたよく知られている。
その串刺し公こと、ヴラド三世(Vlad III。1428~1476)とは、実際どんな人物だったのか。
その恐ろしい残虐性は、いくらか(実際にいくらかはその可能性が高い。彼はイメージ戦略における悪役としてはぴったりだったろうから)脚色されているのではないか、と考えたがる向きがあるほど。
悪魔公と呼ばれていた父
ヴラドの一族は、ルーマニアのトランシルバニア、ワラキア地方の名家だった。ほかの名家の者たちと権力を巡って争いながらも、この地方全体を何代も続けて支配していた。
この時代のヨーロッパでは、より広大な地域の支配者(その最高の権力者がローマ法王)が、各地域で影響力のある名家の者に支配権を勅許する、いわば封建的な政治体制が一般的だった。
そして、ヴラド三世の父、ヴラド二世は1431年、東ローマ帝国から正式に爵位を受けて、トランシルバニア、ワラキア地方の正統支配者と認められる。この年に、後に串刺し公と恐れられるようになる、彼の息子もだいたい同年前後に生まれたのだという。
ヴラドの一族の者みな暴君だったとされている。領民たちから嫌われながら、しかし恐ろしい罰を恐れて、みな逆らえなかった。
ヴラド二世は「悪魔公(Vlad Dracul。~1447)」と呼ばれていた。この父親の時点で、敵対するトルコ( オスマン帝国)軍の兵士への容赦ない仕打ち。それに領民たちや、自身と対立関係にある豪族たちとへのサディスティック(加虐性愛的)な振る舞いが知られていた。
息子の方のヴラドは、(1443年前後くらいから)数年をトルコで人質として生きた。父ヴラドは1447年に、おそらくは政敵に毒殺される。その翌1448年、トルコとワラキアの間で大きな戦闘が起きるが、ヴラドの幽閉もとかれ、彼は領主であった父の跡を継ぐ。
その暴君ぶりは、前領主をあっさり超えるものであったという。
なぜドラキュラと呼ばれていたのか
ヴラド三世は、ドラクル(悪魔)という父の異名にちなんでか、ドラキュラ公(Vlad Dracula。Vlad Drăculea)と呼ばれたとされる。
この異名について、普通には、父の残虐さを子が引き継いでいたことから、いくらか同一視さえされていたとは推測しやすい。
一方、この名前は新領主自身が名乗ったもの、という記録文書もある。
他に、強力な悪の存在、力強さの象徴であった幻獣ドラゴン(Dragon)に関連していたという説もある。
前領主ヴラドは、東ローマ帝国から正式に爵位を受けた時に、ドラゴンの紋章を形どった盾を授けられたらしい。それでそのドラゴンの紋章が一族の象徴となっていたのだという。領主もその紋章より、自らの呼称にドラゴンを使うことになったのかもしれないという説。
伝統的にヨーロッパでは、 神秘的な存在というよりもむしろただの怪物じみた動物、多くの昔話においても退治されるべき魔物と考えられていた。ドラゴンの紋章には、単に力強さだけでなく、悪魔的なイメージも強かったと考えられる。それで、領主の実際の暴君ぶりと合わせて、ドラクル、ドラキュラ(ドラゴン的悪魔)だったのかもしれない。
串刺し公の狂気
ドラキュラ公の残虐さを示すエピソードは数多く残っている。
彼が串刺し公と呼ばれたのは、捕らえた敵を処刑するのに、生きたまま木の棒で体を貫かせ、地面に突き立てる方法を好んだからとされている。
それに、体の一部の切断や、皮の剥ぎ取り、釜ゆで、生き埋め、生きたまま身動きだけ取れなくして獣に食わせるなど、次々と残酷な罰や拷問方法を自ら考案したという。敵の捕虜を処刑した場合、その肉片を、まだ生きている捕虜たちに食わせたとも。
また、トルコの使者がドラキュラ公の城に招かれた時のこと。ターバンを付けたままの使者に、領主は聞いた。「この国ではターバンをつけたままこのような場に参上するのは不敬にあたる。なぜ、それをさっさと脱がないのか?」
使者は「わが国では、こうした場でもターバンを脱ぐことはないのです」と答えた。
ドラキュラは、「それならば我輩が、その頭から二度とターバンが外れないように、釘付けにしてやろう」と、実際に釘で、使者の頭を打ったのだという。もちろん、使者は死んだ。
幽閉生活中の奇行
1453年、東ローマ帝国はトルコに滅ぼされてしまう。
強力な後ろ盾を失ったドラキュラ公も、ついにはトルコ軍の攻撃に屈して、ハンガリーに亡命すること(逃げる羽目)になった。
ハンガリーはヨーロッパの中にあって中立的な土地だったため、トルコと積極的に戦う姿勢は見せなかった。むしろ両国には、何らかの密約が交わされていたという説もある。
いずれにせよ、ハンガリーに逃げてきたドラキュラ公を待っていたのは、また不自由な軟禁生活だった。今度は14年ほど。
幽閉中にも、ドラキュラ公は多くの奇行を見せた。
ドラキュラは仲良くなった看視の兵士に、野ネズミや小鳥を差し入れてもらったが、そうした小動物を、かつては人間に対して行なったような残虐な方法で殺し、楽しんでいたともされる。
暴君の改宗と最後の戦い
1476年頃。政治情勢の変化もあり、ワラキアに戻されたヴラドは、この頃にはカトリックに改宗させられていた。しかしワラキアは昔からギリシャ正教の者が大半であるから、もう暴君特有のカリスマ性もあまり役に立たなかったかもしれない。
しかしカトリックになったことで、ハンガリーの後ろ楯は大きくなったと考えられる。
ドラキュラは軍を率いて、ブカレストを占領することにも成功するが、結局トルコ軍との戦いの中で戦死する。
遺体はスナゴブ修道院に眠っているのか
ある記録によると、ドラキュラ公は、乱戦状態の中で孤立してしまった時に、放置されたトルコ軍兵士の死体から衣服を盗み、トルコ軍兵士に変装することで難を逃れようとした。
しかし、トルコ軍の目をごまかすのには成功したのだが、どうにか味方を見つけて近づいた際に、敵と間違われて殺されてしまったらしい。
その後、ドラキュラ公の遺体は、トルコ軍が見つけて、彼らはその首だけを切断し、コンスタンティノープルに持って帰った。そして、そこのスルタン(領主)は、まさしく彼にやられた同胞たちの恨みを晴らそうとするかのごとく、その首を槍で串刺しにして、自然に朽ち果てるまで城門に晒していたのだという。
首が切り取られたあとの遺体はどうなったのか。
ドラキュラ公は生前に、自分が死んだ後、遺体はスナゴブ修道院(Snagob Monastery)に埋葬してほしいと要求していたらしい。ブカレスト近郊の湖の小さな島にあるというこの修道院は、いろいろとドラキュラ(というかヴラドの一族)との関わりが深いらしい。例えばこの修道院を建てたのはそもそもヴラドの祖父なのだとか。ドラキュラ公の異母兄弟がここの修道士だったという話もある。
とにかく、後にドラキュラの首無しの遺体は、このスナゴブ修道院の僧侶たちに回収されて、修道院にて葬られたのだという噂がある。
血の伯爵夫人、エリザベート・バートリー
現代の吸血鬼物語に強い影響を与えた人物として、おそらくはドラキュラに次ぐとされるエリザベート・バートリー(Elizabeth Báthory。1560~1614)を生んだバートリー家とヴラド家が姻戚関係にあったと考える歴史家も多いという。
例えば、ドラキュラが、1476年にワラキアの王位奪還を企てた時に、バートリー家の王子が支援したとか、少なくとも何らかの関係があったと思わせる記録がけっこうあるという。
魔女ドロテア・ツェンテスとの繋がり
バートリー家も、トランシルバニアにおいて名家だったという。
枢機卿や大臣、国王まで輩出される一方で、この家柄の者には、狂信的な悪魔崇拝者なども知られている。
しかし、血の伯爵夫人と呼ばれたエリザベートは、特に異質と言えよう。
エリザベートは幼い時からの婚約者、ハンガリー貴族のナーダシュディ・フェレンツ(Ferenc Nádasdy。1555~1604)と結婚してから、ハンガリーのニートテ地方のチェイテ城に住むようになった。
武勇に優れた騎士であったという夫は、領主国に囲まれた緊張状態の中、領地の治安維持のために外出時間が多い。時間を持てあましたエリザベートは、いつからか召し使いの男と寝たり、女を虐めたりして楽しむようになったとされる。
一説によると、エリザベートはオカルト趣味の召使いから黒魔術を習った。そうした魔術には、例えば、牝ウマから抜き取った血を敵に塗ることで呪う方法など、血に関連するものもあったという。
さらにその召し使いを通して、ドロテア・ツェンテス(Drolta Tzuentes)なる魔女と繋がりを持ったとも。
この世の地獄の城
まだ、若くして夫が死んでしまった後、エリザベートの残虐趣味はどんどんエスカレートした。
血を浴びた瞬間、若返ったかのように、自らが美しく見えるという現象に、彼女が取り憑かれていたという話はよく語られる。
ある日、小間使いの少女が、エリザベートの髪を整えていた時、髪の毛を強く引っ張ってしまった彼女に、エリザベートは激怒。伯爵夫人は、少女が血まみれになるまで家具で叩いたが、この時に、血を浴びた自分を鏡で見たことが、後の殺戮のきっかけだったとも。
エリザベートは、召使いとして雇った若い女たちを次々と拷問し、大量の血を流させて殺した。
その血を搾り取るために、数々のむごたらしい殺し方を考案していった。
やがて、共犯の召使いたちに、若い娘を誘拐させるようにもなって、さすがにその所業についての噂も止められなくなる。なんとか逃げ出した娘の告発もあったという。
噂はハンガリー国王の耳にまで入り、エリザベートの従兄、ジョージ・ツルゾ伯爵が、チェイテ城の捜査のために派遣される運びとなる。
そして、1610年の冬、一隊を率いて、チェイテ城にやってきたツルゾ伯爵がそこでみた光景は、まさしくこの世の地獄であったという。
結局、王の一族の名誉的な問題か、エリザベートは処刑されることはなく、残りの生涯、ずっと軟禁されることになった。
しかし彼女の共犯者である召使いたちはみな処刑されたそうである。
吸血鬼伝承の起源
吸血怪物、生ける死者の起源
吸血鬼という怪物が紀元前から認識されていたことは、ほぼ確実とされている。例えば古代ペルシアの壺に、血を吸おうとしているような化け物と戦う男が描かれたりしているという。
バビロニアの悪霊とされるリリト(Lilith)も、吸血鬼的な側面があるとされるが、その起源はかなり古いと言われる。
「生ける死者の吸血」という伝説については、アジアに起源があるという説もある。紀元前の中国にそうした伝説があったという説。あるいはインド、マレーシア、ポリネシア、イヌイットの伝説にも吸血鬼を見出せるらしいが、そうした伝承が語られ始めた時期があまりはっきりしない。
いずれにしろ、血液が生命の源であるという説もかなり古くからあるが、血を奪ったり、好んだりする魔物や神に比べると、生ける使者の登場はおそらくかなり遅い。殺すためというより、自身の存在を保つために他者の生命力である血を奪うというような存在、つまり強引に生きている死者という発想は、けっこう斬新だったのかもしれない。
キリスト教の思想の影響
聖書を書いたヘブライ人たちも、 血と生命の強い関連を見い出していた。
それは命を象徴する液体であり、しかし不浄のものとも考えられた。生死は神のみが司る概念であり、血を聖なるものとして確実に正しく扱うのは人間には難しいとも。
女の経血は、最初の女イブが悪魔の誘惑に惑わされたための罰であり、他の者がそれに触れてはならない。
キリストは自らの血を流すことで、全ての人間を救済した、あるいは救済しようとしたが、それができたのは彼自身が神だから。
キリスト教はまた、その形成期に、(3世紀ぐらいに成立したとされる)新プラトン主義に影響を受けたと考えられている。
そして新プラトン主義において「死後の生」という思想があった。肉体は魂が宿る物質。単に器にすぎない体は腐敗するが、魂は最後の審判の時を待つ。
しかし、悔い改めることのなかった罪人や、自殺したり、破門されたりして、聖墓地で埋葬されなかった者たちは、決して救済されない。それなのに、魂は生きなければならない。審判の時までは滅びることがない。
キリスト教に属する者たちは、この世にもあの世にも属していない、ひたすらにさまよう魂を創出したのだとされる。
そして、肉体を失ったさまよえる魂の他、死後に行くあてなく自らの肉体に留まるしかなかった魂というのも考えられるようになった。前者は幽霊、後者は生ける死者の伝説に繋がった。
ジプシーが広めた伝承
中央ヨーロッパの遊牧の民をボヘミアン(Bohemian)とかジプシー(Gipsy)と言うが、地域的な伝説だった吸血鬼信仰を、ヨーロッパ中に広めたのはこの人たちだったと考えられている。
ジプシーは吸血鬼の存在を知っていて、その対抗策などにも詳しかったから、ハンター扱いされたり、あるいは悪魔的な存在と繋がりを有しているとか、噂されることもあったという。
また、ヴラド・ツェペシュはジプシーを嫌い、やたらと串刺し処刑で殺したらしい。
ジプシーの起源はインドの方で、おそらく国を追われてヨーロッパまで流れてきた者たちと考えられている。
14、15世紀くらい。ヨーロッパで急速に数を増すジプシーたちを、ヨーロッパ人たちは、浅黒い肌、汚い身なり、悪臭、芸と占いなどの技に優れている異教徒の人たち、というように見ていたという。
彼らはたいていの土地で嫌われ、迫害され、どこかに安定して定住するということがほとんどなかった。何らかの芸を披露するというのは、当時の基準では、社会の底辺の人たちの仕事とも。
しかし放浪者であったジプシーは、各土地の文化や芸術、神話、伝説などを広める役割も果たした。そうして、土地から土地へと伝えられた話の中に、吸血鬼信仰に関連するものもあったのである。
またジプシーには、魂というものは、死体が分解するまで体のなかにとどまる、という信仰があったという。魂が立ち去るのを早めるため、死体から頭を切って、体と別々に埋葬したとも。
実際の吸血鬼事件の記録
特に中世から近代にかけてのヨーロッパにおいて、吸血鬼、あるいはそれを思わせる「生ける死者」の話はいくつも記録されてきた。
ただし公文書と呼べるような文字記録で、生ける死者の実在が語られたのは、せいぜい18世紀までである。
科学の発展がもたらした啓蒙時代。十九世紀は産業革命を超えて、鉄道やガス灯の時代。都市の風景は劇的に変わり、新しい社会形態に、もはや過去の信仰や迷信が入り込む余地はすくなかった。
一方で、懐古主義、ロマン主義な作家たちは、もう昔の伝承と言えた、吸血鬼を題材としたいろいろな話を書いて、現在の我々がそうした夜の怪物に抱くイメージを固めていった。
アスムンド。友人が魔物として蘇る
スカンジナビアの方に伝わる(少なくとも13世紀ぐらいには、すでに昔の話と考えられていた)古い記録に、友人が生ける死者になってしまった、アスムンド(Asmund)という男の話がある。
昔、アスムンドとアスビィト(Asvith)という2人の英雄がいた。2人はとても固い友情で結ばれていたから、アスビィトが戦死した時、アスムンドは、死者の国へ旅立つ彼と共に行こうと決意。アスムンドは、様々な副葬品を持って、友の墓に一緒に埋葬された。
それから100年くらい時が経ってから、そこに宝物が隠されているはずだと考えたスウェーデン人が、墓を掘り返した。すると、なんと血みどろの姿で、しかしまだ生きていたアスムンドが、這い上がってきた。あるいは、墓の洞窟を探索するのに、ロープに縛られた状態で降りてきた男をどかして、ロープの先の探検家たちに合図し、アスムンドは引っ張り上げられた。
いずれにしても彼の出現に、墓暴きたちは相当に驚かされた。
アスムンドは、そこでいったい何があったのかを語った。
「なぜあなたたちは私を見て驚いたのか? すべての色が空になっているのか? 確かに、生きている人は死者の間では衰退していくだろう。
だが蘇った者たちには、この世界自体が不幸だ悲惨だ。
アスビィトは生き返ってしまったが、それはもう生前の彼ではなかった。鋭い爪を有する凶暴な魔物に変わり果てていた。この悪鬼は副葬された供物を食い終わるや、かつての相棒であった軍馬まで食い殺し、友である私にも襲いかかってきた。
この洞窟の闇は、私からあらゆる喜びを奪ってきた。私がかつて持っていた大きな活力を奪ってきた。
だが私は諦めず、死者と戦い、ついには勝利した」
語り終えたところで、アスムンドは(再び?)死んだ。
スウェーデン人たちは、悪鬼となっていたアスビィトを燃やして灰にして、アスムンドの死体も、同じように生き返らないよう祈りながら、再埋葬した。
この話は複数の古い記録文書に、いくらか異なるバージョンが書かれているというが、この話の骨組み(プロット)自体の古さが窺える。
場合によっては、魔物として蘇る友人の名前がアラン(alan)であったり、魔物を倒した後にアスムンドが自力で墓を脱出したり、その際に宝物を得たりする。
ウォルシェリン。アルルカンの軍隊
歴史家でもあった僧侶オーデリック・ヴィタリス(Orderic Vitalis。1075~1142)は、後世の歴史家に広く参考にされた歴史記録を書く一方で、時に、教会内で噂されていたと思われる怪奇的な話とかも文字に起こしていたらしい。
リジュー司教区の司祭ウォルシェリン(Walchelin)、あるいはゴーシェリン(Gauchelin)は、ヴィタリス曰く「強くて勇敢な男で、活動的だった」という。
1091年1月1日の夜、司祭は教区の病人の家から帰る途中で、大軍が進軍しているよいな音を聞いて、とりあえず木の陰に隠れた。
彼は、イングランド王ウィリアムと敵対していたシュルーズベリー伯爵3世ロバート・オブ・ベレーム(Robert of Bellême, 3rd Earl of Shrewsbury。1052~1130)の軍と思って、それが通り過ぎるまで待つことにした
ところが通りすぎる何千人もの人々は、明らかにただの軍隊ではなかった。
最初には、(略奪品のようにも見えたという)衣服、動物、家具、その他世俗的ないろいろ品物を運んでいた農民たち。次に、馬に乗った女たちで、その鞍には赤く熱気を発する釘が付いていた。その後には、僧侶たち、さらには司教や修道院長の群衆で、みな黒い服に身を包み、通りかかった時に嘆いているような声をあげた。最後に、黒とちらつく火を除いて、色も確認できなかった騎士の軍団。
ウォルシェリンは大きな恐怖を覚えた。彼らの中に知っている者が大勢いたのである。特に聖職者の仲間たち。しかし全員がもう死んでいるはずの者たち。
彼らの中には、明らかにひどい罰を受けている者たちがいた。それは棺台に乗せられ運ばれている人で、棺台には血を流す彼の他、顔だけ巨大な小人が偉そうに座っていたという。
ウォルシェリンは、彼が司祭スティーブンの殺害者と認識する。おそらく彼は、無実の血を流した罪悪感のために耐え難い苦痛に苦しんでいるのだと。
ウォルチェリンはそれが「アルルカンの軍隊(Hellequin’s Army)であることに気づいた。アルルカンは、道化の悪魔という説がある。
ウィリアム・ローダン。悪霊との戦い
オックスフォードの司教代理だったウォルター・マップ(Walter Map(1140~1210)は、「生ける死者」 の話をいくつも語ったという。
例えば、剛勇でならしたイングランドの兵士ウィリアム・ローダン(William Laudun)が、ヘレフォードの司教を尋ねた時のこと。
ローダンは言った「猊下、相談があります。最近、ウェールズのある罪人が私の家で死にました。彼は無信心でしたが、死んで4日めの夜から幽霊になり、毎夜欠かさず、昔の仲間の名を1人ずつ呼ぶのです。そして名前を呼ばれた者は、3日後に必ず病で死んでいるのです。もう仲間で生きている者は少なくなっています」
司教は「神は哀れな罪人の悪霊に、よみがえりの力と死体のまま歩く霊力をお与えになった。ともかく死体を掘り出し、遺体と墓に聖水をふりかけ、のどを切ってふたたび埋葬しなければ」と返した。
しかしそうしても、悪霊の悪事は続いた。
そして、ついにある夜、ウィリアムの名前が呼ばれた。だが勇敢な彼は、家から出て剣を抜き、とにかく振り回しながら走った。それで逃げた悪霊は墓に追い詰められ、横たわった。ウィリアムがその首を斬ると、ようやく悪霊の被害はなくなったのだという。
メルローズ修道院の魔物。修道士たちの戦い
歴史家、ニューバーグのウィリアム(William of newburg。1136~1208)が記録した「生ける死者」の話には、かなり近代的な吸血鬼のイメージに近い話がある。
ある高貴な夫人の指導司祭が亡くなった時のこと。彼はメルローズ修道院(Melrose Abbey)に埋葬された。
しかしその司祭は、生前に俗的な暮らしをおくり、かなり不真面目な聖職者であったからか、夜に墓から出てきて、何度も修道院に押し入ろうとして、修道院の者たちを悩ませた。
そこの修道僧たちの人徳と聖性が高かったから、魔物が修道院の中にどうしても入れないことは救いであったが、それで修道院を諦めた彼は、次には夫人の寝室に現れて、夜中、甲高い声でうめき、彼女を恐怖させた。
夫人の訴えを受けて、修道士たちはついに、悪霊退治を決意する。
そして夜に、修道土は、思慮深い老人の修道士と、助っ人である勇敢な若者2人と一緒に、例の司祭の墓の周りを見張ることになった。
ところが、なかなか魔物は現れず、修道士以外の3人は、近く建物の中にしばらく暖をとりに行った。すると、彼が1人だけとなったのを好機と見たのか、ついに墓から、それは現れた。
実際に魔物と向き合い、修道士は恐ろしさに震えたが、すぐに勇気を取戻す。闇の空気を揺らしながら、怪物は修道士に襲いかかってきたが、修道士は持っていた斧を振り回した。そして、傷を追った怪物は、うめき声をあげたかと思うと、どこかへ逃げ去った。あるいは墓の中へと戻った。
夜が明けてから、死体を掘り出してみると、その身体中が傷だらけで、大量の黒い血が、 幕穴一面に血溜まりを作っていた。死骸は、修道院から離れた場所で燃やされ、灰となった。
ペーター・プロゴヨヴィッチ。公式に認められた吸血鬼
伝染病というのは、しばしば生ける死者伝説の文脈で語られてきた。
1710年頃に東プロイセンでペストが流行した際、当局は告発を受けた吸血鬼迷信の全事例を組織的に調査した。
特にベーター・プロゴヨヴィッチ(Petar Blagojević)と、アルノルト・パウル(Arnont Paule)の事例は有名。特にプロゴヨヴィッチは、公式に認められた最初の吸血鬼とも言われる。それと、その報告書、魔物の名称として「VANPIR(英語ではVampire)」 という言葉が記載された、最初の公的記録という説もある。
1725年9月。セルビア領キシロファ村で、生前は農民であったプロゴヨヴィッチが、死後に吸血鬼となり、村の住民を襲うという事件が起きた。
プロゴヨヴィッチの死から1週間くらいで、8人、あるいは9人の村人が謎の病で亡くなったのだが、犠牲者たちはみな、病にかかる前の夜に、プロゴヨヴィッチに襲われていたのだという。
それと、プロゴヨヴィッチは家族の前に普通に現れていたらしいが、彼の暴虐に耐えきれなくなった妻は村を去った。またプロゴヨヴィッチは、食べ物を拒否した息子を襲ったとも。
それから、昼間に教会の者がプロゴヨヴィッチの棺を開けると、そこにあったのは、全く腐敗せず、まるで単に眠っているようなプロゴヨヴィッチであった。その髪や爪は生前より伸びていたとされる。
これは確かに吸血鬼に違いないと認められ、プロゴヨヴィッチは、心臓に杭を刺された後、焼却され灰となった。
そして事件は沈静化したという。
アルノルト・パウル。生前にも取りつかれていたか
彼の事件は、1727年から1728年にかけて、やはりセルビア領のメドヴェギア村で起きた。
この事件はロンドンの新聞で扱われた事で、ヴァンパイア(吸血鬼)という言葉を英語圏に広めた事件でもある。
生前のアルノルト・パウルは憲兵だったらしい。
1727年のある日。干し草の運搬車から誤って転落した彼は、あっさり帰らぬ人となった。だが彼は死後、吸血鬼となって人々を襲うようになってしまう。
被害を聞きつけ、地方司令部の将校と医師が村にやってきた。
村人たちはすでに、全く腐敗していないパウルの心臓に止めをさしていたが、彼に襲われた人や家畜も、やがては吸血鬼になるのだと怯えていた。
また、パウルの生前の憲兵仲間の証言によると、パウルは生前にも吸血鬼に取りつかれた事があったが、その時は死者の血を体に塗る事で身を守ったのだという。その効果は死後もしばらく続いていたのもしれない。彼が吸血鬼として墓から出てきたのは、埋葬から1ヶ月ほども経ってからだったらしいから。
何にしても、村人たちの尋常でない怯えに、事態を重く見た将校らは、パウルの吸血鬼化以降の死亡者たちの墓を掘り起こした。すると掘り起こされた多くの者たちに、吸血鬼の兆候が見られたという。その誰もが、火葬によって灰にされて、ようやく村は恐怖から解放されたのだという。
キリスト教と吸血鬼
キリスト教に吸血鬼伝説が取り込まれるのはいいとしても、普通に考えるなら、その時に吸血鬼そのものの存在と共に、対抗策、防御方法も学ばれたはずだろう。しかし、キリスト教の世界観において吸血鬼はさらにその弱点を(明らかに)追加されている。それはなぜか?
おそらく、キリスト教が、異端的なもの、異教徒のものを、その時点で基本的に悪しきものだというふうに捉える傾向が強い(少なくとも強かった)からだろう。 その点はキリスト教徒たちの、立場の弱い異教徒たちへの強制や弾圧の歴史から、かなり確実なことだ。
吸血鬼がもともと異教徒の怪物だというなら、(元々の伝承そのままに)その存在が悪しきものなのは当然として、しかしもともと全体として異教徒の伝説なのだから、もちろんその対抗策も異教徒の魔術的なものだったろう。つまりキリスト教徒の者から見てみれば、その伝えられる対抗策自体も、異端的な魔術のように考えられておかしくなかったはず。だがそうなると、吸血鬼に対抗する手段をどうすればいいか。そこで新たにキリスト教独自の、十字架だの聖水だのというようなものが考え出されたのでないだろうか。
実際、教会は結構、キリスト教的な防御方法を吸血鬼対策として推奨していた面もあったようである。でないとしても、異教徒の防御方法を積極的に導入していたなんてことは普通に考えにくいだろう。
吸血鬼リスト
ヴリコラカス(Vrykolakas)
ギリシャに伝わる吸血鬼。ヴロウカラカスとか、ブルコロカスと呼ばれる場合もある。
元々ヴリコラカスは人狼の事だったという。しかし、やがて人狼も死後に吸血鬼となるという説が生まれ、だんだんと吸血鬼の側面が強調されるようになっていったらしい。
 「オオカミ人間」狼憑きと呼ばれた呪い。獣に変身する魔法使いたちの伝説
「オオカミ人間」狼憑きと呼ばれた呪い。獣に変身する魔法使いたちの伝説
これは寝ている人をしゃがんで押し潰す怪物とも言われ、悪事を働いた者や、神を嫌う者などが、死後にヴリコラカスになると言われる。生前よりも体つきがごつく、怪力とも。しかも時間と共にひたすらに強くなっていくとか。
さらには、ヴリコラカスに襲われた者は新たなヴリコラカスになるとされる。ただしヴリコラカスは日曜日には墓から出れないという説もあるから、退治するならその時であろう。
また、大元のヴリコラカスさえ退治すれば、ヴリコラカスにされた者たちは共に滅びるようである。
ルガト(Lugat)
アルバニアに伝わる吸血鬼。血を求める死者であるが、霊体化する事も、物質化する事も出来るという。
ルガトは霊体の時の呼び名で、物質化している時はククチと呼ばれるらしい。
オオカミが天敵だという。オオカミに噛まれたルガトは、埋葬された墓に戻り、二度と出てこれないとも言われる。
ピジャヴィカ(Pijavica)
スロベニアやクロアチアに伝わる吸血鬼。例によって悪党が死ぬとこれになるらしい。
ピジャヴィカになった者は、家族と親戚一同を次々襲うとされる。
また、ピジャヴィカは血の繋がりを感知する事が出来るようで、生前には存在すら知らなかったほど疎遠な親戚まで見つけてしまうという。
素早く強いのに加え、高い再生能力を持ち、心を読むことまでできる。しかし直射日光に弱く、長時間浴びてしまうと焼け死ぬとも。
バラバラにしてもくっついてしまうが、この時に、首に足をくっつけたり出来る。それはけっこう有効的な退治方法らしい。
ウーストレル(Ustrel)
ブルガリアに伝わる吸血鬼。土曜に生まれ、洗礼を受けられずに死んでしまった子供が成る、霊的な吸血鬼。
ウーストレルは埋葬から9日後に墓から出て、家畜などに取りつき、取りついた者の血を吸い付くす。
実態がなく、無敵に思われがちだが、火や熱にかなり弱いとされる。また、土曜生まれの者にはその姿を探知されてしまうとされる。
ウポウル(Upour)
これもブルガリアの吸血鬼。この世に未練を亡くした者が、この吸血鬼になるという。
同じくブルガリアのウーストレルとは違い、物理的に巨体の吸血鬼であり、その巨体の形成のためか、死後40日ほどは現れないとか。
鼻の穴がひとつしかないとされる。
血液の他、家畜の糞からも栄養を得る。というかそっちの方が好みのようである。
トゲのある舌からは、火を吐く事もあるという。
どういうわけか、柵を超えられず、ロウソクを恐がるらしい。
モーラ(Mora)
やはりブルガリアの吸血鬼。睡眠中の者を窒息させて、心臓から血を奪うという。
ポーランドに伝わるズモーラと同じ吸血鬼だとされる。
赤い膜に包まれて生まれてきた女の子が、適切なお祓いを受けられなかった場合に、この吸血鬼になると言われる。
一説によると、吸血鬼にはならなかったが、その力をしっかりと残した者が魔女になるらしい。
また、生物だろうが無生物だろうが、サイズも素材も関係なく様々なものに変身出来る。それにその鋭い目には、悪夢を見せる力があるという。
ニンニクや十字架が苦手と言われる。
お菓子好きで、好みのお菓子で手なずけれるという話もある。
ヴコドラク(Vukodlak)
ユーゴスラビアの地域に伝わる吸血鬼。ヴリコラカス同様に、本来は人狼だったのが、いつの間にやら吸血鬼扱いされていたという。
元々人狼だった事もあり、オオカミへの変身能力を持つ。ただし名前を呼ばれると変身は解除されてしまう。
吸血鬼らしく、夜にしか力を発揮出来ない。
赤い膜に包まれた子が成ったヴコドラクは、クドラクと呼ばれ、オオカミに限らない多彩な変身など、より強力な存在。このクドラクは、白い膜の吸血鬼ハンター、クルースニックの最大の宿敵ともされる。
ストリゴイ(Strigoii)
ルーマニアの吸血鬼の典型だと言われる。赤い毛に青い目、それにふたつの心臓を持つ吸血鬼。
自殺者や犯罪者、魔女に殺された者、七番目の子、この世に未練を残した者が、死後にこの吸血鬼になる。
また、ストリゴイに襲われた者もストリゴイになる。
死後に猫に跨がれた者もストリゴイになるというが、この猫は変身した魔女か何かなのではないだろうか?
ストリゴイになる者は、左目がまず開くらしいので、死者の左目が開いていたら、それはストリゴイになってしまう兆候なのだという。
たいてい生きていたころの家族や親戚を襲う。
最大の弱点はやはりその第二の心臓だという説が有力。
ヴァルコラキ(Varcolaci)
ルーマニアに伝わる吸血鬼。別名プリクリクス
伝承によって、イヌだのドラゴンだのと姿が様々だが、単に変身能力によるものかもしれない。ただし人間の姿を取る場合は美青年とされる。
 「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
「西洋のドラゴン」生態。起源。代表種の一覧。最強の幻獣
その優れた容姿で誘惑した人を、変身した姿で襲い、血を吸う。
その魔法的能力は高く、魂を肉体から離して、それを空に広げる事で日食すら引き起こせるらしい。
洗礼を受けなかった者、不浄な行いを繰り返した者、未婚の母の子、真夜中に暗闇で働く女性の子などが、死後にヴァルコラキになるとも言われるが、やはり伝承により統一感がなく、はっきりしない。
ノスフェラトゥ(Nosferatu)
これもルーマニアに伝わる吸血鬼。私生児の親から生まれた子が死後に成るという。
ノスフェラトゥは、死後すぐに吸血鬼としての行動を開始するため、事前の予防は立てにくい。
吸血はもちろん、人間の苦しみを糧にすると言われる。
普通に家庭を持つ場合があり、ノスフェラトゥと人間の子はモロイという半吸血鬼になるという。
ノスフェラトゥを退治する有効な方法は、刃物でも弾丸でもいいから、とにかくその体を貫くことだとされている。
モロイ(Moloii)
ルーマニアの、半吸血鬼とも生ける吸血鬼とも言われる存在。
幽体離脱などが出来るほか、男女の違いによって、わりと明確に異なる性質を持つ。
男は基本的に頭に毛がなく、女は顔が赤い。
男女どちらも幽体離脱能力を持ち、適当な誰かに取り付いて悪事を働くが、女のモロイはさらに動物を操ったり変身出来る能力を持つらしい。単にモロイにも、デキる奴とそうでないのがいるというだけの話かもしれないけど。
死後はストリゴイになる確率が高いらしい。
ビビ(Bibi)
ルーマニアの女吸血鬼。霊的な吸血鬼でもあり、襲うのはもっぱら子の母か、子供らしい。子を亡くしてしまった母親の怨念が起源だという説がある。
たいてい赤い衣装で、二人の少女と、二匹の山羊を連れているという。この少女たちが実は、哀れな女の霊を利用する、ビビなんではないだろうか?
吸血鬼ではあるが、仲良くなると幸福をもたらすとも言われている。
ネラプシ(Nelapsi)
スロバキアに伝わる吸血鬼。死者由来だが、生前に何かしたとかはあまり関係なく、死後にどうにかなった者が、この吸血鬼になるという。
とにかく血を求め、人だろうが、家畜だろうが見境なしに襲うようである。さらに視線で、人に致命傷をもたらす事すら可能。
教会を恐れないどころか、教会により、その力を増幅させる事すら出来るという説まである。もしかすると聖なる力を使う吸血鬼なのかもしれない。だとすると最大の弱点は、他の吸血鬼だったりするか。
ウピオル(Upior)
ポーランドに伝わる吸血鬼。男はウピエル。女はウピエルツィカとも言う。
昼間にも普通に行動する吸血鬼で、舌についたトゲで、血を奪う。しかし決して満たされず、喉は常に乾いていてるらしい。
特に吸血を好む吸血鬼だが、自分の血は苦手ともされる。
オヒン(Ohyn)
ポーランドの吸血鬼。生まれた時にすでに鋭い歯が生え揃った赤ん坊で、すぐに死んで、赤ん坊吸血鬼になるという。
オヒンは見かけのわりには恐ろしい存在だが、死ぬまでのわずかな期間に、その歯を抜いてしまえば、無力になるとも言われている。
ウピル(Upyr)
ロシアに伝わる吸血鬼。女のウピルはウピールチカと呼ばれる。名前の似たウピオルと同様に、昼間でも平気な吸血鬼。
墓や棺に拘りはなく、地中に巣を作り、定期的に出てきては、血を求めるという。たいてい子供を狙うらしいが、飢えている場合は大人も襲う。
天候を操るともされる。
敵にした場合、一撃で上手く仕留めねば、多少の傷はすぐに再生してしまうとも。
エレティカ(Eretica)
ロシアの吸血鬼。悪魔と関わりを持った女性が、死後に成るという。
昼間、肌を隠した厚着姿で、人に近づき、仲良くなった相手を夜に襲う。
恐ろしい事に、集団行動を好む。
また、その目に睨まれると、徐々に衰弱してしまうとも。
エレティカは起きてる時は無敵なので、退治するには、寝てる隙を狙うしかないらしい。
マーラ(Mara)
北欧に伝わる吸血鬼。ブルガリアのモーラが伝わり、改変されたものと考えられる。
基本的に女性であり、適当な男性と結婚したり、恋仲になったりした相手の血を、知らず知らずの内に奪う。ただしよく磨かれた鉄などには、その吸血鬼としての真の姿が映る場合がある。
正体を知られるとマーラは逃げてしまうという。
アルプ
ドイツの霊的な吸血鬼。子供が死後に成るようで、母くらいの年代の女性の血を特に好む。
 「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
「ドイツ」グリム童話と魔女、ゲーテとベートーベンの国
あまり暴力は振るわない。しかし、長い舌で舐めた相手や、霧などに変身して体内に侵入した相手に、悪夢を見せたりするという。
人前に姿を見せる時は動物の姿が基本。どんな姿でも帽子を常に被っていて、この帽子が力の源。なので帽子を取り上げれば無力化出来る。
帽子が実はアルプなのかもしれない。
ナハツェーラー(Nachzdhrer)
ドイツの吸血鬼。ドイツのアルプ同様、子供吸血鬼だが、こちらの方が遥かに恐ろしい存在。
呪いで弱らせた家族の前に現れ、血を奪う。さらに、鐘を鳴らし、その音を聞いた者全員に致命傷をもたらす事が出来る。また、その影に触れた者には死の呪いがかかるという。
ナハツェーラーは血の他に、自らの体を糧とするのだが、寝てる間にコインを口に含ませる事で、その食事を防ぎ、餓死させられるらしい。
ノインテーター(Neuntoter)
ドイツの吸血鬼。疫病を振り撒く吸血鬼で、生まれつき歯のあった者が、死後にノインテーターとなる。歯のある者でなく、生まれつき口の中に銀が含まれていた者という説もある。
レモンが弱点であり、攻撃にも防衛にも使えるらしい。
エストリー(Estrie)
ヘブライの伝承に登場する吸血鬼。何らかの原因により、肉体を得た悪霊らしい。
子供の血を特に好むという。
変身能力や浮遊能力を持つが、使いすぎるとまた肉体を失ってしまうようである。
肉体を持つ時にしかダメージを与えられないが、肉体がない時は無害でもある。
アサンボサム(Asanbosam)
ガーナに伝わる吸血鬼。森に住み、森に迷いこんできた者を襲い、血を奪う。
アサンボサムは人間そっくりだが、歯が鉄製で、足には鉤爪があるという。単に特殊な装備した、未開の部族かもしれない。
イムプンドゥルゥ
南アフリカに伝わる、魔女に仕えるという吸血鬼。基本的に美青年だが、吸血以外にあまり興味がない恐ろしい存在。
仕える魔女がいなくなってしまうと、歯止めが効かなくなり、ひたすらに血を求め、暴れ続ける。主人を失ったイムプンドゥルゥは、イショログゥと呼ばれる。
鳥に変身出来るという話もある。
おそらく退治するには、動きを封じて餓死させるしかない。
アスワン(aswang)
フィリピンに伝わる吸血鬼。昼間は美しい女性だが、夜になると正体を表す。
キキキというような鳴き声を発しながら空を飛び、得物を決めては、長い舌を使ってその血を奪う。また、影を舐める事で、相手に死の呪いを与えられるとも言う。
ニンニクが苦手らしい。
バジャン(Bajang)
マレーシアに伝わる吸血鬼というか吸血動物。イタチに似ていて、鳴き声は猫のようだという。
バジャンは死産した子供から生じるとされている。
飼い慣らす事も出来るが、致死性の高い謎の疫病を抱えるので、ペットには全く向かない。しかし魔術師はよく、この生物を使い魔として飼い、気に入らない相手に病気を運ばせたりするという。
バジャンは飼われても、実は主人に忠義を誓うでもなく、意思疏通が出来る者には、簡単に主人の情報を渡したりする。優れた魔術師相手に、武器として使う場合は、パジャンは諸刃の剣なわけである。
ペナンガラン(Penanggalan)
マレーシアの吸血鬼。主に子供や妊婦の血を求める女吸血鬼。
体を自ら切り離す事が出来、臓器をぶら下げた状態の首から上状態でさ迷ったりする。そもそも顔と臓器だけの姿なんだという説もある。
ペナンガランのその滴る血は恐ろしい疫病をもたらすが、力自体はあまり強くないとされる。
ランスイル(Langsuir)
マレーシアの吸血鬼。出産時に死んだ母がランスイルに成るとされる。
ランスイルは緑色のローブを纏う美人だが、首の後ろに第二の口があるという。
吸血は第二の口で行う。
非常に爪が長いとも言われる。
第二の口は弱点でもあり、その口で何かを噛んでいる時は、かなりおとなしくなり、簡単に退治出来るようになるらしい。
吸血巨人
中国の南方の島に、巨人吸血鬼が住む島があるという。
この巨人たちは、10メートル近くものサイズであり、島に訪れた者を歓迎して、油断させた上で襲うらしい。
全く恐ろしい存在で、最も有効な対処法は、急いで島から逃げる事だという。
また、この吸血巨人は洞窟暮らしらしいが、どれほどでかい洞窟なのであろうか?
ムラート(Mrart)
オーストラリアに伝わる吸血鬼。霊的な存在、深夜に人間含む動物の血を狙う。
闇の中ではその力は非常に強力。しかし何かを攻撃するには闇の中でないと駄目なようで、まずは得物を明かりから無理やり引き離すという。




